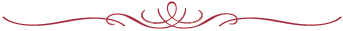
| 良寛和尚考 |
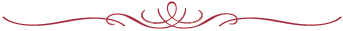
(最新見直し2013.07.28日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、良寛和尚考をものしておく。 2013.07.28日 |
![]()
| 「関 袈裟夫」氏の2018年5月11日付け「「山房五月黄梅の雨」 良寛」。
越後「五合庵」山房で詠んだ「半夜」、良寛の代表的漢詩「生涯懶立身」他数詩、70歳の良寛に30才も若い美貌の尼僧「貞心尼」との間に生まれた交情「相聞歌」重ね寄す。 (1) 漢詩 ① 「半夜」(はんや) 回首五十有餘年 首を 回らせば五十有余年 (大意) 生涯懶立身 生涯 身を立 つるに懶く 補記 良寛代表作、良寛が好んで使う「優游」といった心境・心事を最も良く表している作品。 花無心招蝶 花は無心にし蝶を招き 補記 無欲一切足 欲無ければ一切足り 独往伴糜鹿 独往して 糜鹿(びろく)を伴とし 補記 (大意) 補記 一思少年時 一に思ふ 少年の時
|
||||||||||||||||||
| (2)良寛、晩年の恋
孤独と清貧に生きた良寛の晩年に、明るい華やぎが生まれた。「五合庵」から島崎の木村家裏屋に移り棲んでいた良寛70歳に、30才若い美貌の尼僧「貞心尼」(ていしんに)が訪れ、交情が生まれた。仏道の師と弟子としての二人は良寛の亡くなるまでの3年間、貞心尼は大腸がんに罹っていた良寛の下の世話もしつつ、恋い慕う心を和歌に託して交流した。良寛74才死後、「貞心尼」がまとめた『はちすの露』―最初の良寛詩集には、二人の「相聞歌」50数首収められている。中から以下を寄す。
|
||||||||||||||||||
|
(3)来歴 良寛(1758~1831)は、江戸時代後期の詩歌・書に優れた托鉢僧。越後出雲崎の名主橘屋の長男として生まれ18歳で出家し越後を訪れた国仙和尚に従い備中(岡山県)玉島の円通寺門に入る。10年余りの修行の後、二十数年間諸国を行脚、奇行に富んだ飄逸の生活を送る。帰郷後、国上山(くがみさん)中腹にある「五合庵」や乙子神社の草庵に住庵した。生涯寺を持たず、名利にとらわれぬ生活を送り、清貧の中で生きとし生けるものすべてへの愛を失わず、子どもと戯れ、友と語り、和歌や漢詩を詠み、書に興じた。「大愚」と号した良寛詩約500首は、40歳から59歳までに「五合庵」に暮らした20年足らずの晩期に書いた。万葉風の「和歌」及び「書風」共々、天衣無縫で高い評価を得て、秘かな良寛ブームが続いている。 |
||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)