「せん妄」と「お迎え」は違う
こうしたお迎え現象は、医学的には「せん妄」と診断され、脳の機能低下が主な原因と考えられている。しかしせん妄の特徴は、突然発症し、数時間から数週間にわたって継続し、かつ症状が時間とともに変化するというもの。その症状も、突然暴れ出す、意味不明なことを口走る、妄想・幻覚・幻聴、攻撃的になるなどで、お迎え現象とは似て非なるもののような気がする。実際に、介護現場で働き、せん妄の患者に寄り添うことが多い施設の職員は、「せん妄の方は、恐怖におびえて苦痛を訴え、話す内容も混乱しています。でも、お迎えが来たとおっしゃる患者さんは、意識ははっきりしておりストーリーもきちんとしています」と違いを語る。症状がひどい場合は治療の対象にもなる「せん妄」も「お迎え現象」も、原因は明確にされていない。岡部氏は「この現象を科学的に解明したり否定したりするのではなく、安らかに旅立つ死へのプロセスと考え、まず実態を調べるべきだ」と主張していた。お迎えと似た現象は、認知症の一種であるレビー小体型認知症でも見られる。「小さな子どもが家のなかで遊んでいる」「戦死した夫がやってきた」、「知らない男性がたくさんいる」など、幻視がかなりはっきりと見えるらしい。頭の後ろ側(後頭葉)の血流が悪くなることが原因と説明されているが、患者本人にとっては「現実」そのもの。それなのに、家族が気持ち悪がって否定することで、家族間の関係が悪くなるケースが多いといわれている。まずは「本当に見えている」ことを理解し、否定せず、受け入れることが大切だ。
生涯が、走馬灯のようにかけめぐる
SF作家の故・星新一氏の傑作に『午後の恐竜』(新潮社)という作品がある。「現代社会に突然出現した巨大な恐竜の群れ。蜃気楼か? 集団幻覚か? それとも立体テレビの放映でも始まったのか? ──」というわけで世間は驚き、大騒ぎになるのだが、恐竜は蜃気楼でも幻覚でもなく、「地球」が「死ぬ間際」に、走馬灯のようにかけめぐっていた「生涯」だった。筆者の父親は、病気で亡くなる一ヶ月前、「幻聴」を走馬灯のように楽しんでいた。父は病気の影響で耳がほとんど聞こえていなかったのだが。「面白いんだ、この頃。小さい頃から聞いてきた会話や音楽や、さまざまな音が、ずーっと蘇って聴こえてくる。だからこうしてベッドに寝たきりでも、全然退屈しないんだ」と微笑んだ。地球はどうか知らないが、人間には、死を穏やかに受け入れるための準備的な能力が備わっているのだろう。
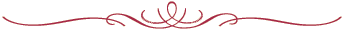
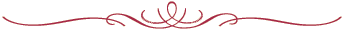
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)