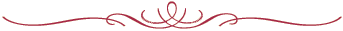これは、明治七年二月二十二日の夜の五つ時のお筆なり。 辻先生はいつも、多くは昼は家業をして、夜分に参拝せられることなるが、この夜、お宅にありて歯が痛み耐えられぬにつき、さっそく神様へお参りせんと、痛むを堪(こら)えて歩み来られしに、三島の村地へかかるとパッと痛みが治まりしゆえ、不思議にも、かつ有り難く思い、神様へお参りして、御教祖様(おやさま)にこの事を申し上げたるところ、『今、これを書きました。これを見て思案しなされ。そして「かきもち」があるが、食べてみなされ』と仰って、この「御筆先(おふでさき)」と「かきもち」とを下されしと。実に不思議のことなり。
辻様は、御筆先をとくと眺めて、やがて「かきもち」も食べ試(こころ)みしに、少しも歯に障ることなく、そのまま歯は痛まざりしという。思うに、このお筆をお付けあそばされたるより、辻様にも、身上よりお知らせ下されて、お引き寄せ下されたるなるか。
『高山の説教聞いて』云々(うんぬん)というは、ご維新(明治維新)後、大いに神道を知らしむる御上(おかみ)の目的より、教導職という者を命じて、神道の説教や、演説を各所にてやるようになって、この頃が一番盛んの頃でありしゆえ、この事を仰せらるるならん。そこで、『神様のお話と、ひき比べて思案して、神様の真実なる話の理を悟って、楽しむよう』との事なりかし。
〔諸井政一「正文遺韻」249頁〕