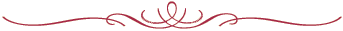
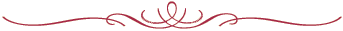
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.9.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
| ここで、「天理教教理を学び神意を悟る」の「古老より聞いたはなし」の「古老より聞いたはなし ⑸、井筒梅治郎」を確認しておく。
2006.1.23日、2012.9.18日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【 |
| ①
明治十三年の春、陰暦三月四日、たね母の身上のご守護を頂いたお礼参拝に、初めて親子三人(井筒梅治郎/妻とよ/娘たね)おぢばへ帰らせて頂いた。出発の時、生憎(あいにく)の雨天でしたが、家を出て数丁、本田(ほんでん/現大阪市西区本田1丁目)の大渉橋(おおわたりばし)の辺りまで来ると、雨はすっかり上がって、好天気のご守護を戴いた。教祖にお目通りをさせて頂いたら、『あの雨の中を、よう来なさった』と。さらに、たね母の頭を撫でて下さった。『お前方は大阪から来なさったか。珍しい神様のお引き寄せで、大阪へ大木(たいぼく)の根をおろして下されるのや。子供の身上は案じることはない』と仰せ下さった。
② 道の伸びるとともに、迫害はますます激しくなり、迫害の激しくなるとともに、人々は教会の公認を得ようと焦り、明治十八年三月七日には、教会創立事務所に集まって会議を開いた。その席上、藤村成勝らは、会長幹事の選出に投票を用いることの可否、同じく月給制度を採用することの可否などを提案した。議論沸騰して容易に決しない時、その席上にいた梅治郎祖父が、激しい腹痛を起こして倒れてしまった。教祖にお伺いしたところ、『さあ/\今なるしんばしら(真柱)はほそい(細い)ものやで、なれど肉の巻きよで、どんなゑらい(偉い/豪い)者になるやわからんで(分からんで)』と仰せられた。この一言で、皆はハッと目が覚めた。竹内や藤村などと相談していたのでは、とても思召に添いがたいと気付いたのであった。『しんばしらの眞之亮(しんのすけ)』と仰せられ、「道の芯」を明らかにしておられるのに、一時的にも、何の理も無い人を責任者とすることは、まったく心の置き所が外れていることを、身上でもって皆々にお教え下されたが、こんな肝心な時に身上でもってお教え下さる、ありがたさを痛感するのである。
③ 教祖がいつもジッとお座りになっておられるので、祖父が、「教祖、ご退屈でございましょう。一度どこかへお伴させて頂きましょう」と申し上げたところ、教祖が、『ちょっと、ここへ顔をあててごらん』と仰せられた。祖父が教祖のお袖に顔をあてると、ちょうど牡丹(ぼたん)の花の旬で、「見渡すかぎり牡丹の花ざかりだった」とのこと。「教祖は居ながらにして、どこの事をもご存知なのだと驚いた」とのことである。
④ ご本席様が、まだ「伊蔵さん」と呼ばれておられた頃、伊蔵様のご家族の生活が、あまり〈にも〉お気の毒なところから、皆々話し合って「頼母子講(たのもしこう)でもして伊蔵さんを助けようやないか」と相談をしていたところ、教祖は、『思惑あって苦労さしてあるのや。かまってくれるな』と仰せられた。後になって「本席」という理を戴かれて、皆々「なるほどと合点がいった」とのことである。以上、たね母から聞いたことを書かせて頂いた。
〔みちのだい第33号「教祖特集号」26-27頁〕 井筒梅治郎氏「道のさきがけ」116頁より謹写 牡丹の花盛り 頼母子講 |
|
【①の参考】「逸話篇」 七一 あの雨の中を
明治十三年四月十四日(陰暦三月五日)、井筒梅治郎夫婦は、娘のたねを伴って、初めておぢばへ帰らせて頂いた。大阪を出発したのは、その前日の朝で、豪雨の中を出発したが、お昼頃カラリと晴れ、途中一泊して、到着したのは、その日の午後四時頃であった。早速、教祖にお目通りさせて頂くと、教祖は、 『あの雨の中を、よう来なさった』と仰せられ、たねの頭を撫でて下さった。さらに教祖は、『おまえさん方は、大阪から来なさったか。珍しい神様のお引き寄せで、大阪へ大木の根を下ろして下さるのや。子供の身上は案じることはない』と仰せになって、たねの身体の少し癒え残っていた所にお紙を貼って下さった。たねが間もなく全快のご守護を戴いたのは、言うまでもない。 梅治郎の信仰は、この教祖にお目にかかった感激と、ふしぎなたすけから激しく燃え上がり、ただ一条(ひとすじ)に、にをいがけ・おたすけへと進んで行った。 〔「天理教教祖伝逸話篇」123-124頁〕 |
| 「道のさきがけ 教祖伝にみる人物評伝」 梅治郎夫婦は、子供が授かっても育たなかった。五人目に生まれた長女たねも、生後三ヶ月頃から下半身にイボのような腫れ物(はれもの)ができ、花が咲いたように赤く腫れ上がって、どうしても治らなかった。大阪の商人(あきんど)・萬(よろづ)綿商「播清(はりせい)」の主(あるじ)梅治郎は、金に糸目を付けず、娘を救けようと医者、薬と手を施したが、一向に効き目がない。当時、大阪商人の旦那方(だんながた)の間では、大峰山(おおみねさん)の行者(ぎょうじゃ)として、行場(ぎょうじょう)を回りながら修行を積む人がいた。梅治郎も修行者の先達(せんだつ)として大峰山の熱心な信心家であったので、家で護摩(ごま)を焚(た)き、祈祷(きとう)して長女たねの平癒(へいゆ)を祈ったが、やはり効き目はなく、途方に暮れてしまった。
隣家の紺屋(染物屋)に出入りしていた花の種売り、通称「種市(たねいち)」こと前田藤助(まえだとうすけ)から、「大和(やまと)に生き神様がいる」と聞き、藁(わら)にも縋(すが)る思いで「たすけ」を求めた。種市は水垢離(みずごり)をとって、梅治郎夫婦とともに東方に向かって神名を唱え、真剣に祈った。
あれほどまで赤く腫れ上がっていたたねの身体から、赤みが引いていく……。時に明治十二年(1879)七月三十日のことである。元来、神仏への信仰心のあつい梅治郎は、「救けられた喜びを、どうしてご恩返しすればよいものか」と思案の末、「病気で苦しむ人を救けることだ」
と悟った。早速折しも、突然眼病を患い失明した隣家の紺屋の主、中川文吉(後に真明組の講脇になった人)の「おたすけ」にかかった。お灯明(とうみょう)を点け、水垢離をとって、三日のお願いを済ませた時、「ああ、お灯明の明かりが見える……」
と文吉。ご守護を戴いたのである。
明けて春四月。娘たねと、文吉を救けて頂いたお礼を教祖に申し上げたい一念から、一歳になったたねを連れて、梅治郎夫婦は初めておぢば帰りをした。家を出る時は大雨で難儀(なんぎ)したが、途中、河内の国分村(現大阪府柏原市国分)で一泊し、翌四月十四日、晴天の中、おぢばに到着した。教祖は、『あの雨の中を、よう来なさった』『……子供の身上は案じることはない』と、癒え残ったたねの腫れ物にお紙を貼られ、梅治郎に、『珍しい神様のお引き寄せで、大阪へ大木の根を下ろして下されるのや』とお言葉を戴いた。おぢばに居ながら、すべてを見抜き見通しの教祖。「これぞ真実の神である」と悟った梅治郎は、『大木の根を下ろす』との教祖のお言葉を、全身全霊で噛み締めていた。 梅治郎は、五尺九寸(約179cm)、二十貫(約75㎏)の、恰幅(かっぷく)のある大阪の商人であった。街では相撲も取り、どんな揉め事でも、梅治郎が顔を出すと治まるという、頼もしい顔役でもあった。『大阪の地に、たすけ一条の大木を下ろす』と仰せられた神様の思いを受けた梅治郎は、おたすけに奔走した。文吉をはじめ、不思議な守護を目の当たりにした人々は、たすけを請(こ)うてきた。その数は夥(おびただ)しく、戸板で担ぎ込まれる人、人力車で駆けつける人、家の中は「たすけ」を求め、話を聞きに来る人が増えたので、明治十三年から十四年にかけて、向かいの二階を開放し、人々の集まる集会所とした。これを「本田寄所(ほんでんよりしょ)」と呼んだ。 やがて講名拝戴の機運が持ち上がり、そのお許しを戴くため、梅治郎は信者と共におぢばに帰った。明治十四年五月十四日、教祖から「真明組(しんめいぐみ)」の講名を拝戴。入信して二年目であった。梅治郎は、「救けて頂いたご恩、日々生かされているご恩は、人を救けることによって報いることができる」と自らも信じ、それを人々に説いた。それで、この道を聞き分けた人々は皆、人だすけに励んだ。 〔「道のさきがけ」116-119頁〕 |
| 【②の参考】「教祖伝」 当時、人々の胸中には、「教会が公認されていないばっかりに、高齢の教祖にご苦労をおかけする事になる。とりわけ、ここ両三年来、西も東も分からない道の子どもたちの心ない仕業が、ことごとく皆、教祖にご迷惑をおかけする結果になっている事を思えば、このままでは何としても申し訳がない。どうしても教会設置の手続きをしたい」との固い決心が湧き起こった。 四月十四日には、お屋敷から山本利三郎、仲田儀三郎の二人が教興寺村(現大阪府八尾市教興寺)へ行って、この事を相談した。同じく十八日には、大阪の西田佐兵衛(さへえ)宅に、眞之亮、山本、仲田、松村、梅谷、それに京都の明誠組(めいせいぐみ)の人々をも加えて協議した。が、議論はなかなか纏(まと)まらず、「一度お屋敷へ帰ってお伺いの上、よく相談してから方針を決めよう」ということになった。 当時、京都では明誠組が、心学道話(しんがくどうわ)を用いて迫害を避(さ)けていたのに倣(なろ)うて、 明治十七年五月九日(陰暦四月十四日)付、梅谷を社長として「心学道話講究所天輪王社」の名義で出願したところ、五月十七日(陰暦四月二十二日)付「書面願之趣指令スベキ限ニ無之依テ却下候事」ただし、願文の次第は差し支えなし。との回答であった。それで、大阪の順慶町(じゅんけいまち/現大阪市中央区南船場)に「天輪王社」の標札を出した。 この頃(明治十七年)北炭屋町(きたすみやまち/現大阪市中央区西心斎橋一丁目)では、天惠組(てんえぐみ)一番、二番の信者が中心となって心学道話講究所が作られ、その代表者は竹内未誉至(みよし)、森田清蔵(せいぞう)の二人であった。 九月には竹内が、さらにこれを大きくして「大日本天輪教会」を設立しようと計画し、まず、天惠組、眞心組(しんじんぐみ)、その他大阪の講元に呼びかけ、続いて兵庫、遠江(とおとうみ/現静岡県の大井川以西)、京都、四国にまでも呼びかけようとした。
こうして道の伸びるとともに迫害はますます激しくなり、迫害の激しくなるとともに人々は教会の公認を得ようと焦り、ついに、信者たちの定宿(じょうやど/常宿)にしていた村田長平(ちょうべえ)方に教会創立事務所の看板をかけるまでにいたった。… …さて、竹内らの計画は次第に全国的な教会設置運動となり、明治十八年三月七日(陰暦正月二十一日)には教会創立事務所で、眞之亮、藤村成勝(なりかつ)、清水与之助、泉田藤吉、竹内未誉至、森田清蔵、山本利三郎、北田嘉一郎、井筒梅治郎らが集まって会議を開いた。その席上、藤村らは、会長幹事の選出に投票を用いることの可否、同じく月給制度を採用することの可否などを提案した。議論沸騰して容易に決せず、剰(あまつさ)えこの席上、井筒は激しい腹痛を起こして倒れてしまった。そこで教祖に伺うたところ、『さあ/\今なるしんばしらはほそいものやで、なれど肉の巻きよで、どんなゑらい者になるやわからんで』と仰せられた。この一言で皆はハッと目が覚めた。竹内や藤村などと相談していたのでは、とても思召に添いがたいと気付いたのである。 が、本格的な教会設置運動の機運は、この頃からようやく動き始め、この年三月、四月にわたり、大神教会の添書を得て、神道管長宛てに眞之亮以下、十名の人々の教導職補名の手続きをするとともに、四月と七月の二度、大阪府へ願い出た。 最初は四月二十九日(陰暦三月十五日)付で「天理教会結収御願」を大阪府知事宛て提出した。「十二下りのお歌」一冊、「おふでさき」第四号および第十号、「この世元初まりの話」一冊、合わせて四冊の教義書を添付しての出願であった。教導職補名の件は五月二十二日(陰暦四月八日)付、眞之亮の補名が発令された。続いて同二十三日(陰暦四月九日)付、神道本局直轄の六等教会設置が許可され、さらに、その他の人々の補名の指令も到着し、六月二日(陰暦四月十九日)付、受書を提出した。
この年、四国では、土佐卯之助らが修成派に伝手(つて)を求めて補名の指令を得た。世間の圧迫干渉を緩和(かんわ)しようとの苦衷(くちゅう)からである。しかし「天理教会結収御願」に対する地方庁の認可は容易に下がらず、大阪府知事からは六月十八日(陰暦五月六日)付、「願の趣聞届け難し」と却下された。… …翌七月三日(陰暦五月二十一日)には再度の出願をした。「神道天理教会設立御願」を、大阪府知事宛てに提出したのである。この時には男爵、今園國映(いまぞのくにはえ)を担任としての出願であった。
十月八日(陰暦九月一日)には教会創立事務所で、眞之亮も出席の上、講元らを集めて相談していたところ、その席に連なっていた藤村成勝、石崎正基(まさもと)の二人が、にわかに中座して布留の「魚磯」へ行き、しばらくして使者(つかい)を寄こして、眞之亮と清水与之助、増野正兵衛の三名に、「ちょっとこちらへ来てもらいたい」 と言うてきたので、「これは必ず悪だくみであろう」とて行かなかったところ、藤村のみ帰って来て、清水に小言をならべた。しかし、その夜、石崎は逃亡した。
十月になると二十八日(陰暦九月二十一日)付で、またまた「聞き届け難し」と、却下の指令が来た。この時、教祖に思召を伺うと、『しんは細いものである。真実の肉まけバふとくなるで』とお言葉があった。親神の目からご覧になると、認可云々(うんぬん)の如きは全く問題ではなく、親神がひたすらに急き込んでおられるのは「陽気ぐらしへのつとめ」であった。激しい迫害干渉も実は「親神の急き込みのあらわれ」に他ならない。しかるに人々は、そこに気付かずにして、ただ皮相(ひそう/物事の表面・うわべ)な事柄にのみ目を奪われ、人間思案に没頭していたから、空(むな)しい出願を繰り返していたのである。かねがね教祖は、『しんばしらの眞之亮』と仰せになり、「道の芯」を明らかに示しておられる。しかるに、『いかに焦ればとて、何の理も無い人を、たとえ一時的にもせよ、責任者とすることは、まったく心の置き所が逸脱していたからである。ここのところをよく考えて、まずしっかりと心の置き所を思案せよ。「しんに肉を巻け」とは「しんばしらに誠真実の肉を巻け」という意味で、親神の思召のままに、眞之亮に理の肉を巻けば、たとえ今は若輩でも、立派なしんばしらとなる』と、人間思案を混えぬ、神一条の道を教えられた。 〔「天理教教祖伝」274-281頁〕
|
|
「正文遺韻」
また、今の教長(初代真柱)様、ご若年の頃にお話あり。『しんばしらは今はまだ若い。年がいかぬから神の入り込みが薄いけどな、しんばしらが二十四、五となったら、神が入り込んで、どんなこと言わすや知れんで。「あんな草深い中に、えらい大木がなあ」と、世界から言うようになるほどに。 さあ、側の者は、しっかりと心を合わせて、しんばしらに、真実芯の肉を巻いてくれ。芯が太うなる。幹がえろうなる。したならば、どんなえらい枝が出るや知れんで。これ楽しんで、真実芯の肉を巻くよう』 とお聞かせ下されし。 〔諸井政一「正文遺韻」119頁〕
|
| 【③の参考】「逸話篇」 七六 牡丹の花盛り 井筒たねが、父から聞いた話。井筒梅治郎は、教祖がいつも台の上にジッとお座りになっているので、「ご退屈ではあろうまいか」とお察し申し、どこかへご案内しようと思って、「さぞ、ご退屈でございましょう」と申し上げると、教祖は、『ここへ、ちょっと顔をつけてごらん』と仰せになって、ご自分の片袖を差し出された。それで梅治郎がその袖に顔をつけると、「見渡すかぎり一面の綺麗な牡丹の花盛り」であった。ちょうどそれは牡丹の花の季節であったので、梅治郎は、「教祖は、どこのことでも自由自在(じゅうよじざい)にご覧になれるのだなあ」と思って恐れ入った。
〔「天理教教祖伝逸話篇」133頁〕
|
| 「道のさきがけ 教祖伝にみる人物評伝」123頁、牡丹の花盛り
教祖がお屋敷で、いつも台の上に座って居られるのを見て、繁華な大阪出の梅治郎には、「教祖はさぞ、ご退屈であろう」と思われた。そこである日、「一度、大阪の芝居にでも、お伴させて頂きたい」と申し出た。すると教祖は、『ここへ、ちょっと顔をつけてごらん』と、ご自分の袖をお広げになった。梅治郎が言われる通り顔をつけてみると、 そこは、一面見渡すかぎり、牡丹の花が咲き乱れていた。ちょうど、牡丹の花咲く季節であった。梅治郎は大いに感じ入り、「教祖はおぢばに居られても、世界中のことは見抜き見通し、自由自在に、ご覧になられるのだなあ」と思ったという。 |
|
【④の参考】「正文遺韻」
明治十五年旧二月八日、ご本席様〈お屋敷へ〉お入り込みあそばさる。もっとも神様より度々(たびたび)、『入り込め』とのお話あり。奥様と小児二人は前年の暮れ十二月より、『今、行かねば旬が外れる、遅れてしまう』と仰るゆえ、「どうあっても、やらしてもらう」とて、お屋敷にお勤めになり、ご本席様と、姉娘よしゑ様とは、躊躇(ちゅうちょ)してお残りなされたりしが、ここに至りて決断し、ついに諸道具売り払い、また、値安物はみな人にやりて、わずかの日用品のみを持ち、お入り込み相成(あいな)る。これは神様のお話に、『道具も何も一切、屋敷の物を使えばよいから何も持ってくるに及ばぬ』とお聞かせ下されしゆえなりと。 しかるに入り込みてみれば、秀司先生の未亡人まちゑ(松枝)様は、厳しき痛手をなされて何一つお貸し下さらず、火鉢を借りても、布団を借りても、みな損料貸しにして(使用料をとって)、すべて神様より聞いたことと違うにより、なかなかの困難にて、また、折々それがため不足心を起こすことも多かりしと。それより後、ある時ご家内おさと様、ご身上お障りに付き、お願い申したるに、『親としては「子によいもの着せたい」と思うやろ。子供が「あれ欲しい、これ欲しい」と言えば「不憫(ふびん)」に思うやろ。なれど「よいもの着せたい」と思うやないで。よいもの要らん、不自由しよう。 「難儀しよう」と言うたて、出けぬ日があるほどに』と仰せられ、それまでは、とかく子供をいじらしく思うて、不足の心の湧くこともありしが、これより心改めて、末を楽しんでお暮らしあそばしたりと。『正月になりて「子供に一かけの襟(えり)を買うてやりたい」と思うたが、買えなんだ』と、ある時、ご本席様のお物語りのなかに聞けるが、さまで(ここまで)困難の道なれば、ご不足の心の湧くも尤も(もっとも)の事にて、因縁にあらざれば、とてもその道通りきることは能(あた)うまじきなり。
〔諸井政一「正文遺韻」113-114頁〕
|
| カテゴリなしの他の記事 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)