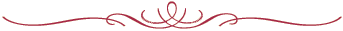
| 古老より聞いたはなし ⑵-2、仲田、山本、高井 |
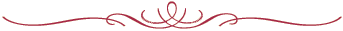
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.9.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
| ここで、「天理教教理を学び神意を悟る」の「古老より聞いたはなし」の「古老より聞いたはなし ⑵、山澤ひさ」を確認しておく。
2006.1.23日、2012.9.18日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
|
【参考】「天理教教祖伝逸話篇」222-223頁〕一三二/おいしいと言うて
仲田、山本、高井など、お屋敷で勤めている人々が、ときどき近所の小川へ行って雑魚獲(ざこと)りをする。そして、泥鰌(どじょう)、モロコ、エビなどを獲ってくる。そしてそれを甘煮(うまに)にして教祖のお目にかけると教祖は、その中の一番大きそうなのをお取り出しになって、子供にでも言うて聞かせるように、『みんなに「おいしい」と言うて食べてもろうて、今度は出世しておいでや』と仰せられ、それからお側に居る人々に、『こうして一番大きなものに得心さしたなら、あとはみな得心する道理やろ』と仰せになり、さらにまた、『みんなも食べる時には「おいしい、おいしい」と言うてやっておくれ。人間に「おいしい」と言うて食べてもろうたら、喜ばれた理で、今度は出世して、生まれ変わるたびごとに人間の方へ近うなってくるのやで』とお教え下された。各地の講社から、兎(うさぎ)、雉子(きじ)、山鳥などが供えられてきた時も、これと同じように仰せられた、という。 |
|
【参考】諸井政一「正文遺韻抄」154-155頁〕、一三二/動物の進歩に就て(ついて)
(おいしいと言うて」の典拠・出典元であろう逸話) 仲田様、山本様、高井様など、常住詰め切りの先生方は、時々ご閑暇(かんか)もあることなれば、折に触れて雑魚獲りなどにお出かけあそばさる事も少なからず。その時には教祖様(おやさま)へお願い申し上げ、お暇のお許しを受くるを例とせり。さて、お暇願いに伺えば、教祖様(おやさま)仰せには、『獲りてきたなら必ず煮て、わしの所へ持ってくるのやで』とお指図(さしづ)あり。それから人々勇み立ちて出かけ、やがて、どじょう(泥鰌)、もろこ(諸子)、えび(海老)などを獲りて、帰ればすぐさまうまに(甘煮)になし、そっくりと教祖様(おやさま)のご覧に供(そな)う。すると教祖様(おやさま)は、その中について最も大きいものを見澄まし、お箸にお取りあそばされて、『こういうものに生まれてくるさかいに、人間に食われてしまわにゃならん。早う人間に引き上げてもらえよ』と仰って、お口に入れ給い、やがて一同に向かって、 『さあみんな、おいしゅう食べてやって下され』と仰って、お下げに相成(あいな)りしという。かようの事はたびたびありしと。それにつき、ある時お話に、『こうして、この中で一番大きいものを得心さしたなら後は、みな得心する道理やろ。講を結ぶにも同じ事やで。一村の中で、大頭(おおあたま)の者が得心したと言うたら、あとは皆ついて来るやろ。もし、ついて来ぬにしても邪魔をするような事はあろまいがな(ないであろう)』とお聞かせ下され、また、『生き物は、みな人間に食べられて「おいしいなあ」と言うて喜んでもらうで、生まれ変わるたびごとに人間の方へ近うなるのやで。そうやからして、どんなものでも「おいしい/\」と言うて食べてやらにゃならん。なれども牛馬というたら、これは食べるものやないで。人間から堕ちた、穢(けが)れたものやでなあ』とお聞かせ下されしという。されば講社の先々より、兎(うさぎ)あるいはきじ(雉子)、山鳥など、「神様へ」とて持ってくる者ある時は、教祖様(おやさま)は三度までお撫でなされながら、『こういうものに生まれてくるさかいに、人に食われてしまわにゃならん。早う人間に引き上げてもらえよ』と仰って、一同にお下げ下されしという。しかしてその時には必ず、『どうぞ、おいしゅう食べてやって下され』とお言葉を添えて下されしとなん。魚類にてもその通りなりしとぞ。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)