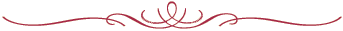
| 古老より聞いたはなし ⑵、山澤ひさ |
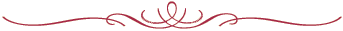
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元)年.9.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
| ここで、「天理教教理を学び神意を悟る」の「古老より聞いたはなし」の「古老より聞いたはなし ⑵、山澤ひさ」を確認しておく。
2006.1.23日、2012.9.18日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【松村まち (本部婦人) /女のやさしさ 】 |
| 〔みちのだい第33号「教祖特集号」24-25頁〕松村まち (本部婦人) /女のやさしさ 幼い頃に、よく里の母(山澤ひさ/旧梶本ひさ)が言ってくれました。「教祖はな、『魚は食われて成仏(じょうぶつ)するのや。「おいしい」と言うて食べてやるのやで』とお聞かせ下さった」と。この短いお言葉の中に、女のやさしい心遣いをお教え下されていると思います。人間というものは「一言の言葉で、人を生かすこともあれば、また殺すこともあるもの」でございます。助け一条の上にお使い頂く私ども「道のよふぼく」としては「一番に心得ねばならぬこと」だと存じます。どんなに味のない魚でも、それはそれだけの味わいしか与えられていないのですもの、「おいしかった」と言えるような味の付け方を工夫することが料理をする者の真心として肝心なのと同じように、人間も、味のない者にも味わいを付けてあげられるように、苦心して導かせてもらうのが「真のお助け」ではないかと悟らせて頂きます。ともすれば感情的になって「役〈に〉立たぬ」と切ってしまいやすい、人間心の浅薄(あさはか)さを反省したいと思います。 なお母は、「教祖は『親に孝行はぜにかね(銭金)要らん。とかくあんま(按摩)でたんのう(堪能)させ』と、よく歌われていた」と聞かしてくれましたが「日々のちょっとした心遣いの中にも、親を満足させ、喜ばすことのできる道のあること」をお教え下されていると思います。年を重ねるにつれて、よく老人の心理が解らせて頂けるように思いますが「親に喜ばれる道は難しい事ではなく、日々の身近な言葉の端にも、些細な心配りの優しさの中に言い知れぬ嬉しさを味わえるものであること」を、つくづく感じさせて頂きます。 教祖が常に、こうしたお優しい御心で、ご両親様にお仕えあそばした、数々のひながたをお偲び申し上げるにつけても、あの秀司様がお生まれになる、そのご妊娠中に舅(しゅうと)善右衛門様が出直されて、お一人寂しくお塞ぎがちな、お母様のお心を察せられて、身重の教祖が、お母様をを背に負われて、お心やすい誰彼をお訪ねになり、お母様のお心をお慰めあそばされた、あの優しいご孝行のご行動が、目に映るように思い浮かんでまいります。
『親に孝行は、月日の孝行に受け取る』 (親孝行は、この世人間の元の親である月日親神への親孝行と受け取り守護する)
とお聞かせ頂きますが、最近の世の中の思想が、銘々自分本位になりがちである。この中にあって道の若人が、道なればこそ味わえる親孝行の喜びを、世の若い人々に映していくことが、親神様から自然のお恵みを戴く、明るく大きなにをいがけ、お助けの道ではないかと思案させて頂きます。
難しい事せいとも、紋型無き事せいとも言わん。皆一つ一つのひながたの道がある。ひながたの道通れんというような事ではどうもならん…ひながたの道通らねばひながた要らん。ひながたなおせばどうもなろうまい。
明治二十二年十一月七日 刻限
|
|
【参考】「天理教教祖伝逸話篇」261-262頁〕、一五七/ええ手やなあ
教祖がお疲れの時に、梶本ひさが「按摩をさして頂きましょう」と申し上げると、『揉んでおくれ』と仰せられる。そこで按摩させてもらうと、後でひさの手を取って、『この手は、ええ手やなあ』と言うて、ひさの手を撫でて下された。また教祖はよく、『親に孝行は銭金要らん。とかく、按摩で堪能させ』と、歌うように仰せられた、という。
|
|
【参考】諸井政一「正文遺韻抄」250-251頁、「親孝行」について 親が尽した理は
『一代尽した理は、末代の理に受け取る』という。『親が尽しておいて、その子に悪因縁深き理が現れてくるようでは、神の道も、教祖の教えもありゃしょうまい。そのような道は必ずないほどに。親が尽した理は、子供まで、孫までも皆受けていく』…『何でも素直な心もって、神様の言う通りの道を守って、神妙に勤めにゃならん。親が尽しておいたら、子の出てくるのを神が待っている。親が道に背いたら、子が出てきても、横向いている』と仰る。よって尽した理は一代切りやない。子孫に伝えて末代の理や。よって、何でも真実を尽さにゃならん。 |
|
諸井慶一郎「天理教教理大要」335-336頁、親の心の筋を
家族の親-子-孫という縦の系列において、自分の前生因縁を思案させてもらえるのであります。なぜかと言えば、『人は他所(よそ)へ生まれることもあるが、大体は、親が子となり、子が親となって、元へ元へと生まれ変わってくる』のだと仰せになっているからであります。また、『因縁の者同士を寄せる。血筋(ちすじ)と言うが、血筋やのうて、親の心の筋を、子が引くのや』と仰せられます。自分の因縁は、父祖代々のことを尋ねると、いろいろ具体的に知らされるのであります。特に、悪因縁を拵えるに至った具体的所業のことは、先祖の事を知るのが一番の近道であります。 |
| 親のあとを子が伝う (諸井慶一郎「天理教教理大要」478-483頁、抜粋) 親と子の間柄は、『親が子となり、子が親となって、恩の報じ合いをするのや』と仰います。また、『親となり、子となるは、前生の因縁から』と仰るのであります。したがって、子供の選り好みはできぬのでありまして、親子の理、いんねん理聞き分け、善い子持つも悪い子持つもいんねん。 〔おさしづ 明治34.3.11〕
我が子の示し出けんのは、親の力の無いのや。
〔おさしづ 明治30.12.11〕
真実の理を見た限り、親のあと子が伝う。
〔おさしづ 明治26.6.21〕
「親の通る姿通り、子に映る」
のであります。その事からすれば、「親が子に尽せば、子は親に尽すかというと、そうでなく、親がその親に孝を尽せば、親のあと〈を〉子が伝う〈の〉で、子も親に孝を尽すようになる」のであります。 『親への孝心は、月日への孝心と受け取る』 と、かくまで仰って、親孝心をお促し下さるのであります。
親の恩は、否定しようのない事実であります。「人間十五才までは親がかり」なのであって、親がかりの十五年のその間には、どれほどの大恩を受けているか知れない。その「親のご恩」が解るようになるのが「独り立ち」ということであって、以後の人生は「報恩の人生」ということになるのであります。その報恩の第一が「親への報恩」であって、それをせねば「恩が重なる」のでありまして、身が沈まざるを得なくなるのであります。 『立てば立つ、転(こ)かせば転けるのが天の理』であって、立てる第一は「親」である。その親を転かせば、我と我が身(自分自身)が転けてゆかねばならぬ。天理として転けてしまう。それが不憫(ふびん)だから、親への孝心を称揚(しょうよう)下されているのであります。親は「根であり元」である。その親を立てず、潰してゆけば「根を切って回るようなもの」で、遂には枝が枯れる。また、倒れる日も出てくるのであります。 親孝行せぬと出世せぬ。自分が親を立てぬと、自分が立たん。出世せんのみならず、子供が自分を立てなくなる。子供で末長く楽しみ喜ぶ人生を、逆に、子供で泣いて通らねばならなくなる。また、枝が枯れる。つまり「子孫が育たん」ということになる。 「むほん(謀反)」というのは、子が親に刃(やいば)を突き付ける。親を覆(くつがえ)すのが「むほん」であります。自分がそうした「むほん」に遭わねばならぬのは「通り返しの道」である、と思案せねばなりません。 五ッ いづれもつきくるならば (いずれ(誰で)も随き来るならば)
六ッ むほんのねえをきらふ (謀反の根を切ろう)
親神様への、つとめの道につきくるならば、であります。
親に小遣いを差し上げるのも、「小遣いをやるような思いではなりません」。 「親のご苦労あっての今日の自分」であることからすれば、自分の働き、自分の稼ぎには「親の働きが込められている」のであります。そこで、御礼心を添えて親に差し上げる。親につかって頂く。それでこそ、親孝行の一端となるのであります。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)