|
大本神歌
(一)
東雲(しののめ)の空に輝く天津日(あまつひ)の、豊栄昇る神の国、四方に周(めぐ)らす和田の原、外国軍(とつくにいくさ)の攻難き 、神の造りし細矛(くわしほこ)、千足(ちたる)の国と称えしは、昔の夢となりにけり。今の世界の国々は、御国に勝りて軍器(つわもの)を、海の底にも大空も、地上地中の選みなく、備へ足らはし間配りつ、やがては降らすアメリカの、数より多き迦具槌(かぐづち)に、打たれ砕かれ血の川の、憂瀬(うきせ)を渡る国民(くにたみ)の、行く末深く憐れみて、明治の二十五年より、露の玉散る刃(やいば)にも、向かいて勝を取らせつつ、なお外国(とつくに)の襲来を、戒め諭し様々と、神の出口の口開き、詔らせ給(たま)へど常闇の、心の空の仇曇り(あだぐもり)、磯吹く風と聞き流し、今の今まで馬の耳、風吹く如き人心、アァ如何にせん戊(つちのゑ)の、午の春夏秋に懸け、心落ち居ぬ荒浪(あらなみ)の、中に漂ふ苦しみは、神ならぬ身の知る由も、なく泣く縋(すが)る神の前、水底潜(くぐ)る仇艦(あだぶね)と、御空に轟(とどろ)く鳥船の、醜(しこ)の荒(すさ)びに悩まされ、皆散り散りに散り惑ふ、木の葉の末ぞ哀れなる。
|
|
(二)
聯合(れんごう)の国の味方と今迄は、成りてつくせしカラ国の、悪魔邪神(まがつのかみ)が九分九厘、モウ一厘の瀬戸際に、旗を返すと白露の、その振舞(ふるまい)の非義非道(ひぎひどう)は、凡(すべ)ての計画(しぐみ)を狂わせて、勝つべき戦争の負け始め、永びき渡る西の空、黒雲晴るる暇もなく、独り気儘(きまま)の仕放題 、印度の海も掠め取り、ここにも深き経綸(しくみ)為し、次いて浦鹽(ウラジオ)日本海、我物顔に跳梁し、トントン拍子に乗り出して、神の御国を脅迫(おびやか)し、モウ一と息と鳴戸灘、渦巻き猛る荒浪に、大艦小艦残りなく、底の藻屑と亡ぶるも、綾の高天(たかま)に最(い)と高く、空に聳えし言霊閣(ことたまや)、天火水地と結びたる、五重(いづえ)の殿に駆け登り、力の限り聲(こえ)限り、鳴る言霊の勲功(いさおし)に、醜(しこ)の鳥船軍艦(とりふねいくさぶね)水底潜(みなそこくぐ)る仇艇(あだぶね)も、皆夫々に亡び失せ、影をも止めぬ惨状(みじめさ)に、曲津軍(まがついくさ)も慄(おののき)きて、従ひ仕へ来る世を、松と梅との大本に世界を救う艮(うしとら)の、神の稜威(みいづ)ぞ尊とけれ。
|
(三)
綾の高天に顕れし、国常立(くにとこたち)の大神の、神諭(みこと)畏(かし)こみ謹みて、厳(いづ)の御魂と現はれし、教御親の神勅(かみこと)に、日清間の戦ひは、演劇(しばい)に譬えて一番叟、日露戦争が二番叟、三番叟はこの度の、五年に亙りし世界戦、龍虎相打つ戊の、午の年より本舞台、いよいよ初段と相成れば、シベリア線を花道と、定めて攻め来る曲津神。力の限り手を盡し、工夫を凝らし神国を、併呑(ひとのみ)せんと寄せ来たり、天の鳥船(とりふね)天(そら)を蔽ひ、東の空に舞い狂ひ、ここに二段目幕が開(あ)く。三段いよいよ開く時、三千餘年の昔より、国の御祖(みおや)の選まれし、身魂(みたま)集る大本の、神に仕えし神人が、御祖の神の給ひたる、日本心(やまとごころ)を振り起し、厳(いづ)の雄猛(おたけ)び踏み猛び、厳の身魂を元帥に、瑞の身魂を指揮官に、直日の身魂を楯と為し、何の猶予も荒身魂、爆裂弾の勇(いさぎ)能く、神の軍(いくさ)の奇魂(くしみたま)、奇しき勲功(いさお)は言霊の、天照る国の幸魂(さきみたま)、言平和(ことむけやわ)す和魂(にぎみたま)、魂の助けの著るく、轟く御代を松の代の、四十有八(よそまりやつ)の生御魂、言霊閣(ことたまのや)に鎮まりて、四方の国々天の下、治めて茲に千早振、神代ながらの祭政一致(まつりごと)、開き始めて日の本の、現津御神(あきつみかみ)に奉る、常盤の御代ぞ楽しけれ。
|
|
(四)
カラ国の天に漲る叢雲(むらくも)も、砲煙弾雨も晴渡り、日の出の守護と成るなれば、こよなき御国の幸なれど、十重(とえ)に二十重(はたえ)に累(かさ)なりし、糸のもつれの彌繁(いやしげ)く、解くる由なき小田巻の、繰り返しつつ行く程に、東の空にもつれ来て、退くに退かれぬ破目と成り、
彌々(いよいよ)出師(いくさ)と成る時は、五十余億の軍資をば、一年経(たた)ぬ束の間に、烟散霧消(えんさんむしょう)の大惨事、巨万の生霊土と化し、農工商の国本も、次第次第に衰ろえて、青菜に塩のその如く、彼方此方に溜息を、つくづく思案に暮れの鐘。進退ここに谷(きわ)まりて、天(あめ)を拝し地に伏し、狼狽えさわぐ弱虫の、カラの身魂は自から、現はれ狂ふ憐れさよ。しかれど日本は千早振り、神の守りし常盤国、国の真秀国(まほくに)珍の国(うづのくに)、神が表面(おもて)に現れまして、御国を守り給いつつ、世界を救ひ玉へども、未だ未だ心許されぬ、一つの国の御空より、降るアメリカの一時雨、木枯さへも加わりて、山の尾の上(へ)の紅葉(もみぢば)も、果敢なく散りて小男鹿(さおしか)の、泣く聲(こえ)四方に龍田山、神のまにまに四ツの尾の、山の麓の龍館(たつやかた)、集り居ます神々の、厚き恵みに照り返す、紅(からくれない)の楓葉(もみじば)の元の姿ぞ目出度(めでた)けれ。
|
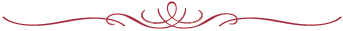
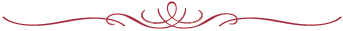
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)