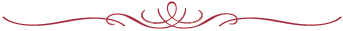
| 大本教法 |
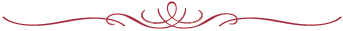
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4)年.9.1日
(目下草案書き直し中)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「大本教法」を確認する。 「真之と大本教」、「大本教法」その他参照。 |
![]()
| 【大本教法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在使われている大本教法は次の痛り。(出典「おほもとのりと」天声社、昭和63年8月27日)。
|
| 【大本教法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口王仁三郎(おにさぶろう)が九州巡教の際、熊本県阿蘇郡小国町の杖立温泉から持ち帰った竹の杓子百六十本に歌を書き込み、これに署名と拇印を押して霊を込めた。治病などの神器として用いられている。病人に御手代をかざしながら天津祝詞、感謝祈願詞、神言などを唱えると、御手代から霊光が出て病気が快癒すると云う。また神に祈願したのち、御手代で病人の患部を押えても、同様の効果があると云う。邪心に憑かれている者の改心、邪霊を去らせる効能もあるという。この御手代は世界救世教など大本教系の教団に多大な影響を及ぼしている。杓子は、招福の呪物として神社仏閣の授与品の一つになっているなど、昔から各地で信仰されている。 言葉の護符として代表的なのが「惟神(かむながら)霊幸(たまち)倍坐世(はえませ)」である。「神の御心のままに、御加護下さいますように」という意味で、朝拝、夕拝、大祭などの祝詞の最後にもこの祈りを唱える。出口王仁三郎の「霊界物語」には、「惟神(かむながら)霊幸(たまち)倍坐世(はえませ)」が霊界探査において危険に遭遇したときの「護身用の万能呪文(じゅもん)」として記されている。この呪文を叫ぶだけで窮地を救われた例も多いと云う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「天の数歌」(あまのかずうた)は我が国古来から伝わる祝詞(のりと)で呪術的要素が強い詞(ことば)とされており、病気平癒の祈願から鎮魂法に至るまで多様な用途がある。神に祈願し、天の数詞を奉唱すると、神の助力を受けて病難などが解消されると云う。唱え詞は次の通りである。末尾の「もも、ち、よろず」のところを「布留部(ふるへ) 由良由良止(ゆらゆらと)布留部(ふるへ)」(ふるべゆらゆら ふるべゆらゆらと ふるべ)と唱える。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この数え歌を大括して略解すれば、霊力体(れいりきたい)によって世が発生し、水火の呼吸(いき)燃え上り、初めて地成り、弥々益々水火の気凝り固りて宇宙天界が完成され、諸々の地の光は暗夜(あんや)に出現して総てのものの目に入るといふ天地剖判(天地創造)のプロセス、世の成り立ちを諭して居る。併せて造化三神の神徳を称へ奉り、その徳にあやかりて紫微(しび)天界を修理固成(しゅうりこせい)し、諸神安住の清所(すがと)に照らさむとの意を謳(うた)ひ給ひし言霊と知るべし(出口王仁三郎「霊界物語」第73巻第10章・婚ぎの御歌参照)。「ひふみ祝詞」では「ひふみよいむなやこともちろ」と唱える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大本聖師・出口王仁三郎が口述した、古今東西第一の奇書と思われる「霊界物語」の中で、「これは重要なる賛美歌で、天の数歌と云ひます。皆さまもこれから間(ま)があれば、この数歌をお唱ひなさい」と、ある登場人物に言わせている。 凡そこのように解することができる。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)