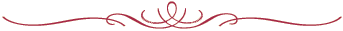
| 大平良平の教理エッセイその7 |
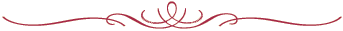
更新日/2024(平成31.5.1栄和改元/栄和6)年.1.8日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「大平良平の教理エッセイその7」をものしておく。 2024(平成31.5.1栄和改元/栄和6)年.1.8日 れんだいこ拝 |
![]()
| 大和の地場にて 大平良平 |
| 天理教教理より見たる 人生の意義及価値 大平良平 本論(中)「サア/\月日(神)あつて此の世界(地球)世界あつてそれ/\(万物)あり。それ/\あつて身の内(人間)あり。身の内あつて律(法律)がある。律があつても心の定め (信仰)之が第一」。 この言葉は教祖の臨終に先つてその弟子に向つて神楽勤めを要求した時、弟子達は何れも官憲の圧迫を憚つて之に応じなかつた為、高弟飯降伊蔵氏に神が降つてこの言葉があつた。弟子達はこの言葉によつて始めて最後の決心をしたのである。千九百余年の昔、猶太の救世主が人皆なの祈るべき祈祷の文句として教へた「天に在ます吾らの父よ。御名を崇めさせ給へ。御国を臨らせ給へ。御心の天に成る如く地にも成らせ給へ。我らの日用の糧を今日も与ひ給へ。我らに負債ある者を我らが免るす如く我らの負債をも免し給へ。我らを試みに遇せず悪より救ひ出し給へ。国と権と栄とは 限りなく汝の有なればなり」には、現実我(人)が理想我(神)に対する直接の祈祷を表象せる如く、天理教に於けるこの天啓の声は理想我(神)が現実我(人)に対する間接の命令を表象してゐる。且つ後者をもつて基督教信仰の精髄を語つてゐるものとせば、前者は天理教信仰の根底を形造つてゐるのである。 事実かくも簡単なる言葉の中にかくも偉大なる人生の始終を包含せる言葉は世界の頭脳をもつて目せられつゝある英国図書館に行くとも発見することはできないであらう。真やこの簡単なる言葉の中には全人類にとつて祖先以来の懸案であつた神観、世界観、万有観、人間観、法律観、信仰観が寓せられてゐるのである。こう云ふ理由の下に私は先づこの天啓の言葉の順序に従つて天理教の神観、世界観、万有観、人間観、政治観、信仰観を略述し漸次天理教の細緻なる人生観に説き及ぼさうと思ふ。 |
| 第一章 天理教の神観 |
| 月日あつて(天啓の声) 天理教で云ふ神とは国床立尊、重足尊の男女両神を始めとして月読尊(男)、国狭土尊( 女)、大戸辺尊(男)、雲読尊(女)、惶根尊(男)、大食天尊(女)、伊邪那岐尊(男)、伊邪那美尊(女)の八柱の神を指して云ふのであつて、総称して南無天理王命略して天理王命とも天理大神とも云ふ。南無とは梵語真実を意味し、宇宙の実体を指したものである。また天理王命とはこの宇宙に天理より大なるものなく、この世界に王より大なるものなきをもつて天理王命と云ひ、宇宙の理体を指したものである。この実体と理体と抱合して全宇宙を形造るのである。従つて南無天理王命と云へば宇宙間にありと凡ゆる凡ての神を召び出したことになるのである。ここにやゝもすれば初学の天理教信者にとつての碍(がい)は神々の姿である。これは独り初学の天理教信者のみならず生中半可通の常識によつて養はれたる一般学徒の碍の基となる問題であるから複雑を忍んで一言私見を述べてをかうと思ふ。 天理教で国床立尊の姿を大龍と云ふは、この世は「理」の世界である即ち理世であると云ふ意味を具体化せるものである。又重足尊の姿を大蛇と云ふのは女はこの世の「台じや」と云ふ意味を具体化せるものである。その他月読尊の鯱、国狭土尊の亀、大戸辺尊の黒蛇、雲読尊の鰻、惶根尊の鰈、大食天尊の鰒、伊邪那岐尊の人魚、伊邪那美尊の白蛇は泥海時代に棲息せる当時の最高動物であつた。その当時の最高動物の凡ゆる特徴をとつて成し上げたも のが人間である。けれどもここに一つの問題は当時の鰌の形を具備した人間が今日の人間に進歩した点より見れば、これ等の神々が何時迄も元の姿であるとは思はれない。事実当時道具衆として使はれた神々の魂が今日天理教の地場に人間として表はれつゝある点より想像して、一切の生物の上に進化の事実を否定する訳には行かない。畢竟大龍と云ひ、大蛇と云ひ、鯱と云ひ、 亀と云ひ、黒蛇と云ひ、鰻と云ひ、鰈と云ひ、鰒と云ひ、人魚と云ひ、白蛇と云ひ皆なそれ/\の特殊の形態を具備するには必ず一種の心理的特徴をもつて居る。 (例へば長い物には長い影が映じ、円い物には円い影が映ずるが如きものである。それが生格化(具体化)して大龍となり、大蛇となり、鯱となり、亀となり、黒蛇となり、鰻となり、鰈となり、 鰒となり、人魚となり、白蛇となり、それが無生格化(抽象化)して消極力となり、積極力となり、緊張力となり、継続力となり、牽引力となり、運輸力となり、旋動力となり、切断力となり、父性となり、母性となつて人間並びに万有を通じて一切の物質を支配するのである)それが種々に変化して自然並びに人生を動かす不可思議力となるのである。之を要するに国床立尊と重足尊とは宇宙の両極性(二大自然力)を代表せるものにしてその他の神々はこの二大自然力の変化したものに外ならない。御筆先の「この世の真実の神月(国床立尊)日(重足尊)なり、後なるは皆な道具なるぞや」は即ちこの大自然力と小自然力との関係を歌つたものと見るべきである。 蓋し神とは人間の如く或る限られたる力と限られたる形をもつてゐるものではない。万有を創造しもしくば破壊して行く自然力をさして云ふのである。之を有限の人間力相対の人間性と同一視する時は遂に神の実体を捕捉することができないであらう。殊に天理教でいふ神の如き最もそうである。従つて私はここに天理教の神観の発達史を略述して天理教でいふ神の精神内容は如何なるものであるかを研究したいと思ふ。 教祖布教の第一期に於て神を表象する言葉として用ゐたのは月日と言ふ言葉である。これは信仰の最も幼稚なる初期の時代に於て、眼に見えざる偉大なる超人間力(神)の存在を、信徒に信ぜしめんが為に眼に見ゆる偉大なる物質を借りて云ひ表はしたものに外ならない。その証拠に明治十二年八月の御筆先には、「今日までは月日と云ふて説いたれど、もふ今日からは名前換へるで」と断つて、それ以後の御筆先にはズツト親と云ふ名で説かれてある。これが天理教の後期である。 この他初期の天理教では 「水と火とが一の神。水火風の外に神はない」と云つてゐる。之を天理教々理より云へば水は即ち国床立尊の御守護である。火は即ち重足尊の御守護である。風は即ち惶根尊の御守護である。こう云ふ火の神、水の神、風の神の存在はその神の名こそ異れ原始時代より世界を通じて行はれたる信仰である。現に天理教で云ふ十柱の神の宇宙人生の分担の御守護の如きもその一層複雑化したものに外ならない。 けれどもここに一つの疑問は、火水風を生ずる原動力即ち火力水力風力が神であると云ふことは直ちに信ずることができるけれども、火水風が即ち神であると云ふことを信ずるには多少の隔りを感ぜずにはゐられない。これは月日が即ち神であると説く場合に於ても亦同様である。けれども一歩転じて人間の肉体を組織する元素が火水風であると見る時は、天理教で云ふ火水風が実の親と言ふ言葉は無條件で承認することができる。 またこの地球はその昔、月もしくば太陽と一身同体であつた。それが長い間に分離して一個の独立した天体となつたと云ふ天文学上並びに地文学上の学説より云へば、「この世の真実の神月日なり、何か万の守護するぞや」は何ら異論を挟むべき余地がない。更に吾人々類の出所は之を狭い眼より見れば肉身の父母に相違なけれども、之を広い眼より見れば天地が即ち吾人々類の父母であり且つ生れ故郷である。この点より見て、人間は神(天地)の懐住ひをしてゐると云ふ教祖の言葉並びにこの世の天と地とが元の親それよりできた人間であると云ふ御筆先に表れたる思想は元より議論を要しない問題である。唯吾人の問題は物質を動かす大自然力を神と云はずして物質そのものを神と称した初期の物質的神観である。けれどもこの物質的神観は信徒の信仰の進歩に伴つて漸次精神的に進んで来た。例へば、「神は理やで理は神やで」と云ふ言葉の如き真実は神、神は真実と云ふ言葉の如きは神を本質的もしくば本体的に説明した言葉である。これによつて見れば、教祖の認めてもつて神と云つたのは眼に見ゆる物質その物にあらずして眼に見えざる無形の大真実大真理をさしたものであることが訳る。 この他御筆先に表はれたる、「いかほどの強敵あらば出して見よ、神の方には倍の力を」、「いかほどの強敵たるも発明でも、月日の心之は叶はん」によつて見れば神は大智力なり、神は大勇猛力なり、と云ふことができる。またこの神は助け一條の親神様であると云ふ点より見れば、神は大慈悲心なりと云ふことができる。 更に天理教の神とは如何なる神であるか、その史的本性を知るには、天保九年十月二十四日に教祖ミキ子に神憑つて霹頭に発せられた自己紹介の言葉である。「然るにその日は何時も市兵衞の加持台に立つ勾田村のオソヨが外出して行先が不明であつた。それで臨時にミキ子を加持台に直して祈祷に取り掛つたのである。暫時するとミキ子の態度は次第に荘重を加へ持つて居た幣束がパチリと音して止まるかと思ふと一人の神が降つた。市兵衞が降つた神を尋ねると、ミキ子は四辺を払ふばかりの威厳に満ちた態度で 「我は天の将軍である」。……………………… 。「天の将軍とは何方様で御座います?」と尋ね出ると、「天の将軍は月日ぢや」、市兵衞は畳みかけて聞いた。「月日と仰せられると?」。「根の神、元の神、実の神である」。 之によつて見れば、天理教の神は決して今日の非天理教徒の誤解してゐる様な狐や狸の如き淫祠邪神ではない。明らかに天地開闢の始めより存在して万有を創造した又創造する、更に創造して行く所の宇宙の第一大原因、世界の原動力、万有の根元、人類の大祖である。之を要するに 「生物が一個体の卵よりその生物として完成するに至るまでの発生の状態は、その生物に属する種類がその過去より今日に至る迄次第に進化し来れる道程を繰り返すものである」と云ふ生物発生の原則は同時にまた心理上に応用することができる。即ち天理教が今日の状態に発達する迄には或る期間の間原始時代より今日に至る迄経験して来た人類の信仰発達の道程を繰り返してゐるのである。少くともその歴史的経験を応用してゐるのである。 例へば、月日が神である 、水火風が神であると云ふ如き物質的神観は即ちこの歴史的経験を応用したるものに外ならない。従つて真の天理教の神観を伺ふには、神は理なり、神は誠なり と云ふ本質観本体観に到達せねばならない。けれども神は理なり、神は誠なり、神は智なり、神は仁なり、神は勇なりと云ふだけにては天理教の神観が従来の宗教と何らの異る点はない。天理教の神観が従来の宗教より一歩進めた点はその一元的多元観にあらず、その分担の御守護(これ等は天理教によつて始めて詳細に説かれたものには相違なけれど)にあらずして実に理が親である、神が親であると云ふ神人親子の関係が一層家族的に徹底してゐる点である。これは神人父子を説く基督教よりも更に一層親密の度を加へてゐる。天理教の神観の長所は寧ろこの点にある様に思はれる。 |
| 第二章 天理教の世界観 |
| 月日あつてこの世界(天啓の声 ) カントとラプラースの説によれば我が太陽系統の諸天体は最初は高温の一大瓦斯球であつて太陽はその中心の核を形造つてゐたのである。然るにその温度の冷却するに連れてこの一大瓦斯球は漸次収縮した。凡て球の廻転速力は球が収縮すればする程早くなり、早くなるに従つて赤道部の遠心力の増大するのが自然の法則である。けれどもその速力が或る度に達すれば赤道の遠心力は却つて球の求心力に打ち勝ち、赤道部は球より分離してここに環を造り出すのである。彼の一大瓦斯球もこの理によつて遂に赤道部が離れて環を生じ、更にその速力の増進するに連れて分離した環は更に分離して幾條の環を生じた。而してその分離した新球は旧速力を維持して西より東に向つて廻転して居たのである。けれどもこの新球も漸次冷却収縮するにつれてその或る部分が分離した。その切れた個所は一個所のこともあれば数ケ所のこともある。一個所の時には切れた環が一塊に凝集し、数個の時には数塊に団結したのである。かくの如くして分離した球が今日の天体である。我が地球の如きもこの方法によつて生じたのである。 次には月と太陽との発生であるが月とは遊星が同じ方法にて環を生じ、その輪が分離して更に団結したものであり、太陽とは環ができてしまつた跡に残つた中心の部分の凝集したものであるといふのである。この他今日の天文学乃至地文学の学説を総合するに、地球が太陽より分離したこと並びに月の年齢は地球より古きことを否定するものはない。これ月日あつてこの世界と云ふ天啓の声と科学上の学説と期せずして一致する所以である。 今この地球の発達の歴史を分類すれば大略次の三期に区別することができる。第一期は気体の時代である。第二期は液体の時代である。第三期は固体の時代である。今日の世界は即ち第三期に属するのである。今之を天理教々理より観察すれば人類発生当時の地球は既に第一期の気体の時代を過ぎて第二期の液体時代に入つてゐたのである。而かも当時の世界には既に植物動物が人間の先駆者として表はれてゐた点より見れば、恐らく液体時代の後期に属してゐたのであらう。その後人類の発達と地球の発達とは相並行して発達し、人類が八寸に生長した時、天地海山速かに分かれたと伝へられてゐる。ミキ子はこの世界発達の状態を形容して「紙袋の膨らむ如くや」と云つてゐるが、恐らく世界発達の状態は稲の穂の実るが如く紙袋に米の充つるが如くに充実して来たものに違ゐない。けれどもこれを九億九万年水中の棲ひと云ふ天啓の声より想像して、人類の陸上生活は最近一万年以前の生活に属する故、それ迄の地球は泥海の状態にあつたと思つてはならない。今日地質学の研究がまだ充分に発達してゐないから水陸の区別を生じたのは果して何万年何億年以前であるか不明であるが、何んでも余程長い間人間は両棲生活を続けて来たものに違ゐない。 けれども天文学地質学より云つても生理学より云つても今日の世界今日の人間はまだ発達の過程にあつて完成の域に達してゐない。将来人心の改造が理想通り行はれた暁にはこの世界も亦地震、落雷、海嘯、噴火、暴風、洪水の如き変調なき理想の状態に変化すると云ふのである。これが天理教の世界観である。思ふに人間と世界の関係は蝸牛(かたつむり)と殻との関係の如く常に不可分離的関係にあるのである。その一方のみ発達して一方が遅れると云ふことはない。常に二個の線が相並行して進むが如く相並んで発達して来たのである。これは自然科学者の等しく承認する所である。 けれども人間の精神的価値の進歩に伴ふて世界の状態も全然一新理想の状態に入ると云ふ事は天理教祖によつて始めて説かれたことである。蓋し天理教の理想は彼の所謂心の入れ換へ、世の立て換へにあることは云ふ迄もないが、この世の立て換へといふ言葉の意味は単に人間社会の改造を意味するものではない。同時にまた自然界の改造をも意味するのである。即ち人間の精神状態の変化に伴つてその生活状態も一変し、その生活状態の一変すると共にその社会組織も一変し、その社会組織の一変すると共にその自然界の状態も亦理想的の順潮に一変するにあるのである。これが神の理想でありやがて天理教祖の理想である。之を要するに天理教の世界観はこの客観の世界をもつて人間と没交渉なものとは見ない。寧ろ全人類の主観の表現として見るのである。 「この世界山喰へなぞも雷鳴も地震大風月日立腹」、「雷鳴も地震大風水つきもこれは月日の残念立腹」。これによつて観れば人類の主観が変更すると同時に客観の世界は自ら変更せざるを得ないのである。従つてこの世界を地獄とするも極楽とするも谷底にするも甘露台にするも全く全人類の意志にあるのである。事実この言葉の真理は篤信なる農家の上に実現しつゝある。即ち彼ら天理教の篤信家は世間の飢饉の中に独多分の収穫を楽みつゝあるをもつても知られるのである。 天理教徒が捧ぐる朝夕の祈祷の文句に、「悪しきを払ふて助け急き込む一列澄まして甘露台」とあるは即ち人心改造の結果、この世界を宛然そのまま蓬莱の仙境無上快楽の甘露台とせんとする神の理想を歌つたものである。ここに天理教の世界観の根底がある。仏教では月日の照す範囲を十万億土と云ひ(天理教祖の説明に従へば)世界の始めより終りまでを十万億年と云ひ、末世の予言を語り基督又世界の終末期の近づけることを予言してゐる。けれども始めあるものは必ず終なかるべからざるは自然の法則である。従つてこの世界は一旦進化の極に達すれば更に退化して死と破壊の状態に入るであらう。けれども有は無を生ぜず無は有を生ぜざるは自然の法則である。従つて一度死と破壊の状態に入つた世界は草木の再生するが如く人間の再生するが如く蘇生して更に新しき世界を形造るであらう。されどその時はまだ幾億万年の後であるか、そは予言の限りでない。 吾人は吾人の前面に絶対に向つての進化と云ふ必然の運命と事業とを附与せられてゐる。吾人は唯必然の命ずるままにこの世界を甘露台化することに向つて努力しなければならない。その余の結果は唯必然の力に任ずべきのみ。これ本覚者の世界観である。この世界観は元より自分一個の想像より成れる仮設的世界観である。けれどもミキ子の想脈には少くともこう云ふ世界観が流れてゐたことは看取するに難くはない。従つて天理教の終末観は如何にも尋問せられたる場合、天理教の終末観はかくの如しと断言するも過言ではあるまいと思はれる。少くとも自分一個人は天理教々理より推論してかくの如く断定するをもつて最も至当と信ずるのである。 |
| 第三章 天理教の万有観 |
| 世界あつてそれ/\あり(天啓の声 ) この地球が太陽より分離した時はまだ高熱の瓦斯球であつたことは科学の証明する所である。それが漸次温度の冷却するに連れて気体は液体となり次第に鉱物植物動物を生ずるに至つた。けれどもその最初の植物動物は地球の状態がまだ複雑なる動植物の生活に耐へざる為にあつても最も簡単なる構造を有した動植物に過ぎなかつた。それが地球の状態が漸次高等植物高等動物の生活に耐え得る様に進化するに連れて次第に高等植物高等動物を生ずるに至つたのである。 凡そ万有特に動植物の価値を決定するに大体二つの観方がある。その一は生物学的価値である。その二は世界的価値である。第一の生物学的価値は単に構造上の価値に過ぎないからここに深く立ち入つて研究する必要はない。第二の万有の世界的価値こそ吾人の当面の研究問題である。ミキ子は動物が漸次人間に向つて進化するのは献身犠牲の生活によつて功徳(道徳的価 値)を天に積むが為であると説明してゐるが、之によつて見れば万有は夫々一個独立した価値創造体である。云ひ換へれば万有はそれ/\一個独立した日の寄進体(献身犠牲体)である。而してその日の寄進的価値の大小がやがてその物の価値を決定するのである。蓋し万有は夫々自己以上に大なる価値体に奉仕することによつて宇宙の進化に貢献するのである。そこに万有の存在の意義及び価値があるのである。ミキ子は元より特に万有観なるものを発表したことはない。従つてここにこれが天理教の万有観であるといふことを述べることは困難であるが、唯一つ万有は人間生活を完成せしむる為に神が貸し与へたものであるといふことゝ、万有は神の貸物なるが故に必要以外に之を濫費すべからざるのみならず、大にその恩を感謝せざるべからずといふことは彼女の万有観の核心を形造つてゐるのである。 蓋しこの世界に有りと凡ゆるものはそれが生物であると無生物であるとに論なく皆な一定の存在の意義及び価値を有しないものはない。之を云ひ換へればたとへ一塊の土一椀の水も之が一つ不用と云ふものはない。而かもそれが殆んど凡て人間生活を完成する為に神の貸し与へたものであることを知る時、ここに始めて神の大恩と万物の恩恵を知ることができる。天理教の万有観は即ちこの自覚の上に建てられたるものである。 |
| 第四章 天理教の人間観 |
| それ/\あつて身の内あり(天啓の声) 天理教で人間のことを身の内と云ふは美(伊邪那美尊)の内即ち伊邪那美尊の胎内より生れた者なることを意味するのである。また人間と云ふ名称の起源は人類の父親なる人魚の人とげんが良いと云ふげんとを合して人間と云つたものである。天保九年を過去に遡ること十億万年の昔神が人類を創造せんと計画しつゝありし当時は既に魚類爬虫類の如き半高等動物が全盛を極めてゐた点より見て世界は予想外に進歩してゐたことを知ることができる。神は即ちその当時に於ける最高等動物の凡ゆる特徴をとつてここに人間と云ふ新生物を創造したのである。勿論当時の人間は水中動物の凡ゆる特徴を備へた小動物であつた。それが十億年の間に種々なる生物界を通過して最後に今日の人間に発達したものである。この過去の実験によつて今日の人間は如何なる動物の心理をも理解し且つその生活を模倣することができるのである。 御筆先 「この世を 始めた神の 事ならば 世界一列皆な 我が子なり」 「この世界 高山にても 谷底も 親の為には 子供ばかりや」 「確かと聞け 高山にても谷底も 見れば月日の 子供ばかりや」 天理教の第一の人間観は全世界の全人類は神(自然)の小児であると云ふことである。云ひ換へれば大自然の分身(小自然力)であるといふことである。「この世界一列我が子なり」と云ふ神の自覚せる愛より生れたる宗教が天理教である。「世界中一列は 皆な兄弟や 他人と云ふは 更にないぞや」。天理教の第二の人間観は世界一列兄弟姉妹であると云ふことである。この二つが天理教の人間観の大綱である。彼の天理教々理の殆んど凡ては砕いて云へば親(神)と兄弟姉妹(人)とに対する円満なる関係を説明したものに外ならない。更に通俗的に云へば父母に孝に兄弟に友にと云ふことを教へたものに外ならないのである。 次には天理教の人性観である。人間性に関しては古来種々なる説が唱へられた。或る者は性善説を唱へ或る者は性悪説を唱へ又或る者は折衷説を唱へた。天理教では、「人の心といふものはちよとにわからんものなるぞ」(御神楽歌十下り目)とか、「人の心と云ふものは疑ひ深いものなるぞ」とか、「人間はあさないものである程に 月日する事知りたものなし」とか云つて人間性は信じ易く疑ひ易い浅薄な相対的有限のものであると云ふことは教祖の著書(天啓によつて書かれたもの)の随所に見えるけれども、人間性を悪なりと説いたことは一度もない。即ち「人間に悪しきと云ふて更になし一寸の埃がついたばかりや」と云ふのが天理教祖の人性観であると共に神の人性観である。 更に人間力の有限相対的なることを歌つたものには、「いかほどの強敵あらば出して見よ神の方には倍の力や」、「いかほどの強敵たりと発明でも 神の力やこれは叶はん」の如き即ちそれである。之を要するに神とは大自然力、人とは小自然力である。従つて前者の力は絶対無限であり、後者の力は相対有限である。けれども相対がなければ絶対なく絶対がなければ相対がない。云ひ換へれば神あつての人、人あつての神である。この絶対と相対との一致云ひ換へれば神と人との抱合、そこに始めて人生の妙味があるのである。彼の御神楽歌九下り目及び三下り目の 「神の心に凭たれつけ」とか「神に凭れて行きまする」とか言ふ言葉は即ちこの絶対者と相対者との抱合を歌つたものである。 天理教では基督教の如く人間全体の堕落を説かない。人間その者は始め下等動物の形に造られ漸次神の力によつて今日の人間に進化発展せしめたものであり且つ将来に亘つて無限に向上進化せしむるものであると説くのである。元より中には進化を停止して却つて人間以下の世界に堕落して行く者もある。(天理教では牛馬は人間の中で罪の重い者が堕落したものであると説くのである)けれども、その大多数は退化するにあらずして進化しつゝ あるのである。これ人間堕落説を主張する基督教と全然その人間観を異にするのである。けれども之を公平なる立場より両者の所説を批評する時は、現在の人類は或る完全なる者より不完全なる者に堕落して行くのではなく、全く不完全なるものより完全なる者に向つての向上進化の過程にあるのである。これは啻に世界文明史の認むる所であるのみならず凡ゆる生物学の認むる所である。天啓に「人間は今迄どの様な者にも生れて来たから、どんなものゝ真似でもできんことはない」とある如く、今日の人間は生物界の凡ゆる階級を通過して遂に今日の如き生物界の最高地位を占めて居るのである。 けれども今日の人間はまだ真に完成の域に達してゐない。その中で比較的完成の域に近づけるものが今日の所謂文明人である。けれども今日の所謂文明人と云つてもまだ甚だ幼稚なるを免かれない。唯これら人類をして完成の域に達せしむるには時間と努力とが必要である。ミキ子はこの人類永遠の向上進化の努力を称して「限(きり)なし普請」と云つた。蓋し人類永遠の創造的進化を意味するのである。 以上は天理教の人間観の大体であるが、之を要するに神の人類に対する要求は全人類を して神子(自然児)の自覚と神子の生活とを得せしめんとするにあるのである。云ひ換へれば第二の神々を創造するにあるのである。この神の終局の大理想を啓示したのが天理教である。 |
|
第五章 天理教の法律観 |
| 身の内あつて律がある(天啓の声) 以上述べたる所は何れも天理教の新人生観を語るに最も有力なるものであるが、就中この天啓の声の結論に近き重要なる価値を有するものはこの一句である。この一句は人間と法律との関係を述べて当時法律を盲目的に恐れてゐた無智の信徒の自覚を促したものであるが、これは当時の信徒に限らない、今日でも真に人生と法律との関係を明かに自覚してゐる人間は少ないのである。そう云ふ人達は法律は国民の生命財産を保護する国民相互の後天的約束なることを知らないで、唯それをもつて暴君の如くに恐れて居る。そう云ふ無智の人達に向つて真の法律観を教へたものがこれである。蓋し吾人が法律を尊重する所以は、それが或る程度迄吾人の幸福の保護者たるからである。元より絶対のものではない。従つてそこに法律以上の絶対価値を有するものゝ表るゝ場合には法律を捨てゝもそれに従はなければならぬ、天啓の最後の句は即ちこの絶対者たる信仰と相対者たる法律との関係を述べたものである。 |
| 第六章 天理教の信仰観 |
| 律があつても心の定めこれが第一(天啓の声) 明治二十四年一月廿七日夜九時の刻限「神の道、上の道一寸云へば同じ事。上の道とは世上の道。神の道とは胸の道。世上の道はどんな事して居ても通つて行けるなれど、胸の道は皆な身にかゝる。道に二つあつて世上の道は眼にさへ見えにや通つて行ける。世上の道にはどんな穴があるやら知れん。神の道は胸三寸の道であるから通らうと思ふても通れん。これさへ充分説き聞かせばどんな事も皆な治まる」。凡そ宗教と法律との相違は一は自然の法則にして他は人為の法則一は神の約束にして他は人の約束たる点にある。従つて一は先天的にして他は後天的、一は絶対的にして他は相対的、一は外延的にして他は内包的である。それが主観化せられて人間生活の中に織り込まれて来た時、信仰となり政治となるのである。この法律と信仰との関係並びに政治と宗教との関係を的確に説明したものが如上の天啓の声である。 之を詳しく云へば法律とは即ち人間が共同生活をなすについて相互の安全を保証する必要上定めた一種の人為的の約束である。之に反して宗教とは神(自然)が宇宙の統治上定めた天然自然の約束である。従つて一は後天的の約束に属し他は先天的の約束に属するのである。 けれどもこの二つは全然固定的なものではない。常に人間の進歩に伴つて進歩発達するのである。これは法制史並びに宗教史の証明する所である。蓋し法律とは之を云ひ換へれば眼に見ゆる外界の法則である。之に反して宗教とは之を云ひ換へれば眼に見えざる内界の法則である。一は帝王の権限に属し他は神の大権に属するのである。この二者は常に内外表裏より相待つて人間を幸福の世界に導いて来たのである。けれども法律の欠点として法網を潜つて悪事を働く犯罪者を取締る力もなければ処罰する権力もない。この法律の遁竄者を攫へる為に眼に見えざる神の法網が布かれてある。それが即ち宗教である。従つて真にこの世界を統治するには不完全なる有限の法律の力に委任することはできない。どうしても宗教の力を借りなければならない。 明治廿四年二月七日夜二時の刻限「さあ/\刻限を以つて話し掛ける。どう云ふ事話し掛けるなら、もふ一日の日もよふの日あけるなり一つと云ふ。如何なるも皆んな今一時筆に書き取る処一日の日が経つ。一日の日が移る。五年/\と五年の日に移る。四方/\処々にも何れ/\五年/\どう云ふ 事万事何かの事話し掛けるによつて事情は一つ。人間の心と云ふはさら/\持たぬ様五年経つたらどう云ふ道とも訳ろまい。世界の道も訳ろまい。一年経てば一つの事情。また一年経てば一つの事上。年にとりて六十一年お蔭/\と待ち兼ねた。又一つには改正/\と 云ふ明治の代と云ふ国会と云ふ知らず/\待つて楽しみはさらにあらうまい。一夜の間の事情を思案せよ。国会二十三年と云ふた。また一つの事情。又お蔭/\の事情よふ思案せよ。 さあ/\明ければ五年と云ふ。万事一つの事情を定めかけ。定めるには人間の心は更々要らん。弱い心は更に持たず気兼遠慮は要らん。さあ思案してくれ。これから先は神一條の道、国会では治まらん。神一條の道で治める」は即ち法律時代の後に必らず宗教時代の来るべき予言である。その予言の実現せられた時こそ真に人生が根本的に改造せられた時である。 明治廿五年五月十六日午前九時 「今の処は二つある。一つの道は表の道。一つの道は心の道や。表の道一寸の道や。心の道は違はして何んならん。訳らんから皆な見免してある事を何んな事であつたやらなあ見免してあるから遅れて何んならん。胸の道あればこそ是迄通つて来た。これをよふ聞いてをかねばならん。世界道と云ふものはとんと頼りにならん。確つかりした様でフワ/\してある。世界の道に力を入れると胸の道は薄くなる」と。之を要するに宗教と法律との関係は太陽と提灯の関係である。太陽のまだ昇らざる間は提灯は唯一の光明であるであらう。けれども一旦太陽の昇つた暁には誰も提灯を点じて途上を歩く者はないであらう。その如く将来天理教の信仰が全人類の精神深く徹底して行つたならば法律は全く無用の贄物となるであらう。蓋し宗教は第一義である。法律は第二義である。信仰は第一義である。政治は第二義である。従つて真にこの世界をして理想の世界たらしめんと欲せば法律改正や政治の改良の如き皮相の改革ではならない。どうしても真に全人類をして宗教的に自覚せしめなければならない。然らばこの世界に自ら無法律の時代が実現して来るのである。 天啓の結句「律があつても心の定め之が第一」は即ちこの信仰の絶対価値を肯定せるものである。教祖ミキ子が折々子供に向つての教訓に「人は道がなくては何処へも行かれんで。お婆様は人の心に道をつけるのやで。お前達を良い所へ導いてやるで」 と。凡て人をして安全に目的地に達せしむることを得るのはこの地上を走つて居る有形の空間的道路があるからである。けれども多くの人はそれと対して天上を走つて居る無形の時間的道路のあることを知らないでゐる。その無形の時間的道路こそ即ち宗教である。けれども普通道路に新道と旧道とある如く精神的道路にも亦新旧の別がある。ミキ子は即ちその無形の新しき時間的道路を人の精神界に開拓せんが為に或は衣食住と断ち或は親戚故旧と断つてその信路を一直線に貫通した。ここにミキ子の絶対的信仰観がある。 之を譬へて云へば信仰は根である。法律は枝葉である。従つて信仰の根が広く深く強く張れば張る程その人、その家、その村、その町、その郡、その県、その国、その社会は栄えるのである。之に反してその信仰の根が狭く浅く弱まるに従つてその人、その家、その村、その町、その郡、その県、その国、その社会は衰へるのである。之は歴史上に表はれたる偉人強国の歴史に徴して明きらかである。こう云ふ点より結論して信仰は人間生活の源泉であるといふことができる。天理教の信仰観は即ちこの現実的要素の上に立てられたる人生の出発点であり且つ人生の帰着点である。 |
| 第七章 天理教の生死観 |
| 天理教では生れるといふ言葉は用ゐるが死ぬといふ言葉を用ゐない。もし死ぬといふことをいふ場合には「出直し」とか「お迎ひ取り」とか「お引き取り」とか云ふのである。就中最も多く用ゐる言葉は「出直し」と云ふ言葉である。「出直し」とはこの世界に生存する時が充ちて再生もしくは再来する為に一旦この世界を去ることを云ふのである。また死ぬことを「お迎ひ取り」とか「お引き取り」とか云ふことは凡てこの世に生れるも死するも皆な神の意志に依つて行はれるからである。
御筆先の「このところ止める心で来るならば、そのまま何処へ月日出るやら、出るのもな 何んな事やら知ろまいな。月日迎いに出るで承知せ」の如き、「胎内へ宿し込むのも月日なり、生れ出すのも月日世話取り」の如きは即ち生死は神の権能に属することを歌つたものである。 之を詳しく云へば、人間の生れる時は大戸辺尊と大食天尊と国狭土尊との三神が揃はなければ産はできないのである。三神の手が揃つて大戸辺尊が胎内より子供を引き出し、大食天尊が母体との縁を切り、国狭土尊が後の皮継ぎをして母子共に健全に発育するのである。よつて子供をもふけることを産をする(また子供を喜ぶとも子供を授けて貰ふともいふ)と云ひ産の神と産(三)神を云ふのは三柱の神の御守護によつて生み且つ生まれるからである。また死ぬ時、この世の縁を切るのは大食天尊である。と云ふのは生死共に人間力にて行はれるものではなく分娩力、切断力、継続力と云ふ自然力が加つて始めて生死の事実が実現せられるのである。畢竟生理的の死とは神の貸物なる肉体を神に返済するの謂にして生理的の生とは神より身上を貸し与へられることを云ふのである。 教祖の次の言葉は天理教の物質的生死観を最 も明瞭に説明したものである。曰く「身体は神の貸物だで、古くなつたらお返し申してまた新しい身体を貸して貰ふのやで」と。更に死後復活迄の径路を説明して「何処へも遣りやせんで。元へ元へと返へすのやで。彼はお爺様に似てゐる。お婆様に似てゐると云ふやろ。似てるのやない、正の者を返へすのだがわかりやしやうまい」と。之には多少の注釈を要する。と云ふのはその人の因縁即ち生活価値の善悪によつて必らずしも前世貴族であつたから今生も貴族に生れ、前世平民であつたから今生も平民に生れ、前世動物であつたから今生も動物に生れ、前世人間であつたから今生も人間に生れると云ふことはできないからである。凡て皆な一定の年月の後自分の持つた魂の価値に相応した世界に生れ出るのである。例へば今生因縁の悪い人もその積んだ功徳によつて来世は幸運の家に生れ今生因縁の善い人も不徳を積めば不運の家に生れ、甚しきは畜生界に堕落する 者さへあるが如きものである。「だん/\と恩を重ねたその上は牛馬と落ちる道があるなり」(御筆先)。 次には年齢の問題である。年齢もその人の因縁によつて一様ではない。一日を一生とするものもあれば十年百年を一生とするものもある。御筆先には、この世の人間は皆な神の子や、神の云ふ事確かと聞き分け、埃さへすきやか払ろふた事ならば、後は珍らし助けするぞや。真実の心次第のこの助け、病まず死なずに弱りなきよふ。この助け百十五歳の定命と定めつけたい神の一條、とある。即ち之によつて見れば、人間はその精神が健全化せられた暁には百十五歳の定命 を享け更に神の絶対境に迄進化したならば不老不死の仙境に入る事ができる。 以上は主として天理教の物質的生死観を述べたものであるが更に之を精神的方面より観察すれば人類の霊魂は今日迄退化もしくば進化を経験して来たがまだ死を経験したことはない。彼の精神的の意味に用ゆる「生れ更り」と云ふ言葉は霊の一段の進化を意味せるものに外ならない。今日の所物質不滅の法則は一部科学界の疑問になつては居るが、さればと云つて何人も今日の所有より無は生ぜず、無より有は生ぜずと云ふ宇宙の原則を明かに否定し得るものはない限り、吾人は進んで物質不滅の法則を信ずると共に更に霊魂不滅の法則を信ぜんとするものである。その論拠は再生の事実に基くは云ふ迄もないが更に一つの補助観念は、生は死を生ぜず死は生を生ぜずと云ふ前法則の姉妹法則である。吾人の霊魂はエネルギーの法則に従つて積極力が消極力に変ずることはあつても生命力そのもの、霊魂そのものが消滅することはないのである。普通云ふ所の死とは即ちこの積極力が消極力に変化して行く状態をさして云ふのである。 尚ほこの問題は後の天理教の霊肉観に於て述べる心算であるが、一言この問題の結論と して云つてをくことは、天理教では生理的乃至心理的の大小の変化は認めるが、真に世人の考へて居る様な死即ち無と云ふことを認めないことである。天理教で認むる所は唯古き肉体を捨てゝ新しき肉体を衣、古き思想を捨てゝ新しき思想を求むるの一事あるのみ。これが天理教の物質的乃至精神的生死観である。 |
| 第八章 天理教の霊肉観 |
| 霊肉の問題は今日でも屡々起る所の問題であるが在来の宗教哲学乃至倫理道徳の多くは概して霊を善とし肉を悪とし霊を尊とし肉を卑として来た。その結果、霊を神もしくば天使に擬し肉を悪魔に擬するに至つた。彼の有名なるゲーテのフアウストの如きも全くこの霊肉を人格的に取り扱つたものに外ならない。けれども天理教の霊肉観は全然在来の宗教哲学乃至倫理道徳とその観方を異にしてゐる。即ち仏教でも古神道でも女子の月経は不浄のものとして月経期の女子は神社仏閣に参ることを禁じたものであるが、天理教では穢れ不浄はこれ云はん。心の穢れが身の穢れと云つて物質乃至肉体の不浄を論じない。天理教でやかましく云ふのは精神が澄んで居るや否やの問題である。 これについて一つの逸話がある。或る時、山本利八氏が教祖の前に出た時、教祖は山本氏に「利八さん外の方を見ておいで」と命じた。当時は警察の監視の厳しい時代であつたから、その心算で外へ出て四辺を見たが誰も居ない。帰つて来て教祖に云ふには「神さん(その頃は教祖を神さんと云つてゐた)何んにも変りはありやしません。向ふの畑には南瓜がなつてゐます。こっちの畑には茄子が沢山でけました」。教祖はそれを聞いて膝を打つて、「それ/\あの南瓜や茄子を見たかへ。大きい実がなつてゐるが、あれは花が咲くから実があるのやで。花が咲かにや実がありやせんで。そこで良ふ思案して見いや。女は不浄やと世上で云ふけれども、何も不浄な事あありやせんで。男も女も寸分違はぬ神の子や。女と云ふものは子を宿さにやならん一つの骨折りがあるで。女の月経はな花やで。花がなうて実がのらうか。能ふ悟つて見や。南瓜でも大きな花の美しいのに無徒花といふがあるやろ。あれは花が散ればそれ限りのものやで。無徒花と云ふものは何んにでもあるけれどな。花なしに実がのるといふ事はないで。能ふ思案して見りゃ何も不浄やないで」。これを今日の人間より見れば女子の月経は最も自然なる生理的変化であるから何ら不浄視するものはないが、当時の社会にあつては一種の新説であつたのである。 天理教では、身体は神の建て流しの館と云ひ、心澄み切れば神同体と云つてゐる。この意味は人間の肉体は神の借家である。そこに神と同一の精神が宿つて始めて神の社となるのである。かくの如く天理教では霊を自分の物、肉は神の物といふ区別は立てゝも、霊を尊とし肉を卑としない。否な却つて之を尊重するのである。その理由は肉体は元来神の貸物なるが故に之を汚損することは貸主なる神に対し申訳ないと云ふ観念に基くのである。この観念より天理教では文身とか点灸とか負傷とか自殺とかを最も嫌ふのである。就中自殺といふが如き不自然の方法にて身上を神に返したものは来世には再び人間界に生れ得ないものとしてゐる。この点に於て天理教は最も自然にして且つ最も進歩せる霊肉観を有してゐるのである。 かくの如く天理教の肉体を尊重すること他の宗教に越えたりとはいへ、元よりこれに対して第一義的価値を附する訳ではない。明きらかに霊を主とし肉を従とし霊を第一義とし肉を第二義としてゐるのである。之を詳しく云へば人間の肉体はその者の精神的価値に対して貸し与へられたるものである。更に云ひ換へれば人間の肉体は精神の反映であると云ふことができる。これを称して天理教では 身上は心の鏡といふと云つて居る。蓋し一切の心理状態は凡て生理的に肉体に表れることを云ふのである。例へば健全なる肉体には健全なる精神が宿り、不健全なる肉体には不健全なる精神が宿るが如きその一例である。 以上は天理教の霊肉観の大体を述べたものであるが最後に取り残されたる重要問題は心理的要求と生理的要求との衝突した場合である。例へば我は今飢渇に瀕してゐる。けれどもそこにある食物は自分のものではない。この場合、自己の生理的要求に従へば心理的要求即ち良心と衝突する。また心理的要求即ち良心に従へば自分は餓死しなければならぬ。ミキ子はこう云ふ場合に臨んで、「身体は神の貸物だ、水を呑んでも死ぬことあるまい」と云つて不浄の弁当で敢て飢渇を禦がうとはしなかつた。何故なれば人間の肉は霊の真実、自然の要求を満足せしむる為に神の貸し与へたものであるからである。従つて真実自然の心理的要求を充たす為には時として生理的要求を犠牲にすることは止むを得ないのである。これが天理教の主観的霊肉観である。之を要するに天理教では客観的には霊肉の平等を認め主観的には差別を認むるのである。この平等兼差別的霊肉観に天理教の新霊肉観があるのである。 |
| 第九章 天理教の物質観 |
| 従来の宗教はやゝもすれば肉体と共に物質を卑しむ風があつた。その反動として今日は極端なる物質的傾向を帯びて来た。元より絶対に喜ぶべき現象でないとは云へ確かに一部の理由はあるのである。天理教の物質尊重の観念は肉体尊重の観念と同じく貸物借物の理より来たものである。即ち金銭でも物品でも凡て皆な神の貸物なるが故に之を粗末にするは勿体ないと云ふ点より来たものである。その結果三千年来金銭の価値を知らなかつた日本人に確かに金銭並に その他の物質の価値を知らしめたのである。と云ふのは今日迄の日本人はやゝもすれば金銭の事を口にするを恥づる風があつた。その結果として一部の上流社会には金勘定を知らぬものがあつた。就中最も厭はしきものは故意に傲放淡泊を装ふ所謂東洋流の豪傑と、金の為には眼のなき強欲の守銭奴である。彼らは二人共金銭の価値を知らない。何故なれば真に金銭(天理教では金銭のことを一名継ぎと云ふ)の価値を知つてゐるものは、出すべき所には数百万円をも惜まず、出すべからざる所には一文も出さないからである。こう云ふ調子外れた日本人に多少なりとも金銭の価値を理解せしめたものはミキ子である。彼女はたとひ紙一枚銭一文と雖も粗末にはしなかつた。また出すべき時には全財産は勿論のこと生命その物迄も施すことを惜まなかつた。けれども普通人にとつては倹約は往々吝嗇となり出費は多く濫費となり易きものである。その物質の濫費の結果が即ち乞食となるのである。それでミキ子は屡々乞食を引例に信徒を戒めて云ふには 「世間では乞食/\と云つて厭がるけれども、あれも矢つ張り神の子供だ。可愛がつてやつてくれ。彼らは前世でこれでは食へん、彼れでは食へんと云つて食を粗末にした報いで今生は人の門に立つて物を貰つて歩くのやで」と。蓋し濫費は吝嗇(惜しみ)と等しく罪悪である。それを知つてゐる者は或は多いであらう。けれども宋襄の仁が屡々濫費に陥つてゐることを知つて居る者は真に少い。ミキ子は乞食を憐れめと云つても五体の自由に叶ふ横着な乞食に物を与へよとは教へなかつた。何故なれば彼に物を与へることは却つて彼らを亡す原因であるからである。之を要するに凡ての物質は神が生活の必要上貸し与へたものである。従つて必要以上にそれを濫費することも罪悪なれば必要以下に吝嗇することも罪悪である。要は唯必要を充たせば足るのである。然るに多くの人間は一人にて二人前も三人前も貪り中には一人分を二分しもしくば三分して蓄財するものがある。その何れも生の真義に叶つたものではない。人は一人なる以上一人の生活資料より以上にまた以下に求むべきものではない。それより余つたならば神に返し不足したら神より借りるだけである。これが天理教の物質観の結論である。 |
| 第十章 天理教の両性観 |
| 凡そ様々の人生問題中最も吾人々類に重大な意味をもつてゐるのは両性問題である。何故なれば性の問題は直ちに生の問題であるからである。少くともその根本問題であるからである。然るに従来の宗教は多くこの問題を根本的に解決することを恥づるの風があつた。為にこの主要な人生問題は今日迄殆んど無解決のままに残されて来たと云つて良い。少くともそれは不徹底の解釈の下に葬られて来た。この際に立つてこの問題に対して最後の解決を与へたものが天理教である。天理教の聖典御神楽の開巻第一に次の言葉が書かれてある。「ちよと話し神の云ふこと聴いてくれ。悪しきの事は云はんでな。この世の地いと天とを象どりて夫婦を拵らへ来るでな。これはこの世の始めだし」と。 従来の宗教別けても仏教の如きは最も大なる両性生活の呪誼者であつた。彼にあつては男女の性交と云ふが如きは救ふべからざる大罪であつた。その結果は多くの不自然なる独身生活者を産出した。今尚ほ産出しつゝある。彼の両性生活に比較的大なる意義を認めた基督教の如きすら両性生活の大なる避忌者をつくつた。然し彼らは何も両性生活が自然であるか不自然であるかと云ふ問題を自覚した結果ではない。唯先人の誤れる人生を盲目的に信じてそれに合せんとして性欲と無益の苦闘を続けて来た迄である。これは独り生欲の主脳である性欲に対して計りではない。食欲とか住居欲とか睡眠欲とか社交欲とか云ふ者に迄無益の反抗を続けて来た。その結果はどうであらう。個人は衰弱し社会は疲弊して来た。こう云ふ虚偽と不自然とに充ちた社会の病弊を救ふ為に表はれた近代的偉人は僧親鸞であつた。彼の識見は当時に於ては実に群を抜いてゐた。けれども彼を始めその弟子もまだ人間生活の根本義に徹底して居なかつた為、末世の僧俗に多くの堕落者を生んだのは悲しむべきことである。 この人間生活の欠陥を救ふべく表はれたのが天理教である。天理教では性欲を始め凡ゆる自然の生欲より生るゝ一切の人間生活は凡て皆な肯定する。家庭生活でも社会生活でも。この点に於て天理教は真宗と最も多くの共通点をもつて ゐる。けれども天理教の生欲を肯定する態度は真宗の如く半自覚的ではない。又彼の如く消極的ではない。一層根本的であり一層自覚的であり且つ一層積極的である。ここに挙げたる「この世の地いと天とを象りて夫婦を拵らへ来るでな、これはこの世の始めだし」と云ふ御神楽霹頭の文字は即ち両性生活の最も強き肯定である。夫婦が天地陰陽の表象(生命力の両面の表れである)と云ふ思想は古くより伝はつた東洋伝来の思想であるが、ここに何故に「天と地いとを象りて」と云はずして「地いと天とを 象りて」と云つたかと云へば、一つは口調の為と他の一つは、女は「この世の台ぢや」と云ふ意味より地を先にして天を後にしたものである。元より女尊男卑を意味したものではない。 これは二大自然力の別名である国床立尊と重足尊との神性を研究すれば明きらかである。即ち国床立尊(月)の神性は水性である。また重足尊(日)の神性は火性である。普通の考えによれば月の偉力は太陽の偉力に及ばない様に考へるであらうが、之を水と火とより論ずれば火は如何に強くとも水に打ち勝つべからざる自然の運命を有して居るが如きものである。この点に於て男女両性の関係は一面に於て差別的である。けれども之を他の一面より観察すれば水があつても火がなければ生活することができない。水気温味即ち冷熱二個の力が調和して始めて体温を適度に保つが如く男女二個の力が調和して始めて人生を円満に保つことができるのである。この点に於て男女両性の関係は平等である。御筆先の「この木いも雄松雌松は云はんでな、如何なる木いも月日思はく」は即ちこの男女両性の平等相即ち男女同権主義を歌つたものである。 明治三十一年十月二十六日、「この道どう云ふ事から成つた。男女隔てない。一つの台にして始め掛けた。この理はト ント分り難ない。この道の始めた教祖一代の所は女、後席は男女の隔てあるかないか。この順序の理を日々取り次ぎ男女の隔てない」。之を要するに天理教で云ふ男女両性の差別は心理的乃至生理的の先天的差別(これは後天的に変更すべからざるものである)であつて人格的乃至道徳的の差別ではない。少く とも男女両性の人格乃至道徳の実質的差別ではない。これは男を人と呼んで女を人と呼ばざることなきと同様に真理である。唯男性的人格もしくば女性的人格、乃至男性道徳女性道徳の差別はある。けれどもその人格的価値乃至道徳的価値は男女によつて何らの差別はないのである。この男女の同権は「男も女も同じ神の子供やで」と教祖の言葉が之を証明してゐる。 けれどもここに注意しなければならぬことは、男女は同権なるが故に男と同一の職業を男と同一の生活をなさんとする所謂近代的女性の考へてゐる男女同権と天理教で云ふ男女同権の相違である。天理教では男女の人権を両者共に同一に認むるけれども、それと共に女には女の道があると云つてその職業や生活迄も同一視しない。例へば、男は外を働き女は内を働くとかまた細かいことは女がし荒いことは男がすると云ふ様に男女両性の天分に従つて生活することを教ゆるのである。即ち天理教では男性生活乃至女性生活に限らず一般人間生活に於ても一つとして不自然(無理)の生活法を教へない。凡て皆な真実自然の先天性に従つて生活すべきことを教へざるものはないのである。 もし男性も女性も同一の職業を営み同一の生活を行ふべきものならば、始めより男女の必要はないのである。苟くも男女両性の差別がある以上はそこに心理的乃至生理的に異つた天分がなければならぬ。これは凡ての個人に通じて同一である。即ち凡ての人間が農となり凡ての人間が商となり凡ての人間が工となるべきものならば、この広大無辺の人間生活は忽ちにして停止しなければならない。これ人間に個性の必要なる所以である。これと同一の原理が男女両性間にも行はれつゝあるのである。この法則を称して分業律と云ふ。社会の進歩は実にこの分業の盛衰に正比例するのである。 その最も良き実例はアミーバである。彼には両性の区別がない。また分業の区別がない。何処迄も単細胞のままに原始的生活を継続しつゝあるのである。然るに漸次高等動物になるに従つて性の区別を生じ個性と分業を有するに至るのである。こう云ふ意味に於て男女両性はその人格的価値に於て益々接近すると共にその生活の形式は益々分離すべきものである。そこに性の進歩がある。性の進歩はやがて生の進歩となるのである。然るに従来の宗教哲学倫理道徳はこの男女両性の平等性と差別性とを明かに区別することができなかつた。それが為に人類分けて女性は長い間囚れた牢獄の中に不自由な生活を続けなければならなかつた。この不自然の牢獄より人間性を解放し男女両性を解放したものが天理教である。天理教は恋愛及び結婚の自由を尊重する。けれども天理教の云ふ恋愛とは単なる性的愛ではない。その人格的愛である。更に云ひ換へれば信仰と信仰との共鳴である。且つそこに性的愛を超越した人間的愛がなければならぬ。この点に於て天理教の恋愛は今日の動物的恋愛とその高さ広さ深さ強さを異にするものである。 次には結婚の自由である。天理教で云ふ結婚は単なる性欲の満足ではない。異性の人格的結合である。こう云ふ徹底した結婚に向つて元より結婚を承認しない筈はない。けれどもここに一つの問題は自由と我がままとの区別である。自由とは即ち自己の行為に対する責任を感ずるものを云ひ、我がままとは自己の行為に対する責任を感ぜざるものを云ふ。之を結婚に就て云へば一時の感情や利害関係によつて結婚もしくば離婚するものはこれは自由結婚にあらずして野合結婚である。真の自由結婚とは如何なる境遇に於ても変ることなき真情と真情との結合でなければならぬ。かくの如き結婚に向つては人は許さずとも神が許すのである。けれども貸物借物の理より云へば十五歳以上の男女に向つてはたとひ親と雖も強制結婚を強ゆるの権利がない。また自由結婚を制止する権利がない。これ人間の自由意志は神より与へられたる特権であるからである。けれどもこの場合には責任は移つて結婚当事者にあることは云ふ迄もない。もし結婚当事者にしてその結婚より生ずる一切の責任を負ふ力がなかつたならば、それは結婚する資格がないのである。凡て人間は恋愛の自由、結婚の自由のみならず信仰の自由も不信仰の自由も愛の自由も憎の自由も天より許されてある。けれども予め凡ての人間の心得なければならぬことは自分の蒔いた種は自分が苅り取らなければならぬと云ふことである。こう云ふ條件の下に天理教は恋愛並びに結婚の自由を承認するのである。 以上は天理教々理より見たる両性観の大体であるが之を要するに男女両性は各々人生 の向上発達の責任体である。従つて未婚者も既婚者も常にこの責任観念に生きざるべからず。天理教の両性道徳一夫一婦主義はこの責任観念より生れたのである。 |
| 第十一章 天理教の病理観 |
| 天理教の特種の新人生観の一つは一切の生理的故障は心理的故障の反映であると云ふ所謂精神的病理観である。この問題は既に前説の天理教教理中に略述したからここに再び繰り返すことを省く。唯一つ云つてをきたいことは人間が進歩すればする程疾病も進歩すると云ふことである。これは彼の動物病の種類を研究すれば訳る。即ち動物病の数は人間病に比してその種類が少い。等しく人間と云つても彼の乞食労働者の如きは疾病の種類も単純な疾病が多い。然るにそれが漸次精神内容の複雑なる所謂文明人乃至上流社会になればなる程その疾病の性質は複雑になるのである。これは人間の心理が複雑になればなる程その心理的故障も複雑になり、その心理的故障が複雑になればなる程その生理的故障も複雑になるのである。その証拠には下等動物下等植物程疾病の種類が単純であり遂に無生物に至つて全く根絶するのである。凡そ生あれば疾あり、疾は生に伴ふ一種の障害である。 その障害を除去するには先づ第一に心理的故障を除去しなければならぬ。それが疾病を根絶する唯一の根本的治療法である。これが天理教の病理観とその治療法であるが、将来この病理観が普及したならば人類は第一に高価なる診察料と無法の薬価とより救はるゝのみならず更に肉体的に精神的に苦痛と罪悪とより救はれるのである。こう云ふ点からして天理教がこの点に主力を注ぐのは寧ろ当然の事である。 之を要するに人間は従来疾病の器としては作られなかつた。その疾病の器として病床(教祖はこれを布団牢と云つた)に呻吟しなければならぬのはその者の精神に於て天理人道と合せぬ不自然な精神があるからである。天理教が最後に疾病門を開いて漸次この世界を根本的に救済せんとするのは最も卑近にして且つ要領を得たる社会の根本的改造法である。 |
| 第十二章 天理教の運命観 |
| 凡そ影あれば形あり、形あれば影あるのは自然の事実である。この形と影との関係が恰度性格と運命との関係である。この関係に就ても前説の天理教々理中に一寸暗示してをいた筈であるが、今之を歴史上の人物に就てその実例を求むれば、彼の戦国時代の三大英雄たる信長と秀吉と家康とである。この三者は夫々歴史上稀れに見る英雄であつたが、その中前二者は一旦は天下の覇権を握つても遂に最後の勝利が家康に帰したのは最も深く味はふべき史実である。今之を三者の性格より観察すれば、信長は古今稀に見る勇者であつた。けれども短慮にして人を容るゝの雅量に乏しかつた。この短慮と狭量とは計らずも名将明智光秀の反感を買ひ遂に本能寺に戦死するに至つたのである。また秀吉はその智に於て古今稀に見る名将であつたけれども、その智は一時的にして遂に老将家康に天下を渡さなければならなかつた。最後に家康である。彼は智と勇とに於て遥かに秀吉信長に及ばなかつたとは云へ、その天賦の仁徳は遂に前二者に代つて日本六十余州の覇者たることができたのである。 之は最も著明な一例に過ぎないがこの他東西古今の人物に就いて観察すれば不思議にも性格と運命との一致を発見するのである。由来運命は正直である。それは曲つた棒に真直な影のさゝない如く曲つた性格に真直の運命は決して来ないのである。また真直の性格に曲つた運命は来ないのである。もし来ればそれは過去の性格の反映に外ならないのである。従つて運命を改造せんとせば先づ性格を改造せざるべからず。これが天理教の運命観である。 |
| 第十三章 天理教の家庭観 |
| 古来宗教といふ宗教の中で凡そ天理教程家庭生活を尊重する宗教はあるまい。これは教祖の一生が何よりの生きた証拠である。今彼女の一生の生活より観察すれば、所謂宗教家たることは彼女の一生の目的ではなかつた。それが往々信徒が殖えた為に遂に立つて人類教育家となつたのである。これは彼女の思想を研究すれば明かなることである。即ち彼女は人は皆な何人も朝起き、正直、働きをしなければならぬ。家業第一に親孝心をせよとは教へたが、人は皆な宗教家たらざるべからずとは教へなかつた。何故なれば彼女の理想は宗教家として生活するよりも人間として生活することにあつたからである。少くとも客観的には宗教家であつても主観的には人間であることあらしむることが彼女の理想であつたからである。彼女が家庭を離れずして円満なる人間生活の雛型を示したのはこれが為である。即ち釈迦及び釈迦の弟子にとつては人生の牢獄であつた家庭は、彼女にとつては当然人間として持たねばならぬ小社会であつた。この一面に於て家庭の一員とし他の一方に於て社会の一員として模範的人間生活を行つた点が彼女の新世界の救世主として大なる価値の存する所である。 之を要するに従来の宗教家は何れも家庭の必要とか家庭の真味とかを知らなかつた。ミキ子によつて始めて家庭生活の真味が一般に紹介せらるゝ様になつた。蓋し人間はこの世界に生れたる以上生き甲斐のある生活を行はなければならぬ。それには自分一身を生き甲斐のある人間たらしむることの必要なることは云ふ迄もないが自分の住んで居る家庭、自分の住んで居る国家、自分の住んでゐる社会を真に快楽に充ちたるものとしなければならない。彼女はその家庭、国家、社会をして真に快楽に満ちたる家庭、快楽に充ちたる国家、快楽に充ちたる社会たらしむるには互ひに同情と親切とに生きなければならぬことを教へた。即ちその結果は「一月三十日は三十日共陽気な笑をもつて梁木を揺ぶる」様な賑かな家庭となるのである。それで「内々睦じく」と云ふのが天理教の家庭に対する理想である。 以上は天理教々理より見たる理想の家庭観を述べたものであるが以下に少しく天理教々理より観たる現実の家庭観を略述せう。天理教では家庭を分ちて、一、敵の因縁、二、味方の因縁 の二つとする。敵の因縁とは互ひに怨を構へた因縁同士の集合である。また味方の因縁とは互ひに意気投合した親しい間の関係である。それで天理教々理より家庭を定義すれば、家庭は因縁の集合なりと云ふことができる。けれどもその内部に立ち入つて観察すれば以上挙げたる二種の家庭が存在するのである。かくの如くどんな子をもつのも、どんな親をもつのも、亦どんな夫をもつのも、どんな妻をもつのも、どんな兄弟をもつのも、皆なこれ自己の因縁なれば善い因縁の集合は云ふ迄もなく、悪い因縁の集合は互ひに同情と親切とをもつて因縁の果し合ひをしなければならぬ。神の因縁を寄せ集めたのはこれが為である。 之を要するに家庭とは社会の単位をなす一個独立した小社会である。その健全と不健全とは個人の直接の幸不幸に関するのみならず間接に社会の盛衰に関するのである。従つて家庭をもつて住むに快き小社会となすのみならず、之を清潔化し健全化することは家庭の各員の義務であり且つ特権である。 |
|
第十四章 天理教の国家観 |
| 天理教より云へば国家とは家庭と同様に一つの因縁によつて結合せる一大団体である。その中で日本民族は伊邪那美尊が人間生み下ろしの第一番に大和に生み下ろした人間であるからこれを大和魂と云ひ人類の兄姉である。またその他の諸外国民はその後大和以外の諸国に生み下ろした人間が漸次水草を追ふて諸国に移住したものであるから之を日本国民より云へば弟妹である。よつて之を長幼の序より云へば日本は本家にして外国は分家、日本は本国にして外国は植民地である。然るに今日迄はこの本末始終の区別が明かでなかつた為に分家が蔓つて却つて本家を圧倒して来たが。この度は月日(神)元へと立ち帰り、木の根確つかり皆な顕はすと云ふのが神の予言である。それで天理教の理想より云へば各国民が生活の便宜上地理的に国家を組織することは認めるけれども、他国の侵略を目的とした勢力的国家を認めないのである。之を詳しく云へば、世界の各国民が互ひに相提携してもつて人類共通の目的のために勤勉努力するのである。更に詳しく云へば、全世界の国民が日本を中心として世界一国の理想的国家を実現するにあるのである。そうなれば勿論現在の国家と云ふものは現在の府県の大なる物と同じく独立した自治体となるのである。元よりその間に今日の如き国家的競争を許さない。凡て皆な「互ひ助け合ひ」の理に従つて一致団結して各国相互の利益を計る。これが天理教の理想の国家である。尚ほ本問題に関しては後の天理教と大日本主義との條にもう一度述べる心算であるから、問題をここに止めて次に天理教の社会観を述べもつて天理教の新人生観の概説を了り、更にその詳論に亘つて研究の歩武を進めたいと思ふ。 |
| 第十五章 天理教の社会観 |
| 仏教(小乗仏教)では、この世を穢土と観じて更にこの社会を全く遠離した別天地に生を求むることを理想としたが、天理教では「ここがこの世の極楽や」と云つてこの世界、この社会、この家庭、この肉体以外に幸福を求めない。と云つて天理教では何も現実の世界現実の社会現実の家庭現実の自我が完全だと云ふのでない。否なその不完全なことを認むることは他の凡ての宗教に優るとも劣りはしない。けれども天理教では薄情の夫の様に現在の妻が醜婦だからと云つて、それを捨てゝ他に理想の妻を求むることをしない。醜婦なれば醜婦なる程これを愛して段々美婦に仕立てゝ行くのである。かくの如く一つの困難、一つの障害物の表るゝ毎に他の宗教の様にそれを避けて別途を選まない。どこ迄もその困難を排斥しその障害物を破壊して、そこに新しき平坦の道を開拓するのである。ここに天理教の積極的社会観がある。 この積極的社会観よりミキ子の所謂「山の仙人よりも里の仙人」なる社会的人物が生れるのである。之を要するに天理教では現実の社会が多くの欠陥に富んだ不完全な社会なることを認めて居る。けれどもその欠陥を欠陥として残さずに飽く迄その欠陥を填充して行く所に天理教の新社会観があるのである。現実の社会の欠陥とは云ふ迄もなく相互扶助的共同生活の真面目なる精神の欠乏してゐることである。ミキ子はこの人生の最大欠陥を八種に分類しそれを八埃と云つた。八埃とは即ち 「ほしい、をしい、かはゆい、にくい、うらみ、はらだち、よく、かうまん」の八つである。その八埃を現実の社会から一掃した時、自らそこに実現して来る理想の社会を彼女は甘露台と云つた。天理教の終局の理想は実にこの甘露台社会を実現するにあるのである。以上は天理教の新人生観の大体であるが、以下にその詳論を述べて本問題の結としようと思ふ。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)