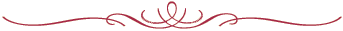
| 松村吉太郎 |
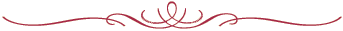
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年.11.20日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「松村吉太郎」を確認する。 2007.11.30日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【松村吉太郎履歴】 | ||||||||||||||||||
| 慶応3年、生れる。 昭和27年、出直し(享年86歳)。 |
||||||||||||||||||
| 慶応3年、生れる。 | ||||||||||||||||||
| 明治19年、肋膜炎(ろくまくうえん)のご守護を頂きおぢばへ帰る。 | ||||||||||||||||||
| 明治23年、高安分教会設立、初代会長。 | ||||||||||||||||||
| 明治32年、天理教の一派独立に尽力。大阪教務支庁長、満州布教管理者、天理中学校校長、本部教学部長など要職を歴任。 | ||||||||||||||||||
| 昭和6年、三昧田宣教所設立。 | ||||||||||||||||||
| 昭和27年、平等寺分教会設立。それぞれ初代会長。 | ||||||||||||||||||
| 「甘露台座談会」座談会メンバー 管長様(中山正善) 山澤為造(元治元年より、父良治郎に連れられて参拝していた) 松村吉太郎(明治19年に身上を助けられてから本格的に入信) 髙井猶吉(明治12年に身上を助けられ本格的に入信) 飯降政甚(明治7年、飯降伊蔵の次男として出生) 梶本宗太郎(明治13年、父松治郎の長男として出生) 上原義彦(東大教会2代会長) 史料集成部より 桝井孝四郎氏、上田嘉成氏 道友社より 堀越儀郎氏、中山慶一氏、上田理太郎氏、高野友治氏、出沖虎夫氏 |
||||||||||||||||||
| おつとめの変遷 | ||||||||||||||||||
おつとめが二十一回なのはどのように決まったの?
松村氏と言えば、天理教の一派独立のために中心となって動いた先人です。その活動の最中は教外だけでなく、教内からも応法だと冷たい視線にさらされ、一時は独立運動を辞退しようとさえ思い詰めていた時期もありました。そんな時に、初代真柱より 「お前は生命を捧げる覚悟で従事して居るのではないか。それに、生きて居て辞退するとは何事である。死んだら、やれとは言わぬ。生きて居る間は、どこまでもやれ。内部にどんな事があっても、俺が引き受けるから、安心してやれ」。 と励まされ、なんとか独立運動をやり切りました。ですから、 勿論そう言うお話は前から仰せになっておられたのだが、それを確定的に実行さして頂く事に決めたのは、教会本部が置かれるようになった時だったと思う。 この主張は、一派独立を果たすために政府と折衝を重ねていた、松村氏ならではの強い思いが込められていると思います。また、 三遍ずつ七遍するのか七遍ずつ三遍するのか判らないのでお尋ねしたら、どちらでもよいと仰ったのや。 「三遍ずつ七遍するのか七遍ずつ三遍するのか」どちらでも良いというのは驚きでした。現在、神楽づとめの第三節は、七遍ずつ三遍行なっていますが、もしかしたら三遍ずつ七遍になっていた可能性もあったのかもしれません。ここで一つ気になることは、「七遍は何言はいでもよいという理」この言葉の意味です。言い回し的には、耳馴染みのある言葉のような気がするのですが、いまいち意味が分かっていません。(勉強不足ですみません)考えられるのは、「人間が何も言わなくても(思わなくても)神様が良いようにして下さる」という意味でしょうか? |
||||||||||||||||||
| 第二節の成立 | ||||||||||||||||||
第二節「ちよとはなし」の成立時期は、どうやらこのメンバーでは判らなかったようです。 稿本天理教教祖伝を見ますと、 明治三年には「ちよとはなし」の歌と手振りを、同八年には「いちれつすますかんろだい」の歌と手振りとを教えられ、ここに、かんろだいつとめの手一通りが初めて整い、つづいて、肥え、萠え出等十一通りの手を教えられた、更に、明治十五年に、手振りは元のままながら「いちれつすます」の句は「いちれつすまして」に改まり、それに伴うて、「あしきはらひ」も亦。「あしきをはろうて」と改まった。 明治三年が、第二節「ちよとはなし」の成立時期だと書いてあります。予想していた明治七、八年〜十年と時期がかなりずれています。山澤氏がお屋敷に行くのを怠っていた期間が少し気になりますが、他のメンバーが入信した時期を見ますと、第二節の成立時期を間違えても仕方ないと思いました。しかし、そういったところも含めて、教祖御在世当時を知る先人達が対話を繰り広げる座談会は、大変面白い内容となっていました。 |
| 【松村吉太郎】 | ||
松村吉太郎「道の八十年」。
|
| 【松村吉太郎逸話】 | |
190「この道は」。
|
| 【松村吉太郎相対お指図】 |
| 明治二十一年一月八日(陰暦十一月二十五日) 松村吉太郎おぢばへ参詣おさしづ さあ/\尋ねる一条々々、十分一つ聞き分けば十分よし。神一条の道一寸難しいようなものや。一寸も難しい事はないで。神一条の道こういう処、一寸も聞かしてない。天理王命というは、五十年前より誠の理である。こゝに一つの処、天理王命という原因は、元無い人間を拵えた神一条である。元五十年前より始まった。元聞き分けて貰いたい。何処其処で誰それという者でない。ほん何でもない百姓家の者、何にも知らん女一人。何でもない者や。それだめの教を説くという処の理を聞き分け。何処へ見に行ったでなし、何習うたやなし、女の処入り込んで理を弘める処、よう聞き分けてくれ。内々へも伝え、身の内かしものや、かりものや、心通り皆世界に映してある。世の処何遍も生れ更わり出更わり、心通り皆映してある。銘々あんな身ならと思うて、銘々たんのうの心を定め。どんな事も皆世上に映してある。何程宝ありても、身の内より病めばこれ程不自由はあろうまい。自由自在心にある。この理をわきまえ。又々内々の処、銘々の処にも速やかの日がある。銘々ほんと思うた事あれば尋ねに出よ。 |
| 明治二十一年一月十五日(陰暦十二月三日) 松村吉太郎おぢばへ参詣再度おさしづ さあ/\よう聞き分け。幾重どうとの話分かる。成程の話、三度は三度の理を分かる。五度は五度の理を分かる。どうでも理を成程分からんではどうもならん。何よの所へも理を運べば、銘々も成程と運べば、身は速やか思えば、内々話成程。内々身の処尋ねる。成程理を分かる。又々内々気を勇む。さあ/\速やかという処尋ね出よ。 |
| 明治二十一年一月三十日(陰暦十二月十八日) 松村吉太郎おぢばへ参詣三度おさしづ さあ/\尋ねる処/\一つ/\の理、さあ/\尋ねる処、さあ/\もう一度、二度諭し、内々の処、余の儀済んだら、又余の儀/\だん/\に聞くと、これだけ異ると思う。一寸一つ/\身の速やか、心速やか、この理をよう聞き分け。これだけことこと身の速やか、心の速やか一寸渡すに難しい。内々速やかなれば、大きな理を渡したい。内々だん/\一寸さしづ、内々一寸心得えぬという処尋ね出よ。 |
| 明治二十一年一月三十一日 午前九時 松村吉太郎おぢばへ参詣四度おさしづ さあ/\一つの事情定め。内々の事情もある。幾重家内何人ある、皆かりもの。幾名何人家内一人でも、一名一人でもよう聞き分け。よう聞き分けば、分からんであろうまい。今までこれだけ尽すのにと思うはいかん。一名でも一人でも理を分かれば渡そ/\。これを生涯と定め。さあ/\渡そ。さあ/\受け取れ/\。さあ/\さづけ/\、どういうさづけ/\、神水として、清水の水のさづけ。 |
| 明治二十一年五月二十三日(陰暦四月十三日) 松村吉太郎東京に於てさづけの事に付伺 さあ/\尋ねる処、一寸分かるまい。一名一人さづけ処、内々しん/\処々、あちらこちらで違い、代として又一つ代理勤めさそう。 押して代理勤は内々さづけの代理なるか伺 さあ/\代理にさづけは無いで。代理勤め、内々しんに一つさづけ、日々内々の処、だん/\それ/\どうもならん。代理一人心差しつかえ無いよう、三遍心に心やで、一人他人へうつす。 |
| 明治二十一年六月十五日(陰暦五月六日) 東京北稲荷町四十二番地を地主より他へ売却するに付、此所を買い求むるか、但し他に適当の地所を選定するものかに付伺 さあ/\買入れるまでやで。だん/\事を言い立てるで/\/\。出越す処ほんの気休め/\ばかり。成ると成らん一寸思やん。遠く所、さあ暫くの処、一寸どちらなりと、一寸印があったらよいのや。一々所々、ほんの印やで。さあ/\運ぶ処、どういう事に成ろう。どうする。世界の運び、一寸気休みだけ許してある。さあさあ何か当分処、こちら成らんとも言わん。ほんに世界神一条、一日の日があるで。心治めくれ。だん/\伝えある理聞き分け、治めくれねば計り難ない。さあ/\さあ何かどうするにも、軽い思案、その日の心を以て一つの思案第一。 明治二十一年六月十九日 東京に於て増野正兵衞詰合中身上障り、松村吉太郎も同様に付、両人より願う時の増野正兵衞へのおさしづ さあ/\早く尋ね一つの返事、さあ/\身の処心得ん。尋ねるどういう事を諭す。又々不足あちらこちら思う一条、大望理を受け、大望と思う、大望世界長い。身上聞いて銘々事情運ぶ。世界事情運ぶとも、一つ難しい。神一条神の働き見える見えんはない。先々所や。銘々は忘れんがため、一つ控え付ける処、一つ日々掛かる理見える。日々聞いた理を聞かせ。先々先一つ一時世界という。一つ神一条、多く世界の理が立つか立たんか一つの理、見え来る理、早く定め。難しい成るも成らんも日がある。心の道の運ぶ、日々までの一つの道、難しいではない。世界大きい一つ思案、世界の理だけの事、神一条の理は成る成らん、たゞいつであるようなと。神がいずみ、神一条いずみ、人が頼り多く、人運ぶ人気大き心を早く思案立て替え。銘々一条取り直し、それ/\道のためなら世界一条、神の自由早く取り替え。思う身も何も恐れるではない。真実定めて風の用意胸にある。神一条これまで聞いたる話を、大きな心と立て替えて、心を治め居よ。 (風の用意とは風が吹けば風の用意せねばいかん、つまり心を大きに持って落ち着く事と考えます) 右同時、松村吉太郎居所及胸悪しきに付伺 さあ/\同じ一つ事情、通る/\一つ談示神一条、今一時世界を取り扱い、世界の思案要らん。神一条通り難くい、世界広い道は通り難くい。日々に一つの理同じ理である。同じよう聞かしてくれ。 押して、東京本部に於て参詣人に神一条の道を伝えても宜しきや、又本部にてするは差し支えなきや伺 さあ/\神一条の理、たすけ一条の理、遠慮気兼は要らん。尋ねて来るなら聞かせ。この理何程人が寄るとも知れん。これが自由。聞かせ/\置きたる、尋ね来る、聞かせ。十分遠慮は要らん。日々真実聞かすなら、多くの中なれば、神一条世界の身の内たすけ一条のため出て来るなら、一つ話聞かせ/\。聞かさねば分からんで。何もたすけ一条の事は後へ引くでない。 |
| 明治二十一年八月十三日 松村吉太郎東京出張所に於て、両手指先痺れ身上苦しむに付伺 さあ/\尋ねる/\。長らえて一つの事情、身上一つの処心得ん/\。どういうものであろう。身上一つ判然と思う処/\。里元一つの所思うように思て居る。一つ戻りて運ぶ。一つ一度戻りて運ぶと身上の処に一つ事情ある。ほっとに思う/\いつまでもと思う。一度戻りてたんのうの事情、又運ぶと遠くの所、どういうもの、あこはどうでもと思う。運ぶ一つ事情、里々結構やと運ぶ。あの者と思て居るやろう。なれども余儀無くして身上の事情あれば、又々の事情と諭して置こう。 |
| 明治二十一年十二月十五日 午前十時 松村吉太郎縁談の件伺、(萱振芦田は信者にあらず、吉太郎は信者より貰い受けたく、然れ共両親は是非貰い受けたしと、何分両親の言う事なり、夫婦の縁があるなら貰い受けねばならぬに付、如何に致して宜しきや伺) さあ/\縁談一条/\のさしづという。一度さしづしてある処、まあ内々談示々々談示、第一怪しと言えば怪しい。銘々の処、急く事も要らん。道の道なら十分という。銘々理を鮮やかに治めば、内々の理も基かねば行くまい。銘々も元の理を早く治めにゃなろまい。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)