東亞論壇7-中山みきと幕末日本社会ー神秘体験の社会的背景ー 林泰弘
中山みきは、1798年から1887年まで、約90年間生きていた。その90年は、日本では社会・政治的に大きな変化が起こっていた時期である。徳川将軍家が政権を握っていた約260年間の江戸時代が終わり、明治維新によって新たな時代に変わった。幕末から明治へと大きな変革に迎えていた時期に、中山みきは生まれた成長して、そして新しい宗教を創始している。
小論では、日本社会のこうした変化を中心に中山みきの神秘体験と思想の背景を検討して見ることにする。
まず研究者たちが行ってきた中山みきの全生涯に対する年代区分を紹介し、それを基礎にここでの年代区分を試みる。
上田嘉成は、中山みきの生涯を、1839年の10月26日の神秘体験を中心に大きく二つに分ける。そして神秘体験以前は、二つの区分線を引くことができると述べながら、1810年、13歳の時の結婚と1829年32歳の時に隣家の子供を救った事件を挙げている。神秘体験以後は、五つの区分を設けている。1853年(56歳)の夫の死去、1863年(66歳)の信者の入信、1867年(70歳)の神祇管領の公認、1874年(77歳)の奈良県庁の召喚、1881年(84歳)の息子秀司の死去を挙げる。
一方、天理教教会本部編の『稿本天理教教祖傳』は、中山みきの一生を、次のように総10個の章に分けて紹介する。
①第1章「月日のやしろ」:1839年の神秘体験を紹介
②第2章「生い立ち」:出生から神秘体験直前の1838年まで
③第3章「みちすがら」:第7章までは天理教を創立し布教していく過程(1839年-1882年)を記述
④第4章「つとめ場所」
⑤第5章「たすけづどめ」
⑥第6章「ぢば定め」
⑦第7章「ふしから芽が出る」
⑧第8章「親心」:『おふでさき』の執筆紹介を中心に記述
⑨第9章「御苦労」:政府からの干渉や弾圧を中心に1882年(明治15年)以後のことを紹介
⑩第10章「扉ひらいて」:1887年(明治20年)の死去を中心に記述
ちなみに高木広夫が、天理教教団成立の過程を考察するに際し、行った年代区分を挙げてみる。彼は以下の四期にわけ、それぞれ歴史的解釈も行った。
①第一期:中山みきの神がかりから仏教の一派として、組織を持ち始めた頃(天保9年明治13年)まで。天保改革より西南戦役までの絶対主義の確立期に該当する。
②第二期:これに続いてみきの死去まで(明治13年-明治19年)。資本主義育成のための原始的資本蓄積期である。
③第三期:死後から1899年の独立請願まで(明治19年-明治32年)。日清戦争を中心とした帝国主義への移行期である。
④第四期:これより1908年の独立まで(明治32年-明治41年)。日露戦争に表われたような帝国主義段階に該当する。
中山みきの生涯だけを見れば、三つの期間に分けている。神秘体験以前、神秘体験から1880年頃まで、そして死去までである。「神秘体験以前」の期間は、高木は教団成立の過程に入れていない。
以上、中山みきに関する幾つかの年代区分をみてきた。共通する区分点は、中山みきの神秘体験だけである。上田の区分は、中山みきの生活史に重視しており、『稿本天理教教祖傳』は教理を重視する立場である。高木は社会・歴史の流れから年代区分の手掛かりを探している。ここでは、まず神秘体験を一つの境界に設定し、その後の生涯は、明治維新の1868年を重視し、次のように分けてみようとする。
1)準備期(1798-1837):出生から神秘体験の前年までであり、『稿本天理教教祖傳』においては第2章に該当する。みきが40歳の時までの期間である。準備期というのは、以後の宗教的生涯の準備という意味によるものである。
2)教団成立期(1838-1867) :神秘体験以後、神陶官領の吉田家に公認を出願し、その認可を得た1867年(慶応3年)までの期間である。彼女の41歳から70歳の期間である。『稿本天理教教祖傳』では、第1章と、第3章より第7章までの期間である。上述した高木広夫の場合は、天理教教団の成立を、明治政府より別派独立の許可を得る時と見ている。むろん教団レベルでは、氏のような時期区分が妥当であろうが、中山みきの生涯に限って言えば、吉田家より公認された慶応3年の時点を教団成立の時と見てもよいのではないかと考えられる。明治政府が、宗教教団許可の新しいルールを打ち出していたため、新たに教団独立の請願が必要であったわけで、慶応3年(1867年)の時点で、天理教教団はすでに、吉田家の許可を得る程度の、一つの宗教教団としての規模や資格を持っていたのである。こうした認識で、1867年を教団の成立年として見なそうとする。
3)教理完成期(1868-1887) :明治維新以降の期間である。天理教教団としては新たな試練の時期であり、国家権力による干渉と弾圧の時期でもある。中山みきとしては、巨大な国家権力に立ち向かいながら、『おふでさき』を執筆したり、「こふき話」を語ったりして、規模のある宗教教団としての必要な経典や教理を完成させた期間である。『稿本天理教教祖傳』においては第8章、第9章、第10章に該当する。
ここでは、紙面の関係上、「準備期」という時期だけを取り上げ、中山みきの思想の社会的背景を探ってみることにする。(文末の表1の神秘体験以前の中山みきの年表を参照せよ。)
1798年から1837年までの期間は、江戸幕府の11代将軍徳川家斉の時代である。中山みきはこの時期で生まれて、13歳の時に結婚をし、7人の子供を出産、そのうち3人の子供に死なれる。40歳の時には、翌年の神秘体験の直接な原因であった家族の病に苦労する日々を送っている。
彼女が40歳まで生きていた時の日本社会は、徳川家康から始った江戸時代もすでに200年以上の年月が経ち、その末期を迎えていた。国外からは、ロシア、アメリカ、イギリスなど西洋の国々の商船や軍艦が来航し、通商を要求していた。江戸幕府はそれらの要求をいっさい拒否し、異国船打払令で対応していた。社会的には、天保の大飢饉(1833年)、大塩平八郎の乱(1837年)、そしておかげ参りが流行した時期である。百姓一揆や打ちこわしが頻繁に起こり、しばしばコレラが流行し、また大地震や大飢饉に襲われる時代であった。文字通り内憂外患の時代であった。
思想・文化的には、みきが産まれた1798年は、本居宣長が『古事記伝』を完成した年である。1823年にはオランダのシーボルトが来日し、1833には蘭和辞典が刊行されている。要するに国学と蘭学が絶頂期に達していた。明治維新直後に一世を風靡した福沢諭吉が1834年に産まれている。また明治維新の成功に大きく貢献した坂本竜馬もこの時期に産まれている。
以下では、「1、中山みきの成長と結婚生活」、「2、百姓一揆の時代」、「3、おかげ参り・ええじゃないか踊り」、「4、蘭学・水戸学・国学の流行」、「5、外国船の来航と開国」で分けて、中山みきの生涯と当時幕末日本社会の状況を探ってみよう。
1、中山みきの成長と結婚生活
(1) 出生と成長
中山みきは、1798年 (寛政10年)4月に、大和国山辺郡三昧田村で生れた。現在の奈良県天理市に属する。父は、当時34歳の前川半七(正信)で、母はきぬ(当時26歳)であった。
前川家は、豊かな家柄で、20戸(2百石)の庄屋であった。藩から一代限りの無足人という、武士に準ずる身分をあたえられ、近所の村を含めての目付役をつとめていた。名字帯刀を許され、具足、鎗、鉄砲各一と下人数人を持っていたといわれる。また、大和神社の総代でもあった。要するに、農家というより武家に近く、郷士層に属する地方の有力者であった。
彼女は7歳頃には、父から文字を習った。9歳から11歳までは、近所の寺子屋に通っていたといわれる。また、10歳の時には、母が唱える和讃を聞き、暗唱したこともあった。後の彼女の話によれば、幼い時に、彼女は人の前にはあまり出ようとしない、陰気な少女であった。また生来身体もあまり丈夫ではなかったという。
(2) 結婚
中山みきは13歳の時に結婚する。父親の前川半七の妹きぬが紹介した結婚であったが、きぬは、同じ藤堂藩領の庄屋敷村(現在の天理市三島町)の中山家に嫁ぎ、当主の善右衛門の妻となった。きぬは、みきの叔母にあたる。ところで、彼女は、みきを自分の長男善兵衛の嫁にしようと強く望んでいた。自分の息子善兵衛とみきの結婚の縁談もきぬが進めた。
1810年13歳の時みきは、こうした叔母きぬの願いを受け入れ、その叔母の長男中山善兵衛の嫁として中山家に迎えられるようになる。中山善兵衛は当時、みきより10歳年上の23歳であった。
中山家は、耕作地主で、藤堂藩領三十余戸(300石)の庄屋をつとめ、十数町歩の田畑山林を所有していた。綿屋とよばれて綿の仲買もしていて、使用人も多いときには20人ほどであって、かなりの収入のある豪農であった。
結婚して3年後の16歳に、彼女は、姑より所帯をまかされ、中山家の生活一般の責任を負うようになる。いわゆる「へらわたし」という主婦権を譲渡されていたのである。叔母であり姑であったきぬから中山家の生活全般を任されたのは、中山みき本人の家庭主婦としての能力や誠実さが認められからであろう。
主婦權を譲ってもらっただけ、16歳のみきにとって、中山家での生活は辛いものであったに違いない。彼女は、朝早く起き、朝餉の仕度にはじまり、炊事、洗濯、針仕事、機織りと少なからぬ家事に追われた。そして農繁期には、田植え、草取り、稲刈り、麦まき、麦刈りにまでおよんでいた。晩年、みきは、「私は幼いころはあまり達者ではなかったが、百姓仕事は何でもしました。ただしなかったのは荒田起しと溝堀りだけで、他の仕事は二人分くらい働きました。」と言うほど、生活面で大変苦労していたようである。
19歳の時、彼女は長子を出産したが、まもなく失う。24歳の時に、長男の秀司が生れた。そして4年後には、長女まさが、さらに2年後には、次女やすが生まれた。このようにして、彼女は、天保8年すなわち1837年まで、次々と7人の子供を生み、そのうち三人の子(最初の子、次女、四女)を失っている。これらの相次ぐ子供たちの死去は、彼女にとっては、かなりの心の痛手をあたえたはずである。
彼女の結婚生活においては、夫との葛藤もしばしば指摘される。彼女は結婚してから、たくさんの家事労働だけでなく、使用人へのいたわりや、しゅうと・しゅうとめへの孝行をこなし、夫への貞節も尽くしていたが、夫の善兵衛は、怠惰て不身持ちな生活をしていた。彼女は、夫とのあいだに何の心の触れあいも感じない毎日を送るようになった。みきが、嫁いでしばらくしたころ、夫は妾をかこい、下女にまで手を出していた。下女かのは、みきに代って中山家の主婦の座におさまろうとし、あるとき、みきに毒を盛った。みきは毒の入った汁を飲み激痛に苦しんでいたが、幸い命は助かった。
総じて言えば、彼女の結婚生活は、子供の出産と死去、過重な家事、夫との不和などの言葉で要約できる。もちろん当時は、度重なる飢饉や大洪水、コレラの流行など自然災害が頻繁に起こっており、そうした危険にさらされなかったことだけでも幸福な結婚生活であったとも言えないことはない。しかし、富裕な家柄出身でありそうした家に嫁いだ彼女にとっては、生存の問題よりは、生活の質、または生の意味がより切実に問われていたのではないかと思われる。
(3)仏教的環境
高木宏夫は、中山みきの神秘体験の宗教的環境として、①みきが幼い時に浄土和讃を暗誦していたこと、②みきの母が、大和神社の巫女の家筋であった長尾家の娘であったため、神がかりの素地があったこと、③修験者に長男の足痛平癒の祈祷を依頼していたことなどを挙げる。そして彼女は①お寺、②神社、③民間信仰のいずれにも熱心な信者であって、その点においてもっとも庶民的な信仰を持っていたことを指摘している。
ここでは、高木が挙げている三つの環境のなかで、仏教的環境だけを検討してみる。
彼女は、幼い時には、尼になりたいと言っていたと伝えられている。彼女は、中山家と結婚の話が交わされていた時、自分の家族に次のような結婚の条件を出していた。すなわち、「そちらへ参りましても、終えて後は、念仏唱える事をお許し下さる様に」ということであった。中山家も熱心な浄土宗徒であったのでこうした条件は受け入れられた。これらのことから彼女が仏教へ大きな関心を持っていたことが窺える。
江戸時代、大和地方の農村は浄土宗の地盤で、村ごとに念仏講があり、念仏踊りや和讃の集まりが盛んであった。みきの実家である前川も浄土宗の熱心な壇家で、その菩薩寺は丹波市の迎承寺であった。両親は朝夕、仏前に回向頂礼を欠かさず、この寺への参詣もおこたらなかった。幼いみきも両親と一緒に念仏を唱え、「浄土和讃」を聞き覚えていた。たとえば、その内容は、「沙婆世界は厭ふべし、厭はば苦海を渡りなん、安養界をば願うべし、願はば浄土に生るべし、草の奄は静かにて、八功徳池に心すみ、夕べの嵐音なくて、七重宝樹にわたるなり」というようなものであった。
彼女は、19歳の時には、中山家の菩提寺であり壇家であった善福寺で「五重相伝」を受けた。五重相伝とは浄土宗の奥義をきわめた篤信者に授ける儀式で、7日間5回にわたって勧請聴聞をし、その上で剃度式(おかみそり)を受け、秘密の伝法を口伝で頂くものである。彼女は、1816年春、勾田村の浄土宗・善福寺に入り、そこの住職、報誉上人からその秘密の伝法を貰った。当時みきの戒名は「連誉勝岸智宝禅定尼」であったという。仏教とりわけ浄土宗からの深い影響が窺われる。
2、 百姓一揆の時代
1630年代から1830年代までの約200年間は、百姓一揆の時代と称される(110頁。「第7章百姓一揆」深谷克己『要説』。とりわけ中山みきが神秘体験を経験している1838年前後の天保期は、天明期、慶応期とともに、百姓一揆や打ちこわしがもっとも高揚した時期として指摘される。
百姓一揆とは、幕藩領主に対する農民の反乱あるいは抗議騒動であるが、こうした一揆は、江戸時代を通じて約3200件にも及んでいる。百姓一揆は、江戸時代前期(17世紀後半)には、農民の代表が、村役人に頼んだり、村役人自らがその代表になり、年貢の減免や代官の交代などを領主に越訴するいわば代表越訴型が多かった。そして江戸中期の18世紀には、強訴が大規模化し村役人が農民を指導し、領主に年貢の減免や専売制の廃止などを要求する惣百姓一揆型が多くなった。ところが、江戸後期(19世紀幕末期)には、貧農が土地の再配分や物価の引き下げ、または専売制の廃止を、村役人や領主に直接要求する世直し一揆が多くなっていく。
中山みきが生まれてから40歳までの期間中、特に数多くの一揆が発生していた。1799年には、大和の各地で百姓一揆が起り、1802年には柳本藩領で百姓一揆が起っている。また、1816年、1818年、1823年にも一揆が起こった。みきが34歳で三女を出生した年の1831年には、防長で10万人が暴動を起こしている。1836年にも、郡内騒動で3万余人が暴動を起こし、三河加茂にも一揆が発生した。
1836年には、大阪で「打ちこわし」が起こった。「打ちこわし」とは、人々が役人や米屋・金融業者らを襲った事件である。江戸時代の中期・後期には、こうした「打ちこわし」も続発していた。同時に、村内の対立である「村方騒動」も、江戸時代の中・後期より激増していた。
こうした百姓一揆や打ちこわし、村方騒動などの騒乱は、幕府が農民の要求を適切に対応できなかったことが原因として挙げられる。例えば、徳川家斉時代に松平定信(1758-1829)によって推進された寛政改革(1787-1893)では、農村再建や社会安定を図るためにさまざまな改革や制度を推進したが途中で挫折し、むしろ社会はより混乱に陥って、百姓一揆はより頻繁に行われるようになった。
中山みきの時代の混乱な社会状況のもう一つの原因として、自然災害や天災も挙げなければならない。例えば、みきが9歳の時、1806年には米の大凶作と共に、江戸では大火事が発生した。彼女が結婚した1810年には、米・綿が大豊作であったものの、各地ではまた飢饉が発生している。その翌年には、丹波市・檪本村等の地に大洪水が発生、25歳の1822年には、四国にコレラが流行した。1823年と1835年には、米の大不作、1828年と1830年には、越後や京畿に大地震が発生している。また、1830年には、全国的に大飢饉が続いた。
もちろん、こうした災害は、政治が円滑に作動すれば、ある程度は防いだり免れることができたはずであるが、次々と改革が失敗したため、民衆は、洪水や米不作、コレラ、地震、火事などの厳しい自然災害に、対応させられていた。
1833年には、日本歴史上、三大飢饉の一つとして言われる天保大飢饉が起こる。この大飢饉は、幕府経済の根底をゆるがすほど大規模のものであった。一度飢饉になると種籾まで食べ尽くしてしまい、数年飢饉が続くことが普通であったが、この年の飢饉は、6年間も続き、中山みきが36歳から42歳まで続いた。
こうした飢饉によって中山みきがどのような影響を受けていたのかは明らかでない。中山家は、相当の土地を持つ富農であったため深刻な影響は無かったはずである。ところで、村の年寄役や庄屋役を務めていた中山家は、江戸時代の多くの村々と同様に、年貢のとりたて、村の治安や村人のもめごとの解決、さらには農業の奨励、貧民救済、飢饉の対策などの責任を負っていた。その責任が、中山家の家事全般を管理していた中山みきに少なからぬ負担を与えていた可能性もあり得る。この期間中に、彼女が神がかり体験をしたのは注目に値する。
全国的な飢饉、凶作がつづぎ、一揆や打ちこわしが横行するなかで、みき40歳のころ(1837年2月)、大坂で「神武帝御政道」への復帰をかかげて、もと大阪町与力の大塩平八郎(1793-1837)が決起した。陽明学者である大塩平八郎は当時、学塾をひらいて多くの門人の教育にあたっていた。彼は檄文に次のように記していた。近年に「四海困窮」は為政者が仁政の基を忘れていることに原因があり、天災地変の続出は天の戒めである。にもかかわらず、町奉行所の役人どもは政治を私して民を苦しめている。また、多くの者の苦しみをかえりみず贅沢の限りを尽くしている豪商を許すわけにはいかない。ゆえに、彼らに天誅を加えて金銀米殻を配布するから、大阪に騒擾が発生したと聞いたらただちに駆けつけよ。大塩平八郎の乱はわずか半日で鎮圧されたが、幕府の矛盾を一挙に噴出させ、かねてから圧政に苦しんでいた広汎な民衆にその矛盾を気づかせた。また、その後の世直しの状況を出現させた起爆剤としての役割を果たした。
中山みきの中山家は、大阪の綿商人と密接な取引きをしていた。それだけ、大坂での大塩の乱は、戦災で大坂の町が炎上した様子とともに、大事件として中山みきのところへ伝えられていたに相違ない。
3、おかげ参り・ええじゃないか踊り
1830年、中山みき33歳の時、各地では伊勢神宮のご恩、つまり「おかげ」を感謝する「おかげ参り」が大流行した。わずか4ヶ月の間に、約500万とも言われる大勢の人々が伊勢神宮に参詣する旅に出、伊勢に向って流れだしていた。家族や雇い主の同意もなしに(ぬけ参りと呼ばれる)、旅の仕度もなく、飛び出した形の旅も多かったという。これらの参加者たちは沿道の人々から食事や宿の提供を受けたりした。このころ、中山みきの住む庄屋敷村に近い丹波市も、参宮の群衆で混雑をきわめ、人々のために施行所もつくられていた。民衆にとっては、封建的な束縛からの脱出を意味し、政府も民衆の息抜きの機会として大目に見てくれるものであった。
おかげ参りは、17世紀半ばごろから始ったものである。村々に「天照皇太神宮」という伊勢のお札が天から降ったなどといううわさが、集団的おかげ参りを誘発した。60年ごとにおかげ年が来て、その年にはお札が降るのだといわれた。18、9世紀の大規模なおかげ参りはほぼ60年目に起こっている。1650年・1705年・1771年・1830年(文政13)・1867年(慶応3)年のそれが特に大規模であった。上述した1830年のおかげ参りの時には、日本全国の人口が約2720万人と言われるので、約5人のうち一人が、その「おかげ参り」に参加し、伊勢神宮に参り込んでいたわけである。
また1867年(彼女の70歳の時)から翌年にかけて、「ええじゃないか踊り」が大流行した。ええじゃないか踊りは、徳川幕府が倒れた年に起こったもので、おかげ参りと同様のものであるが、「日本国の世直りええじゃないか」、あるいは「諸仏諸神のお降りが、日本国中いちじるし」などの歌と踊が伴われるのが特徴であった。伊勢神宮や名古屋地方に御札が降ったという噂がきっかけで人々は、歌と共に熱狂的な群舞を踊り狂った。ついには、八幡、イナリ、出雲でも、カミ、弥陀、大日、弥勒までが天降ったという噂が流行した。こうした行動には民衆の世直しへの切実な期待がこめられていた。大規模の群衆の狂乱的踊りは、治安を麻痺させ、幕府に反対する新政府の軍事行動を助けることになったと言われる。
大規模に起こった二回のおかげ参りが、中山みきにどのような影響を与えたのかは、明確にされていない。ところが、彼女が創り出した天理教の教理や儀礼のなかには、こうした民衆の熱気に応じるようなものが少なからぬ見られる。例えば、この世を助けるために天下ったという神の観念、そして音楽と歌と手振りで行われる神楽つどめなどがそれである。
4、蘭学・水戸学・国学の流行
中山みきが神がかりを通じて、宗教的自覚を持ち、新しい宗教を築き上げていた当時、社会一般の知識人層には蘭学、水戸学、国学などが流行していた。当時のそれぞれの学問の動きを簡略に見てみよう。
(1) 蘭学
『蘭学事始』の著者杉田玄白は1814年(中山みき15歳の時)に、「初一念には、この学今時の如く盛んになり、かく開くべしとは曾てよらざりしなり」と、蘭学が盛んになるとは思いもよらなかったと語っている。当時、蘭学が如何に盛んであったのかが窺える。
オランダ人を通じた西洋学、すなわち、「実学」・「洋学」とも言われる蘭学は、1830年代頃になると、医学などただの実用の学問だけに留まらず、日本の社会や政治にもその発言力を広めていた。たとえば、1850年に死去した佐藤信淵は、西洋の科学・西洋の政治制度についての知識を基に、中央集権的な政府の形態も論じていた。幕府は、こうした蘭学者の批判を弾圧していた。
1838年中山みきが、神がかり体験をしていたその年、渡辺崋山(1793-1841)は、「慎機論」で、1837年、アメリカ船モリソン号を撃退した事件を批判している。モリソン号は、日本人漂流者を助けて連れてきたのに、むしろ幕府は、誤った判断で、大砲でそれを撃退したと、幕府の鎖国政策を批判した。1839年、渡辺崋山・高野長英ら尚歯会員は、密貿易の嫌疑で弾圧を受ける。渡辺は故郷に軟禁されるが、のちに自殺する。
年を遡って、1822年、みきの25歳の時には、伊能忠敬が、西洋科学の道具や知識を借りて、実測の「大日本沿海輿地全図」を完成している。そして1833には、稲村三伯(1758-1811)によって蘭和辞典が刊行されている。
シーボルト事件も、中山みきが31歳に起こっている。シーボルトはオランダ人で、1823年に来日し、長崎市外の鳴滝塾で全国から集まってきた学生たちに西洋の学術に関して組織的な講義を行った。蘭学の学問的水準は、彼によって一段と高められた。どころが、1828年、帰国するに際し、国禁であった日本の地図を持っていたことが発覚した事件である。この事件で、シーボルトは国外追放された。多くの蘭学者も配流されたり追放されたりし、蘭学が大きく萎縮していった。
しかしながら、蘭学はペリーの軍艦が浦賀に来て通商を要請した1853年頃にも、まだ知識人の間には流行していたようである。当時22歳であった漢学者中村敬宇は、「誓詞」の中で「蘭書の業、半途にして廃すべからざる事」を書いているからそうした事情が窺える。この時は中山みきが、ちょうど布教活動を始めた時期である。ところが1859年、福沢諭吉は蘭学を止め英学を始める。ペリー来航以降、蘭学はようやく衰退しはじめていたのである。1859年は、中山みきのところにより寄せる人が増え始めた二年前である。
(2)水戸学
1841年、中山みき44歳の時に、水戸の藩校である水戸弘道館が開かれ、水戸学の興隆を迎えていた。
水戸学は、朱子学の大義名分論を基礎とし、古代の天皇による政治を理想とした学問一派である。水戸藩の第2代藩主徳川光圀の提唱で『大日本史』の編纂が始り、国家の伝統と天皇の位置についての歴史的関心が起こった。『大日本史』は、1810年、みきが13歳で結婚していた年に、献上された。
水戸学は、現実的には、幕府を否定するのではなく、将軍が天皇を尊敬すれば、士民も大名や将軍を尊敬するという論理であった。ただし、士民が直接、天皇に忠誠を尽くす場合は、乱民として規定された。水戸学は倫理観・道徳観においては、神道とは異なる立場であったが、仏教・神仏習合・民俗信仰などを批判し、結果的には国学者たちと同様の結論に達していた。
水戸学の形成が明確になったのは、天保期に、藤田東湖(1806-1855)と会沢安(1781-1863)ら革新派が、藩主徳川斉昭(1800-1860)を補佐し、藩政改革を行ってからのことである。その後、政治的状況の流れによって、強力な尊王攘夷運動の指導理念になり、幕府転覆に寄与するようになった。会沢安が『新論』を書き、激烈に尊王論を主張し、幕末の内政・外交に至大な影響を与えていたのは、1825年、すなわち、中山みき28歳の時であった。藤田東湖は中山みきが58歳、会沢安はみき66歳のときに死んでいる。
(3) 国学
国学は、主に神官・町人たちによって研究、支持されていた学問一派である。古代神話や古代史書、古代文学を実証的に研究し、古代の真の姿を究明しようとした。要するに古典研究とそれに由来する復古思想である。日本の古典の文献学的理解を通じて、日本固有の「古の道」を明らかにしようとした国学は、方法としては、古典から見出される日本古代の道を無上の理想とし、中国思想や仏教思想、すなわち「から心」や「仏心」によって歪められない純粋の古道を求めた。徂徠学の古文辞学の影響と受けたとされているが、徂徠学派の場合は、儒教の古典の研究によって孔子や孟子の古義を明らかにし、中国の聖人の教説を絶対の権威としていた。その絶対的権威を日本の純粋な道に置き換えたのが国学である。
国学者たちに共通する特徴は、古代の理想視と中世の否定である。彼等によれば、古代とは神話時代を含む奈良時代以前の時代で、仏教・儒教など外来思想の影響が強くない、神の霊威と恩恵で健全なるかつ清浄なる生活をしていた理想の時代であった。こうした観点から、神国日本の優秀性が強調され国粋主義と天皇を中心とした政治を志向する尊王思想が形成された。
国学の先駆者は契沖(1640-1701)という真言宗の僧侶である。その脈は、荷田春満(1669-1736)から、賀茂真淵(1697-1769)、本居宣長(1730-1801)、平田篤胤(1776-1843)へと伝承されていた。
中山みきが生まれた1978年、本居宣長は畢生の作である『古事記伝』を完成している。本居宣長は国学の思想的体系と研究の方法を確立したと言われる。彼は師である賀茂真淵から古事記の研究を勧められていた。賀茂真淵は『万葉集』の研究を通じて純粋な日本精神を提示しようとしていた。本居は、『古事記』を古代の心の純粋な表現として見なした。また『源氏物語』を研究し、独自の文芸観である「もののあわれ」論を展開していた。ただし、本居と賀茂の政治的立場は、現実を肯定し、幕府の政治を支持したものであった。
こうした本居宣長を継いだ平田篤胤は、国学の国粋主義的な側面をより激烈に打ち出していた。平田は、本居の学問的研究を、神道的実践の方向に発展させ、思想界に一つの勢力を構築するに至る。「古道」に根拠した天皇親政を志向した平田一派は、明治維新前後に大きな勢力を形成し、明治維新の一つの精神的動力であった尊王思想を呼び起こした。こうした立場は、幕府の政治を肯定した前代の国学者賀茂や本居とは異なるものであった。平田は、中山みきが46歳であった1843年死去している。
「から」(中国や朝鮮)あるいは「からごころ」に対する厳しい批判は、国学、とりわけ本居宣長の思想においては中心的テーマの一つである。宣長は、天地自然の事や人間世界に起る事は、すべて神の御所行(みしわざ)によるものと認識する。彼によれば、神の御所行は、人間の知恵によっては推量できないのに、「漢意(からごころ)」はいろいろな理屈をつけてあたかもすべて説明できるかのように論ずる。それに対して、「やまと魂」すなわち、「御国ごころ」(日本のこころ)は、神の御所行を「くすし(奇霊)く、たへ(微妙)なる物」として、そのまま素直に受け容れる。こうした観点から宣長は、「日本」の精神を尊び、「から」やからの精神を排斥した。このような認識は中山みきにも共通に見られる。中山みきの『おふでさき』などの文章には国学や復古神道の体系的知識は見られない。また、宣長の中山みきへの影響、国学と天理教教義との影響関係も明らかではない。ところが、「からごころ」を排除し「日本的精神」を確立しようとした知識人層の上述した動きは、中山みきの神秘体験を取り巻く時代的かつ文化的背景として挙げることができよう。
5、外国船の来航と開国
丸山真男は日本における近代的な国民意識や国民主義の登場は明治維新以降と見なしている。しかし、国民意識の割拠的分裂を自覚し、それを止揚することによって国民的統一の観念が生まれたのは外国軍艦の到来と見る。要するに国民主義や国民意識の形成の契機を外国船の到来と見ているわけである。
オランダや清の船を除いて、外国船が日本の沿岸に来て通商を要求したのは、早くも1778年のことである。ロシア船が蝦夷地(北海道)の厚岸に来航して通商を要求したが、松前藩はそれを拒絶した。その後、1792年にも、ロシア使節のラスマンが蝦夷地の根室にきて、通商を要求している。
以後、19世紀に入って、ロシア船の他に、アメリカや、イギリスなど西洋の国の船が次々と来航し、通商を要求している。
中山みきが生まれてから、神秘体験の前年すなわち、40歳の1837年まで、日本の沿海には頻繁に外国船が来ており、民心は騒然としていた。例えば、1803年にはアメリカ船が、1804年にはロシア船が、1808年にはイギリス船が、それぞれ長崎に来て通商を要求したり、薪水食糧を強奪していた。
幕府は、通商要求を拒否していたが、その後もやって来て通商を要求している。とりわけイギリス船は、1813年、1816年、1817年、1818年に、琉球や浦賀等の地に来航し、通商を要求している。幕府は、1825年(みき28歳の時)に、異国船打払令を下し、一切の外国船は見つけたらすぐさま撃退するように命令を頒布している。
ところが1840年、中国でアヘン戦争が起り、戦敗した中国は1842年、英国に香港島を割譲し、広州など五港を開港するようになる。アヘン戦争は幕府にとっては、「唇亡びて歯寒し」の思いをさせる衝撃であった。そこで、「無二念打払令」を廃止し、外国船に薪水の給与を許す「薪水給与令」を布告する。外国と摩擦を避けるために、外国の船が必要な物資を一部提供することを許すものであった。しかし、列強はそれに満足せず、1846年には、諸外国の船舶が来航し、新たに通商を要求した。そして1849には、アメリカによる正式の通商要求があったが、幕府はいずれも拒否する。
堀一郎は、アメリカインディアンの宗教と日本の新興宗教とを比較したマックファーランドの説を紹介しながら、新宗教が流行した一要素として「侵入する文化によって激化した社会的危機」をあげる。実際、アメリカのペリーが、軍艦4隻を引きいて浦賀に来航、通商を要求していたその年(1853年)、中山みきは五女こかんを浪速に行かせ布教活動を開始している。
アメリカの強硬な姿勢に圧倒され、幕府はその翌年、再び来航したペリーと日米和親条約を結び、開国する。そして、イギリス・ロシアとも和親条約を締結し、1856年には、下田に米国領使館を置いた。また、1858には、アメリカと日米修好通商条約結び、翌年には、神奈川、長崎、箱館3港を開港し、貿易を開始している。
西欧勢力の圧迫で開港・開国してはいたが、社会はより混乱な状態に陥った。貿易額が輸入超過状態になる(1867年)など海外貿易で物価が高騰し、一揆や打ちこわしもより多く発生していた。そのうえ開国は、政治的にも混乱を招き、幕府は窮地に置かれることになる。1860年、西日本の諸藩の支持を得た天皇側から、外国との条約を破棄し、攘夷実行を要求したのである。幕府は攘夷令を布告するが(1863年)、それが長州藩や薩摩藩と外国軍艦との衝突を招いた(薩英戦争と1864年の四国連合艦隊の下関戦争)。天皇側では、前の措置を改めて、外国との諸条約を許可するが(1865)、結局、幕府の政治的立場は大きく揺すぶられる結果となったのである。
大阪とみきの住んでいた村は目と鼻の先である。列強による強要された開国や通商による生活必需品の不足、そして物価の急騰は、おそらく中山みきのような庶民に大きな影響を与えていたはずである。
終わりに
神秘体験の原因
堀一郎は、宗教指導者がどのような状況から神秘体験を経験するのかについて次のように指摘している。
多くの教組は、社会の比較的低い層から、多くの社会的、個人的辛酸と苦難に遭遇し、その結果として突如とした神秘体験、神がかり、神示などを得て、人格転換と自己変革をとげ、教組として確信を持ち、みずから生き神としてふるまっている。
氏は、黒住教の黒住宗忠、天理教の中山みき、金光教の川手文治郎、大本教の出口なおと出口王仁三郎などを例に挙げてい。社会的、個人的辛酸と苦難に直面した結果、そうした体験をするのだという。
本論では、中山みきの生涯と社会との関連に注目し、当時の社会の状況を詳しく検討してきた。まず中山みきの神秘体験の直接的な原因を整理して見よう。
中山みきの神がかりの体験は、基本的には修験者の中野市兵衛によって誘発されたものである。つまり、家族の病を治すために設けられた加持祈祷が第1次的原因であった。ところがただこれで、彼女に起った激しい神秘体験の全てを説明するには物足りない。彼女が強烈な神がかり体験をし、それに圧倒されて三日もそうした状態に置かれ、またその後も3年間の長い閉じこもり生活をしていたことを考えれば、より根本的は原因を探さなければならない。
彼女自身の身体的、精神的虚弱さ、そして家族間の不和、とりわけ夫との不和が挙げられる。具体的には、相次ぐ子供の出産と死亡による身心の疲労、流産や過重な家事の負担、長男秀司の足病や自分の腰痛、夫の眼病など家族の病による危機感、夫の無責任な生活による不満、などを挙げることができる。
これらの個人的原因のほかに、社会的混乱や危機感もその遠因として挙げられる。すなわち、伝染病・洪水・凶作・飢饉など、連年続く自然災害や、一揆の多発、そして外国船の来航も、彼女に危機感をもたらし、精神的に不安の状態に陥る一原因であったと言えよう。
中山みきの神秘体験とその思想の背景
高木宏夫は、中山みきの神がかり体験の社会的環境として、①彼女の身分が貧民であると同時に地主であること、②当時、天災や事件が多発していたこと、③中山みきの家庭生活が不幸であったこと、などを指摘する。
ここで高木が言う「神がかり体験の環境」とは、「神秘体験及びその思想の背景」として理解することもできよう。もちろん、これらの背景はある意味においては、天理教発生の背景としても考えられる。高木は、以上のように三つの点にまとめたが、本論での結論では以下のことが考えられる。
第一、中山みきの時期は、自然災害や飢饉などによる百姓一揆が非常に多かった。中山みきにとっては、不安と危機感をもたらす現象として理解されていたはずである。
第二、おかげ参りや、ええじゃないか踊りが大規模で起っていた。多くの人々が集団で移動しながら踊る様子は中山みきに深い印象を残していたと思われる。
第三、蘭学・水戸学・国学の流行も遠い背景として挙げられる。ただし、これらの学問が中山みきや天理教の思想に直接、影響を与えたかどうかは不明である。しかしながら、彼女は、こうした学問が流行していたその時代の人であったことは注目に値する。
第四、外国船の来航と開国が挙げられる。周知のように、開国は日本社会に大きな混乱と変化をもたらした。中山みきの思想と天理教は、そうした混乱と変化の中から生まれたものである。
神秘体験は精神における一種のパニック状態である。極度の不安感・恐怖感によって生じた脳の不具合なのである。西洋人の進出は日本社会に一種のパニック状態をもたらし、それが中山みきの神秘体験に深い影響を与えていたと考えられる。
(註)
1)小論は私が2003年3月に東京大学人文社会系研究科博士論文として提出した『東アジア新宗教に見られる神秘体験とその思想』の一部分(第1部の第3章)を修正したものである。
2)隣家の子供を救った事件は、天理教教会本部『稿本天理教教祖傳』(天理教道友社、1956年初版、2000年 )には1828年31歳の時となっており、上田嘉成の指摘とは異なる。
3)上田嘉成「天理教々祖傅に於ける年代區分に就て」(『宗教研究』第四輯、通年114号、1943年)787-790頁。
4)天理教教会本部『稿本天理教教祖傳』。
5)高木宏夫「宗教教團の成立過程-天理教の場合-」(『東洋文化研究所紀要』第6冊、1954年)270-271頁。
6)天理教教会本部『稿本天理教教祖傳』。以下、『稿本天理教教祖傳』で記述した中山みきの伝記事項は、特別な場合を除いて注記しない。
7)加納宗治郎「忽如、神が天降る-天理教開祖・中山みきの自虐と反逆の生涯-」(『日本及日本人』1582、1986年)91頁。
8)天理教教会本部『稿本天理教教祖傳』13頁。以下、『稿本天理教教祖傳』で記した中山みきの伝記事項は、特別な場合を除いて注記しない。
9)天理教道友社編『ひながたき紀行-天理教教祖伝細見-』(天理教道友社、1993年初版、1999年)20頁。
10)加納宗治郎「忽如、神が天降る-天理教開祖・中山みきの自虐と反逆の生涯-」(『日本及日本人』1582、1986年)92頁。
11)高木宏夫「宗教教団の成立過程」(『東洋文化研究所紀要』第6冊、1954年)283頁;島薗進「神がかりから救けまで」215頁。
12)島薗進「神がかりから救けまで」(『駒沢大学仏教学部論集』第8号、1977年)215頁。
13)高木宏夫「宗教教団の成立過程-天理教の場合-」287-289頁。
14)天理教教会本部『稿本天理教教祖傳』13頁。
15)天理教教会本部『稿本天理教教祖傳』13頁。
16)加納宗治郎「忽如、神が天降る-天理教開祖・中山みきの自虐と反逆の生涯-」92頁。
17)本居宣長も浄土宗の五重相伝を受けたことがある。彼は、相伝の儀式前の7日間の様子について、日記に次のように記している。すなわち、「毎日、称名一万返。沐浴一度、礼拝三度也。七日、魚酒煙草等断慎ム」と(松本滋「本居宣長と中山みき-比較思想的考察の試み-」、『聖心女子大学論叢』88、1997年 65頁より再引)。
18)加納宗治郎「忽如、神が天降る-天理教開祖・中山みきの自虐と反逆の生涯-」93頁。
19)島薗進は、中山みきは浄土宗の救済理念を信ずる信仰者であったわけではない、と見る。彼女にとっての浄土宗は、強かった実父と前川家の精神を象徴するものであったと評価する。なお、浄土信仰と彼女の宗教的自覚との関わりを、民俗<宗教>との関連から、否定する(島薗進「神がかりから救けまで-天理教の発生序説-」214頁)。
20)青木美智男『百姓一揆の時代』(校倉書房、1999年)225頁。
21)閔斗基編『日本의 歴史』(知識産業社、1976年)157頁。
22)中山家は庄屋敷村では地持ちとして知られていた(天理教道友社編『ひながたき紀行-天理教教祖伝細見-』、天理教道友社、1993年初版、24頁)。
23)天理教道友社編『ひながたき紀行-天理教教祖伝細見-』30-31頁。
24)岩田健「大塩平八郎の乱」(歴史教育者協議会編『図説 日本の百姓一揆』東京・民衆社、1999年)224頁。
25)岩田健「大塩平八郎の乱」227頁。
26)大石慎三郎『日本の歴史 幕藩制の転換』(第20巻、小学館、1975年)340-342頁;。
27)加納宗治郎「忽如、神が天降る-天理教開祖・中山みきの自虐と反逆の生涯-」93頁。
28)おかげまいりやええじゃないかでは、大神宮などの神が突然人に降りてくることが少なくなかったと伝えられる(西垣晴次『ええじゃないか-民衆運動の系譜』1973年、53,99,227頁。これは島薗進「神がかりから救けまで-天理教の発生序説-」226頁より再引)。
29)久木幸南『日本の宗教』140頁。
30)高木宏夫は「『ええじゃないか踊り』は、庶民の乱衆行動であるが、天理教の教理にはその雰囲気が伝えられている」と指摘する(高木宏夫「宗教教團の成立過程-天理教の場合-」272頁)。島薗進「神がかりから救けまで-天理教の発生序説-」226頁も参照。氏は、天理教とおかげまいり・伊勢神道との関係は、「陽気」、「世直り」、「あしきをはらふ」、「月日」、「真柱」、「十柱の神々」、そしてかぐらづとめやておどりなどの祭、治病活動などに窺えるという。
31)杉田玄白『蘭学事始』(緒方富雄校註、岩波文庫、岩波書店、1979年)46頁。杉田玄白は、蘭学が流行した理由として「漢学は章を飾れる文ゆゑ、その開け遅く、蘭学は実事を辞書にそのまま記せしものゆゑ、取り受けはやく、開け早かりしか。また、実は漢学にて人の知見開けし後に出でたることゆゑ、かく速かなりしか、知るべからず」(杉田玄白『蘭学事始』46頁)と、蘭学が辞書を用いることと、すでに漢学で人々の知見が開いていたことことを挙げている。
32)厳密に言えば、オランダから入ってきた学問は蘭学、後の幕末に、イギリス、フランス、ドイツなどの国の言葉が知られ、これらを広く洋学と呼んだ(尾藤正英『日本文化の歴史』岩波新書、岩波書店、2000年、194頁)。
33)渡辺崋山の「慎機論」において、注目されるのは彼の大臣や儒臣などに対する厳しい批判もさることながら、彼の西洋に対する詳しい情報であろう。こうした側面においても当時の蘭学の水準や有効性が窺える。崋山は「そもそもわが国が厳重な鎖国の体制をとっていることは、海外諸国の熟知するところである。その証拠は、オランダ刊行の諸地誌、またロシアのクルウセンの紀行記やゴローニンの手記に詳しく見えている。したがって漂流民の送還と引きかえに、交易を願い出ても、許されないことは、もちろん承知のうえで来るのだから、ロシア使節にたいするレサノットのように、交易を拒絶されたからといって、(モリソン号が)おめおめと帰国するようなことは絶対にあるまい」(渡辺崋山「慎機論」『渡辺崋山・高野長英』日本の名著25、中央公論社、1972年、116頁)と正確な分析を行っている。
34)佐藤昌介「経世家崋山と科学者長英」(『渡辺崋山・高野長英』日本の名著25、中央公論社、1972年)を参照。
35)家永三郎『日本文化史』(岩波新書、岩波書店、1959年)215-216頁;閔斗基編『日本의 歴史』181頁。
36)村山吉廣「中村敬宇」(『漢学者はいかに生きたか-近代日本と漢学-』あじあブックス018、大修館書店、1999年)96頁。
37)閔斗基編『日本의 歴史』177頁。
38)丸山真男は国学を徂徠学の克服として見なす。儒教を政治化した徂徠学が、非政治的契機を導入することによって国学の近代的意識に繋がっていると見る。ただ、国学の非合理的かつ神秘的な側面は、前近代的な様子と理解されるが、これは文献学の実証的な傾向を伴っていた点からみて「近代的」であると言う。丸山は、西洋のスコラ哲学に対抗した有名論者やフランシスコ学派の例を挙げて、国学の両面的な側面を「近代的」と解釈する(丸山真男『日本政治思想史研究』、岩波新書、1961年、307-311頁)。注目すべきところは、丸山の解釈よりは、国学にはこうした実証主義的傾向と共に神秘的傾向が強かった点である。
39)家永三郎『日本文化史』、岩波書店、1982、212頁。
40)閔斗基編『日本의 歴史』175頁。
41)宣長の学問は儒教批判を中心としたものである。彼は儒教の道を作為として批判し、古事記や日本史紀に見られる社会や自然に対する道、すなわち、自然であり真実の道を尊んだ(守本順一郎『日本思想史』김석근訳、理論と実践、1988年、405-406頁)。
42)松本滋「本居宣長と中山みき-比較思想的考察の試み-」(『聖心女子大学論叢』88、1997年)69頁。
43)松本滋も、「から」あるいは「からごころ」に対する批判を、本居宣長と中山みきの思想構造上の共通点の一つとして挙げている「本居宣長と中山みき-比較思想的考察の試み-」70頁。
44)丸山真男『日本政治思想史研究』469、486頁。
45)井上清『日本の歴史』(岩波新書、岩波書店、1965年)76頁。
46)マックファーランド『神々のラッシュアワー』(堀一郎「日本のシャーマニズム」258頁より再引)。
47)当時、西日本の諸藩を牽制していた幕府は、最後まで自分の手で貿易を独占しようとしていた。これに対して西日本の諸藩は自らの力が弱められることを恐れて猛反発し、反対する。幕末の政治運動、すなわち尊皇攘夷運動、公武合体運動、倒幕運動などの底流には、開港の仕方をめぐる幕府と諸藩の対立があった(安岡重明「第6章 市場構造」108頁)。
48)堀一郎「日本のシャーマニズム」、『堀一郎著作集』第8巻・第3部、未来社、1982年、260頁。
49)高木宏夫「宗教教團の成立過程-天理教の場合-」281-284頁。
50)参考資料は以下の通りである。表8、表9も同様である。明治5年までは陰暦で、明治6年以後は陽暦である。年齢は数え歳。
1)天理教教会本部『稿本天理教教祖傳』。
2)天理教道友社編「参考年表」(『ひながたき紀行-天理教教祖伝細見-』天理教道友社 、1993年初版、1999年)323-329頁。
3)児玉幸多編『日本史年表・地図』(吉川弘文館、1999年) 。
4)『近代日本総合年表』岩波書店、1968年。
5)閔斗基「日本史略年表」(閔斗基編『日本の歴史』ソウル・知識産業社、1976年)。 |
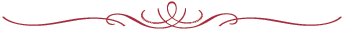
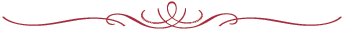
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)