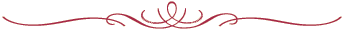
| �ʏ́y�����̖��O�����j�z |
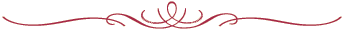
�@�i�ŐV�������Q�O�O�T�D�R�D�P���j
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
| �@���{�������v�z�y�т��̉^���ɔ���O�̐l����O�^���̐��Ƃ��āu�S���Ꝅ�A�ł����킵�^���v���������B�����ېV��A�����J���̗���Ƌ��ɁA�ݗ��̓`�����y���A���a���v�z�A���R�����^���A�A�L���X�g���I�q���[�}�j�Y���A�Љ��`�A���Y��`�A�����{��`�A�Ж���`���̑����X�̐����v�z�ɔ��čs�����B �@���̌��ʂ��̗v�ł���B������ɉ]�킹��A��������O�����̂͊O���ł��荪�t���Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A��͂芴���I�Ȃ��̂��Ⴄ����B���Ă݂�A�u�S���Ꝅ�A�ł����킵�^���v���������A���̓`���I�Ȃ��̂̂����ǂ����̂��p�����A���̏�ɊO���̗D�ꂽ���̂��z�����Ă�����@�ōč\�����˂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B �@�Q�O�O�T�D�R�D�P���@������q |
| Re:������̃J���e�����]���̂Q�Q | ����� | 2005/03/02 |
| �@�y�u��V�^���Ƃ��Ă̕S���Ꝅ�A�ł����킵�A��������Ȃ����^���_�v�z �@�����ېV�̈̋Ƃɂ́A�u�ォ��̊v���v�Ƃ��Ă̓|���^�����x����u������̊v���v�^�����������A����́u�S���Ꝅ�A�ł����킵�A��������Ȃ����^���v�ł���A�X�Ɂu���Z�A�����A�V���v�ɑ�\�����_���n���O�@�����d�Ȃ��Ă���B�������x�����O�I�����̋`���A������҂����݂����B������҂ɂ́A��̐V���u���W���A�W�[�̑��ɍ��ۋ��Z���{����Ȃ��Ă����B�܂�A�����ȗv�f������ł������ƂɂȂ�B �@������́A�����ېV�̈̋Ƃ����̂悤�Ȏj�ςő����Ă���B�������̕��͂ŏ����������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA�e���ڂ��ƂɌ����悤�Ƃ��Ă���B�����ł́A�u�S���Ꝅ�A�ł����킵�A��������Ȃ����^���v�����グ��B�T�v�́A�����̖��O�����j(minsyushi.htm)�ɏ����t�����B �@�剖�������̂Q�O�O�S�D�P�Q�D�T���t���u�r�d�m�j�h�A�P�P�U�R���R�ʁv�́u���N�͒��������}�I�N����P�Q�O�N�A���������w����x�ɋ����������{�̖��O�A�S���Ꝅ�͑g�D���ꂽ�ًc�\�����Ă������v(http://www.bund.org/opinion/20041205-1.htm)�Ɏh�����A������Q�Ƃ��A��荞�B�剖�������͋��炭���쌠�]�X�]��Ȃ����낤�Ǝv���A�n���Ɏ�荞�B�ǂݒ����A�ǂ�ǂ���������ł��B �@�v���A���y�O�����̌���u�J���C�`�v���S���Ꝅ�̐��Ԃ�`���Ă����B�m���A�P�X�U�O�N��㔼�̎����ł���A����͑S�����^���̍V�g���Əd�Ȃ��Ă���B���������A�o�����g�{���́u�_���`�v���ʔ��������Ȃ��B�]���鎖�́A�^���̍V�g�ɂ͂�����x���鎍�A���y�A�G�A��������Ƃ������Ƃ��B���͂��ꂪ�Ȃ��B�e���r�̐��]�W���[�i�����Ԑ���ŁA�u���|��ԁv��N�H�������Ă���悤�Ɏv����B �@����ɑ���u�C���^�[�l�b�g��ԁv��n�����˂Ȃ�Ȃ��B�V�������e���r�����ׂɂȂ�����_�]���I�m�ȕ��|������\�z���˂Ȃ�Ȃ��B������͍��̂Ƃ���u���C���v�Ɍ��o���Ă���B�S���͓ǂ݂���Ȃ��̂ŁA���C�ɓ���̂Ƃ����ǂ܂��Ă��������Ă���B���̎�̃l�b�g�V���ł��o��Ζʔ����ƍl���Ă���B���N�����炻���������悤�Ȃ��̂��~�����B���̑����e���r�͊Q����������B �@�b��߂��B�����̖閾���O�����̌�ǂ��]�ς��Ă������̂��A������ꂽ�̂��A���ꂱ���������ېV�_�ƂȂ�ׂ��ł͂Ȃ��낤���B�Ȃ�A���̓]�ς��������������߂ɂ��A�����ېV�O�̏ォ��Ɖ�����̊v���̑����ƍ\�}���m�F���Ă����˂Ȃ�܂��B���̕ӂ�̍l�@���ア�̂ł͂Ȃ��낤���B �@�ŋ߂̃q�b�g�́A���ƃ��[�j�����A���{�̖�����V�^���Ɍ��������{�l�̔\�͂𒍎����A�����]�����Ă��邱�Ƃ�m�������Ƃł���B�����j�`�F���R�i�ɏW�@�r����j���̢���[�j���Ɠ��{�������������Ă���A������́A�u���[�j���̓��{�y�ѓ��{�l�_�A�����ېV�_�v(marxismco/marxism_lenin_nihonron.htm)�ɏ����t�����B �@�������[�j����`�̕肪���炩�ɂ�����邪�A����͂���Ƃ��āA���[�j���̊v���R���ƂƂ��Ă̌��т͕]�����˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�ёR��ł��낤�B�������̎�̎v�z�̈Ӌ`��������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�����]���鎖�́A�o�ς̑ǎ��ň�l�Ɏ��s���Ă���B����͂Ȃ��Ȃ̂���₤���Ƃ��ʔ������A����͕ʍe�ł��Ă݂����B �@�F���r���[�ɂȂ��Ă��邪�A�F�l���̂��͓Y�������肻�̂����L�v�Ȃ��̂ɂ������Ǝv���B �@�Q�O�O�T�D�R�D�Q���@������q |
||
| �y�������̎Љ��z |
|
�@�������̓��얋�ˑ̐��������Q�O�O�N���o�߂�������蒁�����]�тĂ������B�����O�����ɂ�����䂷�����\�͂Ɍ����A�����@�\�ɗh�炬�������Ă������B���얋�ˑ̐��̎����̗���́A���ɓI�ɂ͐l���̑啔�����߂�_���ւ̈����Ƃ��ċA�����A�c���̌�G�����_����������������A�E��������@�\���Ȃ��Ȃ�A�����̓I�_���Љ����Ⴓ���Ă������B�x�d�Ȃ鎩�R�ЊQ�A�s��ɂ��\�킸���˂̔N�v�Ă̎�藧�Ă��������A�_���ɓh�Y�̋ꂵ�݂��Ȃ߂����A���U�A�Ԏq�̊Ԉ����̂Ďq�A�쎀�A�l�Ȃ►�̐l�g������i�s�����������B���̌o�߂Ŋn��Ƃ������n��K�w�����܂�n�߁A�_���K�w���ɕx�_�ƕn�_�̕ʂ��ۗ����Ă������B |
| �y���쐭������̕S���Ꝅ�A�ł����킵�l�z |
|
�@�Q�O�O�S�D�P�Q�D�T���t���u�r�d�m�j�h�A�P�P�U�R���R�ʁv�̑剖���������u���N�͒��������}�I�N����P�Q�O�N�A���������w����x�ɋ����������{�̖��O�A�S���Ꝅ�͑g�D���ꂽ�ًc�\�����Ă������v�����Q�Ƃ���B �@�������A�Ꝅ�̎�d�҂����߂ŖƐӂ���邱�Ƃ͂Ȃ������B�k�}��g�ނ��Ǝ��̂��@�Ƃ���Ă�������A�Ꝅ�̗v����������������Ꝅ�̐ӔC�҂͍߂����A������������ꂽ�����Y���ꂽ�肵���B�Ꝅ�����U�����퐶���ɖ߂������ƂŁA�̐����͈͂Ꝅ�̎w���҂�E�����đߕ߁A�������s�����B ���l�́A�g����䋟�Ɖ������ނ���`���Ƃ����߁A���̉Ƒ��̐�����}�������B����́A�S���Љ����������R�^����g�D������������ׂ̒m�b�ł������B���݊e�n�Ɏc���Ă���`���˂͂ȂׂĂ��̂悤�Ȃ��̂ł���B �@�����������͂̒e���ɑ��Ė��O�́A�ł��邾���]���҂��o���Ȃ��悤�ɓw�͂����B���͑��ƂP�S�T���Ԃɂ��킽����𑱂������ʁA�����ړI��B��������ɁA��l�̏����҂��o���Ȃ��ł��܂����P�W�T�R�N�́u�암�O�Ɂi����ւ����j�Ꝅ�v�ȂǁA�]���ҊF���ő叟�������Ꝅ�������Ⴀ��B �@�]�ˎ����������17���I���ɂȂ�ƁA��̔˂̒��̂قƂ�ǂ̑����S���Ꝅ�ɎQ������u�S�ˈꝄ�v�i����[�l�X�g�j����������悤�ɂȂ�B�S�ˈꝄ�́A���X�̊Ԃ������ĈꝄ���Ăт�������Ƃ��납��n�܂�B�Q�������߂����̑�\�҂����ɏ�����A�ˁA���ӂ�����������Ă����B�����̑��̍��ӂ��m�F�����̂ƕ��s���āA�����ƂɖI�N�̏������������A���悢��剹�ʂ̍��}�i�ق�L����A�e�̔��C���Ȃǁj�ň�ĂɖI�N����B�@�̍s�����Ăт�������ɂ̓��X�N�������B���ɂ͐_�X�ւ̐������q�ׂ��N�������t�����A�V�є����̗U���ł��u���Ƃ�{���v��㩂ł��Ȃ����Ƃ�ۏႷ��`�ɂȂ��Ă����B �@ ���������Ꝅ�̑�K�͉��ɑΉ����Ė��{�́A18���I�O���ɂȂ�ƑS���ꗥ�̕S���Ꝅ�֗߂���B�֗߂ł́A�I�N�̎w���ҁi����j�P�l�����Y�ɂ��邱�Ƃ���߂�ꂽ�B�t�Ɍ����A�ō��w���҂ƌ��Ȃ��ꂽ�P�l�ȊO�̎Q���҂͏�������Ȃ��������m�����ꂽ�̂��B���{�͂���ɂ���āA�w���҂ƈ�ʎQ���҂Ƃ̊ԂɋT������邱�Ƃ�_�����B
�@����ɑ��A�Ꝅ�̑��̍��ӕ����i�Ꝅ�_��A�A����j�̓��e�́A�Ꝅ�ŏ��Y���ꂽ�҂��o���ꍇ�ɂ��̈⑰�̐������Q���҂������ŕۏႷ�邱�ƂȂǁA��̓I�Ȍ_����e�𖾕���������̂ɂȂ��Ă����B���̑��A�Ꝅ��p�̕��S���@�Ȃǂ��A����ɖ��L����邱�Ƃ���ʉ����A���O�̑��͈Ꝅ���w���Ҍl�̐����ɂ����̂łȂ������ӔC�ɂ����̂ł��邱�Ƃ��ӎ��I�ɖ�������悤�ɂȂ��Ă������B �@�P�V�W�O�N������ɁA�l�ʂ�̑����ꏊ�ɈꝄ�̌Ăт��������f�����钣�D���A���ɂƂ��Ă����B���Ƃ��Ɠs�s���ł́u�ł����킵�v�ł͂��̓������@���̂��Ă����B�S���Ꝅ�����̕��@���̂�悤�ɂȂ����B���P�ʂ̉E������݂̈Ꝅ�Q����O��Ƃ���閧���ɉ����A���X�ƒ��D�Ō��N���Ăт�����悤�ɂȂ����B �@�����̕S�����Q�������Ꝅ�ɓ����̕x�_���G�����悤�ȏꍇ�A�Ꝅ�����̕x�_�̓@��ł��̑ΏۂƂ��邱�Ƃ��������B�܂��A���Q�W�ɂ����ċ��ʂ���͂��̎ғ��m�ł��A�Ꝅ�Q���ҁi�u�����ҁv�j�ƈꝄ�Q����K���݂��������Ă��܂��ҁi�u�Q�ҁv�j�Ƃ̕��������܂�Ă���B �@�u�ł����킵�v�́A�ꌾ�ł����Γs�s�\�������A�����I�Ȗ\�͍����Ƃ͑S���Ⴂ�A��������g�D�I�s�������ɂ̂��Ƃ��čs����̂��킾�����B�����������������Ă���ƌ���ꂽ�����⍂���݂��̓X�Ȃǂ��W�c�ŏP����������j��̂���̓I�ȍs�����e�ŁA�@�E�l�g�̎E���͂��Ȃ��A�A�E�֏悵�Ă̗��D�s�ׂ����Ȃ��A�B�E�Ђ������N�����Ȃ��悤���ӂ���A���̂R��������{�I�ɂ͌��i�Ɏ��ꂽ�B |
|
�@�Ꝅ�́u�����v���x�����m�F���Ă����B�S���Ꝅ�ɂ͓S�C���g���邱�Ƃ��������B�Ƃ��ɂ͒��������̉��{���̏e���Ꝅ�����������Ă�������������B�ɂ�������炸�A�S���Ꝅ�Ŗ��O�������C���Đl���E������������͂P�����L�^����Ă��Ȃ��B���Њd�Ȃ����͖蕨���ʂŎg�p���ꂽ�悤�ł���B�]�ˎ����ʂ��ďe�́A�p�����ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A���b���̂��߂Ɏ��p����Â��Ă����B �@�s�s���ł́u�������킵�v�ł����l�̖ړI�ӎ������������ꂽ�B�o�ϓI��҂����ڂ̂��̂̏W������古�ƂȂǂ��P������̂�����A�ǂ̂悤�ȗ��O�𗧂Ă悤�ƌ���ł͗��D�s�ׂ��N����B�����A���ꂪ������ΕK�����l�͒��Ԃ������牣������A�����̂͂��̏�Ɏ̂ċ��邱�Ƃ����v���ꂽ�B���������͌��͂̐����ύX�𔗂邽�߂̍R�c�s�������Ă���̂�����A���݂̗v�f���Ԉ���Ă����������Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂��������łȋ��ʔF���ɂȂ��Ă����̂��B�@ |
| �y���쐭������̕S���Ꝅ�A�ł����킵�l�z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@��P�X���I���{�̖��O�v�z������Q�Ƃ���B �@�Q�U�O�N�Ԃ̍]�ˎ����ʂ��āA�L�^�Ɏc���Ă���S���Ꝅ�͂R�Q�P�Q���A�ł����킵�͂S�W�W���B�]�ˎ���̓��{�́A��ʏ����̎��������ߑ�ȑO�̎Љ�Ƃ��Ă͐��E�ɗ�����Ȃ��قǍ����A�Ꝅ�ɎQ���������O�̑����c�����L�^���c��Ɏc����Ă���B����ƌ��͑���������L�^�Ƃ��Ƃ炵���킹��ƁA������ł������ɋq�ϓI�ȁu�S���Ꝅ�̎����v�ɔ��邱�Ƃ��ł���B�ۍ�q���u�S���Ꝅ�Ƃ��̍�@�v�i�g��O���فu���j�������C�u�����[�v�j��ؔ��q�j���u�S���Ꝅ�̎���v�i�Z�q���[�j�A�ؓ��́u�S���Ꝅ�����N�\�v�ɂ���đ�\�I�Ȃ��̂���Ă݂�Ǝ��̂悤�Ȏ��Ⴊ�F�߂���B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@���������S���Ꝅ�ŋ��ꂽ���e���m�F���Ă����B
�@�܂�A�S���Ꝅ�ł̗v���̔w�i�ɂ́A�א��҂ɂ͓V���̂������_�ɏƂ炵�Đm�����{���`��������A����ɔ�����ꍇ�ɂ͐l����O������̝y�I��������A�V���������ē��R�Ƃ���ϔO�����������Ƃ����炩�ɂ���Ă���B |
| �y�������̕S���Ꝅ�A�ł����킵�l�z |
| �@�����E�ېV���́A�S���Ꝅ���u�������Ꝅ�v�ւƓ]�Ă����������ł������B�x�z�K�������ł��F���E���B�̃��[�_�[��������V�^���ɏ��o���Ă���A����Ɍĉ����邩�̂悤�ɖ��O�̑�������������������J�n���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B����O�ӎ��̓`���ɂӂ������������̐��ϊv�^������W�J����Ă������B
�@�]�ˎ���̈Ꝅ�ɂ́A�������̂��̂����͂��������B�v���ѓO�͂������A�����]���҂��ŏ����ɗ}����A����ȈꝄ�̕��@���m������Ă������̂́A���O�̑����Ꝅ�̋L�^���ӎ��I�Ɍ�i�ɏ����c�����������Ƃ̐��ʂ������B�L�^�̓��e���u���͂������������v�Ƃ������P�Ƃ��čL�����L����A���ꂪ�S���I���x���ɂ܂ōL�����Ă������Ƃ��A�ߔN�����炩�ɂȂ��Ă���B |
| �y�_�R����Y�ē̉f��u���̗��v�l�z |
| �@�_�R����Y�ē̉f��u���̗��v���b������ł���B�P�W�W�S�N11���P�������S�g�c�����_�ЂɁA���E���E�e�ŕ��������_���R�O�O�O�l���W�܂����B�������{�ɂ��̐\�����Ɍ������������}�̖I�N���B���N�͖I�N����P�Q�O���N�ɂ�����B |
| �y�p�����g�I�[���R�b�N�̎w�E�l�z |
| �@�������ɓ��{��K�ꂽ�p�����g�I�[���R�b�N�́A�㋉�҂̉����҂ɑ��錾�������J�Ȃ��Ƃ���{�l�̓����Ƃ��ē��M���Ă���B�퍑����ɓ��{�ɑ؍݂��Ă����L���X�g���`���t�������A�����҂̖ʖڂ�ׂ����㋉�҂͕K�����Q�����̂ŁA�n�ʂ������Ă����l�J���Ȃ��悤��ɒ��ӂ��Ă���̂����{�l���Ə����c���Ă���B |
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)