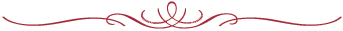
| 第3章の4(15から19)(後編4) |
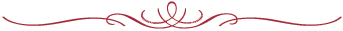
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路第3章の4(15から19)(後編4)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第3章の4(15から19)】 |
| 十五 |
| 一つは他に友達もないところから、自然彼は末松とよく会っていた。しかしその頃、末松は祇園の三流芸者との新しい関係で幾らか有頂天になっている時で、謙作は此方から訪ねて行くような場合、多少はその心遣いもしなければならなかった。末松の方は又、直子に対する遠慮から謙作を其処へ誘おうとはしなかった。或る晩、謙作は出先から晩(おそ)く末松の下宿を訪ねた。出掛けるものなら、もう出掛けているだろうと思いながら行った。ところが、末松はこれから出掛けようとするところで、二人は両方でちょつと気の毒な想いをした。「いいんだ。本統にいいんだよ」。こんなに云い、末松は殊更寛(くつろ)いだ風で、火鉢に炭を次(つ)いだりした。しかし暫くするとやはり落ち着かぬらしく、「此所へ呼んでみようか」と云い出した。「呼ぶぐらいなら、彼方へ行こう。その方がいいよ」。謙作が云った。「本統にいいのかい? 何だか奥さんに悪いな」。末松は羞(はじ)入ったような嬉しそうな顔をして頭を掻(か)いた。二人は間もなく寒い戸外に出たが、その時はもう九時を過ぎていた。平安神宮の前の広い静かな通りを真直ぐに電車路の方へ歩いた。「何所で呼ぼう?」。末松が云った。「君の普段行く所でいいじゃないか」と答えた。「芸者も赤切符なら、茶屋も赤切符なんだよ。どうもヴァニティ(自尊心)を傷つけるからな」。末松はこんなに云って笑った。「それより何所か料理屋へ行こう」。「肝心の本人が居なかったら仕方がないね。僕は今飯を食ったばかりだし、君もそうだろう?」。「うむ。だけど、余り売れっ児でもないから、---」。 とにかく、何所かで一度電話を掛ける事にして、二人は電車で祇園の石段下まで行き、近いカフェーに入った。末松は直ぐ電話口へ立った。「うむ」---「うむ」---「うむ」。末松は返事ばかりしていたが、「じゃあ、さいなら」。がチャンと邪見に受話器を掛け、不愉快な顔をしてテーブルに還って来た。「六十円じゃ威張れないが、何しろ癪に触るな」。こんな事を云いながら、傍に立っていた給仕女に強い酒を命じた。「居ないのか」。「大阪の芝居へ行って、今日は帰らないと云うんだ。---嘘だよ」。気の毒なほど露骨に苛々してた。彼は何所かで自身以外のいわゆる旦那と一緒に騒いでいるその女をまざまざと見るかのような不愉快な顔をした。電話が鳴って給仕女の一人がそれに出た。「俺か? 俺なら居ないぞ。そう云ってくれ」。その時末松は神経質に云った。そして、それが当っていた。給仕女は送話器を掌(てのひら)でふさぎ、振り返って、「おいやすと申したんどっせ」と当惑したような顔をした。「そんなら電話には出ないと断ってくれ」。しかし結局末松はしつこい茶屋の女将(じょしょう)の為に呼び出され、暫く押し問答の末、やはり茶屋まで行く事を承知して了った。「きたない家だよ。---しかし居ないなら、急ぐ事もない。もう少し此所へ居よう」。彼は続けて強い酒を云い、無理にも落ち着こうとした。亦、女将に云われ、直ぐ出向く事も業腹だと云う風だった。そして、「本統にいいね? 何だかつまらないおつき合いをさせて、悪いな」とも云った。「僕はいいよ」。謙作は末松を気の毒に思い、何気なくそうは云ったが、末松の今の気分と自分の気分とが如何に離れているかが顧みられ、それが具合悪かった。実際彼の心はともすると、淋しい衣笠村の家に彼の帰りを待ちわびている直子の上へ帰って行った。彼はそれが末松に映る事を恐れ、できるだけ自分でも何気なくしていた。 「花見小路(こうじ)にもう一軒知ってる家があるんだ。初めからそっちへ行く方がよかった」。こんな事を末松はいっていた。カフェーを出て、茶屋への途(みち)でも末松はまだ茶屋の安っぽい事を気にしていた。彼は酔ってもいたのだ。そして茶屋へ来ると、やはり彼はどうしても上がる事を厭(い)やがり高台寺の方の料理屋へ行く事にして、既に十時を過ぎていたから、茶屋から先へ電話をかけさせ、二人だけでその家へ向った。植込みの奥の小さい中二階に電燈がついていた。二人は其所へ通された。二十分ほどすると植込みの踏石を踏む三四人の忙(せわ)しい履物の響きがして、女将と若い芸者二人とが女中に導かれ、賑やかに乗り込んで来た。末松は絶えず苛々しながら、女将に当り散らした。若い芸者たちがその女の事で揶揄(からか)い、彼の機嫌を幾らかでも直そうと努めたが、末松はその手に乗らず、意固地に憎まれ口をきいた。「何しろ六十円の旦那だからな。威張れねえよ」。みこんなことを云い、そう云う女にこんなにも嫉妬を起こす自身を憐れむ風さえあった。女将も無理に呼び出しながら今は持て余していた。そしていよいよ白け切った座を持ち兼ねると、女将から云い出し、其所を引上げる事にした。 謙作は早く直子の所へ帰りたかった。十二時過ぎまで、家を空けた事がなかったから心配していそうにも思えた。が、やはり彼は一人先へ帰る事もできなかった。寝静まった町を五人は安井神社の境内を抜けて帰って行った。背の低い、癖毛の、ちょっと美しい芸者が何か末松に揶揄いながら暗い路で謙作の手を握った。謙作は握り合した手をそのまま自分の二重まわしのポケットに入れ、女の肩を二の腕に感じながら歩いた。彼は前夜直子との散歩で同じ事をした。そして、今、芸者とそうしながら、彼はやはり眠らずに待っている直子の上を考えた。握り合した手は両方で握り締めなかった。そして、何時か、何方(どっち)からともなく離して了った。茶室へ帰ると女将は泊る事を勧めたが、末松は芸者二人だけを其所へ泊らす事にし、直ぐその家を出た。二人は何となく別れ悪(に)くかった。謙作の方はそれ程でもなかったが、末松のどうにも法のつかないそう云う場合の気分は一年前の生活で謙作にも明瞭(はっきり)していた。「二時頃までに帰ればいいよ」。彼はこんなに云った。「花見小路の家へ寄ってもいいかい?」。末松は気兼ねをしながらいった。「うん」。「俺は暫く時任のの家へは行かないよ。奥さんに具合が悪いから---」。こんな事も云った。 二人は暗い路次を抜けて行った。其所で末松は一人後(あと)になり、立小便をした。丁度同じ方へ抜けて行こうとする、中折帽を眼深(まぶか)に被った若い男が彼の背後(うしろ)を通り過ぎると、「失礼」と末松は真面目な調子に云った。しかしその男は知らん顔で通り過ぎた。「馬鹿。人が挨拶するのに黙って行く奴がおるか」。かつとして、そして小便を済ますと、末松はその細長い身体を波打たすようにしてその男の後を追い駆けて来た。謙作は暴れ馬でも止めるように狭い路次に両手を広げ、それを遮った。その男は急いで行って了った。「おい、今晩俺に喧嘩さしてくれ。いいか」。末松は酒臭い息を吐いて云った。「君がやるのはいいが、俺は関係しないよ」。「それはいいさ、しかし今の奴を撲(なぐ)ってやるよ。何方(どっち)へ行った?」。末松は謙作の手を振り離し、往来まで駆けて出ると、その辺を見廻していたが、もうその男の姿はなかった。花見小路の茶屋は新建(しんだ)ちの余り気分のない家だった。それでも前の茶屋よりは幾らか格がいいらしく、身体の大きな如何にも素人臭い感じの女将が出て来て、「長いこと」とお辞儀をした。「太夫(たゆう)さんを呼んでくれないか」。末松が云った。「へえ」。「僕はいいよ。直ぐ帰るから」と謙作は云った。女将はそれでいいのかと末松の顔を見て黙っていた。「奥さんに悪くないといいんだがなあ」。末松は具合悪そうに云い、しかし実は謙作にも泊って貰いたいらしい風を見せていた。謙作にはこれまでのそう云う習慣から、それ程貞節である良心もなかったが、そう云う事で、末松の前に妻を侮辱する事が何となく厭だった。妻を侮辱する事は間接に自身を侮辱する事だった。この寧ろ主我的な心持からも彼はやはり帰ろうと思った。間もなく車を云い、寒い風の吹く往来を遥々(はるばる)衣笠村の方へ帰って行った。 二時を過ぎていた。椿寺の前で車を乗り捨てると、一町余りの路を彼は走った。そして家の十何間か手前まで来て、走るのを止めると息を切りながら彼は何気なく咳をした。その咳で直子が急いで茶の間を出て来るのが女中部屋の硝子窓を透(とお)して見られた。「婆ァや。旦那様がお帰りだよ」。こう大きな声で云うのが、彼の所には遠く小さく聞こえて来た。謙作は門を開ける間も待たず、苗木のまばらな、まだ低い要冬青垣(かなめがき)を跳び越えて入って行った。台所口を開け、直子が飛び出して来た。「ああ、よかった。よかった」と云い、直子は両手でとんびの下の手を探し、それを握り締めた。「寝ていればいいのに」。茶の間へ来ると直子は直ぐ前へ廻り二重廻しのホックやボタンを忙しくはずしながら、「私ね、貴方が路で倒れていらっしゃるかと思ったの---」と云った。「奥さんの又、阿保らしい事をおいやす」と次の間から仙が云った。「婆ァや、本統だよ---婆ァやにそう云われるんですけど、本統に心配しましたわ。まあ、よかった、よかった」。「馬鹿だね。俺が行き倒れになってると思ったのか」。彼は笑った。「そうよ」。「一時頃にこれから尋ねにいて見よう仰有(おっしゃ)って---そんな事したかて、何所へおいきやしたかも知れへんのに」。仙は次の間で茶を淹(い)れながら笑った。「もう茶はいいよ。早く寝るといい」。謙作は直ぐ寝間着に更(か)え、寝室に入った。直子は彼の着物を畳みながら、妙に亢奮していた。そして「よかった」と云う言葉を頻りに繰り返しながらよく笑った。謙作は枕に頭をつけ、その方を向いてその晩の話をしたが、亢奮している直子はそれを聞こうともしなかった。 |
| 十六 |
| 謙作夫婦の衣笠村の生活は至極なだらかに、そして平和に、楽しく過ぎた。が、平和に楽しくと云う意味が時に安逸に堕(お)ちる時に謙作は変な淋しさに襲われた。そう云う時、彼は仕事をよく思った。しかし彼にはまとまった仕事は何もできなかった。前に信行を介して話のあった雑誌社からの催促も受けていたが、それができなかった。不相変(あいかわらず)末松とはよく会った。末松は謙作がそれを嫌っている事を知っていて余り連れて来ようとはしなかったが、それでも三度に一度、或いは二度に一度、水谷も一緒について来た。花合わせの遊びをする為には三人では物足りなかった。その必要からも自然水谷が時々仲間に入るようになった。或る時四人でその遊びをしている時だった。偶然にも謙作は、それで直子を疑った、その同じ過ちを危うく自身犯(おか)そうとした。丹一の手役がついたと思っていると、菊の札に盃がついていた。彼はこの偶然を面白く思い、愉快にも感じた。直子のはやはり見損ないだったのだ。同じ誤りを何かが故意に自身にさせたかのようにも思われた。そして事実、その事で直子を少しも避難していなかったにしろ、それが全く猾(ず)るでなかったと思える事は嬉しかった。彼はその事を直子に云おうかと思い、やはり云いにくかった。疑った自身が恥じられたからである。 二月、三月、四月、---四月に入ると花が咲くように京都の町々全体が咲き賑わった。祇園の夜桜、嵯峨の桜、その次に御室(おむろ)の八重桜が咲いた。そして、やがて都踊り、島原の道中、壬生(みぶ)狂言の興行、そう云う年中行事も一通り済み、祇園に繋ぎ団子の赤い提灯が見られなくなると、京都も、もう五月である。東山の新緑が花よりも美しく、赤味の差した楠の若葉がもくりもくり八坂の搭や清水の搭の後ろに浮き上がって眺められる頃になると、流石に京都の町々も遊び疲れた後の落ち着きを見せて来る。実際謙作達も、もう遊び疲れていた。そして、謙作はその頃になって直子が妊娠した事を知った。 六月、七月、それから八月に入ると、よく云われる如く京都の暑さはかなり厳しかった。身重の直子にはそれがこたえた。肉附きのよかった頬にも何所か疲れの跡が見られ、ぼんやりと淋しい顔をしている事などがよくあった。丁度国から直子の年寄った伯母が出て来て、それからは謙作も幾らか気持に肩抜けができた。伯母は大柄な、そして顔に太い皺のあるちょっと恐ろしい感じのする人だった。が、如何にも気持の明るい、それに初めて来た家のようになく総てを自由に振る舞い、謙作に対しても、それを包むような子供扱いをするところが、実の伯母であるかのような親しい感じを謙作にも起こさせた。余りの暑さに謙作は避暑を想い、この気のいい年寄りと三人で何所か涼しい山の温泉宿に二三週間を過ごす事を考えると、子供から全くそう云う経験がなかっただけに、彼にはそれが胸の躍るほどに楽しく想像された。彼は直ぐこの思いつきを二人に話さないではいられなかった。「どうですやろう」。伯母は何の遠慮もなく云った。「今汽車に乗せたら障らんかな」。「まだ大丈夫でしょう」。謙作は答えた。「いいや。そら、このくらいの暑さには別に障るまいが、それより動かさんがいいやろう。お湯でお腹の児が育ち過ぎても困るしな」。折角の思いつきも日の反対でそれっきりになった。直子の淋しくぼんやりしているような事もなくなった。月見、花見、猪鹿蝶、そう云う旧いやり方の花合わせなどをして遊ぶ事もあった。伯母は一月ほど居て帰って行った。 九月に入ると、直子も段々元気になり、謙作がおそく二階の書斎から降りて来ると、電燈の下に大きな腹をした直子が夜なべ仕事に赤児の着物を縫っている事などがあった。「可愛いでしよ」。一尺差しの真ん中を糸で釣った仮の衣紋竹(えもんだ)に赤い綿入れのおでんちを懸け、子供の立った高さに箪笥の環(かん)から下げてある。「うむ、可愛い」。謙作は其所にそう云う新しい存在を想像し、不思議な気がした。それは不思議な喜びだった。肩上げにくびられ、尻の辺りが丸くふくれているところが後ろ向きに立った肉附きのいい子供をそのままに想わせた。「あなたは本統は何方がいいんだ? 男がいいか、女がいいか」。自分でもそんな事を思いながら謙作は訊いてみた。「そうね。何方でも生れた方がいいのよ。どうも、こればかりは神ごとで仕方がないのよ」。直子は貫(と)おした糸を髪でしごきながら済まして答えた。「伯母さんがそう云ったんだろう」。謙作は笑った。それに違いなかった。赤児の着物は国の母親の縫った物が何枚も届いた。伯母からも洗いざらした単衣(ひとえ)で作った襁褓(むつき)が沢山に来た。「まあ、きたならしい物ばっかり」。その小包を解いた直子は予期の違った事から顔を赤くしながら云った。「羞(はず)かしいわ。こんなもの---」。「勿体ない事おいやす。こう云うものは何枚あったかて足りるものやおへんぜ。きたならしい云うて、そない洗い晒したんでないと、ややはんには荒うてあきまへんのどっせ」。「これはあなたが着ていたんだろう?」。謙作にはこう云う荒い中形(ちゅうがた)を着ていた時代の直子が可愛らしく想い浮んだ。「そうよ。だから羞かしいのよ。幾ら田舎でもこんなになるまで着てたかと思うと。伯母さんも本統に気が利かない」。直子がそう腹立たしそうに云うと、仙が傍から、「奥さん。ご隠居はんなりゃこそどっせ---」と多少厭やがらせの調子に乗って云って笑った。産は十月末か十一月初めと云う事だった。産を病院でするか、自家でするか、万一国の母親が出て来られないようなら、病院でする事に決めておいた。もし早くなると、田舎は穫(とり)入れ時で忙しく、ちょっと出にくいとの事だった。しかし何れにしろ伯母の父は又出て来るに相違なかった。 或る日思いがけなく信行が不意に訪ねて来た。それは晴れた気持ちのいい朝で、謙作は直子を連れ、裏の畑道を真直ぐに金閣寺の方まで散歩して帰って来ると、信行が洋服姿に庭下駄を穿(は)き、巻煙草をふかしながら、門の前に立っていた。「やあ」と信行は簡単に頭を下げ、直子の方を向いて、「お前もずっと丈夫だね」と云った。「何時? 今朝着いたの?」。謙作が云った。「うむ。急にちょっとお前に相談する事ができたんでね」。謙作が先に立って、玄関から上がった。「---却々いい家じやないか」。信行はその辺を見廻しながら云った。仙が出して置いた座布団を縁に近く持ち出し、腰を下ろすと信行はすぐ云い出した。「実はお栄さんの事なんだがね。----今、お前のところに三百円ばかり金あるか?」。「あるよ」。「そうか。そんなら早速それだけでも送ってやるかな」。「どうしたんだ」。謙作はお栄が少しも自分の方に相談せず、信行ばかり頼るようなところが、そうする気持は解っているが、ちょっと不満に感ぜられた。「お才かね、あの女はお前も云っていたが、やはり、本統の親切気はなかったらしいんだね。お前の方には知らさなかったそうだが、この六月からお栄さんはもう天津に居なかったんだよ。何でもそれから奉天の方へ暫く行っていて、今は大連に居るんだ」。「何をしているんだ」。「何にもせずに印判屋の二階で近所の小娘を使って自炊してるんだそうだ。---それはいいが半月ほど前に泥棒に入られて今は殆ど無一物(むいちもつ)になっちまったと云うんだがね」。「君の所へさういって来たのかい?」。「一昨日(おととい)そう云う手紙を貰った」。「馬鹿だな! そんならさっさと帰って来るがいいんだ」。謙作は何という事なし苛々して云った。 「俺もそう思うよ。だけど、その印判屋にも少し借りがあるらしく、直ぐも動けないような事が書いてあったすらね、旅費とも三百円あったら足りるだろうと思ったが、生憎(あいにく)俺の所に今まるで金がないんだ。自家から貰ってもいいが、その事を今ちょっと云いたくないからね。尤も、それだけでわざわざ出て来るほどの事もないが、今度寺で庫裏(くり)の修築をやるんで寄付金を集めてるんだ。---此所の〇〇寺の管長は絵描きだって?」。「絵描きでもないかも知れないが、とにかく白木屋(しろきや)あたりで、時々見るよ」。「却々高いそうじやないか。寄付代りに五六枚描いて貰うんで、それを頼みに行く使いうちの和尚(おしょう)に頼まれたんだよ。まあ、そんな事もあるんで急に出て来た」。「お栄さんは無一物になったというだけで、別に心配な事はないんだね」。「瘧(おこり)を病んでいると云って来たが、瘧と云えばマラリアだね。あんな所でもそう云う病気があるのかね」。「それは何所だってあるだろう。しかし別に危険な病気じゃないだろう?」。「大した事ではないらしいよ。そうだ、その瘧で、薬を呑む時間を間違えた為に、それがおこって苦しんだ挙句、すっかり疲れて、うつらうつらしていると、暑いんで夜でも開け放しておいた窓から志那人が二人入って来るのをぼんやりと見てたんだそうだよ。例の東京で買い集めた芸者の衣装が三行李(こうり)とかあって、それを部屋の隅に積んで置いたんだね。つまりそれを資本に、又同じ商売を何所かでやる気だったらしい。それをすっかりく持って行かれたんだ。泥棒だなと思いながら、あんまり疲れているんで、そのまま眠っちまったんだそうだ」。「泣きっ面に蜂だね」。しかし又お栄と会える事が謙作には妙に嬉しい気がした。彼は我知らず快活な気分になっていった。「しかしそれで早く帰って来れば大難が小難みたようなもんだ」。「そうかも知れない」。信行も一緒に笑った。 元々謙作はお栄の支那行きに不賛成だったのだ。間に入った信行の話が不十分で、それがお栄まで徹しなかったのである。しかし今案外早く帰って来る事を知ると、「そら、見た事か」とでも云って、手を差し伸べてやりたいような気持になっていた。信行は翌日京都での用事を済ますと、直ぐやはり寄付の事で、大阪へ行き、そして帰途、又衣笠村に寄って一泊して行った。「どうだい。お前も少し寄付しないか」。こういって信行は角張った手提鞄(てさげかばん)の中から、袈裟の古布(ふるきれ)か何かを表紙にした鳥の子紙の帳面を出した。謙作はそれを取上げて見た。「二百円、---二百五十円、---三拾円---拾円、五百円、---却々大きいんだな。百伍拾円、---これが君か」。「金がないから、払わないんだ」。「払わずに只書いておくのかい」。「そりゃ何時か払うよ、ある時に---」。信行は笑った。「お兄様。幾らでもよろしいの?」。傍(わき)から直子が云った。「お兄様、幾らでもいいよ。二円でも三円でも」。「そう? そんなら私五円奉納しますわ」。「それは、ありがとう。早速これへ書いておくれ」。直子は箪笥の上の硯箱(すずりばこ)を持って来て、「貴方は?」と云った。「あなたがすればもう沢山だよ。僕は寺なんかがよく保存される事は大賛成だが、自分が寄付するのは不賛成だよ。そう云う事はもっと政府で金を出すのが本統だよ」。「猾(ずる)いのね」。「猾かないさ。しかし幾らでもいいなら、僕は十円だ。一緒に僕のも書いてくれ」。謙作は人並みはずれて字が下手だった。殊に毛筆で書くと自分でも下手なのに感心した。そして彼に較べれば直子の方が遥かに人並みであるところから、近頃は筆の字は大概直子に代筆さす事にしていた。「いや、ありがとう」。信行は墨の乾くのを待ってその帳面を手提げにしまった。晩、三人は寺町、新京極辺を暫く散歩した。そして七条駅で、二人は鎌倉へ帰る信行と別れた。 |
| 十七 |
| 十月下旬のある日、謙作は末松、水谷、水谷の友達の久世などと鞍馬に火祭りと云うのを見に行った。日の暮れ、京都を出て北へ北へ、幾らか登りの道を三里ほど行くと、遠く山の峡(はざま)がほんのり明るく、その辺一帯薄く煙*(けむり)の立ち込めているのが眺められた。苔の香を嗅ぎながら冷え冷えとした山気(さんき)を浴びて行くと、この奥にそう云う夜の祭りのある事が不思議に感ぜられた。子供連れ、女連れの見物人が提灯を下げて行く。それを時々自動車が前の森や山の根に強い光を射つけながら追抜いて行く。山の方からは五位鷺(ごいさぎ)が鳴きながら、飛んで来る。そして行くほどに、幽(かす)かな燻(いぶ)り臭い匂いがして来た。町では家毎(いえごと)、軒前(のきさき)に---と云っても通りが狭いので、道の真ん中を一列に焚火(たきび)が並んでいた。大きな木の根や、人の背丈ほどある木切れで三方から囲い、その中に燃えているのが、何か岩間の火を見るような一種の感じがあった。焚火の町を出抜けると、稍(やや)広い場所に出た。幅広い石段があって、その上に丹塗りの大きい門があった。広場の両側は一杯の見物人で、その中を、褌(ふんどし)一つに肩だけちょっとした物を着て、手甲(てっこう)、脚絆(きゃはん)、草鞋(わらじ)がけに身を固めた向う鉢巻きの若者たちが、柴を束ねて藤蔓(ふじつる)で巻いた大きな松明(たいまつ)を担いで、「ちょうさ、ようさ。---ちょうさ、ようさ」。こういう力ンだ掛声をしながら、両足を踏ん張り、右へ左へよろけながら上手に中心を取って歩いている。或る者はよろける風をして故(わざ)と群集の前に火を突きつけたり、或る者は家の軒下にそれを担ぎ込んだりした。火の燃え方が弱くなり、自分の肩も苦しくなると、一抱えほどあるその松明を肩からはずし、どさりと勢いよく地面へ投げ下ろす。同時に藤蔓は弾*(はじ)けて紫が開き、火は急に非常な勢いで燃え上がる。若者は汗を拭き、息を入れているが、今度は又別の肩にそれを担ぐ。それも一人ではとても上げられず、傍の人から助けて貰うのである。 この広場を抜け、先の通りへ入ると、其所にはもう焚火はなく、今の松明を担いだ連中が「ちょうさ、ようさ」という掛け声をして、狭い所を行き交う。子供は年相応の小さい松明を態(わざ)と重そうによろけながら担ぎ廻った。町全体が薄く煙り、気持のいい温もりが感ぜられる。星の多い、澄み渡った秋空の下で、こう云う火祭りを見る心持は説き別だった。一筋の低い軒並みの裏は直ぐ深い渓流になっていて、そして他方は又高い山になっていると云うような所では幾ら賑わっていると云っても、その賑やかさの中には山の夜の静けさが浸透(しみとお)っていた。これが都会のあの騒がしい祭りより知らぬ者には大変よかった。そして人々も一体に真面目だった。「ちょうさ、ようさ」。この掛け声のほかは大声を出す者もなく、酒に酔いむしれた者も見かけられなかった。しかもそれは総て男だけの祭りである。 或る所で裸体(はだか)の男が軒下の小さな急流に坐って、眼を閉じ、手を合わせ、長いこと何か口の中で唱えていた。清い冷たそうな水が乳の辺りを波打ちながら流れていた。大きな定紋(じょうもん)のついた変に暗い提灯を持った女の児と無地の麻帷子(あさかたびら)を展(ひろ)げて持った女とが軒下に立ってその男のあがるのを待っていた。漸く唱え言を終ると男は立って、流れの端に揃えてあった下駄を穿いた。帷子を持った女が濡れた体に黙ってそれを着せ掛けた。男は提灯を持たず、下駄を曳(ひ)きずって直ぐ暗い土間の中へ入って行った。これはこれから山の神輿(みこし)を担ぎに出る男であるという。こう云う連中が間もなく石段下の広場に大勢集まった。其所には日本の太い竹に高く注連縄(しめなわ)が張り渡してあって、その注連縄を松明の火で焼き切ってからでなければ誰もその石段を登る事ができないとの事だ。しかし縄は三間(さんげん)より、もっと高い所にあって、松明を立ててもその火は却々(なかなか)そこまでは達(とど)きそうにない。沢山の松明がその下に集められる。その辺一帯、火事のように明るくなり、早くそれの焼き切れるのを望み、仰向いている群集の顔を赤く描き出す。やがて、漸く火が移り、縄が火の粉を散らしながら二つに分かれ落ちると、真っ先に抜刀(ぬきみ)を振り翳(かざ)した男が非常な勢いで石段を馳登(かけのぼ)って行った。直ぐ群集は喚声をあげながら、それに続いた。しかし上の門にもう一つ、それは低く丁度人の丈よりちょっと高いくらいに第二の注連縄が張ってある。先に立った抜刀の男はそれを振り翳したまま馳け抜ける。注連縄は自然に断(き)られる。そして群集は坂路(さかみち)を奥の院までそのまま馳け登るのである。「どうだい、もう帰ろうか」と謙作は末松を顧みて云った。「お旅でやるお神楽(かぐら)を見て行こうよ」。神楽と云うのは四五人で担ぐような大きな松明を幾つか、神楽の囃しに合わせて、神輿の囲(まわ)りを担ぎ廻るのである。 「大概もう分ったじやないか。早く帰って寝ておかないと明日の音楽界で参るぜ」。「何時だ---二時半か」。時計を見ながら末松が云った。「これで京都へ帰ると丁度夜が明けるかも知れませんよ」と水谷が云った。「それじゃあ、帰るか」。末松は未練らしく云った。「神輿を下ろす時が却々勇ましいそうだ。坂だから段々早くなるので、太い縄をつけといて、それを女が大勢で逆に引っ張るのだそうだ。この祭りで女の出るのはそれだけなんだ」。「とにかく帰りましょう。夜が明けてから三里、陽に照らされて歩くのは想いですよ」と水谷が云った。末松も納得した。焚火の町では、来る時、岩間の火のように見えていたのが今は盛んに燃えていた。町を出ると急に山らしい冷気が感ぜられた。四人は時々振り返って、。明るい山の峡(はざま)を見た。道は往きより近く思われ、下りで楽でもあつたが、やはり皆は段々疲れて、無口になった。「眠くて敵(かな)わん」。一番先に末松がこんな事を云った。「僕が腕を組んでいって上げるから、眠りながら行き給え」。そう云って水谷は末松と腕を組んで歩いた。 京都へ入る頃は実際水谷が云ったように叡山の後ろから白ら白ら(しらじら)と明けて来た。出町の終点で四人は暫く疲れた体を休めた。間もなく一番の電車が来て、それに乗り、謙作だけは丸太町で皆と別れ、北野行に乗換え、そして秋らしい柔らかい陽ざしの中を漸く衣笠村の家に帰って来た。「旦那はんのお帰りどっせ」。何かあわただしい仙の声がし、直ぐ台所口から出て来て、「お産がござりましたえ」と仙はにこにこして云った。謙作の胸は理(わけ)もなく轟(とどろ)いた。そして急いで玄関を上がると、前から産室に決めて置いた座敷へ入って行った。リゾールか何か、薬の匂いがして、其所には蒼白い顔をした直子が解いた髪の毛を枕から垂らし、仰向けに---よく眠入つていた。赤児は其所から少し離した小さい蒲団の中に寝ていたが、謙作はそれを見たいと思うよりも直子の方が何となく気遣われた。若い看護婦が黙って叮嚀なお辞儀をした。小声で、「どうでした?」と彼は訊いた。「お軽いお産でございました」。「そりゃあ、よかった。そりやあ、よかった」。「ぼんさんでごさりまっせ」と敷居の所に坐って居た仙が云った。「そうか」。彼は安心した。そして、枕元に立ててある風炉前(ふろさき)屏風(びょうぶ)の上からちょっと赤児を覗いて見たが、頭からガーゼを被せてあって顏は見られなかった。「何時でした?」。「一時二十分でございました」。「夜前早うに奥さんがお迎いをだしてくれ、おいやして、直ぐ車を出しましたんどっせ。お会いしまへなんだっしゃろな」。「うん、会わない---とにかくあっちへ行こう。起きるといかん」。謙作は先に立って茶の間へ行った。 前日、謙作が家を出る時、入れ違いに夕刊配達の入って来たのを覚えているが、それが中まで入って来ずに、玄関に坐っていた直子を目がけ、新聞をほうって行った。新聞は靴脱ぎの上に落ちた。それを何気なく手を延ばして取ろうと屈んだ時に直子は腹に変な痛みを感じたと云う。そして間もなく又痛みが来て、自分でも気づき、直ぐ仙に産婆、医者、それからS氏の所へも電話をかけさせ、自分はその間に丁度入ろうと思っていた風呂に入り、身仕舞をすっかり済まして待っていたと云う。---それを仙が話した。「そりやあ、偉らかった」。謙作は直子がそう云う時、案外しっかり、よくやった事を愉快に感じた。「Sさんの奥さんが女中はんを連れて来てくれはりました。今、お帰りやしとところどっせ」。「そうか。---赤ん坊の方も丈夫だね」。「へえ、そら立派なややはんどす」。「ちょつと看護婦さんを呼んでくれ」。彼は赤児の事をもっと精しく聞きたかった。看護婦は来て、白い糊の利いた袴をぶわりと広く、縁に坐った。「どうぞ入って下さい。---大分早かなかったんですか?」。「いいえ、---でも七百五十目ですから、普通よりは幾らか少ないかも知れませんが、早産と云う程ではないと思います」。「ふむ、そう。---まあ二人共、心配ありませんね」。「そりゃあ---」。「どうも、ありがとう」。謙作はそう云って、何気なく頭を下げたが、心では看護婦よりも、もっと何かに礼を云いたい気持だった。看護婦は産室の方へ還(かえ)って行った。 着物を着更え、湯殿へ顔を洗いに行こうとした時に、看護婦が、「奥様がお眼覚めでございます」と云いに来た。直子は仰向けのまま上眼使いをして、縁から入って来る彼を待っていた。その疲れたような血の気のない顔を謙作は大変美しく思った。彼は枕元に坐ったが、云う言葉が見出せず、「どうだい」と無造作に云った。直子は静かに只微笑した。そして静脈の透いた蒼白い手を大儀そうに出し、指を開いて彼の手を求めた。彼はそれを握り締めてやった。「苦しかったか?」。直子は上眼で彼の眼を凝っと見詰めたまま、微(かす)かに首を振った。「そう。それはよかった」。そう云う直子が謙作には堪らなくいじらしかった。彼は頭をなぜてやりたい衝動を感じた。そして握った手を解こうとすると、直子は尚それを固く握り締めて離させなかった。彼は坐り直し、畳に突いていた方の手で頭をなぜてやった。 「どんな児?---いい児?」。直子は疲れから低い声で云った。「まだよく見ない」。「眠っているの?」。「うむ。---あなたもまだ見ないのか?」。直子は点頭(うなず)いた。「御覧になりますか?」と傍(わき)から看護婦が云った。そして返事を待たず、屏風を除(の)け、被せたガーゼを取ると、割りに手荒く(と謙作には感ぜられた)蒲団を引き寄せ、直子の床にそれを附けた。真っ赤な変に毛深い顏で、頭の先がいやに尖(とが)り、それに長い真黒な毛がピッタリとかぶさっていた。眠った眼の丸く晴れ上がっているのも気味悪かった。謙作はこんな赤児を初めて見るように思い、ちょっと失望した。「男だからいいようなものの、少し変な顔だな」と彼は笑った。「どんな赤さんでも初めは皆そうでございますわ」。看護婦は謙作の言葉を非難するように云った。 赤児は指でも触れたら、一緒に皮がむけて来そうな唇を一種の鋭敏さをもって動かしていたが、それを開けると、急に顔中を皺にして泣き出した。直子は首だけ其方(そっち)へ向け、手を差し延べて、産着(うぶぎ)のふくれ上った肩を指で押し下げるようにして見ていた。その眼が如何にも穏やかで、そしてそれは如何にも、もう母親だった。「これが本統に変でなくなるかね」。謙作には父らしいと云えるような感情は殆ど湧いて来なかった。「今お顔が腫れていますが、それが干(ひ)けるとろもむそれはお可愛くなりますよ。立派なお顔立ちでございますわ」。そう看護婦が云った。「そうですか、そんならまあ安心だが、このまま大きくなられた日には大変だからね」。謙作は幾らか快活な気分になって、「奈良の博物館に座頭か何かの面でこう云うのがあるよ」。こんな串戯(じょうだん)を云ったが、直子も看護婦も笑わなかった。そして、茶の間で膳拵えをしていた仙の「旦那さんの、まあ何をおいやす」と云って笑う声がした。「いろんなとこ、電報まだだろう?」。「ええ」。「そんなら直ぐ打っておこう」。そう云って、謙作は直ぐ二階の書斎へあがって行った。 |
| 十八 |
| 総て順調に行った。謙作は時々眠っている赤児を覗きに行った。しかし、それは一種の好奇心のようなものからで、これが自身の肉親の子であると云う事は、どうも、しっくり来なかった。彼は何か危なっかしい感じで、抱いて見たいとも思わなかった。直子の方はもう本統に母親になり切っていた。乳の時間が来て、寝ながらそれをやっている時の様子などには如何にも落着きがあった。そして赤児も安心し切って鼻を埋めるくらいに吸いついているところなどを見ると、謙作はそれを大変美しい物のようにも思うし、又どうかしてそれが白い乳房にえたいの知れぬものが喰い入っているような感じで気味悪く感ずる事もあつた。それはこれまでこう云う生れたての赤児を見る機会が彼には殆どなかったからでもある。 敦賀の方からは誰も出て来なかった。母はもう少し後でなければ出られず、直ぐ飛んで来る筈の伯母は持病の神経痛で動けずにいると云う便りがあった。しかし直子は別にそれを淋しがらなかった。お七夜と云う祝い日が近づき、早く名を命(つ)けねばならなかったが、却々(なかなか)気に入った名が浮ばず、結局直子の直と謙作の謙とを取って、直謙(なおのり)としたが、赤児には何か厳(いか)めし過ぎて、気に入らなかった。「尤もいつまで赤ん坊でいるわけでもないから」と彼はそれに決めた。一週間は至極無事に過ぎ、そして八日目の夜になって、もう皆床に就いてから赤児が泣き出し、どうしても、それを止めなかった。乳首を含ませるとちょっとの間泣き止むが、直ぐ又泣いた。臍を調べて見たが、どうもなく、もし虫にでも刺されているのではないかと、着物を総て取り更えてみたが、それでも泣き止まなかった。原因が分からないだけに変に不安を感じた。熱を計ると、少し高かった。「どうだろう、Kさんに来て貰おうか」。「そうね。その方がいいかも知れませんわ」。直子も不安そうに云った。しかし間もなく、赤児は泣き疲れたように段々声を落して行って、仕舞いに泣き止んだ。そして安らかな呼吸(いき)をしながらよく眠入った。「どうしたんだろう?」。謙作はほっとするような気持で直子を見た。直子は、「よかったわ」と云った。「もう夜啼きちゆう事をされるややはんがござりまっせ」と仙が云った。そして仙は天井に「鬼の念仏」を張るといいといつて、それを勧めた。赤児は続いてよく眠っていた。皆はできるだけ静かに自分達の寝床へ還(かえ)った。 謙作は独り二階の書斎に寝ながら、やはり却々眠れなかった。そして直子もきつと眠れずにいるだろうと思った。産褥(さんじょく)に居る直子は昼間も時々眠っていたから尚眠れないに違いなかった。。しかし赤児を覚ます恐れから彼は降りて行く事もできなかった。彼は気を更(か)える為に気楽な本を読んでいた。暫くすると、階下(した)の茶の間でボンボン時計の十二時を打つのが聴こえた。そして赤児は又泣き出した。直子と看護婦と何か云ってる声がして来た。彼は二階を降りて行った。「時計、どうかできなくって? あれで眼が覚めたのよ」。直子は謙作を見上げ、腹立たしそうに云った。「止めておこう」。「ええ、そうして頂戴。---あの時計、これから使わなくていいわ」と直子は云った。謙作は茶の間へ行って時計を止めて来た。直子は切(しき)りと乳を呑まそうとしたが、赤児は却々その乳首を口に含もうとはしなかった。「とにかく、近所の医者にでもちょっと見せておこうじゃないか。Kさんと云っても今からでは遠くて少し気の毒だし、それにまた直ぐ泣き止むだろうと思うし」。「ええ---」。「そんなら早速、俺が自分で行って来よう」。 謙作は台所口から直ぐ戸外へ出た。戸外は風の少しもない、曇った真っ暗な晩だった。彼は歩いたり、馳(か)けたりしながら行った。近所の医者としては、彼は、五町ほどある御前通りに仕舞屋(しもたや)のような格子の填(は)まった家で、只「医」としたを出してある家きり知らなかったので、そこへ行った。二三度叩くと戸の内から、「何御用」と云う女の声がした。「ちょっと、先生に来て頂きたいのです」。「どちらはんどす」。「この先の衣笠園の中です。赤ん坊(あかんぼ)の様子が少し変なので診て頂きたいのです」。「ちょっと、待っておくりやす」。そう云ってそのまま女は奥へ入って行った。そして直ぐ又もどって来て、「衣笠園のどなたはんどす?」と云った。「時任です」。「へえ?」。「と、き、と、お」。「ときとお」。「そうです」。そして女は「ときとお」そう独り言をしながら奥へ入って行ったきり、何時まで待っても出て来なかった。謙作は苛々して来た。「どうか早くお願いします」。彼は大きい声で云ったが、返事がなかった。暫くして女は漸く戸を開けた。「お待たせ致しました」。女は寝間着姿で、瘠せた脊(せい)の高い見すぼらしい女だった。医者は中で着物を更えていた。これも見るから見すぼらしい小男で、年は謙作よりも少し上らしく、薄い天神髭(ひげ)を物欲しそうに生やしていた。医者は帯をしめながら、「どんな御様子ですか?」と云った。「只無闇と泣き続けるだけで、原因が分からないのです」。医者は今になって、却って忙しそうに出て来て、「お待たせしました」と云った。「こんなに晩(おそ)くお願いして---」。「いや。それじやあ直ぐお供しましょう」。こんな風にしきりと調子よく仕ようとした。少し酒に酔っているらしかった。謙作にはこの医者が如何にも頼りなく思われた。気の毒でもやはりK氏を頼めばよかつたと思った。途々(みちみち)医者は生後幾日目かとか、母親に脚気(かっけ)の気はないかとか、そう云う事を少し訊いた後で、何時から京都へ来たか、そして何の為に、というような要らざる事まで訊き出した。謙作はなるべくそう云う話を避ける為に医者よりも一足先に歩いた。小さい医者はそれに遅れまいと息を切りながら、ついて来た。 医者の診断は不得要領だった。医者は襁褓(むつき)に着いている粘膜から、やはり一種の消化不良だろうと云った。そして泣いても、なるべく乳を飲まさぬようにと云うような注意をして、間もなく帰って行った。赤児は夜中(よじゆう)泣きとおした。---少なくとも皆にはそう感ぜられるほどによく泣いた。泣き疲れて、時々は眠りもしたが、皆も一緒にうとうととすると、直ぐ又泣き声に覚まされた。夜の明けるのが待たれた。漸く戸外が白み始めると、謙作は直ぐ家を出たが、いつも電話を借りる家はまだ寝静まっていた。彼は馳けて北野まで行き、其所の自動電話で、K医師の自宅にかけ、病院に出る前に来て貰いたいと云う事を頼んだ。一時間ほどしてK医師は来た。半白の房々とした口髭を持った大柄な人で、前夜の見すぼらしい医者とは見るから何となく頼りになつた。医者は挨拶もそこそこに赤児の今までの経過に就いて色々訊ねた。赤児は丁度乳を飲んで泣き止んでいる時だったが、医者がちょつと手を額に当てると直ぐ泣き出した。医者は手を離し、泣いている赤児を凝っと暫く見ていた。その顔を又直子は寝たまま上眼使いに凝っと見詰めていた。「とにかく、身体を一つ拝見しましょう」。医者が云った。看護婦は障子を閉めてから赤児を受取り、小さい蒲団に寝せて、何枚も重ねてある着物の前を開いた。「それでよろしい」。医者は近寄って、胸から腹、咽(のど)、それから足まで叮嚀に調べ、二つ三つ打診をしてから、自身で臍の緒の繃帯(ほうたい)を解き、大きな年寄りらしい手で下腹を押して見た。赤児は火のつくように泣いた。「ちょっと背中の方を出してください」。看護婦は袖の肩から赤児のいやに力を入れて屈(ま)ている小さい手を一つずつ出して、裸の赤児を医者の方に背中を向け、横にした。赤児は両手を担(かつ)ぎ、両足を縮めて、力一ぱいに無闇と泣いた。腹を波立たせながら泣く、その声が謙作には胸にこたえた。直子は怒ったような妙に可愛い眼をして黙ってそれらを見ていた。 医者は叮嚀に背中を調べた。そして尻からちょっとばかり上に拇指(おやゆび)の腹ほどの赤い所を見つけると、尚注意深く其所を見ていたが、やがてこごんだまま、顔だけ謙作の方へ向け、「これです」と云った。「何ですか」。「丹毒(たんどく)です」。「------」。直子は眼を閉じ、そして急に両手で顔を被うと寝返りして彼方を向いて了った。「しかしまだ広まっていませんから、早く手当をすれば御心配なく済みましょう」。こんなに医者は云った。看護婦は黙って赤児に着物を着せていた。「急いで病院から薬を取寄せましょう」。医者は縁で手を洗いながら云った。「近くに電話を借りられる所がありますか?」。「此所の大家さんにあります。私で分る事ならかけましょうか?」。「分らん事もありませんが、自分でかけましょう」。謙作は直ぐ医者を大家へ案内した。医者は注射液、イヒチオール、油紙(ゆし)、アルコール、その他(ほか)、考え考え必要な品々を云った。「昇こう(しようこう)はお宅にありますか?」。医者は振り返って云った。「多分ありますまい」。「それじゃあ、昇こうと、---誰でもいいから自転車で大急ぎで持って来てくれ。---衣笠園。---わかったね」。二人は帰ると、二階で薬の来るのを待った。階下では絶えず赤児の泣き声がしていた。謙作は明瞭(はっきり)した事を訊くのが恐ろしかった。彼はそう云う不安と戦いながら、それでもやはり訊かずにはいられなかった。「どうでしょうか」。「せめて生後一年経っておられると余程易(らく)なのですが、---しかし早く気が附いたから、どうか食い止められるかもしれません」。 医者は尚、丹毒は大人の病気としてもかなり困難な病気で、まして幼児では病毒と戦って仕舞いまで肉体がそれに堪えられるか否かで分れるのだから、とにかく栄養が充分でないと不可(いけない)と云う事、それには母乳に止まられる事が何より恐ろしく、できるなら、母親だけ赤児の泣き声の聴こえぬ所へ離して置きたいものだと云った。「お母さんの方も産後そう動かす事は面白くないのですが、あの泣き声を始終側で聴いておられたら、乳は直ぐ止まりますよ」。そう医者は云った。「勿論泣き声が聴こえなくとも、心配されるでしょうが、其所は貴方がよほど上手にやられないといけませんね。できるだけ気を楽に持って、赤さんの事は心配要らん、と云う風な安心を与えん事には乳はきっと止まりますからな」。「ええ」。そう答えたが、謙作にはそれが不可能な事のように思われた。医者が、どうにか食い止められるかも知れないと云っている、それも信じられなかった。医者自身そう思っていないとしか考えられなかった。「幼児の丹毒と云えば普通まあ絶望的なものになっているんじゃないですか」。謙作は弱々しい気持になってこんな事を云った。「さあ、そうも決まりますまい。が、とにかく却々(なかなか)困難な病気です。蜂窩織炎(ほうかしきえん)、それから膿毒症(のうどくしよう)とまで進まれたら、これはどうも致し方ありますまいな。しかしそうせん内にできるだけ一つ手を尽くして見ましょう」。謙作は黙ってちょっと頭を下げた。「今、持って来る注射液が毒の進みそうな先へ先へ射(さ)して行って、毒の進行を食い止める薬ですが、それがうまく行けば、大した事にならずに済むかも知れません」。「ほとんど泣きづめに泣いていますが、やはり痛むんですか」。「それは痛むのです」。「痛みを止めるわけには行かないのですか」。「ちょっと難しいでしょう」。間もなく病院の使いが来た。医者は縁に片膝立(かたひざだて)をし、注射器を消毒しながら、看護婦に、「この昇こうを解いて、金盥(かなだらい)に入れて置いて下さい。そして貴女もあとで手を消毒せんといけませんよ」と云った。 注射は直ぐ済んだ。その上にイヒチオールを濃いままに周囲から内へ向けて丹念に塗り着けた。医者はその外側から内へ内へと塗って行くやり方を看護婦に説明していた。赤児は絶えず泣き続けた。「今御主人にも申し上げましたが、赤さんの栄養が充分でないと結局病毒に勝てん事になりますからな」。医者は金盥の昇こう水で手を洗いながら直子の方を向いて云った。「貴女はできるだけ気を楽に持ってお乳の止まらんようお心掛けなさるんですな。これが大事な事です。しかし赤さんの方も早く手当ができましたから、---これからも多少進むかも知れませんが、大した事にはならんと思っております、---お解りですな」。直子は子供のように只点頭(うなず)いていた。「それでね」。謙作が云った。「あなたの床は茶の間の方へ移すからね。お乳の時だけ此方へ来て飲ますのだ」。「ええ」。直子は小さな声で微かに答えたが、そのうち急に泣き出した。間もなく医者は帰って行った。「あなたは余ほど気をしっかり持っていないと駄目だよ。あなたが幾ら心配したところで、直接病気の為には何にもできないんだからね。それより乳がよく出るよう、できるだけその方には呑気(のんき)になる心掛けをしていなければいけないよ」。直子は泣き腫(は)らした眼で、そんな事を云う謙作の顔を睨むように見ていたが、「随分無理な御註文ね」と云った。「幾ら無理でも、あなたがその気になっていてくれねば困る事は分っているね」。謙作も不意に亢奮しながら、早口に云った。 直子は黙って眼を伏せて了った。謙作は前夜一睡もしなかったところから亢奮し易かった。それに、こう云う降って湧いた不幸が彼には変に腹立たしかった。「子供が病気になったのを呑気にしていろと云うのが、無理な註文くらい初めから分った事だ。それを無理でもそうしなければ、乳が止まるからそう云ってるんだ」。「どうかそう云わないで頂戴。私にもよく分っているの。---実は実家(さと)の近くで、丹毒で亡くなった赤ちゃんがあるのよ。それを知っているので、何だか心配で仕方がないの---だけど、本統に私、できるだけ病気の事、忘れるように心掛けますわ。貴方が心配していらっしゃるところに、そんな事を云って悪かったわ」。「うむ。そんなら、それでいいけど、---その赤ちゃんの病気は何時頃の話だい」。「もう四五年前」。「そう。それじゃあ、今日の注射液のできてない頃だな。その時分からはそう云う方もきっと進んでいるだろう。Kさんも早く気が附いたから、大丈夫だと云っているのだから、あなたは本統にその気でいる方がいいよ」。「ええ」。「それに林さん(看護婦)がいい人で大変幸いだ」。「本統に、私も安心してお任せして置けるわ」。 玄関に誰か来たらしいので、謙作は直ぐ自分で起って行った。赤児が眠っていた時で玄関には看護婦が先に出ていた。来たのは前夜頼んだ近所の医者だった。看護婦は前夜その医者が来た時から、変に軽蔑(けいべつ)を示していたが、今日はそれより、もっと反感を現わしてつけつけ何か云っていた。消化不良ではなく丹毒と云う事、栄養が大事だから乳はなるべく飲ますようと云う事だった、など、先にこたえる事を立て続けに云った。「ははあ、いや、それはどうも、おいたわしいですな---」。こんな事を云いながら、小さい医者は引っ込みのつかぬ形で弱っていた。「実はついこの先の病家まで来たものですから、どんな御様子かと思って---」。医者は具合悪そうに謙作の方を向いて云い訳をした。謙作は医者が気の毒でもあり、それにどう云う場合、簡単な事で又頼まぬとも限らぬ気がしたので、「折角ですから、貴方にも、もう一度診て置いて頂きましょうか」と云った。「いや。K先生のお診断でしたら、決して間違いはございません。では、まあお大事に---」。こう云うと小さい医者は逃げるように帰って行った。 |
| 十九 |
| 赤児は殆どひっ切りなしに泣き続けた。眉間に太い皺を作って、小さい唇を震わしながら、「ふぎゃあふぎやあ」と云うように泣く。その声が謙作や直子の胸を刺した。そうして絶えず聴いていると、偶々(たまたま)泣き止んだ時でも、耳の底からその声が湧いて来た。往来へ出る。其所はもう自家から泣き声の聴こえぬ遠さなのに、不意にそれが聴こえて来たりした。「オイ、どうしたらいいか---どうすればいいのか」。余り烈しく泣かれる時に謙作は思わず、こんな独り言を云う。こう云う場合の癖だった。が、実際どうしようもなかった。赤児の声は段々に社がれて来た。到頭仕舞いに顏ばかり泣いていて、声は出なくなった。これは赤児には苦痛の表明の二つを一つにされたようなもので、不憫な事だった。が、まわりの者には絶えざる刺激の泣き声が聴こえなくなっただけでも幾らか助かった。直子の乳は幸いに止まらなかった。赤児もそれ程苦しみながら、乳だけは思いの外、よく飲んだ。まわりの者はそれに希望を繋いでいたが、十日経ち、二週間経つ内に、やはり蜂窩織炎(ほうかしきえん)を起こして了った。国から出て来た直子の母が台所口の柳を鬼門の柳だと云って、切(しき)りに植え替えたがった。謙作は母と一緒にそう云う御幣を担ぎたくなかったが、度々云われ、それを植え替えさした。 彼がそれより何となく気になっていたのは、赤児の誕生の日の夜、前からの約束で末松らと三条の青年会館に演奏会を聴きに行った。其所で彼はシューバートのエールケーニヒを聴いた。その事だった。彼は前から曲目をもっとよく見ていたら、この演奏会へ行かなかったろう。この嵐の夜に子供を死神にとられる曲は今の場合、聴きたくなかった。しかし彼は何気なく行って、誕生の日に聴くには如何にも縁起の悪い曲を聴くものだと思った。彼はちょっと厭な気持になった。若いコントラルトの唄で、その晩の呼び物だったが、謙作には最初から知らず知らずの悪意、反感が働いていた。彼にはその曲を少しも面白いとは感ぜられなかった。総て表現が露骨過ぎ、如何にも安っぽい感じで来た。それは只、芝居がかりに刺激して来るだけで、これだけの感じなら、文学のままで沢山だと思った。シューバートのこの音楽は文学を文学のまま、より露骨に、より刺激的に強調しただけで、それは音楽の与えられた本統の使命には達していない曲だと彼は考えた。ゲーテの詩までが彼には気に入らなかった。それは本統に死を扱った深味のある作ではなく、芸術上の一つの思いつきだという気がした。比較的若い時の作に違いないと思った。この点メーテルリンクの「タンタジイルの死」の方が彼には好意が持てた。寺町を帰って来る時、水谷が亢奮しながら、「エールケーニヒは素敵でしたね」と云った。「あれはやはりいいね」。末松が答えた。末松は自身では何もやらなかったが、好きで、音楽の事は精しかった。末松は黙っている謙作の方を向いて、「あの曲はシューバートの中でも最もいいものだと思うよ」と云った。謙作は返事をしなかった。彼は音楽の事では余り明瞭(はっきり)した事を云いたくなかった。云うだけの自信がなかった。そして、彼は二重廻しのポケットの中で丸めていたプログラムを何気なく道へ落した。厄落し、そんな気持ちで---。 彼はこんな事を気にしたくなかった。気にしても仕方なく、気にする程の事ではないと思った。勿論それは直子にも話さなかった。そして自分でも忘れていたが、今、赤児にこんな病気になられると、誕生日にエールケーニヒを聴いた事がしん*をなしたというような気もされるのだ。丹毒は伝染する恐れがあり、皆も割りに注意深く手先の消毒をしていた。或る麗(うら)らかな朝だった。謙作と母とが茶の間で食事をしている時に、直子が、廻り縁を静かに寝間着の裾を曳きながら赤児の病室の方へ行った。乳を飲ます為である。「あら! ベルや。ベル! いけません」。「どうしたんだ」。謙作は茶の間から声をかけた。「ちょっと来て頂戴。べるが昇こうを飲みそうにするの」。謙作は茶の間の前から下駄を穿いて庭へ出た。ベルというかってこの家に飼われていた子犬が、喜んで、飛び回っていた。「これを飲みそうにするのよ」。更(か)える為に踏み石の上へ下ろしてあった、洗面器の昇こうを指して直子が云った。「そりゃあ、飲みやしないよ。只好奇心で匂いを嗅いでたんだろう」。「そうでしょうか? 今本統に飲みそうにしてたのよ。こんな水を飲んだら、それこそ、直ぐ死んで了いまいわ」と直子が云った。引越しの時、手伝いに来ていた爺やが貰って来てくれた犬で、しかし直子の妊娠が分ると、同じ年の動物は飼わぬものだというような事で、小屋ごと、一軒措いた隣りの家へやって了った。しかし犬はそれからも始終遊びに来て、今は何方(どっち)の犬ともつかず、行ったり来たりしていた。 看護婦の林が出て来て、黙ってその昇こうの洗面器を取上げると怒ったような顔をして、どんどん台所の方へ下げて行った。謙作達はこの一っこくなようなところのある、勝気な看護婦に信頼していた。林は赤児の事では緊張し続けた。よく健康が続くと思うくらいだった。謙作は寧ろ林の健康の為に、もう一人看護婦を頼んだが、林は却ってそれを喜ばなかった。赤児に対する、その看護婦のやり方が気に入らなかった。そして自分は自分で一人の時と全く同じに働き、その人に任せてゆっくり休養すると云う事はしなかった。或る時、その看護婦が風邪で帰ると、林は「もし私の為でしたら、どうかもうお頼みにならないで頂きます。---だけど私一人で御不自由だと思召すんでしたら別ですけど」。こんなに云った。 謙作はもし林に倒られたら、どんな代りが来るとしても、赤児の為には大打撃だからと云ったが、林は大丈夫倒れる事はないからと云っていた。今の場合、赤児の為に直子に要求するところは、母であって貰うよりは乳牛になり切っていて貰う事だった。で、乳の時以外は全く赤児に近づけない事にしていたが、しかし赤児としては、生れたてのまだ何も分からない赤児ながら、母乳以上の母愛をも要求しないとは云えなかった。そう謙作には思えた。そしてこの感情---この母愛に近い感情は他の看護婦では却々(なかなか)求められそうになかった。---とにかく、林のやり方が看護婦としての義務を遥かに越えていた事は謙作達には嬉しい事だった。赤児の病気は益々望み少なくなって行った。今は背中全体が赤く腫れ上がり、ぶくぶくと中で膿血(うみち)の波打つのが分かった。K医師は同じ病院の外科医と一緒に来てそれを切開する事にした。外科医は切開の結果は請合えないと云った。それは一か八(ばち)かの手術だった。勿論そのままにして置いては駄目なのだが、幸い今、手術に堪えられたとしても、結局十中八九、やはり駄目らしかった。其所までは医者も云わなかったが、それが本統だろうと謙作は思った。それは一か八よりも、結局一か一かのものに違いなかった。 謙作はK医師が食塩注射の支度をする手伝いなどをしていた。しかし彼は自身手術に立会う気にはなれなかった。恐ろしかった。「かまいませんか?」。「ええ、かまいません」。みこうK医師に云われ、彼は庭へ出て了った。手術着を着た若い外科医が縁側でシャボンとブラッシで根気よく手を洗っていた。間もなく皆病室へ入って行った。謙作は直子のいる部屋の方へ行った。「お立合いにならないの?」。直子は非難するような眼附きをして云った。「いやだ」。謙作は顔をしかめ、首を振った。「可哀想だわ、そりゃあ、可哀想ですわ」。「Kさんがいいって云ったんだ」。「そう仰有(おっしゃ)ったかも知れないが、誰も血筋が行っていなくちゃ、可哀想よ。じゃあ、お母さんに行って頂きましょうか」。直子は傍に坐っていた母を顧みた。「はい」。そう云って母は直ぐ出て行った。謙作は又庭を病室の方へ歩いて行った。障子を〆切った中からは時々医者達の低い話声と、ちょっとした物音がするだけで、勿論、声の全く潰れて了った赤児の声は聴こえて来なかった。謙作は急に不安に襲われた。もう死んで了ったんだ。そう思わないではいられなかった。彼はじっとしていられない心持で庭を往ったり来たりした。ベルが、頻りにその足元に戯(じや)れついた。 少時(しばらく)して、障子が開いて、林が顔を出した。亢奮し切った可恐(こわ)い顔をしていた。謙作を見ると、「どうぞ、直ぐお乳を上げて頂きます」。そう云って直ぐ又障子を〆て了った。「助かった」。謙作は思った。彼は急いで直子の部屋に行き、「オイ。直ぐお乳---」と云った。「よかったの?」。直子は立ち上がりながら云った。「うむ」。直子は急いで縁を小走りに行った。林が血の付いた綿やガーゼを山に盛った洗面器を隠すように持って風呂場へ急ぐのが見えた。謙作が行った時には病室は綺麗に片付いていた。K医師が赤児に酸素吸入をかけていた。直子は側に坐って泣き出しそうな顔をしてそれを見ていた。「どうも却々えらい膿(うみ)でした」。K医師は顔を挙げずに云った。「------」。「食塩注射と酸素で、どうか取り止めましたが、しかしよく堪えて下さいました」。謙作はK医師に代って、酸素をかけてやった。赤児は疲れから、よく眠入っていたが、そのり顔は眉間に八の字を作り、頬はすっかりこけ、頭だけがいやに大きく、まるで年寄りの顔だった。赤児は眼を閉じたまま急に顔中を皺にして、口を開(あ)く。苦痛を訴えるには違いないが、もう全く声がなく、泣くとも云えない泣き方だった。それを見ると、これが助かるとはとても思えなかった。しかし直子が乳首を持って行くと、これは又どうした事か、死んだようになっていた赤ん坊が急に首を動かし、直ぐそれへ吸いつくのだ。それは生きようとする意志、そういう力をまざまざと現わしていた。それも余り長くは続かなかった。赤児は充分飲む前に又眠りに落ちて行った。 この日からはK医師の代りに毎日外科医が来るようになった。毎日取り更えるガーゼが血と膿でどろどろになっていた。傷の場所は大きさにして大人の開いた手のひらぐらいのものだが、赤児にはそれで背中全体の大きさだった。仕舞いには背骨が白く並んで見えるようになった。もうどんな事をしても助かるとは思えなかった。生きている方が不思議だった。衰え切って呼吸をしなくなる事がある。直ぐカンフル注射をする。酸素吸入をかける。こういう事が度々あった。酸素吸入は毎日一本ずつ使っていたが、用意して置いた方が何時かすっかりなくなっていて、夜中車夫を病院まで取りにやる、その間の不安が堪らなかった。何しろ、夜と云うものがよくなかった。夜の明けるのが切りに待たれる。やがて戸外が白み、雀の声がして来ると皆はほっとするのだ。縁に静かな陽ざしを見ると漸く不安な一晩の過ぎた事を染々(しみじみ)と感ずる。病室には酸素とカンフルの匂いが始終漂っていた。その匂いが鼻について了った。別に希望が持てるわけでもなかったが、その日その日の医者の診察が待たれた。 「どうも不思議なくらいです」。若い外科医は二階の書斎で紅茶を飲みながら云った。「実は昨日の御様子ではとても難しいと思ったので、病院の方へもし此方(こちら)からお知らせでもあったら、直ぐ電話で知らすように云い置いて帰ったのです。今日は直接こちらへ伺うつもりでしたからね」。こんな正直な事を云われても、謙作は今はそれに不快を感ずる事ができなかった。彼は今は、もう死ぬと決まったものなら、少しでも早く苦痛から逃れさせたいという気さえしていた。しかしこの考えは赤児が生きよう生きようとする意志を現わす時に僭越な済まない考えだとも思われた。しかし医者達はとても難しい事を明瞭に云ってい、彼自身見ても何所(どこ)に希望を繋いでいいか、分からない程ひどい様子を見ると、赤児の尚生きようとする意志が彼には堪らない気がした。「死ぬに決った病人でも、死に切るまでは死なさないようにしなければならないんですか。生きてる事が非常な苦痛になっている場合でも」。「仏蘭西(ふらんす)と独逸(ドイツ)で考えが違います。フランスでは権威ある医者が何人か立ち会って、家族の者もそれを希望した場合、薬でそのまま永久に眠らす事が許されているのです。ところがドイツではそれが許されてないんです。医者としては最後の一秒まで病気と戦わねばならぬと云う考えなんです」。「日本は何方(どっち)です」。「日本はまあドイツと同じ考えなんですが、考えと云うより医学が大体ドイツをとつてるからでしょうが、それはまあ何方(どちら)にも考え方の根拠はありますわな」。「医者の判断が例外なしに謝らないという事が確かなら、フランス流も賛成ですがね---」。「それは数ある中では何ともいえませんからな」。謙作と外科医とがこんな事を話し合った翌日、赤児は発病後一月で到頭死んで了った。赤児は苦しみに生まれて来たようなものだった。葬式、その他、簡単に運ばれた。総てはやはりS氏の世話になるより仕方なかった。謙作達は今後どれだけこの地に落ち着いているか分らなかったし、墓にして、仕舞いに無縁仏のようにするのも厭だったので、骨はそのまま、石本の菩提所になっている花園の霊雲院と云う寺に預かって貰う事にした。 赤児死で一番こたえたのは何と云っても直子だった。その上、産後肥立たぬ内に動いた事が障り、身体が却々回復しなかった。謙作はまだ一度も直子の実家へ行っていなかったし、神経痛で寝ている伯母の見舞いを兼ね、二人で敦賀へ行き、それから、山中、山代、粟津、片山津、あの辺の温泉廻りをして見てもいいと思った。しかし直子の健康がそれを許さなかった。それに、直子は心臓も少し悪くし、顔にむくみが来て、眼瞼(まぶた)が人相の変る程、腫れ上がっていた。医者はその方からも、温泉行はもっての外だと云った。直子は毎日病院通いに日を送っていた。 謙作は久しく離れている創作の仕事に還(かえ)り、それに没頭したい気持になったが、まだ何かしら重苦しい疲労が彼の心身を遠巻きにしているのが感ぜられ、そう没頭はできなかった。彼の感情は物、総てに変に白々しくなった。恰度(ちょうど)、脳に貧血を起こした人の眼にそう見えるように、それは白けてしか見えなかった。彼は二階の机に向い、ぼんやり煙草ばかりふかしていた。どうして総てがこう自分には白い歯を見せるのか、運命と云うものが、自分に対し、そう云うものだとならば、そのように自分も考えよう、勿論子を失う者は自分ばかりではない、その子が丹毒で永く苦しんで死ぬと云うのも自分の子にだけ与えられた不幸ではない、それは分っているが、只、自分は今までの暗い路をたどって来た自分から、新しいもっと明るい生活に転生しようと願い、その曙光(しょこう)を見たと思った出鼻に、初子(ういご)の誕生と云う、喜びであるべき事を逆にとつて、又、自分を苦しめて来る、其所に彼は何か見えざる悪意を感じないではいられなかった。僻(ひが)みだ、そう想い直して見ても、彼は尚そんな気持から脱(ぬ)けきれなかった。霊雲院は衣笠村からそう遠くなかったから、謙作はよく歩いてお参りをして来た。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)