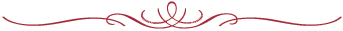
| 第3章の3(10から14)(後編3) |
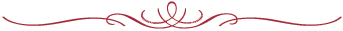
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3)年.8.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「暗夜行路第3章の3(10から14)(後編2)」を確認する。 2021年.8.10日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【暗夜行路後編第3章の3(10から14)】 |
| 十 |
| 謙作はいよいよ新しい寓居(すまい)に引き移る事にした。秋としてはいやに薄ら寒い風の吹く曇り日であったが、仙が後の荷も着いたからと、それを云いに来たので、彼は早速移る事にした。彼は自分の部屋の始末をしたり、菰包(こもづつ)みの藁縄(わらなわ)を解いたり、差し当たり要らないような道具を屋根裏の物入れにかつぎ上げたりすると、頭からは埃(ほこり)を被(か)ぶり、手や顔はざらざらに荒れ、それに寒さから来る頭痛や、埃から来る鼻のむずむずする事などで、すつかり気分を悪くした。婆ァやの仙はよく豆々しく働いていたが、何かにつけ話し掛けるので、彼は気分が悪いだけに少し苛々して来た。「これ、何どすえ?」。こんな風に話しかけて来る。「どれ?」。「お炬燵(こた)と違いますか?」。仙は両手で重そうに鉄の足暖炉(だんろ)を持っている。「足暖炉だ。何所かへしまっといてくれ」。「足暖炉。へえ。これお使いしまへんのか」。「使うかも知れないが、今要らないからしまっといていてくれ」。「------どうぞ私に貸しておくりやはんか。夜(さり)腰が冷えて、かなわんのどっせ」。いじけた賤(いや)しい笑いをしながら仙はちょっと頭を下げた。謙作は不快な顔をしながら、いやに図々しい「目刺し」だと考えた。しかしそう云われて、いけないとは云いにくかった。で、彼は仕方なく、「よろしい」と云うのだが、一度「目刺し」が寝床へ入れた物はもう使えないと思い、勿体ない気もするのだ。しかしわざわざ東京から重い物を持って来て、直ぐ「目刺し」に取上げられて了う、そう云う主人公を滑稽(こっけい)にも感じた。 前に来ていた荷で、大きい金火鉢(かなひばち)と入れこにして来た盥(たらい)の底が抜けかけていると云うので、「それは直しにやったか?」と彼は訊いてみた。「やりまへん」と仙は当然の事のように答えた。「何故やらない」。「桶屋(おけや)はんが廻って来やはらへんもの---」。「来なければ持って行ったらどうだ」。「阿呆らしい。あんな大きな盥、女御(おなご)が持って歩けますかいな。何所までや知らんけど------」。「頭へ載っけて太鼓を叩いて行くんだ」。「阿呆らしい」。謙作は苛々するのを我慢しようとすると尚苛々した。しかし間もなく銭湯へ行き、さっぱりした気持になって帰って来ると、いらいらするのも幾らか直っていた。仙との関係が本統に落ち着くまでは少し時がかかりそうに思えた。仙は書生を一人世話すると云う割りに気軽な心持で来たらしく、そして謙作も書生には違いなかったが、そして雇うた人、雇われた人と云う以上にできるだけ平等にしたい考えもあるのだが、或る気持の上のがさつきに対してはやはり我慢できない事があった。仙がそれを呑み込むまでは時々不快な事もありそうだと彼は考えた。「俺が机に向かっている時はどんな用があっても決して口をきいちゃあ、いかんよ」。こう云い渡した。「何でどす?」。仙は驚いたように細い眼を丸くして訊き返した。「何ででも、いけないと云ったらいけない」。「へえ」。そして仙はこれを割りによく守った。呆然(うっかり)何か云いながら入って来て、その時謙作が机に向っていると、「はあ! 物が云われんな」。こんなにいって急いで口を手で被(おお)い、引き退(さ)がって行った。 謙作は仙の過去に就いて殆ど何も知らなかった。只、もし生きていれば彼と同年の娘が一人あつたという事、それに死別れ、兄の世話になっていたが、最近それにも死なれ、その後、甥(おい)夫婦にかかって見たが、何となく厄介者扱いされるような気がされるので奉公に出る事にした、これぐらいの事を謙作は聴いていた。仙は台所で仕事をしながらよく唄を唄った。下手ではなかったが、少し酒でも飲むと大きい声をかるので、謙作は座敷から、「やかましい」と怒鳴る事もあった。しかし日が経つに従って段々よくなった。謙作の方も仙のする事がそれ程気にならなくなつたし、仙の方も年寄りにしてはよく謙作の気持に順応して行くよう、自身を努めていた。そして京都人だけに暮らし向きを一任して了うと、無駄なく、万事要領よくやって行った。酒も煙草も飲む方で、煙草は謙作の吸い余しをほぐして煙管(きせる)へつめていた。謙作は初め想ったより仙を少しがつよく想うようになつた。 お栄からは無事に着いたという簡単な便りだけで精しい事は何も云って来なかった。彼は此所へ家を持つまでは、家が決まったら落ち着いた気持で一人寺廻りをする事を大きい一つの楽しみとして考えていたのだが、さて実際落ち着いて見ると、何故か却ってそれができなくなった。妙に億劫(おっくう)になった。そして出掛けるとすれば大概新京極のようなごたごたした場所を歩き廻り、疲れ切って帰って来る、そういう方が多くなった。会う友達もなく、時には自分ながら法(ほう)のつかないような淋しい気持になる日もあつたが、それにしろ、それは大森の日のような、又は尾の道の日のような、それ程の参り方をする事は近頃全くなくなった。まとまった物ではなかったが、書く方も少しずつはできていた。 或る朝、彼がまだ寝ている時に、珍しくS氏が会社の出掛けだといい、上がらずに玄関で一通の開封された手紙を仙に渡して帰って行った。一時間程して謙作はそれを見た。敦賀からの承諾の返事だった。彼は繰返して読んだ。「オイ。これはSさんが自分で持って来られたのか?」。「へえ」。「ちよっと起こしてくれるとよかった」。「せんど、そう申したんどっせ。そやけど、会社の出がけやで、日の暮れに又お伺いするたら云うて、直きに去(い)なはりました」。謙作にとってはS氏がそうして自身で持って来てくれた事も嬉しかった。彼は色々S氏には世話になり、それをありがたく思っていながら、妙に機会がなく、これまで一度もS氏の家を訪ねなかった。この事はきになっていた。気になりながら、やはり彼は訪ねて行けなかった。そして同様S氏の方からも一度も訪ねて来ない事が、時々彼を不安にさえした。自分の礼儀なさをS氏が怒っている、そしてこの話にも、今は冷淡になっている、それで返事がこう遅れるのだ、結局こうしてこの話も有耶無耶になるのではないか、さういう不安だった。しかし今、彼はこう云う拘泥した濁った気分までも一掃されると、二重に晴々した気持になっていた。 「ようお決まりやしたか」。「うむ」。仙は今まで立っていたのを其所に坐り、柄になくしおらしい様子で、「お芽出とうござります」と祝辞を云った。「ありがとう」。彼もちょっとお辞儀をした。「そんで、何時---?」。「判然(はっきり)しないが、今年中か来年なら節分前だ」。「ほう。てんと間がおへんな」。「節分と云うと何日頃だ?」。「二月初めでっしゃろ」。その手紙にN老人の息子の友達で或る私立大学の文科にいる人があって、それから謙作の評判を聴き皆も喜んでいると書いてあった。謙作はその人が幸いに自分をよく云ってくれたからよかったが、と思った。そして、もし同じ事をその人の位置で自分が訊かれた場合、そう素直によく云うかどうかを思い、冷やりとした。彼は信行と石本とお栄とにほとんど同じ文句の手紙を書いた。その他に久しぶりで巴里の竜岡にも書いた。 午後彼は自家を出て、竜岡へ送る為に駿河屋という店に羊羹を(ようかん)を買いに行き、其所からS氏の会社へ電話をかけ、都合を訊き、此方から訪ねる事にした。四時に来てくれという事だつた。四時まではちょっと二時間近くある。彼は時間つぶしに四条高倉の大丸の店へ行った。華やかな女の着物を見る、こう云う、私(ひそ)かな要求が何所かにあった。それらを見る事から起こって来るイリュージョンが今の場合、欲しかったのだ。しかし又別に、最近、深草の練兵場で落ちた小さい飛行機を展覧している、それも見たかった。竜岡が、その飛行機---モラン・ソルニエという単葉の---を讃めていた事がある。そして彼は今日竜岡への手紙にその飛行家が、東京までの無着陸飛行をやる為に多量のガソリンを搭載し、試験飛行をしている中(うち)に墜落し、死んで了った事を書いた。半焼けの飛行服とか、焦げた名刺とか、手袋とかその他色々の物が列(なら)べてあった。彼が京都へ来た頃、よくこの隼のような早い飛行機が高い所を小さく飛んでいるのを見た。町の子供たちがそれを見上げ、「荻野はんや荻野はんや」と亢奮していた事を憶い出す。子供ばかりでなく、「荻野はん」の京都での人気は大したものだった。それが今は死に、その遺物がこうして大勢の人を集めている------。いい時間に彼は其所を出て、S氏の家へ向った。S氏の家は潜(くぐ)り戸を入ると敷石の両側が女竹(めだけ)の植え込みになつているというような京都らしい風雅な住まいだった。結納の事、結婚の時期、場所、そんな事が相談されたが、謙作には別に意見がなかつた。時期だけはなるべく早い方がいいとも思ったが、節分前と決まっていれば、その中でも早くというのは変な気もし、総て、いいように石本さんと相談し決めて貰いたいと頼んだ。 |
| 十一 |
| 謙作は二三泊で上京する事にした。わざわざ出るほどの事もなかったが、久しぶりでちょっと帰って見たいような気もしたし、それにこれまで石本が二度その為に来てくれた、それに対し、今度は自分の方から一度出て行こうと考えたのである。鎌倉へ寄り、信行と一緒に上京し、その夜石本を訪ねたが、相談というほどの事もなく、雑談に夜を更(ふ)かし、二人は其所へ泊る事にして、並んで床に就いた。その時信行は、「本郷へ寄る気はないね」と云った。「そうだね」。本郷は何か億劫な気がするが、------咲子や妙子には久しぶりで会いたいようにも思う」。「この間お前の話をしてやったら、大変喜んでいたよ」。「そう。何所かで会って行くかな」。「明日は日曜じやないか?」。「土曜だろう」。「そんなら明後日(あさって)鎌倉へ呼ぼうか」。「そうしてくれ給え」。「そうか、それじゃあ、そう明日電話で話して見よう。きっと喜ぶだろう」。翌日午後二人が鎌倉へ帰る前にその事を電話で話した。妹達は心からそれを喜び、翌日の汽車の時間なども打合わせた。汽車へ乗ると、信行は不意に、「例の写真は持って来ないんだね。------気が利かないなあ」とこんな事を云った。「それも考えたには考えたんだが------」。「考えて止めるところがお前だよ」と信行は何と思ったかそう鋭く云って笑い出した。謙作はちょっといやな気分がした。「しかし君は大森で見たんだし、------そして咲子たちとは今度会うとは思わなかったもの」。「それはそうだ」と信行は自分の云い過ぎを取消すように二三度点頭(うなず)いていた。 その夜二人は早く寝た。そして翌朝謙作は信行を残し、その時間に一人停車場へ出掛けて行った。彼がプラットホームに立っているところに汽車が着いた。二人は大きな荷物を持って降りて来た。「お兄様は?」と妙子が訊いた。「自家で待っている」。「まあ、ひどいわ。こんなに御馳走を持って来て上げたのに---」。妙子ははち切れそうに元気な見えた。そして暫く見ない間(ま)に大きくなっていた。荷だけ車に乗せて、先にやり、三人はぶらぶらと八幡前から学校の横を歩いて行った。長閑(のどか)ないい日で三人とも晴れやかないい気持になつていた。京都の家の話など出たが、謙作は却々(なかなか)結婚の事を云い出さなかった。云いはぐれた形でもあったが、余りそれが出ないので、咲子の方から、「今度の事、本統に嬉しいわ」と云い出した。「お式は何日(いつ)? 京都でなさるんでしょう?」。妙子も云った。「多分そうだ」。「その時、私、京都へ行きたいの」。「お兄さんに連れて来て貰うさ」。「ええ、そのつもり、だけど何時なの? 学校がお休みでないと駄目なのよ」。「その頃かも知れないよ」。「なるべくそうしてね」。「妙ちゃんの都合で、そんな事決められないわ」と咲子が云った。妙子は怒ったように黙って姉を見返していた。咲子は学校が休みでも妙子の京都行は父が許す筈がないと思っているのだ。それは謙作にも分った。分っていながら調子を合わせ、何か話していた事が、自分でちょつと気が差した、で、彼も黙って了った。近くまで来ると、妙子は一人先に駆けて行って了つた。荷を置いて来た車が彼方から帰って来た。 間もなく二人が西御門(にしみかど)の家についた時には妙子は座敷の真ん中に大きい風呂敷包みを解いているところだつた。菓子折りのような物、缶詰、果物、その他シャツや襦袢の類まであった。その他にもう一つ新聞紙で包み、うえを紐で厳重に結わえた函(はこ)ようのものがあって、妙子は想わせぶりな顔つきをしながら、それを別にし、「これは謙様の------」と云った。「今お開けになっちゃあ、いけない事よ、京都へお帰りになってから見て頂戴」。「どら、一寸見せろ」。信行が傍から手を出して云った。「いけない事よ」。「俺にだけ見せろ」。こういって取ろうとすると、妙子は怒ったように、「いやよ」と云った。「お祝いか?」。「お祝いは又別に差し上げるのよ」。「お祝いの手付けか」。「いい事よ、お兄様には関係のない事よ。黙っていらっしやい」。妙子は起ってそれを違い棚に載せた。「意地悪! そんなら口で云え。何だ」。信行は故(わざ)とこう乱暴に云った。「妙ちゃんのお手製の物よ」と傍から咲子が口を出した。「姉さん余計な事を云って------」。妙子は姉をにらんだ。そして京都へ帰るまでは決して開けないと云う堅い約束を謙作にさせ、漸く満足した。「そんなにら勿体つけちゃって、却って可笑しいわ。それこそ、開けて口惜しき玉手箱になつてよ」。こういって咲子はクスクスと笑い出した。「まあ、ひどい!」。妙子は眼を丸くして、昵(じ)っと姉の顔を見凝(みつ)めていた。涙が出かかっていた。「おい、もう直きひるだが、お前達がやるんだよ」。こんな事を信行がいっても怒った妙子は知らん顔をしていた。 午後皆で円覚寺へ行った。その帰途(かえり)建長寺の半僧坊の山へ登った。謙作は二人を東京まで送り、直ぐその晩の夜行で京都へ帰る事にした。帰り支度で妙子が便所へ入った際、信行は串戯(じょうだん)らしい、ちょっといたずらな様子をしながら、「何だ、見てやろうかな」といって違い棚の函を持ち出して来た。「まあまあ」。謙作も串戯らしくそれを取上げて了った。咲子は笑っていた。信行とは鎌倉の停車場で別れ、三人で東京へ帰った。そして其所で又妹達に送られて謙作は京都へ帰って来た。妙子の贈り物はリボン刺繍をした写真と立てと、宝石入れの手箱だった。「玉手箱」で怒ったわけだと彼は一人微笑した。手箱に小さい洋封筒の手紙が入っていた。健兄様。お芽出度うございます。先だってお兄様からお話伺いまして泣きそうになりました。私は一人直ぐ御洋室へ逃げて了いましたが、何だか、あんまり想いがけないのと、嬉しいのとで変になったのです。この箱は未知の姉上様に。この写真たては姉上様の御写真か、御新婚の御写真の為めピアノを習いに行くBさんの奥様に教えて頂いて私が作りました。こんな事が書いてあった。謙作は会った時何にも云わず、只気楽そうにしていた妙子が、自分の結婚をそれ程に喜んでくれた事を意外に思い、嬉しく思った。彼は涙ぐんだ。* |
| 十二 |
| 謙作の結婚の日取りは案外早く決まった。それはやはり石本や信行の意向からだった。支度は何も要らない。謙作もどれだけ京都に住むか分らないし、家もどうせ広い所を借りる筈はなし、今、色々な物を持ち込まれても困るから、と、こうS氏から彼方へ云って貰ったのである。そして、式その他もなるべく簡単に済ませたい、と云う事だった。十二月初めの或る日、敦賀からの一行(当人、母、兄)が出て来た。翌日皆はS氏の家に呼ばれ、其所で見合いをし、晩はやはりS氏の案内で南座の顔見世狂言へ行った。謙作は直子を再び見て、今まで頭で考えていたその人とは大分異う印象を受けた。それは何と云ったらいいか、とにかく彼は現在の自分に一番いい、現在の自分が一番要求している、そういう女として不知(いつか)心で彼女を築き上げていた。一言で云えば鳥毛立屏風(とりげだちびょうぶ)の美人のように古雅な、そして優美な、それでなければ気持のいい喜劇に出て来る品のいい快活な娘、そんな風に彼は頭で作り上げていた。総ては彼が初めて彼女を見た、その時のちょっとした印象が無限に都合よく誇張されて行った傾きがある。そして現在彼は同じ鶉(うずら)の桝(ます)に大柄な、豊頬(ほうきょう)な、しかし眼尻に小皺(こじわ)の少しある、何となく気を沈ませている彼女を見た。髪はその頃でも少し流行らなくなった、旧式ないわゆる廂髪(ひさしがみ)で、彼は初めて彼女を見た時どんな髪をしていたか、それを憶い出せなかつたが、恐らくもつと無造作な、少しも眼障りにならないものだつたに違いないと思った。 横顔が母親とよく似ていた。母親もN老人の妹として彼が想像していたとは全く反対であった。顔の大きい、ずんぐりと背の低い、如何にも田舎/\した人で、染めたらしい髪の余りに黒々しているのも、よくなかった。で、彼女が、それに似ていた事は、同じ場合を書いたUnfortunate Likeness というモウパッサンの短編小説を憶い起こさせたけれども、彼はその小説の主人公のようにその事には幻滅を感じなかった。それにしろ、彼女は彼が思っていたように美しい人でなかった事は事実である。尤もこの事は後で彼女自身話したところであるが、前日の汽車の疲れと、前夜の睡眠不足---疲労が却って彼女を興奮させ、ほとんど明け方まで、眠れなかった---為にその日は軽い頭痛と、幾らかの吐き気もあり、彼女としては半病人の状態にあったのだと云う事だ。実際彼もその日のような彼女を見る事はその後、余りなかった。 そして気を沈ませていたのは彼女ばかりではなかった。謙作も変に神経を疲らせていた。一体彼は初めて会う人と長く一緒にいると神経を疲らす方だった。殊にそれが無関心でいられない相手である場合一層疲れた。兄という人も感じは悪くなかったが、共通な話題のないところから、とかく不用意に文学の話をされるには彼は時々返事に困った。話の為の話で、一々責任を持った返事をする必要はないと思っても、彼にはその程度に淡泊(あっさり)とはそれが口に出て来なかった。只その人が時々如何にも人懐(なつこ)そうな眼差しで真正面(まとも)に此方の眼を見ながら、「不束者(ふつつかもの)ですが、何卒(どうぞ)」とか「母も段々年を取るものですから---」とか、こんな事をいう時には如何にも善良な感じがし、そして親しい感情を人に起こさせた。会ってまだ僅かな時間であるのに、謙作には既に赤の他人でない感情がその人に起っていた。 舞台では「紙屋治兵衛」河庄(かわしょう)うちの場を演じていた。謙作は何度もこの狂言を見ていたし、それにこの役者の演じ方が何時(いつ)も、余りに予定の如く只上手に演ずる事が、うまいと思いながらも面白くなかった。そして彼は何となく中途半端な心持で、少しも現在の自身---許嫁(いいんずけ)の娘とこうしている、楽しかるべき自身を楽しむ事ができなかった。彼はむしろ現在眼の前にいる直子を見、二月(ふたつき)前の彼女を憶い、それが同一人である事が不思議にさえ思われた。直子は淋しい如何にも元気のない顔つきをしながら、舞台に惹き込まれている。そのぼんやりした様子が謙作にはいじらしかつた。が、同時に彼自身、どうにも統御できない自身の惨めな気分を持て余していた。彼は努めて何気なくしていた。しかし段々に今は一秒でもいい、一秒でも早くこの場を逃れ出たいと云う気分に被われて来た。こう云う事は彼に珍しい事ではなかったが、場合が場合だけに彼は一層苦しい一人角力(ずもう)を取っていた。お栄との結婚の予想が彼を一時的に放蕩者にしたように、此度(こんど)も亦、多少病的にそうなった事が、彼を疲らし、彼の神経を弱らし切っていたのだ。 芝居のはねたのはもう晩(おそ)かった。戸外(そと)には満月に近い月が高くかかっていた。彼は直ぐ皆と別れ、籠(かご)を出た小鳥のような自由さで一人八坂神社の横から知恩院の方へ歩いて行った。とにかく一人になればいいのであった。知恩院の大きな山門は近寄るに従って、その後ろに月が隠れ、大きな山門は真っ黒に一層大きく眺められた。結婚の第一歩がこんなにして始まった事は幸先(さいさき)悪い事のような気がした。しかし何よりも悪いのはやはり自分だと彼は思った。自制できない悪い習慣---そういって自身責任を逃れる気はないが、もしかしたら祖父からの醜い遺伝から自分は毎時(いつも)、裏切られるのだ。そんな気も彼はするのであった。何しろ慎もう。今日の事は今日の事だ。これから本統に慎み深い生活に入らなければ結局自分は自分の生涯をその為め破滅に導くような事をしかねない。そして結婚後は殊にこの事は慎まねばならぬ。そう考えた。彼はこの何度でも繰り返す、そしていつも破れて了う決心をみの時も亦繰返した。 彼が直子と結婚したのはそれから一週間ほどしてからであったが、その前一度直子ら親子三人が彼の寓居を訪ねて来た事がある。曇った寒い日の午後だった。仙が台所で何か用事をしている時で、彼は石本と信行に出す端書を出しに二三町ほどある、ポストまで出かけて行くと、彼方から歩いて来る親子三人を遠くから見た。母だけ一足後れに、直子は先に立った兄にその大きな身体を寄り添うようにして何か快活に喋っているところだった。見違えるほど美しく、そして生々して見えた。謙作は心の踊るのを覚えながら立止って待った。謙作も至極気持が自由だったし、万事気持よく行き、皆、愉快そうにしていた。仙もこの女主人公の為にできるだけの好意を見せたがり、その為、焦っていた。謙作は久しく出した事のない手文庫の写真---亡き母、同胞(きょうだい)、母の両親、お栄、その他学校友達などの---を出して見せたりした。 銀閣寺へ行く事にして歩いて出る。安楽寺、それから法然院を見、そこの阿育王(あしょかおう)搭の由来を話すとき、直子は丁度女学生が崇拝する教師の話でも聴くような様子で熱心に耳を傾けていた。銀閣寺へ入ろうとすると、不意に兄が、「少し気分が悪いから先に帰る」と云い出した。青い顏をして、額に油汗をかいている。皆ちょつと心配したが、謙作自身の寒がり癖から、無闇と部屋に炭火をおこした。それに当たったらしい。一人でもいいと云うのを丁度車があって、母と二人、直子だけを残して先に帰る事になった。二人は瓦を縦に埋(うず)めた坂から、黙って門を入って行った。「徳」と一字の衝立(ついたて)があって、その側(わき)で案内者を待つ間も話しが途断(とぎ)れていたが、間もなく短い袴を穿(は)いた案内の子供が出て来て、「向月台(こうげつだい)に銀砂灘(ぎんさたん)」、「左右の唐紙は大雅堂(たいがどう)の筆」こんな風に一人大きな声をしていてくれるので具合悪さは何時(いつ)か去(と)れた。「帰り、もし直ぐ車で帰るようなら、置いて来た日傘や信玄袋は宿の方へ、晩にでも届けて上げますが、どうしますか」と謙作は訊いた。直子は黙ってちょっと怒ったような眼つきで、彼の方を見ていた。「それとも寄って行きますか?」。こういうと、当り前だというように「ええ」と不愛想に答えた。 南禅寺の裏から疎水(そすい)を導き、又それを黒谷に近く田圃(たんぼ)を流し返してある人工の流れについて二人は帰って行った。並べる所は並んで歩いた。並べない所は謙作が先に立って行ったが、その先に立っている時でも、彼は後から来る直子の、身体の割りにしまった小さい足が、きちんとした真白な足袋(たび)で、褄(つま)をけりながら、すっすっと賢(かし)こ気(げ)に踏み出されるのを眼に見るように感じ、それが如何にも美しく思われた。そういう人が---そういう足が、すぐ背後(うしろ)からついて来る事が、彼には何か不思議な幸福に感ぜられた。小砂利を敷いた流れに逆らって一疋(ぴき)の亀の子が一生懸命に這(は)っていた。如何にも目的あり気に首を延ばして這っている様子が可笑しく、二人は暫く立つて眺めていた。「私、文学の事は何にも存じませんのよ」。直子はその時、とつけもなく、そんな事を云い出した。謙作は踞(しゃが)んで泥の固鞠(かたまり)を拾い、亀の行く手に目がけて投げた。亀はちょっと首を縮めたが、解けた泥水が去ると、甲羅に薄く泥を浴びたまま歩き出した。「知らない方がいいんです」。謙作は踞(しゃが)んだまま答えた。「ちょっとも、いい事ありませんわ」。「その方が僕には却っていいんです」。「何故?」。こう云われると謙作も判然(はつきり)した事は云いにくかった。昔はそうでなかったが、今の彼は細君が自分の仕事に特別な理解があるとか、ないとか、そういう事は何方(どっち)でもよかったのである。お栄と結婚したいと考えた時に既に不知(いつか)その問題は通り過ぎていた。そして寧ろ「文学が大好きです」と云われる方が、堪らなかった。 直子の方はこの事を早く断っておかぬと気になるらしかった。それともう一つ、直子の伯母(おば)で、出戻りで、直子の生れる前から自家にいる人がある。この人が、自身に子のないところから直子を甚(ひど)く可愛がっていた。今はもう六十余りで直子と別れる事を淋しがっている。この伯母はこれからも時々京都へ出て来て御厄介になる事があるかも知れない。その事をどうか許して頂きたい。「伯母からもくれぐれもお願いしておいてくれと申されましたの」と云った。寓居へ帰って二人は暫く休んだ。直子は次の間の本棚を漁(あさ)りながら、「どういう御本を読んだら、よろしいの?」とまだこんな事を云っていた。二人は一緒に出て、謙作は宿まで直子を送って行った。兄はもう起きていた。帰って暫く眠ったら直ったという事だった。 |
| 十三 |
| 二人り結婚はそれから五日ほどして、円山(まるやま)の「左阿弥(さあみ)」と云う家で、簡単にその式が挙げられた。謙作の側からは信行、石本夫婦、それから京都好きの宮本、奈良に帰っている高井、そんな人々だった。直子の側はN老人夫婦と三四人の親類知己、その他は仲人のS氏夫婦、山崎医学士、東三本木の宿の女主(おんなあるじ)等で、感嘆と云っても謙作が予(かね)て自身の結婚式として考えていたそれに較べれば賑やかで、むしろ自分にはそぐわない気さえした。そしてこの日も上出来にも彼は自由な気分でいる事ができた。種々(いろいろ)な事が、何となく愉快に眺められ、人々にもそういう感じを与え得る事を心から喜んでいた。舞子、芸子らの慣れた上手な着つけの中に直子の不慣れな振袖姿が目に立った。その上高島田の少しも顔になずまぬところなども、変に田舎染みた感じで、多少可哀想でもあったが、現在心の楽しんでいる謙作にはそういう事まで一種ユーモラスな感じで悪くは思えなかった。十一時頃に総てが済んだ。帰り際に信行は、「俺は石本の宿へ行くよ。それからお栄さんには明日早く俺から電報を打っておこう。精しい事は少し落ち着いたところでお前から手紙を出すといいね」とこんな事を云った。信行はこの日かなり酷く酔い、一人でよく騒いでいた。しかしその騒ぎ方も何となく厭味がなく、少しも皆に不快な感じを与えなかったが、それでも初めて信行のこんな様子を見る謙作はそれが物珍しくもあり、同時に多少心配でもあった。今はいいが、もう少し酔ったら脱線しはしまいかという気がした。が、今、信行から、思いの外の正気さで、そかな事をいわれると、彼は流石(さすが)信行だというような心持で、心から肉親らしい親しさを感じないではいられなかった。帰ると仙が、昔風な小紋の紋附きを着て玄関に出迎えた。 翌日早く二人は先ずS氏の家へ礼に行った。出勤の時間になっていたが、S氏は待っていてくれた。それから石本夫婦の宿へ行き、其所から信行も一緒になって東三楼の実家の連中のいる所へ行った。二三日は何のかの、帰る人の見送りやら、奈良行きのつき合いやら、そんな事で忙しく日を過ごした。謙作の寓居は八畳に次の間が北向きの長四畳、それに玄関、女中部屋、という小さな家だった。北向きの四畳が使えない部屋なので二人になると、どうしても又引越さねばならなかった。 謙作は直ぐ仕事をする必要もなかったのであるが、結婚後暫くは何もできなくなったと云う風になりたくない気持から、殊更何時でも仕事のできる状態を作っておきたかった。或る日二人は前に一度見た事のある高台寺の方の貸家を見に行った。前に見た家は既にふさがっていたが、同じ並びに新築された二軒棟割りの二階家があって、その東側のが気に入って大概それと決めた。「此所がちょっと具合悪そうだな」。二階の南向きの窓から首を出して謙作は云った。「隣りから首を出すと、直ぐ向かい合いになる」。「本統に」と直子も云った。鍵を持って案内に来た大家の若い息子が、「其所でしたら、その便所の屋根に小さい塀を立ててもよろしいです。西日除けにもなりますって---」と心地よく云った。「そう。そうして貰えば上等です。それから、この電気の紐を部屋の隅に置く机の上まで引っ張れないと困るのですが、もし何だったら私の方で直してもいいけど---」。「へえ、それぐらい、私方(わたくしかた)でさせましょう」。この辺りまではよかつた。が、それから又階下(した)に下り、茶の間になる部屋の電燈がやはり天井から二尺ほどしか下がっていないのを見ると、謙作は、「これも少し困るな」と云った。「これじゃあ針仕事に暗いだろう」。「延びるんじやないこと」と直子がちょっと脊延びをしてそれを下げようとした。「延びまへん」。大家の息子は気色(きしょく)を害したような調子で云った。そして少し離れた所に立って黙ってそれを見ていた。 謙作は自分達が余りに虫がいいのを怒っているな、と思った。虫がいいには違いないが、又どう云うわけでこんな事まで吝(しわ)くするのだろうと思った。大家の方は延ばそうとは云わない。延ばして貰いたいと云っている事が分かっていて、知らん顔をしている事が謙作には彼の我が儘な本性(ほんしょう)からちょっと癪(しやく)に触った。「これは私の方で入ってから延ばしてかまいませんね」と彼は云った。「困ります、---それは」。不愛想に若い大家はそれをはねつけた。「どうしてかしら」。「京都の者にはそれで事が足りとるさかいな」。「------」。謙作は腹を立てた。「そう紐を長うしたら見ようのうなる」。「還(か)えす時元通りにして返したら、いいだろう。それでも駄目か?」。「あきまへん」。若い大家は顔色まで変えている。「そんな馬鹿な奴があるもんか。そんなに借りるのはやめだ。---帰ろう」。謙作の方も短期にこんな事を云い、挨拶もせずにさっさと出て来た。直子一人閉口していた。それでも直子が何か云ってお辞儀をすると、若者も「いや」と云って、叮嚀に頭を下げた。「まあ、両方お短気さんなのねえ」と日傘を開きながら小走りに追って来た直子が笑った。「しかし彼奴(あいつ)、割りに気持のいい奴だ」。謙作は苦笑しながら云った。若者の怒るのも無理ない気もしたし、自分が一緒にむかっ腹を立てた事も少し気まりが悪かった。「喧嘩してほめちゃ仕方がないわ。あんないい家、惜しいわ」。「幾ら惜しくても、もう追いつかない」。「今度はね、黙ってて、入ってから勝手に直すのよ。そんな、初めっから色々註文(ちゅうもん)をするから怒って了いますわ」。 その日はもう貸家探しをやめ、二人は祝い物の返しの品を買いに行く事にした。五条坂の有名な陶工の家を一軒一軒寄って見た。六兵衛、清風、宗六、---宗六の家の多分宗六と云う人だろうと思う、至極質素な身なりをしたまだ割りに若い人が親切に参考品としいう先々代宗六の赤玉の香合(こうごう)などを見せてくれた。初代宗六は伊勢の亀山からだた人で、謙作の母方の叔母が片附いた先がこの陶工の近い親類であるところから、その叔母は京都では何時もこの家に宿るというような話を前に聞いていた。彼はそう云う心持からもこの人には或る親しみを感じた。しかし何故か彼は自分がその叔母の甥である事を云う気はしなかった。宗六の家が陰気にじめじめしているに反し、宗六から出て新しく一家をなした木仙(もくせん)の家に行くと総てが変に生き生きしている事が感ぜられた。彼は親しみを持った宗六の家で買う物がなく、やはり木仙へ来て返しの品々を揃える事ができた。店一杯に品物を置いた中に坐って、一人で茶をつぎ、客の応対をしている二代木仙は如何にも覇気のあ人物らしかった。彼は赤絵の振出しを幾つか買う事にした。その箱だけは今病床にいると云う初代が書いた。 二人がその家を出た時には既に日暮れ近く、寒い風が道に吹いていた。謙作にはその寒さがこたえた。「早く何所かで飯を食わないと風邪をひきそうだ」。彼はこんな事を云って二重まわしの襟を立てた。「きつと仙が支度をして待ってますわ」。「どうだか?」。「そう?そんなに平時(いつ)もそとでうがっていらしたの?」。「そうでもないが、出掛けた時間がおそかったから、そとで食って来ると思ってるだろうよ」。なだらかな五条坂を二人はこんな事を云いながら下りて行った。五条の橋はかけ更(か)えで細い仮橋が並べてかけてある。二人はそれを渡って行った。「これが五条の橋なの?」。「うむ」。「伯父(おじ、N老人)さんがSさんのお世話で、五条の橋杭(はしぐい)の旧(ふる)い台石を頂く事になったとか、大層喜んでいらしたわ」。「何にするんだろう?」。「お茶室の踏み石にするとか、何だかそんな事を云ってらしたようよ」。「伯父さんは中々お茶人なんだね」。「ええ。自家のお母さんとは大分異う方(ほう)なのよ」。「そうかね。初めて東三楼に出た時、古い羅紗(らしゃ)の袋で中々いいのを見せて頂いたが、そう云う物も凝られる方かね」。「あれは古い袋ですわ。私が子供の頃からよく腰に下げていらしたのを覚えてますわ。あんなのがいいの?」。「中々いいしゃないか」。「貴方も中々お茶人なのね。今日のお買物を見てもそうらしいと思ったわ」。こんな事を云って直子は笑った。「兄さんはどうなの?」。「兄さんも私もお母さんの子ですもの、そう云う方は一向いけない方よ」。「その方がいい。若い人のお茶人はあまりいいものじゃないよ」。「貴方のは何でも解らない方がいいのね。文学も解らない方がいいし、風流も解らない方がいいし」。「本統だよ」と謙作は云った。「文学が解ったり、風流が解ったりすると云う事は一種の悪趣味だ」。「妙なお説ね。私、それも解らないわ」。直子は大きな声をして笑い出した。謙作も笑った。直子はそれを覗き込むようにして、「やはりそれも解らない方がいいの?」と云って自分でも堪らなさそうに笑いこけた。「馬鹿」。そして謙作も思わず、こんな言葉を口に出した。 二人は橋を渡ると、其の所から四条まで電車で行き、菊水橋という狭い橋の袂(たもと)から蠣船(かきぶね)に行った。謙作には尾の道以来の蠣船である。で、彼にはあの頃の苦しい記憶がちょっと気分を掠(かす)めて通ったが、しかしそれから被われるにしては今の彼は余りに幸福だった。一つは居る場所の雰囲気が全(まる)で変っていた。あの薄暗い倉庫町の蠣船とは此所は余りに変っている。前に祇園の茶屋/\の燈(あか)りがある。四条のけばけばしい橋、その彼方に南座、それらの燈りがまばゆいばかりにきらきらと川水に照り反していた。一時間ほどして二人は其所を出た。二人は軽い気持を味わいながら、美しい着物を着た舞子や髪を引っつめて結った小さいおちょぼらの行き交う祇園の茶屋町を抜けて、東山側の電車通りに出た。その出た所に、前にも一度書いた場末の寄席のような小さい芝居小屋がある。其所で謙作がかって蝮(まむし)のお政と云う女を見た、その小屋である。 「あなたは蝮のお政と云う女を知ってるかしら?」。彼はその時を憶い出して云った。「何だか、講談で読んだ事があるようよ」。「此所でその女を見た事がある」。「まあ。まだ生きてる人なの?」。「自分の一代記を芝居にして歩いてい」。謙作はその時のあの頭を丸めた男のような大きな女の話をした。「決して心の楽しむ事のない絶望的な憂鬱」そんな印象を受けた事などを話した。そして彼はそれと一緒にその春何度も書いて遂に書き上げられなかった栄花(えいはな)と云う女の事も話した。「懺悔と云う事も結局一遍こっきりのものだからね」。彼はこんな事を云った。「二度目からはもう最初の感激はないんだから、懺悔の意味はなさないと思うよ。それを芝居で興行(こうぎょう)して歩くというのだから無理もない話だ。無論懺悔の意味は少しもないね」。彼はそれよりも、現在、罪を犯しながら、その呵責の為、常に一種張りのある気持を続けている栄花の方が、既に懺悔し、人からも赦されたつもりでいて、その實、心の少しも楽しむ事のないお政の張りのない気持よりは、心の状態として遥かにいいものだと思うと云うような事を云った。 「そうでしょうか? 私、悪い事をしても、云わない間は、それは苦しいの。だけど、それを云って了うと本統にせいせいしますわ」。「あなたの悪い事と、お政や栄花の悪い事とは一緒にならないよ」。「違うの?」。こう云った直子の言葉の調子が謙作には無邪気に響いた。「そりゃあ、異うよ。あなたのは云いさえすれば誰でも赦せる程度のものだし、お政や栄花のはそう簡単には行かないだろう。あなたのは云って直ぐあなたがそれを忘れたところで誰も何とも思わないが、悪い事によっては懺悔したらそのままその気持を持ち続けていてくれなければ困るというようなものがあるだろう。直ぐせいせいされたらいい気がしないよ」。「誰がいい気がしないの?」。「誰がって---悪い事をされた人が---」。「執念深いのね」。「懺悔もいっそ後悔しなければ悔悟の気持も続くかも知れないが、してしまったら却って駄目だね」。「そんなら、どうすればいいの」。「------」。謙作は不意に云い詰まった。彼には不図亡き母の事が想い浮んだ。彼は陥穴(おとしあな)に落ちたような気がした。そして、口を噤(つぐ)んで了った。二人は暫く黙って歩いた。五六歩行った時に、「もうそんな話、やめましょう。ね?」と直子も何か不安な気持に襲われたかのように云った。直子は謙作の母の事は聞いていた。が、それがその時、想い浮んだのではないらしかった。只何となく気配が彼女を不安にしたらしかった。そして、「何か、もっと気持のいいお話ないの? 気持のいいお話をして頂戴。---ねえ、私、そんなお話よく解らないのよう」。殊更甘えるような調子に云って、その丸味のある柔らかい肩で押して来た。「何でも解らないとね」。謙作は笑った。「解らないと云えば讃められるかと思って---」。「そうよ。私、何にも解らないから、分からす屋よ。いいこと。貴方もその方がいいんでしょ」。間もなく二人は軽い気持になって北の坊の寓居へ帰って来た。 |
| 十四 |
| 十日ほどして二人は衣笠村にいい新建(しんだ)ちの二階家を見つけ、其所へ引き移った。一月の、それは京都でも珍しい寒い日だった。建って漸く壁の乾いたところで、まだ一度も火の気の入らぬ空家では、寒さは一層身に堪(こた)えた。S氏の会社の年寄った小使いが手伝いに来た。その小使いが、「此所は女御はんだけでは御留守が淋しいですな。別に物騒なちゅう事もありますまいが、犬を飼われたら、よろしいな」と云った。それで謙作はその人に犬の世話を頼んだ。その晩は、あるだけの火鉢に火を一杯におこして部屋を温めてから寝た。 彼は二階に書斎を決めた。机を据えた北窓から眺められる景色が彼を喜ばした。正面に丸く松の茂った衣笠山がある。その前に金閣寺の森、奥には鷹ケ峰(たかがみね)の一部が見えた。それから左に高い愛宕山(あたごやま)、そして右に、ちょっと首を出せば薄く雪を頂く叡山が眺められるのである。彼はよく机に向かったまま、何も書かずにそう云う景色を眺めていた。二人はよく出歩いた。花園の妙心寺、太秦の広隆寺、秦の河勝を祭った蚕の宮、御室の仁和寺、鷹ケ峰の光悦寺、それから紫野の大徳寺など、この辺りをよく散歩した。そして夜は夜で、電車に乗って新京極の賑やかな場所へもよく出掛けた。近くでは、「西陣京極」と云われる千本通りのそう云う場所へも行った。 その頃丁度中学では謙作より二つほど下だったが、家の近いところからよく遊んでいた末松が、岡崎の或る下宿に来た。四五年前に此所の大学に入ったのだが、病気の為に二年ほど休んで、未だに年の半分ぐらいずつ東京から出て来ては残った試験を受けている。この末松が或る晩、謙作の書いた物をよく見ていると云う青年を連れて訪ねて来た。「水谷君は君の書くものと阪口君の物とが一番好きなんだそうだ」。こう末松が云った。謙作は返事に困った。阪口と一緒に好かれてる事も困ったが、面と向かって自分の作物をこう云われると彼は何時も返事に当惑する方だった。「水谷君も文科で、今年大学へ来るんだ。僕にはよく分らないが詩でも歌でも何でもやるよ」。「その内何かできたら、お暇な時に見て頂きます」。水谷は割りにハキハキした調子で云った。「阪口には会った事あるんですか?」。「いえ、まだ一度もお眼にかかりません」。 直子が茶や菓子を持って入って来た。謙作は末松に紹介した。それから水谷にも。直子は何時の間にか着物をかえ、髪も綺麗になでつけて、如何にも新妻らしい、しとやかさで、客の前に茶や菓子を進めた。「君は奥さんのお従兄(いとこ)を知ってるんだね」。末松は顧みて云った。「ええ。要(かなめ)さんとはずっと中学が一緒でございました。それから、久世君もそうです」。直子は故(わけ)もなく赤い顏をした。要と云うのはN老人の息子で今東京の高等工業に入っている。謙作は会った事はないが、名だけはよく知っている人だ。そして彼は、「久世君というのはどう云う方?」と直子の方を向いて訊いた。「要さんの御親友で、同志社の大学にいらっしゃる---そら! 貴方のもの讃めていらっしゃる方よ」。直子は謙作にだけは如何にも自由な調子で後を早口に云った。結婚の話の時、作家としての謙作の評判を訊いたと云うその人である。「そうか」。「久世君も是非お伺いしたいと云っておりますがお差支えございませんか?」。「ええ。何時でも」。 直子はほとんど寄り添うように近く謙作の側(そば)に坐っていた。謙作は何か、客の手前、具合悪い感じをしながら、故意(ことさら)、直子に無関心でいようと努めたが、それが又、故(わざ)とらしくなりそうで困った。彼は何気なく居ずまいを直す時になるべく直子から身を離した。「要さんからは時々お便りがございますか?」。水谷は年に似合わず、こんな風に直接直子に話しかけたりした。「いいえ、ちょっとも」。こう云いながら直子は謙作の方を向いて、「ひどいわ。此方へあがってから一度も便りをくれないのよ」と云った。謙作は黙っていた。「この春休みには敦賀の行きか帰りに京都へも寄るような事を久世君の所へ云って来たそうですよ。此方の新家庭を拝見しがてらに---」。水谷はそう云って一人笑った。「いやな人!」と直子は腹立たしそうに云い、ちょっと赤い顔をした。末松が謙作とは親しい間柄でいながら側(わき)に馴染の薄い直子が居ると、平時(いつも)の半分も喋(しゃべ)れずにいるのに、初めての水谷が年に似ず何の拘泥(こだわ)りもなくそんな串戯(じょうだん)をよく喋れる事が謙作にはいい感じがしなかった。水谷は色の白い小作りの、笑うと直ぐ頬に大きく縦に笑窪(えくぼ)の入る、そして何となく眼に濁りのある青年だった。紺絣(こんがすり)の着物にセルの袴(はかま)を穿(は)いて、袴の紐を駒結びに結び切って、その先を長く前へ二本垂らしていた。末松とは同じ下宿で今度初めての知り合いで、将棋、花合わせ、玉突き、そう云う遊び事がうまく、二人はその方での友達であった。 「奥さん」。仙が唐紙の彼方で呼んだ。「奥さん、ちょっと、来ておくりやすな」。直子は急いで立って行った。その姿が隠れると、今までそれを待っていたかのように、末松は花を打ちつける手真似をしながら、「やるかい?」と云って笑った。「いや」と謙作も微笑し、首を振った。二人はまだ中学生だった頃お栄と三人でよくそれをした事があった。「道具はあるの?」。「何所かにあるわけだよ。例の古い奴が---」。「やりたいなあ」。末松は如何にもその遊びをしたいらしく、子供らしい調子で云った。「何だい、そんなに熱なのか」。「末松さんの熱は下宿でも一番高いんです」。「奥さんはどうだい?」と末松が云った。「どうかな」。直子が仙に襖を開けさせ、林檎(りんご)の切ったのを山に盛った大きい切硝子(きりこ)の鉢を両手に持って入って来た。「花を知ってるかい?」。謙作はまだ立っている直子を見上げて訊いた。「花って---?」。直子は立ったまま首を傾けた。「これだ」。謙作もその手附きをして見せた。「ああ、そのお花?」。直子は坐り、鉢をいい位置に置きながら、「知っててよ」と云った。「うまいな!」。水谷が浮かれ調子にそう云って如何にも乗り気な風をした。「道具のあるとこ分るかしら?」。「お引越しの時ちょっと見たんですけど、赤い更紗(さらさ)の風呂敷に包んであるのがそうでしょうか」。「それだ」。「持って来るの?」と、よくする癖で直子は又首を傾けて訊いた。「うむ」。 少時(しばらく)して四人は電燈の下の白い切れに被われた一つの座布団を囲んで。「総て四倍勘定なんだ、その他は別に変りはないけど」。そう石を分けながら末松が云った。「私の知ってるのと異ってそうだわ」。「あなたのはどう云うんだ。やはり役何かあるんだろう?」。「そりゃあ、ありますわ。月見、花見、とか、猪鹿蝶(いのしかちょう)とか、そんなのがあるのよ」。「それじゃあ、異うな」と謙作が云った。「そう? そんなら私、初め見てましょう。その方がいいわ」。「奥さん、かまいませんよ」と器用な手つきで札を切りながら、水谷が云った。「直ぐ覚えられますよ。それに四人なら誰か寝ますから、寝た人が後見(こうけん)をすればいいんですもの」。「入るといい。直ぐ覚えられるよ。役を書いてやるから、紙と硯(すずり)を持って来ないか」。直子は立って、それを取りに行った。水谷が黒の札を四つに分け、それを開けると謙作のところに親の鶴があった。謙作は赤い札を取り、それを播(ま)いた。「私が書きましょう」。水谷は入って来た直子の手から紙と硯を取り、手役から一つ一つ説明をしながら書いた。謙作はちょっと自分の手を見てから、それを伏せ、手持ち無沙汰に巻煙草に火をつけた。「竜岡君は今何所だい? やっぱり巴里かい?」。末松が云った。「そうだ。中々勉強してるらしいよ」。「飛行機の発動機では竜岡君が日本で一番いいんだそうだね」。「そうかね。既に一番いいとなっているのかね」。謙作は此処目から嬉しく思った。「そう云う噂だよ。---君の所へは始終便りがあるかい?」。「時々ある」。 水谷は一通り手役を説明してから、「光一(ぴかいち)が一名ガチャ。丹一が丹兵衛---」。こんな事を云いながら、「光一」の下に「ガチャとも云う」などと書いた。「おい。いい加減にやろうよ」。待遠しがって末松が云った。「待ち給え、手役が済んで、これからが出来役の部だ」。そして水谷はその方の説明を始めた。「お栄さんは?」と末松が訊いた。「天津(てんしん)に居る」。「天津に?」。末松は驚いたように云った。「又、どうしてそんな所へ---」。「彼方に従妹(いとこ)がいるんだ。それが去年の秋に出て来て、それと一緒に行ったよ」。謙作はお栄の商売を訊かれたくなかった。隠す必要もなかったが、初めての水谷の前ではそれが云いたくなかった。しかし末松はやはりそれを訊いた。「何か商売でもしてられるのかい?」。「何かちょっとした事をしているんだろう。その従妹と共同でやってるんだ」。末松はそれ以上追及して訊かなかった。その時丁度、「さあ、じゃあ、始めましょう」と水谷が云った。謙作は直ぐ自分の手をそのままめくり札に重ねて、「何貫」と云った。「二貫です」。謙作はそれだけを場へ投げ出すと直子の方へいざり寄り、「どうだい。分った?」とその手を覗(のぞ)き込んだ。「どうなの?」。直子は札を両手に持ったまま謙作の顔の前へ出した。「出て御覧」。「これ、役なの?」。直子はそういって自分の札と水谷の書いてくれた紙と見較べた。皆は笑った。 こんな風に初めてなのであるが、誰か一人ずつ寝た者が後見についていると、何時か直子が一番の石高(こくだか)となっていた。そしてその後に水谷の後見で五光を作ると、これで大概銀見(ぎんみ)は決って了った。直子の大きな銀見で、一年済んだところで、「今度は一人でやって御覧。大概解ったろう?」と謙作がいった。「ええ、いいわ。今度は一人でやるわ」。しかし一人になると、直子はやはりよく負けた。結局又誰か後見する事になったが、一勝負済んで数勘定の時など、直子はよく、「私に何か手役なかったこと?」。こういって考える事があった。「あったわ、たて三でしょ」。「何いってんだ。そりゃあ、前の勝負だ。欲が深いな」。謙作は串戯(じょうだん)らしくそう云いながら、直子には女らしい小心で、実際欲の深いところがあるようだと云うような事を思った。水谷の親で、親が出ると云った。次も出ると云った。その次が謙作で、謙作には二役(ふたやく)がついていたので、出ると云い、最後の直子が追い込まれる事になった。「買ってやろう。何かあるかい」。そう云って謙作は直子を顧みた。直子は扇形に開いた七枚の札を彼に見せて、「丹兵衛さんよ」と云った。「よし。桜の丹だ」。こう皆にいって、何気なくもう一度見た時にかすの菊がちょっと彼の注意をひいた。彼は手を出し其所だけ扇をもっと開いて見た。それは盃(さかずき)のある菊で、それがあってはその手は役にならなかった。謙作はその盃だけが上の札で完全に隠されてあるところから、これは直子がずるをしようとしたのだと思った。「ちょっとも気がつきませんでしたわ」。直子もちょっといやな顔をして云った。「よろしい。それじゃあ、桜の丹があるが、罰として只だ」。彼は何気なくその札を受取り、めくり札に切り込んで、直ぐ勝負にかかったが、「狡(ずる)い奴だな」と直ぐ一口(ひとくち)に串戯の云えなかった処に何となく、それが実際直子のずるだったような気がした。勝負をしながら、彼はその事を考えた。彼は気を沈ませた。そして、思いなしか、皆も妙に黙って了ったような気がした。 十一時頃、帰るという二人を送って、彼は直子も連れ、自家を出た。「そのうち、下宿へやりに来ないか」と末松が云った。「行ってもいいが---」。謙作は曖昧に答え、しかし水谷のような連中と一緒にやるのは気が進まなかった。「どうか是非お出で下さい」と水谷も云う。「大概毎日、何所かの部屋でやってます」。「花は余り得意でもないから---」。「そんな事はありませんよ。時任さんの花は理詰めで大変面白いと思いますよ。末松君のは思念術流と云うんですが、時々定跡(じょうせき)にない事をやるんでね」。こんな事を云って水谷は末松の方を向いて大きな声を出して笑った。「思念術とはどういうんだ」。謙作は末松に云った。「ええ? 思念術か?」と末松は只笑っていた。「つまり思念術で何でもおこしで打ち当てようというのですよ」。 椿寺、それから小さい橋を渡って一条通りの町になる。が、晩(おそ)いので何所ももう店を閉め、ひつそりしていた。直子は毛の襟巻(謙作の)に深く頬を埋め黙り勝ちに謙作の後からついて来た。「どうだい。もう帰らないかい」と末松が云った。「あなたはどうだい?」。謙作はいたわるように云い、直子を振り返った。「わたし、いいのよ」。「そんなら大将軍の前あたりまで行こう」。寒い晩で皆が黙ると、凍った路(みち)に下駄の歯音が高く響いた。「もう少し温かくなったら、一緒に何所かへ行って見ようかね」。十年程前の春、末松と富士の五湖を廻った事がある。それを憶い出し、謙作は云った。「それは賛成だね。僕はこの春、月ヶ瀬へ行って見ようと思ってるよ。君がまだなら、月ヶ瀬でもいいね、笠置(かさぎ)の方から越して行くんだ」。「月ヶ瀬はいいでしょうね。僕も未だ行かないが」と直ぐ水谷も云った。が、二人はそれには答えず、五湖廻りをした時の話などを始めた。 そして間もなく大将軍という町中にある丹塗(にぬ)りの小さい社(やしろ)の前まで来て、其所で謙作達は二人に別れて引き返して来た。直子は何となく元気がなかった。やはり先刻(さっき)の事が直子の心を傷つけているのだと謙作は思った。謙作はもしそれが云える事なら何とか云って慰めてやりたかった。そして彼にも亦それが自身の事がらのように心を傷つけているのであった。「疲れたかい?」。「いいえ」。カタリコトリ冴えた音をさせながら、野菜を積んだ牛車がすれ違って行った。牛は垂れた首を大きく左右に振りながら鼻から出る太い気霜(きじも)を道へ撒(ま)き撒き通り過ぎた。「ずるは悪い」。謙作は思った。「悪い事は大概不快な感じで、これまで自分に来た。が、今、自分は毛ほどの不快も悪意も感じていない。これは不思議な事だ」と思った。彼には堪らなく直子がいじらしかった。彼はその事があって、反(かえ)ってかって感じなかったほどに深い愛情を直子に感じていた。彼は黙って直子の手を握り、それを自分の内懐(うちふところ)に入れてやった。直子は媚びるような細い眼つきをし、その頬を彼の肩へつけ、一緒に歩いた。謙作は何かしら甚く感傷的な気持になった。そして痛切に今は直子が完全に自分の一部である事を感じた。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)