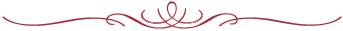
| 文革史(二)、将軍の絶頂期から「林彪事件」で失脚するまで |
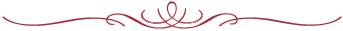
(最新見直し2006.9.15日)
(「文化大革命」解析中)
これより前は、「文革史(一)」
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「文革」の第二段階は、林彪が毛沢東の後継者としての地位を約束される第9回党大会へ至る過程から急転直下失墜するまでの1969~73年とすることが出来よう。 「文革」のなかでも、最もドラマチックなのは、林彪の躍進と墜死事件である。69.4月の第9回党大会では毛沢東の「最も親密な戦友」として後継者としての地位を約束されていたが、こともあろうに「71.9月には毛沢東暗殺に乗り出し、失敗し、ソ連に逃亡を図り、モンゴル領内で墜死する」という奇怪な事件を引き起こしている。その真偽は未だ定かではない。林彪の失脚過程は現代史の最大の謎であり、興味をそそられないわけにはいかない。 2006.9.15日 れんだいこ拝 |
| 【「8期12中全会」前の動き】 |
|
1968.3.24日、人民大会堂で林彪が長い講話を行い、余立金を叛徒して逮捕し、楊成武総参謀長代理を解任し、傅崇碧北京衛戌区司令員を解任した。いわゆる楊成武事件である。楊成武は二月逆流以後も、林彪の指示を無視して、中央文件を葉剣英に配付していた。 他方、江青が楊成武を嫌った理由として挙げられているのは、上海や北京から報告されていた江青関係の資料(江青は30年代に女優であった当時の離婚問題をめぐる証拠を湮滅させるために、たいへん熱心であった)を楊成武が握りつぶしていたというものである。江青はこれを知って大いに怒り、林彪を証人にしたてて、自ら焼却させた。 いずれにせよ、この楊成武事件を経て、軍事委員会副主席たちの指導権はいっそう弱まった。たとえば葉剣英は「傅崇碧の黒幕」と非難されて、活動を封じ込められた。徐向前、聶栄臻らの立場も同じであった。 1968.3.25日、軍事委員会弁事組が改組され、黄永勝が組長、呉法憲副組長、メンバーは葉群、邱会作、李作鵬となった。 1968.9.5日、チベットと新疆自治区の革命委員会成立をもって、全国に革命委員会が成立し、奪権闘争の段階は一段落し、翌年4月、第9回党大会を迎える運びとなった。 |
| 【紅衛兵運動の暗雲】 | ||
|
W・ヒントンは清華大学における内戦さながらの100余日間の武闘を活写している。実権派打倒のためには彼らのエネルギーを利用した毛沢東は、頻発する武闘に手を焼いて、1968.7.28日早朝、これら五人の指導者を呼びつけ、引導を渡した。曰く、「君たちを弾圧している“黒い手”は実は私である」(『万歳』六八七頁)。 こういう過程を経て、1968.7、8月から紅衛兵への再教育が叫ばれ、次の毛沢東最新指示が繰り返された。
1968年末に毛沢東はこう呼びかけた。
文件にいう四方面のうち、3)工場鉱山と4)基層とは、秩序が混乱しており、新規労働力を受け入れる余裕はまるでなかった。そこで卒業生は事実上、1)農村と2)辺境に分配された。 下放運動がいかに絶対化されたかは、つぎの記事に一端が示されている。曰く、下放を望むか否か、労農兵と結合する道を歩むか否かは、毛主席の革命路線に忠実であるか否かの大問題である。修正主義教育路線と徹底的に決裂し、ブルジョア階級の“私”の字と徹底的に決裂する具体的な現れである(『人民日報』一九六八年一二月二五日)。 1968年、69年の二年間で約400万余りの卒業生(66~68年度、16~21歳)が農村や辺境に下放させられた。しかし、都市部の知識青年たちは現地でさまざまの問題に直面した。生活面では長らく自給自足の生活はできず、食糧(原文=口糧)、住居、医療などの面でとりわけ問題が大きかった。 |
| 【「8期12中全会」】 |
|
1968.10月、8期12中全会(党8期中央委員会第12回拡大会議)が開かれ、この時、劉少奇は「中国のフルシチョフ、中国最大の実権派」として攻撃された。決議では裏切り者、敵の回し者、スト破り(原文=叛徒、内奸、工賊)のレッテルを貼られて、永遠に党から除名され、党内外の一切の職務を解任された。鄧小平は党籍は保留されたが、一切の公職から追放された。劉少奇の冤罪に抗議して刑事処分を受けた者は2万8千人を超え、巻き添えになったり、批判された者の数は数えられぬほど多い(金春明「“文化大革命”論析」57頁)。 第三に劉少奇審査組は、劉少奇関係の全資料を会議に提示せず、康生、江青、謝富治らがデッチ上げた資料だけを提出した。しかもこの「罪状資料」は事前に毛沢東の承認を得ていた。こうして8期12中全会は劉少奇に対して「叛徒、内奸、工賊」のレッテルを貼り、党から永遠に除名した。この審議において当初は賛成の意志表示をしないものもあったが、批判されて最後には支持した。賛成しなかったのは陳少敏(1902~1977年、全国総工会副主席、八期中央委員)だけであった。彼女は投票に際して机に泣き伏し、挙手できなかった。その後彼女は残酷な迫害を受けた死亡した。そして劉少奇は名誉回復されるまで10年間、「中国最大の修正主義者」として対する名指しで批判され続けることになった。 劉少奇は8期11中全会以後も依然として政治局常務委員であったが、彼の経歴を審査する委員会を作ることがなぜ可能であったのか。劉少奇の妻王光美をまず落としたのであった。1966.12月、王光美専案組が作られた。これは名称こそ王光美であったが、実際にはその夫たる劉少奇の罪状をデッチ上げる組織となった。江青、康生グループはまず王光美をアメリカCIAのスパイとし、これに劉少奇を巻き込み、劉少奇=アメリカスパイ論を捏造しようとした。王光美はもと北京の輔仁大学学生時代に地下党員になったが、英語が得意であった。解放戦争の初期に国共双方の協議に基づいて北平(北京)に軍事調処執行部(代表葉剣英)が設けられ、王光美はそこの通訳となった。王光美はこうして解放区入りし、河北省平山県西柏坡で劉少奇と結婚した。だが、これを取り上げて康生は王光美スパイ説をデッチ上げ、劉少奇打倒と葉剣英打倒を狙ったという。 こうして王光美はアメリカのスパイ、劉少奇はアメリカ極東情報局代表であるとする報告をまとめたが、ズサンなため、この報告は党中央に送付されなかった。当初の劉少奇スパイ説が破産したので、劉少奇裏切り説に転換した。劉少奇は一九二五年春、上海から湖南に帰ったところで湖南省長趙恒慯に逮捕され、一月後に釈放され、湖南省境に追放されている。1929年満洲省委員会書記として、工作していたときも一度逮捕されたことがある。法廷闘争を通じて2カ月後に無罪釈放となった。 長年党内で幹部の審査工作を行ってきた康生は、これらの事実をもとに劉少奇をスパイにデッチ上げたのであった。白区工作において劉少奇と関係のあった者が偽証を強要されたが、拷問に耐えきれず発言した者のうち、カギになる偽証をしたのは、二人であった。一人は丁覚群で1927年当時武漢で劉少奇と工作をし、建国後は湖南省参事室の参事を務めていた。もう一人は孟用潜であった。彼は1929年に満洲省委員会委員となり、劉少奇書記のもとで奉天でストライキを指導して逮捕され、同時に釈放された。 1967.5月、彼は「隔離審査」され、偽証を要求されたが、一貫して拒否していた。ついに7.5日~13日の十数人による7.7日夜のつるし上げに耐えきれず、偽証を書いた。毛沢東は劉少奇の「転向」についての報告を当初は信用せず、全資料の提出を求めた。それらを点検した後、報告を承認し、かくて劉少奇冤罪が党中央によって決定された。 1966.8.5日に毛沢東が大字報を書いたのは「ブルジョア司令部」批判というイデオロギー問題、政治路線の問題であった。その当否はさておくとしても、文革の精神、あるいは毛沢東の真意からすれば、劉少奇は路線の誤りを自己批判すれば、それで済むはずであった。しかし、陰謀家たちは劉少奇の裏切り──転向という革命家にとって最大の汚点をデッチ上げた。毛沢東はこれらの偽証にだまされ、劉少奇追放を承認した形である。劉少奇は1969.11.12日、汚辱のなかで、惨死した。 劉少奇の遺骨の保管証にはこう書かれていた(朱可先ほか「最後の二七日間」『人民日報』1980.5.20日)。遺骨番号:123、保管申請者氏名:劉原、現住所:××××部隊、故人との関係:父子、死亡者氏名:劉衛黄、年令:七一歳、性別:男。つまり国家主席劉少奇は死去に際して、本名を名乗ることすら許されなかったのであった。 軍委副主席グループは指導権を奪われたが、軍内や大衆の間で依然、声望をもっていたが、8期12中全会でふたたび二月逆流批判が繰り返された。譚震林はすでに叛徒とされて、12中全会への出席を拒まれていた。陳毅、葉剣英、李富春、李先念、徐向前、聶栄臻ら6人は出席したが、それぞれ別の小組に配置され、つるし上げられた。このほか谷牧、余秋里も名指し批判された。 |
| 69.1月、手に負えなくなった全国の紅衛兵1500万人は、一斉に農村に「下放」されることになった。 |
| 【珍宝島事件―中ソ戦争の危機勃発】 |
|
1969.3.2日、珍宝島で中ソが武力衝突するという珍宝島事件が発生。別名ダマンスキー島事件とも言う。中ソは60年の援助条約破棄以来、小規模な国境紛争を繰り返してはいたものの、本格的な戦争まで発展することはなかった。しかし、この珍宝島事件によって、いよいよ中ソは戦争の危機を迎えた。 |
| 【第9回党大会】 |
|
1969.4.1-24日、三結合による大連合により奪権闘争が一段落し、北京で第9回党大会が開かれた。出席した代表は1512名、全国2200万人の党員を代表していた。この大会で、文革の勝利が宣言され、林彪が毛沢東の「親密な戦友であり後継者である」ことが確認された。大会決議に書き込むよう強調したのは江青グループであった。江青グループは、林彪グループと提携することで、「文革」の力強い後ろ盾としていた。林彪の後継者としての地位は、第9回党大会で採択された党規約のなかにまで書き込まれた。 こうして林彪グループは、軍隊を直接掌握するほかに、軍事委員会弁事組を通じて、そして軍事管制体制を通じて、中共中央と国務院の一部部門、一部の省レベル権力を掌握した。これに対して、江青を初めとする中央文革小組系は政治局には張春橋、姚文元、汪東興(毛沢東のボデイ・ガード、のち党副主席)を送り込んだものの、国務院や軍内にはいかなるポストも持たず、中央文革小組はもはや中共中央、国務院、中央軍事委員会と連名で通達を出すような地位を失った。江青グループがセクトとして、活動しうるようになったのは、1970.11月に中央組織宣伝組が成立して以来であり、これによって江青は再び合法的な活動の陣地を獲得したのであった。 第9回党大会で文革派が権力を掌握したが、これはいわば奪権連合であり、林彪派と江青ら“四人組”との間、そして周恩来グループとの間に深刻な権力闘争が発生した。第9回党大会以後は「権力の再配分」の矛盾が熾烈となった。9期2中全会で陳伯達が失脚し、葉群らが批判されたのは両者の権力闘争が爆発したことを示している。周恩来が党中央の日常工作を主持するようになり、1972年周恩来は極左思潮を批判しようとしたが、毛沢東は批判対象を「極右」だとして、これを妨げた。 |
| 【林彪グループと江青グループの隙間風】 |
|
林彪グループは、“四人組”をどう見ていたか。林彪グループの目から見ると単なるモノカキにすぎなかった。林彪派の「571工程紀要」は、自らのグループに対して銃をもつ者(原文=槍杆子)を自称し、江青らをペンを持つ者(原文=筆杆子)と表現していた。江青グループがモノカキの理論家中心であったことは確かである。そして、これはまさに文化大革命の初期、中期においては重要な役割を果たした。しかし毛沢東の支えを失ったときに一挙に瓦解せざるをえなかった。彼らは毛沢東の文革理念を論文にまとめる側近グループ、あえていえば皇帝毛沢東の宦官としての役割を果たしたのであった。 では銃をもつ宦官たる林彪グループとペンをもつ宦官江青グループの関係はどうであったのか。張雲生の「毛家湾紀実──林彪秘書回憶録」(邦訳『林彪秘書回想録』)は、興味津々の事実に溢れている。林彪の妻葉群はしばしば釣魚台一一号楼の江青宅を訪れ、密談しているが、林彪自身は江青に対して、かなりの警戒心を抱いていた。1967.2月には毛家湾で林彪と江青が激論していことを林彪秘書が証言している。 林彪は康生(中央文革小組顧問)を当初は警戒していたが、1968年初夏あたりから、林彪と康生の関係が改善された。これを陳伯達が嫉妬するようになったと林彪秘書が書いている。葉群自身は陳伯達に親しみをもち、「先生」と尊敬していたが、康生に対しては親しみよりは畏敬していた。陳伯達は康生の関係は必ずしもよくなかったが、葉群は極力バランスをとってつきあおうとしていた。 第9回党大会以後、毛家湾と釣魚台との関係はますます複雑微妙になった。互いに騙し合いこそすれ、譲り合うことはなくなった。政治的傾向としてはどちらかというと釣魚台に不利だったが、彼らは他の人々の近寄ることのできない特殊な条件(毛沢東夫人としての立場)をもっていると自負していた。 林彪グループと江青グループとは、文革を収拾し、第9回党大会を開く上では、結託したが、大会前後から仲間割れが生じ、1970.8月の9期2中全会の頃までには鋭く対立するに至った。この間の経緯は『林彪秘書回想録』に詳しい。表向きの論争テーマは憲法改正問題である。憲法のなかに毛沢東が天才的に、創造的に、全面的に、マルクス主義を発展させたとする三つの形容句をつけるか否か、国家主席を設けるかどうかなどがポイントであった。前者は毛沢東を天才としてもち上げることによって、その後継者としての林彪自身の地位をもち上げる作戦であり、後者は林彪が国家主席という名の元首となることによって、後継者としての地位を固めようとするものであった。 |
| 【林彪が「緊急指示」(一号通令)発令】 |
|
1969.10.17日、林彪は「緊急指示」(一号通令)を出して、戦時動員を命令した。鄧小平夫妻と鄧小平の継母は10.20日、南昌に送られ、数日後江西省新建県望城崗の福州軍区南昌歩兵学校に付設されたトラクター組立て工場に移され、以後3年余、ヤスリでネジを磨く作業を監視つきでやった。後には歯車を磨く作業もやらされた。65歳の老人にしてはきつい仕事であったろう。それまでは鄧小平の月給は月402元、妻卓琳のそれが165元、計565元であった。しかし1970.1月以後生活費として鄧小平120元、卓琳60元、継母夏培根25元、計205元が支給されるようになった。そこで鄧小平はパンダ印の煙草を止めて、安い前門印に切り替え、酒も普通の米酒に変え、時には自分でドブロクを作った。 鄧小平は北京で批判・闘争にかけられていた間、しばしば不眠症に陥り、昼寝前にミンルトン二片、夜の睡眠前にベンバヒト一片、スークーミン(速可眠)一片、眠爾通一片、非那根二片を飲む習慣であったが、1970年元旦以後、睡眠薬を飲まないと宣言し、これを断行した。林彪事件以後、江西省東郷紅星開墾場に送られていた王震(生産建設兵団司令)が北京に戻り、江西省で労働する鄧小平の状況を毛沢東に報告した。 |
1969年暮れ、劉少奇氏が、河南省開封で非業の死を遂げる。王光美夫人は獄中、子供達は離散していた。
1970.夏、りょ山会議。憲法改正問題のグループ討議で、国家主席存続の是非論が話し合われた。
| 【毛沢東と林彪グループとの隙間風】 |
|
1970.8.23日-9.6日、2中全会が廬山で開幕した。この頃、毛家湾と釣魚台との緊張関係が白熱したものとなった。「このバカ騒ぎの内幕はすでに世に知られたものよりもはるかに複雑である」と秘書が書いている。 8.31日、毛沢東は「私のわずかな意見」を書いて、陳伯達を名指し批判した。9.1日夜、政治局拡大会議が開かれ、私のわずかな意見が伝達され、陳伯達が批判されたが、この会議を主宰したのは皮肉なことに林彪であった。9.1日以後、各組で私のわずかな意見が学習され、陳伯達が批判され、呉法憲、葉群、李作鵬、邱会作の誤りも批判された。9.6日、2中全会が終わった。 こうして林彪の陰謀と野心に気づいた後、毛沢東は周恩来と協力して、林彪グループ批判に着手した。こうして2中全会を契機として、林彪グループの勢力が削減され始めたことは、江青グループの勢力を増大させることになった。
毛沢東が林彪への危惧を感じたのは、江青への手紙によれば、1967年夏のことだが、いまや林彪への不信は動かしがたいものとなり、その勢力を削減する措置を講じ始めた。 |
| 【林彪グループ「571工程紀要」=毛沢東暗殺計画に着手】 |
|
1971.2月、林彪グループは、3.21日を期して決起する「五七一工程紀要」の作成に着手した、と云われている。林彪派のクーデタ計画書「571工程紀要」なるものがどこまで正確なものなのかヴェールに包まれており真相は未だ分からない。 |
「571工程紀要」の内容が明らかにされていないので評しようがない。「571工程紀要」が存在するのか、漏れ伝わるところの内容なのか何も分からない。れんだいこは、それが存在するとして、その内容は伝えられているものと全く異なると思っている。但し、確かめようが無い。 2006.9.15日 れんだいこ拝 |
| 【キッシンジャーが北京へ忍者外交】 |
|
7.9日、キッシンジャーが北京へ忍者外交。極秘に北京を訪れ、周恩来との間に米中の和解について話をまとめた。頭越し外交で日本に衝撃。7.15日、「ニクソンが訪中し、中国首相・周恩来と会談する」と報道された。 |
| 【林彪グループ「571工程紀要」=毛沢東暗殺計画に着手】 | |||||||||
|
8、9月、毛沢東は南方を巡視した。彼は5大軍区、10省市の責任者と話をし、林彪とそのグループを名指し批判した。8月末に南昌に着くや、それまでは林彪にすり寄っていた程世清(江西省革命委員会主任、江西軍区政治委員)から葉群や林立果の異様な行動を報告され、警戒を深めた。 林彪グループは「毛沢東が南方を巡視する旅行中にを謀殺する陰謀を立て、これに失敗するや広州に独立王国をつくるべく画策していた」とされている。上、中、下、三つの対策を検討した。上策は毛沢東を旅行途中で謀殺したあと、林彪が党規約にしたがって合法的に権力を奪取するものである。中策は謀殺計画が失敗した場合、黄永勝、呉法憲、李作鵬、邱会作らと広州に逃れ、割拠するものである。下策は以上の両策が失敗した場合、外国に逃れるものである。 1971.9.5日、林彪、葉群は毛沢東が彼らの陰謀を察知したことに気づき、毛沢東謀殺を決定した、とされている。9.8日、林彪は武装クーデタの「手令」を下している。しかし、毛沢東は9.12日夕刻無事に北京に戻り、謀殺計画の失敗は明らかになった。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 【林彪の最後】 |
|
9.12日の経過はこう描かれている。9.12日、林彪は翌日広州に飛ぶべく飛行機8機を準備させようとした。当夜トライデント機256号が秘密裡に山海関空港に移され、北戴河で静養していた林彪、葉群、林立果が翌9.13日、広州へ飛ぶ予定であった。 林立果、劉沛豊は北京から256機を山海関空港に飛ばし、9時過ぎに北戴河の林彪の住まいに着いた。10時過ぎに翌朝出発することを決定した。林彪の娘林立衡は林立果から広州へ飛ぶことを知らされ、これを周恩来に密告通報した。すなわち9.12日夜10時過ぎ、林彪の娘林立衡からの通報は北戴河8341部隊を通じて周恩来のもとに届いた。周恩来は256号機を北京に戻すよう指示するとともに、追及を始めた。林彪事件処理に見せる周恩来の手際は鮮やかである。 林彪事件に対する周恩来の処理は、あまりにも的確であったために、かえってその後、さまざまな憶測がくりかえしあらわれることになった。秘密保持が徹底していたために、中国政府外交部でも党核心小組の符浩(元日本大使)らごく一部の者しか事情をしらなかった。実は許文益大使をはじめ、モンゴル駐在大使館の一人として、だれの遺体かをしらずにモンゴル政府と折衝し、遺体を現場に埋葬したとされている。 9つの遺体は林彪、葉群、林立果、劉沛豊、パイロット潘景寅、そして林彪の自動車運転手、専用機の整備要員3名であった。副パイロット、ナビゲーター、通信士は搭乗していなかった。このため、燃料切れの情況のもとで、平地に着陸しようとして失敗し、爆発したものと推定した。機内で格闘した形跡は見られなかった。 事件当時の林彪は64歳、毛沢東は78歳であった。14歳も若い後継者が権力の継承を待てなかったのはなぜか、である。金春明『“文化大革命”論析』は、林彪の健康問題から奪権を急いだと説明している。張雲生『林彪秘書回想録』もむろん健康問題に少なからず言及している。しかし林彪の健康問題について決定的な事実を指摘しているのは、厳家其、高皋夫妻の『中国文革十年史』である(香港版は上巻255頁以下、大陸版は251頁以下)。 林彪は戦傷を癒すために、「吸毒」(モルヒネ注射)の習慣があった。毛沢東はかねてこの事実を知っており、50年代に曹操の詩「亀雖寿」を書き贈り、戒めとするよう忠告していた。しかし、林彪秘書の記録によると、悪習はやまず、たとえば1970.5.20日、天安門広場の百万人集会で毛沢東声明を林彪が代読したが、これはパレスチナをパキスタンと読み誤るなどシドロモドロであった。これは当時は睡眠薬を過度に服用したためと説明されたが、実はモルヒネが切れたためではないかと示唆されている。毛沢東の親密な戦友にして後継者がアヘン中毒であったという事実は、やはりわれわれに衝撃を与えないわけにはいかないであろう。 |
| 【林彪グループの処分】 |
|
事件の伝達情況はつぎのごとくであった。まず、9.18日、中共中央は各大軍区、各省市、軍隊、中央各部門に対して文件を発出し、高級幹部に対して、林彪事件の概要を伝えたが、林彪についての記述、写真、映画などは暫時動かさないことも指示した。 ついで9.28日、中央は林彪事件の伝達範囲の拡大を通知した。10.6日、10月中旬に伝達範囲を支部書記レベル、軍隊の中隊レベル幹部まで拡大することを決定した。10.24日、全国の広範な大衆に伝達するが、新聞に掲載せず、放送せず、大字報やスローガンとして書かないよう指示した。12.11日、1972.1.13日、7.2日、中央専案組のまとめた「林彪反党集団の反革命クーデタを粉砕した闘争」についての三つの資料をそれぞれ発出した。 林彪の墜死以後、毛沢東暗殺を図った逆賊として、徹底的な林彪批判が展開された。その際の林彪の罪状は、彼の参加したほとんどすべての戦役について、林彪の功績が小さなものだと矮小化しようとするものであった。それらはそれなりになんらかの事実を踏まえたものであったことは、確かだが、およそ牽強付会が甚だしく、説得性を欠く批判であったといえよう。 墜死事件後十数年を経ると、行き過ぎた批判への軌道修正が行われるようになった。たとえばある論文(于南「林彪集団の興亡・初探」)は、前述のような林彪批判を斥け、次のように再評価して注目された。総じていえば、民主革命期(49年革命のこと)の林彪は、林彪グループのその他のメンバーも含めて、功績が誤りよりも大きかった。つまり林彪は文革初期に一部の者が誇張した姿とも、事件以後の批判論文が非難した姿とも異なっているのであり、林彪の功罪は実事求是のやり方で解釈すべきである、と。 1973.8月、第10回党大会の際に林彪、黄永勝、呉法憲、葉群、李作鵬、邱会作・解放軍総後勤部部長、陳伯達の党除名を決定し、公開批判を開始した。1981.1月下旬、最高人民法院特別法廷は黄永勝18年、呉法憲17年、李作鵬17年、邱会作16年、江騰蛟18年の懲役を判決した。 |
| 【毛沢東の落胆の様子】 |
|
毛沢東は1971年春から、病いに悩まされるようになったが、林彪事件以後、急速に老いこんだ。晩年を見守ったある女性秘書(張玉鳳は当初は「生活秘書」であったが、のちに「機要秘書」になった。一般には愛人と見られている)が、神格化された毛沢東ではなく、生身の人間としての痛々しい毛沢東の姿について、こう証言している。 このとき彼はすでに77歳の高齢であり、人々が想像するような元気溌剌では全くなく、髪は白く、明らかに老衰していた。人々がこの方に“限りないご長寿を”とどんなに祈ろうと、自然法則の発展には抗しようがなく、彼も普通の老人と同じく、老年のさまざまな疾病に悩まされていた。 われわれの国家指導者たちの身体状況は、なべて秘密にされている。毛主席の場合はなおさら厳しい秘密にされており、通常は極めて小さな範囲の者しか主席の病気を知らない。病気の程度を知る者はなおさら少なかった(『炎黄子孫』八九年一期)。 では病はどの程度であったのか。張玉鳳の証言が続く。71年春以来、気管支炎を患い、咳のため寝られず、日夜ソファに坐り続けるありさまであった。張玉鳳と看護婦長呉旭君が昼夜を問わずつきそった。1972.1.6日、陳毅元帥が死去し、10日午後、陳毅の追悼会が開かれた。毛沢東は突然時間を聞いて、パジャマ(原文=睡袍)の上からダブダブの人民服をはおり、50年代にソ連政府から贈られたジムに乗って八宝山に向かった。毛沢東はこの追悼会に出席したシアヌーク殿下を通じて、三カ月前の林彪事件を洩らし、「林彪は私に反対したが、陳毅は私を支持した」と陳毅を再評価し、同時に鄧小平復活を示唆したのであった。 1972.1月、毛沢東は肺炎と酸素不足のためにショックで倒れた。主治医が注射し、心臓専門家の胡旭軍が毛主席、毛主席と呼びつづけ、ようやく意識を回復した。1974年春から毛沢東は書類が読めなくなった。8月に武漢の東湖賓館で検査したところ、老人性白内障とわかった。1975.8月中旬のある夜唐由之医師が手術を行い、片目が見えるようになり、600余日の見えない状態から解放された。この間、張玉鳳が文件、報告、手紙などを読み、代筆した。元来はこの仕事は「機要秘書」徐業夫の仕事であったが、徐業夫が不治の病を得て入院したため、張玉鳳にその仕事が回ってきたのであった。 |
| 【林彪事件の謎】 | |||||||||||||||||||||||
| 1969.4月の第九回党大会で後継者に選ばれたばかりの林彪が一体なぜそのような事態に追いこまれたのか、今も謎である。 「第2節 文化大革命と解放軍」は、「林彪事件の真相その1・一九八八年に明らかになった事実」として以下のように記している。
事件当時外交部「党核心小組成員、弁公庁主任」であった符浩(ふこう・のちに日本大使)の回想によれば、周恩来の指示をうけつつ外交部内において極秘裡に事件の処理にあたり、モンゴルの中国大使館といかに連絡したかを概要次のように記録している。
符浩の記録は、最悪の事態展開を懸念しながら会議をつづけている席上へ、報告がとどき一同安堵する過程をリアルに描いており、サスペンス・ドラマの感がある。 当時のモンゴル駐在中国大使・許文益(きょぶんえき)のモンゴル当局との交渉記録は、軍用機の領空侵犯を非難するモンゴル当局に対して、許文益は中国「民航機」が進路をあやまってモンゴルにはいったものと主張し、両者は鋭く対立したこと。事件16日後の9.29日、モンゴル放送は中国「空軍機」の墜落を一方的に初めて報道し、世界がこの事件に注目することになった、ことを明らかにしている。 許文益の記録でなまなましいのは、中国大使館関係者が誰の遺体かを知らずに、モンゴルと交渉していたとする証言である。彼らは国慶節前夜になって「中共中央文件」をよむことができ、ようやく概要を知ったのであった。北京の中国政府外交部とウランバートルの中国大使館との緊急連絡は専用電話線でおこなわれたが、周恩来は秘密保持のために、大使にさえも真実を知らせていなかった。 林彪事件はあまりにも極秘裡に処理されたために、そのごさまざまな憶測をよぶことになったわけだが、最大のナゾのひとつは、墜死者のなかに林彪がいたかどうかであった。この疑問がうまれた直接的契機は外電が遺体のなかには林彪の年齢にあてはまる者がなかったと報道したことだ。林彪はモスクワで治療をうけたことがあるから、ソ連・モンゴル側が「確認しようとすれば」簡単に確認できたはずであるが、中国側関係者でさえ林彪事件などまるで知らずに処理したから、ソ連・モンゴル当局が林彪の歯形をとりよせる労をとらなかった。
埋葬現場には「中国民航1971.9.13日遭難九同志の墓、中華人民共和国駐モンゴル大使館」の墓標がある。旧ソ連解体後に明らかになった事実は、旧ソ連のKGBは二度にわたって遺体を掘り起こしていたことである。 このほか金春明の「<文化大革命>論析」は燃料タンクの構造の問題を指摘している。トライデント機は、翼と胴体下部に燃料タンクをもつ構造になっていたため、満タンにするとバランスが崩れる。そこで通常は離陸直前に満タンにしていたといわれる。これは1の燃料積込みの不十分な理由とかかわり、また3の着陸失敗の原因とかかわるものである。要するに、強行離陸のため十分な燃料を給油できなかったこと、副パイロットおよびナビゲーターの不在が不時着失敗の原因であったようだ。 1981.1.23日、中国の最高人民法院特別法廷はこう判決した。
これが林彪の「武装クーデタ」問題に対する中国当局の説明である。問題のポイントは林彪グループと江青グループの権力闘争である。林彪は毛沢東から江青への権力継承が成功するとは考えなかったが、その可能性が強まることを危惧した。他方、毛沢東から林彪への継承が毛沢東の生前に行われる可能性は全くないと判断して、江青グループの勢力が強まる前に毛沢東の謀殺をねらったというのが判決の説明である。 文化大革命をつうじて、実権派から権力をうばう段階では、緊密に協力しあった林彪・江青グループがポスト毛沢東の最高権力をねらってしのぎを削るという構図は、いかにもありそうなことであろう。ただ、理解に苦しむのは、すでに後継者として認知されていた林彪が毛沢東の死をまてなかったのはなぜか、である。この疑問に直接こたえているのが金春明の分析である。金春明は林彪の健康問題から説明している。 林彪は抗日戦争期に肺部を被弾し、ソ連に治療におこなったが、完治しなかった。解放戦争期に吐血したこともある。建国後は療養生活が長かった。一九五九年に彭徳懐の後を襲って国防部長に昇格し、軍事委員会を主宰したが、やはり大連、蘇州、杭州、北戴河などで療養することが多かった。天安門上に一、二時間立つ時は、何日も英気を養ってからというありさまであった。林彪は一九〇七年生まれ、一九七一年当時六四歳、当時七八歳の毛沢東よりも一四歳若かったが、毛沢東は七三歳のとき、揚子江を一〇数キロ泳ぐほど元気だった。そして林彪の健康問題を最も懸念していたのは妻葉群と息子林立果であった。 金春明はこのように林彪の健康問題からクーデタ事件の背景を説明し、説得的である。むろん張雲生『毛家湾紀実』は林彪の私生活を詳しく描写し、健康問題についてもすくなからず言及している。 続いて「林彪事件の真相その2・ 一九九四年に明らかになった事実」として次のように記している。
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)