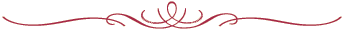
| 第4部 | 吉野ケ里遺跡考 |
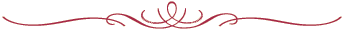
(最新見直し2012.08.18日)
| (サイト元が分からなくなったが転載しておく)
佐賀県神埼郡三田川町.神埼町 吉野ケ里遺跡の発見は、日本の歴史上最大の謎とされる邪馬台国、あるいは魏志倭人伝に記された二から三世紀の日本の状況を解く鍵を、遺跡の上で初めて具体的な形で、私たちの前に提供したといえる。その特徴は、弥生時代中期後半(前1世紀)の遺溝、特に巨大な墳丘墓を見せる時期と弥生時代中から後期(前1から後3世紀)の遺溝、日本の最大規模の環濠集落(まわりを大きな濠で囲まれた集落)との二つの時期から成り立っていることにあり、弥生時代後期は邪馬台国出現の時期とほぼ重なることに有る。地理的位置について 筑紫平野の一角を占める佐賀平野の東部、すなわち鳥栖市から佐賀郡にかけての背振山地南麓では多くの洪積世丘陵が発達しており、農耕のための良好な自然環境を盛っていた。その丘陵は高位.中位.低位の三種に分類され、丘陵の分布状態およびローム層の有無、その他の特徴から、鳥栖市付近、朝日山付近、神埼.三田川.中原地域、佐賀市北方地域の、四つの地域的特性が指摘されている。吉野ケ里丘陵は、これらのうち神埼.三田川.中原地域に含まれるが、この地域は、高位.中位の丘陵が山麓部から南の平野部へ舌状に細長くのびる地域である。これらの丘陵上には、姫方遺跡、船石遺跡、切通遺跡、二塚山遺跡、横田遺跡、三津永田遺跡など弥生時代の墓地を主体とする著名な遺跡が数多く立地する。吉野ケ里遺跡は、丘陵上すべてが甕棺墓地といわれる吉野ケ里丘陵の南部に位置する。地理的に自然の要害を為し、また生産力も豊かなこの地域を時の権力者が把握することは、内政的にも対外的にも重要な政治課題でもあったことと思われる。 ◎環濠集落について ◎墳丘墓について 近年の発掘で、この地域からも多くの青銅器、鉄器の異物が出土し、その中には銅鐸.銅剣.銅戈.円形銅器などの鋳型も含まれていて、この地域も又やはり弥生時代の北部九州の文化の中心地の一つであったことが伺われる。有る柄細い形銅剣が注目されており、この銅剣が出土した例は三例しかなく、佐賀県唐津市柏崎遺跡、福岡県糸島郡前原町三雲遺跡、山口県西端の向津久保遺跡とである。姫方遺跡、船石遺跡、切通遺跡、二塚山遺跡、昭和49年に発見された。吉野ケ里遺跡から、東へ約2km、三養基郡上峰村、神埼郡東背中振村、三田川町にまたがる丘陵地帯にある。背中振り山山地の南麓に位置している。 甕棺159基、土 墓89基、箱式石棺6基など、弥生中期から後期にかけての群集墓が見いだされている。副葬品として、前漢鏡や後漢鏡などの6面の青銅鏡、鉄刀2、鉄剣1、鉄矛1や、ガラス製の管玉や小玉などの玉類3800余が発掘された。この地域は、日本でも有数の青銅器出土地帯であるといえる。 佐賀県教委は、2000.10.26日吉野カ里遺跡から九州で初めて出土した銅鐸と、島根県宍道町に保管されている「出雲木幡家伝世銅鐸」が同じ鋳型を使って作られたものであることを確認した、と発表した。「出雲木幡家伝世銅鐸」は、島根県宍道町の木幡家が代々受け継ぎ、花器として使用されていたが60年に銅鐸と確認され、現在は八雲本陣記念財団が所有している。 横田遺跡 神埼郡東背中振村にある。 弥生後期の箱式石棺。1面の漢式青銅鏡多数の甕棺墓と箱式石棺墓からなる。副葬品として、3面の漢式青銅鏡、太刀1、鉄剣1が発掘された。、 三津永田遺跡 吉野ケ里遺跡の北東部、神埼郡東背中振村にある。 多数の甕棺墓と箱式石棺墓からなる。副葬品として、3面の漢式青銅鏡太刀1、ガラス製の管玉などが多数発掘された。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)