
| 第4部 | 「邪馬台国」比定諸説 |

更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).4.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「邪馬台国比定諸説」を検証する。「邪馬台国大研究」の「邪馬台国比定地一覧」が詳しいのでこれを参照する。邪馬台国比定を廻って、これだけ多くの諸説が為されていることに驚くであろう。「研究者の数だけ比定地があるという邪馬壹国説」と評されている。このうちの二大説は「近畿大和」と「筑後山門」である。問題は、両者ともが邪馬台国をして原大和王朝と位置付けていることにある。これでは歴史の真相に迫れまい。れんだいこ邪馬台国論によれば、邪馬台国は大和王朝に滅ぼされ史実からも抹殺された「幻の邪馬台国」であり、原大和王朝説の視点から邪馬台国を追うのは「虚妄の邪馬台国」でしかない。この観点から再検証することが求められているという観点が欲しい。 2006.11.29日、2009.2.23日再編集 れんだいこ拝 |
| 【畿内大和説】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畿内説(邪馬台国大和説)は大和説、奈良県説と重なる。奈良県説は桜井市三輪山麓、天理市、郡山、飛鳥に比定している。九州説ほど比定地が多くない。新井白石が「古史通或問」において大和国説を説いた。しかしのちに]「外国之事調書」で筑後国山門郡説に転じている。 畿内説(邪馬台国大和説)は次のような論拠に依拠している。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畿内大和説は専ら卑弥呼論で見解が分かれている。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【九州説】 | ||||||||
邪馬台国九州説は次のような論拠に依拠している。
|
||||||||
| (「第四章、邪馬台国時代の遺跡と遺物」)より転載 | ||||||||
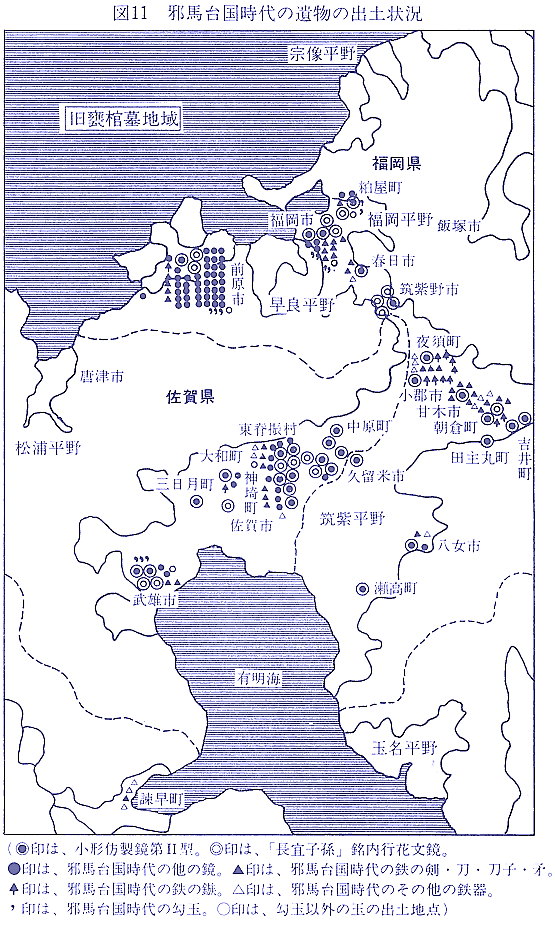 |
||||||||
| 九州説論者は次のように説いているようである。 | ||||||||
| 福岡県 | 福岡市博多一帯 | 久米邦武/筑紫国造説(「住吉社は委奴の祖神」)。 | ||||||
| 松本清張(巫女説)。 | ||||||||
| 古田武彦ら。 | ||||||||
| 北九州 (九州北部、北部九州) |
中島河太郎(巫女説)。 | |||||||
| 大谷光男。 | ||||||||
| 川野京輔(シャーマン説)。 | ||||||||
| 鯨清(天照大神説)。 | ||||||||
| 森浩一(豪族説)。 | ||||||||
| 井上光貞(「日本の歴史」)。 | ||||||||
| 和辻哲朗(「日本古代文化」で天照大神説)。 | ||||||||
| 藤間生大(「埋もれた金印」)。 | ||||||||
| 実吉達郎ら。 | ||||||||
| 北九州沿岸 | 大林太良(シャーマン説)。 | |||||||
| 筑後川流域 | 山村正夫(女酋巫女説)。 | |||||||
| 阿部秀雄ら。 | ||||||||
| 吉野ヶ里広域 (博多・吉野ヶ里・甘木朝倉に及ぶ) |
久保雅男/卑弥呼の墓を日吉神社の鳥居周辺に比定。 | |||||||
| 奥野正男ら。 | ||||||||
| 福岡県一帯 | 古田武彦ら。古田氏は「博多湾に臨む平野と周辺丘陵地帯」に比定している。 | |||||||
| 太宰府市近辺 | 松田正一 | |||||||
| 佐藤鉄章ら。 | ||||||||
| 筑後山門郡 (福岡県柳川市付近) |
奴国から筑後川を舟行し、この地へむかったとする説。 | |||||||
| 新井白石/神功皇后説(「外国之事調書」)。 | ||||||||
| 星野恒/田油津媛の先代説(「日本国号考」)。 | ||||||||
| 橋本進吉(「邪馬台国及び卑弥呼に就いて」)。 | ||||||||
| 津田左右吉(「邪馬台国の位置について」で一女酋説)。 | ||||||||
| 喜田貞吉/大和朝廷配下の九州の王説。 | ||||||||
| 村山健治/教祖族長説。 | ||||||||
| 吉田修/シャーマン説。 | ||||||||
| 榎一雄(「魏志倭人伝の里程記事について」)。 | ||||||||
| 牧健二(「邪馬台国問題の解決のために」)。 | ||||||||
| 田中卓。 | ||||||||
(福岡県久留米市御井町 高良山を中心とする筑後 川南岸付近) |
ここには高良大社が祀られ、それを取り囲むように城石が廻らされていて、この城域は高良山神籠石と呼ばれている。 | |||||||
| 筑後 福岡県久留米市御井町、三井郡 |
植村清二(「邪馬台国・狗奴国・投馬国」)ら。 | |||||||
| 筑後京都郡 | 重松明久ら(「邪馬台国の研究」)。 | |||||||
| 筑後田川郡 | 坂田隆(「邪馬一国の歴史」)ら。 | |||||||
| 築前博多(福岡県福岡市付近) | ||||||||
| 築前甘木 (福岡県甘木市・朝倉郡付近) |
筑後川北岸中心。安本美典氏が指摘していることの一つに、甘木市と大和の奇妙な地名の一致がある。甘木に住んでいた集団が大和に入ったことの証明になると云う。神話の「天の安河」と思われる「夜須川」もあり、日本書紀の神話が史実からの伝承である可能性も出てくる。天皇家が渡来系であるなら、朝鮮半島から甘木付近に入った後、大和に移住したことになる。 | |||||||
| 安本美典。 | ||||||||
| 村山義男/天照大神説。 | ||||||||
| 奥野健男。 | ||||||||
| 木村俊夫ら。 | ||||||||
| 朝倉郡 | 高倉盛雄 | |||||||
| その他筑前(福岡県瀬高町) | ||||||||
| その他筑前(福岡県鳥栖) | ||||||||
| 佐賀県 | 八女郡八女市 | 中堂観恵/日の御子説。 | ||||||
| 井沢元彦ら。 | ||||||||
| 筑紫平野 | 藤沢偉作ら。 | |||||||
| 長崎県 | 肥前島原(長崎県島原半島) | 宮崎康平。 | ||||||
| 肥前千綿(長崎県東彼杵町付近) | 野津清。 | |||||||
| 佐世保市 | 恋塚春男。 | |||||||
| 大村湾東岸 | 鈴木勇/天照大神説。 | |||||||
| 熊本県 | 肥後山門 (熊本県菊池郡小源村) |
伊都国から舟で玄界灘沿岸を西へ行き、長崎県西彼杵半島をまわって有明海に入ったとする説。 | ||||||
| 近藤芳樹/九州の一豪族説。 | ||||||||
| 白鳥庫吉。 | ||||||||
| 黛弘道ら。 | ||||||||
| 肥後玉名(熊本県玉名市付近) | 宮崎康平。 | |||||||
| 玉名郡江田村 | 古屋清/神功皇后。 | |||||||
| 阿蘇郡 | 藤井甚太郎/神功皇后説。 | |||||||
| 阿蘇神社周辺 | 渡辺豊和。 | |||||||
| 阿蘇郡蘇陽町 | 藤芳義男/百襲姫説。 | |||||||
| 下益城郡佐俣町 | 安藤正直ら。 | |||||||
| 人吉市 | 工藤篁。 | |||||||
| 山鹿市 | 鈴木武樹。 | |||||||
| 八代市 | 李鉦埼/インドの王女説。 | |||||||
| 東九州 | 石崎景三ら。 | |||||||
| 菊池川流域 | 岩下徳蔵/豪族の娘せつ。 | |||||||
| 大分県 | 豊前山戸宇佐 (大分県中津、宇佐八幡神宮付近) |
不弥国から舟で関門海峡を通り、豊前の海岸を南下して大分県宇佐市に入ったとする説。宇佐八幡神宮はその由緒により、後の大和朝廷時代に至っても一朝事あった際の神託のお告げを授かる地位にあったとする。卑弥呼の墓を宇佐八幡神宮に比定。 | ||||||
| 富来隆。 | ||||||||
| 久保泉。 | ||||||||
| 高木彬光(作家)。 | ||||||||
| 伊勢久信/神功皇后説。 | ||||||||
| 安藤輝国/応神天皇一族説。 | ||||||||
| 高橋ちえこ/巫女説。 | ||||||||
| 市村其三郎ら。 | ||||||||
| 宇佐神宮領地内 | 神西秀憲。 | |||||||
| 周防灘沖合海中(知珂島) | 大羽弘道。 | |||||||
| 別府湾岸 | 山本武雄。 | |||||||
| 中津市 | 横堀貞次郎。 | |||||||
| 宮崎県 | 日向地方 | 林屋友次郎。 | ||||||
| 延岡市構口 | 小田洋。 | |||||||
| 日向 | 尾崎雄二郎。 | |||||||
| 霧島山周辺 | 高津道昭/巫女説。 | |||||||
| 西都原 | 清水正紀/天照大神説。 | |||||||
| 西都市 | 原田常治/天照大神。 | |||||||
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 加治木義博/王仲殊。 | ||||||
| 霧島山一帯 | 霧島山南峰の高千穂峰は、神話の伝説峰として尊崇されてきており霧島山の南の麓にある霧島神宮は旧官幣大社であり、主祭神は邇邇芸命書紀では杵尊。霧島付近がなんらかの形で日本創世に関係が在ることは疑いない。霧島山の東方には、高原.高崎.高城、少し離れて高岡.高鍋などの地名がある。山の名前も高千穂をはじめ、高隅山.高畑山など高のつく地名が多く、これらは神話にでてくる高天原と無縁ではないように思われると為す。 | |||||||
| 薩摩・大隅国 (鹿児島県大隅半島。) |
鶴峰戊申/熊襲の女首長。 | |||||||
| 薩摩国・そお | 吉田東伍。 | |||||||
| 大隅国姫木 | 那珂通世。 | |||||||
| 九州南部 | 本居宣長/熊襲の女首長説。 | |||||||
| 奄美大島 | 小林恵子。 | |||||||
| 徳之島 | ||||||||
| 沖縄 | 木村政昭。 | |||||||
| 【四国説】 | ||
| 四国説論者は次のように説いているようである。 | ||
| 愛媛県川之江市一帯 | 大森忠夫(「邪馬台国伊予説」)。 | |
| 愛媛県松山 | 浜田秀雄(「切丹秘史と瀬戸内の邪馬台国」)。 | |
| 四国東半 | ||
| 徳島県 | 阿波国 | 古代阿波研究会/神功皇后説(「邪馬壱国は阿波だった」)。 |
| 岩利大閑ら。 | ||
| 徳島高根 | ||
| 四国山頂 | 大杉博/徳島県神山町山上を比定。卑弥呼の墓を八倉比売神社に比定。 | |
| 高知県伊野町 | ||
| 【中国地方説】 | ||
| 中国説論者は次のように説いているようである。 | ||
| 吉備 | 日差山 | 久保幸三/卑弥呼の墓を楯築遺跡に比定。 |
| 岡山・香川 | 広畠輝治/蒜山高原を高天原に比定。 | |
| 吉備津神社 | 薬師寺慎一/卑弥呼の墓を楯築遺跡に比定。 | |
| 熊山町 | 若狭哲六/卑弥呼の墓を熊山に比定。 | |
| 出雲 | 大川誠市。 | |
|
安芸
|
安芸郡府中村 | 多祁理宮(埃宮)、現在の府中町にある多家神社を中心とした地域であるとする。その根拠として、この地域は古の莵狭國の中心地であり、神武天皇はこの地の多祁理宮で亡くなっており、後世の厳島または宮島は「神ろぎ磐坂」として祭祀を厳修した社殿が存在したりする。 |
| 【その他地域】 | ||
| その他地域論者は次のように説いているようである。 | ||
| 大阪府 | 大阪市 | 大熊規短男(「神社考古学」)。 |
| 難波 | 泉隆弐(「邪馬台国の原点倭」)。 | |
| 京都府 | 京都府京都市 | 江戸達郎/神功皇后説。 |
| 滋賀県 | 近江説(琵琶湖畔) | 小島信一/神功皇后説。 |
| 野洲町 | 大内規夫/天照大神説。 | |
| 和歌山県 | 吉野から紀州一帯 | 立岩巌/神功皇后説(「邪馬台国新考」)。 |
| 北陸地方越前説 | 小島信一/神功皇后説。 | |
| 福井県 | 福井県鯖江市 | |
| 福井県福井市 | 八岐 大蛇/高志の国(福井県福井市)。同所の丸山古墳(直径縦150m、横100mの楕円形円墳)を卑弥呼の墓と比定している。 | |
| 石川県 | 石川県眉丈山 | |
| 石川県羽昨市 | 能坂利雄/能登ヒメ説。 | |
| 新潟県 | 新潟県栃尾市 | |
| 長野県 | 諏訪地方 | 武智鉄二/南シベリア族の女王説(「月刊歴史と旅」)。 |
| 山梨県 | 逸見高原 | 奥平里義/(「新日本誕生記」)。 |
| 東海地方説 | ||
| 静岡県 | 静岡県登呂 | |
| 南伊豆、下田 | 肥田政彦。 | |
| 旧東山道 | ||
| 千葉県 | 伊藤邦之(「邪馬壱国」)。 | |
| 総国(上総・安房) | 鈴木正知/巫女説(「邪馬台国に謎はない」)。 | |
| 福島県 | 会津若松市 (旧耶麻郡山都町) |
遠藤谷吉(「耶馬台国は耶麻郡だった」) |
| 【海外】 | |||
| ジャワ、スマトラ | 内田吟風/神功皇后説(「朝日新聞紙上」)。 | ||
| エジプト | 木村鷹太郎(「日本太古小史」)。 | ||
| 朝鮮半島 | 山形明郷。 | ||
| 【偽書説】 | ||||||
|
| 【折衷説】 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 【折衷変遷説】 | ||||||||||||
「横浜市 井上友幸」氏の「新説・日本の歴史第6弾邪馬台国の真相」を転載しておく。
|
| 【邪馬台国吉備説】 | |
若井正一(全国歴史研究会本部会員)「邪馬台国吉備説の提唱」。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)