
更新日/2018(平成30).9.21日
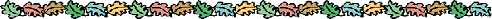
| 【明治天皇崩御】 |
| 同7.18日、明治天皇重体となる。7.20日、宮内省、「天皇陛下、尿毒症で重体」と発表。 24日、お見舞いに参内。7月28日、桂太郎ら訪欧使節団、天皇危篤の報を受け、急遽ペテルブルグを出発。
7.29日、明治天皇崩御(59歳)。皇族会議が開かれ発表を2時間遅らせる。 |
| 【嘉仁親王が大正天皇として即位する】 |
1912(明治45)年、34歳の時、7.30日、明治天皇崩御を受け、皇室典範第10条「天皇崩する時は皇嗣即ち践そし祖宗の神器を承く」に従い、皇太子嘉仁親王が34歳で践そ即位し123代皇位に就かれた(これにより、以下皇太子改め大正天皇ないし単に天皇と記す)。裕仁親王が皇太子となった。
その夜、「御政事向きのことにつき十分に申し上げ置くこと必要なり」として、首相・西園寺公望、山県有朋が大正天皇を訪問。まず西園寺が「十分に苦言を申し上げた」のに対して、天皇は「十分注意すべし」と返答している。だが山県は「僅かに数言申し上げたるのみ」であった。その理由として、天皇が山県を嫌っているという緊張関係が介在していた。
翌7.31日、朝見の儀が執り行われた。政府関係者の居並ぶ中、天皇皇后がお出ましになり、天皇が「朕今万世一系の帝位を践(ふ)み、統治の大権を継承す。祖宗の皇ぼに遵(したが)い憲法の条章に由り、これが行使を誤ることなく、以って先帝の遺業を失墜せざらんことを期す」と勅語を朗読。
年号が大正と改元された。改元の詔書として次のように宣べられている。
| 「朕(ちん)菲徳(ひとく)を以て大統を承(う)け、祖宗の霊に詰(つ)げて万機の政(まつりごと)を行ふ。茲(ここ)に先帝の定制に遵(したが)ひ、明治四十五年七月三十日以後を改めて大正元年となす。主者(しゅしゃ)施行せよ」。 |
ちなみに大正とは、五経の一つである「易経」の「大享以正、天之道也」、「春秋」公羊伝の「君子大居正」を出典としているが、公式には発表されていない。2002.3月に公開された「大正天皇実録」によれば、「大正」のほかに「天興」、「興化」の候補があり、枢密顧問が審議した結果、「易経」の「大享以正、天之道也」に由来して「大正」が選ばれたことが判明した。大正天皇の在位期間である1912(大正元).7.30日から1926(大正15).12.25日までの15年間が大正時代となる。 |
 (私論.私見) 「大正天皇の反軍的傾向考」 (私論.私見) 「大正天皇の反軍的傾向考」 |
| 即位に際して、山県有朋を嫌っている素振りを見せる大正天皇の性格ないし時代の緊張関係は注目されるに値する。 |
| 【元老勅語】 |
| 8.11日、桂太郎ら帰国。 8.13日、大正天皇は、明治天皇の遺業を継ぐにあたっての勅語を元老5名(山県、大山、桂、松方、後に西園寺)に対し下す。山県、大山、桂、松方、井上の5公候が元老の勅語を賜る。桂太郎が内大臣兼侍従長に任命される。この年の12.5日、西園寺公望(きんもち)が元老に加わり「最後の元老」となる。 |
| 【大正天皇としての窮屈な生活】 |
新天皇を待ち受けていたのは生活の激変であった。践そしてからは、午前6時起床、8時半には大元帥の軍服を着用、表御所に出御し、正午まで執務した。大正天皇は、皇太子時代のように思い通りの行動がとれなくなった。明治天皇との違いが早速現われることになった。大正天皇は規制を厭い、自由を述べられ、山県有朋ら元老らが何かにつけ「先帝を云々」するという日々が続くことになった。このために病気におかされ、体調を崩すことが多くなった。
大正天皇のこの頃からの変わり様について、秩父宮は次のように記している。
| 「父上は天皇の位に付かれた為に確かに寿命を縮められたと思う。東京御所時代には乗馬をなさっているのを見ても、御殿の中での御動作でも子供の目にも溌剌としてうつっていた。それが天皇になられて数年で別人のようになられたのだから」(「思い出の明治」)。 |
原武史・明治学院大教授は次のように評している。
| 「大正天皇は人間味豊かではつらつとしていた。天皇になってから、次第にバランスを失っていった。過度の自由を与えたことが悲劇につながった」。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「大正天皇は人間味豊かではつらつとしていた。天皇になってから、次第にバランスを失っていった」はその通りで、「過度の自由を与えたことが悲劇につながった」は余計な推理だろう。 |
|
| 【明治天皇の「大喪の儀」、乃木希典夫妻が殉死】
|
9.4日、天長節(天皇誕生日)だった11.3日を「明治天皇祭」と改める。 9.13日、明治天皇の御大葬が青山葬場殿で執り行われ、翌日、伏見桃山陵に奉葬する。(「明治天皇の「大喪の儀」」)。
乃木希典夫妻殉死。 大正天皇は、明治天皇に殉死した乃木希典陸軍大将を追悼する漢詩を3首詠まれている。「懐乃木希典」と題された漢詩「平生忠勇養精神 旅順攻城不惜身 颯爽英姿全晩節 淋漓遺墨々痕新」。これを見れば、大正天皇が漢詩に造詣が深かったことが判明する。9.16日、国民新聞に乃木大将の遺書が掲載される。
|
| 【大正天皇と明治天皇派の対立】
|
9.17日、天皇は原敬に対して、「当秋大演習に行幸のはずなるが、先帝の御時代には先帝だけの御事ありしも、今回はなるべく簡単にいたし、委細は侍従長に話し置くにつき打ち合わせよ」と述べている。原はこれを受け、山県の強引な政治工作により践そ直後に内大臣兼侍従長となっていた桂太郎に会い、「なるべく諸事簡単を望ませられ、又随いて行幸の御道筋も時々変更せらるる事あるべし」と天皇の意思を伝えている。
11.5日、明治天皇100日祭で京都・桃山行幸。天皇は、その際原敬を「汽車中にて御召しあり」、「両陛下の御前において種々の御物語をなしたり(先帝の御時代にはかくの如き事無し)」。これ以降、天皇の行幸の際に原が随行し、車中の話し相手を務めている。
11月10日、西園寺公望と山県有朋が朝鮮2個師団増設問題について協議するが決裂に終わる。11月11日、皇太子、海軍少尉として第1艦隊に赴任。
11.14日、川越、陸軍特別大演習統監。大演習の直前、天皇は念を押すように、「多人数御跡(おんあと)より付き添い来たるは面白からざるに付き、これを止むるよう」意見を述べている。しかし、この行幸随員を減らせよとの要望は叶えられなかった。道筋の変更も、取締り警備上非常に困難として認めなかった。こうした大正天皇の明治天皇とは異なる御意思が、軋轢を生んでいった。陸軍大将・山県有朋と海軍大将・山本権兵衛とは、前者が長州閥であり陸軍を代表し、後者が薩摩閥であり海軍を代表していたが、日頃何かと対立していたが、大正天皇を廻って気脈通じ始めている。
11.15日、大正天皇が陸軍特別大演習に、飛行機と飛行船が参加。11.17日、天皇、所沢に行幸し飛行機演習を観閲する。11.22日、上原勇作陸相が朝鮮二個師団増設案を閣議に提出。11.30日、閣議が、財政難を理由に朝鮮二個師団増設案を否決。
|
| 【大正政変】 |
1912(大正元).12.2日、上原陸相が二個師団増設否決を受けて辞表を提出。12.5日、第二次西園寺内閣が陸軍の二個師団増設問題をめぐって陸軍と衝突し、陸相の後継人事に陸軍の協力を得られず総辞職。12.7日、元老会議が松方正義を後継内閣に推挙。12.10日、松方正義が首相指名を辞退。12.12日、元老会議が平田東助を首相に指名。
12.17日、桂太郎に組閣大命。桂は、三度目の首相就任となった。斎藤海相、海軍充実計画延期に反対して内閣留任を拒否する。 12.24日、山県有朋暗殺未遂事件発生。
12.27日、桂首相、政友会切り崩しのため、新党結成を発表。 桂は自ら政党を作り、衆議院を支配する西園寺、原らの立憲政友会に対抗。議会停会の勅令や内閣不信任案決議案撤回を命じる勅語を次々と降下させ、政友会勢力を押さえ込もうとした。しかし、この強引なやり方が反発を呼び起こし、犬養毅や尾崎行雄を中心に「閥族打破、憲政擁護」を掲げた倒閣運動となる第一次憲政擁護運動が高まり、桂内閣打倒へと繋がる。
1913(大正2)年、35歳の時、1.19日、政友会と国民党が大会を開き桂内閣打倒を決議。 1.20日、桂首相が新党結成を発表。1.21日、桂首相が15日間の議会停会を宣言。1.30日、桂新党の結党宣言が行われ立憲国民党脱党者らを含め83名が参加する。2.5日、議会が再開され、政友会などが内閣不信任案を提出。尾崎行雄が弾劾演説。桂首相は5日間の議会停会を命令。
議会議事堂周辺に桂内閣糾弾の民衆数万人が集結。 2.7日、桂新党を立憲同志会とし国民党離党者らが合流。 2.8日、桂太郎が西園寺公望と会見し不信任案撤回を要請。西園寺がこれを拒否する。2.9日、大正天皇が、政友会総裁の西園寺公望に議会での政争緩和の勅諚を出す(西園寺違勅事件)。
2.10日、桂首相、内閣不信任回避のため議会3日間の停会を命令。これに反発した護憲派民衆が議会を包囲。また各地で暴動が起こり、警察署や政府系新聞社などを襲撃。軍隊が出動する騒ぎとなる。2.11日、桂太郎内閣総辞職する。これを大正政変と云う。 |
| 【大正元年の政変】 |
2.12日、 山本権兵衛に組閣の大命降下。2.19日、政友会が山本内閣支持を決議。国民党と決裂する。 2.20日、山本権兵衛内閣成立。 2.23日、尾崎行雄ら政友会の入閣反対派が政友倶楽部を結成。
7.17日、有栖川威仁親王の国葬を行う。
11.13日、名古屋で飛行機も参加して陸軍大演習を実施。 |
| 【大正天皇が体調を崩し始める】 |
1913年頃から、天皇は再び体調を崩すことが多くなった。1月に風邪をこじらせ、5月には肺炎にかかった。5.24日の東京朝日新聞は次のような記事を掲載している。
| 「陛下には御年14、5歳の御時一度肺を患い給い、その時には各侍医も殆ど匙を投げたくらいであったが、遂に御全快遊ばされた。その後、陛下は日に御壮健に赴かせられ、殊に近年は御健やかに御血色も殊のほか宜しきように拝し奉っている。これ東宮時代より北海道より中国地方(九州地方の誤り)に至るまで、御見学旅行を遊ばされたる為、自然に御運動の結果だろうと思われる。然るに昨年御践そ後、政務御多端にあららるるが為、遂に運動の御不足を来された結果でないかと拝察される」。 |
天皇は5月末回復し、6月より公務に復帰している。「明治天皇の後を継ぎ皇位についた後も、歩行障害により開院式に出席できず、言語障害のため勅語を朗読する事が困難であったとも伝えられている」が真偽不明であろう。この後、明治天皇時代にはなかった毎年夏の日光御用邸での長期避暑、冬には葉山御用邸への行幸が復活する。
この頃、漢詩「宮中苦熱」を詠んでいる。葉山御用邸から皇居に戻ると、釜の中にいる魚と同じで死んでしまいそうだといった内容を詠っている。
|
| 【山本権兵衛内閣が瓦解】 |
| 1914(大正3)年.35歳の時、1.22日、シーメンス社東京支店社員カール・リヒテルの恐喝事件判決が伝わる。日本海軍に対する贈賄の機密書類を盗み出し恐喝行為をしたというもの(シーメンス事件)。 1.23日、シーメンス事件の報道を受け、衆議院予算委員会で同志会の島田三郎議員が汚職について質問。1.28日、シーメンス事件を受けて海軍に査問委員会が設置。イギリス・ヴィッカース社の戦艦「金剛」発注に絡む収賄が発覚する。2.9日、シーメンス事件に関して沢崎寛猛海軍大佐を拘禁。
2.10日、シーメンス事件で国民党・同志会・中正会の野党3派が共同で衆議院に山本内閣弾劾決議案を提出。弾劾決議案は与党政友会の反対で否決。議会周辺で抗議の民衆と警官隊が衝突する。
2.10日、日比谷公園で内閣弾劾国民大会が開催され軍隊が出動する。2.12日、衆議院、海軍拡張費3000万円を削除して予算案を可決。2.25日、河野広中ら、警察官刃傷・民衆拘留事件で、原敬内相弾劾決議案を衆議院に提出。3.13日、貴族院、海軍拡張費をさらに4000万円削減し、計7000万円削減の予算案を決議。3.23日、同志会・国民党・中正会が内閣弾劾上奏書を衆議院に提出。議会3日間停会命令がでる。3.23日、貴族院、両院協議会を否決し、1914年度予算案は不成立となる。
3.24日、シーメンス事件(三井物産と海軍首脳との贈収賄事件)と予算案不成立の責任を取って山本内閣総辞職。 |
| 【第2次大隈内閣成立】 |
後継内閣の組閣は困難を極めた。2週間過ぎても新内閣が出来ないという異常事態となった。3.29日、元老会議、徳川家達を後継首相に推薦し、大命降下する。3.30日、徳川家達、首相就任を辞退。3.31日、清浦奎吾に組閣大命が下る。3.31日、シーメンス事件に関して、松本和呉鎮守府司令長官を収監。
4.7日、加藤友三郎、海相就任を拒絶し、清浦奎吾、組閣を断念。 4.11日、昭憲皇太后没。
4.13日、大隈重信に組閣大命降下。 4.16日、第2次大隈内閣成立。 大隈はしばしば天皇と面会したが原とは不仲であった。5.4日、第32臨時帝国議会招集(~8日)。5.11日、海軍人事大異動発令。山本権兵衛海軍大将、斉藤実海軍大将が、シーメンス事件の責任をとって予備役編入となる。
5.29日、海軍軍法会議、シーメンス事件で、松本和中将、澤崎寛猛大佐に有罪判決。 6.18日、原敬、立憲政友会総裁に就任。 6.20日、第13回臨時帝国議会招集(~28日)。
6.23日、大隈内閣、陸海軍軍備拡張計画の調整のため、防務会議を設置。6.26日、衆議院、軍艦建造費補充案を可決。 6.28日、貴族院、軍艦建造費補充案を可決。
|
| 【第一次世界大戦勃発】 |
| 8.14日、天皇、日光から還幸。御前会議を開き、ドイツに対する最後通牒の発信を決定。 8.23日、政府、ドイツに対し宣戦布告。 10.28日、大隈首相、貴族院・衆議院の両議員に対し、防務会議の結果を説明。陸軍2個師団増設、戦艦3隻、駆逐艦8隻、潜水艦2隻の建造計画決定という内容。
12.25日、衆議院で二個師団増設予算を否決したため、議会を解散。 1915(大正4).6.2日、衆議院、朝鮮2個師団増設案を可決。12.9日、大正天皇、上野公園に行幸し市民の大礼祝賀を受ける。
|
| 【皇太子裕仁親王が帝王学学ぶ】 |
| 1914(大正3)年、皇太子裕仁親王は、学習院初等科を卒業し、東宮御所構内に開設された東宮御学問所(総裁・東郷平八郎元帥、副総裁・波多野敬直宮内大臣)で、次代の天皇となる為の帝王学に専念されることとなった。日本中学校長の杉浦重剛が倫理を担当した。その他当代一流の学者が選任され、学業を補佐していくことになった。 |
| 【第一次世界大戦勃発、山県有朋と原敬の確執が演ぜられる】 |
| 1914(大正3).7.28日、第一次世界大戦が勃発した。この時大正天皇を輔弼していた山県有朋と原敬の確執が演ぜられ、悩みを深めさせた。山県は、専制君主的な名君論を説き、中国大陸への影響を強めていく方策を進言した。国際関係についてはアメリカとの対抗を基本としてロシアとの同盟が必要であるとしていた。原は、イギリス型の議会制的君主制論を説き、中国内政不干渉方策を進言した。国際関係については対米英協調を説き、とりわけ対米関係を重視していた。 |
 (私論.私見) 山県有朋と原敬の確執考 (私論.私見) 山県有朋と原敬の確執考 |
「山県有朋と原敬の確執」が伝えられており、それは事実であるが、「国際関係についてはアメリカとの対抗を基本としてロシアとの同盟が必要であるとする山県/国際関係については対米英協調を説き、とりわけ対米関係を重視する原」なる見立ては如何なものだろうか。真相は、「対米強硬派のようで実は国際ユダ屋の駒として使われている山県と国際協調派としての大正天皇派の原」の確執だったのではなかろうか。こう見ないと歴史の真相が見えてこまい。
2015.7.21日 れんだいこ拝 |
1915(大正4)年、36歳の時、2-3月、葉山御用邸での避寒が復活した。4.29日、大正天皇陛下が靖国神社の臨時大祭に参列。
| 【即位式】 |
| 1915(大正4).11.10日、昭憲皇太后薨去のため延期となっていた即位式が京都御所の紫宸殿で行われ、正式に新天皇となった。全国各地で派手なお祭り騒ぎが繰り広げられた。が、これについても即位式をなるべく簡素にするよう度々要望していたものの結局認められなかった。 |
| 【第四皇子・澄宮(すみのみや)崇仁(たかひと)親王(三笠宮)誕生】 |
| 1915(大正4).12.2日、第4皇子・澄宮(すみのみや)崇仁(たかひと)(三笠宮)ご誕生。皇后との間に皇位継承者を4名も授かった天皇は、歴代の中で大正天皇だけという記録を為している。 |
| 【大正天皇の内治主義的な御言葉】 |
1916(大正5)年、37歳の時、4月、畝傍行幸(神武天皇2500年祭)。
5月、東京で地方官会議が開かれ、全国の道府県の長官や知事が集まった。5.18日、宮中で午餐会が開かれ天皇が臨席。この時、皇太子時代の行啓時に顔見知りとなっていた笠井氏(東北巡啓時の岩手県知事、この時岡山県知事)に気軽に声をかけ感激させた旨伝えられている。
| 概要「岡山県の教育は如何に。貧民は如何に暮らせるや。汝の管内の産業の消長はどうであるや云々」。 |
|
| 【大隈首相と元老・山県との確執】 |
| この頃、大隈首相と元老山県の対立が進行している。山県は何かにつけ「先帝を云々」し、大隈は「先帝は先帝なり。今上陛下はその御考えによるべからず」として大正天皇を擁護した。この対立は、山県が大隈内閣を瓦解させ山県と同じ長州閥の寺内正毅内閣へと導き、大隈は加藤高明を推していくことになる。この一部始終に対し、大正天皇は反山県の立場を取りつづけている。 |
| 【裕仁親王が皇太子となる】 |
| 1916(大正5).11.3日、迪宮(みちのみや)/裕仁(ひろひと)親王、満15歳の時、立太子礼により皇太子に就任する。 |
| 【政党政治に反対する山縣有朋との抗争、角逐】 |
| 1917(大正6)年、立憲政友会などの政党政治に反対する山縣有朋への反感から枢密院議長の辞任を迫り、寺内内閣がそれを押しとどめる事件も起きている。大正天皇はこの頃より心労が重なり始め公務を休むことが多くなった。
|
| 【皇太子裕仁と皇族/久邇宮良子(ながこ)との婚約が内定】 |
| 1918(大正7)・1.17日、皇太子裕仁と皇族/久邇宮良子(ながこ)との婚約(翌年6月に正式の婚約)が内定した。良子が東宮妃に選ばれたのは、貞明皇后(節子)の強い希望によっていたと伝えられている。6.10日、婚約勅許の正式発表が行われている。久邇宮良子(ながこ)女王の生母・俔子(ちかこ)は最後の薩摩藩主・島津忠義(ただよし)の娘であり、久邇宮良子(ながこ)女王は久邇宮(くにのみや)邦彦王と俔子(ちかこ)夫妻の長女である。さらに忠義は維新の大立者・島津久光(ひさみつ)の息子であった。
|
| 【米騒動】 |
| 1918(大正7)年、39歳の時、7月、富山県で起った米騒動が全国に波及。大正天皇はこれを憂慮して東京府知事に情報収集を命じたりするなど、日々の公務に機動的な対応を見せている。 |
| 【政友会の原敬が、近代日本最初の本格的な政党内閣を組織】 |
1918(大正7).9月、寺内内閣が総辞職。それまで国政をリードしてきた藩閥官僚勢力に替わって、政友会の原敬が、近代日本最初の本格的な政党内閣を組織することとなった。
大正天皇にとって実懇の原敬の首相としての登壇は慶事であったが、この頃から次第に体調は悪化の一途を辿り、10年10月には宮内省も容体回復が難しい事を示唆した。議会開院式への出席が困難な状況に陥っていた。
1918(大正7).10.31日、39歳の時、天長節観兵式を風邪を理由に欠席。11月、原の日記に天皇の病気を憂慮する記述が俄かに増えていく。
|
| 【大正天皇と皇太子が軍事演習親閲】 |
| 1919(大正8)年、40歳の時、5.2日、大正天皇陛下、皇太子殿下(後の昭和天皇)が靖國神社鎮座五十年記念祭に参列 。5.7日、40歳の時、裕仁皇太子成年式。5.9日、東京奠都50年祭出席。10月、海軍特別大演習 横浜で御召艦・戦艦「摂津」に乗艦 洋上にでて演習を統制。演習終了後、横浜沖で特別大演習観艦式を親閲。11.9日、兵庫大阪陸軍特別大演習に皇太子とともに出席。 |
12.5日、清水澄(とおる、1868-1947)の第60回法学講義。この後の講義記録が見当たらない。皇太子教育に移行していると考えられる。
| 【大正天皇が、帝国議会開院式への臨席中止事態発生】 |
1919(大正8).12.26日の第42回帝国議会の開院式への臨席も中止となった。理由付けとして、「まことに遺憾の次第であるが、数日来、勅語朗読を練習したものの、なにぶんにも御朗読は困難で云々」とされている。「原敬日記」によると、食事を摂ることも勅語を読むこともできなくなるほど病状は悪化していた。勅語などを読み上げる間に集中力が途切れて、途中で黙り込むことがあったという。この年の8.31日の天長節式典でも簡単な勅語をきちんと読み上げることができなかった。この日の第42帝国議会開院式、翌1920年の新年祝賀、2.11日の紀元節式典を欠席している。
内大臣・松方正義公爵と宮相・波多野敬直男爵が原敬首相に伝えている。以後、大正天皇は他の公式行事にも出席されず、大正9年を迎える新年の儀式、紀元節の宴席にも姿を見せず、ようやく国民の間に「天皇御不例」の様子が広がっていった。 |
1920(大正9)年、41歳の時、4.29日、皇太子殿下(昭和天皇)、閑院宮載仁親王(大正天皇御名代)、閑院宮載仁親王智恵子妃(貞明皇后御名代)が靖国神社の臨時大祭に参列。5.15日、貞明皇后陛下が靖国神社に行啓。
| 【大正デモクラシー運動活発化する】 |
| 1920年頃より、東京市内の各所で普通選挙の促進を求めるデモが為されるようになった。5.2日、日本最初のメーデー。6.6日、3万人の市民が演説会。民衆運動が高まる。 |
| 【皇太子裕仁の摂政就任の動きが具体化し始める】 |
1920(大正9)年、6月この頃から、皇太子裕仁の摂政就任の動きが具体的に動き始めた。これについて最初に言及したのが内大臣・松方正義公爵内大臣で、原首相に摂政設置提案が為されている。皇室典範第19条「天皇久しきにわたるの故障により大政を親(みずか)らすること能わざるときは、皇族会議及び枢密顧問の議を経て摂政を置く」の規定に基づき、裕仁皇太子の摂政につき検討するよう提議している。
これに対する原の見解は、「遂に摂政を置かるる必要に至らん事と恐察するもそれまでにはたびたび御様子を発表して国民に諒解せしむるの必要もこれあるべし云々」と答えている。注意すべきは、摂政を置く必要があるという事態の認識では一致していたが、心身症的理由によるもので「脳の病気」的観点は見られないことであろう。 |
10.23日-25日、御召艦「摂津」に於いて千葉県館山沖で海軍特別大演習を統裁している。10.28日、特別大演習観艦式のため、横浜に行幸。10.31日、天長節観兵式で雨に濡れながら閲兵。11.9日-19日、陸軍特別大演習統裁のために兵庫県須磨、明石に行幸。この時、18歳の皇太子裕仁親王が始めて参加した。大阪府伊丹に行幸。京都で諸陵を参拝。11.25日、海軍大学校などの卒業式への行幸を中止。12.26日、帝国議会開院式を欠席。「勅語朗読が数日間練習しても困難であったため、行幸できなかった」とある。
| 【大正天皇の病状が発表される】 |
1920(大正9)年、41歳の時、3.26日、東京大学教授三浦謹之助が、「幼小時の脳膜炎のため(中略)緊張を要する儀式には安静を失い、身体の傾斜をきたし、心身の平衡を保てない」とする診断書を提出している(林栄子「近代医学の先駆者 三浦謹之助」 pp.211、叢文社、2011年)。
3.30日、第1回病状発表される。4.9日、「聖上には当分御静養の必要上、御座所に於いて政務を*はせらるるの他は一切公務の御執務あらせらざる事に御願いする事」、「今後は内外人の拝謁等も表向きには聖上の出御なかるべく、必要やむをえざるの場合には皇后皇太子代わってその御役を勤めさせ給う事」が決定された。5.2日、葉山御用邸から還幸。6.16日-7.17日まで沼津御用邸で静養。7.27日ー9.16日まで日光田母沢邸で避暑。この間の7.24日、第2回病状発表。「御倦怠の折節には御態度に弛緩を来たし、御発語に障害起こり、明晰を欠く事偶々これあり」。この発表の直前に、宮内大臣が波多野氏から中村雄次郎氏に交代している。 |
| 【皇太子裕仁(ひろひと)親王の「宮中某重大事件(婚約解消問題)」が発生】 |
| 1920(大正9)年夏から秋頃、皇太子裕仁(ひろひと)親王の后問題が発生している。既に婚約勅許の発表までされていた良子の家系的色盲遺伝の恐れが問題にされ、元老・山県、時の宮内大臣・波多野敬直らが火種元となった。これを首相の原敬が支持し、元老の西園寺公望も同調した。山県は首相原敬と相談して,専門医師の調査書をもとに元老西園寺公望らとも協議の末,久邇宮家にやんわりと辞退を迫った。これに対抗したのは東宮御学問御用係の杉浦重剛とそれに繋がる玄洋社の頭山満、黒竜会の内田良平、北一輝らであった。政界が日増しに騒然と化していった。この一連の経過が「宮中某重大事件」と云われている。 |
| 【大正天皇の帝都不在続く】 |
| 1920(大正9).12.23日-1921(大正10).4.12日、葉山御用邸での避寒療養。5.17日-6.22日、沼津御用邸で療養。7.15日-22日、塩原御用邸。7.22日-9.21日、日光田母沢邸。天皇の帝都不在が続いている。 |
| 【皇太子裕仁(ひろひと)親王の渡欧が決定される】 |
1921(大正10).2.8日、皇太子裕仁(ひろひと)親王の渡欧が決定された。2.10日、宮内相から、先に御婚約が成立している九に宮家の良子(ながこ)妃との御成婚に変更がない旨の発表が為された。ここにさしもの騒動も一件落着し、山県は責任を取って元老を辞任した。宮内大臣の中村雄次郎が辞任し、薩摩出身で大久保利通の次男に当る牧野伸顕が就任した。
牧野の登場は、大正天皇の「押し込め」への動きを加速させた。「脳膜炎ようの疾患」なる表現が公然と使われるようになり、幼少時よりの宿亜のものであるとして「やや赤裸々に御様態の公表」が為されていくことになった。
|
1921(大正10)年、42歳の時、4.29日、貞明皇后陛下、東伏見宮依仁親王(大正天皇御名代)が靖国神社の臨時大祭に参列。
| 【メディアが皇太子のプロパガンダに乗り出す】 |
7.24日の第2回病状発表、皇太子の外遊正式決定後より、マスメディアが一斉に皇太子をプロパガンダし始めた。新聞社に加え活動写真各社による皇太子の動静を伝える報道が為され始めた。皇太子の外遊のご様子もタイムリーに知らされ、東京の日比谷、上野、芝公園、その他各種会館、歌舞伎座で多数の市民を集めて観覧された。この動きが地方にも広がっていく。
注意すべきは、「東京で皇太子の実像が上映された場所の多くが、日比谷公園や上野公園、芝公園など、普通選挙の実現を求めていた民衆運動の拠点であったことである」(原、「大正天皇」)。 |
| 【皇太子裕仁(ひろひと)親王が半年間の欧州歴訪の旅に出発】 |
| 1921(大正10)..3.3日、皇太子裕仁(ひろひと)親王は、戦艦「香取」に乗船し、横浜港から半年間の欧州歴訪の旅に出発、外遊している。「それまで籠の鳥だった私が初めて自由を知った」と後年回想されている。その後の動きから見て、皇太子裕仁の欧州外遊は、摂政就任の準備行為で、広く外国の空気に接し、皇統としての心構えを早急に身につける必要から企図されたものであったと推定される。
訪問先はイギリス、フランス、ベルギー、オランダ、イタリア(バチカン含む)の欧州5カ国、日本の皇太子が外遊するのはむろん初めてのことであった。艦上には供奉長として随行した外交界の重鎮、珍田捨巳(メソジスト派)、山本信次郎海軍大臣(カトリック)、そして澤田節蔵(クエーカー)の日本のクリスチャン・エリートが勢揃いしていた。バチカン訪問をねじ込んだのは山本信次郎だと云われている。奈良、入江、澤田も供奉していた。(萬晩報通信員・園田義明氏の2006.10.6日付け「萬晩報、薩長因縁の昭和平成史(4)」参照)。
3月、東宮御学問所が閉校されている。
|
| 【大正天皇のより詳しい病状が発表される】 |
4.16日、第3回病状発表。この頃から風説として大正天皇の「脳の病気」説が流され始めた。5.31日、原の日記に「9月の皇太子の帰国後、速やかに皇太子を摂政にすることで山県と合意」とある。5月から8月末日までに、原首相や山縣元老を中心に根回しが行われ、政府内の了解が固まった。9.3日、皇太子帰国。9.8日、日比谷公園で皇太子帰朝奉祝会が開かれ、約3万四千人が集まる。この時、東京市長の後藤新平が皇太子に捧げる「奉賀」を読み上げている。9.13日、平安神宮で皇太子帰朝京都市奉祝会。
10.4日、宮内省が「快方に向かう見込みがない」旨の第4回病状が発表された。大正天皇のより詳しい病状が発表され、この時初めて病気が幼少時の「脳膜炎ようの疾患」によると言及された。これを機に各宮家からの了解を取り始めた。10.10日、元老松方正義公爵が摂政設置を皇后に内奏、10.11日、皇后の承諾を得、続いて10.27日、松方内大臣が当時20歳だった裕仁親王に摂政設置を言上して御承認を得ている。この時、皇太子が「令旨(りょうじ)」を読み上げ、熱狂されている。
11.16日、神奈川東京陸軍大演習を皇太子が統監。この時も、皇太子が「令旨(りょうじ)」を読み上げ、万歳三唱で熱狂されている。 |
| 【原敬が東京駅で暗殺される】 |
1921(大正10).11.4日、原敬が東京駅で暗殺される(65歳)。原敬の暗殺は、大正天皇支持基盤を瓦解させることになった。(翌年2.1日、山県が病没する。84歳)
政治状況は変わったが、摂政設置スケジュールは何の変更もなく、牧野宮相は、裕仁皇太子に天皇の病状と、摂政設置は20日に終わる陸軍特別大演習の直後に行いたい旨、進言している。
|
| 【摂政設置、皇太子の摂政就任スケジュールが動き出す】 |
| この頃、牧野伸顕宮内大臣が、摂政設置やむなし、時期は皇太子が外遊から帰って後のできるだけ早い機会に、ということになった。10月頃より摂政就任スケジュールが動き出している。
帰国後一気皇太子摂政の動きが強まった。但し、当の大正天皇は強く拒否している様子が伝えられている。引退推進派の宮内大臣牧野伸顕日記によると、摂政を置くことを奏上しても、「聖上陛下には、ただだアーアーと切り目切り目に仰せられ、御点頭遊ばされたり」とある。しかし重大な要件なので、改めて宮内大臣・牧野と内大臣・平田東助より同じ説明をしたところ、「恐れながら、両人より言上の意味は御会得遊ばれざりし模様と両人とも拝察し奉りたり」(1921.11.22日)とある。
11.20日、「宮中重要会議」が近い事が新聞報道される。11.22日、議題が皇室典範の摂政に関する条項に関連すること、24日には議題が「皇太子殿下の重大御任務」であることなど、間接的表現で皇太子の摂政就任が近い事が報道された。
|
| 【皇太子裕仁(ひろひと)親王が摂政に就任】 |
| 1921(大正10).10.25日午前11時、皇太子を議長とする皇族会議が開かれ、摂政を置くことを満場一致で可決。「朕久しきにわたるの疾患により大政を親(みずか)らすること能はざるを以って、皇族会議及び枢密顧問の議を経て、皇太子裕仁親王摂政に任ず」との大詔を受ける形で、東宮(皇太子裕仁親王→昭和天皇)がその職に就く事が議決された。続いて午後1時、枢密顧問が開かれ、満場一致で裕仁親王の摂政就任が了承された。枢密院会議が午後2時に終了した直後の午後2時30分、天皇は詔書を発し、皇太子裕仁親王を摂政に任命した。以降、皇太子が公務を代行することになり、大正天皇は実権を完全に喪うに至り、一線を退くことになった。(原死去の直後、皇太子の摂政就任となる)
|
| 【大正天皇の病状経過が同時発表される】 |
この時、宮内省から大正天皇の病状経過として次のような発表が為されている。第5回病状発表。
| 「天皇陛下は御誕生後間もなく、脳膜炎様の御大患に罹らせられ、その後病患多く云々」、「御壮年期に入らせたまいたるにより以来12、3年間は格別の大病も無く、動作も活発になった。然るに天皇になってからは政務の多忙によって心労が重なったのか、大正3、4年ころより起居が以前のようにならず、姿勢は端正を欠くようになり、歩行が安定せず、言語も渋滞をきたすようになった」。 |
11.26日付け東京日日新聞を参照すれば次のように報道されている。
| 「大正8年以後は万機御親裁あらせらるる外、帝国議会の開院式にも臨御あらせにれず、御避暑、御避寒の期間はこれを延長し、務めて御静養あらせたまうも、御軽快に向わせられず」、「御脳力は日をおいて衰退あらせらるるの御容態を拝するに至れり。しこうして御姿勢その他外形の御病状も末梢機関の故障より来るものにあらず、すべて御脳力の衰退に原因し、御脳力の衰退は御幼少の時御悩み遊ばされたる御脳病に原因するものと拝察することは、拝診医の一致するところなり」。
|
別文では、意訳概要「天皇陛下におかせられては、記銘、判断、思考らの諸能力が漸次衰へさせられ、殊に記憶力に至りてはご衰退の兆し最も著しく云々」(宮内省公表文「聖上陛下御容体書」)と記されているのもある。
原敬日記によってもこのことは次のように裏付けられている。
| 概要「(御位後4、5年目で体調が勝れなくなり、)御心神に幾分かご疲労の御模様あらせられ」、要約概要「実に恐懼に堪へざる事ながら、御年を召すに従て御健康に御障あり。就中(なかんずく)御朗読ものに御支障多く、既にこの間の天長節にも、簡単なる御勅語すら十分には参らず、臣下として、殊に余当局として、国家皇室の為に真に憂慮しおれり」(大正8.11.8日付け原敬日記)。 |
この経過に少し疑問が発生する。この宮内省発表文に拠れば、逆に、大正天皇は親王時代も含め結婚した20歳から即位するまでの32歳頃までの皇太子時代には元気であったことが読み取れる。この実像研究について、原武史著「大正天皇」(朝日新聞社・平成12.11月刊)が克明な調査で、「髄膜炎によって病弱で影が薄かった説のベールを剥がして、行動的で活発、多弁な全く別人のような大正天皇像を明らかにしている」。
特に、精神状態に問題あり説の最大の根拠とされてきた「遠眼鏡事件」についても、最近になって次のような真相が明らかにされている。
| 「(大正天皇から直接聞いたというお付きの女官証言によれば)、ある時、議会で勅語が天地逆さまに巻きつけてあったので、ひっくり返して読み上げ、随分恥ずかしい思いをした。このようなことがないよう、詔書を筒のように持って中を覗いて間違っていないことを確かめて読み上げようとしたものだ」(平成13.3.14日付け朝日新聞)。 |
大正天皇の出生以来の病歴が別途発表された。このため、後々にも「病弱な天皇」として一般に認識されることになった。 この後、大正天皇が政務に復帰することはなかった。 |
| 【大正天皇が皇太子摂政に不快を表明す】 |
11.22日、牧野は内大臣の松方と天皇に会い、皇太子の摂政就任を告げている。この時の大正天皇の様子が次のように記されている。
| 概要「誠に恐懼限りなき事ながらこの段申し上げ御許しを願い奉る旨言上に及びたところ、天皇は、ただあぁあぁと切り目切り目に仰せられ、御点頭遊ばされた。恐れながら両人より言上の意味は御会得遊ばされざりしよう我々両人とも拝察し奉り」。 |
| 「今日松方とともに御前に伺候し、摂政を置かるべきことを奏したるもついにご理解あらせられず。まさに退かんとする時、松方を呼び留めたまいたるも、御詞は全く上奏に関係なきことなりしなり。実に畏れ多きことなり」。 |
|
| 【大正天皇が強制的に閉居させられる】 |
大正天皇は、この強制的引退に抵抗した模様である。11.25日、侍従長・正親町(おおぎまち)実正が天皇の使う印鑑を摂政に渡したいと取りに行くと、天皇は不快感を露にし、いったんは拒んだ。その後、侍従武官長が天皇の元に出ると、「さきほど侍従長はここにありし印を持ち去れり」と云ったという(四竈孝輔(しかまこうすけ)「侍従武官日記」)。
原氏は云う。
| 「天皇は自らの意思に反して、牧野をはじめとする宮内官僚によって強制的に『押し込め』られたというのが私見である」。 |
|
| 【大正天皇の女官の肉声、摂政めぐる対立詳細に】 |
2019.5.3日、「 大正天皇の女官の肉声、摂政めぐる対立詳細に」。
歴史的な資料の発見です。およそ100年前、大正天皇と貞明皇后に仕えた女官の肉声を収めたカセットテープをJNNが発見しました。大正天皇の人柄や昭和天皇が摂政についた際の宮廷内の対立が語られていました。「陛下のお毒見しますでしょ。魚ならこんなひと切れとか」。女官は坂東登女子さん、通称「椿の局」と呼ばれ、大正天皇と貞明皇后の最側近として仕えていました。JNNが発見したテープは、方言を研究する山口幸洋さんが1976年に録音したもので、音声が公開されるのは初めてです。「お上(大正天皇)は天才的。お教えせんでもちゃんとお素読あそばした。あんまりおつむさんが良くって、お体がお弱くあらっしゃったんでしょう」(椿の局の肉声)。テープには、皇太子時代の昭和天皇が大正天皇の摂政についた際、宮廷内で起きた対立の様子についても収められています。「大炊御門さん(侍従)なんか、摂政を置くのに反対だった。御寿命が短くてもええで、陛下のままで終わらし申したいと」(椿の局の肉声)。近現代の天皇制について研究する原武史教授は、非常に貴重な録音だと話します。「まさか肉声が、こういう形で残っているとは想像もしなかった。昭和天皇が摂政になった際に、宮中がぎくしゃくした関係になった。裏側に一体何があったかまで、必ずしも明らかになっていないが、その裏側の話が椿の局の証言から浮かび上がってくる気がする」(放送大学
原武史教授)。
|
|
| 【皇太子の巡啓、行啓再開する】 |
| 1922.7月、裕仁皇太子は巡啓、行啓再開し、北海道を訪問する。この時、注目すべき変化が起っている。大正天皇の皇太子時代の時と比べて、「日の丸を振り、最敬礼して君が代を斉唱し、万歳を叫ぶ」というその後敗戦時まで続く光景のひながたが現出している。この「規律と秩序を重んじる政治空間」が、全国レベルに波及していくことになる。 |
| 【その後の大正天皇の御姿ぶり】 |
| 以降、崩御までの5年間を、天皇は葉山や日光、沼津の御用邸を行き来し、幼い崇仁親王と遊んだり、葉山では岩崎家の別荘や油壷の臨海実験所などを見学している。毎晩のように2時間ほど四竈らを相手にビリヤードを楽しんでいた。脳に障りのある人ができる競技ではない。 |
| 【第6回病状発表】 |
| 1922(大正11、43歳).10.7日、第6回病状発表。 |
| 【関東大震災】 |
| 1923(大正12、44歳).9.1日、関東大震災が発生し、焼失家屋24万戸、崩壊家屋2万4千棟、死者5万9千人の被害が発生した。これにより関東一円の商工業地区が壊滅的大打撃を受けた。被害総額は約100億円(当時の一般会計の6.5年分)と推定される。直後、朝鮮人、中国人、社会主義者の大量虐殺事件発生。事件は、無抵抗の者を陸軍将校、近衛兵、憲兵、警察官、自警団員、暴徒らが一方的に撃ち殺したところに特質がある。正力は、秩序維持の責任者の地位にあったから、事件発生に責任がある。 |
| 【虎ノ門事件】 |
| 1923(大正12、44歳)・12.27日、難波大助、摂政宮裕仁に発砲(虎ノ門事件)。 |
| 【裕仁皇太子と久爾宮良子の御成婚儀が挙行される】 |
| 1924(大正13、45歳).1.26日、 1923年の関東大震災の発生で延期されていた皇太子裕仁親王と久爾宮良子の御成婚儀が挙行された。3.16日、第7回病状発表。 |
| 【大正天皇の第7回病状発表】 |
| 1924(大正13)年、45歳の時、3.16日、大正天皇の第7回病状発表。 |
| 【大正天皇の憂鬱】 |
| 1925(大正14)年、46歳の時.2月、感冒のため体温が38℃まであがるが、まもなく全快。5.10日、銀婚式奉祝会。5.27日、第2皇子秩父宮擁仁親王、約2年の予定で英国に留学。6.19日、第8回病状発表。7.7日、日光にて避暑。12.6日、第1皇孫照宮成子内親王誕生。12.19日、脳貧血で卒倒し、沼津行幸を延期。 |
1925(大正14)年、46歳の時、4.29日、皇太子殿下(昭和天皇)が靖国神社で第一次世界大戦臨時大祭に参列。
| 【大正天皇病床に伏す】 |
| 1926(大正15)年、47歳の時、2.10日、第9回病状発表。5.11日、第10回病状発表。8.15日、避暑のため、原宿駅から葉山御用邸へ出発。9.17日、第11回病状発表。10月、感冒で発熱。11.11日、御不例発表。明治神宮へ御平癒祈願の礼拝客が引きも切らぬ。11.18日、摂政宮裕仁、葉山御用邸へお見舞に参内。11.28日、3000人あまりの女学生が皇居前広場に参集して御平癒祈願。12.10日、生母柳原二位局、若槻首相などがお見舞いに参内。このころより皇族や大臣など葉山御用邸への往来が増える。12.15日、これ以降、御容体を官報にて発表。 |
| 【大正天皇が葉山御用邸で崩御】 |
1926(大正15).12.25日午前1時25分、静養中の葉山御用邸において、長く会えなかった実母・柳原愛子(二位局)の手を握ったまま崩御した(享年47歳)。臨終の床に生母を呼んだのは皇后の配慮だったという。
同日、御用邸で剣璽渡御の儀、皇居賢所では、新天皇代拝として掌典長が践祚の奉告を行い、ここに新天皇裕仁が誕生。昭和と改元。大喪使官制公布。
12.25日付け米国のロサンゼルス・タイムズ紙の追悼記事は次の通りである。
| 「短い治世にも関わらず、天皇嘉仁明宮、日本天皇の123番目の男子継承者は国民の啓発や外国との友好関係を果たすという望ましい業績を残した・・・・嘉仁は日本の最も人気のある元首の一人であった。大礼の際、彼のために書かれた詩は3万にのぼる・・・・東京の学習院の教育を受け、さらに個人教育も受けた。英語、フランス語やドイツ語も含め、外国語が達者で、『世界平和や国際道徳に関し、進んだ思想』の持ち主だといわれていた」。 |
|
|
1926(大正15)年、大正天皇(実質は摂政の裕仁皇太子=昭和天皇)の命令で、南朝を正統とした後も即位の是非で意見が別れていた寛成親王を、即位が確認されたとして「長慶」天皇とした。
これは、水戸藩による大日本史を通じて形成された水戸学及び国学の影響により歴代天皇(帝)史の見直しの一環のものである。この作業により、明治以前は神功皇后を15代の帝と数えていたが、歴代天皇から外した。壬申の乱で敗死した大友皇子は、即位が確認されたとされ、明治3年に「弘文」天皇した(現在では非即位説が有力である)。47代「淡路廃帝」に対して明治3年に「淳仁」と追号した。承久の乱に敗れた「九條廃帝」は天皇に数えていなかったが、明治3年に「仲恭」と追号した。明治44年に明治天皇の命令で、南朝2代を正統な天皇と認め、従来の96~100代の天皇を北朝として正統から外した。*義良親王(南朝)は、即位が確認されたとされ「後村上」天皇とした。*熙成親王(南朝)は、即位が確認されたとされ「後亀山」天皇とした。この流れのものである。(「ヒロさん日記」の「北朝の明治天皇が南朝を復権させたのはなぜか」参照) |
| 【皇太子裕仁親王が昭和天皇として即位する】 |
| 12.26日、昭和と改元され、皇太子裕仁親王(当時25歳)が第124代の皇位を就任し、昭和天皇となった。これより昭和の御世が始まった。 |
| 【大正天皇の埋葬】 |
| 1927(昭和2).1.20日、「大正天皇」と追号。2.7日、新宿御苑にて大葬。2.8日、多摩御陵(東京府下南多摩郡横山村、現・東京都八王子市長房町)に葬る。毎年12月25日には大正天皇例祭が行われている。 |
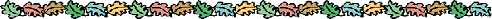



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)