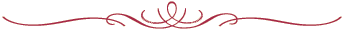「元号」(文春新書)、「日本年号史大事典」(雄山閣)などの著者である所功・モラロジー研究所教授に聞いた。「明治」が天皇のくじ引きで決まったことはよく知られている。それまでに10回落選していて、やっと日の目を見た。「元号の文字の持つ意味が、その時代にふさわしいと考えられるから、何度も提案されてくる」と話す。「明治」が最初の候補になったのは室町時代の「正長」改元(1428年)の時で、正式採用まで480年かかったことになる。江戸時代末期に何度もノミネートされていたので、明治が有力案のひとつであることは、朝廷の公卿らに認識されていただろう。現在の「平成」も、幕末の「慶応」(1865年)の際に検討されていた。2度目で早くも昇格した。源頼朝が鎌倉幕府を開いた建久3年(1192年)から、今日まで約930年間に元号は140あり、初出の候補がそのまま起用されたケースは38回あった。江戸時代からの約400年間では元号39に対し8回で、最も新しい初出採用の元号は「昭和」(1926年)。ひとつ前は「元治」(1864年)まで遡る。逆に言えば、近世から現代までで、未採用候補からの登用は約8割だ。中国の古典を基にして考案するから、1300年以上も経過すれば、どうしてもアイデアが似通ってくるということはあるかもしれない。これまでの年号は、約80種類の漢籍から出典されている。一番多かったのは書経からの35回(未採用案には85回)という。248番目の今回は日本の古典からの候補もありそうだが、所教授は「聖徳太子の十七条憲法などをみても、元号にふさわしい語句の出典は、漢籍に由来するケースが多い」と指摘する。近世の元号で、最も多く候補に挙げられたのは「天保」(1831年)の15回。最初は平安中期の「正暦」(990年)だった。用いられるまで約840年待ったことになる。朝廷は7つの元号案を徳川幕府に送り、特に天保を推していることを伝えたところ、幕府も同意したという。所教授は「幕末に近づくと朝廷が主導権を握って元号を決めたケースが多い」としている。未採用の元号案で最も落選回数が多いとみられるのが「嘉徳」だ。春秋左氏伝にある「上下皆有嘉徳、而無違心」のほか、史記などにも「群臣嘉徳」といった表現がある。28回以上の改元時に論議されながら、いま一歩及ばなかった。学識者が別々に答申したり、異なる漢籍からの引用で提案されたケースも重複して数えると、40回提案されたことになるという。嘉徳は「延久」(1069年)から「文久」(1861年)まで登場した。惜しかったのは「弘化」(1845年)の改元時。朝廷は「弘化、嘉徳、万安、万延、文久、嘉永、嘉延」を幕府に提示し、弘化か嘉徳を選ぶように伝えた。「嘉」の字を使った3案のうち嘉徳がトップ候補だった。しかし結局、弘化が採用された。嘉徳ファンとしては字画数の多い点が気になるところだ。
★主な元号未採用候補★(日本年号史大事典などから)
落選24回の「文長」も惜しい元号案のひとつ。史記に「文武両用、長久之術也」といった記述がみえる。南北朝時代から幕末の「万延」(1860年)まで候補に挙がった。「文も長も、たびたび元号に使われている縁起の良い字」と所教授。「文政」(1818年)改元では最終2候補のうちの1つにまで残った。さらに黒船来航などを理由にした「安政」改元(1855)では、朝廷は「文長、安政、和平、寛裕、寛禄、保和」を幕府に送り、文長を第1候補とした。しかし幕府が推薦したのは安政だった。ほかにも「寛安」「建正」「大応」「貞正」などが数多く候補に上っている。所教授は「未採用案のいずれもが、良い時代を表象しようという希望が込められている。今後の元号に採用されても不思議ではない」としている。(松本治人)