孫引き。「令」の字は中国語で「美」や「謙遜」といった意味を持ち、「和」の字は「柔らかい」という意味を持つことがあるため、一見して柔和な感じのする元号だと思いました。「日中で共通して使われたことのある元号は少なくとも貞観、建武、弘治の3つがある」。中国稀代の名君と謳われる唐の太宗の時代に使われた「貞観」が日本でも859~877年に使用されていた。
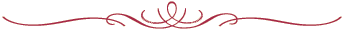
| 歴代の元号 |
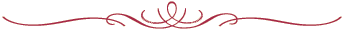
(最新見直し2007.4.7日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、元号論をしておく。今はスケッチ段階であるが追々精緻にして行くことにする。
2006.7.11日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【元号一覧】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飛鳥時代
奈良時代
平安時代
鎌倉時代
大覚寺統
持明院統
南北朝時代・室町時代
南朝(大覚寺統)
北朝(持明院統)
南北朝合一後
戦国時代
安土桃山時代
江戸時代
明治時代以降(近代・現代)
中央政府以外の元号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代
|
天皇(漢風諡号)
|
読み
|
おくり名(和風諡号) | 古事記 | |
| 日本書紀 | |||||
|
第1代
|
神武天皇
|
じんむ
|
カムヤマトイワレヒコ命(尊) | 神倭伊波礼琵古命 | |
| 神日本磐余彦尊 | |||||
| *日本書紀は更に始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)と記している。 | |||||
|
第2代
|
綏靖天皇 |
すいぜい
|
カムヌナカワミミ命(尊) | 神沼河耳命 | |
| 神渟名川耳尊 | |||||
|
第3代
|
安寧天皇
|
あんねい
|
シキツヒコタマテミ命(尊) | 師木津日子玉手見命 | |
| 磯城津彦玉手看尊 | |||||
|
第4代
|
懿徳天皇
|
いとく
|
オオヤマトヒコスキトモ命(尊) | 大倭日子鉏友命 | |
| 大日本彦耜友尊 | |||||
|
第5代
|
孝昭天皇
|
こうしょう
|
ミマツヒコカエシイネ命(尊) | 御真津日子訶恵志泥命 | |
| 観松彦香殖稲尊 | |||||
|
第6代
|
孝安天皇
|
こうあん
|
オオヤマトタラシヒコクニオシヒト命(尊) | 大倭帯日子国押人命 | |
| 日本足彦国押人尊 | |||||
|
第7代
|
孝霊天皇
|
こうれい
|
オオヤマトネコヒコフトニ命(尊) | 大倭根子日子賦斗邇命 | |
| 大日本根子彦太瓊尊 | |||||
| *賦斗邇はフト(マ)二と読める。 | |||||
|
第8代
|
孝元天皇
|
こうげん
|
オオヤマトネコヒコクニクル命(尊) | 大倭根子日子国玖琉命 | |
| 大日本根子彦国牽尊 | |||||
|
第9代
|
開化天皇
|
かいか
|
ワカヤマトネコヒコオオビビ命(尊) | 若倭根子日子大毘々命 | |
| 稚日本根子彦大日日尊 | |||||
|
第10代
|
崇神天皇
|
すじん
|
ミマキイリヒコイリ(二)エ命(天皇) | 御真木入日子印恵命 | |
| 御間城入彦五十瓊殖天皇 | |||||
| *日本書紀は更に御肇國天皇(はつくにしらすすめらみこと)と記している。 | |||||
|
第11代
|
垂仁天皇
|
すいにん
|
イクメイリヒコイサチ命(尊) | 伊久米伊理毘古伊佐知命 | |
| 活目入彦五十狭茅尊 | |||||
|
第12代
|
景行天皇
|
けいこう
|
オオタラシヒコオシロワケ天皇(天皇) | 大帯日子淤斯呂和氣天皇 | |
| 大足彦忍代別天皇 | |||||
|
第13代
|
成務天皇
|
せいむ
|
ワカタラシヒコ天皇(尊) | 若帯日子天皇 | |
| 稚足彦尊 | |||||
|
第14代
|
仲哀天皇
|
ちゅうあい
|
タラシナカツヒコ天皇(天皇) | 帯中日子天皇 | |
| 足仲彦天皇 | |||||
| 神功皇后 | じんぐうこうごう | オキナガタラシヒメ | |||
|
第15代
|
応神天皇
|
おうじん
|
ホムタワケ←イササワケ*(尊) | 品陀和気 | |
| 誉田別尊 | |||||
|
第16代
|
仁徳天皇
|
にんとく
|
オオササギ(尊) | 大雀命 | |
| 大鷦鷯尊 | |||||
|
第17代
|
履中天皇
|
りちゅう
|
(オオエノ)イザホワケ命(尊) | 大江之伊邪本和気命 | |
| 大兄去来穂別尊 | |||||
|
第18代
|
反正天皇
|
はんぜい
|
タヂヒノミズハワケ命(尊) | 水歯別命 | |
| 多遅比瑞歯別尊 | |||||
|
第19代
|
允恭天皇
|
いんぎょう
|
オアサズマワクゴノスクネ王(尊) | 男浅津間若子宿禰王 | |
| 雄朝津間稚子宿禰尊 | |||||
|
第20代
|
安康天皇
|
あんこう
|
アナホ天皇(天皇) | 穴穂天皇 | |
| 穴穂天皇 | |||||
|
第21代
|
雄略天皇
|
ゆうりゃく
|
オオハツセノワカタケ命(尊) | 大長谷若建命・大長谷王 | |
| 大泊瀬幼武尊 | |||||
|
第22代
|
清寧天皇
|
せいねい
|
シラカノタケヒロクニオシワカヤマトネコ命(天皇) | 白髪大倭根子命 | |
| 白髪武広国押稚日本根子天皇 | |||||
|
第23代
|
顕宗天皇
|
けんぞう
|
オケ命(天皇) | 袁祁王・袁祁之石巣別命 | |
| 弘計天皇 | |||||
|
第24代
|
仁賢天皇
|
にんけん
|
オケノミコト命(天皇) | 意祁命・意富祁王 | |
| 億計天皇 | |||||
|
第25代
|
武烈天皇
|
ぶれつ
|
オハツセノワカサギ(ヲハツセノワカサザキ)命(尊) | 小長谷若雀命 | |
| 小泊瀬稚鷦鷯尊 | |||||
|
第26代
|
継体天皇
|
けいたい
|
オフトツメ(ヲホド)命(王) | 袁本杼命 | |
| 男大迹王 | |||||
|
第27代
|
安閑天皇
|
あんかん
|
ヒロクニオシタケカナヒ命(天皇) | 広国押建金日命 | |
| 広国押武金日天皇 | |||||
|
第28代
|
宣化天皇
|
せんか
|
タケヲヒロクニオシタテ命(天皇) | 建小広国押楯命 | |
| 武小広国押盾天皇 | |||||
|
第29代
|
欽明天皇
|
きんめい
|
アメクニオシハルキヒロニハ天皇(天皇) | 天国押波流岐広庭天皇 | |
| 天国排開広庭天皇 | |||||
|
第30代
|
敏達天皇
|
びだつ
|
ヌナクラフトタマシキ命(尊) | 沼名倉太珠敷命 | |
| 渟中倉太珠敷尊 | |||||
|
第31代
|
用明天皇
|
ようめい
|
タチバナノトヨヒ命(天皇) | 橘豊日命 | |
| 橘豊日天皇 | |||||
|
第32代
|
崇峻天皇
|
すしゅん
|
ハツセベノワカサザキ天皇(皇子) | 長谷部若雀天皇 | |
| 泊瀬部皇子 | |||||
|
第33代
|
推古天皇
|
すいこ
|
トヨミケカシキヤヒメ命(尊) | 豊御食炊屋比売命 | |
| 豊御食炊屋姫尊 | |||||
|
第34代
|
舒明天皇
|
じょめい
|
オキナガタラシヒヒロヌカ天皇 | 息長足日広額天皇 | |
|
第35代
|
皇極天皇
|
こうぎょく
|
アメトヨタカライカシヒタラシヒメ天皇 | 天豊財重日足姫天皇 | |
|
第36代
|
孝徳天皇
|
こうとく
|
アメヨロズトヨヒ天皇 | 天万豊日天皇 | |
|
第37代
|
斉明天皇
|
さいめい
|
アメトヨタカライカシヒタラシヒメ天皇 | 天豊財重日足姫天皇 | |
|
第38代
|
天智天皇
|
てんじ
|
アメミコトヒラカスワケ尊 | 天命開別尊 | |
|
第39代
|
弘文天皇
|
こうぶん
|
あまのぬなはらおきのまひと天皇 | 天渟中原瀛真人天皇 | |
|
第40代
|
天武天皇
|
てんむ
|
アマノヌナハラオキノマヒト | ||
|
第41代
|
持統天皇
|
じとう
|
オホヤマトネコアメノヒロノヒメ | ||
|
第42代
|
文武天皇
|
もんむ
|
ヤマトネコトヨオホヂ | ||
|
第43代
|
元明天皇
|
げんめい
|
ヤマトネコアマツミシロトヨクニナリヒメ | ||
|
第44代
|
元正天皇
|
げんしょう
|
ヤマトネコタカミズキヨタラシヒメ | ||
|
第45代
|
聖武天皇
|
しょうむ
|
|||
|
第46代
|
孝謙天皇 |
こうけん
|
|||
|
第47代
|
淳仁天皇
|
じゅんにん
|
|||
|
第48代
|
称徳天皇
|
しょうとく
|
|||
|
第49代
|
光仁天皇
|
こうにん
|
|||
|
第50代
|
桓武天皇
|
かんむ
|
|||
|
第51代
|
平城天皇
|
へいぜい
|
|||
|
第52代
|
嵯峨天皇
|
さが
|
|||
|
第53代
|
淳和天皇
|
じゅんな
|
|||
|
第54代
|
仁明天皇
|
にんみょう
|
|||
|
第55代
|
文徳天皇
|
もんとく
|
|||
|
第56代
|
清和天皇
|
せいわ
|
|||
|
第57代
|
陽成天皇
|
ようぜい
|
|||
|
第58代
|
光孝天皇
|
こうこう
|
|||
|
第59代
|
宇多天皇
|
うだ
|
|||
|
第60代
|
醍醐天皇
|
だいご
|
|||
|
第61代
|
朱雀天皇
|
すざく
|
|||
|
第62代
|
村上天皇
|
むらかみ
|
|||
|
第63代
|
冷泉天皇
|
れいぜい
|
|||
|
第64代
|
円融天皇
|
えんゆう
|
|||
|
第65代
|
花山天皇
|
かざん
|
|||
|
第66代
|
一条天皇
|
いちじょう
|
|||
|
第67代
|
三条天皇
|
さんじょう
|
|||
|
第68代
|
後一条天皇
|
ごいちじょう
|
|||
|
第69代
|
後朱雀天皇
|
ごすざく
|
|||
|
第70代
|
後冷泉天皇
|
ごれいぜい
|
|||
|
第71代
|
後三条天皇
|
ごさんじょう
|
|||
|
第72代
|
白河天皇
|
しらかわ
|
|||
|
第73代
|
堀河天皇
|
ほりかわ
|
|||
|
第74代
|
鳥羽天皇
|
とば
|
|||
|
第75代
|
崇徳天皇
|
すとく
|
|||
|
第76代
|
近衛天皇
|
このえ
|
|||
|
第77代
|
後白河天皇
|
ごしらかわ
|
|||
|
第78代
|
二条天皇
|
にじょう
|
|||
|
第79代
|
六条天皇
|
ろくじょう
|
|||
|
第80代
|
高倉天皇
|
たかくら
|
|||
|
第81代
|
安徳天皇
|
あんとく
|
|||
|
第82代
|
後鳥羽天皇
|
ごとば
|
|||
|
第83代
|
土御門天皇
|
つちみかど
|
|||
|
第84代
|
順徳天皇
|
じゅんとく
|
|||
|
第85代
|
仲恭天皇
|
ちゅうきょう
|
|||
|
第86代
|
後堀河天皇
|
ごほりかわ
|
|||
|
第87代
|
四条天皇
|
しじょう
|
|||
|
第88代
|
後嵯峨天皇
|
ごさが
|
|||
|
第89代
|
後深草天皇
|
ごふかくさ
|
|||
|
第90代
|
亀山天皇 |
かめやま
|
|||
|
第91代
|
後宇多天皇
|
ごうだ
|
|||
|
第92代
|
伏見天皇
|
ふしみ
|
|||
|
第93代
|
後伏見天皇
|
ごふしみ
|
|||
|
第94代
|
後二条天皇
|
ごにじょう
|
|||
|
第95代
|
花園天皇
|
はなぞの
|
|||
|
第96代
|
後醍醐天皇
|
ごだいご
|
|||
|
-
|
[光厳天皇]
|
こうごん
|
|||
|
-
|
[光明天皇]
|
こうみょう
|
|||
|
第97代
|
後村上天皇
|
ごむらかみ
|
|||
|
-
|
[崇光天皇]
|
すこう
|
|||
|
-
|
[後光厳天皇]
|
ごこうごん
|
|||
|
第98代
|
長慶天皇
|
ちょうけい
|
|||
|
-
|
[後円融天皇]
|
ごえんゆう
|
|||
|
第99代
|
後亀山天皇
|
ごかめやま
|
|||
|
第100代
|
後小松天皇
|
ごこまつ
|
|||
|
第101代
|
称光天皇
|
しょうこう
|
|||
|
第102代
|
後花園天皇
|
ごはなぞの
|
|||
|
第103代
|
後土御門天皇
|
ごつちみかど
|
|||
|
第104代
|
後柏原天皇
|
ごかしわばら
|
|||
|
第105代
|
後奈良天皇
|
ごなら
|
|||
|
第106代
|
正親町天皇
|
おおぎまち
|
|||
|
第107代
|
後陽成天皇
|
ごようぜい
|
|||
|
第108代
|
後水尾天皇
|
ごみずのお
|
|||
|
第109代
|
明正天皇
|
めいしょう
|
|||
|
第110代
|
後光明天皇
|
ごこうみょう
|
|||
|
第111代
|
後西天皇
|
ごさい
|
|||
|
第112代
|
霊元天皇
|
れいげん
|
|||
|
第113代
|
東山天皇
|
ひがしやま
|
|||
|
第114代
|
中御門天皇
|
なかみかど
|
|||
|
第115代
|
桜町天皇
|
さくらまち
|
|||
|
第116代
|
桃園天皇
|
ももぞの
|
|||
|
第117代
|
後桜町天皇
|
ごさくらまち
|
|||
|
第118代
|
後桃園天皇
|
ごももぞの
|
|||
|
第119代
|
光格天皇
|
こうかく
|
|||
|
第120代
|
仁孝天皇
|
にんこう
|
|||
|
第121代
|
孝明天皇
|
こうめい
|
|||
|
第122代
|
明治天皇
|
めいじ
|
|||
|
第123代
|
大正天皇
|
たいしょう
|
|||
|
第124代
|
昭和天皇
|
しょうわ
|
|||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国紙・環球時報は1日、日本の新元号「令和」が初めて日本の古典から選ばれたとされていることについて、日本のネットユーザーから続々と異論が出ていることを伝えた。 「令和」は日本最古の和歌集「万葉集」の「初春の令月にして、気淑(よ)く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」との一文から取られたもので、初めて日本の古典から選ばれたという。しかし記事は、「多くの日本のネットユーザーがすぐに気付いた。この頭を絞って考え出した新年号が、『孫悟空』と同様に中国文化から飛び出すことはできないということを」という言い回しで、日本のツイッターユーザーから上がった声を紹介している。 まず、アカウント名「平林緑萌@骨折中」さんは「『万葉集』の『令月』は中国古典からの引用。『儀礼』の『士冠礼』などに見える。やはり中国古典からは逃れようがないのだなあ」とツイート。さらに、「そもそも『万葉集』の当該部分は後漢の張衡『帰田賦』の『於是仲春令月、時和氣清』とクリソツ(そっくり)では?」とも指摘している。この点については、複数のユーザーから同様の声があったようだ。 また、「新元号は和語から取ると言っていたがやめたんですね。万葉集巻五、『梅花の宴』の序文は漢文で、しかも変体漢文ではなく中国語そのものの純漢文。令月も漢語」という指摘や、「漢字自体が中国由来だし、そもそも元号の風習も中国由来なので、実は中国の影響から全然解放されてない」といった声が上がったと記事は紹介している。 一方、中国のネットユーザーからは「文化についての知識で日本のネットユーザーに負けていることを実感」「日本人がこれほど中国文化に詳しいとは。中国人でも、これほど自国の歴史文化について知っている人は少ない」といった声や、「日本人が中国文化を尊重してきたのは事実だからな」「少なくとも日本人は、『漢字は自分たちが発明したものだ』とは言わない」といった声が寄せられた。 また、「文化は流動するもの。中国文化は日本文化の母であり、日本の『血』の中には中華文明が息づいている。同様に、中国文化も世界の優秀な文化を吸い取り、融合してできた。日本人は悲しむ必要はないし、中国人もおごり高ぶる必要はない」というコメントも多くの共感を集めていた。(翻訳・編集/北田) |
|
孫引き。「令」の字は中国語で「美」や「謙遜」といった意味を持ち、「和」の字は「柔らかい」という意味を持つことがあるため、一見して柔和な感じのする元号だと思いました。「日中で共通して使われたことのある元号は少なくとも貞観、建武、弘治の3つがある」。中国稀代の名君と謳われる唐の太宗の時代に使われた「貞観」が日本でも859~877年に使用されていた。 |
|
新元号「令和」で初めて元号に使われた「令」の字は、これまでに案の段階では2度挙がったことがある。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)