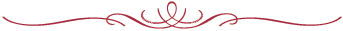
| 大神神社詣り関連詣り順路 |
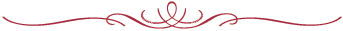
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).2.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、大神神社の関連詣り順路を確認しておく。「山の辺の道を歩く」その他参照 2006.12.3日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【空海と大物主(大黒天)】 |
| 大物主の妻が眠る箸墓の東にあたる民家の裏に箸中長者屋敷跡がある。昔、箸中村に貧しいが信仰心が篤かった清助という者が、この長者屋敷跡に住んでいた。それを知った弘法大師(空海)が自作の大黒天(大物主)を清助に与えたところ、さらに信仰心を深めることで長者になった。この話は日本子ども昔話にもなっている。その清助の長者屋敷跡には、ネズミモチの木が植えられており、今も姿を見ることができる。このネズミモチは不思議なことに何年経っても枯れず、大きくなることもなく、箸中の人達を田んぼの中から見守っている。 余談。弘法大師の想いが詰まった大黒天は、奈良県大和郡山市山田町松尾山にある、松尾寺に安置される最古型の大黒天(重文)とされている。清助の長者屋敷は三輪山を望むところに位置し、大物主と大黒天は同一視されることから、大黒天を通して三輪山に鎮まる大物主を拝していた。ネズミモチは初夏に花序の多い白花を咲かせ、晩秋にはネズミの糞に似た黒紫色の小さな実を付ける。名前の由来も、この実からネズミモチと名付けられている。 |
| 【大神神社境外摂社/率川坐大神御子神社/率川(いさがわ)神社】 |
| https://www.facebook.com/groups/784547378758410/permalink/906114169935063 |
| 率川坐大神御子神社/率川(いさがわ)神社は奈良市本子守町18に鎮座する。本殿三棟の社で平城遷都以前の593(推古天皇元)年に大三輪君白堤(おおみわのきみしらつつみ)の勅命により創建された奈良市最古の神社である。852(仁寿2)年、文徳天皇の代に従五位下を授けられ、神封6戸(左京4戸、丹後国2戸)を与えられている。 祭神は神武天皇の皇后、媛蹈鞴五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめのみこと)。全国の神社の中では珍しい皇后を主祭神とした神社である。三棟の本殿左には媛蹈鞴五十鈴姫命の父神である狭井大神(さいのおおかみ)、右には同じく母神の玉櫛姫命(たまくしひめのみこと)が祀られ、中央に祀られる媛蹈鞴五十鈴姫命を両親が寄り添う姿で守るように鎮座する。この事から、古くより俗に子守明神とよばれ、子育ての神、子どもの守り神として信仰を集めている。摂社の中では、磐余の里(大和桜井市)三輪から少々遠いところにある。境内は第9代開化天皇(かいかてんのう)の宮である「開化春日率川宮」があったとされる。 率川神社本殿の東側には三輪明神の摂末社が並ぶ。 末社・住吉社。祭神は上筒之男命(うわつつのをのみこと)、中筒之男命(なかつつのおのみこと)、底筒之男命(そこつつのおのみこと)、息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)=神功皇后。 摂社・率川阿波神社。祭神は天皇を守護する託宣の神事代主神(ことしろぬしのかみ)。出雲の国譲りの際に釣りをしており、釣りの神が転じて、豊漁の神として崇められることの方が多い。別名は「えびす神」ともよばれる。 末社・春日社。祭神は武甕槌命(たけみかづちのみこと)、斎主命(いわいぬしのかみ)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)です。武甕槌神は雷神、刀剣の神、弓術の神、武神、軍神、武道・競技の必勝、事業の創始、旅行安全の神で別名は「斎主神・伊波比主神(いわいぬし)、天児屋根命(あめのこやね)、比売大神(ひめのおおかみ)」。天児屋根命は祝詞の神、出世の神とされ、中臣連の祖(中臣鎌足を祖とする藤原氏の氏神)である。 境内南側には本社である三輪明神(大神神社)の逢拝所が設けられている。その隣には縁起物の「カエル石」が四方八方を守るように鎮座する。蛙は一度に沢山の卵を産むことから繁殖力、命の再生、豊富、裕福の証として伝えられる。特に「カエル」と言う名の語呂「お金がカエル、幸せがカエル、若カエル、無事カエル、貸した物がカエル」などと言われ参拝者の健康回復、旅行安全、筋力増幅などの御利益を願いこの石を撫で親しまれている。三輪明神の「なでうさぎ」と共に率川神社の「なでカエル」とよばれ人気がある。 |
|
■率川神社のゆり祭り・・
三輪明神で育てられた「笹ゆり」を、率川神社に奉納し「三枝祭(さいくさのまつり)」が6.17日に執り行われる。境内には笹ゆりの香りが漂う通称「ゆりまつり」として親しまれる。この祭りは神前に酒樽を供え、四人の巫女が笹ゆりをかざして「うま酒みわの舞」を奉納する。また奉納された笹ゆりは厄除けとして参拝者に配られる。神域には神々の食事とされる特殊神饌(とくしゅしんせん)「鯛、鰹、アワビ、イカ、かます」など、生の魚介類と「ニンジン、ゴボウ、餅、白蒸(ごはん)、ゴマ、黒豆、枇杷(びわ)」などが折櫃(おりびつ)に並べられ、両端が細くなった箸が添えられる。柏の葉で編んだ蓋をして黒木の棚にのせて供えられる。701(大宝元)年に制定の「大宝令」では国家の祭りとして定められ、疫病を鎮めることを祈る由緒のある祭りである。媛蹈鞴五十鈴姫命が住む三輪山の麓の狭井川(さいかわ)の畔には、笹ゆりが美しく咲き誇ってていたという古事記に記される伝説から、酒樽を三輪山に咲く笹ゆりで飾り神殿に奉納する神事になっている。笹ゆりの茎先が三本に分かれるところから三枝といわれる。三枝祭は平安時代、盛んに行われたが時代と共に中絶し明治十四年に再興され現在に至る。 |
| 海柘榴市、仏教伝来の地 | |
| 八坂神社から金拆社に向かう道中に「海柘榴市(つばいち)」や「仏教伝来の地」に寄り道できる。桜の季節には初瀬川のせせらぎを聞きながら、桜並木のトンネルの中を歩く快いところでもある。初瀬川の桜並木は、昔からここで男女が集い、詩の掛け合いをして歌垣を催されたと日本書紀・古事記・万葉集に記されている。 泊瀬川畔一帯は磯城瑞籬宮(しきみずがきのみや)、磯城嶋金刺宮(しきのみつかきのみや)、海柘榴市(つばいち)などの史跡を残し「しきしまの大和」とよばれる古代大和朝廷の中心地といわれる。この付近は大阪湾の難波津(なにはづ)から大和川を上ってきた舟の終着地でもある。難波津に着いた聖明王の使者は、大和川を船で上り、初瀬川河畔の海柘榴市に上陸したと伝わる。大和朝廷と交渉を持つ国々の使節が発着する都の外港として重要な役割を果たしてきた。横大路・磐余山田道・上ツ道・山の辺の道などの主要な道路が交わり、多くの人や物が行き交う水陸交通の要衝として発達した。海柘榴市周辺は古代より栄えた交易市の跡で、最古の交易の市として万葉集や源氏物語、枕草子にもたびたび登場する。海石榴市の説明文は次の通り。
|
|
|
■長野県長野市元善町にある善光寺の本尊(秘仏)とされる善光寺式如来は百済よりこの地に届いた一光三尊阿弥陀如来。
欽明13年(552年)の冬10月に百済の聖明王(せいめいおう)は西部姫氏達率怒利斯致契等を遣として釋迦佛金銅像(一光三尊阿弥陀如来・百済大仏)・幡蓋若干(はたきぬがさ)・經論(きやうろん)をたてまつると日本書紀に記されている。仏教伝来の百済の使節もこの港に上陸し、直ぐに南方の磯城嶋金刺宮に向かったとされている。また「推古16年(608年)遣隋使の小野妹子が同じ遣隋使である裴世清を伴って帰国し飛鳥の京に入るとき、飾り馬75頭を遣して海柘榴市の路上で阿倍比羅夫(あべのひらふ)
に迎えさせた」と記されている。
|
| 御県神(みあがたのかみ) |
| 御県神(みあがたのかみ)は田の神で、大和では高市御県、葛城御県、十市御県、志貴御県、山辺御県、曾布御県の六つの御県神が著名である。御県神は大きな川の流域の田圃の中などにも祭られていることが多い。志貴御県坐神社の境内につづく西側、現在の天理教敷島大教会と北隣りの三輪小学校の両敷地から、縄文式土器、弥生式土器、石器をはじめ須恵器や土師器のほかに金屋の地名どおり製鉄に関係のある金クソ、フイゴの口、石製模造品、玉製品などが出土している。このことから、このあたりが皇居跡ではないかとの説もある。この台地は海抜7~80mの地で、考古学上からも三輪遺跡として重要視されている。 |
| (三輪山)平等寺(びょうどうじ) | |
| 581年、平等寺は、聖徳太子が賦徒を平定するため、賦徒平定後の世の中の平和安寧を念じ、三輪明神に祈願して賦後十一面観音を彫んで三輪山麓に寺を建立し、大三輪寺と称したのに始まるという。本尊は聖徳太子の御自作と伝えられる十一面観音。現在の本尊は平安期に復元したものという。 寺伝は次のように記している。
その後、大御輪寺、浄願寺と共に三輪明神(現・大神神社)の神宮寺で、曹洞宗の寺院。「大神神社史」は、「平等寺境内の開山堂に慶円の像を安置していた」ことを根拠に寺伝を否定し、僧/慶円上人(三輪上人)を開山者としている。「大三輪町史」は空海説にも触れているが、史料上はっきりとした記述は古代にはあらわれない。慶円は鎌倉時代初期の僧で、大神神社の傍らに真言灌頂の道場「三輪別所」を開き、平等寺と改称してから大伽藍を建立したと伝えられる。境内には吉野朝時代の僧/善教が大和の国の熱病平癒のために彫られたという「熱取り地蔵」等がある。関ヶ原の戦いに破れた島津義弘が、一時この寺でかくまわれていたという。江戸時代には、真言宗の寺院ではあるが修験道も伝えていた。平等寺は明治の廃仏毀釈によって一旦廃絶するが、明治23年になって翠松寺(すいしょうじ)が河内から移され、旧平等寺の山門付近に再建された。その後、昭和52年3月に元の「(三輪山)平等寺」という名前に戻った。 |
| ホケノ山古墳 |
| 檜原神社から九日神社への道筋にはホケノ山古墳・箸墓古墳等の有名な古墳がある。豊鍬入姫命の墓との伝承が残るホケノ山古墳はのどかな風景が楽しめる。また、卑弥呼の墓との説もある箸墓古墳は池側からの眺めが素晴らしい。 |
| 箸墓古墳 |
| 檜原神社から九日神社への道筋にはホケノ山古墳・箸墓古墳等の有名な古墳がある。豊鍬入姫命の墓との伝承が残るホケノ山古墳はのどかな風景が楽しめる。また、卑弥呼の墓との説もある箸墓古墳は池側からの眺めが素晴らしい。 |
| 渋谷向山古墳 |
| 「渋谷向山古墳」は全長約300メートルの巨大前方後円墳で、景行天皇山辺道上陵として、宮内庁により陵墓治定を受けている。これは4世紀後半に築造された古墳時代前期後半の古墳と思われ、この時代の古墳としては国内最大の古墳という。第12代と数えられる景行天皇に関しては日本武尊(ヤマトタケル)の父と言われているが、実在性には疑問が出されている。 |
| 行燈山古墳 |
| 行燈山古墳も前方後円墳で、三輪山の山麓に築かれた大和、柳本古墳群の中でも渋谷向山古墳に次ぐ大きさであり、崇神天皇陵に比定されている。崇神天皇は、3世紀から4世紀初めにかけて実在した大王と捉える見方が少なくない。 |
| 中山大塚古墳 |
| 中山大塚古墳はこのあたり一帯に展開する大和古墳群の南側に位置する前方後円墳で、前方後円墳が築かれ始めた頃、古墳時代初頭の古墳と判断されているという。ここに「大和神社お旅所」がある。「4月1日は大和神社よりここお旅所(大和稚宮神社)まで神輿渡御が行われる。祭り始めは、ちゃんちゃん祭り、祭り納めはおん祭り、大和の俚謡に歌われる大和の代表的な祭りになっている。「‘ちゃんちゃんと鉦鼓の音が大和に春を告げます」と説明されている。 |
| 燈籠山古墳 |
| 燈籠山古墳も前方後円墳だが、発掘調査が行われていないため、埋葬施設は不明。築造時期は古墳時代前期前半(4世紀前半)と考えられている。 |
| 西山塚古墳 |
| 西山塚古墳は古墳時代後期前葉の前方後円墳で、前期古墳が大半を占める大和古墳群の中で、後期の大型前方後円墳はこの古墳だけという。ここも発掘調査は行われていないが、墳丘の地面から古墳時代後期前葉の埴輪が採集されているという。 |
| 波多子塚古墳 |
| 波多子塚古墳も前方後円墳。墳丘が畑や果樹園等に開墾されていて、築造当時の本来の墳丘形状からは大幅に改変されていると考えられている。築造時期は出土した埴輪の年代から、古墳時代前期、おおむね4世紀前葉と考えられている。この辺りには数多くの古墳が存在していて、大和古墳群と呼ばれている。 |
| 第10代崇神(すじん)天皇御陵(山辺道勾岡上陵) |
| 檜原神社からさらに北へ向かうと穴師(あなし)の集落に入り、その先には第10代崇神(すじん)天皇御陵がある。天理市柳本町。 |
| 黒塚古墳 |
| 黒塚古墳は、天理市柳本町。ここから卑弥呼の鏡といわれる三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)が33面も出土している。 |
| 纏向遺跡(まきむくいせき) |
| 奈良県桜井市、御諸山(みもろやま)とも三室山(みむろやま)とも呼ばれる三輪山の北西麓一帯に広がる弥生時代末期から古墳時代前期にかけての大集落遺跡。3世紀を主時期とする。前方後円墳発祥の地とされている。遺跡名称は、奈良県の旧磯城郡纒向村に由来し、「纒向」の村名は垂仁天皇の「纒向珠城(たまき)宮」、景行天皇の「纒向日代(ひしろ)宮」より名づけられたものである。 |
| 纒向・日代宮跡(まきむく・ひしろみやあと) |
| 纒向・日代宮跡(まきむく・ひしろみやあと)。「紀元730年、第12代景行天皇・大足彦忍代別命(おおたらしひこをしろわけ)が、即位後この地に宮を設け、大和朝廷による全国統一を進められた」。 |
| 九日神社(国津神社) | |
九日神社は九日(くにち、くじつ)または国津(くにつ)と呼ばれる小さな神社である。「国津」と言えば、すでに通ってきた箸墓古墳の手前にある神社も国津神社であった。国津神社(箸中)付近は、祭祀遺跡である。芝と箸中の二つの国津神社は、纏向川を挟んで深い関係にある。国津神社(箸中)にある説明板には次のような説明がなされている。
ちなみに纏向川下流の芝の国津神社(九日神社)には、素盞鳴尊の剣を物実としてうまれた奥津島比売、市杵島比売、多岐津比売の三女神を祭祠している。この箸中と芝で、神の山三輪山を水源とする纏向川をはさみ、二神の誓約によって成り出た神をそれぞれ祭神としていることに、古代神話伝承の原景を見る思いがする。また、天照大神の祭祀に奉じた豊鍬入姫命は崇神天皇の皇女で、その墓所が国津神社裏のホケノ山古墳であるという伝承が地元に伝わっている。(ホケノ山古墳は国津神社から徒歩で往復4分) |
| 穴師坐兵主(あなしにますひょうず)神社 | |
| 奈良県桜井市穴師にある穴師坐兵主(あなしにますひょうず)神社。通称は大兵主(だいひょうず)神社 。式内社で旧社格は県社。山の辺の道から300m程東へ、なだらかな坂を上ると神社の入口がある。この地はもと穴師大兵主神社の鎭座地であった。元の穴師坐兵主神社は山中・弓月岳にあった。垂仁天皇2年に倭姫命が天皇の御膳の守護神として祀ったとも、景行天皇が八千矛神(大国主)を兵主大神として祀ったともいう。応仁の頃、上社が焼失した。巻向坐若御魂神社は巻向山中にあった。穴師大兵主神社、穴師坐兵主神社、巻向坐若御魂神社の三社とも式内社に比定されている古社を合祀した。拝殿後方に、穴師坐兵主神社(名神大社)、巻向坐若御魂神社(式内大社)、穴師大兵主神社(式内小社))の本殿3棟(3社)が配置されている。祭神は右殿・若御魂神(稲田姫命)、中殿・兵主神(御食津神)、左殿・大兵主神。境内には慶応2年(1866)の常夜燈が立っている。 | |
次のように説明されている。
|
| 相撲(すもう)神社 |
| 穴師坐兵主神社の摂社として「相撲(すもう)神社」がある。この神社には鳥居はあるが社殿はない。ただ左手に小さな祠がある。神社境内の中央に土俵があり、土俵の盛り土の四隅には四本柱の代わりに桧の木が4本植えられている。日本書紀によれば第11代垂仁天皇7年、大兵主神社神域の小字カタヤケシで、出雲国出身の野見宿禰と大和国出身の當麻蹶速が天皇の御前で日本最初の勅命天覧相撲(今の天覧試合)を行った。日本最初の勅命天覧相撲が相撲節(7月7日)となり、それがもとで後世、宮中の行事になった。その取り組みを行ったとされている所に鎮座して野見宿禰を祀っており、相撲の祖神として信仰されている。相撲神社の万葉歌碑 「巻向の 山邊響(とよ)みて行く水の みなあわの如し 世の人吾は」(作者/柿本人麻呂)。相撲はもとは神の信仰から出ていて、国土安穏、五穀豊穣を祈る平和と繁栄の祭典であった。 境内には勝った野見宿禰を祀る祠や土俵などがひっそりと佇み、市内の出雲地区には野見宿禰の墓といわれる塚やゆかりの地の十二柱神社がある。弓月岳にあった穴師坐兵主神社の古社地と考えられる場所は「ゲシノオオダイラ」と呼ばれており弓月岳-上社跡-下社-箸墓古墳後円部中心が一直線に並ぶ。垂仁天皇の都は纒向珠城宮(まきむくのたまきのみや、古事記には師木玉垣宮(しきのたまかきのみや))とあり、奈良県桜井市穴師周辺に比定されている。 |
| 大神神社別宮/村屋坐弥冨都比売(むらやにますみふつひめ)神社 |
| https://www.facebook.com/groups/784547378758410/permalink/864315900781557 |
| 大神神社別宮/村屋坐弥冨都比売(むらやにいますみふつひめ)神社は奈良県磯城郡田原本町藏堂426に鎮座している。延喜式内大社で旧社格は県社。三輪明神(大神神社)の別宮。境内摂社として村屋(むらや)神社、服部(はっとり)神社、境内末社として久須須美(くすすみ)神社、恵比須(えびす)神社、境内末社として市杵嶋姫(いちきしまひめ)神社、物部(もののべ)神社、境外摂社として岐多志太(きたした)神社、森市(もりいち)神社が鎮座している。元は現在地の東の川辺、字宮ノ山に鎮座していたが、天正12年に兵火にかかり、現在地境内に遷座した。
祭神は天津屋根命、経津主神、比咩大神、武甕槌神、大伴健持大連、室屋大連。三穂津姫命(別名/弥富都比売神、ミホツヒメ)を主祭神とし、大物主命を配祀している。三穂津姫命は大国主命の后神で、日本書記によるとミホツ姫は高皇産霊(タカミムスビ)命の姫神。記紀神話では大物主(オオモノヌシ)命と大国主命は同神。大物主は大神神社の祭神で、その妃神(きさかみ)を祀ることから大神神社の別宮とも呼ばれる。大物主が国譲りをした時、その功に報いるためと大物主に二心のないようにという願いから自分の娘を嫁がせたという神話に出てくる神である。その時、高天原から3本の稲穂を持って降り、稲作を中津国に広め国を豊かにしたと云われる神でもある。 大物主と三穂津姫の夫婦神を祭ることから「縁結びの神」として知られ、家内安全の神、商売繁盛の神としても信仰されている。かつて、この地では正月の大とんどで大神神社と村屋神社の火種子を戴き、夫婦火とし、それで雑煮を炊いて一年の家内安全を家族で祈願していたという習慣が残っている。大和国一之宮である大神神社の主祭神の妃神を祀っていることから、大神神社を参っただけでは片詣りで両方お参りすることでいっそう利益が得られるとも云われる由緒正しい神社である。 五穀豊穣を祈るお田植祭神事、祝詞のあと畦切りと荒田おこし、畦捏ねと畦塗りに続き籾蒔き、牛男に扮した牛を使っての田植え準備、巫女が豊作の祝い神楽奉納があり、最後に神主が田植えを行う。
|
|
狛犬奉献年は、1839(天保10)年己亥9月吉日。
|
| 創立の年代は不詳である。延喜式神名帳式下郡に、村屋坐弥冨都比賣神社、村屋神社、久須須美神社、服部神社が記載されており、673(天武天皇元)年の壬申の乱のときに「村屋神」が22代当主/室屋喜久麿にのりうつり「わが杜の中を敵が来る。社の中つ道を防げ」と大海人皇子方の大伴連吹負将軍に軍備に対する助言をし見事勝利に導いた。この功績により神社として初めて位階を皇室(天武天皇)から賜ったと日本書紀に記されている。神階の授与の記事はこれが初出である。その後も何度か位を賜り現在正一位森屋大明神の呼称が残る。延喜式神名帳では大社に列しており、月次・相嘗・新嘗の奉幣に預ると記されている。
壬申の乱の功を後世に伝えるため、このとき功のあった三神を回る御渡が秋の例祭に行われていた。三神とは村屋神を祭る村屋神社(境内摂社)、事代主命を祀る久須須美神社(境内摂社)、生雷神を祀る森市神社(境外摂社)。また天正の頃(1580年頃)、松永久秀と十市氏の戦に巻き込まれ、戦火に遇い社地を奪われ財源がなくなり、一時神事祭祀は中絶していたが、1599(慶長4)年、52代神主大神/守屋政重により、現在の規模に縮小して再興を果たしたとされている。 |
| 十二柱(じゅうにはしら)神社 |
| 奈良県桜井市出雲にある。十二柱神社は旧初瀬街道沿いにある旧指定村社で、十二柱の名前のどおり国常立神(くにとこたちのかみ)など神世七代の神々と天照大神など地神五代の神、十二柱の神々を祀っています。参道から石段を上ると鳥居脇の大きな狛犬を片方4人ずつで力士が支えている。境内には第25代武烈(ぶれつ)天皇「泊瀬列城宮(はつせのなみきのみや)伝承地」として武烈を祀る武烈天皇社の祠と石塔があり、付近に天皇屋敷や御屋敷などの地名が残されている。出雲集落は当麻蹴速(たいまのけはや)と、我が国初の天覧相撲で勝利した 野見宿禰(のみのすくね)を祖として、相撲を行った穴師の相撲神社と並ぶ相撲発祥の地として知られている。 |
| 増御子神社 |
| 猿田彦神、天鈿女命(あまのうすめ)、神武天皇の功臣、椎根津彦の子孫市磯長尾市氏命を祀る。例祭 4月1日 知恵の神、受験・就職・産業開発を祈る。 |
| 高●(たかおおかみ)神社 |
| 御祭神/高●大神。天候、産業を司り水利を受け給う。祈雨、祈晴、暴風除けを祈る。社は古く大倭神社注進状にも記載され丹生川上神社上社の本社でもある。 |
| 祖霊社 |
| 戦艦大和第2艦隊戦没者霊を祀ると共に、大国主神・氏子崇敬者が鎮まる。昭和20年4月7日 鹿児島県坊ノ岬沖にて撃沈され、伊藤整一命他2736柱を合祀される。 |
| 朝日神社 |
| 桜井・奈良街道を行く方は必ず詣でしと言う。殖産を興し交易を奨め給う。 |
| 夜都岐神社(やつぎじんじゃ) |
| 夜都伎神社(やつぎじんじゃ)は奈良県天理市にある。旧社格は村社。夜都伎神社とも書かれ、「やつき」「やとぎ」などとも読まれる。乙木(おとぎ)集落の北端に鎮座する。祭神は、春日大社の4神(武甕槌命、姫大神、経津主命、天児屋根命)が祀られている。社地は宮山(たいこ山)と呼ぶ前方後円墳で、現拝殿前附近は土をならして平面にしたという。拝殿は萱葺でこの地方では珍しい神社建築で、屋根の美しい秀麗な神社で、元は神宮寺で十来子(十羅刹)を祀っていたという。 |
| この地には元は夜都伎神社と春日神社の2社があったが、夜都伎神社の社地を約400m東南の竹之内の三間塚池(現在の十二神社の社地)と交換し、乙木は春日神社1社のみとして社名を夜都伎神社に改めたものと伝えられている。この神社は昔から奈良春日神社に縁故が深く、明治維新までは当社から蓮の御供えと称する新饌を献供し、春日から60年毎に若宮社殿と鳥居を下げられるのが例となっていたと伝えられている。 現在の本殿は、1906(明治39)年に改築したもので、春日造檜皮葺高欄浜床向拝付彩色7種の華麗な同形の4社殿が末社の琴平神社と並列して美観を呈する。拝殿は萱葺でこの地方では珍しい神社建築である。鳥居は嘉永元年(1848年)4月奈良若宮から下げられたものという。石碑には、「山の辺の道ははるけく 野路の上に 乙木の鳥居 朱に立つ見ゆ 東畝」と刻まれている。 |
| 日本大国魂大神(やまとおおくにたまのおおかみ) |
| 大地主大神(おおとこぬしのおおかみ)で、宮中内に天照大神と同殿共床で奉斎されたが、第十代崇神天皇六年に天皇が神威をおそれ、天照大神を皇女豊鋤入姫命をして倭の笠縫邑に移されたとき、皇女淳名城入姫命(ぬなきいりひめ)に勅して、市磯邑(大和郷)に移されたのが神社の創建であると伝えられている。(2000余年前)奈良時代、朝廷の命により、唐の国へ渡って学ぶ遣唐使、その他使臣は、出発に際して、当社へ参詣し、交通安全を祈願された。 |
| 雄神神社(雄神神社) |
| 雄神神社は、〒632-0221 奈良県奈良市都祁白石町に鎮座する。天理市布留町に鎮座する「石上神宮」の境内摂社「出雲建雄神社」、藺生町に鎮座する「葛神社」と共に式内社「出雲建雄神社」の論社となっている。創建・由緒は詳らかでない。祭神は「出雲健男命」。社格は式内論社。背後にある山には二つの頂があり、東側は標高550.6mの「雄神山」(雄雅山)、西側は標高531.5mの「雌神山」(雌雅山)で、総称して「野野上岳」(野野神岳)と呼ばれている。神社には本殿がなく、野野上岳を神体山としている。野野上岳の山頂には白蛇が住んでいると伝えられ、現在も禁足地となっている。桜井市三輪に鎮座する三輪山の大神神社の元宮(奥宮)と伝わる。三輪山の周辺が大和の中心になる前、この社のある都祁が大和の本来の中心であったとされる。 |
| 神社の西方500mほどの地に鎮座する「国津神社」との間の田圃には四カ所の「休ん場(ヤスンバ)」と称する小さな森があり、これは神が往来する際に休むところであると伝えられている。 |
| 式内摂社/出雲建雄神社 |
| 式内摂社/出雲建雄神社。拝殿は元は内山永久寺の鎮守の住吉社の拝殿だった。大正3年に現在地に移築されたという。内山永久寺は神仏分離令により明治9年に廃絶。その後も鎮守社の住吉社は残されたが、その住吉社の本殿も明治23年に放火によって焼失し、拝殿だけが荒廃したまま残されていたので、当神宮摂社の出雲建雄神社の拝殿として移築したという。従ってこの建物は内山永久寺の建物の遺構として貴重なもので、国宝に指定されている。建立年代については、はじめは保延3(1137)年に建立され、その後13・14世紀に2回の改築によって現在の構造・形式になったと考えられている。 |
| 出雲建雄神社は江戸時代には所在不明となっていたようで、江戸時代中期の地誌「大和志」は所在未詳としつつ「或いは曰く」として現在の藺生町の「葛神社」を挙げている。対して現在では式内社/出雲建雄神社を境内社に比定する説が有力となっているが、雄神神社がそうであるとする説も唱えられている。現在に貴重な信仰的風景を伝える神社となっている。 |
| 三輪山出雲屋敷跡(いづもやしきあと) |
| 出雲屋敷跡(いづもやしきあと)は別名「高佐士野(たかさじの)」とよばれ三輪山の麓、狭井川の川縁近くにある七乙女伝説の地である。伝説ではこの地で暮らしていた七人の乙女たちのことで、その中の一人、伊須気余理比売(いすきよりひめ)を大久米命(おおくめのみこと)が初代天皇である神武天皇に勧めたところ、神武天皇は伊須気余理比売をすぐに気に入り妃にした。 出雲屋敷跡の由来は次の通り。出雲は素戔男尊(須佐能袁命、すさのおのみこと)の子孫、大国主命(おおくにぬしのみこと)を神とする出雲神話の地である。三輪の神は大物主(おおものぬし)とよばれ、大国主命の分身とされる。その大物主の娘たちが住んでいたので出雲屋敷とよばれたとのこと。神武天皇(神倭伊波礼琵古命、かむやまといわれひこのみこと)は、九州高千穂出身の高天原系。それに対し伊須気余理比売は出雲系。この高天ヶ原系と出雲系が結婚することにより、この二つの系譜や神話が一つに統合され、初代天皇誕生へと発展する。 伊須気余理比売(いすけよりひめ)は古事記に伝えられる神武天皇の皇后。その出生にまつわる物語として丹塗矢(にぬりや)の神婚説話がある。三輪の大物主が美女、勢夜陀多良比売(せやだたらひめ)に思いをかけ、その用便中に丹塗矢と化して陰部(ほと)を突いた。丹塗矢は立派な男に変じて姫と結ばれた。その後、生まれたのが富登多多良伊須須岐比売(ほとたたらいすすきひめ)で、後に「ほと」の名を嫌い、伊須気余理比売と改名した。伊須気(いすけ)は「いすすき」(身震いする)、余理(より)は神霊の依(よ)り憑(つ)くという意味合いがある。 |
| 素盞雄神社 |
| 素盞雄神社は奈良県桜井市に鎮座する。 |
| 大物主ゆかりの緒環塚(おだまきづか) |
| 緒環塚(おだまきづか)は三輪明神の三輪(みわ)と言う地名の由来が残る塚でもある。この緒環塚には縁結びに肖ろうと、多くの人が赤いリボンを結ぶ赤い糸伝説がある。カップルが石の椅子に座ることで結婚できるという。 昔々、この地に住む三輪氏の祖と伝えられる陶都耳命(すえつみみのみこと)に活玉依姫(いくたまよりひめ)という美しい姫がいた。その姫のもと真夜中になると紫の上衣を着た一人の男が現れるようになり何時の間にか姫と男は夫婦のちぎりを結んだ。姫は姫は間もなく妊娠した。そのことを知った父母は姫に問いかけた。父母は「お前は夫もいないのに妊娠しているがどうしたのか」と尋ねると。姫は「名前すら知らないお方ですが姿の凛々しい男の人が深夜に現れ夜明けになると何処へと帰られます」と答えた。心配になった父母は姫に「今夜、男が現れる前に寝床へ赤い土を撒いて緒環(おだまき)の糸の端を針に通して、その男の着物の裾に刺しておくように」と教えた。姫は教えられたとおりに男の着物の裾に針を刺したそうです。明くる日、周囲の赤土を見ると足跡はなく糸が戸の鍵穴から抜け出ており、その糸をたどると三輪山の神の社に続いていた。毎夜通う男の正体は三輪の神(大物主)とわかった。その時、姫の家の緒環には糸が三輪(三巻)だけが残っており、これが三輪という地名の由来となる。姫は始めて大物主と知り、残った緒環の糸を土に埋めた所が緒環塚である。三輪素麺が糸のように細く作られることから緒環に関係してる可能性もある。 |
| 長岳寺(ちょうがくじ) |
| 長岳寺(ちょうがくじ)は、天理市柳本町508。824(天長元)年、淳和天皇の勅願により空海(弘法大師)が大和神社(おおやまとじんじゃ)の神宮寺として創建したという。庫裏(旧地蔵院本堂及び庫裏)はかって48もあった塔頭のなかで唯一残った旧地蔵院の遺構で、寛永7年(1630)~寛永8年(1631)の建築。室町時代の書院造の様式を伝えており、重要文化財に指定されている。本堂は天明3年(1783)に再建された建物で、阿弥陀三尊像と多聞天・増長天立像を安置している。 楼門をくぐって境内に入るが、これはかっては上層に鐘楼が吊られていたために「鐘楼門」と呼ばれる日本最古の鐘門で、下層は室町~安土桃山時代、上層は平安時代のものという。寺伝では空海による創建当初から現存する建物というが、上層部分も空海の時代まではさかのぼらず、平安時代末期頃の建築とされる。 |
| 内山永久寺跡 |
| 内山永久寺跡は、平安時代後期の永久2年(1114)に鳥羽天皇の勅願により興福寺僧頼実が創建したと伝えられ、往時は壮麗な大伽藍を誇ったといわれているが、明治年間の廃仏毀釈より徹底的な破壊を受け、いまは境内の本堂池などにわずかに面影を残しているのみになっている。 |
| 笠荒神☆笠山三宝荒神社(かさやまさんぽうこうじんしゃ) |
| 奈良県桜井市笠の西端、標高480mの山中に位置する「笠荒神☆笠山三宝荒神社(かさやまさんぽうこうじんしゃ)」。笠荒神は、初めて火を起こし物を煮て食べる事を教えられた興津彦神(おきつひこのかみ)、興津姫神(おきつひめのかみ)、土祖神(はにおやのかみ)を祀り、カマドの神様として人々から厚い信仰を集めている。清荒神(兵庫県宝塚市)と立里荒神(奈良県野迫川村)の日本三大荒神の一つである。年三回(1月・4月・9月)に行われる大祭、竹林寺からお渡りや甘酒が振る舞われる。氏子代表を先頭に神職によりご神体が到着、祭壇に奉られ厳かに神事が行われる。参拝のあと、笠栽培のソバ100%使用の香り豊かな蕎麦がいただける「笠そば処」に立ち寄り、高原野菜や可憐な花苗を買い求めるのが倣い。 |
| 三輪明神摂社・神御前神社(かみのごぜんじんじゃ) |
| 三輪明神摂社・神御前神社(かみのごぜんじんじゃ)は三輪明神の北西に位置し、占いの場所として知られる神浅茅原(かむあさぢはら)のシャーマンの故郷に鎮座する。神御前神社の祭神は第七代孝霊天皇の皇女「倭迹迹日百襲姫命」(やまとととびももそひめのみこと)。日本書紀では第十代崇神天皇の御代、度々起こる国難を憂いた天皇が「神浅茅原」に八十万神を集めて占い、神意を問うたところ、大物主が倭迹迹日百襲姫命に乗り移り「我をよく敬い祀れば天下は平穏になるであろう」と答えたので、神託に従い丁重に祀りを続けたところ、国内は平穏になったと云う。その後、倭迹迹日百襲姫命は大物主の神妃として鬼道を用いて神意を伺い朝廷に貢献した。時が経つにつれて倭迹迹日百襲姫命は、大物主が昼には現れず夜にだけ通ってくるので、ある時「どうかもうしばらく留まってください。明朝謹んであなたの端正なお姿を拝見しとうございます」と願ったところ、大物主は「では明朝お前の櫛笥の中にいるから驚かないでくれ」と答えた。姫は不思議に思いながらも夜明けを待って、櫛笥を開けると中に美しい紐のような小蛇が入っており、それを見た姫は思わず驚き叫んでしまった。怒った大物主はたちまち人の姿に化身し、天空に舞い上って三輪山へ帰った。姫は空を仰ぎながら深く後悔し、尻もちをついてしまった。その時、箸が陰部に刺さり亡くなった。姫の亡骸は「大市墓」に埋葬、人々はこの陵墓を「箸墓」とよぶようになった。この箸墓は大阪山(現在の香芝市穴虫付近)」の石を手渡しで昼は人が運び、夜は神が運び造られたと伝わる。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)