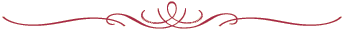
| 欠史八代考 |
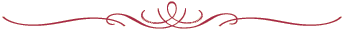
(最新見直し2014.12.22日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、欠史八代考をしておくことにする。「欠史八代」は実在しなかったとの説があるが実在したと思われる。たとえば、7代の孝霊天皇は中国地方の「楽々福(ササフク)」に事跡を残している。「欠史八代」の事績が時の政権の正統性を記すのに不都合な故に記されなかった、記していたところも削除されたと考えられる。「知られざる欠史八代・葛城王朝
」を参照する。 2014.12.22日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【欠史八代考】 |
| 欠史八代とは、初代からの天皇のうち、二代から九代までの八人の天皇のことを云う。これを確認する。以下、アウトラインを素描する。詳細は後々点検し正確をきすことにする。 |
| 【初代/神武天皇()】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【二代/綏靖天皇()】 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【三代/安寧天皇()】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【四代/懿徳天皇()】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【五代/孝昭天皇()】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【六代/孝安天皇()】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【七代/孝霊天皇()】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【八代/孝元天皇()】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【九代/開化天皇()】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【十代/崇神天皇()】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これら八代の天皇は、記紀では系譜だけが伝わり事績がほとんど伝えられていない。古語拾遺では記事さえも省略されている。よって後世の創作ではないかと考えられている。歴史上、ヤマト王権の王として実在が確からしいのは、十代・崇神天皇からだとされる。考古学的には、纏向遺跡の頃。崇神天皇の没年は、戊寅年(古事記)から、258年または318年とする説がある。魏志倭人伝で、卑弥呼が邪馬台国を統治したとされる年は、おおよそ、175年頃~248年頃と考えられている。邪馬台国畿内説では、崇神天皇と同時代の巫女・ヤマトトトヒモモソヒメの墓である箸墓古墳が卑弥呼の墓ではないかと考えられている。この場合、邪馬台国時代の終りと欠史八代時代の終りが重なることになる。欠史八代時代に、魏志倭人伝にある倭国大乱を経験したことになる。考古学上では、瀬戸内海に高地性集落が作られている。記紀の欠史八代の項に、広域の戦乱を裏付けるような事績は書かれていない。邪馬台国九州説(東遷説)では欠史八代の存在は否定される。欠史八代天皇が、おもに奈良県葛城地方に宮を置いていたことから、崇神天皇から始まるヤマト王権以前に、奈良県葛城地方を拠点とした王朝があったのではないかする説が登場する。鳥越憲三郎氏の葛城王朝説が有名である。葛城には、由緒ある高鴨神社や高天原伝承のある高天彦神社がある。欠史八代の葛城王朝に対し崇神天皇からを三輪王朝と呼んだりする。ただし、文献史学からは欠史八代天皇の実在が疑問視され、考古学上からも墳墓や遺跡などがないので存在を否定されている。しかしながら、邪馬台国所在地問題と欠史八代、葛城王朝の関係如何を廻る研究課題は残されているとすべきだろう。 |
| 葛城は、現在、奈良県葛城市という地名で残っているが、古くは「葛城県」として存在した。古来、ヤマトには六つの「御縣神社」があり、高市、葛木(葛城)、十市、志貴 (磯城)、山辺、曽布(添)の御県に生い出づる甘菜・辛菜を天皇の御膳に捧げていたらしい。それぞれに、県(あがた)を支配する首長がいて、連合国としてのヤマト王権を構成していたと思われる。謎を解く鍵は、「大和の六御縣神社」 である。
|
| 葛城国以外の御縣神社は「坐」の字を持っている。「坐」にはどういう意味が込められているのだろうか。「在地の神」という意味だろうか? だとすれば「坐」のない神社の神は逆に「外来の神」と云うことになる。古代、夜麻登(やまと)/奈良盆地では西側/葛城国、東側/倭国と東西を二分する勢力が存在した形跡が認められる。西側の葛城(かつらき)は秋津嶋(あきつしま)と呼称されている。
神武天皇は、葛城の腋上の丘に登り、ヤマトを秋津洲(あきつしま)と呼んだと言う。それに対応するように、磯城は、磯城嶋(しきしま)と呼ばれ、欽明天皇元年に磯城嶋金刺宮が置かれた。「あきつしま」と、「しきしま」は、どちらも「やまと」の国の代名詞となっている。夜麻登(ヤマト)は、山辺(やまのべ)の郡(こほり)の倭郷(やまとのさと)から始まるらしい。但し、葛城の高尾張には元々は土蜘蛛がいたとされる。「土蜘蛛」と「出雲」は関係があるようにも見える。御室山、御諸山(御諸→御所)、葛城山、二上山、金剛山、高天山。御諸山、三輪山・鳥見山、香具山・畝傍山・耳成山。 御巫八神(宮中八神)には、葛城の神とされる「事代主神」の名がある。日本神話は葛城地方の昔話がベースとなっている形跡が認められる。
|
| 初期の天皇の宮と神格が「大和の六御縣神社」 に関係しており、どれも葛城に拠点を置いている気がする。崇神天皇以前の大王は葛城地方に本拠を置いていたという伝承は御縣神社の位置関係と整合性がある。「葛城県」は、「葛城国」とも呼ばれていたらしい。剣根命が葛城国造とされ椎根津彦命が倭国造とされたと日本書紀・神武天皇2年にあるので確認しておく。倭国造・椎根津彦は、神武東征のとき、海上で神武を手助けした「海人(あま)」である。神武天皇二年に倭国造に任じられた。奈良県天理市あたりを本拠にするという。葛城国造・剣根命は、その祖は高魂命(高皇産霊尊?)。鴨県主とは親戚同士である。葛木御縣神社で祭られている。宇陀にある劔主神社でも祭られてる。神武が宇陀から、大和に攻め入ったことと関連しているのかもしれない。 ちなみに、ニギハヤヒが降臨したのは斑鳩の峰白庭山で、ナガスネヒコの本拠地は富雄だったという。これを関係的に見ると、葦原中国平定を命じた高皇産霊神と、天皇家に繋がる天孫族・ニニギを祭っているのは葛城地方であり、ヤマト王権が生まれたとされる纏向のある三輪地方は征服された側のニギハヤヒを祭っている。山辺御縣坐神社の建麻利尼はニギハヤヒの末裔とされる。スサノヲが祭られている地の斑鳩ではニギハヤヒが降臨したという伝承があり、ニギハヤヒが祭られている地の三輪山ではスサノヲ系の大物主が祭られている。 葛城国にある葛木御縣神社の祭神は、ニニギであり、倭国(磯城・三輪)にある志貴御縣坐神社の祭神は、ニギハヤヒである。 |
|
三輪山麓を勢力範囲とする「磯城県主波延」は、その後も欠史八代のヤマト王権に妃を送り続ける。磯城県主波延の波延(haye)は、饒速日、黒速の速(haya)と通じる。日本書紀によれば、橿原で即位した神武天皇は、事代主神の娘の、媛蹈鞴五十鈴媛命を妃にする。そして高皇産霊神を鳥見山の中に天神として祀る。上小野の榛原・下小野の榛原という。神武天皇は「秋津州」と呼んだ。伊邪那岐は「ヤマトは心安らぐ国」と呼んだ。大己貴大神は「玉垣の内つ国」と呼んだ。饒速日命は「空見つヤマトの国」と呼んだ。
ここで、一つの疑問が沸く。日本書紀では、神武天皇は、橿原で即位したとき、高皇産霊神を祀っているのに天照大神を祭っていない? これは何故か。つまり、「天照大神」は神武天皇が持ち込んだ神ではなかったことになる。あるいは、「高皇産霊神」が、古代の太陽神だったのかも知れない。神話上でも、高天原に先に現れた神は高皇産霊神である。天照大神の登場は、イザナギ・イザナミが国産みをしたずっと後のこととなる。「高皇産霊神」が神武天皇系の祖神だったことになる。高皇産霊神は、葦原中国平定を命令した神であり、東征してきた神武天皇の祭った神でもあるので、したがって、高皇産霊神は、天照大神登場以前に、ヤマトの外から流入してきた神と考えられる。 日本書紀は、1~4代の天皇は葛城の神・事代主系の皇后を迎えたと書いている。古事記では、磯城系の娘を皇后にしたと書いている。事代主系と磯城系が同一と見なされていることになる。尾張系の皇后を迎えた孝昭天皇。尾張系の世襲足媛を皇后にした孝昭天皇の子は以下の二人。天足彦国押人(和珥氏・春日氏祖)日本足彦国押人(孝安天皇)。日本足彦国押人(孝安天皇)は、天足彦国押人の娘・押媛を皇后とし、孝霊天皇を産む。尾張系の血を濃くした孝霊天皇は、奈良県磯城郡田原本町黒田に、廬戸宮を作る。孝霊天皇の代から、複数の妃を迎え、系譜が非常に豊富になってくる。廬戸宮のあたりには、弥生時代前期に始まり、古墳時代前期まで600年間以上継続した、環濠集落が存在していた。東海系搬入土器が多い。(唐古・鍵遺跡) 尾張系の進出を契機に、葛城が衰退したように見えなくもない。ちなみに、畿内で銅鐸祭祀が廃れた後も、尾張では、銅鐸祭祀はしばらく続いていたようだ。 物部系の皇后を迎えた、孝元天皇。次の孝元天皇は、欝色謎・伊香色謎と婚姻している。物部系氏族が、天皇家の外戚となった。物部氏の祖のニギハヤヒは、尾張氏の祖でもある。物部姓は、後の11代・垂仁紀に登場してくる。垂仁紀の五大夫。阿倍臣・武渟川別(大彦の子・大彦の母は、物部氏系)和珥臣・彦国葺(天足彦国押人の後裔)中臣連・大鹿島。物部連・十千根(物部十市根)。大伴連・武日。 七代・孝霊天皇以後は、宮は奈良盆地の西側に置かれるようになった。彦五十狹芹彦(吉備津彦)は、七代・孝霊天皇/廬戸宮で生まれているはずである。母は倭國香媛で、その父は淡道之御井宮にいた和知都美。吉備津彦は、四道将軍で、桃太郎のモデルとされる。ヤマトトトヒモモソヒメも、ここで生まれている。「モモ」の名が共通しているのが興味深い。モモソヒメとモモタロウは、姉・弟の関係である。八代・孝元天皇/境原宮は、神武の宮のあった橿原にある。孝元天皇は、ニギハヤヒ・物部氏系の欝色謎・伊香色謎と婚姻している。ここで、「大彦」が生まれているはずである。大彦は、四道将軍である。稲荷山古墳出土の金象嵌鉄剣銘に、古代の王(?)として、「意富比垝」の名が刻まれている。
|
| 【古代の部族国家地名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 孝霊天皇后、細比売の父は、日本書紀では、「磯城県主祖・大目」とあり、古事記では「十市県主祖・大目」と、区別している。古事記では、物部氏の祖は、十市県主と、さりげなく言及しているのかもしれない。 実は、物部氏・物部十市根とは十市県主・大目の末裔だった。十市県と、師木県は近いので、血縁はあっただろう。師木県主「波延」・「ニギハヤヒ」と、十市県主「大目」・「物部十市根」とは、ニギハヤヒを同じ祖としていても、おかしくない。地理的に、葛城とも接触していただろう。 日本書紀の一書では、磯城県主が皇后を出した記録が残っている。しかし、磯城県主のことは、ほとんど語られることがない。これこそが歴史の改竄と言えよう。(市販の現代語訳日本書紀でも一書の件を記載してないものがある)物部氏はニギハヤヒを祖と主張している。しかし、ニギハヤヒと血縁だったとしても、実質はナガスネヒコの系譜だったのではないだろうか?武闘派のイメージは、ナガスネヒコゆずりだろう。物部氏と関係が深いとされる、矢田坐久志比古神社(奈良県大和郡山市矢田町)[祭神・櫛玉饒速日神 御炊屋姫神]は、ナガスネヒコの本拠とされた地にある。物部氏が祖神とするのは、ウマシマヂで、櫛玉饒速日と、御炊屋姫神の子。物部氏の系譜には、ナガスネヒコの地も入っている。ナガスネヒコの本拠の近くには、添御縣坐神社があり、スサノヲが祭られている。「物部十市根」という名前から、その頃の物部氏の祖は、十市を拠点にしていたのは、間違いないだろう。もし、物部氏が国津神と関係していたなら、祖神は、十市御縣坐神社の「市杵嶋姫命」だったろう。隣の磯城とは、ライバルだったはずである。 十市県主・大目の「目(め)」は「物(も)」に通じる。物部十市根の後の系譜上には、「目」という大連がいる。垂仁紀には、古墳をつくるときに、近親者を全員生き埋めにしたという記述がある。モモソヒメが死んだときに、磯城氏はすべて生き埋めにされたのかも知れない。そして、磯城氏亡き後、物部氏が祭祀を引き継いだ?原因は、ヤマトトトヒモモソヒメの死?神武以前のヤマトの王で、神武に恭順したはずのニギハヤヒの後裔が、垂仁紀の物部十市根の登場まで姿を現さぬのは、おかしいではないか?真のニギハヤヒの後裔は、磯城県主波延と考えれば、すべて辻褄が合う。磯城県主波延は、欠史八代時代に、皇后(女王)を出していた、神武以前からの正統派の王族だったが、ヤマトトトヒモモソヒメの死(祭祀の失敗?)によって、祭祀権を失った。磯城県の隣にあった十市県に、祭祀権が移行し、権力が増し、後の物部氏を出した。磯城県主と十市県主が同族であれば、物部氏は、ニギハヤヒと血筋だったかも知れない。堂々とニギハヤヒの後裔を名乗りたいがために、日本書紀編纂時に、ニギハヤヒ直系の磯城県主の系譜を消し去り、代わりに鴨王の系譜を挿入した。抗議しようにも、その頃の磯城県主は、モモソヒメが死んだ一件で、勢力を弱めていたに違いない。
|
| 葛城王朝が仮に存在したとすれば、時代的には魏志倭人伝の伝える卑弥呼の邪馬台国時代と関係しているように思われる。日本書紀では、崇神天皇は大物主大神・倭大国魂神・天照大神を祭ったとある。大物主大神、倭大国魂神、天照大神を祭った3人の巫女がいた。大物主大神巫女・ヤマトトトヒモモソヒメ。父:孝霊天皇、母:倭國香媛(磯城・淡路・吉備系?)。倭大国魂神巫女・渟名城入媛命。父:崇神天皇、母:尾張大海媛(尾張系)。天照大神巫女・豊鍬入姫命。父:崇神天皇、母:遠津年魚眼眼妙媛・
紀伊国荒河戸畔の女。次の巫女・倭姫命。父:垂仁天皇、母:丹波国日葉酢媛。 ヤマトトトヒモモソヒメは大物主大神を祭った。そして大物主大神の正体を知って死んだという。崇神天皇の娘・渟名城入媛命は倭大国魂神を祭った。そして体が痩せお祭りできなくなったという。崇神天皇の娘・豊鍬入姫命は天照大神を祭った。 天照大神の祭りは現在まで続いている。3人の巫女のうち、生き延びたのは、天照大神を祭った豊鍬入姫命である。モモソヒメ(倭跡跡日百襲姫)の死後、ヤマトの祭祀の後を継いだのは、トヨ(豊鍬入姫命)。ヤマト王権のカミの祭祀は、ヤマトの巫女から、紀伊国・丹波国の巫女に移行した? そうして、巫女を失った磯城、淡路、吉備、尾張系は、ヤマト王権の中心から脱落し、残った丹波、紀伊がヤマト王権を支えていくことになる。そしていわゆる河内王朝へと続いていく。応神天皇の母・神功皇后は、丹波を出自とする息長宿禰王と、葛城高額姫の娘神功皇后を補佐した建内宿禰の母は、古事記では、山下影日売・木国造祖・宇豆比古の妹とされる。
|
||||||
| 天照大神と距離を置く格上の神社 | |
|---|---|
| 杵築大社 | 島根。祭神・大国主命(大己貴神)。出雲大社のことだが、もとは「杵築大社」と言った。丹波国風土記によれば、「奈良朝のはじめ元明天皇和銅年中、大国主命御一柱のみを島根の杵築の地に遷す。すなわち今の出雲大社これなり。」と記されているという。「出雲」の名と「大国主」の神は、丹波の出雲大神宮からの勧請か?もとは、スサノヲと関係の深い土地だったはず。 スサノヲを祀る出雲の熊野大社は、火の発祥の神社として、「日本火出初之社」(ひのもとひでぞめのやしろ)とも呼ばれている。イザナミが葬られたとされる伝承地がある。(島根県と広島県の境の比婆山) |
| 熊野本宮 | 熊野坐神社、熊野速玉神社、熊野那智神社熊野。祭神・家都御子神、祭神・熊野速玉神 祭神・熊野夫須美神。熊野大社は、出雲にもあるが、全国の熊野系神社は、紀州の熊野三山を根本社としている。出雲の熊野大社からの勧請という説もある。イザナミが葬られたとされる伝承地がある。(三重県熊野市・花の窟神社) |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)