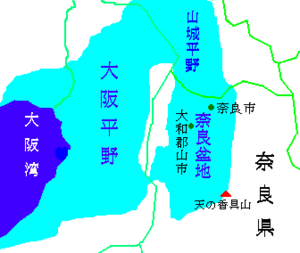舒明天皇の『万葉集』2番の「国見」の歌は謎の歌でもある。
⇒2016年9月29日 (木):象徴の行為としての「国見」/天皇の歴史(8)
⇒2016年11月24日 (木):舒明天皇の「国見の歌」の謎/天皇の歴史(11)
原文
高市岡本宮御宇天皇代 [息長足日廣額天皇]
天皇登香具山望國之時御製歌
山常庭 村山有等 取與呂布 天乃香具山 騰立 國見乎為者 國原波 煙立龍 海原波 加萬目立多都 怜A國曽 蜻嶋 八間跡能國者
(A 扁左[忙]旁[可] は外字)
かな書きすれば、以下のようである。
やまとには むらやまあれど とりよろふ あまのかぐやま のぼりたち くにみをすれば くにはらは けぶりたちたつ うなはらは かまめたちたつ うましくにぞ あきづしま やまとのくには
古田武彦氏は、次のように問題を提起する。
| 「講演会では何回も「なぜ大和盆地で海が見えるのですか」と質問を良く受けてまいりました。今までは「良く考えておきます」とその度保留してきた。今回はこれを正面から取り組んでみて、確かにおかしい。万葉学者が「おかしくない」と言ってみても、常識ある人間からはおかしい。池のことを海原と言い換えても、他にそのような例があるかと確認すれば全然無い。典型的なのは「山常庭
村山有等 取與呂布 やまとには むらやまあれど とりよろふ」の中の「とりよろふ」の解釈に疑問を持った。なぜかというと万葉学者の解釈にはいろいろ有るけれでも、どんな解釈をしても、大和盆地にいろいろある岳(やま)の中で天の香具山が一番目立っているという意味には違いない。しかしこれは知らぬが仏で、奈良県の飛鳥に行ったことのない人は騙されますが、実際に行ってみたら一番目立たない山である。澤潟久孝氏の『万葉集注釈』という本の写真を使わせていただきますが、畝傍山、耳成山は立派ですね。香久山は目立たない平凡な山ですね。これは写真に撮れば良く分かる。上の二つは良く撮れる。香久山は写真に撮れば逆にどこかと探すぐらい分からない。よほど現地の人に確認しないと分からない。この写真には立派に写っているが、素人が撮ればそんなにうまく写らない。しかも高さは百六十三メートルしかなく、奈良盆地自身が海抜百メートルぐらいありますので、山の麓(ふもと)に立っている高さは、五十メートル位であるので、私が歩いても頂上までさっと十分ぐらいで上がって行けた。非常に低い丘である。それが山の中でも目立つ山とは言えない。これは明らかにおかしいと、おそまきながら気が付いてきた」。 |
そして、冒頭と末尾の2つの「やまと」に着目する。「山常庭 村山有等 蜻嶋 八間跡能國者」。最後の「八間跡」と表記する大和は他に全くない。その前の「蜻嶋」については次のように言う。
| 「これについて私の『盗まれた神話』で分析したことがありまして、これは古事記などに豊秋津島と言う形で出てまいります。この豊秋津に対して私は、これは「豊」は豊国のことであろう。豊前・豊後の豊国。「秋」と言うのは、例の国東半島の所に安岐町、安岐川がある。大分空港のあるところである。そこの港が安岐港である。しかしこの「秋津」は安岐川の小さな川口の港ではなくて、関門海峡からやってくると、安岐町のところが別府湾の入口になる。そうすると「秋津」は別府湾のことではないか。別府湾を原点にして、九州島全体を指すのが「豊秋津島」ではないか。そう考えた研究の歴史がある。そうするとこの歌の「秋津島」とは九州島のことではなかろうか。そう思い始めた。これを考えたときはおっかなびっくりだったのですが、さらに進んで別府湾なら「海原」があって「鴎(かもめ)立ちたつ」も問題なし。のみならず「国原に煙立つ立つ」も問題がなくなった。私の青年時代、学校の教師をやったのが松本深志高校。そこに通うとき浅間温泉の下宿させていただいた。坂を下り学校に通うとき、冬など温泉のお湯がずっと溝に流し出され、それが冷たい外気に触れて湯気が立ち上がっていて、本当に「煙立ちたつ」の感じだった。そこをぬうようにして降り、なかなかいい光景だった。浅間温泉のような小さな温泉でそうだから、別府となりますと日本きっての温泉の一大団地。そうすると、まさに「煙立ちたつ」ではないか。学校の授業の時は「民のかまどの煙が立ちこめ」と注釈にもそう書いてあったので「家の煙」だと解説していた。しかし良く読んでみると、「海原は鴎立ちたつ」は自然現象。鴎が自然発生しているのと同じように、それと同じく「国原煙立ちたつ」も自然現象。煙が自然発生しているのと同じ書き方である。同じ自然現象です」。 |
確かに温泉地では湯煙が見える。私も霧島の鹿児島大学病院に入院していた時に、周辺が湯煙だらけだったのを思い出す。そして、別府に「天香具山」はあるのか、と問う。
まず「天 あま」はあった。別府湾に「天 あま」はあるのかと調べると、まずここは『倭名抄』では、ここら一帯は「安万 あま」と呼ばる地帯だった。この間行ってきた別府市の中にも天間(あまま)区(旧天間村)など、「あま」という地名は残っている。天間(あまま)の最後の「ま」は志摩や耶麻の「ま」であり、語幹は「あま」である。奈良県飛鳥は「天 あま」と呼ばれる地帯ではない。現在でも大分県は北海士郡・南海士郡というのが有り、南海士郡は大分県の宮崎県よりの海岸から奥地までの広い領域を占め、北海士郡は佐賀関という大分の海岸寄りの一番端だけになっている。点に近い所だけだが大分市や別府市が独立して喰いちぎられていったことは間違いない。これはもう本来は北海士郡は別府湾を包んでいたに違いない。それで海部族が支配していて「天 安万 あま」と呼ばれる地帯だったことは間違いがない。それでは香具山はどうか。別府の鶴見岳の存在です。……ですからもう一言言いますと、「土蜘蛛 津神奇藻(つちぐも)」というばあいも、「くも」というのは「ぐ、く」は不思議な、神聖なという意味、「も」は(海の)藻のように集まっているという意味で、「くも」は不思議な集落という意味で、「津神奇藻(つちぐも) 土雲」は「港に神様をお祭りしている不可思議な集落」という誉め言葉なのです。それをへんな動物の字を当てて卑しめていて野蛮族扱いにイメージをさせようとしているのが『古事記』・『日本書紀』です。それを見て我々は騙されている。本来はこれは良い意味です。岡山県には津雲遺跡などがあります。そういう知識がありましたので、「ほ」は火山のことになる。それで平安時代に、この鶴見岳の火山爆発があり『三代実録』にめづらしく詳しい状況が書いてあります。頂上から爆発し、三日三晩かけて吹っ飛び、大きい磐がふっ飛んできて、小さい岩でも水を入れる瓶ぐらいの大きさの岩が飛んできた。又硫黄が飛び散って川に流れて何万という魚が全部死んだという非常にリアルな描写があります。現在はそれで一三五〇メートルで、今は隣の由布岳より少し低い。その鶴見岳は吹っ飛ぶ前は高さが二千メートル近くあったのではないかという話があり、もしそうであれば鶴見岳の方が高かった。それで元に戻り、鶴見岳には火軻具土(ほのかぐつち)命を祭っている。「か」はやはり神様の「か」で神聖なという意味で、「ぐ く」は先ほどの不可思議なという意味であり、「神聖な不可思議な山」が「香具山(かぐやま)」である。火山爆発で神聖視されていた山である。もう一つ後ろに神楽女(かぐらめ)湖という湖がある。非常に神秘的な湖ですが、その神楽女湖も、「め」は女神、「ら」は村、空などの日本語で最も多い接尾語で、これもやはり語幹は「かぐ」である。だから並んで山も「かぐ」、湖も「かぐ」である。ですからやはり本来のこの山の名前は「かぐやま」であろう。「香具山(かぐやま)」とは本来ここで有ろう。それで安万(あま)の中にありますから「天香具山(あまのかぐやま)」である。
|
ちなみに「国見町」をWikipediaで検索すると、以下の3例が出てくる。
- ・国見町(くにみまち) - 福島県伊達郡にある町。
- ・国見町 (長崎県)(くにみちょう) - かつて長崎県南高来郡にあった町。現在の雲仙市の一部。
- ・国見町 (大分県)(くにみちょう) - かつて大分県東国東郡にあった町。現在の国東市の一部。