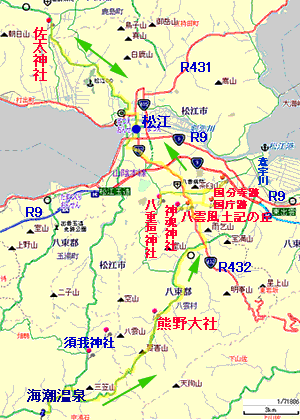2010.04.17日 れんだいこ拝
熊野大社(島根県松江市八雲町熊野2451。TEL0852ー54-0087)は出雲国意宇(いう)郡の名神大社で、出雲大社と共に出雲の国一之宮。熊野大社が本来の出雲国の一宮であったと推定できる。出雲国風土記には熊野大社と杵築大社(現出雲大社)の二社のみが大社であり、熊野大社が筆頭だった。
出雲国造神賀詞でも、「出雲の国の青垣山の内に、下津石根に宮柱太敷き立て、高天の原に千木高知りて坐す伊射那伎の日真名子、加夫呂伎熊野大神櫛御気野命、国作り坐しし大穴持命、二柱の神」と先に熊野大神の名が出る。
熊野大神/櫛御気野(クシミケヌ)命を御祭神を主祭神として祀る。出雲国風土記には伊佐奈枳乃麻奈子坐熊野加武呂乃命とあり、素戔嗚(スサノオ)命と同神とする説もある。「日本火出初之社」とも呼ばれており、十月には鑽火祭が行なわれる。創建は出雲大社より古い。
熊野大社絡みの国造家の出雲臣一族が出雲大社創建時に杵築に移住、分家し千家家、北島家となったと云う。出雲国造の末裔である出雲大社宮司家では、世継の神器として熊野大社から燧臼、燧杵を拝受することになっている。燧臼、燧杵は火を起こすための道具であり、熊野大社の鑽火殿に収納されている。
原出雲、元出雲に遡る。スサノウ出雲の御世になって、八岐の大蛇退治後に新たな伝説が加わっている。素戔嗚尊がこの地で結納の品として御櫛を櫛名田比売命に渡されている。これに因み札守所に八雲塗の櫛が頒布されている。「八雲立つ・・」の和歌はその時に詠まれたとの説もあり、そこから「八雲」の地名が付いたともいわれている。「熊」とは、「隈々しい(奥まっていて暗く、その意味で神々しい)」という意味で、「隈々しい場所」から名付けられている。延喜式には、熊野の名を持つ神社が五箇所あり、古代には各地にあった。現在は県道が通っているが「日本初之宮・須我神社」と向かい合っている。
日本書紀(720)に出雲國造をして厳神の宮を作らしむとの記載あり。出雲國風土記(733)、令義解(834)、日本三代実録(901)、延喜式(927)に熊野大神、熊野大社の記載あり。延喜式神名帳(927)に熊野坐神社と見え、日本火出初神社(ひのもとひでぞめのやしろ)とも称され、古来杵築大社(出雲大社)と並びて出雲の國の大社と遇された。意宇六社の一つ。