
(最新見直し2011.8.25日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、万葉集の文人歌について確認しておく。
2011.8.28日 れんだいこ拝 |
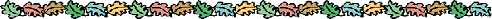
(165)萬葉集燈卷之四
平安 富士谷御杖著
本集卷之一 其四
藤原(ノ)宮之※[人偏+殳]民(ガ)作歌
持統天皇八年、清御原宮より此宮にうつり給ふ。その宮つくる時の※[人偏+殳]民がよめる也となり。されど、古言はたゞ、表のみをたのみがたきもの也。この歌のよみざま、いふかひなき※[人偏+殳]民のよめりともおぼえぬ詞づくりなれば、誰かは知らねど、※[人偏+殳]民が歌になしたるにもあるべし。かくいふは、はゞかる所あればなり。下にいふをみて思ふべし。されどなほ、※[人偏+殳]民がうちにも心あらむは、かかる歌よむまじきにもあらねば、ひとへにはいひがたし。
八隅知之《ヤスミシシ》。吾大王《ワガオホキミ》。高照《タカテラス》。日之皇子《ヒノミコ》。荒妙乃《アラタヘノ》。藤原我宇倍爾《フヂハラガウヘニ》。食國乎《ヲスクニヲ》。賣之賜牟登《メシタマハムト》。都宮者《オホミヤハ》。高所知武等《タカシラサムト》。神長柄《カムナガラ》。所念奈戸二《オモホスナヘニ》。天地毛《アメツチモ》。縁而有許曾《ヨリテアレコソ》。磐走《イハバシノ》。淡海乃國之《アフミノクニノ》。衣手能《コロモデノ》。田上山之《タナカミヤマノ》。眞木佐苦《マキサク》。檜乃嬬手乎《ヒノツマデヲ》。物乃布能《モノノフノ》。八十氏河爾《ヤソウヂガハニ》。(166)玉藻成《タマモナス》。浮倍流禮《ウカベナカセレ》。其乎取登《ソヲトルト》。散和久御民毛《サワクミタミモ》。家忘《イヘワスレ》。身毛多奈不知《ミモタナシラズ》。鴨自物《カモジモノ》。水爾浮居而《ミヅニウキヰテ》。吾作《ワガツクル》。日之御門爾《ヒノミカドニ》。不知國依《シラヌクニヨリ》。巨勢道從《コセヂヨリ》。我國者《ワガクニハ》。常世爾成牟《トコヨニナラム》。圖負留《フミオヘル》。神龜毛《アヤシキカメモ》。新代登《アラタヨト》。泉乃河爾《イヅミノカハニ》。持越流《モチコセル》。眞木乃都麻手乎《マキノツマデヲ》。百不足《モヽタラズ》。五十日太爾作《イカダニツクリ》。泝須良牟《ノボスラム》。伊蘇波久見者《イソハクミレバ》。神隨爾有之《カムカラナラシ》。
〔言〕八隅知之より日之皇子 まへに註せるに同じ。これは、 持統天皇をさし奉れり。荒妙云々 たへは、布の古名也。いにしへは、栲《タヘ》といふ物もて織れりければ也。妙の字は、かりたる也。やがて、卷三に、荒栲藤江之浦爾《アラタヘノフヂエノウラニ》とかゝれたり。その布の中にも、いと麁なるを、あらたへといふ也、鎭魂祭祝詞に明妙《アカルタヘ》・照妙《テルタヘ》・和妙《ニゴタヘ》・荒妙《アラタヘ》云々 祈年祭にも、かくの如くみゆる、これなり。藤もておれるは即、あらたへなれば冠らする也。かく冠詞を置たるは、この藤原の地のよきことを、ほむるにかへたる也。あらはにほむるよりも、思はせたるは、おもひやりいと深きが故也。我《ガ》とは、乃《ノ》といふにはたがひて、それにはたらきをあらせていふ詞なる事、くはしく上にいへり。君が代とつねによむを、君のよとは絶ていはぬに思ふべし。梅が香とつねによむを、古今集に、梅の香のふりおける雪にまがひせばといふ歌あり。源氏物語をとめの卷に、梅の香とかけり。その餘にはみず。これらは、香の方を主にいはむがため也。これひとへに、藤原の美地なるをさとせる也。荒妙乃と冠辭をおけるをも、おもひあはすべし。宇倍とは、此の卷の終にも、高野原(167)之宇倍《タカノハラノウヘ》とよめるも同じ。字倍は、方《ヘ》といふに同じ。方《ヘ》は、その方をさしていふ詞なり。この藤原に都し給ふなれば、方《ヘ》とはいふまじき事のやうなれど、なに事も、さしつけていはぬが、わが御國ぶりなれば、うちゆるべて、藤原がうへとはよめる也。かやうの詞づかひは、みづからさかしらならじとての事なり。上古の風俗、これひとつにも思ふべし。後世人のおもひもかけぬ詞づかひなり。○食國乎 まへにくはしくいへり。 帝のしろしめす國をひろくいふ名なり。○賣之賜牟登 賣之《メシ》は、見之《ミシ》と同じと眞淵が説也。げに、賣《メ》・見《ミ》通音なれば、同詞なりといはむに、理なきにはあらねど、通音の事、通ふとだにいへば、さてやみぬる事、世のならひとなれゝど、通ふは通ふにて、そのかよふにつけて義のわかるればこそかよへ。かよふをもて、同じとはいふべからざる事なり。もとより。見《ミ》は以緯なり。賣《メ》は江緯なり。されば、見之《ミシ》は、見たまふ事也。賣之《メシ》は、めさるゝにて、事はことなり。かく、異事ながら、見之《ミシ》とも、賣之《メシ》ともいふは、ともに、食國をしろしめす也としるべし。これにかぎらず聞之《キコシ》も亦しろしめす事をいふにておもふべし。されど、くはしくいはゞ、見之《ミシ》は、御目のうへにて、天下の事を見あきらめさせ給ふなり。聞之《キコシ》は、御耳のうへにて、天下の事を聞あきらめさせ給ふなり。賣之《メシ》は、天下の事をめしつどへさせ給ふなりとしるべし。登《ト》は、次の句の等とともに、所念奈戸二《オモホスナベニ》にうちあふ也。○都宮者 古點みやこにはとあれど、にもじ用なし四言にはいふべし。眞淵、おほみやは、又みあらかはともよめり。みあらかのかもじは、處の義にて御在處《ミアラカ》なり。いづれにもあるべきが中に、おほみやは(168)の方穩しかるべし。者《ハ》もじ、大かたにいはゞ、乎《ヲ》といふべき所也。食國は乎《ヲ》といひ、都宮は者《ハ》といへる、めをとゞむべし。食國をめし給はむ爲に、都宮をば高しらせたまはむとおもほす心なり。此都宮にて、食國をめし給はむとおもほす心をおもはせむがために、乎《ヲ》とよみ、者《ハ》とよめる也としるべし。高所知武等 高は前にいへるが如く、たけき心にて、御稜威《ミイツ》を云也。されど、この稜威もと、大かたの威にはあらず。くはしくは古事記燈にいへり。○神長柄 まへに同じ。此神ながらと、おもほすなべにの二句の間に、上の荒妙乃以下六句は、はさまりたる心にみるべし。されば畢竟、荒妙乃の上に、神長柄の一句はあるべきを、こゝにおきたる也。かく上にあるべきをこゝに置たる所以は、例の標實の法を以てなり。此神長柄は、持統天皇の御くしびをたゝへ申せる也。奈戸二とは、二事のならぶをしめす詞なり。されど、もとよりならぶべき事を、奈戸二とよむは詮なし。ならぶまじき事の並ぶをさとす事、此の詞の詮也と心うべし。さればこゝも大かたの人事は、心にもおもふばかりにて、いまだ發言もせぬに、その事と、他の事、ならぶべきにあらず。しかるに此 帝遷都の事を御心におぼしめすとならびて、良材おのづからあつまり來るを、奈戸二とはいふなり。おもほすといふ詞、かろくみまじき也。いまだ御心のうちになしていへる妙也。まことは、勅命もありつればこそ、さわぐ御民ともよめれ。それをばかく、御心のうちなるほどになして、詞をつけたるは、ひとへにこの みかどの神にますを思はせむがため也。古人の詞のつけざまおもふべし。○天地毛云々 天地もよりてとは、天神地祗も、(169)帝に御心をよせ給ふを云。これ、わが御教の大本にて、よろづの所思、天神・地祗の御力にて成就したまふを、いたりとする也。この毛《モ》もじは、天も・地もといふ心におけるにはあらず。その故は御民はすべて、 天皇の御心によりてつかへまつるは、いふもさら也。その御民のみならずとの心を、毛《モ》とはよめる也としるべし。下に御民|毛《モ》とあるは、又この天地を主としておけるなり。詞の條理みなしかり。心えがたからむ人は、わが門にまねぶべし。安禮《アレ》は、安禮婆許曾《アレバコソ》の婆《ハ》をはぶけるなり。許曾は、下の浮倍流禮《ウカベナガセレ》の句にてうけたる也。許曾《コソ》の義は、前にくはしくいへり。こゝも、天地のよるにあらずは、なにの妙用ありて、かくおのづから良材こゝにあつまりくべき。との心なり。○磐走云々 走は、橋の假名なり。くはしくは前にいへり。これは、藤原まで行程いとはるかなるを、おもはせむがための冠なり。○衣手能云々 くはしくは、眞淵冠辭考に論らへり、その説、手長能大御世《タナガノオホミヨ》・手長乃御壽《タナガノミイノチ》など祝詞にある心にて、いにしへは袖せぱく長かりければ、手長とつゞけしにや。又袖は、即衣の手なればにや。又たたなはるといふ心につゞけたる歟《カ》。と三説をあげたり。されど、たゝなはるは迂遠なるべし。手《タ》とかゝれる歟。又は手長とつゞけたるかなるべし。田上山は、淡海國栗本郡なり。○眞木佐苦云々 これも、くはしく冠辭考にあげつらへるをみるべし。されど、眞木は檜なり。とさだめていふまじき也。檜は眞木ともいふべし。檜は眞木なるが故に、かく冠とはしたるものなり。佐苦《サク》は、かのぬしが説のごとくいにしへは、ひきわる事はせで、斧などにて析たるが故なり。嬬手の嬬は假字にて、拆たる木は(170)必|※[木+爪]《ツマ》あればいふなるべし。手《テ》は麻手《アサテ》などいふが如し。たゞ添たる辭也。と古釋にはみゆれど、しかありては、たゞその木の※[木+爪]をいふ詞となりて、※[木+爪]ある拆木の事にはならざるべし。されば思ふに、手《テ》といふ事、いかなる故とは明らめざれども、※[木+爪]ある拆木の、宮材の用に便よく、木造りなしたる名とおぼしき也。麻も物に用ひむに、便よくしなしたるを、いふなるべくおぼしければ也。乎《ヲ》は、さばかり藤原よりは遠き田上山なれば、その檜のつまでは、宇治川にながすべき事にあらぬを、との心を思はせたる也。○物乃布能云々 物とは、兵具《ツハモノ》の事をいふ歟。そのつわものを執る人のともがらを、物乃布といふにや。冠辭考に【眞淵】ちはや人うぢとつゞけたる心にて、うぢは稜威《イツ》にかよはせたるなりといへり。此集卷六に物部乃八十友能壯者《モノノフノヤソトモノヲハ》。また物負之八十伴緒乃《モノノフノヤソトモノヲノ》などよめるは、そのともがらの多きにかゝれる也。又神典に、宇受賣命《ウスメノミコト》あり。この御名のたぐひに、宇知とつゞけたるにや。この御名の義は、古事記燈にくはしくいへり。爾《ニ》もじは、此宮造るに便よきをおもへる也。○玉藻成云々 かのつまでどものうかびながるゝさまを、玉藻にたとへたるなり。成《ナス》の事まへにいへり。如といふ類也。されど、如にはたがひて、成《ナス》はまことはさならぬものを、しか見なしいひなすを別とす。成《ナス》に、如の字をかられたるは、たゞ義のかよへるをもて也。これによりて、混じいふまじき也。如しを成《ナス》といふは古言也などおもふも非なり。如《ゴト》・成《ナス》ふたつながら、いにしへ用ひたる詞なるをもて、同詞ならぬをしるべし。かくたとへたるは、うかびながるゝ良材どもの、ひまなきさまを思はせむとて也。流禮《ナガセレ》は、前にいへるごとく、天地・神祗(171)の御わざにて、ながしたまふをいふ也。上の天地毛縁而有許曾《アメツチモヨリテアレコソ》をはづさずして、みるべし。これをとるより、人力とせり。禮《レ》は、上の許曾のうちあひ也。○其乎取登云々 其《ソ》は、それなり。されど、曾《ソ》といひ、曾禮《ソレ》といふ、同じからず。許禮を許、和禮を和、可禮を可、多禮を多といふ類、皆義あるを、世には混じたり。許禮を許、曾禮を曾といふを、古言也などおもふ人あるは麁なり。此集に、許禮能《コレノ》ともいへるをおもふべし。すべて、禮《レ》もじをそふる時は、外に對する物ある義なり。禮《レ》もじなきは、對する物なく、やがてその物をさす時の用なり。この法いづれも同じ。さればこゝも、此良材ども、外に對する物なければなり。取とは取あぐる也。登《ト》は、とての心なり。○散和久御民毛 さわぐは、その人夫のいと多くて、いそしきさまを云也。毛《モ》は、天地・神祗のみならざるをさとしたるなる事、上にいへるが如し。委しくいはゞ、天地・神祗の御心をよせ給ふにつれて、おのづから御民も、といふ義也。天地・神祗を主とたてゝ、自然のかたちにみるへし。畢竟命じもし給はぬにとの心なり。○家忘 家には父母妻子もありて、しばしも家をはなるれば、忘れがたき通情をたてゝいふ也。ひとへに、 天皇の御徳によれるよしを云也。○身毛多奈不知とは、身はもと、安逸をこひねがふが常なる事をたてゝいふにて、毛《モ》は、さる身なれどもといふ也。多奈は、契冲は、たなびくを輕引とかける心にて、身を輕むずる事かといへり。いかゞあらむ。東麻呂は、直の義といへり。長流も同説なり。又、勞をいふともいへり。しかるに、此集卷九に、金門爾之《カナドニシ》。人乃來立者《ヒトノキタテバ》。夜中母《ヨナカニモ》。身者田菜不知《ミハタナシラズ》。出曾相來《イデヅアヒケル》。また卷十三に、葦(172)垣之《アシガキノ》。末掻別而《ウレカキワケテ》。君越跡《キミコユト》。人丹勿告《ヒトニナツゲソ》。事者棚知《コトハタナシリ》。などよめり。これらの歌につけて思ふに、知る知らずといふ詞のかゝる物なる事明らかなれば、これらの諸説かなへりともおぼえず。さればおもふに、多奈とは、から人の恕といふ心にて、その物の、欲せざる所を思ひて、いたはる事をいふとおぼしき也。いづれも/\、此義にてかなへり。身毛とも、身者とも、また事者ともかけるを思ふべし。されどいかなる故にて、これをば多奈とはいふらむ。おもひよるよしもあれど、くはしくも考へぬ事は、なか/\なればいはず、これ又、 天皇の御いつをたゝへたる也。○鴨自物云々 水に浮居といふ事に冠らせたる也。自物《シモノ》といふは、常にその物のごとくいふ心に用ひたり。犬自物《イヌシモノ》・馬自物《ウマシモノ》などの類、いと多し。この例にたがへるやうなるは、男自物とよめる也。これはなほ、そこにていふべし。自《シ》は、もし、時自久《トキシク》の自にや。しからば、時自久《トキシク》は時頻《トキシク》の義なれば鴨じき物といはむを、つゞめていふにやあらむ。しくは、重・及などの字をあてられて、間なきかたちをいふ詞なれば、鴨と間の透《ス》かぬ物、といふ心にもやあるべき。これは、かの材をとりあげむために、御民どもの舟にのりて、川中にうかびをるさまを云。而《テ》もじ、古來、論區々なり。上にも、而《テ》もじの事をいへれど、而《テ》もじの義を心うべきには、此歌最上なり。學者よく/\めをとどむべし。或説に、この而《テ》もじ、下の泉乃河爾持越流といふにつゞけてみるべしといへれど、しかしては、不知國依巨勢道從といふ句に、その終なくて、心えがたし。又は、この而《テ》もじの下に脱語あるべしなどもいへるは、而《テ》もじの義をよくも探らぬ故にて、此、水に浮ゐて吾作る。と直(173)につゞけるが、理なさにいへる説どもなれどしからず。此|而《テ》もじに、水にうきゐてその良材どもをとりて、藤原にはこびて、切もしこなしもして、などいふほどの事をもたせたる也。さて、不知國依以下は、又別事としてみざれば、事交はりて義をなさゞる也。おのれ今かくいふを私なりとみる人もよには多かるべけれど、大かた、而《テ》もじの義、水にうき居ての下、直につゞく詞ならば、もとより而《テ》もじの詮はなき也。數事をひとつの、而《テ》もじにもたするに、而《テ》もじの詮はある事なり。これにかぎらず、すべての脚結みなその法かくのごとし。わが門に學ばぬ人は、信じがたかるべし。上古の用ひざま、此歌のやうにはなくみゆるも、この法を出る事なし。後世直言のひがみに、この而《テ》もじの心えがたき也。かへす/”\、後世の弊をさとるべき也。○吾作云々 吾とは、われ一人の事にいふにあらず。※[人偏+殳]民のともがらをひろくさしていふ也。我道・我國などいふがごとし。【我國吾我などすべて文字にはかゝはらぬなり。】日之御門は、日之《ヒノ》は、日神の御子のおはします宮の御門なれば也。大かた、宮をいはむとて、御門をもて詞とする事、わが御國言のてぶりなり。さればこゝも、猶宮をさしていふ也と心うべし。爾《ニ》は、われらがつくる宮處にといふ心なり。下の泝須良牟にうちあへるにて、此宮にとてのぼすらむの心なり。○不知國依云々 しらぬ國とは、いと遠き國をいふ也。大かた、ゆきて國こそあらめ。わが御國内にしらぬ國とてはあるべくもあらぬを、かく不知國といふは、いと/\遙なる國々をおもはせむがための詞づくり也。依《ヨリ》は、此下の從もふたつながら泉乃河爾持越流におちゐるなり。巨勢道は、この都にたよりよき道なれば也。(174)遙なる國々より良材をきり出て、巨勢の道より泉川に持こすをいふ也。○我國者云々 これより以下五句は、泉【出、とかけたるなり。】といはむがためのよせにて、よせながら此 帝をほぎ奉れる也。されば、此五句は、こゝにはさめる也とみるべし。常世爾成牟、これ、みかどの御徳にて、神龜さへ出たるを云也。常世とは、こゝは常《トコ》しき世といふ也。この名もと、神典に【古事記上卷】常世往《トコヨユク》とあるこれなり。大かた天地二性をそなふるを、わが御國ぶりの大本とす、しかるを何事をもひとつにたつるを、常夜と名づく。晝なくて、常に夜なる義也。これ、深き理ある事、古事記燈にいへるをみるべし。他域の俗は、みな何事をもひとつにたつれば、すべて他域をさして、常世といふ也。 垂仁天皇の御紀に神風伊勢國則常世之浪重浪歸國也傍國可怜國也《カムカゼイセノクニハトコヨノナミノシキナミヨスルクニナリカタグニノウマシクニナリ》とある、即これ外蕃を、常世《トコヨ》國といへる也。されば、雁・燕などの常世より來るといふも、他域をさせるなり。いつの頃よりか、それを蓬莱の事とす。先達、常夜と常世はことなりといふ説もあれど、上古にはことならぬ事、神典すでに、常夜とも常世ともかきかへられたれば、これにしるきをや。その説、もとは此歌などよりいへるなるべし。これはたゞ、世の常《トコ》しへなるを常世といへるにて。後世のも、上にいへる本義より、うつりたるなるべし。これは、常世國の事にはあらずかし。○圖負留神龜とは、日本紀廿七云 天智天皇九年六月邑中(ニ)獲v龜(ヲ)背書2申(ノ)字(ヲ)1上黄下玄とあるをおもへるにや。禹の時、龜負v園(ヲ)出2洛水(ニ)1とあるを思へるにや。毛《モ》は圖おへる神龜はよにありがたき物なるに、それもとの心也。この外、神瑞多きを思はせたる也。○薪代登とは、あたらは、(175)新の字の義となれるも、もとは、新らしき物は、なれ、古びむ事のをしき心よりいふ也。此集卷廿|年月波安多良々々々爾《トシツキハアタラアタラニ》などよめり。里言にアツタラといふ、是なり。後世も、あたら夜の月と花とをなどよめり。この新京に、宮しろしめす御はじめなれば也。登《ト》はとての心なり。神龜が心に、あたら代と思ひていづるよしをいふ也。泉は、出といふによせたる也。前にいへるがごとく、こゝまで五句は挿める也とみるべし。○泉乃河爾持越流云々 泉河は、山城國相樂郡なり。 崇神天皇の御紀に、もとの名、挑河《イドミガワ》なるよしみゆ。今この河を木津といふは、かくやまとに、宮材などをうかべてのぼすにたよりよかりければ、名づけたるにや。持越流は、かの遠國より巨勢路をもち來て、此泉河にうくるを云。越としもいふは、その國にてきり出けむ山にも、又路のほどにも、河・海など必ありて、そこにうけたりし材なるを、一旦陸路にあげて、さて又泉河にうかぶる故にいふ也。○眞木乃都麻手乎 上なる眞木佐苦檜乃嬬手にいへるに同じ義なり。されど前のは田上山の材《キ》なり。こゝは、かの不知國よりのぼす材《キ》なり。ひとつにみまじき也。古註には、これをも、やがてまへの嬬手とひとつにみて、田上山のなりと心えためれど、前にもいへるが如く、大かたかみしもの語意もとゝのはず。しかのみならず、まへに檜乃嬬手とよみ又同じ嬬手をばふたゝびいはむは、いと稚く、古人の詞づくりにあらねば、かへす/\、これは、前のとはことなるぞかし。乎《ヲ》は、此宮に來べきにあらぬ遠國の材なるに、それをとの心也。〇百不足云々 百の數にたらぬものゝ冠也。百傳ふとよむも同じ。これは、五十に冠らせたる也。さ(176)れど、五十日太は筏の假字なり。五十日をいかといふ事、例多し。土左日記によそか《四十日》・いか《五十日》まで我はへにけり。ともよみ、宇都保物語・源氏物語等に、子うまれての五十日をほぐいかのもちひ多し。くはしく、土左日記燈に引おけり。かの良材をば筏につくりて、泉河をのぼすを云。良牟《ラム》は、ある註に、田上の宮材につかへまつるものゝ、おしはかりていへるなれば、良牟《ラム》とはいへりと註したれど、これは、中の良牟《ラム》の例にて、次のいそはくに、上の義をつゞけて心うべき法なり。かの註、語勢にも、詞の法にもそむけり。中の良牟《ラム》は、たとはゞ、いかだにつくりのぼすなるいそはくみればといふべきを、そのわざをまのあたりにみぬが故に、良牟とはよむ也としるべし。此卷の末に行來跡見良武樹人友師母《ユキクトミラムキビトトモシモ》とよめるなど、此例なり。この京になりても、多く用ふる例にて、けむにも、此例ある也。大かた、事がらにより、時・所により、妖氣にさはるべき事には、さだかなる事をも、わざと、良牟《ラム》・計牟《ケム》など、ゆるべてよむも常也。これもたゞ、そのわざをまのあたりみぬゆゑのみにもあらず。さだかにいふ時は、あまりに、帝の御徳をたゝへ奉る事、めざましければにもあるべし。この良牟《ラム》、この句ばかりにかけてみるべからず。上の不知國依以下、この良牟の中なりとみるべし。何十句にても、下におく詞、上を自在する事、鳥・魚などの、尾もて身を自在するがごとし。舟の舵《タギシ》をも思ふべし。【舵は、今のかぢなり。和名抄に、舟尾也とあり】○伊蘇波久見者とは、 孝徳天皇の御紀に、天平勝寶二年三月戊戌駿河(ノ)國(ノ)守從五位(ノ)下|楢原造東人《ナラハラノミヤツコアヅマト》等(ヲ)於2部内廬上郡多胡(ノ)浦(ノ)濱(ニ)1獲《テ》2黄金(ヲ)1献v之【練金一分沙金一分】於v是東人等(ニ)賜2勤臣《イソシノヲミノ》姓1云々。文徳實録(ニ)云仁壽(177)二年二月乙巳參議正四位(ノ)下兼行宮内卿相模守|滋野《シゲノ》朝臣|貞主《サダヌシ》卒(ス)貞主(ハ)者右京人也曾祖父大學(ノ)頭兼博士正五位(ノ)下楢原(ノ)東人該浦通2九經(ニ)1號(シテ)爲2名儒(ト)1天平勝寶元年爲2駿河(ノ)守(ト)1于v時出2黄金(ヲ)1東人探(テ)而獻v之(ヲ)帝|美《ホメタマヒテ》2其功(ヲ)1曰2勤哉《イソシキカモ》臣(ト)1也遂(ニ)取2勤臣之義(ヲ)1賜2姓(ヲ)伊蘇志臣《イソシノヲミト》1云々 又仲哀天皇の御紀に筑紫(ノ)伊覩《イトノ》縣主(ノ)祖|五十迹手《イトテ》【中略】 天皇即|美《ホメタマヒテ》2五十迹手(ヲ)1曰2伊蘇志《イソシト》1故時人號2五十迹手之本(ノ)土《クニヲ》1曰2伊蘇《イソノ》國(ト)1今謂2伊覩《イト》1訛也《ヨコナマレルナリ》また 聖武天皇の御紀に加以祖父大臣乃殿門荒穢須事旡久守在《シカノミナラズオホヂヲトドノトノドアラビケガスコトナクモリマ》【自之《シシ》】事伊伊蘇《コトイソ》【之美《シミ》】宇牟賀《ウムカ》【斯美《シミ》】忘不給《ワスレタマハズ》【止自※[氏/一]奈母《トシテナモ》】孫等一二|治賜《ヲサメタマヒ》【天《テ》】云々 又日本記(ノ)通證といふものに、かの 仲哀天皇の御紀なる伊蘇《イソノ》國を、風土記(ニ)作2恪勤《イソノ》國(ニ)1とみゆ。【此風土記は筑前歟】又比集卷四に勤和氣登將譽十方不在《イソシキワケトホメムトモアヲズ》など、さま/\みえたり、【これは、わが友隆※[王+連]が抄録をもて、わが管見を補へる也。みたる書の數も、抄録の數も、予は、隆※[王+連]が十が一なり。】又 敏達天皇の御紀にも、勤乎をいそしきとよめる、みな、そのなすわざの怠なきを云。いそぐ・いそがはしなどいふもこの詞也。波九《ハク》の波《ハ》は伊蘇布《イソフ》といふ布《フ》を、波《ハ》にかよはして、やがて九《ク》を添たるなり。良九《ラク》・計九《ケク》・麻九《マク》・左九《サク》など、いづれも、その詞の韻を同韻にかよはして、やがて、九《ク》をそふる格なり。すべて、この類の詞は、用の詞にかたちをあらせていふ時の用なり。予が隨筆に論らへる老らくの條をてらして心うべし。さればこゝも、そのいそはしき體をみればといふほどの心也としるべし。見者は、見ざりしほどの心とは、たがふをいふ也。すべて、何|婆《ハ》といふ詞の心得、みなかくのごとし。こゝは、此 帝の御徳、今までよりもひときはめざましくおはします心をさとしたる也。○神隨爾有之 古點、かみのまゝならしとよめるはうけがたし、ある點、かむながらならしとよめり。まゝとよめるに(178)くらぶれば、ながらとよめるはめでたけれど、ながらの義一首に切なりともおぼえぬがうへに、此兩訓ともに八言なり。されば、かむがらならしとよむべし。 天皇やがて神にますよりの事ならしといふ心也。もし、神にまさずば、御民はさら也。天地・神祇御心はよせ給ふまじければ也。ならしは、爾有之《ニアラシ》のつゞまれるなり、良之《ラシ》は、さだかには定めがたき所あれど、十に八九は、しかならむとおぼゆる事にいふ脚結也。かく、神までも御心をよせ給ふばかりの帝にませば、神がらなる事さだかなれど、さだかにいはむはさかしらにて、さま/\弊もあるべければ、良之《ラシ》とはよめる也。
〔靈〕此歌、表は、この みかど遷都したまふにつきて、天地・神祇も御心をよせ給ひ、諸氏も身をもいとはずつとむるさまをみれば、 帝の御徳今ひときはめざましくますを、驚き歎じたるによみふせたる也。されど、これもし倒語にあらすば、必諂諛におつべし。古人、さるいたりなき事を直言する物にあらねば、これ疑なく、此遷都に※[人偏+殳]せらるゝ諸民外見こそ、家をも身をも忘れてつかふまつるやうにはみゆれ。實は、家をはなれ、身を勞して、よろこばしきわざにあらねば、その心中には、遷都の役をわぶる心必然なる事なり。しかれども、公をおそりて、いさゝかもさるけしきもみせぬ、いかに心くるしかりけむ。此歌よめる※[人偏+殳]民、みづから深くわびしく思ふ心をば諸民のうへに恕して、詞をつけたる歟。又は前にいへるが如く、※[人偏+殳]民の名をかりての歌ならば、ふかく民をあはれめる心なり。大かた、遷都に民を因しむる事、甚しきを歎きたる、げにその歎(179)ことわりなる事也。もし、此歌實に、※[人偏+殳]民ならば、※[人偏+殳]民いかなりしものぞ。此詞のつけざまに、その人ざまのめでたさもおしはからるゝ也。うはべは、ひたぶるに帝の御徳をたゝへ奉りて、ふかく遷都の弊をなげきたる詞のつけざま、よく/\めをとゞむべし。
右日本紀(ニ)曰朱鳥七年癸巳(ノ)秋八月幸2藤原(ノ)宮地(ニ)1八年甲午(ノ)春正月幸2藤原(ノ)宮(ニ)1冬十二月庚戌(ノ)朔乙卯遷2居藤原(ノ)宮(ニ)
從2明日香《アスカノ》宮1遷2居藤原(ノ)宮(ニ)1之後|志貴皇子《シキノミコノ》御作歌
※[女+委]女乃《タワヤメノ》。袖吹反《ソデフキカヘス》。明日香風《アスカカゼ》。京都乎遠見《ミヤコヲトホミ》。無用爾布久《イタヅラニフク》
〔言〕古來、※[女+采]とあれど、※[女+采]は、字彙に※[女+采](ハ)倉代(ノ)切音菜。女(ノ)字とみゆ。しかれば、※[女+采]女とはいふべからず。ある説に、※[女+采]は、※[女+委]の誤なるべし。字書に、※[女+委]は、弱好の貌とありといへり。これしかるべし。たわやめは、たわやぎめといふな、はぶきたる也。たわはとをともいひて、すべて物のちからなく、たわ/\としたるを云。これは、宮女をひろくさしたまへるなるべし。されど、かく廣くいふ中に、さす人はある事、古言のならひ、前にいふが如し。○袖吹反 風の袖をふきてうらがへすを云。下のいたづらにふくに照らして思ふに、吹反といふにて、風のつねに、※[女+委]女の袖に馴て袖ふきかへすを、心やりにもしたらむやうによませ給へる也。○明日香風とは、明日香にてふく風を云。佐保風・いかほ風などよめるに同じ。これは、藤原宮にうつらせ給ふまでの、もと(180)の宮地にて吹ける風をさしたまへる也。されば、上の二句も、もとの明日香の宮にはべりし程、宮女の袖に、風の馴たりしを云也。○京都乎遠見 乎見の義、まへに釋せるが如し。京都とは、今の藤原宮をさし給へる也。明日香風の、今の都にゆきて、宮女の袖をふかむと思へど、此新京まで吹來む事の遠くて、吹かよひがたさにといふ也。これ皆、風の心にしてよみ給へる也。○無用爾布久 今は、明日香の里には、宮女の袖もあらねば、いたづらにふくとはよませ給へる也。いたづらにといふ詞は、必なすべき事のあるに、その事をもせぬをいふ詞なり。されば、こゝも※[女+委]女の袖をふきかへし馴たる風の、かへすべき袖もなきをいふにて、風の心も、あへなくさぶしからむをおぼして、無用爾布久とは、よませ給へるなり。
〔靈〕此御歌、表は、明日香にて、吹かへし馴し宮女たちの袖もなくて、今は、新京にふきかよはむ事も遠ければ、むなしく、もとの都にふきをるその風のこゝち、いかにあへなく、物さぶしくおぼゆらむ。と風の心をあはれみてよませ給へるなり。されど、もと、非情なる風を、心あるやうにいひなし、かつ、風は、明日香より藤原まで吹かよはむにかたきばかりの物にもあらぬを、都の遠さに行がたき事をいひ、大かた※[女+委]女の袖をふくを、ふく風の詮のやうによみなし給へる御詞づくり、直言たるべきやうなし。風の心をいたはり給ふも、もとより、古人の歌とよむべき情にあらず。さればおもふに、此皇子は、 天智天皇の御子 光仁天皇の御父にて、追號したてまつりて、春日宮御宇天皇と申せり。この皇子、明日香にとまり居たまひて新京につかふまつる御思(181)ひ人のあひがたさを佗て、その人につかはされし御歌なる事、明らか也。されど、これをいさゝかもあらはにおほせらるれば、遷都をうらみたてまつり給ふになりぬべきを、はゞかりたまへる御詞づくり也。公私を、詞のうちにそなへて、いづれにもよらぬ御詞づくり、めでたしともよの常なり。歌は、いかで、かくよまゝほしくぞおぼゆる。此集中の歌、いづれともいひがたきが中に、この御歌は、妙中の妙ともいふべき御詞づくり也かし。上古の人の倒語の道に心をもちひたりし事、このひとつにも思ふべし。
藤原(ノ)宮(ノ)御|井《ヰノ》歌
これ、新京なる御井なり。この歌、作者なきは、これも、志貴皇子の御歌にや。此端作、こゝろえある事、この下にいふべし。
八隅知之《ヤスミシシ》。利期大王《ワコオホキミ》。高照《タカテラス》。日之皇子《ヒノミコ》。麁妙乃《アラタヘノ》。藤井我原爾《フヂヰカハラニ》。大御門《オホミカド》。始賜而《ハジメタマヒテ》。埴安之《ハニヤスノ》。堤上爾《ツヽミノウヘニ》。在立之《アリタヽシ》。見之賜者《ミシタマヘバ》。日本乃《ヤマトノ》。青香具山者《アヲカクヤマハ》。日經乃《ヒノタテノ》。大御門爾《オホミカトニ》。春山跡《ハルヤマト》。之美佐備立有《シミサヒタテリ》。畝火乃《ウネビノ》。此美豆山者《コノミツヤマハ》。日緯能《ヒノヌキノ》。大御門爾《オホミカドニ》。彌豆山跡《ミツヤマト》。山佐備伊座《ヤマサヒイマス》。耳爲之《ミヽナシノ》。青菅山者《アヲスガヤマハ》。背友乃大御門爾《ソトモノオホミカドニ》。宜名倍《ヨロシナベ》。神佐備立有《カミサヒタテリ》。名細《ナグハシ》。吉野乃山者《ヨシヌノヤマハ》。影友乃《カゲトモノ》。大御門從《オホミカドユ》。雲居爾曾《クモヰニゾ》。遠久有家留《トホクアリケル》。高知也《タカシルヤ》。天之御蔭《アメノミカゲ》。天知(182)也《アメシルヤ》。日御影乃《ヒノミカゲノ》。水許曾波常爾有米《ミヅコソハツネニアラメ》。御井之清水《ミヰノマシミヅ》
〔言〕八隅知之以下、日之皇子以上、まへにいへるに同じ。これも、 持統天皇をさし奉れるなり。和期とかゝれたるは、賀於とつゞく音便のまゝにかゝれたる也。〇麁妙乃云々 上に、藤原とつづきたるに同じ。藤井が原は即藤原なり。もとは、藤井が原といひけむをつゞめて、藤原といひなりしなるべし。爾もじは、こゝならでも、所も多かるにとの心をいふ也。さて下に、此御井をほめたるに應ぜり。○大御門云々 御門をもて、大宮をさとす事、前にいへるが如し。門は大かた、その宮の咽喉なれば也。これらにさへ、わが御國言のならひはそなはれるをや。大御門始賜とは、こゝに遷都し給ふを云也。而《テ》もじの義、まへにくはしくいへり。こゝに、新京をはじめ給ふと、埴安の堤の上にたゝせ給ふは、事、次第につゞかぬ御わざなるを思ふべし。○埴安乃堤上爾 これは、埴安池の堤なり。此集卷二にしかよめり。香具山のすそへつゞきて、いと高き堤なりけるなるべし。○在立之云々 あり何といふ詞古言に多し。古事記上卷の歌に佐用婆比爾《サヨハヒニ》。阿理多々斯《アリタタシ》。用婆比爾《ヨハヒニ》。阿理加用婆勢《アリカヨハセ》【長歌上下畧】此集中にも、この例多し。かく用ふる心得は、【これは、上つ世の挿頭なり】ありわたるかたちをいふ詞なり。此集中に、戀乍不有者《コヒツヽアラズハ》などよめる例にて、いづれも同じ。或説に、ありは、昔今と絶せぬ事にいへば、 天皇はやくより、此堤に立たまひてみやりたまひしをいふ也とあるは、近きがごとくにして遠し。わが伯父皆川※[さんずい+其]園、すべて書をみるに、實もたれといふ事をいましめたるうべ也。これ、ありといふを、有・在などの字にもたれたる説(183)なり。これは、昔今と絶ぬさまをいふにはあらで、ありわたるかたちをさとす詞なり。このけぢめ精微にして、心くはしからぬ學者は、元おもひわくまじき也。よく心をとゞむべし。こゝの地相をよく察し給ひし事を思はせむがために、おかれたる也。立之は、たゝせられの心也。見之賜者は、みさせたまへば也。○日本乃云々 日本は假字にて、大和國の事也。倭といひし處の事、眞淵が萬葉考にくはし。山邊郡大和郷のわたりを、いにしへはやまとゝいひけむといへり。これ、その考索のいたれる事、かのぬしのいさをなり。大和國にして、やまとのといはむはいと稚ければ、しか穿鑿せられけむも、ことわりなる事なり。しかはあれど古人は、心から雅言をいふ事多し。前にいへる、春過て夏きたるらしの類、これなり。しりていはむは稚しとはいふまじき也。古言は、さかしらには見がたきもの也。おもふに、これは、上の、藤井が原にの爾もじにいへるが如く、この大和の國内ならずとも、國所は多かるべきを、おもはせむがためなり。されば猶、大和一國の事なるべし。これ、古人上手の手段なり。青香具山の青は、樹の繁茂したるさまを云。山はしげきを貴べば也。者《ハ》は御井の爲としもたてるを感歎したる也。〇日經乃云々 成務天皇の御紀云、以2東西(ヲ)1爲2日(ノ)縦(ト)1南北(ヲ)爲2日(ノ)横(ト)1とあるが如く、日經は、東西を云。日のわたる道なればなり、これは、東面の御門をなるべし。南北の御門をふたゝびぃひて、西面の御門なきは、南北は水脈の要たればにや。西面は、御門なかりし故にや、大御門は、大宮をいふ事、まへにいへるが如し。爾もじは、此御門のためにあつらへ置たるが如きをいふなり。○春山跡云々 跡は、と(184)いふ如くにの心なり。されば、此歌よめる時は、春にてはあらざりし事、明らか也。春は木の芽もはりて、木草繁茂する時なればなり。されば、春ならぬに、春のごとくに、山のいたく繁茂したるをほめたるなり。宣長、春は青の誤かといへり。これ穩なるべし。之美佐備立有 しみは繋きを云。佐備は、まへに神さびにいへるが如し。繁茂すべき事を含めるが、おのづから外にみゆるを、しみさびとはいふなり。されど、青香具山といへるに、さらにかくしみさびといはむは、をさなきやうなれど、もとより青みたるがうへに、猶しげりゆかむさまの、みゆるをいふ也としるべし。この山々皆、何さびとよめるは、大かた山つみの御神さびになしていふ也。此下、畝火山には伊座とあるにもおもふべし。立有は、たちてありといふなり。そのたちてありをつゞむれば、たゝり也。このたを江緯にかよはしたる也。大かた江緯にかよはすは、未然を思はする義なる事、前にいへるが如し。○畝火乃云々 此としもいへるは、藤原は畝火の山下にて、他の山々よりもことに近ければ、此とはいへるなり。美豆とは、 神武天皇の御紀、瀰都瀰都志《ミヅミヅシ》。愚梅能固邏餓《クメノコラカ》云々【長歌下略。又一首あり】大祓(ノ)祝詞に、美頭乃御舍仕奉※[氏/一]《ミツノミアラカツカヘマツリテ》云々【祈年祭祝詞にもあり】此集中にもいと多し。いづれも内に、潤澤を含みたるさまを云。これ又、山のよきをいふ事、まへの青香具山にいへるに同じ。わが御國すべて、潤澤ある事を貴ぶは神典に【古事記上卷】其泣|状者《タマフサマハ》青山(ヲ)如《ゴト》2枯山《カラシノ》1泣枯《ナキカラシ》河海(ハ)者|悉《コトゴトシキト》泣乾《ナキホシキ》是以|惡《アシキ》神之|音《オトナヒ》如狹蝿《サバヘナス》皆|滿《ミチ》萬(ノ)物(ノ)之妖《ワザハヒ》悉《コトゴト》發《オコル》とあるにみるべし。潤澤なき事を嫌ふは、物と物和せざるが故也。これふかき理あり。くはしくは古事記燈にゆづれり。(185)者《ハ》もじ、前に同じ。○日緯能云々 上に引たりし 成移天皇の御紀乃、日横これ也。南北をいふ。これは、南面の御門をいふなるべし。大御門爾 まへに同じ。爾もじも同上。○彌豆山跡云々 彌豆、上に同じ。跡《卜》も前の春山跡の跡に同じ。よに、彌豆山とめづる山ある、その山の如くといふ心なり。上に、此美豆山者といひ、さらに彌豆山跡といへるをいぶかる人もあるべけれど、もと、みづ/\しき畝火の山の、なほその上に、みづ山さぶるよしをいふなり。上に、みづ山はといひ、さらにみづ山といふにて、おのづからかゝる心となる、古人の詞づくりおもふべし。されば、みづ山と山さびいますとは、みづ山さびいますといふほどの心也。としるべし。佐備、まへに同じ。伊座、まへにいへるが如く、おほかた此山々みな、山神の御神さびとしてよめるもの也。されど、香具山・耳梨山のふたつは、立有《タテリ》といひ、この畝火山のみ、伊座といへるは、かの二山は、神の御うへにはあらじと思ふ人もあるべけれど、佐備といへる事、神ならではあるべくもあらぬをもて、いづれも、山神の御うへをいへるなる事を辨ふべき也。しかれども此山にしも、伊座とよめるは、ことに此山のみをあがめたるにはあらで、前にもいへるが如く、此山は、藤原にことに近ければなるべし。加具山・耳梨山も、此都に遠き山にはあらねど、程あるが故に立有とはよめる也。○耳爲之云々 今の本には、高の字なれど、或説に爲の誤ならむといへる、從ふべし。此都は、此三山の間の地といひ、香具山・畝火山・耳梨山は、まへの三山の御歌にもしるく、かつ耳高といふ山もなきをや。高・爲、字形よく似たれば誤れるにや。爲は(186)奈之《ナシ》といふ假名なるべし。青菅山者 青は、青香具山の青に同じ。菅は、すが/\しといふ心也。山菅の生ずる山といふ説ゆくりなし。古事記上卷に、我御心須賀々々志《ワガミコヽロスガスガシ》。また、須賀宮《スガノミヤ》、須賀之地《スガノトコロ》などみゆるを、神代卷には、清とかゝれたり。わが御教、心のすが/\しきを貴ぶ事ふかき理あり。神典をまねばむ人に、口授すべし。されば、祓に菅を用ふるも、この須賀の義をたふとぶが故也。大祓祝詞に、天津菅曾乎《アマツスガソヲ》云々 とみえ、此集卷三【長歌上下略】天有《アメナル》。左佐羅能小野之《ササラノヲヌノ》。七相管《ナヽフスゲ》。手取持而《テニトリモチテ》。久堅乃《ヒサカタノ》。天川原爾《アマノカハラニ》。出立而《イデタチテ》。潔身而麻之乎《ミソギテマシヲ》云々 同卷六【長歌上下略】千鳥鳴《チドリナク》。其佐保川丹《ソノサホガハニ》。石二生《イソニオフル》。菅根取而《スガノネトリテ》。之努布草《シヌブグサ》。解除而益乎《ハラヒテマシヲ》云々 などなほあり。須賀《スガ》は、里言にスンガリといふに同じく、物むつかしき事なく、心がゝりなき貌也。後世の物がたりぶみどもにもすが/\しといふ詞多し。宣長これを、すすが/\しき義也といへる可也。されば、青菅山とは樹木繁茂して、こゝらよげなる山を云也。者《ハ》もじは、前のふたつに同じ。○背友乃云々 成務天皇の御紀云、山陽(ヲ)曰日2影面《カゲトモ》1山陰(ヲ)曰2背面《ソトモト》1とある是なり。影面は、日の影のあたる面といふ也。止《ト》は、津於《ツオ》のつゞまれるにて、影津面《カゲツオモ》なり。背面は、日の影の背なる面といふにて、これまた背津面《ソツオモ》をつゞめたる也。されば、此背友は、北面なるべし。後世、外面を曾止毛《ソトモ》といふは、これを誤り用ひたる訓なり。外は、止《ト》といふ。曾止《ソト》といふは里言也。大御門、また爾もじ、前におなじ。○宜名倍 耳梨山を、この御門に宜しと思ふにあはせて、神さびたてりとの心なり。宜《ヨロシ》は、よしといふにはあらず。或説に、そなはり足《タ》りたる心なりといへるは、ゆくりなし。古(187)歌・古文どもに徴して、そのかなはざるを明らめおくべし。里言に、チヤウドヨイといふほどの心也。此集中、此詞あまた所みえたり。神さび、まへに同じ。此山の繁くこゝちよきさまの、人力にはあらぬさまをいふ也。○名細吉野乃山者 くはしくはもと、古事記上卷に、美斗能麻具波比《ミトノマクハヒ》とある、くはひは、咋合《クヒアヒ》のつゞまりたるにて、此集卷十六に、美麗物《ウマシモノ》。何所不飽矣《イヅクアカヌヲ》。坂門等之《サカトラガ》。角乃布久禮爾《ツヌノフクレニ》。四具比相爾計六《シクヒアヒニケム》とよめるこれ也。この久比《クヒ》を【上よりのつゞきにて、具もじ濁音なり。詞の頭を濁る事。古なし、と宣長がいへる、げにしかり。】久波《クハ》にかよはせて、志支《シキ》といふ詞をそへたる詞なり。久布《クフ》といふ詞は、古事記上卷に飽咋之宇斯《アキグヒノウシ》・大山咋《オホヤマグヒ》など咋といふ神名多し。皆同じ。又此集卷十六に、池神乃《イケガミノ》。力士※[人偏+舞]可母《リキシマヒカモ》。白鷺乃《シラサギノ》。桙啄持而《ホコクヒモチテ》。飛渡良武《トビワタルラム》、などもよめり。されば、くはしとは、咋もしたきといふほどの心也。美物をみて里言に、咋ツキタイなどいふこれ也。されば、名ぐはしは、芳野といふ名をきくこゝち、美物をみるこゝちなるをいふ也としるべし。古事記上卷の歌に、美女を久波志賣《クハシメ》とよみし同じ 神武天皇の御卷の大御歌に、伊須久波斯久治良佐夜流《イスグハシクチラサヤル》この外、この集中に、花ぐはしなどもよめり。後世は委精などの義に用ふ。古義にあらず。者《ハ》もじ、同上。○影友乃云々 影友まへにいへるが如し。これも南面なるべし。もし西面をいふ歟。從は、此御門よりみゆるを云。吉野山は、遠ければ從といふ也。○雲居爾曾云々 雲居とは、雲の居る所をいふにて、空の事なり。されど雲居とよめるは、多くは遙なる事をさとす事に用ひたり。こゝもしかり。雲のゐる所をあふぐばかりの、遠さなるをいふ也。曾《ゾ》もじは、吉野山のみひとり、此都にあは(188)ひ遠くて、前の三山の如く近からぬを歎きたる也。けるとは、三山と同じからむと思ふにたがへる事を云也けり。けるはすべておもへりし事とはことなる事あるを歎ずる脚結なり。かく四山の、四門にたてる事をいふは、此四山の神の、此御井をまもります事をいへる也。されどこれは詞の表にて、情は奥にとけるがことし。此四山の神たちを、四門に配したる所以は、この四山の神たちの、此御井に水をたやし給はぬ事をよめるなり。これ、水は、山よりいづる物なれば也。大かた都の四面に、山あるを貴ぶ事、水にかぎらず。すべて有用の物乏しかるまじきが故也。されば、 神武天皇の御紀に東(ニ)有2美地1青山四周とあり。思ひあはすべし。つねにいふが如く、わが御國言は、有用の事をあらはにいへば、必弊ある物なるが故に、そこを、言代主神にまかせ奉りて倒語す。一首・一句・一言にも、此ならひ彌綸せり。よく心をとゞめざれば、古人の心はしるべからず。此倒語の法にあらずして、解したりと思ふは、必古人の心にはあらざるべき事をさとるべし。此故に、かく山神の御うへにのみ、詞をつけたる也。【これ、先學者をそしるにあらず。それは詞の表を檢糺したる事、わが管見の及びにあらぬ事、みづからよくわきまへて、先達の説ども、可否をえらびてしたがふなり。これは古人の詞づくりに、情を鎭めたる法の事をいふ也。學者、おもひあやまるべからず。】○高知也。天之御蔭云々 高知、まへに釋せるに同じ。天の冠における也。天は地の方よりは、よりもつかれぬものなれば、高とはいふ也。知とは、高處を、天の知給ふと云也。天知也は、日の冠なり。日神は、高天原をしろしめせば也。也《ヤ》は、ともに詠歎の詞なり。脚結抄にくはし。天の高しり、日の天しり給ふ事の、凡慮にはかりしられぬことを歎じたる也、大祓祝詞に【祈年祭にも】天之《アメノ》御|蔭《カゲ》日之御蔭《ヒノミカゲ》(189)【止】隱坐【※[氏/一]】《カクリマシテ》云々とあるに同じ。天の御蔭とは、天の上に覆ふその蔭をいひ、日の御蔭とは日の上にてらし給ふその蔭をいふ也。天とさしたるは、天津神もろ/\の御蔭をいひ、日とさしたるは天照大御神の御蔭をいふにて、前に、四方四山の神の此御井をまもりますよしをいひて、さてまたこの天日をこゝにいふは、中央よりまもります神たちをいふ也。御蔭とは、天日の御うつくしみの下にをるよしをいふ也としるべし。此藤原(ノ)御井といふは、宮中にありける井にや。上の句々みな此御井を、主とたてゝよめる也と心うべき也。許曾波《コソハ》といふより以下は、此よみ人の心をいふ也。許曾波《コソハ》は、まへにいへるに同じ。おほくの物の中をひとつとりわきて、その殘りのもののさまをさとす詞也。波《ハ》もじそひたるは、ことにそのけぢめをおもはせむがため也。このはかなき御井だにも、四山の神・天日の神たちさきはひ給へば、他の物はいかばかりさきはひたまはむとの心を、この許曾波《コソハ》におもはせたるなり。大かた、許曾《コソ》にてかくひとくさとりわくるは、必そのすぐれたる方の物は、とりわけぬならひ也。これ、上古人の脚結に精微なる所以也。いかでかすぐれたる方をとりわけぬぞといふに、その妙理こゝにいひつくしがたし。志あらむ人には、口授すべし。なほ下に靈をとくにてらしておもふべし。されど、勝れたる方をこそとりわけめと後世にひがめる人は、此妙理とくとも心えがたかるべしかし。大かた、詞の表は、ひとへに此御井の水を賞するがほに、許曾波《コソハ》とはよめる也。○常爾有米 古點とこよにあらめとあり。又とこしへならめとも、つねにありなめなど訓じたるあり。しかるに、もととこよといはむは、(190)齢の事にあづかる詞也。とこしへといはむは、その方をたつる詮なし。なめのなは、去倫のぬの【よにいふ畢のぬなり。】かよひたるなれば、こゝの語意に用なし。いづれも/\うしろめきたき所あれば、四言に、つねにあらめとよむべくや。されど、いづれにもあれ、この水のかるる事なく、不易なるを云也。米《メ》はもと、牟《ム》のかよひたるにて、安良牟《アラム》といふべきを、許曾《コソ》にひかれて米《メ》とはいふなり、許曾《コソ》には、必江緯にうちあはすべき所以は多かる中を、ひとすぢとりわくるその未然に、そののこりをおもはせむがために、江緯にかよはす也。このことわり、くはしくは經緯【五十韻なり】をまねびてしるべし。○御井之清水 古點はきよみづとあり。されど、清の字詮なし。後にましみづとよめり。これは、眞もじをつけよみにし、しみづ猶清水なり。清の字詮なしといへども、もとこれ此御井をほむる歌なれば、清ともいふまじきにもあらず。熟字は、その詮のありなしにかゝはらず、よめる事多し。たとはゞ、白露・黒髪・雁がねなどの如くなれば、これもその類にや。此一句は、ふたゝびぃへる也。上の水許曾波すなはち、御井の清水こそは、といふ心なれば也。大かた、何事もふたゝびぃふは、一度いひてあかぬ故にて、その物事に心のあつき事をさとす爲也。この歌もはら、此御井をほめたる歌とよめるなれば、重ていへるなるべし。
〔靈〕この歌、表は、此藤原の御井、四山の神たち、中央は天つ神・日神のさきはひ給ふ水なれば、萬世ふとも常ならむ。ともはら此御井をほめたゝへたる歌也。げに、四方・中央より、神たちの(191)さきはひ給はむは、かく稱嘆せむも、ことわりなる水にはあれども、たゞ御井をほむるばかりの事を、古人、こと/”\しく歌によむものにあらず。おもふに、これは、 天皇、この藤原の美地なる事を鑑察まし/\て、こゝにしも遷都したまへる大御心のかしこさを、ほぎたゝへ奉れる歌なり。埴安乃堤上爾在立之とよみたる、おもひあはすべし。されど 天皇を、この御井の水にたとへ奉れるにはあらず。四山・中央の諸神、たゞはかなきこの御井をだに、かくさきはひ給ふばかりの地なれば、なにも/\不變なるべきをおもへとの心なる事、許曾波《コソハ》を釋せる所におどろかし置たるたるが如く、許曾《コソ》にもはら此心はこめられたる也。大かた倒語のうちに、比喩はやすし。比喩ならずして、やがてその物をよみたるやうなる詞づくり、いとかたきわざ也。これらのよみざま、詞をつくる心得ともすべし。 天皇、此都をしもさだめ給ひし事をほめ奉らむとて、ゆくりもなき御井をたゝへたる、かいなでの歌よみのおもひもよるまじき事也。【されば、猶これも、志貴皇子の御歌かとはおぼゆるなり。】先達の註大かた、詞の表をとく事いたれりといへども、此長歌などは、表にさだかにはときかねられたり。げに、四山をよめるよりはじめて、ゆくりなく天日の御かげをさへいへる、ことわり也。いにしへ人は、ほむるもすべてかくのごとし。後世心のあさましき、これらの歌にはづべきなり。○端作、上古は、うはべにてたのむまじき事、かくのごとし。集中の端作、すべてこの心得をもてみるべし。わざと、詞の表をば端作とする事、その情を鎭められたる所を活さむが爲なり。後世の題といへども、もとは此心なるべけれど、いつよりか、つひに情より題を(192)おこす事をうしなへり。さる心にて、いにしへの端作をみば、かへりて、かなたの※[横目/古]獲におち入るわざにぞあるべき。かくいふ故は、この次の短歌に思ふべし。短歌の詞のうへ、御井の事いささかもなければ、すでに反歌にはあらじ。別に、端作ありけるが脱たるならを。とある註書にもいへりとぞ。おのが思ひ、わが御国ぶりにかなはざらむほとは、みだりにはいひがたしかし。
短 歌
藤原之《フヂハラノ》。大宮都加倍《オホミヤヅカヘ》。安禮衝武《アレツガム》。處女之友者《ヲトメガトモハ》。乏吉呂賀聞《トモシキロカモ》
〔言〕藤原之大宮都加倍とは 持統天皇に、この大宮につかへたてまつるを云。都加倍はつかはれの心なり。大宮都加倍爾の心にみるべし。○安禮衝武 今の本、衝哉《ツゲヤ》とあり。この哉《ヤ》もじ、下の賀聞にうちあはず。されば、哉《ヤ》は、武《ム》の誤にて、下の七言、乏吉呂賀聞の誤なるべし。と宣長がいへる、考得たりといふべし。下の一句、古點しきめさむかもとあり。さては、賀聞のあたるべき所ともおぼえねば、必、このぬしが訓にしたがふべし。この訓したがふべきは、たゞ上下のうちあはぬのみならず、この歌を、反歌とみむに、その意よくかなへば也。上の五七五七四句は、藤原の大宮づかへにあれつがむをとめがともは、と一つゞきに心うべし。安禮は、生るゝ事也。されどうまるゝは被v産義なり。安禮はあらはれの義にて、母に屬し、子に屬するけぢめある詞なり。(193)後世は、安禮とはいはずなりぬ。後世は、詞のすくなくなれる事、これにもしるべし。衝は假字にて繼なり。をとめどもの、うまれ/\して絶ざらむをいふ也。武《ム》は、この行末をあらまして云也。○處女之友者 をとめ前にいへり。ある註に、この みかど、女帝におはしませば、女童を多くめしたまひし事有けむとあるは、例の實もたれなり、女帝ならでも、後宮には宮女多くめさるゝ物なれど、女帝にましませば、男子よりも、女は多くめさるべければ也。かつ女童といへるもかなはず。處女とは、すべて年わかき女をいふ稱なる事、男する女をもをとめといへる事、古書に多かるを思ふべし。たゞめしつかはるゝわかき女をいふ也。友は輩《トモガラ》なり。 神武天皇の御紀に、うかひがともとよみ、此集中にも、しづをがとも、ますらをのともなどよめるにおなじ。者《ハ》もじ、乏しくもあるまじき處女を、者《ハ》といへる、構思のほど思ひやられてめでたし。○乏吉呂賀聞 今の本、之吉召賀聞とあり。之は乏の誤。召は呂の誤うたがひなし。乏は、もと物の乏少なる心なれど、羨しき心に用ひたるが多し。いはゆる、此卷に、朝毛吉《アサモヨシ》。木人乏母《キビトトモシモ》。亦打山《マツチヤマ》。行來跡見良武《ユキクトミラム》。樹人友師母《キビトトモシモ》。また卷六に、【長歌上下略】毎見文丹乏《ミルゴトニアヤニトモシミ》の類、これ也。うらやましさを、乏しといふ詞にて思はする、これわが御國言のならひ、かへす/\いへるが如し。宣長すでに、うらやましき義也。とは釋したれど、いかなる故にかゝる詞づかひなりとも、いかなる義にてともしといふとも辯ぜられず。されば後學、たゞ上古はあやしき詞づかひしけり。とおもひてやみぬ。これうらやましきは、乏しきが故なるをもて、こゝを詞とする事、古言これに(194)かぎらず。その味はひおもふべし。此類みな、さかしらならじとての詞づくり也かし、呂《ロ》は、等《ラ》の類に心うべし。されど等《ラ》は安緯也。呂《ロ》は於緯なり。緯の義は、こと也。されば、乏しき事の内にこもりたるに、心つかざりしを歎く詞なりと心うべし。後世は、用ひぬ脚結也。集中例おほし。賀聞《カモ》は前にいひしが如く、計較にも思慮にもかゝらぬほどの事あるを、歎ずる詞なり。これはうまれつがむをとめが輩をうらやましくおぼゆるわが心を、みづから歎じたる也。乏しさを、賀聞《カモ》とよめるにはあらず。【因に云、すべて加毛《カモ》は、かゝる心得なるを、後世は、おもふを、おもふかなとよみ、みゆるを、みゆるかなとよむ事となりぬ。いたくあやまれり。おもふを歎じ、みゆるを歎ずるにこそ、加毛《カモ》とはよめれ。よく/\かへりみるべし。】
〔靈〕この歌、表は、此藤原の宮づかへに、この行末生れつがむ處女がともがらは、ときはにかきはにましますべき此 天皇につかへまつるべきが、うらやましき事。わが心ながら、わりなき事やとよめる也。よにうらやましかるべき物こそあれ。われ大丈夫にして、處女がとものうらやましきは、いかなるわが心ぞ。とみづから歎じたるやうに詞をつけたる也。【呂賀聞《ロカモ》に、もはら、この心をおもはせたるなり。】されど、かばかりの事は、心にこめてもやみぬべき事なるに、こと更に歌とよめるは、必別に情ある事しるし。されば思ふに、この新京遠ながくしろしめすべければ、いかで我も命ながくあり經て、つかへまつらまほしくおもへど、我命は限ありて、 天皇のしろしめさむ御世のきはみ、つかへまつる事も、かなふまじきなげかしさに、このゆくすゑ生れ繼て、宮づかへし奉るべき處女がともの、うらやましきにいひなし、大丈夫にして、處女がともをうらやむを、わりなき(195)ことゝおもひもどくを、むねとしたるやうによめる倒語の手段、神妙いふばかりなし。されば、その情ひとへに 天皇、この新京をとほながくしろしめすべきを、賀《ホギ》たてまつれる歌なる事、あきらか也。これいさゝかもあらはにいふまじきは、長歌に同じく諂らひにおつべきをはゞかれる也。安靈衝武に、天皇の遠長くおはしますべき事を思はせ、處女がともを乏しむに、わが命の遠長くつかへ奉るに堪まじきを思はせ、その歎を賀聞《カモ》におもはせたる詞づくり、なべてのものゝ、おもひもよるまじき事なり。よく/\心をとゞめて、この詞のつけざまを味はひしるべし。○此歌、反歌のやうにあらねば、前にいへりしが如く、古來註者、これをうたがひて、長歌とはことすぢの歌ならむといへるは、例の後世ひがみ也。予つねに、後世ひがみをもて、古をみるべからずといふは此所以也。もと端作に、御井歌とある故に、さるまどひも生ずるなれど、長歌を釋せるが如く、御井をもて、此藤原都のとは長かるべき事をほぎ奉れる歌なれば、御井は表にてこの都をほぎ奉れるが本情なり。されば、此歌もなほ、同じことほぎなり。さらに、別時の歌にはあらず。此歌、表に、御井をよまずとて、端作にまどひて、眞をそこなふまじき也。これらにも古言はすべて、表に目を奪はるまじき事をさとるべし。
右(ノ)歌作者未v詳
大寶元年辛丑(ノ)秋九月太上天皇幸2于紀伊(ノ)國(ニ)1時(ノ)歌
(196)この 太上天皇は 持統天皇なり、文武天皇の御紀に、この幸の事あれど天皇とあり。太上を脱せしにや。
巨勢山乃《コセヤマノ》。列列椿《ツラツラツバキ》。都良都良爾《ツラツラニ》。見乍思奈《ミツヽオモフナ》。許湍乃春野乎《コセノハルヌヲ》
〔言〕巨勢山は、藤原より紀伊にゆく路なればなるべし。○列々椿は、おひつらなれる椿をいふなるべし。これは、此山におひつらなれる椿あれば、下の都良都良爾のよせばかりにおける也。○都良都良爾は、熟《ツラ/\》也。春野を思ふを主として、乍《ツヽ》とはいへるにて、春野を思ふもひたふるならで、つら/\みるをいふ也。見るとは、今の巨勢の秋野を也。思ふとは、巨勢の春野を也。此幸は九月なれば、巨勢野は木葉そめ、鹿のこゑしなど、(おも二字脱す)しろきを思はせて、つら/\にみるとはいふ也。しかるに猶あかずして、春野をおもふをいさめて、奈《ナ》とはいふなり。奈《ナ》は、莫といさめたるにて、同じ從駕の人の、つら/\みつゝ、春野を思ふ人にいひかけたるなるべし。或註に、奈《ナ》は言をいひおさふ詞なりと釋したるは、詠の奈《ナ》の事なるべし。この例と思ひての釋なるべけれど、上下の語勢その例ともおぼえず。又おもはなと訓《ヨミ》て、常に古歌に用ふる奈《ナ》の例とみむも、上下の語勢その例にあらず。莫《ナ》とみれば、語勢もなにも應じて、一首の心もめでたき也。かの説おもふに、これを禁《イサム》る詞とみては、一首の意おぼつかなきが故なるべけれど、大かた歌は、詞の表にてとかむとすとも、上古の歌は、恐らくは心えがたき事多かるべし。くはしく、大旨に論らへるをみるべし。註者よく心うべき事也。もと、詞の表は、言外の情より出たる物な(197)る事、草木の根より幹・枝・花・葉の生ずるに同じ。一もとの木草、その精神はたゞ、根にあるをや。されば、根をしらむ事、枝葉にあり。枝葉をしらむ事、根にあり。竹の根に、松は生せず。木の根に、草は生ぜず。このうちあひ、やむ事なき條理そなはれり。此眞面目をもて、歌をとかば、説おのづから私をまぬかるべしかし。○許湍乃春野乎 この乎もじ、ふかくめをとゞむべし。今秋色のおかしきに、春を思ふをいふ也。この歌のけしきに猶あかぬ心をとゞめたる也。されば、上の奈《ナ》もじ、禁《イサム》る詞なるべき事、此|乎《ヲ》のうちあひにて、思ふべし。
〔靈〕この歌、表は、今この巨勢野、秋色えもいはぬをつら/\みつゝ、猶あかずして、春はいとゞいかならむ。と貪《ツクツグ》くおもふな。といさめたる心なり。同じ從駕の人のうちに、この野のけしき春はいとゞいかならむなど、いひし人ありしに、よみかけたる歌なるべし。後世ならば、しかしか人のいひしかばよめるなど、端作にかゝでは解がたしと思ふべし。古人は、この乎《ヲ》もじ、奈《ナ》もじにて、おのづからしか/\の事ありて、よめる歌なりとはしるければ、端作をもたのまざりける也。されば、予がかくとくを、附會のやうに思ふ人もよにきこゆる、ことわりなる事なれど、詞の條理、古人の用ひざまやむ事(なき二字脱?)法則ある事なり。くはしくは、こゝに辯じがたし。しかるに、春野を思ふなといさむるばかりの事は、古人歌とよむばかりの事がらにあらねば、必別に情ある事うたがひなし。されば思ふに、今この秋の氣しきいとおかしきに、春はいとゞいかならむなど、從駕の人のいはゞ、それを、 帝のきこしめして、又こむ春も幸をおぼし(198)たゝむかとて、制したるにて、ひとへに幸のしげからむをなげきたる歌なる事、うたがひなし。この 帝、幸あまたゝびなりし事、幸をいさめ奉りし事など、前にひけるをてらしてさとるべし。倒語したるは、ひとへにさかしらをはゞかれる也。今更いふも中々なれど、此詞のつけざまいとかろ/\と事もなげなる、めでたしともよの常なり。
右一首|坂門人足《サカトノヒトタリ》
朝毛吉《アサモヨシ》。木人乏母《キビトトモシモ》。亦打山《マツチヤマ》。行來跡見良武《ユキクトミラム》。樹人友師母《キビトトモシモ》
〔言〕朝毛吉木とは、冠辭考に、淺葱《アサキ》をわりたる也とあれど、物名をわらむ事いかゞなり。又一説紀國よりよき麻を出せれば也、といふ考をあげて、國つ物を冠とせる例なく、かつ紀國にもかぎらずとて、此集卷二に、朝毛吉《アサモヨシ》。木上宮乎《キノヘノミヤヲ》卷十三に、朝裳吉《アサモヨシ》。城於道從《キノヘノミチユ》などつゞけたるは、大和(ノ)國|城戸《キノヘ》なりと破せられたり。されど淺葱の説、穩しくもおぼえず。かの麻の説、紀國に縛せられて釋したるが故に、さるもどきまぬかれず。今おもふに、毛吉《モヨシ》の三字は、眞淵が説のごとく脚結にて、麻《アサ》を着《キ》とかけたるなるべし。麻を衣に織て着るなり。【又この集中、眞間の娘子をよめる歌に、麻を裳に着る事をよみ、卷四には、麻裳吉ともかきたれば、毛は裳にて、麻裳を着、とかけたるにやとも思へど、事ひろからねば、猶毛吉は、脚結とみむ方まうるべし。】○木人乏母 木人は、紀國人なり。乏は、此上の歌にいへりしが如く、うらやましき也。母《モ》は、終に多くおける母なり。即、この歌の終にも、ふたゝびおけり。この母《モ》の事まへにくはしくいへり。此まつち山の氣しきのおかしさに、紀(199)國人うらやましけれど、せむかたなき歎也。されば、心えていはゞ乏しくはあれども。といふほどの義也。紀人をうらやむは、もと本意にはあらずして、この亦打山を、つねにみざらむ事をなげくが本意なり。これ、母《モ》もじの本義なれど、置ざまに隨ひて、かゝる義となる事、これ母《モ》にかぎらず。すべての脚結、みなかくのごとし。○亦打山 多宇《タウ》二音|津《ツ》となるがゆゑに、亦打《マタウチ》とはかけるなり。おのれいとまなくて、いまだみず。風景絶勝の地なるべし。○行來跡見良武云々 紀國人はつねに、此まつち山をゆききにみるべければ也。かく行來跡としもいへるは、わざわざとみむともおもはずて、みる事をいはむが爲なり。これ例の言のみやび也。この句即、うらやましき所以をいへる也。跡《ト》は、ゆくとては見《ミ》、來とては見《ミ》、といふ心なり。古今集に、おくとはなけき、ぬとはしのばむとよめる跡《ト》に同じ。【いつゝのとなり】良武《ラム》は、中の良武《ラム》也。この二句つゞけてみるべし。中の良武《ラム》の事、前にいへるが如し。ゆきゝにみるべきは必定の事なるを、せまらずして、良武《ラム》とはよめる也。上の木人乏母も、猶このまつち山を、往來にみるを乏しとよめるなり。かく重ねてよむ事、まへに論らへるが如く、ひとたびいひてあかねば也。上にはたゞ、木人乏母とのみよみ、こゝには、行來跡見良武、とその乏しき所以をよめるは、標實の法によりてなり。大かたこの乏しきが、此歌の眼なるをおもはせて、ふたゝびぃへる也。下に、情をとけるにてらしておもふべし。古人かさねていへるは皆この法なり。いづれもそこを眼とみるべき也。予常に、おのづから言靈を察するに、法則ありといふは、これらの類なり。
(200)〔靈〕この歌、表は、此まつち山の風景、えもいはぬを、紀人はこと更にみむともおもはでみるらむが、うらやましけれど、せむすべなき歎を、むねとよめる也、されど紀人の乏しきばかりの事はたゞ乏しみてやみぬべき事なるを、こと/”\しく歌とよめるは、必情別にあるしるし也。されば思ふに、紀人の常にまつち山をみるらむをうらやむ所以は、紀人はこの地につきたる人なればなり。此地につきて、この山をみば、いかにおもしろからむ。かく遠く來てはかくおもしろき所なれども、心もゆかずといふ心にて、その心ひとへに幸をなげきたる歌なる事明らか也。されどこれ、又上の歌と同じはゞかりに、此山のおもしろさにのみ、むねと詞をつけられたる也。上の歌は、巨勢野のおかしさを賞し、此歌はまつち山のおかしさを賞したる詞づくりなれば、後世人の心にては、この勝地どもを賞したる歌なりとのみ見すぐせど、上古の人はさるはかなき事を、歌とよむものにあらず。これらの詞のつけざま、大かた歌の本、倒語の至ともいふべき歌なり。この淡海ぬし、いかなる人なりければ、かく倒語は明らめられたりけむ。心にくし。
右一首|調首淡海《ツキノオビトアフミ》
或(ル)本(ノ)歌
河上乃《カハノヘノ》。列列椿《ツラツラツバキ》。都良都良爾《ツラツラニ》。雖見安可受《ミレドモアカズ》。巨勢嚢春野者《コセノハルノハ》
この歌は、或本歌とはあれども、これは春よめる歌にて、この幸のたびの歌とはおぼえず。此幸(201)は、九月也。されば思ふに、此歌は古歌にて、此時春日(ノ)藏(ノ)首從駕して、所にかなへる歌なれば、誦せられたりしを、みづからよまれたるやうに、きゝ傳へられけるなるべし。古歌の時にあひたるを誦したるは、あらたによみたるよりも、あはれなる物なれば、此集にも、古歌を誦したるが多し。袋草紙に、よど河の舟中にて、よどのわたりのまだ夜深きに。といふ古歌を誦したりしを、いたくめでたりし事あり。これ、上古の風ののこりたるなるべし。もし又上の、見乍思奈といさめたる歌は、この老《オユ》ぬしの、此巨勢の春野を賞したる古歌を誦せられしによりて、此人によみかけられし歌かともおぼし。しからば置處錯亂したるが上に、或本歌と誤りけるなるべし。
右一首、春日藏首老《カスガノクラノオビトオユ》
二年壬寅太上天皇幸2于參河(ノ)國1時(ノ)歌
引馬野爾《ヒクマヌニ》。仁保布榛原《ニホフハリハラ》。入亂《イリミダリ》。衣爾保波勢《コロモニホハセ》。多鼻能知師爾《タビノシルシニ》
〔言〕引馬野は、遠江(ノ)國敷智(ノ)郡にあり。○爾保布榛原 榛は、まへにくはしくいへり。里言にハンノ木といふ木也。今|梅《ウメ》や澁《シブ》とて染むるものは、榛を煎じたる物なるよしきけり。いにしへは常に、この木もて衣をすれりしなり。あかき色也。にほふとは即、その木の皮の赤きを云。〇入亂 古訓は、いりみだれとあれど、禮《レ》は未然を思はする義なれば、こゝにかなはず。必いりみだ(202)りとよむべき所なり。亂は、この榛原に入りて、榛どもをみだるなるべし。もしこれ、從駕の人のうへならば、亂入とあるべき條理也。この句の意、その木にふるれば、やがて衣のにほふ物のやうにきこゆれど、しからず。これは例の詞づくりにて、まことは此はり原に入りみだりて、その皮をとりて、衣をにほはせといふ也。しかるに、かやうによめるによりて、木にふるれば、やがて色づく物とよには心得たりげなれど、古言の用ひざまにくはしからぬが故也。かの芽子《ハギ》なりといふ説もこの故なるべし。すべて古言は、かくざまに用ふる事、大かた、わが御國ぶり也。かへす/\いひおけるが如く、直言のひがみに泥《ナヅ》むまじき也。○衣爾保波勢は、衣にすれといふ心なり。あかき色のさまをにほふとはいふなり。にほはせとは、從駕の人にいひかけたる也。人のうへにいふは、多くはわがうへなる事、古言のつね也。○多鼻能知師爾とは、旅には摺衣を着る事、いにしへのならひなればかくいへり。とある註にいへれど、もししからば、京をいづる時よりこそ着たらめ。ことに私の旅ならぬに、さるならひあるにそむかむやうなし。この説ひとへに例の實もたれ也。かへす/\古言は實にもたれては、解がたきもの也。これは旅に必着るべきが故に、かくいへるにはあらず。此幸に從駕して、三河・遠江のあたりまで、とほく來たるしるしにといふ也。後世心にては、しからば三河に來たるしるしにとこそはいふべけれど、かくせまらずして、ひろく多鼻といふ事古言のみやびなり。【ひろくいふに、何事も、そのうちにこもれば也。しかのみならず、せまりて詞をつかふに、さかしらなれば也。古人詞を用ひたる法、これのみならず、いたれり。いづれも據る所は神典也。】かやうの詞づかひ、我御國言の法をよ(203)くみしれば、うたがひなき事也。大かたわが御國ぶりの本をきはめずては、たとひ博覧多識たりとも、恐らくはおもはぬあやまりも出くべし。學者心を用ふべき事なり。○知師爾とは、京にかへりて後京の人にみせむに、遠く來ける事を證せむ爲に、といふ心なり。【この二句も倒置也。例の標實の法なり。】
〔靈〕此歌 表は、この引馬野の榛もて衣をにははせて、京にかへりて、此三河・遠江のあたりまでとほく來たるしるしにせよ。と從駕の人にいへる也。されどかばかりの事を、古人歌とよむものにあらねば、思ふに、從駕程久しくなりて、郷思のたへがたきをよめる歌なり。さればこれ從駕の人に心をつけたるやうによめれど、猶みづから家人へ贈れる歌なるべし。かくいふ故は、もと榛もて衣を摺て、歸京ののち旅のしるしありとて、何ばかりの益かあらむ。これ倒語なるしるし也。されど、從駕なれば、家人を思ふ心をあらはにいはむ事憚あれば、かく詞をつけられたるなり。この詞づくりの用意ふかき事、よく/\思ふべし。後世心には、今の釋すぢなき事におもふべけれど、倒語をみつべき法やむごとなきもの也。わが御國ぶりにおもひをこらして、此歌もはら郷思よりなり出たる事をしるべし。
右一首|長忌寸奥麻呂《ナガノイミキオキマロ》
此集卷二に、意吉麻呂《オキマロ》とかける、同人なり。
何所爾可《イヅクニカ》。船泊爲良武《フナバテスラム》。安禮乃崎《アレノサキ》。※[手偏+旁]多味行之《コギタミユキシ》。棚無小舟《タナナシヲブネ》
(204)〔言〕何所とは、此舟のとまるらむ所をしらむとする心なり。可《カ》とは、必いづくにぞ舟はつべければ也。○船泊爲良武 舟はつとは、舟のとまるを云。布奈《フナ》の奈《ナ》は、乃《ノ》のうつれるなり。手の末・足の末を、たなうら、あなうらといひ、足の玉を、あな玉といふ例なり。○安禮乃崎は、美濃(ノ)國不破(ノ)郡|荒崎《アレノサキ》、と和名抄にみゆる、そこなるべし。○※[手偏+旁]多味行之 たむとは、里言にいふタムルなり。矯《タム》るは、直ならぬかたちを云也。うちたをり多武と、つづくるにて思ふべし。舌たむといふもこれなり。すべて、まほにゆかぬかたちを云。之《シ》は去倫の之《シ》なり。この崎をこぎめぐりゆけりし、そのすぢにつきていふ脚結也。○棚無小舟とは、舟棚《フナダナ》なき小さき舟也。されば、棚なしといはゞ、もとより小舟なるべければ、ことに小舟とはいふまじき事なれど、棚なくても、小・大はあるべければなるべし。されど大かたには、棚なきは小舟也。と心うべし。和名抄に、※[木+世]、和名|不奈太那《フナダナ》。大船(ノ)旁(ノ)板也とみゆ。
〔靈〕此歌、表は、安禮の崎をこぎめぐりゆきし小舟の、今はいづくにかはてゝとまるらむ。と思ひやりたる也。かやうの歌をみて、たゞめのまへのさまをありのまゝによむ事を歌の本意なり。と後世心うるは、詞の表にのみめを奪はるゝが故なり。大かた古人は、神ながら言擧せぬわが御國ぶりをしも、よくわいだめたりしかば、もとよりよしもなく、故もなき事の、いはでもありぬべき事をいふ事、たえてなかりし也。さればこれらも、詞のうへにては、たゞゆゑもなきいたづらごとをいへるが如くなれど、必別に情ある事明らか也。されば思ふに、このこぎめぐりゆき(205)し柵なし小舟には、その船中必旅人の乘りゐて、見もしらぬ礒山かげなどに舟はてゝ、舟中の心ぼそくわびしさに、いとゞ故郷をこひてなげきをるらむか。といとをしくおもひやりたる也。されどその旅人しれる人にもあらねば、情におきて何のかゝはりもなき事なるを、かばかりあはれまむやうなし。これわが故郷のいたく戀しく堪がたければ、わが郷思を直に述まほしけれど、從駕のはゞかりに、かの船中の旅人の郷思をおもひやりたるになしたる詞づくりなる事、あきらか也。公・私をそなへてうはべはたゞ、此舟のはてむ處をおもひやりたるより、外の事なき詞づくり、めでたしとも中々なり。胸中あまるばかりの郷思をば、かくはゞかりはてたる詞づくり、そのくるしさ深く思ひやられて、あはれいふばかりなし。これひとへに、倒語の妙用ぞかし。
右一首|高市連黒人《タケチノムラジクロヒト》
與謝女王《ヨサノヒメミコノ》作歌
續日本紀に、慶雲三年六月卒とあり。これは、京に留りたまひて、夫君の、從駕にて旅ねし給ふをおぼしやられての御歌か。又、この女王從駕し給ひて、京に留り給ふ夫君をおぼせるにやとも思へど、此次の御歌、京よりおぼしやられたるなれば、定がたし。
流經《ナガラフル》。妻吹風之《ツマフクカゼノ》。寒夜爾《サムキヨニ》。吾勢能君者《ワガセノキミハ》。獨香宿良武《ヒトリカヌラム》
(206)〔言〕流經妻とは、よるの衣の裾ながくはへたるをいふにて、寐たるさま也、と古説なり。妻とは、何にても端の方をいふ名也。衾は、裾の方ひまありとはなけれど、風の吹いりて寒きものなれば、かくいふなるべし。されど、衣といはずして、妻といふべきにあらず。誤字あるべしと千蔭はいへり。されば久老は、妻は雪の誤ならむといへり。げに此説穩なれど、雪吹風みやびかにもあらぬやう也。又衣といはずして、裾といへる事、あるまじきことのやうなれど、上古の人はながらふる妻とだにいへば、衣とはいはでも、ながらへたるよるの物の妻とは、おのづから聞ゆべきが故に、かゝるいひざま、古言にはこれならず多き物なれど、後世人は目をたふとび、思ひをたふとびざるが故に、かゝる詞づくりは穩しからずみれど、古言は一概にはいひがたし。後世心をもて古言をみば、おそらくは里言にいはゆる、持タル榛ニテタヽカルヽといふ類となりぬべし。されば雪吹風は穩なるやうにて、みやびかならず。妻吹風は、理なきやうにて詞に力あり。後世の學者おそらくは、十人が十たり、久老が説を可なりとすべし。寒夜とは、この事は冬十月なりければなり。端作には、この時を脱せり。○吾勢能君者 勢《セ》は、夫君をさし給へる也。者《ハ》もじは、衆人の中に、ことに心にかゝるをなげき給へる也。この者《ハ》もじのひびきにて、わがひとりねのさむきは、物の數ならずとおもひ捨たまへる心みえてあはれ也。〇獨香宿良武 香《カ》は、ひとりねずは、二人ねたまふべく、一人か、二人がうちは出まじければ、香《カ》とはいふ也。されば一人かねたまふらむ。又はふたりか寐たまふらむ。もし誰とにもあれ、二人(207)ねたまふならば、寒くもおはさじとよろこぶやうにもみえ、又もし二人ならばねたき事や。とうらめしくおぼすやうにもみえて、いづれともわかぬ御詞づくり、いとめでたし。
〔靈〕この御歌、表は、たゞ夫君の旅ねのさむからむをいとをしみたまへる御歌なり。されど、かばかりの事は、たゞ思ひてもやみぬべき事なるに、古人、ことさらに歌とよむ物にあらず。されば夫君のひとりねいかにさむくますらむ、といとをしくおもひやりたまふは、ひとへに、わがさむさに夫君のはやくかへりまさむことを、【もし、從駕たらば、わがはやくかへらまほしき情なり。とみるべきなり。】まち給ふ情を告やらせ給ひし御歌なり。されどこれ、いさゝかもあらはにいふまじきは、從駕をうらむるにおちむをはゞかりたまへる也。人のうへをいふは、多くはわが上なる事、前にもいへるが如し。みなこれ古人倒語の手段なる也。大かた倒語も、かうやうに詞をつくるをば、いたりともいふべしかし。
長皇子《ナガノミコノ》御歌
天武天皇の御子なり。靈龜元年六月薨。と續日本紀にみゆ。これ京に留りたまひて、從駕の官女のうちをこひ給ひし御歌也。上の與謝女王の御歌も、この御歌も、たゞひとり言のやうによませ給へれど、まことは、その人に贈りたまひしなるべし。前にもいへるが如く、さす人なくて、歌はよむものにあらねど、せまる事をつゝしみて、古人はかく、皆ひとりごとのやうによみなすなり。この心法をわきまへずして、後世は、まことのひとり言をよむ。をさなしともをさなし(208)や。
暮相而《ヨヒニアヒテ》。朝面無美《アシタオモナミ》。隱爾加《ナバリニカ》。氣長妹之《ケナガキイモガ》。廬利爲里計武《イホリセリケム》
〔言〕暮相而云々 二句は、隱のよせにおき給へる也。古點は、暮をくれにとよみたれど、もとくるとは、日のくるゝ事をこそいへ。これは、朝にむかへ給へれば、よひにとよむべし。もとよひとは、夜のはじめをいふ名なれど、一夜の事をよひともいふは、夜のはじめをもて、一夜の事にわたす、これ古言のみやび也。朝といひて、一日の事とするに同じ。されば夜のはじめをも、一夜をも、古はよひといへり。これは女の夜男に逢て、くらきほどは、かほもあらはならねど、朝わかるゝlこ及びて、みぐるしからむを恥て、凡帳の陰などにかくるゝさまを、隱《ナバリ》のよせとし給へる也。面無美は、美は例の賀里《カリ》といふ心也。おもながるとは、里言に面目《メンボク》ナイといふ心なり。或註に、面なみは、恥て面がくしするをいふといへるはかなはず。美《ミ》もじの心もうちあはず。又新枕せしあしたなど、面隱しをするを序としたり。と同書にいへれど、新枕にもかぎるべからず。それは、隱を面隱しの事と心えられつとみゆるは、面といふもじ、隱といふもじにかゝづらひての説なるべし。されど面無と、隱とは二事なればこそ、美《ミ》もしはおかれたれ。かへす/\、實もたれにはかゝる弊あるを思ふべし。○隱爾加 隱は、まへにもありし伊賀國名張郡なり。古點、かくれとよめるは非なり。加《力》は、そこならずば、いづかたにぞいほりたるべければ也。かく名張をしもさしたまへるは、やゝ都より程遠からねば也。氣長妹とあれば、これは還御の(209)ほどなるべし。くはしくは、下に情をとけるをあひてらして、此義を心うべし。○氣長妹之 宣長は、氣《ケ》は伎倍《キヘ》の約にて、來經《キヘ》長き心なりといへり。されど、此説おもふ所あり。氣《ケ》は息《イキ》にて、氣長《ケナガキ》とは、長息なるべし。長息はなげき也。されば、氣長妹とは、逢がたさに長息せらるゝ妹といふ心なり。これは、さきにも人のいへりし事なり。逢がたきを、けながきもて思はする事、古言の常なり。○廬利爲里計武 もと、廬は、旅中にかぎらぬ事ながら、此御歌にては、旅舍の事なり。或註に、行宮をいふとあり。げに從駕の事なれば、行宮にこの女房もやどるべければ、やがて行宮なりともいふべけれど、天皇の御うへにあらざれば、行宮とはいふべからず。もとより、行宮のうちに寐たるはいふも更なるを、かくこの女房の私にかり廬つくるらむやうによみ給へるは、例の古言のみやび也。理なき事をも古人はいふ事、皆倒語なれば也。これももと私の事なれば、幸に詞のさはらぬやうによみ給ひしにて、ひとへにこれはゞかりより出たる詞づくりなるぞかし。爲里計武《セリケム》といふ詞、志計武《シケム》といふ心ながら、義はたがへり。廬をつくりての未然をおもはする詞なる事、經緯の江緯の所以なり。されば廬してそこに旅寐せむことをおぼしやりたる心を思はせて、爲里《セリ》とはよませ給へる也。計武《ケム》はきしかたをはかる脚結なり。これは上の加《カ》もじのうちあひなり。これらの脚結、すべて情のためにおかせ給へる也。
〔靈〕この御歌、表は、こよひ妹の旅やとりせむ處を、おぼしやらせたまひし也。されどさばかりの思ひは古人、こと/”\しく歌とよむものにあらねば、情は言外にあるべき事必せり。さればお(210)もふに、從駕日を經て、久しくあひたまはぬ女房を、まちかね給ふ御心を告やらせ給へる御歌也。加《カ》・計武《ケム》など、ひとへにかへりこむ日を待たまふ御心をさとしたまへる也。されどいささかも、詞にあらはなるまじきは、幸の日をふるをうらみ給ふにおつべければ、深くはゞかり給へる御詞づくり也。かく、公をふかく憚りたまひし御詞づくりなれば、私はけしきにだにみゆまじき事なるに、その待かね給ふ御心、言外に森々たり。かくこそ詞はあらまほしけれ。とぞおぼゆるや。
舍人娘《トネリノノイラツメ》從(テ)v駕(ニ)作歌
此娘の事、卷二にいふべし。
丈夫之《マスラヲノ》。得物矢手挿《サツヤタバサミ》。立向《タチムカヒ》。射流圓方波《イルマトカタハ》。見爾清潔之《ミルニサヤケシ》
〔言〕丈夫は、益荒男の義也とある説にいへる、いかゞあらむ。益の義、心ゆかず。さるは、ことにおもひよれる事もなし。しかれども、此集卷十六に、荒雄等。卷十七に、荒し雄などよめるには、別あるやうにおぼゆる也。之は古點がとよめれど、乃《ノ》とよむべし。乃《ノ》・賀《ガ》の別、まへにいへるが如し。こゝは丈夫を主とよめるにあらねば、必|乃《ノ》たるべき也。○得物矢は、古點、とも矢とあれど、仙覺が抄にひける風土記の歌に、さつ矢とよめるに從ふべし。古事記上卷神典に火遠理命者《ホヲリノミコトハ》爲《シテ》2山佐知毘古《ヤマサチビコト》1而|取《トリタマフ》2毛麁物《ケノアラモノ》・毛柔物《ケノニゴモノヲ》1云々とある、この毛麁物・毛柔物を得る心にて、得物とはかけるにこそ。こゝは的矢なれど、矢をいひなりて、かくいふなるべし。手と挿は、片(211)矢は弦にかけ、片矢を小指と食指の間に挿みながら、片矢を射る也。この手挿むは、設《カヘ》矢の方なれど、片矢は今射る時のわざなれば、手挿をもて射る事をさとせるなるべし。○立向は、的にたちむかひ也。以上射流といふまでは、的といはむ爲のよせ也。かく上古には、上句よりも長きよせは置たり。これさらに、詞のあやにはあらず。いはまほしき事の、いへば弊ある事をしりて、それにかへたる也。くはしくは、下に情をとけるにてらしておもふべし。短きは冠詞なり。長きはかゝるも多し。いはまほしき情の長短によりて、よせの長短とはなる也としるべし。〇圓方波 圓方は、浦の名なり。仙覺が抄に伊勢(ノ)國(ノ)風土記(ニ)云。的形(ノ)浦者此浦地形似v的(ニ)故以(テ)為v名(ト)也。今已《ニ》跡絶(テ)成2江湖(ト)1也。天皇行2幸(シタマヒテ)浦(ノ)邊(ヲ)1歌云。麻須良遠能《マスラヲノ》。佐都夜多波佐美《サツヤタバサミ》。牟加比多知《ムカヒタチ》。伊流夜麻度加多《イルヤマトカタ》。波麻乃佐夜氣佐《ハマノサヤケサ》とあるは、この歌をひが聞しけるか、又は此集のたがへるかしりがたし。波《ハ》もじ、此歌の眼なり。これ大かたは、他の浦々どもにぬけ出たるを、歎じて波《ハ》といふ也。しかれどもこれもはら、情のひゞきをむねとす。くはしくは、下に靈をとけるにみるべし。○見爾清潔之とは、この的形の浦は、みるにいとこゝちよしといふ也。爾《ニ》もじ、上の波《ハ》もじに照らしたる脚結にて、目のうへにのみ、さやけしといふほどの心なり。目にむかへたるは心なり。されば此爾もじの裏には、心にさやけしと思ふばかりまではあらず、との義必ありて、別に目にも心にもさやけくおぼゆる物ある事を思はせたる也。下に情をとくをもてさとるべし。清潔之《サヤケシ》とは、里言にサツパリなどいふ心にて、遺憾なくこゝちよき心なり。
(212)〔靈〕この歌、表は、此圓方浦、他處にすぐれて眺望するにいとさやけし。とふかく此浦のけしきをめでたる歌なり。しかれども、かく勝地をめづるばかりのはかなき事を、こと/”\しく古人、歌とよむものにあらねば、必別に情ある事明らか也。されば波《ハ》もじ、爾《ニ》もじのてりあひをくはしく思ふに、この娘は、舍人皇子の御思ひ人なりける事、この卷二に贈答あるにしるければ、この圓方波とあるは、舍人皇子にむかへ奉れるにて、その御かたちのめでたきのみならず、心にさへ忘られず。まことに目にも心にもさやけきは、この浦にいたくまさり給へりとの心にて、從駕日をへで戀しさ堪がたき心を、皇子に告たてまつれる歌なる事必せり。大かた勝れたる物をもて、それよりもいたく勝れたりと思ふ心を、たゞ波《ハ》もじと爾《ニ》もじにさとし、表はたゞ、此浦をめづるになしはてたる詞づくり、まことに絶妙といふべし、されどこれたゞ、たくみに詞をつけたるにあらず。いさゝかも情を詞にあらはすべからぬは、從駕にはゞかりて也。かの皇子の御かたちよりはじめて、御心ざまもいたくすぐれておはす事は、たとひいかばかりいふとも盡ぬべきにあらねば、かく長々しきよせに代たる手段、かへす/\上古の人の倒語の至妙、いはむも中々なりかし。
三野連《ミヌノムラジ》【名闕】入v唐(ニ)時|春日藏首老《カスガノクラノオビトオユガ》作歌
名闕の二字は、後人のくはへしなるべし。三野連の事、古註にくはしくみえたり。春日藏首は、(213)もと弁記といへりし僧なりしを、大寶元年三月、この老に、春日藏首と姓を賜へる事、續日本紀にみゆ。
布根竟《フネハツル》。對馬乃渡《ツシマノワタリ》。渡中爾《ワタナカニ》。幣取向而《ヌサトリムケテ》。早還許年《ハヤカヘリコネ》
〔言〕在根良は、布根盡《フネハツル》の誤か。百船能《モヽフネノ》の誤か。此集卷十五に、毛母布禰乃波都流對馬《モヽフネノハツルツシマ》とよめり。又は、百都舟《モヽツフネ》の誤か。と冠辭考にいへり。げに在根良《アリネヨシ》は、舟人の目當となるがゆゑに、此嶺の在るがよしといふ心也。と長流のいへるを、契冲すでにこれを破して、かの嶺には神ませば、あらねといふ心ならむといへり。宣長は、布根竟《フネハツル》の誤ならむといへり。眞淵が考に同じけれど、良竟字形ちかければ、今この字を用ひたり。いづれも津とかゝれる也。印本、在根良とあるは、かへす/\心えず。○對馬乃渡云々 から國には、對馬よりわたれば也。渡中爾は、海中にといふ也。大かた海を和多《ワタ》といふ事、海神の御名を、綿津見《ワタツミノ》神とまをすにしるべし。これ和多里《ワタリ》の里《リ》をはぶける也。おほかた渡の大なるは海なれば、やがて名としたる也。渡中としもよめるは、いまだから國にゆきつかぬ所をいへるなり。爾《ニ》はひとへにわた中を處としていへる也。○幣取向而 幣を、神にたてまつりてといふ也。取向とは、幣を取りて神に向ふる義也。海路の無恙をいのるためなり。而《テ》もじ、上の藤原(ノ)宮(ノ)※[人偏+殳]民が歌にいへるが如く、上古に用ひたる而《テ》もじは而《テ》もじに多事ををさめたるもの也。されば、こゝも幣とりむけて、船中の無事をいのりて、舟とく※[手偏+旁]《コギ》てなどやうの多事を、この而もじにをさめたるなり。後世のごとく、たとへば、煮てくふ。問(214)ひて知る。などやうに、事のつゞきたる間におく詞也。とのみ心えては、古人の用ひたる而《テ》もじはいぶかしかるべし。されど古の用ひざまの如くならでは、而《テ》としもいふ詮はなきを思ふべきなり。ことに。この而《テ》もじは、上の爾《ニ》もじに照らしておかれたる、此歌の眼なり。くはしくは、この下に靈をとくに、眼なる事をさとるべし。○早還許年 年《ネ》はもと去倫の奴のかよへる脚結なる事前にいへるが如し。この年《ネ》とよまれたるも、ふかく情をひゞかせたり。相照らしてこゝろうべし。
〔靈〕此歌、表は、對馬のわた中にて、神に幣とりむけ、海路の無事をいのり、恙なく公事をしはてて、はやくかへりこね。と船中無事にはやく歸洛あれとよめる也。されどさばかりの事は、かりそめの別にも、なべての人もいふ事なるを、こと/\しく、古人歌とよむべきにあらず。さればおもふに、爾《ニ》もじ、而《テ》もじの義をふかく考ふるに、渡中にて幣たてまつり、船中恙なく公の事しはてゝはやかへれといへるやうなれど、渡中爾としもいへるは、いまだから國にいたらぬ半途をすゑて爾《ニ》といひ、而《テ》もじはおほやけの事しはてて、はやかへれといへるやうなれど、から國の公事もすておきて、半途よりかへれといふ心にて、年《ネ》もじも、この心にうちあはせたれば、いたく待久しからむをかなしめる情を述たる歌なる事しろし。公に對したてまつりては、いとあるまじき情なれど、情の切なる所より出たる也。されど遣唐使はいと重任なれば、ふかくはばかりて、いづれともかたづけず。爾《ニ》もじ、而《テ》もじ、年《ネ》もじに、情ををさめたる也。かへす/\(215)いへるが如く、いづれともかたづけず、公・私をそなふる詞づくりぞ大かた詞づくりの至なる。學者よく/\此妙處を味はふべし。
山上臣憶良《ヤマノヘノオミオクラ》在2太唐(ニ)1時憶2本郷(ヲ)1歌
大寶元年春正月乙亥(ノ)朔丁酉以2守民部尚書直大貳|粟田《アハタノ》朝臣|眞人《マヒトヲ》1爲2唐執節使(ト)1 中略 無位山於憶良《ヤマノヘノオクラヲ》爲2少録(ト)1云々、と續日本紀にみゆ。まへの遣唐使と同時なり。
去來子等《イザコドモ》。早日本邊《ハヤクヤマトヘ》。大伴乃《オホトモノ》。御津乃濱松《ミツノハママツ》。待戀奴良武《マチコヒヌラム》
〔言〕去來は、いざなふ詞なり。佐《サ》もじ、すむは不知の義也。濁れば、誘ふ義となる。おのづから清濁の義によれり。子等 古點、いざや子らとあれど、也《ヤ》もじ詮なければ、いざ子とも、とよむべし。船中の人を云ふ。と或註にみゆれど、端作に在大唐時とあれば、船中の諸人といへるは、遣唐使をはじめその屬官の、唐土にをるわが國人どもをさす也。といふ心にや。船中といふはまぎらはしければ、ことわる也。これは、ひろく在唐のわが國人どもをさせる也ともみるべけれど、去來《イザ》、又、邊などの詞を思へば、※[楫+戈]師《カチトリ》・舟子ともをさしたりとおぼしき也。○早日本邊 古點、はやもと訓じたるは誤なり。此集卷三なる、去來兒等《イザコドモ》。倭部早《ヤマトヘハヤク》。白管乃《シラスゲノ》。眞野榛原《マヌノハリハラ》。手折而將歸《タヲリテイナム》といふ歌も、はやもとはよむまじき也。はやくとよむべし。【子とさす事、歌によりて、さま/\なるべし。なづみてみまじき也。ヨクワキマフベシ。】卷十五に、和伎毛故波《ワギモコハ》。伴也母許奴可登《ハヤモコヌカト》。麻都良牟乎《マツラムヲ》云々また卷十五 奴波多麻能《ヌバタマノ》。欲和多流月者《ヨワタルツキハ》(216)波夜毛伊※[氏/一]奴香文《ハヤモイデヌカ》などを據としての訓なれど、これは兩首ともに、下に可もじありて、そのうちあひに母《モ》とはおけるにて、これとは例ことなり。母もじは、うちあひにも、脚結の義にもかなはぬ也。邊《ヘ》は、早くやまとへかへらむ、と人々にいへる也。邊《ヘ》もじに、此心をさめたる也。邊《へ》もじは、前にもいへるが如く、方角をさす詞にて、そのさす方角のかなたに意ある事をさとす義なる事、例の江緯の常なり。こゝをもて、舟人ならむかとはいふ也。卷十五に、奴婆多麻能《ヌバタマノ》。欲安可之母布禰波《ヨアカシモフネハ》。許藝由可奈《コキユカナ》。美都能波麻末都《ミツノハママツ》。麻知故非奴良武《マチコヒヌラム》といふ歌、下句同じ。これらを思ふべし。○大伴乃云々 冠辭考に、大伴氏の遠祖|道臣《ミチノミノ》命、大久米部《オホクメヘ》をつかさどりたり。神武天皇の御紀に瀰都瀰都志《ミヅミヅシ》。倶梅能固邏餓《クメノコラカ》とあそばしゝは、久米部のみならず、道臣命をもかねたまへれば、みづ/\しといふ心に冠らせたるかといへり。又高師の濱とつゞけたるは、建《タケ》き心にや。又は姓氏録に、大伴大田宿禰の次に、佐伯日奉《サヘキヒマツリノ》造は、談士《タカシノ》連(ノ)之後也。とあるよりいふにやといへり。予もおもふ事もあれど、證をえて後いふべし。こゝに冠をおかれたるは、ひとへに情にひゞかせむがため也。下にとけるをてらしてしるべし。御津は、難波の御津なり。西の國には、こゝより舟出せし所なれば也。この故にそこの濱松をよまれたる也。○待戀奴良武とよめるは、即この濱松が、われらが歸るを待こひぬらむとよまれたる也。家人のまつを、松によせたる也、と古註みないへり。これ予がかねて歎息する所なり。大旨に、表と情を混ずといへるはこれらの事なり。松がまちこひぬらむとよめるは、表なり。家人の事は情也。ゆめ/\(217)これを混ずまじき事也。かくいふ故は、わが神ぶみの御教、内外・幽顯を混ずる事をいたくいましめ給ふ事切なり。今の世までも、神前に淨・不淨を正し、血穢をいむは、もはら内外・幽顯を混ずるを神のいみ給ふが故也。この所謂くはしくは、古事記神典燈にいへり。されば、表は表にて註し、情は情にて註せずしては、神の御心にもそむくべき也。内外・幽顯を混ずる時はすべてなに事も全からぬがゆゑに、古人は、かたく内外を混ぜざりし也。後世心をもてみまじき事この故ぞかし。されど後世心には、松が待らむ事、いとあるまじき事なりと思ふべし。非情の物を有情のごとくいふは倒語の常なり。まへの思賀乃辛崎《シカノカラサキ》、おもひあはすべし。猶この例いと多し。此ぬし、濱松がまちこひぬらむとよまれたるは、ひとへに内外を混ぜじとのかまへなるを、しか註せば、此ぬしが心用ひをやぶり、人がらをもおとすわざなるべし。註者の心を用ふべきは此事也。わが御國言は、とくにも、用ふるにも、この心得肝要ぞかし。奴《ヌ》は、倭をいでしより、年月あまた經たる事をおもはせむとて也。戀しとても、さまで年月へぬほどは、しのびてもあるべけれど、今は年月あまた經て、まちこふるに至れるよしをいふ也。良武はもと、上にうちあひなくては、おかぬもの也。うちあひなきを片響といふ。されど片響は、その法あり。これは中の良武の例なり。まちこひぬらむは必定なれば。といふほどの事をはぶける也。上にひける卷十五の歌もこれに同じ。
〔靈〕この歌、表は、いざやまとへはやくいなむ。今は年月もへたれば、みつの濱松の、われらをま(218)ちこひぬらむが、いとをしきに。と舟人にかたらひたるによみふせられたる也。されど、もとより松の立ちこふべきよしもなく、その松をいとをしまむも理もなき事なり。かゝるはかなき事を、古人、こと/”\しく歌とよむものにあらず。されば思ふに、ひさしく唐土にありて、戀しさ堪かたくなりぬる心を述たる歌にて、松に詞をおほせたる也。これいかなれば、心もなき松に詞をおほせたるぞといふに、遣唐にえらばれたてまつれる身なれば、たとひ年月へたりとも、私情をいはむ事はゞかりあるが故に、かくは詞をつけられたる也。かく詞に、公をおもくせられし心中、いかにくるしかりけむ。とおもひやられて、詞づくりの至妙、いはむも中々なり。かへすがへすも論らへるが如く、いはまほしさの堪がたきを、かくつゝしみて詞をつけたる、そのくるしさいふにはいたくまさる事、よく/\おもふべし。
慶雲三年丙午幸2難波宮(ニ)1時
文武天皇の御紀に、九月幸して十月に還ましゝよしみゆ。
志貴皇子《シキノミコノ》御作歌
葦邊行《アシベユク》。鴨之羽我比爾《カモノハカヒニ》。霜零而《シモフリテ》。寒《サムキ》暮夕《ユフベハ・ヨヒヨヒ》。和之所念《ヤマトシオモホユ》
〔言〕葦邊行 難波の宮のあたりのさまなるべし。邊とは、葦の生たる方にそひて、鴨のうかびゆく(219)を云。鴨の蘆邊にそひゆくは、おのれも寒き故に、陰をたのむなるべし。この上句は、御まのあたりのさまをよませ給へるなり。羽我比は、羽のうちあひたる所を云。山のかひ、又衣のうちあひたる所を、上がひ・下がひといふなどこれ也。かふは、ゆきかふ・ちりかふなどいふに同じく、もと、加比《カヒ》は、久波比《クハヒ》のつゞまれるなり。久波比《クハヒ》は、咋あひ也。くはしくは、前にいへり。○霜零而 鴨の羽がひをしも、霜のふり所とし給へる妙也。水の上にすら、霜のふりたるをおほせられたるにて、その餘の所の霜をおもはせられたる也。もと衣をうちあはせたるは、風を防ぐ爲なれば、かれも猶、羽がひは霜をふせぐ爲ならむに、そこにしもふるは、寒さいかにたへがたからむ。とおぼしめすなり。而《テ》もじ、例の多事をゝさめ給へる也。鴨のはがひに霜ふりしのぎて、木・草・屋のうへなどにも深くて、閨のうちまでもさえとほりてなどやうの多事也。これは霜ふりて寒きとやがて下にうちつゞきたるやうにみゆれば、予がかくいふを、もとめすくしたりと思ふ人もあらめど、しからず。さむきは、御みづからの御うへなれは、鴨の羽がひに霜ふりたりとて直に御身に寒からむやうなし。後世、輕率なる詞づかひになづみて、古人の詞づかひをかろしむまじき也。○寒暮夕云々 この暮夕の二字安からず。夕和の二字、家といふ字の誤ならむか。と或説にいへり。おもふに、もし暮夕はよひ/\とよませむがためにかけるにや。また夕の字は、者《ハ》の誤にもやあるらむ。又は、波《ハ》もじはつけよみにして、夕和二字倭の誤にやあるらむ。いづれにもあれ、波《ハ》もじあるべき語勢なり。和の字をやまとに用ひられしは、奈良の朝よりの事(220)にて、藤原の朝までは、倭の字をのみ用ひられしかば、これ誤なり。と眞淵が萬葉考にあり。かうやうの事、管見の及ぶ所にあらず。しかれども此集は、家持ぬしのかゝれたるにて、志貴皇子の親書にもあらねば、この論無益なるべし。やまとゝおほせられしは、實はさし給ふ人あるなるべし。之れをひろく國になしたまへる、これ古人詞をつけし常なり。之《シ》もじは、倭の筋のみひとすぢに思はるゝよし也。もとこれ從駕なれば、他のすぢはいさゝかも心におこるまじき事なるに、との御心よりおかせ給へる也。されば思はずに、やまとのみ一筋におもはるゝよ。との御歎なりとしるべし。四の句に、波《ハ》もじ必あるべき語勢也。と前にいへるは、かばかりならぬ霜夜には、倭の事も思はれざりしに。との心となれば也。この之《シ》もじにむかへて思ふべし。者《ハ》もじ、之《シ》もじひとへに、從駕の表をたて給へるなり。所念とは、おもはるといふ心也。おもほゆとは、何事にもあれ、心とおもふにはあらで、おのづから思はるゝを云也。これにも今釋せる心はこもれるをや。
〔靈〕この御歌、表は、蘆邊をうかびゆく鴨の羽がひに、ふりしのぐばかりならぬ霜夜には、倭の事いさゝかも心にかゝらざりしに、かゝる寒き夜は、思はずにやまとのみ一筋におもはるゝよ。と從駕の身にして他念あるは、いとあるまじき事や。とみづからわが御心を歎じ給へる也。されどさばかりの歎息は、たゞなげきてもやみぬべきを、こと/”\しく、古人、歌とよむものにあらず。されば思ふに、かゝる寒夜のみならず。倭なる人のこひしき御心を、告やらせ給ひし御歌な(221)る事明らか也。されど、從駕にはゞかりて、かく詞をつけたまへる也。御詞こそあれ。蘆邊行鴨の羽がひをしも、霜の置所とし給ひし御詞づくり、いかに上古の人たりとも、不容易の境たるべし。詞を麁暴につかひ、無味の句調をたふとぶ人、眼をひらくべきなり。
萬葉集燈卷之四 終
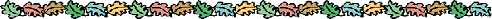



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)