
(最新見直し2011.8.25日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、万葉集の文人歌について確認しておく。
2011.8.28日 れんだいこ拝 |
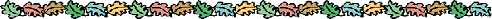
(117)萬葉集燈卷之三 平安 富士谷御杖著
本集卷之一 其三
高市古人《タケチノフルビト》感2傷(メ)近江(ノ)舊堵(ヲ)1作歌 或書(ニ)高市(ノ)黒人《クロビト》
古《イニシヘノ》。人爾和禮有哉《ヒトニワレアレヤ》。樂浪乃《サヽナミノ》。故京乎《フルキミヤコヲ》。見者悲寸《ミレバカナシキ》
〔言〕古訓は、ふる人にわれあるらめや。とあれど、らめ〔二字傍点〕をつけてよむも理なく、義もかなはず。古今六帖に、上を、いにしへの〔五字傍点〕とよめるが正しかるべし。されば、「いにしへの人にわれあれや」とよむべし。此よみ人の名、古人といふより、古訓はしかよめるなるべけれどうけがたし。古の人とは、大津宮の世の人をいふ也。その世の人にてわれあらば、此故京をみても悲しかるべき事なれど、さにもあらぬにかなしきは、心えがたき事やといふ也。安禮也《アレヤ》は、安禮婆也《アレバヤ》をはぶける也。哉《ヤ》は疑なり。○樂浪乃 まへにいへり。○故京乎の乎もじ.心をとどむべし。われ、今の世の人なれば、この大津宮のあれたるをみたりとて、かなしくはあるまじき事なるを、との心もはら此乎もじにあり。悲寸とゝぢめたるは、上の疑の也《ヤ》のうちあひの法なり。
(118)〔靈〕此一首、表は、大津の宮の世の人ならば、此都の荒れたるが悲しかるべき理なり。しかるに、その世の人にもあらぬに、この故京のいたくかなしき、その理のあたらぬをばあやしみたるによみふせたる也。されど、このあやしみを解得たりとて、何の益もあるまじき事がらなるは、これ本情にあらざる所以なり。されば、本情は深く此京都をかなしめる事を述たるなれど、いさゝかも詞にあらはなれば、上の人麻呂ぬしの歌に釋せるが如く、さばかりの みかどをあはめ奉るにもおち、おのがさかしらにもなりぬべきをおそりて、かなしきが不審なる一すぢにのみ詞をつけられたる也。此詞のつけざま容易の構思とはおもはれず。古人、詞に公私をそなふる手段の絶妙よく/\味はふべし。
樂浪乃《サヽナミノ》。國都美神乃《クニツミカミノ》。浦佐備而《ウラサヒテ》。荒有京《アレタルミヤコ》。見者悲毛《ミレバカナシモ》
〔言〕樂浪 まへにくはしくいへり。これはやがて、さゝ浪の國とよめるをもおもふべし。いはゆる吉野の國・泊瀬小國などよめるに同じ。都《ツ》は、時つ風・天津風などいふ津《ツ》もじに同じく、そこにのみつくをさとす脚結なり。されば、此神は此樂浪の國をしもうしはき給ふ神を申す也。美はたたへ奉りていふ也。○浦佐備而は、浦《ウラ》は假名にて、前の卜歎《ウラナゲ》の下にいへるが如し。表にむかへて人の目に見えざる所を云。さればこゝろに思ふ所をいふ也。佐備《サヒ》は、神典【古事記上卷】に「勝佐備《カチサヒ》」その外、をとめさび・をとこさび・神さび・翁さびなどに同じきを、これらには同じからずとて、不樂《サブシ》・(119)不怜など此集にかける心にて、なぐさめがたき心地といふ説あるは、くはしきが如くにして麁なり。もと、佐夫《サフ》といふは銅鐵などのさびといふが如く、内なる物のおのづから外にうかびいづるを云。さればこゝは、國津御神の御心のうちにおぼす事の、おのづから外にうかび出たるよしを云也。國津御神の御心のあらび、つひに世の亂もおこりて都の荒たるをいふ。國津神、もと神典に於此國道速振荒振國神等之多在是使何神而將言趣《コノクニゝチハヤブルアラブルクニツカミダチノサハナルコレイヅレノカミヲツカハシテカコトムケム》。とみゆるをはじめ、すべてはじめをはりたゞことむけやわ(は?)しかたきは國津神なるよし、神典中にむねととき給へり。されば、ここに國津御神とよまれしも、もとやはしがたき神としていふにて、さる故に、浦佐備而《ウラサビテ》とはよめる也。たゞうら〔二字傍点〕とばかりよめれど、さるやはしがたき神の御心のあらびの、外にうかびたるをいふ也としるべし。この國津御神あきらかならざるが故に、古註ども、皆|浦佐備《ウラサビ》の義もくはしからぬなり。而《テ》もじ、上にいへる如く、直に下につゞく義ならぬをしるべし。荒有京《アレタルミヤコ》といふが中にも神のあらび給ひての事なるをもちてみるべし。多流《タル》は、※[氏/一]安流《テアル》をつゞめたる脚結なり。○見者悲毛 こゝまでも、國津御神の御あらびをかけてみるべし。毛《モ》は、上にいへるがごとく、かなしけれどいかにともすべきよしなき歎なり。
〔靈〕此歌、表は、この大津に都し給ひしが、國津神の御心にかなはずして、あらびます御心つひにことむけがたくて、此都のあれたるせむすべなさを、ふかく歎たるによみふせられし也。されどしからば、たゞ歎きてもやみぬべきを、歌としもよまれしは、必別に本情あるが故なる事しるし。(120)されば思ふに、これまた、此宮の荒廢を、ふかくをしみなげかれたる歌也。されどこれも、上と同じはゞかりに、かく國津神の御心になしはてゝ詞をつけられたる、まことに常人の企及ぶべからざる手段なり。後學よく/\この倒語の至妙をおもふべし。
幸2于紀伊(ノ)國1時|川島《カハシマノ》皇子御作歌 或(ハ)云山(ノ)上憶良(ノ)作
この幸は、 持統天皇也。川島皇子は、 天智天皇の御子也。
白浪乃《シラナミノ》。濱松之枝乃《ハママツガエノ》。手向草《タムケグサ》。幾代左右二賀《イクヨマデニカ》。年乃經去良武《トシハヘニケム》 一云|年者經爾計武《トシノヘヌラム》
〔言〕白浪乃云々 仙覺抄すでに、白浪の濱松がえといふつゞき、おぼつかなきよしいへり。眞淵は浪は良の誤にて、紀國なる白良《シララ》の濱にや。催馬樂に紀の國の之良々《シラヽ》の濱とあるによりていへり。しからば、四言によむべし。しかるに、此集卷九に、この歌、白奈彌之《シラナミノ》とていでたり。されば猶、白浪乃《シラナミノ》なるべくはおぼゆれど、おなじ卷九に、同國に白神《シラカミ》の磯とよめれば、それも那《ナ》は加《カ》の誤にて白加彌之《シラカミノ》にやあらむといへり。これによらば、もし浪は紙などの誤にもやあるべき。千蔭は猶、白浪のよする濱といふべきをはぶけるが、かへりて古意ならむといへれど、なほ眞淵がいへる如く、古き詞つきとも覺えぬ事也。また宣長は、古事記なる「幣都那美曾爾奴伎宇※[氏/一]《ヘツナミソニヌギウテ》」とあるによりて、浪といふにしたがはれたれど、これは衣をぬぎ棄るさまをたとへたるにて、據とはしがたくや。土佐日記の「浪の礒には」とあるをもひかれたれど、それは、此京になりての詞つきぞかし。(121)新古の別よくおもひわくべし。眞淵が説、なほみどころありといふべし。濱松之枝は、濱に生たる松の枝なり。此集卷九には、此歌|松之木《マツノキ》とあるを、古本には松之本《マツガネ》とあり。松がねとよむべし。さればこゝの枝も、根の誤にて、松が根なるべしといふ説みどころあり。されど、そこにこの濱松のもとにて、手向せさせ給ひし事を傳へいふを聞きたまひて云々。と註したるは非なり。乃《ノ》もじ、此松がねにてたむけせしを、乃《ノ》とはいふまじきをや。予、根をしかるべくおもふ心は、下にいふべし○手向草 草は假字にて、種《クサ》なり。たむけに用ふる具を云。たむけとは、旅だつ時山上にてする祭の名なり。又首途ならでも、大かた、旅路の無恙をいのるにもいへり。後世、神などに物たてまつるを、たむくといふは誤也。此集卷十三に「相坂山丹《アフサカヤマコ》。手向草《タムケグサ》。※[糸+系]取置而《ヌサトリオキテ》云々」とよめるをみれば、ぬさも手向ぐさのうちなるべし。代匠記には、くさ〔二字傍点〕はそへたる詞にて、松を云。松をむすびてたむくる也。此集卷二に、有馬(ノ)皇子「磐白乃濱松之枝乎引結」とよめりといへり。此説うけがたし。乃《ノ》もじ、手向草乃松とあらばこそあらめ。又かの有馬皇子の結び給ひけむは、又かへりみむのしるしにとこそはむすび給ひけめとぞおぼゆる。これは、松がねにおひたる手向に用ふる物をいふなるべし。されば松之根のかた、心ひかるゝなり。○幾代左右二賀云々 この濱松のあたりにてたむけせしは、今は幾代までになりぬらむと云也。此卷の上に、 齊明天皇紀(ノ)温泉の幸あり。又中皇女命紀(ノ)温泉におはしての御歌あり。 齊明天皇はこの川島皇子の御祖母にまし/\、中皇女命は御伯母なり。されば、 齊明天皇・中皇女命などの紀(ノ)國におはし(122)しついで、此濱松のあたりにてたむけせさせたまひし事をよませ給へるにこそ。左右《マテ》は、眞手の心にてかゝれたる字なること、前にくはしくいへり。集中、左右手《マデ》ともかけり。此脚結は、大かた限あることの、その限を超てのかなたの限をさす詞也。年ふるといへど、大抵かぎりあるべき事なる、その限を超たる限をさして、幾代左右《イクヨマテ》とはおほせられたる也。さまではおほせられずともありぬべき所のやうなれど、これは、この御歌の情、たゞいく代へぬらむとのみにては切ならぬが故なり。猶下に、情をとけるにてらして心うべし。賀《力》は疑のか也。この字濁音なれば、加を誤れるなるべし。その經たりし年のほどをしらむとおもふには、也《ヤ》も同じけれど、幾・何・誰などの類の疑の詞の下には、必|加《カ》をおくべき法なるがうへに、いく代といふばかりの年の數は、大抵もはかりしらるゝ心にいはでは、情に切ならねば也。奴《ヌ》は上にくはしくいへるがごとく、年の經ぬるまでの間に御心はあるなり。これもはら情にあづかる所也。一云の者《ハ》もじにては、年の方むねとなり、乃《ノ》といへば、經ぬる方むねとなるがたがふ也、乃《ノ》とある方あはれなるべし。良牟《ラム》・計牟《ケム》、情においていづれにもあるべし。
〔靈〕此御歌、表は、この濱松がねなる手向草のたむけに用ひたりしより、今はいくよといふばかりまでにか年のへぬらむ、とその手向草のひさしさをおぼすによみふせ給へるなり。されどこれ、歌とよむばかりの事がらにあらねば、必別に情あること明らかなり。されば思ふに、上にいへるが如く、齊明天皇・中皇女命などの、こゝにて手向せさせ給ひしも、今はかくれたまひて、年(123)いたくふりにしかば、その御うへをしのび給ふ御心を述たまひし御歌なるべし。もし、この御うへどもにはあらずとも、必ふりにし人をしのび給ふ御心にはうたがひなき也。しかるにいかでか、かゝる御詞はつけたまへるぞといふに、今 持統天皇の幸の御供にて、かの御うへどもをしのばせ給ふは憚あれば、この手向草のいくよといふばかりまで年經たるらむ、となか/\はかなき物のひさしきをもて詞とはし給へるなり。されば、これ畢竟懷古の御歌なるに、うはべはいはひ歌のやうなる詞づくり、此集卷二、比賣島にて、女の屍をみてよめる歌のたぐひ也。上古はかゝる歌多し。古人の倒語をみむは、たやすからぬ事なり。後世人こそ、かゝはりもなき物どもを、題にひかれては、よしもなき歌をもよめど、古人は、さるはかなきわざかつてせざりしかば、もしかゝる御歎をはばかり給へるにあらずば、何のゆゑありてか此手向草の經たる年をばはかり給ふべき。この故に、幾代左右二賀《イクヨマデニカ》とは、こと/”\しくよませ給へる也けり。かの御うへどもの御歎なるをば、かく手向草の久しきうへにのみ御詞をつけられて、今此幸のはゞかりをそこなひ給はず。此詞づくりのさま、よく/\、めをも心をもとゞめて思ふべし。
日本紀(ニ)曰朱鳥四年庚寅秋九月天皇幸2紀伊(ノ)國(ニ)1也
越(ル)2勢能《セノ》山(ヲ)1時|阿閇《アベノ》皇女御作歌
この皇女は、川島(ノ)皇子と御兄弟也。此幸の時ともに御供なりけるなるべし。日並知(ノ)命の御妃(124)文武天皇の御母なり。
此也是能《コレヤコノ》。倭爾四手者《ヤマトニシテハ》。我戀流《ワガコフル》。木路爾有云《キヂニアリトフ》。名爾負勢能山《ナニオフセノヤマ》
〔言〕此也是能とは、これがこの何か、と下の詞にかけていふ詞也。也《ヤ》は疑なり。これとさすは、なにゝもあれ物ひとつをさしていふ也。「この」とさすは、その「これ」とさしたる物の據をさす也。その據をいふはすべて新意也。後撰集に、蝉丸「これやこのゆくもかへるもわかれつゝ」とよめるも、「これ」とは遇坂の關をさし、「この」とは、その名のよしをさしたる也。この遇坂の名は、もと忍熊王の軍と、こゝにあひしよりの名なる事 神功皇后の御紀につまびらか也。しかるを行人のゆきかひにあふ故の名かといへる、これ新意也といふ所以也。こゝも、此勢の山を、夫君《セノキミ》と同等の名かとよませ給へるなり。その例正しき事おもふべし。○倭爾四手者とは、爾四手者は、里言にデハといふ心也。御客中にむかへてよませ給へる也。御客中にては、夫君の御事もおぼしたえておはすさまを此脚結にさとし給へる也。これひとへに表をつゝしみ給ふ也。されどこれ、詞にあらはなれば、かへりて天津罪をうべし。此けぢめくはしくおもひしるべし。○我戀流 この句は、下の勢《セ》につゞきて、わがこふる所のわが夫《セ》の關(?)といふ心なり。十一字は挾める也としるべし。○木路爾云々 木は假名にて紀路也。有也《アリトフ》は、ありといふの「い」をはぶける也。「ちふ」ともよむべし。紀路にさる山ありと、人のいふをかねて聞おかせ給ひしをおほせられし也。○名爾負勢能山 上にいへるがごとく、倭にしてはわがこふる夫《セ》を、名におふ山かとの心也、(125)初五の也もじ、此山といふ字までにかゝりて、名におふ勢の山か。との心也。
〔靈〕この御歌、表は、此山の名.やまとにては、わが戀ひます夫《セ》の名同等の名したる山、紀路にありとかねて聞おかせ給ひしが、此山即かねて聞及びたる山か。と山の名を問ひあきらむるうへによみふせたまへる也。されど、山の名をとひあきらめむばかりの事、こと/”\しく歌とよむべきにあらねば、必別に情ある事しるし。されば思ふに、御旅寢夜を經て、夫君のこひしさ堪がたき御心を述たまひし也。されどこれ、いさゝかも詞にあらはすべからねば、幸の御供にはべり給ひて、夫君をこひ給ふは、御心供奉に薄くきこゆべければ、つゝしみて、かく山の名の事にのみ御詞をつけられたる、まことに古人倒語の用ひざまいとみやびたり。上にいへるがごとく、爾四手者といふ脚結、やまとにては戀ひたまひ、今この御客中にては思ひ絶ておはすさまをおもはせ給ひし、ひとへに山の名の事に、御心ひたふるなるさまにみえむの手段也。心ざしあらむ人は、よく此御詞づくりをおもひしるべき也。この言靈の事、後世人はうくまじき事なれど、紀路には、この山ならでも、名高き山は多かるを、此山をしもとはせたまひしは、必ゆゑなくてはあるべからざる事を思ふべし。たゞ山の上の御歌也。とみゆるやうにあるこそ此和歌のすぐれたる所なれ。しかみゆとて、しかなりと誣ふるは後世心なり。やまとにしては戀ふとおほせられし夫君《セノキミ》は、日並知命なるべし。さればおもふに、此御歌は、便につけて夫君におくらせ給ひし御歌なるべし。日並知命、この御歌をみそなはしたらむに、いかばかり、此皇女の御つゝしみをば、心くるしく(126)おぼしけむ。歌はおほかた、その情いさゝかも詞にあらはれぬは、その心のうちふかく思ひはからるゝぞかし。
幸2于吉野(ノ)宮(ニ)1之時柿本(ノ)朝臣人麻呂(ガ)作歌二首并短歌二首
八隅知之《ヤスミシシ》。吾大王之《ワガオホキミノ》。所聞食《キコシヲス》。國者思毛《クニハシモ》。澤二雖有《サハニアレドモ》。山川之《ヤマカハノ》。清河内跡《キヨキカフチト》。御心乎《ミコヽロヲ》。吉野乃國之《ヨシノノクニノ》。花散相《ハナチラフ》。秋津乃野邊爾《アキツノヌヘニ》。宮柱《ミヤバシラ》。太敷座波《フトシキマセバ》。百磯城乃《モヽシキノ》。大宮人者《オホミヤビトハ》。船並※[氏/一]《フネナメテ》。旦川渡《アサカハワタリ》。舟競《フネキホヒ》。夕川渡《ユフカハワタル》。此川乃《コノカハノ》。絶事奈久《タユルコトナク》。此山乃《コノヤマノ》。彌高良之《イヤタカカラシ》。珠水激《イハバシル》。瀧之宮子波《タギノミヤコハ》。見禮跡不飽可母《ミレドアカヌカモ》
〔言〕八隅知之 まへにいへり。○所聞食 きこしをすとよむべし。食國とて、領じたまふ國をいふ也。古事記上巻に夜之食國《ヨルノヲスグニ》あり。○國者思毛 しもといふ脚結の事、脚結抄にくはし。多かる物の中に、ひとすぢに心のそふさまをさとす詞也。拾遺集に「あまたみしとよのあかりの諸人の君しも物を思はするかな」とよめるに思ふべし。土左日記に「春の海に秋のこの葉しもちるらむやうに云々」とかける、舟の多くこぎいづるさま、たとへむ物も多かれど、秋の木葉しも似たりとの心也。春なるに、秋のものもてたとへたる、この思毛《シモ》の脚結の義をつくされたりといふべし。されば、此脚結この用ひざまの如く、それにはかぎるまじき物なるを、とりたつるよしをいふ詞(127)也。としるべし。こゝに、國者思毛《クニハシモ》とよまれたる思毛《シモ》の義は、 帝と申せども、御不足におぼす物もあるべけれど、ひろき天下の事なれば、國にかぎりてはよき國も多くあるにといふにて、そのよき國多かる中に、吉野國をばすぐれてよき國也とおもはせむがため也。後世心ならば、秋津乃野邊爾思毛《アキツノヌベニシモ》とそこにこそおかめ。こゝに思毛《シモ》をおかれたる詞の力思ふべし。亡父これを譯してニカギツテといへり。吉野をしも、 帝の御心とゞめさせ給ふをむねといふ事、此歌の主意なり。くはしくは、下に情をとくにしるぺし。澤二《サハニ》とは、多くといふ心也。されど、多しといふ詞も、いにしへならび用ひたるを思へば、必別あるべし。多きの古語也と思ふはくはしからず。思ふに、多しは數の多き事也。澤《サハ》は乏しからぬ心にて、數にはあづからずとおぼし。又ふさ〔二字傍点〕といふ詞も此類也。それは、里にフツサリといふ心にて、その物のかさにていふ心とおぼしき也。○山川云々 かはのかは濁りてよむべからず。山と川ふたつをいふ詞なればなり。濁る時は、山にある川といふ義となる也。【濁音の義、すべてかくのごとし。山櫻もさもじ濁れば、山なる櫻といふ心也。さもじ清《ス》みてよめば、山と、さくら、ふたつの事となるがごとし。】清河内跡とは、山と川の清くてめぐれる地なれば、よき地なりとおぼしての心也。河内とは、河の内といふにて、即川のめぐれるを云也。神武天皇の御紀に、東(ニ)有2美地1青山四周。とあるも、山川のめぐれる地はよき地なる所以也。これたゞ地のおかしきを賞するにあらず。山川あたりに近ければ、山より材を生じ、川より魚を生じなど、よろづたよりよき地なれば也。跡《ト》はいつゝのと〔右○〕のうち也。まへにくはしくいへり。これは、 帝の此吉野をしも御心づきにおぼす所以をはかり(128)奉りていふ也。この脚結もはら靈にひゞきたり。○御心乎云々 乎もじかうやうの冠に用ひたるは、つねにたがへるやうなるもある也。これは御心のよきといふを、かく乎《ヲ》もじをおかれたる也。しかるを、乃《ノ》もじをはたらかせて、乎《ヲ》とよまれたる也。又御心をよすといふ心につゞけたるにや。しからば、みし・きかしなどのしもじにて、よしはよせさせ給ふといふほどの心也。いづれにもあるべし。これは冠詞ながら、この一時の冠なり。冠なりと心得て、ひろく用ふまじき也。吉野國吉野は郡の名にて、國にはあらねど、郡郷などを國といふ事、いにしへは常也。前にもいへるが如し。堺をたてゝ人のすむ所はなべて國といひし也。○花散相云々 これを花ちるといふをのべていふ也、と近世の學者みないひ、人も皆それを信じたれど、延約の事、義なくてはあるまじき事予が隨筆にもいへり。大かた、留《ル》は「字韓」なり。良《ラ》は「安緯」。不《フ》は「宇緯」の音なるに、これ同義にあらむやうなし。よく/\かへりみるべし。この良《ラ》は、里阿《リア》をつゞめたるにて、花ちりあふをちらふといへる也。きりあふをきらふといふに同じ例也。やがて、その時のさまを冠らせていふ也。霞立春などの類也。下に、吉野の幸をあまたあげられたるをみるに、これは、三年八月の幸の時にやありけむ。秋津野は即吉野にあり。此野の名のもとは、雄略天皇の御紀にみえたり。野邊の邊《べ》は、方の義也。方角をさしさだむる脚結也。他の方にわかちたる事、もと上の思毛《シモ》は、此秋津の野べにしもといふべき心なる事、上にくはしくいへるがごとくなれば、此|邊《べ》もじ、即|思毛《シモ》の照應にて思毛《シモ》にかへたる心にみるべき也。○宮柱云々 是は、(129)芳野の離宮の事也。太敷座波《フトシキマセバ》は、布斗斯里《フトシリ》といふに同じく。その宮をやすくしろしめすを云也。神典に【古事記上卷】於底津石根宮柱布斗斯理於高天原氷椽多迦斯理而《ソコツイハネニミヤバシラフトシリタカマノハラニヒギタカシリテ》云々。とあるよりいふ詞なり。この詞の事古事記燈にくはしくいへり。その大要をいはゞ、地氣は天上に達し、天氣は地底に達するを形容したるにて、わが御教の要語也。されば後にもかく、 みかどの御うへにのみ申すも、この故なれど、かく後に歌によめるは、歌の上にはしひてこの本義にもよらずして、ただ みかどの宮處しろしめす事にいへり。ある註に、高知・高敷などに同じ語也とあれど、もと、高は、建《タケ》のうつれるいつくしき義也。太《フト》は細きの反にて、心ぶとき義也。【笠紫人は、大小を、ふとしほそしといふ。これ、大小の義なるべし。】この説くはしからずかし。波《ハ》もじは、下に、大宮人のいそしくつかへまつる事をいはむ爲也。○百礒城乃云々 まへにいへり。大宮人とはすべて百官を云。こゝは從駕の人たちをいふ也。 帝のここにませば、こゝにて宮人のいそしきさまを云。もはら みかどの御徳をいふ也。○船並※[氏/一]云々 並・競は、並は舟の多かるをいひ、競はわれさきにつかへむとするさまを云。ともにいそしきさまをいふ也。旦川・夕川わたるは、此離宮へ川をわたり來て、朝夕いそしくつかへまつるをいふ。川のかなたにやどりしたる人々なるべし。又京よりも、代替してつかへにまゐるをいふにや。旦夕をいふは、今もする如く、諸官人、旦あるひは夕など、時をさだめてかはりて勤仕するをいふか。又おほせごとありて、事わきまふるとて、旦まゐり、夕まゐるもあるにもあるべし。これらをひろくふくみてみるべし。渡の字、上のは和太利《ワタリ》とよみ、下のは和多流《ワタル》とよむ(130)べし。上は「伊緯」たるべき事語をなす常なれば也。さればこゝにて句とすべし。○此川乃云々 乃《ノ》はふたつながら、よせの乃《ノ》也。ノ如クといふ心なり。この四句は、川の如く、山のごとくたゆる事なく、いや高くあるべきよしをいふ也。これは此離宮の事也。これ上の句をうけてそこよりうみ出たる四句なり。爰におはせば、こゝに、かくいそしくつかへまつるばかりの御徳にませば、此宮なほ此後も絶る事なく、いや高くあるらしとの心也。彌高とは、前にいへるが如くいつくしき義也。良之《ラシ》はらしきの心にて、未然をはかりていふ也。此|良之《ラシ》の義、下に情をとくにてらして思ふべし。○珠水激云々 古點たまみづのとよめれど、いはばしると眞淵がよめるに從ふべし。石はしる水の、玉なすさまをもてかける字なるべし。瀧之宮子波《タギノミヤコハ》 今、夏箕川の下に、宮の瀧村といふ所あるはこの宮の跡ならむといふ説あり。猶よくたづぬべし。一夜にてもみかどのおはします所は、都をなす故にやがて都ととなふる事上にいへるがごとし。波《ハ》もじおもくみるべし。行宮も所々にありて、いづこも/\おかしからぬにはなけれど、との心なり。猶下に、情をとくに照しておもふべし。○見禮跡不飽可母とは、いかばかりおかしき物もいくたびもみればあくならひなるに、との心をもちていふなり。可母《カモ》は、上にいへるがごとく、すべて事の常にたがひ、理のあたらざるを歎ずる詞也。こゝはいくたびみてもあかざる事大かたの地にたがへるを歎じたるなり。
〔靈〕此歌、表は、帝のこゝにしも御心をよせさせ給ふもことわりや。とこの吉野の絶勝の地なる(131)事を感歎したるによみふせられたる也。されど、この地を賞歎するばかりの事がらを、古人こと/”\しく歌によむものにあらねば、必別に情ある事しるし。さればおもふに、大宮人者云々の句には、 帝の御徳化をたゝへ奉れるやうなれど、諸臣各家をさかりをり、その勞いふばかりなきを思はれたる情しるく、又此川乃云々の句には、此離宮のさかえむ事をほぎ奉れるやうなれど其後もたび/\幸まさむ事を心ぐるしくおもはれたる情みえ、又このよし野かばかりの勝地なるが故に、數度の幸ことわり也。と思へる心のやうなれど、かゝる勝地ならずは、數度の幸もしたまはじとの情みゆ。その外、脚結どもの義にも情はしるし。もと、幸はから國にて巡狩などいふが如く、國のさまをも御覧ぜむためにはしかるべけれど、しからば、國々・所をかへつゝおはしますべきに、此吉野にしも數度幸したまふは、たゞ此勝地を賞したまひての事なれば、ひとへに御みづからの御心をやらせ給はむ爲ばかりなる事しるし。しかるに、そのたび/\費も多くかつ從駕の人々おほせ事なればやむごとなしとはいへど、各家をさかり勞もすくなからず。又幸のたびには、その國の守・國民までも加恩はありといへども、國守・國民にいたるまで、そのたび/\役せらるゝのみならず、心をも勞し費も多きに、 帝は、まのあたり臣民のいそしきをみそなはして、さる事あらむともおぼしめさず。いよ/\幸もたびかさなるべきをわびしくおぼゆるより、大かた、此芳野の勝地なるさへ、うらめしきまでにおぼゆる心をば述られたる也。臣民うらめば、 帝の御徳もそこなはれたまはむがかしこさに、諫をも奉らまほしき心なるべし。(132)かくいふ所謂は、此下、石上麻呂卿の從駕作歌の左註に、紀の朱鳥六年伊勢國の幸を、三輪朝臣高市麻呂冠位を脱し、朝に擎て「農作之前車駕未可以動」と申ししかど、帝したがひたまはず。つひに幸し給ひし事もみゆればなり。その直諫の行はれざりしと、此歌の言外なるとをくらべて、わが御國ぶりのかしこさ、よくく思ひしるべし。この歌の言靈の妙用ありき、なかりきはしらねど、しるしはなくとも、妖氣にはあたるべからず。直と倒の別、かくの如し。くはしく辨ふべし。
から國にては、かゝるすぢの事、顔ををかし用ひられざる時は、死を以ても諫るをば臣の道なりと心えたれども、わが御國ぶり、直言は詮なくて、しかも弊あることを明らめて、倒語の用はじまれる御國ぶりなるが上に、人麻呂ぬしもと高官にもあらず。いよ/\諫奏したてまつるべきにあらざるが故に、かくのごとく詞をつけられたる也。大かた詞のうちあひ、脚結の置ざまなどにもとつ心はみゆる事、よく/\古人の詞づくりをみしりてさとるべき也。猶この奥にも、幸をわびたる歌あまたあるをもて、思ひあはすべきなり。
反 歌
雖見飽奴《ミレドアカヌ》。吉野乃河之《ヨシヌノカハノ》。常滑乃《トコナメノ》。絶事無久《タユルコトナク》。復還見牟《マタカヘリミム》
〔言〕雖見飽奴 まへに同じ。こゝの勝地なるよしを云。下に應ぜむがため也。○常滑乃とは、とこ(133)しへになめらかに流るゝを云也。此集卷十一に隱口乃豐泊瀬道者常滑乃恐道曾《コモリクノトヨハツセヂハトコナメノカシコキミチゾ》。とよめるも川の事なり。と或説にいへり。乃《ノ》もじはよせの乃也。ノ如クと心うべし。○絶事無久 この川の如くに絶ずといふ也。復《マタ》とは、もと再遍の事をいへど、上の絶事無久にひかれて、いくたびもといふ心となる也。これならでも、上にひかれ、下にひかれて、義のうつる事詞の常なり。拾遺集に「松もひきわかなもつまず」とあるは、下にひかれて、松もひかずといふ義なるがごとし。〇此歌、表は、かくの如き勝地なれば、此のちも、 みかど絶ずおはすべければ、我もたえずこの勝地をみむ事、 帝の御蔭なりとふかくよろこびたる心によめり。されど、情は、長歌の下にいふが如く、もと幸のたび/\なるをなげかしくおもふ情より出たる歌なるを、つゝしみて、表はよろこびたるやうによみなされたる也。臣民の心なべて皆われにひとしかるべし。とあはれみたる心もこもりて、いとも/\めでたし。長歌には、帝の御うへをもはらよみ、此反歌はみづからのうへをよまれたるなり。
安見知之《ヤスミシシ》。吾大王《ワガオホギミ》。神長柄《カムナガラ》。神佐備世須登《カムサビセスト》。芳野川《ヨシヌガハ》。多藝津河内爾《タギツカウチニ》。高殿乎《タカドノヲ》。高知座而《タカシリマシテ》。上立《ノボリタチ》。國見乎爲波《クニミヲスレバ》。畳有《タヽナハル》。青垣山《アヲガキヤマノ》。山神乃《ヤマツミノ》。奉御調等《マツルミツギト》。春部者《ハルベハ》。花挿頭持《ハナカザシモチ》。秋立者《アキタテバ》。黄葉頭刺理《モミヂカザセリ》。-云。黄葉加射之《モミヂバカザシ》 遊副川之《ユフカハノ》。神母《カミモ》。大御食爾《オホミケニ》。仕奉等《ツカヘマツルト》。上瀬爾《カミツセニ》。鵜川乎立《ウカハヲタテ》。下瀬爾《シモツセニ》。小網刺渡《サデサシワタシ》。山川母《ヤマカhモ》。依※[氏/一]奉流《ヨリテツカフル》。神乃御代鴨《カミノミヨカモ》
(134)〔言〕安見知之云々 まへに同じ。○神長柄云々 孝徳天皇の御紀に、惟神我子應冶放寄《カムナガラワガミコシラスベシカレヨサシキ》。とあるを舍人皇子自註し給ひて、惟神|者《トハ》謂d隨2神道1亦自有c神道u也。とみゆ。もと、奈賀良《ナガラ》といふ詞、後世にては心えあやまれり。里言に、ソレナリニ・ソレグチニなどいふほどの心也。されば、惟の字をあてられたる也。神道にしたがひ給へば、やがて神にましませば也。神佐備世須登《カムサビセスト》は、 帝はやがて神にましませば、人のはかりがたき御わざせさせ給ふとの心なり。登《ト》はとての心也。神佐備とは、上の宇良さびの下にくはしくいへるがごとく、セサセラルヽといふほどの心なり。これ此吉野に幸まします事を云也。○芳野川云々 かうち前にいへり。○高殿乎云々 たかどのは、つねには樓をいへども、たゞ高くつくれる殿をいふ也。乎もじ、もはら神さびをいへり。たゞつねます大宮にのみいまして、こゝの高殿はしろしめすべくもおぼえぬにといふ也。高知座而。上にいへるが如く、高知は神典の詞を本とす。いつくしくしろしめす心也。而《テ》もじは、例の下の事に直につゞく義にあらずとしるべし。○上立云々 國見はまへの 舒明天皇の御製にくはしくいへり。から人のすなる巡狩の類としるべし。○疊有云々 これより下、小網刺渡までは、此高殿にましますにつけての妙用を擧たる也。たゝなはるは重疊したるかたちを云。奈波流《ナハル》はうべなふまかなふなどいふ奈布《ナフ》の布《フ》の、波《ハ》にかよひ、それに流《ル》もじを添たる也。すべて、かうやうの詞をそへたる詞は、うつたへにその一事をするとはなくて、おのづからそのわざなるかたちをいふ也。青垣山とは、青山の垣の如くたちたるを云。【或説に、そばだてるをいふとあれど、垣をば聳つ事にもちひたるをみず。】古事記上卷に吾者|伊2(135)都岐奉《イツキマツノ》于倭|之《ノ》青垣《アヲガキ》東《ヒムガシノ》山上(ニ)1此(レハ)者坐2御諸《ミモロノ》山(ノ)上(ニ)1神|也《ナリ》とみゆ。○山神乃云々 山つみは、山神なり。宣長釋して山津|持《モチ》の義といへり。いかゞあらむ。予おもふに津見《ツミ》は神典に【古事記上卷】意富加牟豆美《オホカムヅミノ》命の御名あるを思ふに、大神集《オホカムヅマリ》の義にて、麻里《マリ》をつゝむれば美《ミ》なり。大祓祝詞に高天原爾神留座。をば、古訓「かみとゞまりまします」とよめるがことわりなさに、眞淵これを「かむづまりまします」とよまれたる、そのつまりこれなり。つめともかよはせたる例あり。されば、つまり・つみともに集る義にて、山|津見《ツミ》は山によれる神といふ神の集まります大神なれば、大山津見神とは申す也。大綿津見も、これに同じ。○奉は、古訓たつるとあれど、いかゞあらむ。まつるとよむべし。たてまつる義也。御調は貢物を云。等《ト》といふは、これまことの貢物といふにはあらねど、國々の奉る貢物のごとくといふほどの心也。よせのと也。此下の大御食爾仕奉等も、これに同じ。山神。河伯ともに、神わざなれば、あらはにはみえねど、それにひとしき心にていふ也としるべし。○春部者 部は前にいへるが如く、方をたつる詞にて、他の季にわかちたる也。花挿頭持とは、山上に花のさきたるをば、山つみの花をかざし持たるに見なしていふ也。持は、添たるのみ也といふ説あれど、しからず。これ、山神の貢と奉り給ふさまにいふなれど、添たるばかりにあらずさゝげもちて奉るを云。挿頭、もと、頭に枝を折てさすをいへど、たゞ枝を頭にさゝげたるをも概してかざすといふ事つね也。かの説は、頭に小枝をさすに着したる説也。○秋立者とは、上に春の事をいひたる故に、立者《タテバ》とは、こゝはよまれたる也。黄葉頭刺理 これも、花に同じく心(136)うべし。皆 帝をなくさめ奉らむとての神の御心なるになしていへる也。勢理《セリ》と「江緯」にうつしたるは、例の其未然をおもはせたる也。一云の黄葉加射之を思ふに、こゝは山神の御わざの終にて、下は河伯の御わざにうつる所なれば、かくいはむもしかるべけれど、「江緯」にうつせる詮ふかくもみえず。かつこゝに勢理《セリ》といはゞ、下の刺渡も、さしわたすとよむべけれど、これより下の語勢しかよむべしともおぼえねば、こゝも此一本の方にしたがふべくや。○遊副川之云々今、宮の瀧の末に、ゆ川といふ野あり。此集卷八に「結八河内《ユフハカウチ》」とよめる、これならむかといふ人あり。上の青垣山は名所にあらねば、こゝもその轍にて、上と聯句にみるべしといふ人もあれど、夕川の義ともおぼえず。されど、此下のわざ、鵜川も夜するわざ也。小網さすわざはひるなれば、夕川にはあらざる事しるし。母《モ》は、上の山神によせていふ也。○大御食爾云々 けは、食物を云。大御とたゝふるは、大かた、 帝の御うへの事也。仕奉等 上にいへるが如く、これまた神わざなれば等《ト》とよめり。○上瀬爾云々 四句上津瀬・下津瀬ことによしあるにはあらざるべけれど、神典【古事記上卷】禊祓之件の詞を用ひられて、川のうち悉く大御食のれうになし給ふさまをいはむ爲也。中津瀬はおのづから上下の間にこもるべし。鵜川乎立、鵜つかひどもをたゝするを云。小網は和名抄に、※[〓+麗]。佐天《サテ》。網如2箕(ノ)形(ノ)1狹(クシ)v後(ヲ)廣(クスル)v前(ヲ)名也。とあるこれ也。たゞあみともよむべけれど、此集卷十九に平瀬爾波左泥刺渡《ヒラセニハサデサシワタシ》云々。ともよめれば左泥《サデ》とよむべし。鵜川も、小網もみな人のするわざなるを、かく神の御しわざのごとくいひなせるは、大かた神は御身おはしまさ(137)ねば、人の言わざをかり給ふ事神典につまびらか也。くはしくは、こゝにいひつくしがたし。古事記燈にみるべし。そも/\、人麻呂ぬしをば歌のひじりとたゝへ、今の世となりては神といつかせたまふ事、倒語の至妙なるはいふも更なり。此ぬしの歌どもをみるに、神典にくはしかりしとみゆる事多し。かみつ世の人たちは、このぬしにあひおとらぬもすくなからぬを、ひとり此ねしをしもたふとばるゝは、神道のいたり深くて、その人ざま、たぐひなかりければなるべしとぞおぼゆる。この小網刺渡、前に論らへるが如く黄葉頭刺理とよまばこゝも刺わたすとよむべき事なれど、此下、なほ山神河伯の事をうけて、やがて山川母依※[氏/一]奉流とよめるは、刺わたすとはよむべからぬ語勢也。これ語勢の常也。くはしくはこゝに書とりがたし。志あらむ人には、口授すべし。○山川母云々 山神・河伯もといふ也。川《カハ》のかもじ、清《スミ》てよむべし。山川ふたつなれば也。此母もじは、山神も、河伯もといふにはあらず。臣民のいそしくつかへまつるに、【此事は上の長歌によまれたる事也。】臣民のみならず、山神・河伯もといふ心也。母《モ》もじの用ひざま、これにてみしるぺし。依※[氏/一]奉流とは、臣民とひとつによりてつかふるといふ也。○神乃御代鴨 みかどを、やがて神として神の御代とはいふ也。上にもすでに神長柄とよめり。鴨はかへす/”\いへるが如く、常にも理にもあたらぬ事を歎ずるにて、臣民のみならず、山神・河伯までもつかへ給ふを歎じたる也。
〔靈〕此歌、表は、 みかど此吉野におはしませば、臣民はいふもさら也。山神・河伯までもよりてつかへまつるさま、大かた神にます此 帝の御徳、凡慮のはかり知がたき事かなと歎じたる也。(138)上の長歌には、臣民の勞をわすれて、此離宮につかへまつる事をいひ、此長歌には神までもいそしくつかへまつり給ふ事をよまれたる也。されど、 みかどの御徳をほめまつるを本情ならば、かゝる詞はつけらるべきにあらず。大かた人をほむる事、詞にあらはなるは諂におつるがゆゑに古人かたく直言せぬ事也。しかるを後世のやうに、さしつけてこそよまれね。【神になして、よまれたれば也。】かくよまれたるは、必本情あるが故ならずや。されば、おもふに、これ又上の歌どもに同じく、たびたびの幸に臣民勞しさま/”\の弊あるを思ひて諫め奉らまほしさを、つゝしみてつけられたる詞ども也。かく興足り、食あくばかりなる勝地を、いとなか/\にうるさくおぼえて、かくはよまれし事言外にあふれたり。
反 歌
山川毛《ヤマカハモ》。因而奉流《ヨリテツカフル》。神長柄《カミナガラ》。多藝津河内爾《タギツカウチニ》。船出爲加母《フナデセスカモ》
〔言〕山川毛 長歌なると同じ。因而奉流も、亦同じ。此二句は、神長柄の句へつゞけたる也。臣民はさら也。山神・河伯までもよりてつかへたまふばかりの神にませばといふなり。○神長柄は、猶長歌なるに同じ。こゝは、かの里言の「ながら」にまぎらはしき所也。混ずべからず。○多藝津河内爾云々 これ又上に同じ。離宮ある地を云也。○船出爲加母 爲をせすとよめる、然るべし。此御船出、即長歌にいはゆる御神さびにて、そこにも世|須《ス》とあれば、するとはよむべからず。た(139)とひ長歌にさはなくとも、みかどの御うへなれば世須とよむべし。船出とは、芳野河を御舟にて渡らせたまへば也。鴨は、神ながら舟出し給ふ御心の、はかりがたさをなげきたるなり。
〔靈〕此歌、表は、臣民のみならず、山神河伯までもつかへまつるばかりの神にますを、人のするわざのやうに、此吉野に舟出したまふ御心、凡情にてははかりがたきを歎きたるによみふせられし也。しかれども、たゞ、この帝の御心のくすしくあやしくますをたゝへ奉るを本情ならば、なほ長歌に論らへるが如き弊あれば、これ又、心はたび/”\の幸をなげきたる也。以上長・短四首、今とけるがごとく、その靈ひと筋也。詞のうへ、みなおのづから矩あるを、よく/\みしりて、かへす/\表に目を奪はれずしてみるべし。いと遠く深く、倒語をもとめたる歌は、いよ/\表にめをうばゝれやすし。上手の歌はことに心を用ふべき也。
右日本紀(ニ)曰三年己丑(ノ)正月天皇幸2吉野(ノ)宮(ニ)1八月幸2吉野(ノ)宮(ニ)1四年庚寅(ノ)二月幸(シ)2吉野(ノ)宮(ニ)1五月幸2吉野(ノ)宮(ニ)1五年辛卯(ノ)正月幸2吉野(ノ)宮(ニ)1四月幸2吉野(ノ)宮(ニ)1者未v詳(ニ)2知(ラ)何(レノ)月從(テ)v駕(ニ)作歌(ナルコトヲ)1
幸2于伊勢(ノ)國(ニ)1時留(レル)v京(ニ)柿本(ノ)朝臣人麻呂(ガ)作歌
持統天皇の御紀六年三月、伊勢の幸ありて、志摩をも過給ひし事みゆ。このをり阿胡行宮にもおはししなるべし。左註あやまれり。
嗚呼兒乃涌爾《アゴノウラニ》。船乘爲良武《フナノリスラム》。※[女+感]嬬等之《ヲトメラガ》。珠裳乃須十二《タマモノスソニ》。四寶三都良武香《シホミツラムカ》
(140)〔言〕嗚呼兒乃浦といふ所伊勢になし。志摩國|英虞《アコノ》郡に行宮あればそこなるべし。此集卷十五に、安胡乃宇良爾布奈能里須良牟《アゴノウラニフナノリスラム》。乎等女良我《ヲトメラガ》。安可毛能須素爾《アカモノスソニ》。之保美都良武賀《シホミツラムカ》。といふ歌あるは、この重複なるべし。その左に、安美能宇良《アミノウラ》ともあるによりて、こゝをもあみのうらとよむは誤也。良武《ラム》は、京よりおもひやられし也。此良武《ラム》は、中の良武《ラム》とて、詞の中におく也。下のをとめらにつづけて心うべし。○※[女+感]嬬等之とは、從駕の女房をさせる也。をとめは、少女・未通女などもかきてわかき女の稱にて、をとこに對せる名也。くはしくは、予が土佐日記燈のはじめにいへり。大かたをとめ等《ラ》とよめども、一人のをとめをさす事古人倒語のつね也。これ一人にせまらざるやうに、わざと等《ラ》とはいふ也。これは、數人とも聞ゆれど、猶心にさすをとめありけるなるべし。數人とはみがたき歌もあるはこの故なり。○珠裳乃須十二 珠のごとくめでたき裳といふ也。かの卷十五には、安可母《アカモ》とあるによりて、これをもあかもとよむは非なり。裳をしもいふはしほみつらむかといはむがため也 珠裳としもいふは、潮にぬるらむくちをしさを思はせられたるなり。〇四寶三都良武香 かは疑なり。潮にぬるらむかといふべきをかくいふ事古語のみやび也。これ潮かみつらむの心なれど、こゝに香《カ》をおけば、潮か、又は何かみつらむとの心となり、下におけば潮みつらむか、又はさもなきかとの心となる也。後世は、良武香《ラムカ》とはよまず。後世人は、古風なる脚結也など心えたれど、義かくたがふを以て、香良牟《カラム》・良牟香《ラムカ》、歌によりて、ともによむべき事なるをしるべし。
(141)〔靈〕この歌、表は、從駕し奉りて阿胡の浦に舟乘すらむ女房たちの珠裳のすそに潮みち來てぬらすらむか。とその女房たちの宮中にてならはぬ事なれば、めづらしとやおもふらむ。又はわびしとやおもふらむ。と思ひやりたる也。されど、思ひやるばかりの情は、たゞ心に思ひやるにてやみぬべく、こと更に歌によむべき事にあらぬをおもふに、從駕のをとめのわびしき目みるをいたはりたる歌にて、その本を推せば、これ又、幸をすべなく思はるゝ心よりおこれる也。この情いさゝかもあらはならば、必 みかどの御心にそむくべきをはゞかりて、めづらしからむともわびしからむともいはず。たゞ潮みつらんかとのみいへる、うちみは、その興をわれも羨みたるやうに詞をつけられたる、上手の詞づくりよく思ふべし。これは、從駕のをとめのうちにさす人ありて、贈られたるにこそ。この三者がうち、第一・第三は、女房のうへなり。第二はをのこたちのうへ也。從駕の男女のうち、親屬か、または親友なる三人に贈られたる歌なるべし。かくいづかたにも片つかず詞をつくる、倒語のいたり也かし。これ等を詞づくりのかゝみとはすべきなり。
釧着《クジロツク》。手節乃崎二《タブシノサキニ》。今毛可母《イマモカモ》。大宮人之《オホミヤビトノ》。玉藻苅良武《タマモカルラム》
〔言〕釧着は、手節の冠なり。釧とは、神典【古事記上卷】に佐久久斯侶伊須受能《サククジロイススノ》宮。とみえて、五十鈴の冠とせられたるをおもふに、釧は手につくる物にて、鈴にひとしければなるべし。玉もてもつくる物なればにや、玉釧ともよみたり。今本、釧を劍に誤れり。劍は手節につくるものにはあらざ(142)るをや。手節乃崎は、志摩國|答志《タフシ》郡なるべし。○今毛可母 ある註に、ふたつの毛《モ》は助字にて、今やといふ心也といふは例の麁也。古今集に、今もかもさきにほふらむたちばなの小島のさきの山ぶきの花。とよめるに同じ。上の毛《モ》は、今とさしつけずして、今頃などゆるゝ?かにいはむため也。下の可母《カモ》は、例の疑也。これ、今やの心にはあらぬがうへに、や〔傍点〕とか〔傍点〕の用ひやうたがひめある事脚結抄にくはし。可《カ》は今にあらずば、少しさきか、少し後かをしらむとていふ心也。や〔傍点〕は、いつしかあらむともしられぬにいふ脚結にて、こゝにかなはず。此手節乃崎は、今にあらずは、さきか後かには、必過給ふべき所なれば、もとより也《ヤ》とはよむまじき事がらなるを思ふべし。下の母《モ》も、たゞ助字とはいひあはむべからず。【助字。やすめ字、發語などいふは、國學者の遯辭なる事、予が隨筆にくはしくいへり。】常用ふる疑の可母《カモ》なるをや。○大宮人之云々 從駕のをのこたちをさす也。これも、をとめらに同じく、ひろくはいへど、このうちに必さす人ありてよめるなるべし。之もじ心をとゞむべし。玉藻かるべき身がらの者の刈らば、之《ノ》といふ詮はあるべからず。かるまじき人々のかるを、思はせむがための脚結なる也。之《ノ》もじは、つねに、人の心もとめず、瓦石の如く用ふる脚結なれど、古人はかく心をとゞめて用ひたり。玉藻かるらむは、前の麻續王の贈答によれば、玉藻は食料に刈る也。されどこゝは從駕なれば、さるわびしきわざすべきやうはなけれど、これはたゞ海人どもがするわざを戯にまねびてすらむとおもひやれる心とみるべし。をのことてもならはぬわざなれば、おかしとや思ふらむ。又はわびしとやおもふらむ。との心也。
(143)〔靈〕此歌、表は、從駕のをのこたちの、手節の崎にて、玉藻をかかるらむ。海人こそつねにからめ。大宮人のかるらむは思ひかけぬわざなれば、中々おかしくや思ふらむ。わびしくやあるらむとおもひやりたるに、よみふせられし也。されど、さばかりの事、こと/”\しく歌とよむべきにあらねば、本情は、前の歌にひとしき事明らか也。詞のつけざまよりはじめて、前の歌にてらして同じ情なることをしるべし。これ又、いづれへもよらぬ詞づくりのみやび、よく/\めをとゞむべし。
潮左爲二《シホサヰニ》。五十良兒乃島邊《イラコノシマベ》。※[手偏+旁]船荷《コグフネニ》。妹乘良六鹿《イモノルラムカ》。荒島囘乎《アラキシマワヲ》
〔言〕潮差爲は、潮さきの義かといふ説あれど、きのうつれるならば、爲《ヰ》もじ、以《イ》たるべし。此説非なり。爲《ヰ》は和藝《ワギ》の合音にて、潮さわぎ也。潮のみちくる時、波のさわぐを云といふ説したがふべくや。此集卷三に鹽左爲能浪乎恐美《シホサヰノナミヲカシコミ》云々。巻十一に牛窓之《ウシマドノ》。浪乃鹽左猪《ナミノシホサヰ》云々。卷十五に於伎都志保佐爲多可久多知伎奴《オキツシホサヰタカクタチキヌ》。などよめる、いづれも潮さわぎの義あたれり。まへにいふ潮さきは仙覺が説也。伎《キ》を爲《ヰ》にかよはせりとの心なるべけれどうけがたし。契沖は、鹽のさしあふ所をいふといへり。是は、大祓詞に、鹽の八百會といへるなどをばおもはれけるなるべし。左《サ》・阿《ア》・爲《ヰ》・比《ヒ》ともに同韻なるが故なれど、しかにもあれ、此例どもにかなへりともおぼえず。今思ふに、此集卷十四に、安利伎奴乃《アリギヌノ》。佐惠佐惠之豆美《サヱサヱシヅミ》。伊敝能伊母父《イヘノイモニ》。毛乃伊波受伎爾※[氏/一]《モノイハズキニテ》、於毛比具(144)流之母《オモヒクルシモ》。神典【古事記上卷】に、口大之尾翼鱸佐和佐和邇控依騰而《クチビロノヲハタスヾキサワサワニヒキヨセアゲテ》云々。ともあり。此集卷二に小竹之葉者《サヽノハハ》。三山毛清爾《ミヤマモサヤニ》、亂友《サワケドモ》。吾者妹思《ワレハイモオモフ》。別來禮婆《ワカレキヌレバ》。ともある、この佐惠《サヱ》・佐和《サワ》・佐夜《サヤ》ともに、佐爲《サヰ》に同じく、さや/\と鳴る音をいふ詞也。いづれも、さや/\と鳴る音をもてさわぐ事を思はする事古言の常なり。神典に【古事記上卷】豐葦原之千秋長五百秋之水穂國者|伊多久佐夜藝※[氏/一]有祁理《イタクサヤギテアリケリ》。とみえ神武天皇の御紀に、夫葦原(ノ)中(ツ)國(ハ)猶|聞喧擾之響《サヤゲリナリ》焉。【聞喧擾之響焉此云2左揶霓利奈離《サヤケリナリ》1】など、皆あしき神のさわぐを音もてさとされたる證なり。されば「佐和藝《サワギ》の」の説もさる事なれど、もと、潮のみちくる時、さわ/\と鳴る音を潮佐爲《シホサヰ》とはいふなるべし。〇五十良兒乃島邊 これは、三河なるいらこのあたりなる島をいふなるべし。邊はその島の方をといふ也。○妹乘良六鹿 此妹は、從駕の女房たちのうちをさす也。鹿《カ》は疑のか〔傍点〕なり、此|鹿《カ》もじは、上の潮佐爲爾《シホサヰニ》をもちていふにて、潮佐爲《シホサヰ》の時しも、妹のるらむかといふ心也。良六鹿《ラムカ》の心得まへに論らへるに同じ。○荒島囘乎 この島囘、即いらこの島わをさす也。囘《ワ》はそのめぐりをいふ也。浦囘《ウラワ》・里囘《サトワ》などに同じ。この一句は添たるものなり。一二三四の句意は、もし潮左爲《シホサヰ》の時にしも乘るらむかとの心にて、もはら潮左爲《シホサヰ》のうへにかゝれり。そこもとあらき島囘なるをとの心にて、もとよりあらき島囘なるを、潮左爲の時にしもわたるらむかとの心なり。乎は里言にジヤニ・ジヤノニといふほどの心也。土左日記に、まして女は舟ぞこにひたひをつきあてゝねをのみぞなく。とかゝれたる、おもひあはさる。女の乘らるべき島囘ならぬを。との心にて乎とはいふなり。
〔靈〕この歌、表は、五十良兒の島はかしこき島囘なるに、潮左爲《シホサヰ》の時にしもか、妹のるらむ。をのこすらかしこかるべきを、まして女のいかにかしこかるらむ。とふかく女のかしこかるべきをいたはりたる也。されど、これ又、情はひとへに幸をなげく心よりよまれたるなる事、詞づくり、又脚結に明らか也。詞の表には、たゞ妹のるらむかとのみいひて、くるしからむとも、わびしからむともいはれざりしは、幸にはゞかりて也。詞のつけざま、公私をそなへたる妙處、よくよく味はふべし。以上三首、同じ情なる事、上にいへるがごとし。
當麻眞人麻呂妻《タギマノマヒトマロガメノ》作歌
この當麻眞人麻呂は、同じ行幸の從駕にて、京にとまれる妻のよめる也。此|隱《ナバリ》の山は伊賀にて、大和より伊勢にくだるには、必伊賀を經れば也。猶この次下の歌も、從駕のたびの歌なるをも思ふべし。
吾勢枯波《ワガセコハ》。何所行良武《イヅコユクラム》。己津物《ヲキツモノ》。隱乃山乎《ナバリノヤマヲ》。今日香越等六《ケフカコユラム》
〔言〕吾勢枯波は、おのが夫をさせる也。波《ハ》もじ前にもいへるが如く、後世人はかくざまの所にはえおかずなれり。夫在京のほどは、同居するが常なりしか。今旅にありて、あふべきよしもなき歎よりいふ也。大かたには、たゞ、これはかゝり、かれはしかりなど物事の分別のためにおけるも、つ(146)ねは、大かたにおもへる物の、ぬけ出たるさまをなげく詞なるが故に、おのづから他に異なる事をいふ義はある也。今釋するは、その義のくはしき也。古人、かく用ひたる波《ハ》もじ多し○何所行良武とは、夫が旅中をおもひやりて、いかなる處をかゆくらむ。と夫がゆくらむ處のしらまほしさにいふなり。○巳津物は假字にて、澳津藻乃也 隠の冠なり。澳なる藻はつねに隱れてみえざればいふなり。澳は、鹽干にだに深ければ也。頼政卿の女が、潮干にみえぬ澳の石の。とよめるはこれらより思ひよれるなるべし。已は起の略字なるべし。○隱乃山乎 隱はなばりとよむべし。いにしへ、隱るゝを、なばるといふなり。伊賀國に名張郡あり。そこの山なるべし。乎もじは、今日隱の山を越たらむにもあれ、京まではなほ行程も近からねば、かつてねがはしからざる名張の山をといふ心也。乎もじの義まへにときおけるが如し。○今日香越等六 この今日といふ事、麁にみまじき也。かくいふ故は、今日だにいまだなばりの山をも越ずは、夫が歸期いと待遠ならむ。とその程をまちくらさむ事、いかにくるしからむとの心をもたせてよめるなれば也。されば、此一首の眼なりとしるべし。香《カ》は疑なり。大かた想像のうへなれど、大抵おもひはかりありて、香とはよめる也。上に何所行良武といひて、又下に隱乃山乎今日香越等六とよめる事、いづれにもあれ、ひとつにてありぬべき事のやうなれど、しからず。上はひろくいづこをかゆくらむとよめるにて、さて日をかぞへなどしてみれば、大抵今日などは名張の山をこえもすらむか。とさまざまに思ひわづらふ情、かくをさなげなる詞づくりにて、かへりて、おもひやりはふかき也。其さ(147)ま/”\に思ふ心を、已津物の冠「にかへたる也」。下に靈をとくにてらして、此詞づくりの妙をさとるべし。此妻いかなりし女ぞや。此歌の詞のつけざま至れりといふべし。これは、夫の客中へおくれる歌なるべし。
〔靈〕此歌、表は、たゞいづこあたりをかゆくらむ。もし今日などは、名張の山をこゆらむか。と夫の在處をおもひやりたるばかりによみふせたる也。これは、行さまの路の事にはあらざるべし。しかみらるまじきにはあらねど、かへさの路の事とみむ方、待かねたる情いとゝ切なるべし。しかるに夫の在處をおもひやるばかりの事を、古人はこと/”\しく歌によむべき事にあらねば、思ふに、夫の從駕日を經て歸期のまち遠さに、いかで一日もはやくかへらむ事を促したる情をよめる也。しかれども、たゞあは/\しく、夫の客中を思ひやりたるばかりのやうに、詞をつけたるは、私の旅にあらねば、帝の幸に日をかさね給ふをうらみ奉るに落べければ、憚りてかくはよめる也。前にも論らへるが如く、何所行良武《イヅコユクラム》・今日香越等六《ケフカコユヲム》と等六をふたつかさねて、をさげなるにも、今日といへる餘情にも、心のうちにさま/”\思ふ事どもはあふれて、かへす/\この詞のつけざま、凡ならざるをよく/\思ふべし。
石上《イソノカミ》大臣從(テ)v駕(ニ)作歌
これは麻呂卿也。この時、いまだ大臣にはあらねど、後よりかくはかける也。前の鎌足公の書ざ(148)まにもおもふべし。かゝる集例中に多し。
吾妹子乎《ワギモコヲ》。去來見乃山乎《イザミノヤマヲ》。高三香裳《タカミカモ》。日本能不所見《ヤマトノミエヌ》。國遠見可聞《クニトホミカモ》
〔言〕吾麻子乎云々 いざみむといふ心にいひかけたる也。もと此歌、妹があたりだにみまほしき心より、いできたるなれば、妹をいざみむと思ふ心即本意なれど、冠辭になして公をそこなはぬ古人の手段、これにかぎらず多し。去來見乃山 いづかたにかしられず。伊勢・伊賀・志摩などのうちにある山なるべし。乎《ヲ》・三《ミ》とうちあはせてよむ事、上にくはしくいへり。去來見乃山が高さにかも。といふ心也。くはしくいはゞ、倭國が、此山を高がり思ふ故かもといふ心なり。香裳は疑なり。次の句の、日本能不所見《ヤマトノミエヌ》にうちあひたる也。いざみの山を高み、倭のみえぬかも。といふ心なるを、こゝに香裳《力毛》をおくべからぬ義なるが故に、上に香裳《カモ》を置たる也。私に引あげておけるにはあらず、香裳《カモ》は、もししからずは、いかなる故ぞと云心なり。〇日本能不所見【日本とかけるは、倭國の事也。此事くはしく前にいへり。】みゆべき大和國のみえねが不審なる心によめる、妙なり。先註書に、これを大和なる妹があたりをみむとすれどゝいふ心也。と註したる、もと此歌妹の戀しさよりの詞づくりなれど、直に殊ともいはずして、やまとのみえぬとのみ詞をつけられたる、此歌の妙處なるを、やがてやまとの妹など註するは、此詞づくりの活處を殺すわざなりかし。古註には、かゝる釋多きは内外の混ずる也。内外幽顯はかたく混ずべからざる車、わが神典の要訣、わが御國ぶりのかしこさ也。ただ表を釋すとならば表のみたるべし。此詞づくりふかく心を用ひられ、ひろくおもひをわ(149)たされて、意もなく、味もなき所に詞をつけられたるを、たゞ一言に殺さむは、いとも/\くちをしく、言代主神の御にくみもいとかしこき事にあらずや。内外を混ずれば、すべて歌のよみやうも方たゝず。古歌もつひに、そのたましひを得る事あるべからず。○國遠見可母 いざみの山の高さにみえぬか。もししからずば、國の遠さにみえぬか。とその所謂を決せむとする心也。此|可聞《カモ》の義、くはしくいはゞ、もし國の遠さにてあらずは何故ぞ。いづれにもあれ。ゆゑなくてはみえざらむやうなしとの心也。上に、去來見乃山を高みかもといひ、又國遠みかもとよませ給へるは、ひとつにてはあたらざらむ事を思ひて也。これさらに曲節にあらず。情にひかれてのわざなり。山高さにかといへるも、國の遠さにかといへるも、もとよりそこよりみゆべき大和にあらぬを知ながら、所以を設出たる事、前にいへるが如く、もとみゆべき物のみえぬやうなる、まことに上手の手投なり。よく/\、古人の倒語の用ひやう、めをとゞむぺし。かく、をさなきは倒語の妙所、かつ餘情も、こゝより尋ねしらるかし。〔靈〕此歌、表は、こゝよりみゆべき倭のみえぬは、山高さにか。國遠さにか。このみえぬ所以のしらまほしきを、もはらとよみふせ給へる也。されど、かばかりの心をば、古人歌によむ事なく、かつこのみえざる所以を擧られたる二事ともに、いとをさなきは、必別に情あるしるし也。さればおもふに、從駕に日を經て、都におきたる妹の戀しさ堪がたきを、家の妹に告やられたる歌なる事明らか也。されど、此情いさゝかもあらはなれば、供奉に心專一なるべきにそむき、從駕に(150)日をふるをうらむるになりぬべきをはゞかりて、こゝよりやまとのみえぬをいぶかりたるに、詞をつけられたる也。詞のつけざま、かへす/”\いとあやしきまでめでたくこそ。
右日本紀(ニ)曰朱鳥六年壬辰(ノ)春三月丙寅(ノ)朔戊辰以2淨廣肆廣瀬(ノ)王等(ヲ)1爲2留守官(ト)1於(テ)v是(ニ)中納言三輪(ノ)朝臣高市麻呂脱2其(ノ)冠位(ヲ)1擎上2於朝(ニ)1重諫(テ)曰農作|之《ノ》前車駕未v可2以動(カス)1辛未天皇不v從v諫遂(ニ)幸2伊勢(ニ)1五月乙丑(ノ)朔庚午御2阿胡行宮《アゴノカリミヤニ》1
これは、 持統天皇六年也。朱鳥六年とあるは誤也。此五月云々より以下は、紀をみあやまりたるにて、これは以前の事也。古註書にくはし。
輕皇子《カルノミコ》宿(リタマフ)2于|安騎野《アキヌニ》1時(ニ)柿(ノ)本(ノ)朝臣人麻呂作歌
これは、天武天皇の皇太子草壁皇子損之《クサカベノミコノミコトノ》御子也。【日並知《ヒナメシノ》命の御事也。】この輕皇子は、文武天皇わかくまし/\ける時の御名なり。安騎野《アキヌ》は、式に、宇陀《ウタノ》郡|阿紀《アキノ》神社あり。この野なるべし。此野に、父尊日並知尊の御獵したまひし事、此前にも、又卷二にもみゆ。その頃は、いまだ王にてまし/\ければ、こゝに皇子とかけるは、後よりたふとみてかけるなるべし。
八隅知之《ヤスミシシ》。吾大王《ワガオホギミ》。高照日之皇子《タカテラスヒノミコ》。神長柄《カムナガラ》。神佐備世須登《カムサヒセスト》。太敷爲《フトシカス》。京乎置而《ミヤコヲオキテ》。隱口乃《コモリクノ》。泊瀬山者《ハツセノヤマハ》。眞木立《マキタツ》。荒山路乎《アラヤマミチヲ》。石根《イハガネノ》。楚樹押靡《シモトオシナベ》。坂鳥乃《サカトリノ》。朝越座而《アサコエマシテ》。玉(151)蜻《カキロヒノ》。夕去來者《ユフサリクレハ》。三雪落《ミユキフル》。阿騎乃大野爾《アキノオホヌニ》。旗須爲寸《ハタススキ》。四熊乎押靡《シノヲオシナベ》。草枕《クサマクラ》。多日夜取世須《タビヤドリセス》。古昔《イニシヘ》念而《オモヒテ・オボシテ》
〔言〕八隅知之云々 まへにいへり。これは、此輕皇子をさし奉れるなり。皇子をもかく申す事、つねなり。八隅知之よりはじめて、もと神典の御教のうへにいふ詞にて、天下をしろしめすうへばかりの事にあらず。此故に、皇子にも申す也。此義くはしくは、こゝにいひつくしがたし。古事記燈にみるべし。○高照云々 古事記に多加比加流比能美古。とあれば、こゝも、たかひかるとよむべしといふ説あれど、此集中高光とかかれたる所はさもあるべし。すでに、日神の御名を天照《アマテラス》大御神とも申せば、たかてらすともよむべきなり。○神長柄云々 上にくはしくいへるに同じ。此阿騎野にいでますを、神さびせすとはいふ也。世須登もまへに同じ。○太敷爲云々 ふとしくも、前にくはしくいへり。爲《ス》は例のセラルヽの義也。御心ふとくしろしめさるゝ都といふ也。置而とは、都をたち出させ給ふ事をば、御あとにおかせ給ひてとはいふなり。都を出させ給ふとはいはで、京乎置而といふは、古言のみやび也。前に近江の遷都の事をば、倭乎置而といはれたるは、今とは事重けれど、いづれも立出たまふをいふは同じきなり。○隱口乃云々 泊瀬の冠詞也。こもり國の心にて、冠らせたる也。と眞淵のいへる、可從。隱口の義也。といふ説もあれど、口も山口などこそいへ。こもり口といはむ事あるべくもおぼえず。こもり國、かへす/\(152)しかるべし。冠辭考にくはしく論らへるをみるべし。者《ハ》もじは、こと山とひとしからぬよしを歎じたる也。荒山道なれば也。○眞木立云々 眞木とは、よき木也。よき木は、深山ならではなきものなれば、眞木立荒山とはいふ也。荒は、荒・和といふ和の反にて、人にうとき山をばあら山とはいふ也。【荒・和の事古事記燈神典にみるべし】眞木のたつとつゞけずして、此集卷九に芦檜木※[竹/矢]《アシビキノ》。荒山中爾《アラヤマナカニ》。送置而《オクリオキテ》。還良布見者《カヘラフミレバ》。情苦裳《コヽログルシモ》。とよめるも、なほ深山をいふ也。乎《ヲ》は、里言にジヤニ・ジヤノニなどいふ心にて、深山なれば、人もつねかよはずして路いとわろく、皇子などおはしますべき路にはあらぬを、との心をさとさむがため也。されば、此乎もじは、下の朝越座而にうちあはせたるにて、石根楚樹押靡二句は、はさめる也。としるべし。○石根云々 今の本に禁とあるは、楚の誤なるべし。楚は字書に創祖(ノ)切|粗《ソ》。上聲。叢木。一名※[并+刃]※[并+立刀]。又翹楚翹(ハ)高(ク)起(ル)也。言《イフ心ハ》楚木中之獨(リ)高(ク)起(ル)者也。以(テ)況(フ)2人|之《ノ》出v類(ヲ)拔tv1v萃(ヲ)也とみえて、小さく細き木をいふ也。古點、禁樹をふせきとよめれど、心えがたし。楚樹、しもとゝよむべし。冠辭にしもとゆふかづらき山といふしもとこれ也。押靡は、おしなびかしの心なり。石がねにおひたるわかく細き木どもを押なびかせて、越給ふさま也。ある註に、從駕の人のおしなびかせて越るさまなりといへる、げに皇子の御みづからおしなびかせ給ふにはあるべからず、御さきにたてる人どものするさまなるべけれど、此歌大かたこの皇子の御神さびに、此行がたき山道を越ます皇子の御うへをしも歎じたる歌なれば、これ猶、皇子の御みづからおしなべさせ給ふになしてみむ事、この歌の本意なるべし。たとひ、從駕の人の押し(153)なびかすにもあれ。皇子の御爲にするわざにて、從駕の人の私にするにあらねばしかは註すまじき事なり。大かた、歌の本意にそむき、そむかぬけぢめは、よく心を用ひて註せずば、その歌を殺すべき也かし。この二句、ひとへに皇子の御神さびをたゝへまつれる也。〇坂鳥乃云々 朝越の冠辭なり。くはしく冠辭考にみゆ。谷の木ぐれにやどれる鳥どもの、朝には群て坂を飛越るを、供奉の人の坂路をむれこゆるにたとへたりといへり。しかるに、谷などにやどれる鳥の、朝に坂こゆるを、坂鳥といふべくもおぼえず。さればおもふに、坂のわたりの樹どもにやどりたる鳥をいふ名なるべし。朝には、嶺をむれ越てあさりにいづるさまをいふなるべし。而《テ》もじの義は、朝と夕をつながむため也。されど、直につなぐは、而《テ》の義にあらぬ事、まへに論らへるが如し。朝といふは、終日の艱苦をおもはせむがために、一日のはじめをいひ、夕といふは、終夜の辛苦をおもはせむが爲に、一夜のはじめを云也。かく間をへだてゝつなぐ事、而《テ》もじの専用也としるべし。○珠蜻云々 古點玉きはるとよめれど、夕とつゞかねば非なり。此集卷十五に玉蜻夕去來者《カギロヒノユフサリクレバ》。とあり。されば、限(蜻?)は蜻(限?)の誤にて、かぎろひのなるべし。かぎろひは、かげのきらめく火をいふ事、古事記 履中天皇の御卷に、難波の宮のやくるを加藝漏肥能《カギロヒノ》。毛由流伊弊牟良《モユルイヘムラ》云々。此集卷二に 香切火之燎流荒野爾《カギロヒノモユルアラヌニ》云々。などよめり。春とつゞくるも、かぎろひの如く春日の空にきらめくをたとへたる也。その餘日・ひとめ・ほのかなどつゞくる、皆これに同じ。石とつづくるは、石火に冠らする也。夕とつゞくるは、夕日のかげはことにきらめけば也。蜻※[虫+廷]をかげ(154)ろふといふは、かれがとぶさまを、かぎろ火にたとへたる名なり。玉蜻とかけるは、かれが目の玉のごとくなれば也とぞ。又、博物志に、土に理みおけば、珠となるよしありと、冠辭考にいへり。陽炎をかげろふといふも、皆かぎろ火のたとへよりいふ名也。夕去來者は、夕かたになればといふ也、去といふ事まへに論らへり。これは下の多日夜取世須につゞけるにて、三雪落以下四句は、はさみたる也。三雪落につゞけてみるべからず。〇三雪落 三はほめていふ也。これ此野にやどりたまふ寒さ佗しさをおもはせたる也。阿騎野、まへにいへり。大野としもよまれたるも、ひろき野は、ことに風などもさむきさまを思はせられたる也。上には山路の艱難をいひ、こゝには此野のわびしき事をいはれたる、皆玉しきの都のうちにくらべておもはせむがためにて、荒山道、楚樹押靡、三雪落、四能乎押靡などは、よまれたるもの也。この爾《ニ》もじ、上の京乎置而にむかへて、意味をよく味はふべし。からしなどはいはで、その辛かるべき事どもをいひならべられたる事、後世人の詞づくりにたがへる所を、よく/\みしるべき也。○旗須爲寸云々 はたとは、秋の野中にて、その穂のことにめにたつ物なればいふなり。皮《ハタ》とかけるは、膚の義にて、穂のはだにこもりてやう/\出る故にや、と眞淵はいへり。神功皇后の御妃に幡荻穂出吾也《ハタズヽキホニイヅルワレナリ》。とあるをみれば、穂に出ての名なる事しるし。皮はたゞ假字なるなり。いにしへは、はたずすきとのみいへるを、此集卷八にたゞ一首|波奈須爲寸《ハナズスキ》とあるは、此京になりては、花ずすきとのみいふ事、もと奈良人のいひそめたるよりの事かとも思へど、たゞ此一首の外にはなければ、奈は、必(155)大の誤なるべし。【後世は、波奈とならではいはぬになづみて、後世人さかしらに、奈につくれるなるべし。】四能乎押靡は、すゝきのしなひをおしなびかせの心也。と古説なり。げに、奈比《ナヒ》は能《ノ》とつゞまれば、それはさる事ながら、しなひをおしなびかするといふ事、すゝきのしなひたらむをのみおしなびかせたらむやうにて、めざましきがうへに、乎もじかやうの所に用ふる例ならねば、この説うけがたし。されば思ふに、この能《ノ》もじ、筆のてにて、ぬもじを誤りたるにて、小竹《シヌ》なるべし。しからば旗薄、小竹などをおしなびけて、と二種なるべし。かくみれば、乎《ヲ》もじの義相當する也。これひとへに、一夜だにもやどり給ふべき所にあらぬを思はせむがための乎もじ也。京にては、金樓玉殿に錦繍を褥として、おほとのごもるべきにむかへておもふべし。上の押靡は、道なきをしひておはすよしをいひ、こゝの押靡はおほとのごもるべからざるに、しひてみねますよしをさとされたる也。○草枕云々 草枕は、たびの冠なり。旅には、枕もなけれど、草を枕にむすびてぬるが故也。必しかもすまじけれど、よろづ客中の不自由なるをいふ也。多日夜取は旅宿也。○世須は、これもセサセラルルといふ也。○古昔念而 古點は、おもひてとあり。しかにてもありぬべけれど、おぼしてと眞淵がよめる上の世須のうちあひにしかるべし。これは、父尊の此野に御獵したまひし事を、おぼしてといふ也。父母をしたひ給ふ御心より、かゝる野に旅やどりし給ふよ。といふ心なり。
〔靈〕この歌、表は、輕皇子都にませば、めでたき宮中に起臥給ふ御身にましますを、道もなき泊瀬山をこえ、さむき阿騎野にやどりし給ふは、ひとへに父尊のむかしをしたひ給ふあまりなるべし。(156)凡庸ならば、さるめでたき身にて、心からかゝるわびしきめはすまじきを、此皇子もと神にましてせさせ給ふ御神さびは、さても/\凡慮の外なる事や、とあやしめる心によみふせられし也。されど、さばかりの事は、たゞ心中におもひてもやみぬべきを、かく歌とよまれしは、必別に情あるが故なる事明らか也。されば思ふに、此皇子の、父尊をしたひ給ふ御心、あまりなぐさめがたさに、むかし父尊の御かりし給ひし此阿騎野に、山路の艱難をも、この野のさむきをもいとひ給はずして、かくおはしましゝ御孝心を感じ奉りたる歌也。されどこれ、いさゝかもあらはなれば、諂諛におつべきをはゞかりて、神慮ははかりがたきうへになしはてたる詞づくり、めでたしなどもよのつね也かし。大かた、此歌をみむ人、たゞ此皇子のたふとさをたゝへ奉れる歌也とみすぐしたる事、古註どもにことなる沙汰なきにしるし。古人もと、言擧せぬ國の御てぶりを明らめたりしかば、いはでありぬべき事はいふも更也。いはでかなはぬ事すら、妖氣あるべき事は、倒語するを、いかでかよしなくて、たゞへごとをもいはむ。もしこれ、直言ならば、かへりて毛を吹べき也。後世人はさるけぢめも辨へず、そしらむこそあらめ。ほめむは弊なしと心えたるいとも/\心くるしき事也。されば、此歌ひとへに、表は、神の御うへ凡慮はかりがたきによみふせられたるは、倒語にて、此皇子、父尊のいにしへをしのび給ふ餘りに、宮中の榮華を忘れたまひ、この野に旅やどりし給ふその御心を深く感じたてまつられたる歌なる事、すべて詞の用ひざまにしるきをや。このけぢめをしらむとならば、かりに比情のまゝをあらはによみて、此歌にと(157)りならべて、倒語のやむことなき事をばあきらむべし。
短 歌
こゝも、反歌とあるべき例也。しかれども、目録には、反歌をも短歌とかゝれたるがおほし。されば、これは、反歌なり
阿騎乃野爾《アキノヌニ》。宿旅人《ヤドルタビビト》。打靡《ウチナビキ》。寐毛宿良目八方《イモヌラメヤモ》。古部念爾《イニシヘオモフニ》
〔言〕この野の字、普通の本になし。必脱せる也。こゝにはたゞ、阿騎の野爾とのみあれど、長歌によめるに同じく、雪ふりてさむき阿騎野にとみるべし。宿旅人とは、皇子をもこめ奉りて、從駕の人々をひろくさしていふ也。大かたに、旅人といへる、これ古言のみやび也。皇子を靈としたる詞づくり也。○打靡云々 うちなびきは、草などのかたへになびきふしたるさまを、人のふしたるにたとへていふ也。これおのづから、うちとけて寢たるさまを、形容する詞となれり。こゝも、うちとけたる、いはねられめやとの心なり。良目八方の目の字、今の本には自とありて、いもねらじやもとよめれど、ねらじとはいふべからず。一本目とあるに從ふべし。いとはねむとてふすをいふ詞にや。朝い、いさとし、いぎたなしなどいひ、又、いの安き、安からぬ。などいふも、皆寢入たも事とはみえず。うまいは熟睡の義なれば、寢入りたる事のやうなれど、なほいといふは、寢心地の事とおぼしき也。ぬるとは寢入る事をいふ。ぬるがうちに、おくとはなげき、ぬ(158)とはしのはむ。などいひ、又このぬをかよはして、ねての朝け。このねぬる。などもよめり。されば、寢毛宿良目八方とは、ふし心地もよくはねるらめやの義也。上の毛《モ》はぬるを主とたてゝ、ふしごゝちもよくといふ心也。良目《ラメ》は良牟《ラム》のかよへるにて、八《ヤ》とうくるには、必江緯にかよはす事常なり。八方《ヤモ》は、後世の也波《ヤハ》に同じ。前にいへるが如く、後世これを半反語といふは、わが御國言の眞理を辨へざる説也。この八《ヤ》なほ疑の也《ヤ》にて、人に決定をゆづる詞也。○古部念爾 この爾《ニ》もじは、里言にノデといふ心なり。いにしへを思ふにて、うまくはねられむやとの心也。さればこれ、五四とつゞくべきを、例の標實をはかりて倒置せるなり。
〔靈〕此歌、表は、此阿騎野にやどる人の、いにしへを思ふに堪ずして、いもやすくはねられむや、とそのねられ、ねられじのけぢめをおもひやりがほに、詞をつけられたる也。されど、たゞねられ・ねられじの別ばかりの事は、古人歌によむものにあらねば、これ又、情はこの皇子の御心をいとをしみ奉れる歌なり。もと、父尊をしのびかねて、こゝにおはしけるなれど、こゝにてはなか/\懷古の情も立まさり給はむ。と思はれけるなるべし。されど、此詞にあらはなれば、諂に落むをはゞかりたる事、長歌に同じ。この旅人、大かたにいへれど、まことは輕皇子をさし奉れる也。古註みな、此旅人を從駕の人也といへれど、皇子をおきたてまつりて、從駕の人のうへをいとをしまむ事あるべくもなし。かへす/”\詞のうへにめをうばゝるまじき也。此皇子さばかりの辛苦をも忘れて、父尊のむかしをしのばせ給ふ至孝のほどを感じたてまつれる事を長歌によ(159)み、此歌にはこよひこゝにやどらせ給ふ御心のうち、いかにおはしますらむ。とおもひやれる心をよまれたる也。詞のつけざま返々思ふべし。
眞車苅《マクサカル》。荒野二者雖有《アラヌニハアレド》。黄葉《モミヂバノ》。過去君之《スギニシキミガ》。形見跡曾來師《カタミトゾコシ》
〔言〕眞草、まへにいへり。なにとはなくよき草をいふ也。眞木立荒山とよめるに同じく、人ぢかき野は草もつねにかれば、荒野ならではよき草もおひねば也。かゝる荒野は、たゞ草かるをのこなどこそは來れ。なべてのものゝくべき野にはあらねど、との心也。荒野とは、即阿騎野を云也。○黄葉云々 今の本、黄の字なし。葉の上に必、黄の字脱せりと、代匠記にいへる、從ふべし。黄葉の過にしとよめる歌、集中に多ければ也。古訓ことわりなし。過去者とは、日並知(ノ)皇子尊をさし奉れるなり。○形見跡曾來師。跡は、いはゆるいつゝの跡《ト》也。跡思比而《トオモヒテ》の心也。曾もじの心は此荒野もと、故尊の御形見とみつべきものにあらぬを、ひとすぢに御かたみと思ふはかなさを思はせて、曾《ゾ》とはいふ也。古人|曾《ゾ》もじを用ふるに、必かくしたがふまじき筋にしたがはるゝ歎なり。さらでは、曾《ゾ》といふ詮なきをおもふべし。世に曾《ゾ》を治定の詞といふ事の、麁なるをさとるべし。師《シ》は去倫の師なり。この師は、そのすぢにしたがひたる事、すでに今とは筋たがへる歎也。たゞ過去の詞とばかり心うるは、くはしからぬ也。されば、これは、此阿騎野かゝるあら野なれども故尊の御かたみとのみ、一すぢにおもひて來しか。今この野にやどりては、御形見とみるべくも(160)あらぬ歎也。
〔靈〕此歌、表は、この阿騎野、故尊の御獵ましゝ所なれば、御かたみとて來しに、此荒野の御形見ともなきあぢきなさをなげきたるによみふせられし也。されど、思ひしかひもなしとおもふばかりの事は、歌によまずともありぬべければ、本これ、別に情ある事明らか也。されば思ふに、なか/\こゝに來て、いとゞ昔の戀しければ、皇子の御心、いかにとおもひやり奉れる也。されどこれ、又上と同じはゞかりに、かくは詞をつけられたる也。わが歎をのみいふがほにて、皇子の御うへはよそにしたるやうに詞をつけられたるに、なか/\皇子をいとをしみ奉れる、言外に情あふれたるをや。
東《ヒンガシノ》。野炎《ヌニカギロヒノ》。立所見而《タツミエテ》。反見爲者《カヘリミスレバ》。月西渡《ツキカタブキヌ》
〔言〕東野云々 今本の訓ことわりなし。これは、此阿騎野の東方をいふなり。かく東をしもいはれたるは、下の、月西渡にむかへて思ふに、東方の雲しらみたるを思はせむがため也。○炎 まへにいへり。これは、東野の民家などに、はやく起てたく火のほのかにみゆるを云。ある註に、此炎こゝは明そむる光をいふといへるは、後世心なり。明る光をかぎろひといはむ事、古人の詞づくりにあらず。予つねにいふが如く、後世心をもて、古言はとくべからずといふ所以を思ふべし。東といふにこそ、しらめるをおもはせたれ。これはたゞたく火なるをや。○所見而 後世はたゞ(161)みゆるにいへど、すべてみゆまじき物のみゆるをいふにあらでは、詮なき詞也。これ、そのみゆるにつけて、情ある事にいふ也。たゞみゆるといふ義のみにあらず。いまだ夜はあけじとおもへるに、明るに近きさまのみゆるを云也。このみゆるにつけての情は、下にいふべし。而《テ》もじの義此下に多事を含蓄する事、例のごとし。○反見爲者 夜いまだ明じと思ふに、東方しらみて、民家火をたくがみゆるより、月はいかにと西方をかへりみたる心也。なにのよしもなきやうなる詞つくりなれど、上古詞をつくるには、ふかく力を入れたる事これらの詞にみるべし。後人の及ばざる境これらにしるしかし。○月西渡 この西渡のもじは、心えてかゝれたる也。東方しらみて民家火をたくのみならず、月かたぶきたれば、疑なく、夜ははや明ぬべしとしられたる心なり。
〔靈〕この歌、表は、いまだ夜明むには程あるべくおもへりしに、東方を見れば、空しらみ、野ちかき家にとく起てたく火のみゆるに、西方をかへりみすれば、月さへかたぶきたるは、うたがひなく、夜は明むとするよ、とおもひの外によのはやくあくるを驚きたる心に、詞をつけられたるなり。東方ばかりにては信じがたきを、西方をかへりみて、夜の明むとするを信じたる心なるべし。されど、おもはずに、よのはやく明るを驚くばかりの事を、古人歌とよむ物にあらねば、必別に情あある事明らか也。されば思ふに、もとなぐさめむとて、此野に來ましたるなれど、かへりて懷古の御心しのぴがたさに、こよひ寢やし給ふらむ。ねられたまはずして夜をやあかし給ふらむとて、皇子の御うへをふかくいとをしみたてまつられける歌なり。これ又上と同じはゞかり(162)に、かくは詞をつけられたる也。この長歌・短歌ともに、すべて詞づくり凡ならぬが中に、此歌ことに詞のいたりをきはめられたり。歌はかやうによまゝほしき事なり。たゞ夜のあくるさまをのみいひて、皇子はみねましつらむか、又今までもねられ給はぬか、とさま/\御心のうちをおもひやり奉られたる情、句々・言々の置ざまにてあらはにいひたるよりも、深く思はるゝぞかし。かく、事もなげによみふせられたる詞づくりに、かばかりの情こもりて、今みるにだに涙もさしぐまるゝは、ひとへに倒語の妙用なり。倒語のくしびなる事、おもひしるべし。上古の人の詞づくり、いづれとはなきが中に、此ぬしをばひじりとさへいふだに、よまれたる歌どもなほ優劣あり。そのすぐれたるが中にも、此歌などは、此集中の王ともいふべしかし。
日雙斯《ヒナメシノ》。皇子命乃《ミコノミコトノ》。馬副而《ウマナベテ》。御獵立師斯《ミカリタヽシシ》。時者來《トキハキ》向《ムカフ・ムケリ》
〔言〕日雙斯は、日並知とかけるに同じ。輕《カルノ》皇子の父尊なり。まへにいへるがごとく、此皇子、この野に御獵ましゝ事ありけるを云也、命《ミコト》とは、もと御言《ミコト》の義にて、天神、御言もちて皇孫の命に葦原中國をよさし給ひしより、神の御心のまに/\御言用ひさせ給へば、その御言やがて神の御言なれば、命《ミコト》とは申す也。大かた、神は御身おはしまさねば御言もなし。されば人の口をかり給ひて、妙用をふるまひたまふ也。しかれども、からるべき人の言ならでは、かりたまはぬものなる事、古事記燈にくはしくいへり。紀に、宰の字をみこともちといふにあてられたるも、此(163)義によりてなるべし。神代卷には、尊・命とかきわけたまひて、舍人皇子、至尊(ヲ)曰v尊(ト)自餘(ヲ)曰v命(ト)と自註したまひしは、文字にかゝづらひ給へるにて、美古登《≡コト》といふ訓にはあづからぬ事也。古事記には、悉く命の字を用ひられたるに思ふべし。伊邪邦岐《イザナギ》・伊邪那美《イザナミ》の二ばしら、神世七代には、神と唱へ、游能碁呂島之件《オノコロジマノクダリ》より、命《ミコト》と申し、三貴子黄泉之《≡バシラノタフトキミコヨミノ》件より、又大神とたゝへたるにても、この心はうべき也。【古事記燈にくはしくいへり】○馬副而 從者と馬を並べさせたまひてなり。副の字は物にものゝそひたるかたちなれば、この心をえてかゝれたる也。もはら御在世の時のありさまを思はせむがため也。○御獵立師斯云々 みかりに立出ましゝ時とは、上の東野云々 の歌より連續しておもふに、この時とは、朝獵にたち出ましゝ時の來むかふといふなるべし。ほと/\夜あけむとする事を、前の歌にはよみ、此歌はやゝ朝となりてよめるなるべし。古註にはみかりましし時節の來向ふ也といへり。いづれにもあるべけれど、なほ思ふに大かた獵は四時ともにするわざなりとはいへども、冬を主とす。かの故尊は、いつ御獵し給ひしをしらねど、もし冬ならば、此時こと/”\しく、時者來向といはむははえなかるべく、又さなくとも京を出ます時より、故尊の御かりましゝ時節はあきらかなるべければ、こゝには思ひかけぬやうによまれたるも詮なければ、朝獵の時とせむ方あはれふかゝるべし。とおぼゆる也。立師斯は、たゝせられし也。者《ハ》もじ、此歌の眼なり。朝がりに立出ましゝ時は今來むかへども、外に來向はざる物ある歎なり。この言外は、すなはち靈なり。下に見るべし。多かる物の中に、目にたつ歎前にいふが如し。その(164)言外の情をいはむ爲めに、かへりて、そこをいはで、來向ふ時の方を詞とせられたる也。前にもいひしが如く、すべて、事、兩端をいはでは、その理盡ざる物なれども、兩端をいへば、詞いと稚し。大かた、詞はきかむ人の思慮・分別をまつをむねとつくるべきに、われより理を詞につくす、これを稚しとも、又いやしともいふ也。されば、片方を言外とし、その片方を詞として、言外なる方をおもはする事、脚結の専用なるなり。これにかぎらぬ事ながら、此|者《ハ》もじなどことに此理のしるき用ひざまなれば、くりかへしこれをいふ也。よくく心うべし。
〔靈〕この歌、表はさきに日並知命、この野に朝がりに出たちましゝその時は今來むかふよ。とその時の來むかふを驚きたるに、よみふせられし也。されど時の來むかふをおどろくばかりの事を、古人は歌によむものにあらず。されば思ふに、情は、時は來むかへども、故尊はかへり來たまはぬをなげきたる也。これみづからのうへもあれど、むねとは皇子のふたゝび父尊にあひ奉り給はむ期もなきをいかにかいかにおぼすらむ。と深く御心のほどをいとをしみ奉れる也。しかるを、皇子の御うへをもいはず、たゞ時の來むかふをおどろけるばかりに詞をつけられたる、これ又、上と同じはゞかりによりて也。たゞ、者《ハ》もじひとつにて、うはべは時のうへばかりに、詞をつけられたる至妙、いはゞなか/\なるべし。倒語の御教に、志あらむ人は、よく/\これらの歌に心をとゞめて、詞づくりの妙處をおもひしるべきなり。
萬葉集燈卷之三 終
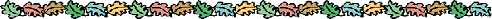



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)