そして縄文は縄文、弥生は弥生と相違点を強調するのでなく、縄文から弥生へと精神は連面と継承されて、各アイテムの共通性や進化系としてとらえる考え方も大切と思います。
縄文文化のさまざまなアイテムが弥生九州へ
弥生文化の成立期に、東北系の縄文土器が九州各地でみられるようになることが、考古学者の方々によって指摘されています。考古学者の瀬川拓郎氏は、青森県の亀ヶ岡系土器が、福岡・大分・熊本・鹿児島・奄美大島などで出土することから、北日本人の九州地方への進出について述べています。
亀ヶ岡系土器は、精選した粘土で作られた土器です。国立博物館にも展示されていました。青森県十和田市滝沢原川出土の壺は、美しく均整のとれたフォルム、施された模様は流麗で、磨(す)り消し縄文や漆塗りの技巧など、実に見事な壺でした。亀ヶ岡式土器の西日本への流入からは、遠賀川式土器(板付Ⅱ式土器)との共通性も、縄文研究者が指摘するところです。
さらに縄文を代表するアイテム「ヒスイ」も、はるばる新潟県から、縄文晩期の北部九州の遠賀川河口に運ばれます。ヒスイや鹿角製の装飾品とともに女性の人骨が出土しています。縄文スタイルのヒスイ大珠(たいしゅ)を胸に、鹿角製の垂飾りを身に着けた、きわめて縄文的な女性です。これもまた縄文展に展示がありました。自然に考えれば、ヒスイの流入とともに、ヒスイという石の最高難度の加工技術者、玉振り・玉鎮めという祭祀を司る人々も、東日本から九州地方に移動したと考えられます。寒冷化という気候条件の中で、その活路を新天地の北部九州へ見出した人々もいたでしょうし、技術力に期待されて招かれた人々なども想定されます。
……このように縄文時代までさかのぼって考察することで、これまで大陸渡来文化との共通性に目が向けがちであった文物も、異なった見解が出てくるのでした。今後も縄文から弥生へと連続している文物が判明し、増加してくるものとみられます。
日本人がものごとを多面的に見られるのは
こうして考えてみると、大陸から離れた1万年の縄文時代に、日本人の文化・精神の源が形成されたものと考えられます。四季の自然の恩恵・自然の脅威という、相反する自然と共生してきた先祖でした。「和魂(にぎたま)」と「荒魂(あらたま)」という、一柱の神さまに両面を見出す考え方に重なります。そのような自然との付き合い方は、日本人がものごとや人物を多面的に見る、という懐(ふところ)の広さ、寛容さを育んだのではないでしょうか。
縄文から弥生へ多くのアイテム・精神は継承されました。三種の神器のヒスイ=八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)もその一つです。
筑紫の国では、祖霊を祭る山上崇拝など、神武天皇に係わる伝承が顕著です。出雲方面では、比婆(ひば)山にイザナミノミコトをお祭りします。大国主命(おおくにぬしのみこと)は、立山の大汝(おおなんじ)山に、安曇氏の穂高見命(ほだかみのみこと)は、穂高岳に祭られます。それも縄文人の精神を継承したものとすれば、自然に納得できます。
寒冷化という自然状況の中で、それまで高い文化をもっていた北日本・中部高地から、西日本へ移住した人々が想定されます。いち早く水田農耕を取り入れ、新たに移住してきた人々を受容した北部九州の筑紫の国の人々は、新たな大陸文化と縄文文化を融合して、より豊かな国作りへの道を歩みだしました。物づくり集団である部(べ)を統合し、国家統一へのイニシアティブをとったのではないでしょうか。
ものづくりの心と女性の尊重を育む「平和」
1万年の縄文時代は、大陸から切り離されて独立した「平和な時代」でした。ものづくりに打ち込めて、女性が尊重されたのも平和な時代だからこそと思われます。その長い平和こそが、縄文文化を育み、日本人の源泉を育てたのでしょう。
縄文時代が、決してユートピアであるとは思いませんが、現在の私たちが見失い薄らいでしまった精神の拠りどころがあるのではないでしょうか? それを顧みることによって、明日への行く先や生きる力が見えてくるところが確かにあるようです。…………
勉強会に参加された皆さんの感想や質問は、共感することばかりで、教えていただけることが多かったのです。
「土偶も土器も何千年前の人が作ったとはおもえないほど、オシャレで洗練された現代的な感性を感じます」
「みみずく土偶などとにかく可愛い!」
「縄文展では、あまりにもスバラシイものを一気に見たので、これからは一つ一つじっくり丁寧に見ていきたい」
「野性的と思っていた縄文人が、芸術性や感性が高い」
「出産を真剣に祈った土偶を見ていたら、その気持ちが胸に迫ってきてジンとしてしまいました」
「縄文も弥生も知っているつもりでしたが、よくわからなくなりました」
「弥生グッズのミニチュアは、三角縁神獣鏡でなく内行花文鏡にしてほしいですよね」
「土偶は乳首が目立つのに乳房がめだたないのは?」
「世界最高の土器」
「日本人の源流があるようです」
「渦巻き模様など、土器の模様について深く考えたい」
「諏訪から伊那地方を訪ねて、古く深いものを感じました」
「鮭神社は福岡だけでなく、出雲にも全く同じものがありました」
「抜群のプロポーションを誇る縄文の女神についてもっと知りたい」
…………
驚きや感動がありました!お土産のお菓子も合わせて、お礼申し上げます。「一つ一つのものを丁寧にゆっくり見て考えたい」「ここから日本の歴史は始まる」まさにそのような思いです。 今日は終戦記念日です。1万年の平和な時代を享受して、ものづくり打ち込んだ縄文人に思いを馳せるにつけても、平和への思いを強くします。
-
-
-
-
-
-
-
|
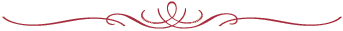
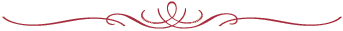
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)