
| ふとまに考 |

(最新見直し2013.08.21日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、ふとまに歌の№1から39を確認する。「ウィキペディアのホツマツタヱ」、「ほつまつたゑ 解読ガイド」その他を参照する。 |
| 【フトマニ図】 |
| フトマニは、和歌体の31文字の和歌128首を本文とする。全宇宙の構成を表した元明けに準拠して、アメツチ(天地)の動向を察知する哲理歌となっている。前書きの「フトマニを陳(の)ぶ」から始まり、ア(1~16)、イ(17~32)、フ(33~48)、へ(49~64)、モ(65~80)、ヲ(81~96)、ス(97~112)、シ(113~128)の順で8篇128首が編纂されている。「ア、イ、フ、へ、モ、ヲ、ス、シ」の順に編纂されている。その意味は分からない。「ももふそやうた ゑりたまふ」(百二十八歌 選り給ふ)とあるので、参照原本には更に数多くの和歌が記されていたことになる。内容を見るのに凡そ出雲-三輪王朝の御世の編纂であることが窺え、治政論であると同時に帝王学的な御教示文ともなっている。但し、出雲-三輪王朝御世の大和言葉で書かれており、その解読は難しい。「読文百ぺん、意自ずから通ず」で味わうしかない。 8代アマカミのアマテルカミがアマカミを引退してから最晩年に至った頃、記したと前文にある。今日にいう占いの原初に相当するものである。ホツマツタヱ、ミカサフミの解読において、フトマニの寄与するところは大きい。 トヨケ神(伊勢外宮祭神)が初めてイサナギとイサナミの両神(フタカミ)に天上モトモトアケ(元元明)のサゴクシロ宮に坐す四十九(ヨソコ)神の座席図を五十一文字で表わし授けた。後にアマテル神(伊勢内宮祭神)は、このフトマニ図で吉凶を占おうと考え自ら編集長となり、八百万(ヤオヨロズ)の神に命じ万葉の情を歌に作らせて添削し、その中から百二十八歌を選んで大占(フトマニ)の紀(フミ)を著して占いの元とした。
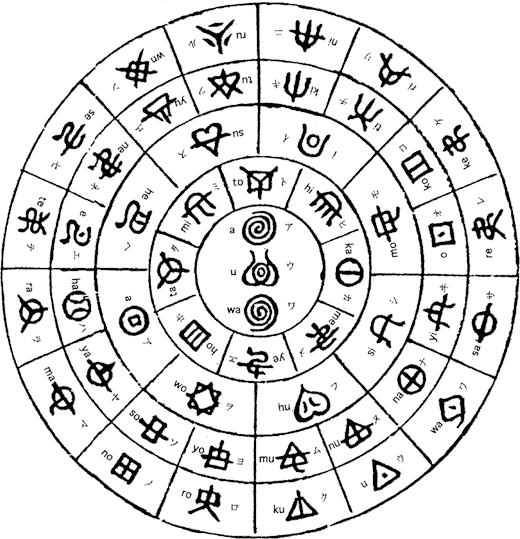 |
| フトマニ図 http://www.hotsuma.gr.jp/futomani.html 八元神・天並神・三十二神を加えると四十八(ヨソヤ)神で日本語の音韻の数である。日本語の一音一音は神とされ、ここに言霊の観念の発生を見る。各々の神は季節や方位を始め、自然界のあらゆる事象を管掌することから、フトマニ図は占いに用いられるようになった。タカミムスビ家はこの祭祀をタカマの祭りとして、自家で体系化し祭行してきたが、タマギネはイサナギ・イサナミ(両神)と天照大御神に伝授する事によって、これを国家祭祀にまで高めた。タカマの祭りをひと言で言えば、天地創造から万物の生成、人類の誕生、国家創建、そして縄文のあらゆる文化の発展経過を凝縮した思想体系である。 |
| ふとまに解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1、アヤマ(あやま) | ||||||||||
|
||||||||||
| 2、アハラ(あはら) | |||||||||
|
|||||||||
| 3、アキニ(あきに) | |||||||
|
|||||||
| 4、アチリ(あちり) | ||||||||||
|
||||||||||
| 5、アヌウ(あぬう) | ||||||||||
|
||||||||||
| 6、アムク | |||||||
|
|||||||
| 7、アエテ(あえて) | ||||||
|
||||||
| 8、アネセ(あねせ) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 9、アコケ(あこけ ) | |||||||||
|
|||||||||
| 10、アオレ(あおれ) | ||||||||
|
||||||||
| 11、アヨロ(あよろ) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 12、アソノ(あその) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 13、アユン(あゆん) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 14、アツル(あつる) | |||||||||
|
|||||||||
| 16、アナワ(あなわ) | ||||||
|
||||||
| 17、イヤマ(いやま) | |||||||
|
|||||||
| 18、イハラ(いはら) | ||||||||
|
||||||||
| 19、イキニ(いきに ) | ||||||||||
|
||||||||||
| 20、イチリ(いちり) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 21、イヌウ (いぬう) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 22、イムク(いむく) | ||||||
|
||||||
| 23、イエテ(いえて) | |||||||||
|
|||||||||
| 24、イネセ (いねせ) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 25、イコケ(いこけ) | |||||||||
|
|||||||||
| 26、イオレ(いおれ) | ||||||||
|
||||||||
| 27、イヨロ(いよろ ) | |||||||||
|
|||||||||
| 28、イソノ(いその) | ||||||
|
||||||
| 29、イユン(いゆん) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 30、イツル(いつる) | ||||||||||
|
||||||||||
| 31、イヰサ (いゐさ) | ||||||||||
|
||||||||||
| 32、イナワ(いなわ) | ||||||
|
||||||
| 33、フヤマ( ふやま) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 34、フハラ (ふはら) | ||||||||
|
||||||||
| 35、フキニ( ふきに) | ||||||||||
|
||||||||||
| 36、フチリ(ふちり) | ||||||
|
||||||
| 37、フヌウ(ふぬう) | ||||||
|
||||||
| 38、フムク (ふむく) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 39、フエテ(ふえて) | |||||||||
|
|||||||||
| 40、フネセ (ふねせ) | ||||||||||
|
||||||||||
| 41、フコケ( ふこけ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 42、フオレ(ふおれ) | ||||||||
|
||||||||
| 43、フヨロ(ふよろ) | ||||||||||
|
||||||||||
| 44、フソノ(ふその) | |||||||
|
|||||||
| 45、フユン (ふゆん) | ||||||||
|
||||||||
| 46、フツル(ふつる) | ||||||||
|
||||||||
| 47、フヰサ(ふゐさ) | ||||||||
|
||||||||
| 48、フナワ (ふなわ) | ||||||
|
||||||
| 49、ヘヤマ (へやま) | ||||||||||
|
||||||||||
| 50、ヘハラ (へはら) | |||||||||||
|
|||||||||||
| 51、ヘキニ(へきに) | |||||||||
|
|||||||||
| 52、ヘチリ(へちり) | ||||||
|
||||||
| 53、ヘヌウ (へぬう) | ||||||
|
||||||
| 54、ヘムク ( へむく) | ||||||||||
|
||||||||||
| 55、ヘエテ(へえて) | ||||||
|
||||||
| 56、ヘネセ (へねせ ) | |||||||
|
|||||||
| 57、ヘコケ (へこけ) | ||||||||
|
||||||||
| 58、ヘオレ(へおれ) | |||||||
|
|||||||
| 59、ヘヨロ (へよろ) | ||||||||
|
||||||||
| 60、ヘソノ (へその) | ||||||
|
||||||
| 61、ヘユン(へゆん) | ||||||
|
||||||
| 62、ヘツル(へつる) | ||||||||||
|
||||||||||
| 63、ヘヰサ (へゐさ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 64、ヘナワ (へなわ) | ||||||||||
|
||||||||||
| 65、モヤマ ( もやま) | |||||||||
|
|||||||||
| 66、モハラ (もはら) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 67、モキニ ( もきに) | ||||||
|
||||||
| 68、モチリ(もちり) | |||||||||
|
|||||||||
| 69、モヌウ (もぬう) | ||||||
|
||||||
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)