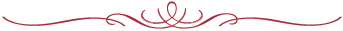
| 第一次田中内閣組閣 |
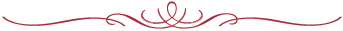
更新日/2020(平成31→5.1栄和元/栄和2).1.6日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
|
1972(昭和47)7.5日、自民党総裁に選出される。同7.7日、総理大臣に就任し、第一次田中内閣発足。橋本幹事長、竹下副幹事長。事実上の竹下幹事長であったと云われている。福田に入閣を求めたが、福田は拒否し、福田派からの入閣も断っている。これほどの確執が生じたということである(福田が入閣するのは、5ヵ月後の第二次田中内閣で行政管理庁長官としてであった)。以降2年5ヶ月の任期となった。 角栄はかくて頂点に立ち、「決断と実行」をメインスローガンに掲げた。「二期六年はやらないよ。おれは人が六年でやることを三年でやる」とも云い為しており、自身満々のスタートを切った。この頃の内閣支持率60%を越している。マスコミも礼賛記事で、「小学校卒が東京帝大卒に勝った」、「今太閤」ともてはやした。 |
| 【第一次田中内閣発足】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1972.7.7日、第一次田中内閣が発足した(1972.7.7日〜1972.12.22日)。発足時の政権ワードとして「決断と実行」を掲げた。福田派の入閣拒否となり、郵政相三池信と経済企画庁長官有田揆一が応ぜず、角栄兼任でスタートした。総裁公選のしこりであった。その後田中・福田会談で覆水を盆に帰した。首相秘書官に通産官僚・小長啓一(のちのアラビア石油社長)を抜擢した。閣僚名簿は次の通り。
|
| 【この時の母フメの言葉】 | |
この時、母フメが次のように述べている。
|
| 【田中内閣の顔ぶれ考】 |
| 藤井裕久氏の二階堂進氏の秘書官入りが注目される。藤井氏は、大蔵省主計局主計官を最終役職に退官し、1977年、政界転身し第11回参議院議員通常選挙全国区に自民党公認候補として立候補し当選、2期務める。2005年、神奈川14区より衆院議員に転じる。以降、小沢一郎の側近の1人として活躍する。1993年、自民党を離党して新生党結成に参加。細川、羽田内閣で蔵相。その後、新進党を経て、自由、民主党で幹事長を務める云々。現在、民主党最高顧問。 |
| 【保守長期政権と対米協調】 | |
出典元を失念したが、次のような評が為されている。
|
| 【政権発足直後の田中の気概の言葉】 | ||
第1次田中内閣を成立させた直後、田中は秘書の佐藤昭子にこう漏らしている。
|
||
|
| 【政権発足直後、小長啓一氏起用】 | ||
第1次田中内閣を成立させた直後、田中は小長啓一氏を起用している。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)