| 亡くなった後もつなぎ続けた縁 |
| ――著書では角栄さんの意外なリーダー像を浮き彫りにされていますね。
|
| 「一般的に田中さんは『コンピューター付きブルドーザー』と言われ、強引に物事を進めるイメージがあるかもしれません。確かに強力なリーダーシップを持った政治家であったことは事実です。しかし、田中さんの本当の凄(すご)みは人との縁をつないでいく力です。この力こそ田中さんのリーダーシップ力の源泉であることを、この著書を読んでいただいたみなさんに知っていただければと思います」。 |
| 「田中さんはいったんつないだ縁をとても大切にしつなぎ続けていく。その人が亡くなった後もです。田中さんが通産大臣だった時、こんなことがありました。ある朝、田中さんが秘書官の私にこう言うのです。『おい、小長君、今日は誰かの葬式がなかったかね』。驚きました。確かにお葬式があったのです。しかし、この日は産業構造審議会という重要な会議の日でした。それに出席してもらうスケジュールを組んでいたのです。そう説明すると田中さんは静かにこう話してくれました『これが結婚式なら君の判断は正しい。日を改めて祝意を伝えればいい。だが葬式は別だ。2度目はない』。縁を大事にする人でした」。 |
| 誠心誠意、人と付き合う |
|
――田中さんは学閥も閨(けい)閥もない。どうやって縁を結んでいかれたのでしょうか。話術やお金の力という人もいますが。 |
| 「誠実さです。田中さんは誠心誠意、人と付き合う。そこが素晴らしい人でした。今は情報技術(IT)全盛期、オフィスで隣の人とコミュニケーションをとる場合もメールを使う時代です。もちろんITを活用することはいいですが『ここぞ』という時はバッと裃(かみしも)を脱いで裸になって相手と向き合う、その真剣さと真摯さが相手を動かすのです」。 |
| 「大蔵大臣に就任した際の『私は高等小学校卒。諸君は全国から集まった秀才』の演説はまさにその典型例でしょう。胸襟を開いて『大臣室の扉はいつでも開けておくから我と思わんものは誰でも訪ねてきてくれ。上司の許可はいらん』と言われれば心が動かない人はいないでしょう」。 |
| ――小長さんと田中さんの縁も不思議ですね。 |
| 「後で聞かされた話ですが、1971年7月、佐藤栄作内閣の改造が決まった時、ある取り決めが通産省幹部の間でなされたそうです。それはこうです。『それまで通産大臣だった宮沢喜一さんが変わり、若い大臣が来た場合は、秘書官も現在の昭和32年(1957年)より若返らせ昭和35年(1960年)から出す。その逆なら秘書官もベテランをあて昭和28年(1953年)入省組とする』」。 |
| 「結果的に宮沢さんよりもキャリアの長い田中さんだったので昭和28年入省の私が自動的に秘書官となりました。それまで田中さんと特別な縁があったわけではない。しかし、ここで田中さんと出会った。そのおかげで後の私の人生がブラッシュアップされていくことになります」。 |
| ――通産省を辞めようかと思ったこともあるとか。もし辞めていれば田中さんとの縁もなかった。
|
| 「大学で日本がなぜ第2次世界大戦に追い込まれていったのか、あの失敗を繰り返さず日本が発展していくにはどうすべきなのか、を徹底的に研究しました。そこで得た結論が貿易立国。これで国を立てていくしかないと確信、通産省に入省しました。ところが配属になったのは特許庁。特許庁は専ら法律行政をやるところで貿易立国の仕事とは縁遠い。学生時代に司法試験に受かっていましたし、そのまま役所に残るかちょっと迷う時期もありました。そんな時、通産省の仲間たちが『僕たちは学生時代、法律しか勉強してこなかった。こんな時だからこそケインズを原書で読んで勉強しよう』とい言いだしました。『やっぱり通産省はいい気風だなあ』と思い直しとどまることにしました」 |
| 一番好きな言葉「努力なくして天才なし」 |
| ――良い縁をもらい人生を豊かにしていくコツは何でしょうか。 |
| 「努力だと思います。田中さんが一番好きな言葉は『努力なくして天才なし』でした。田中さんは33本の議員立法をつくった人ですが、作ろうとする法律が関係しそうな条文を六法全書からとりだして、おなかのなかにのみ込んだんじゃないかというくらい徹底的に勉強していました。そんな田中さんの姿勢に若手官僚たちもひきつけられました。徹底的に議論をして一緒になって法案をつくっていくうちに田中さんと根っこから同志的な関係になっていきました。だから、通産大臣だった田中さんが『日本列島改造論』を書いた時にもオール霞が関で応援し最新のデータを出してくれたのです」 |
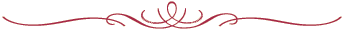
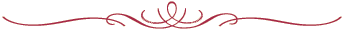
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)