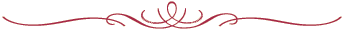
| 田中角栄の政治姿勢 |
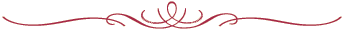
(最新見直し2010.11.19日)
| (れんだいこのショートメッセージ) | |||
| 田中角栄の評価は毀誉褒貶である。評価するものにとっては「霊能的万能者」であり、批判する者にとっては「諸悪の元凶」である。このどちらの言い分に信があるのだろうか。 れんだいこは角栄政治を次のように評したい。
角栄の政治姿勢を一言で述べることは難しいが、敢えて言えばこうなる。
角栄こそは、M・ウェーバー云うところの政治家としての資質「政治から収入を得る必要がない」、「政治のためだけに生きる実践家」像に限りなく近いのではないのか。新野哲也氏は、「角栄なら日本をどう変えるか」の中で次のように述べている。
「官に対する政の相対的な優位政治を主導し、その結果有能官僚の取り込みとそれによるリアクションが発生した」。これも角栄ならでは生起した現象であった。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その1、角栄の政治風景】 |
| 角栄の政治的姿勢を三つの観点からベクトル化させることが可能である。一つは、角栄は越後新潟に生まれ育った。越後の雪国性、恒常的な出稼ぎは、太平洋側と日本海側の格差を語る。この裏日本に政策的な光を当てようとする【1・格差是正ベクトル】である。もう一つは、角栄が戦後の引き揚げ時に東京の廃墟に佇んだとき、国土の復興を地から強く意思させた。若くして実業家として頭角を著していた角栄は、その事業手法で持って今度は国を相手に改造計画を立てることになった。この土建手法による日本列島全域的な【2・国土復興ベクトル】である。付加すれば、復興後の姿として【均衡ある国土の発展ベクトル】的観点を持っていた。もう一つは、中小企業の育成に主眼を置いた【3・経済再建、民力向上ベクトル】である。 この【1・格差是正ベクトル】、【2・国土復興ベクトル】、【均衡ある国土の発展ベクトル】、【3・経済再建、民力向上ベクトル】こそ角栄政治の原点であった。これらの政策は至極真っ当なものであり、左派的にはこれを批判するような政治論は有り得てならない。ということは、角栄の政治的姿勢は基本的に支持されるべきものだということになる。角栄を悪し様に批判してそれをすればするほど天にも昇る勢いで得意がるサヨ人士は、ここを弁論してみよ。 敗戦期の角栄は20代後半の青春真っ盛りであったが、下積みの兵役体験を持つと同時に一代で事業の成功経験を持つ稀有な人士であった。その角栄はいち早く、戦後憲法の本質を嗅ぎ取った。憲法に規定されたアメリカン風民主主義制度によれば、「土建屋でも国会議員になれる、国会議員になれば立法権が行使できる世の中になった」こと、学閥・門閥・閨閥を持たぬ者でも成り上がって行けるドリームの可能性があることをキャッチした。これをその通りに実践することで「時代の子」となった。それは同時に、戦前の「負の時代の政治批判」をバネにしていた。 |
| この面は隠されており、故にれんだいこも推定する以外にない。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その2、普通選挙選出代議士】 |
|
角栄の議員活動はこの基盤の上に花開いていくことになった。代議員選出の普通選挙制度の仕組みは、個々の有権者の力は弱くても、層としての有権者となるとこれは大いなる権力であった。角栄はこのことを的確に見抜き、当然の如く有権者の関心に応えることから議員活動を出発させた。これは他に何ら権力を持たなかった角栄ならではに見えた虚心坦懐な絵図面ではなかったか。 |
| 角栄は選挙に強かった。このことの政治史的意味が見過ごされがちで有るが、普通選挙制度下の代議員政治家の要素として重要なことではなかろうか。角栄は、自らの選挙区のみならずあらゆる選挙区事情に精通していた。このことは誉れであっても批判されることではなかろう。この面での考察は、「議会政治家の申し子としての角栄」の項に記した。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その3、金権利権政治家】 | |
金権政治というのは角栄が始めたものではなかろう。明治の文人の斎藤緑雨は既に次のように記している。
角栄にとって金権力はどのような意味を持っていたのかは別に考察するとして、角栄の金権政治批判する者は我が身の清廉潔白を証しつつそれを為さねばなるまい。自身が金権にまみれていたり望んでまみれようとしている者が、自身の腹立ちを角栄に向けて放つのはいただけれない。斎藤緑雨の明快な指摘の方が面白みがあってはるかに上等だろう。 こうした角栄の確固とした政治姿勢による議員活動は、新潟県に多くの補助金をもたらす事になった。常に全国5位から4位に位置する国庫金を引き出すことに成功した。これをもっては補助金政治と云われている。主に土木事業に費やされたことから土建政治家とも云われている。 |
|
| 普通に読み取れば、角栄政治が選出母体地元への恩返し政治であり、その際経済中心の実利主義にあったということである。「経済中心の実利主義による地元への恩返し政治」は果して批判されることであろうか。これを逆に問えば、地元無視の中央スター政治がそれほど評価されることだろうか、ということになる。れんだいこの結論は記すまでも無い。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その4、暴力団との直接的盟約関係不存在】 |
| 角栄と広域暴力団との直接的関係は認められない。 |
| そういう意味でも評価に値しよう。この面での角栄論は全く為されていないが、稀有事例のように思われる。ちなみに、岸、中曽根、小泉を見よ。戦後タカ派と云われる連中は広域暴力団との親交が認められ過ぎている。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その5、党人政治家】 | |
|
経歴と風貌から「元帥」と呼ばれていた佐藤派の長老木村武雄の弁は次の通り。
|
|
| れんだいこも実にそう思う。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その6、実質社会主義】 | |
|
角栄の万事実質主義思考は次の言葉によく現れている。1982年「早稲田大学某サークルに呼ばれた折の講演内容が語り継がれている。
|
|
| れんだいこがこれにコメントする。角栄はここで、機械的均等分配式社会主義、共産主義を批判しているが、社会主義、共産主義が機械的均等分配式を予定しているように説く左派モンが居るとすればそれはニセモノで、本来は角栄の「それが自由経済云々」の方こそ正統の社会主義、共産主義論である。ということは、角栄こそ社会主義、共産主義論をぶっており、世上の社会主義、共産主義屋の方がいかがわしい社会主義、共産主義論を言説しているという滑稽なことになる。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その7、実質民主主義】 | ||||||
|
角栄は、民主主義、民主政治の重要性について次のように述べている。
「2002.5.18日付読書録214小室直樹『痛快!憲法学』(集英社インターナショナル、2001年)」に次のような興味深い内容が記されているので転載しておく。
|
| 【れんだいこの角栄政治論その8、権力志向】 | |
|
透徹したリアリズムの世界に棲む角栄は、力を欲し、権力を目指した。「田中型政治を数による支配とよく言ったね。これは天に唾する言葉だ。多数を握らずに何ができるのか。その批判は論評に値しない」、「角栄がね、多数派を握る為に駆使した手法はカネとポスト。この二つを強力な媒介にしてね、自民党の人心、これを集めることにあった」(早坂茂三秘書)とある通りである。「敵と味方の峻別と懐柔」、自派閥強化に向けて清濁合せ呑んでいった。この対極に政治権力を悪と考える自由主義者、あるいは又クリーン政治家(三木武夫・市川房枝・青島幸男)が位置し、その他権益的権力の裡に生息する者、只の利権にぶら下がる者、角栄を目指しつつ凡そ器量の至らない者等々が蠢くことになった。
|
|
| 政治に於ける権力志向の反対は、万年野党であろう。その万年野党組が正義面して角栄批判に興じるのもええ加減にせねばなるまい。 |
| 【れんだいこの角栄政治論その9、弁証法思考】 | |||
|
ここに角栄の政治姿勢を物語る好例の遣り取りがある。1969(昭和44).5月の毎日新聞社主催の国会方式安保討論。自民党・田中角栄、社会党・江田三郎、石橋政嗣、民社党・佐々木良作、曽弥益、公明党・矢野じゅん也、黒柳明、共産党・宮本顕治(宮顕)、不破哲三らの論客が参加した。この時、「角栄の弁証法的思考と宮顕の硬直思考との遣り取り」の典型例が残されている。
宮顕はこれに喰いついて、占領下の国会で共産党の河上貫一が安保条約反対の演説をして除名されたことを取り上げ、そこに反共主義が存在するのではないか、と反論した。角栄は次のように再反論している。
宮顕は「それは形式論で、問題の中身のことを言っているんですよ」と笑いながら言った。角栄は次のように答えている。
|
|||
| この遣り取りは興味深い。れんだいこに云わせると、宮顕の方が硬直図式系公式主義的ご都合論を振り回している。戦後型保守本流の雄として台頭してきた角栄の方が弁証法的歴史観を披瀝しており、何とも対照的な差が顕著に見える。驚くことにと云うべきか、角栄の方が弁証法的思考をしているということである。れんだいこには、角栄の方がマルクス主義者としての資質ありと見る。滑稽な話ではなかろうか。 |
角栄のハト派的側面は、「戦後憲法体制と角栄、そのハト派的意義考」に記した。
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)