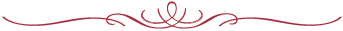
| 田中派の流れ、「七日会」 |
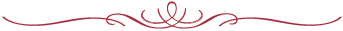
更新日/2016.10.15日
| Re::れんだいこのカンテラ時評830 | れんだいこ | 2010/10/21 | |
| 【政局を好み政治を疎かにした粗脳の行く末考】
2010.10月現在の菅政権下の政治を見て、いやましに見えてきたことを書きつけておく。菅首相、仙石官房長官、その他云わずもがなの前原、岡田らは、長い議員生活で政局遊泳術を身につけてきたが、肝心の政治能力を学び損なっているのではなかろうか。そのツケが今一挙に噴出しているのではなかろうか。政治の矢面に立ってみて、外交も内政も結局は自公政治の延長でしか事を処理できない。スッタモンダの挙句必ずそうなる。これは何を意味しているのだろうか。 鳩山政権以来、事業仕訳で悦に浸っているが、内政上の細かなことを論い予算削減する他方で軍事防衛費予算はズルズルと水増しされている。何の事はない、節約した分を軍事防衛費予算に貢いでいるに過ぎない。結局何をやってんだと云うことになろう。これが悲願の政権交代を実現した民主党政権の生の政治能力と云うことになる。 れんだいこには対極的にかっての田中派の凄さが見えてくる。田中派は「田中軍団」と形容され、実に「量的にも質的にも最強の政治集団、政策研究、相互扶助、家族主義的な絆を持つ同志的結合」を誇り、「政治の総合病院」と号していた。この結束を「金権力」によったなどとみなすのは皮相的というより児戯的であろうが、当時のマスコミメディアは、ロッキード事件で田中逮捕後も七日会が結束し続け、田中派の結束が崩れなかったことに対し、「金権つながり」と云う下衆の勘繰りから叩き続けた。 真実はこうであろう。角栄本人が、「派閥とは何か」と訊かれて次のように答えている。
西村英一は、「そりゃ、あの男が、いざ何かやろうと云う時、仕事ができるようにしておいてやるためだ。それ以外にはない」と述べている。木村武雄氏は、「(なぜ田中の周りに我々がこうしてたくさん集まっているかというと)みんなカネだというておるが、カネばかりではないぞ。なぁ、田中にはカネ以外の何かがある」と述べている。他にも、「(なぜ田中派だけが増えつづけるのかとの問いに対して)田中先生の魅力です。具体的には抜群の決断力と実行力。スケールの大きさ、頭のよさ、人情のこまやかさ、どれ一つとっても、田中先生の右に出る人はいないからです。それに仲間達が多士済済ですしね」というコメントが残されている。 興味深いことに、田中軍団には、旧帝大卒、官僚経験者が極端に少ないというかいない。その意味では、旧帝大卒が牛耳っていた政界構造に風穴を開けつつ新風を吹き込みつつあったことが判明する。この流れに有能と判断された官僚出身者、例えば山下元利、小長啓一、後藤田正晴、鳩山邦夫などを組み入れようとしていたことになる。この観点から考察されることは面白いと思うが、さほど為されていない。 近視眼的「田中角栄諸悪の元凶観」から一度離れて遠望すれば田中派の凄さが見えてくるのではなかろうか。田中派はまず政策集団として形成されている。個々の議員の政治能力を磨き議員立法を生みだすよう指導されていた。その政策を実行する為の頂点として権力闘争を闘い抜いた。ポスト佐藤の後継が約束されていた福田派を抑えて政権奪取に成功した。政権掌握後は約束通りに果敢にマニュフェストを履行実施した。その手始めが日中国交回復交渉であった。 政治の質で云えば、ストレートに公約を守る表裏のない良質政治を目指していたことになる。これを思えば、最近の政権交代以来の民主党政権のマニュフェストからの逃げまくりほど劣質の政治はあるまい。鳩山―菅政権は、有料高速道路の無料化マニュフェストのように景気浮揚策に繋がるものにつき、修正でも良いのに実施すること自体を「上から忌避」している。反対に財政悪化によりいずれ増税に繋がるような子供手当マニュフェストについては実施している。例の勢力の差しガネ金ではなかろうか。 もとへ。そういう田中角栄政治の後継が小沢派であり、2010.10月現在も政治及び政局の目玉になっている。よくぞ風雪耐えて生き延びてきていることよと思う。かの時も今もマスコミメディアは、この流れを指弾し続けている。この系の御用評論家は掃いて捨てるほど居る。新聞、テレビ、雑誌に跋扈し続けている。思うに連中の虚報が逆に弾劾される日もそう遠くないであろう。これを論証するのは難しいが、世界が刻々変化しつつあり風向きが変わりつつあるからである。 菅政権下の政治を見て思うことは、菅首相及びその一派が政治の「良き師」を持たなかったと云うことであろう。「良き師」を持たぬままズルズルと議員生活を続け、念願の政権取りに成功し、いざ事に臨むや腰砕けしていると云うことになる。しかも、政権交代に小沢どんの働きが顕著だと云うのに、政権取ったら手のひらを返して用済みにせんとしている。日本政治の良心とも云える小沢派をそのように待遇して我が世の春を迎えたとして所詮ろくなことにはなるまい。数年後、誰も見向きもしない残骸を晒すだけになろう。 2004.1.29日再編集、2010.10.21日再編集 れんだいこ拝 |
|||
| 【政治評論家の戸川猪佐武氏の田中派論】 | |||
政治評論家の戸川猪佐武氏は、田中派について、著作「君は田中角栄になれるか」の中で次のように述べている。
森下仁丹の会長にして参議院議員だった森下泰氏は、角栄の「側近の集め方」について、次のように語っている。
山下元利(大平内閣防衛庁長官)は、田中派について、次のように語っている。
|
| 【田中派結成】 | |
|
1972.5.9日、田中派結成。東京.柳橋の料亭いな垣に佐藤派81名(衆院40名(代理人7名)、参院41名(代理人5名))が結集した。呼びかけ人は木村武雄。田中派発足当時に旗幟鮮明にしたのは次の通り。愛知揆一、足立篤郎、植木、大村襄治、小沢辰男、小渕恵三、金丸信、亀岡高夫、仮谷忠男、木村武雄、久野忠治、小宮山重四郎、竹下登、二階堂進、西村英一、橋本登美三郎、箕輪登、山下元利、山田久就、渡辺肇、小山省二、石井一、小沢一郎、奥田敬和、梶山静六、高島修、中山利生、羽田孜、林義郎、渡部恒三の30名。 この時の渡部恒三の証言は次の通り。
|
| 【七日会】 | |
|
1972(昭和47).9.12日、田中派が七日会を発足させる。この時の勢力は衆院41(38)、参院42(45)の83名。同年末93名。代表世話人として西村英一と愛知揆一。最高顧問・田中角栄、顧問・橋本登美三郎、木村武雄、久野忠治、前田正男、植木庚子郎、郡祐一、前田佳都男、江藤智、二木謙吾。会長・西村英一、副会長・二階堂進、江崎真澄、吉武恵市、徳永正利。理事・足立篤郎、井原岸高、田村元、金丸信、亀岡高夫、小沢辰男、木村睦男、西村尚治、大森久司、宮崎正雄、柳田桃太郎、岡本悟、寺本広作、上田稔、長田裕二。幹事・橋本龍太郎、小宮山重四郎、大村襄治、松野幸泰、梶山静六、佐藤守良、奥田敬和、林義郎、渡部恒三、愛野興一郎、戸井田三郎、村岡兼造、金井元彦、梶木又三、川野辺静、安西愛子、世耕政隆、井上吉夫、遠藤要、亀井久興、戸塚進也、山東昭子。他に斎藤昇、小渕恵三、仮谷忠男、竹下登、箕輪登、山下元利、山田久就、渡辺肇、小山省二、石井一、小沢一郎、高島修、中山利生、羽田孜、林義郎、郡祐一、上田稔、永野鎮雄、橘直治、白井勇、木村睦男、鬼丸勝之、細川護煕、長谷川仁、大松博文、山本利寿、一龍齋貞鳳、斎藤滋与史、高橋英吉、山下春江、安西愛子。 1976(昭和51).4.26日、大幅な機構改革。西村英一会長、田中を最高顧問、副会長4名(二階堂進、江崎真澄、吉武恵市、徳永正利)と顧問9名(橋本登美三郎、木村武雄、久野忠治、前田正男、植木庚子郎、郡祐一、前田佳都男、江藤智、二木謙吾)、理事16名と幹事22名。 物故者西村揆一 箕輪登−田中派の切り込み隊長。 総裁候補を持たなかった弱点。 |
|
ベンジャミン・フルフォード氏の「テロ世界戦争と日本の行方」(211ページ)を引用転載しておく。
|
| 【1979年時点の田中派の面々】(「1979年11月6日衆議院本会議・首班指名選挙における投票行動(四十日抗争)」) |
| 江崎真澄、久野忠治、西村英一、二階堂進、足立篤郎、田村元、金丸信、井原岸高、竹下登、亀岡高夫、小沢辰男、小渕恵三、小宮山重四郎、橋本龍太郎、箕輪登、山村新治郎、松野幸泰、山下元利、田村良平、大村襄治、小沢一郎、渡部恒三、高鳥修、羽田孜、斎藤滋与史、山本幸雄、奥田敬和、左藤恵、石井一、佐藤守良、林義郎、竹中修一、梶山靜六、染谷誠、渡辺紘三、愛野興一郎、保岡興治、村岡兼造、愛知和男、中村喜四郎、中島衛、後藤田正晴、西田司、福島譲二、山崎武三郎、保利耕輔、畑英次郎、大城真順。 |
|
【木曜クラブ】 |
|
1980(昭和55).10.23日、東京・平河町の砂防会館に衆(56名)参(37名)両院議員93名が集まって発足。昭和58.3月現在で110名に膨張。会長・二階堂進、副会長江崎真澄・郡祐一、代表幹事・竹下登、事務総長・小沢辰男、運営局長・小沢一郎、広報担当・渡部恒三。角栄と衆参両院の自民党議員からなる。二階堂進、金丸信、竹下登をドンとして、中堅は後に七奉行と呼ばれる羽田孜、橋本龍太郎、小渕恵三、小沢一郎、梶山静六、奥田敬和、渡部恒三がいた。他には綿貫民輔、野中広務。 参院徳島地方区の内藤健が入会。 昭和59年1月、羽田が2代目事務局長(初代は渡部恒三とある)。 |
| 角栄直系派−二階堂(第一の腹心)、小沢辰男(金庫番)、山下元利(後継候補) 世代交代派−竹下登、金丸信 途中加入派−江崎真澄、田村元 新参組 −小坂徳三郎、野中英二 |
| 1984.3.10日、田中派総会。「かごに乗る人、そのまたワラジを作る人というが、ワラジを作っているのが木曜クラブだ」。日本の戦後史上、最大の政治派閥を形成したのが田中派である。1984年、第2次中曽根内閣に於いて、田中派議員は衆参合わせて140人、秘書は総勢1000人以上となっていた。「隠れ田中派議員」を含めると、その権勢はもっと強大だったと推測される。 |
|
1985年、竹下、金丸信らによって派内の勉強会「創政会」が結成された。田中はこれに憤慨するが、直後に脳梗塞で倒れた。田中が一線から退いたことで、派内抗争が激化する。二階堂は、江崎真澄、田村元、小坂徳三郎らを擁し、木曜クラブ会長であることを盾に、自身が田中派の総裁候補であると発言、総裁選出馬を臭わせると、創政会グループの橋本龍太郎、小沢一郎、梶山静六らがこれに猛反対し、創政会結成を痛烈に批判し、派内の一本化を目指す奥田敬和らの中立グループが形成されるなど、木曜クラブは完全に分裂した。 1987.7月、木曜クラブから120名が参加して、竹下派(経世会)結成大会が行われた。二階堂系だった田村グループや、奥田ら中立組も竹下派に参加し、木曜クラブは完全に衰退。大派閥としての地盤は竹下−金丸ラインの経世会に引き継がれていった。 竹下派の脱退により、二階堂が江崎、小坂、山下元利らを率いて二階堂グループとして派閥を牽引するが、少人数で閣僚ポストの獲得もままならず、政界への影響力は低下した。1990年の総選挙で田中角栄、小坂、久野忠治が政界を引退し、保岡興治、角栄の女婿である田中直紀が落選。大量に所属メンバーを減らしたことで、同年2月、木曜クラブは解散を表明し、田中政治の終焉を告げた。 |
【7日会】
当選5回以下の衆院議員中堅幹部で組織される。会長は斎藤滋与史。
【しあわせ会】
当選7〜9回の衆院議員。代表世話人は山下元利。
【田西会】
木曜クラブの中の大臣経験者の集まり。
【木曜クラブ秘書会】
総勢500名の秘書軍団。
【5日会】
参議院議員で組織される。
【新総合政策研究会】
木曜クラブの議員を中心に、官界、財界、学者などの有力メンバーを集め、昭和52年9月に発足。274名を結集した自民党最大のシンクタンク。
【 越山会】
佐藤栄作―周山会(山口県・周防の国から一字を拝借)
| 田中派(衆議員.参議員) | 大平派 | 福田派 | 中曽根派 | 三木派 | 中間派 | ||
| 72.7.7 | 田中角栄首相に就任 | (44.) | |||||
| 72.9.12 | 七日会発足。 | 83(41.42) | |||||
| 72年末 | 七日会の代表世話人として西村英一と愛知揆一が就任。 | 93(48.45)
党内最大派閥となる |
65 | 88(55.) | 43 | 49 | 58 |
| 74.7 | 参院選後 | 90 | |||||
| 76.7.27 | ロッキード事件。田中派から政治同友会に名称変え。 | ||||||
| 76.12 | ロッキード選挙後 | 84(42.) | |||||
| 77.7 | 参院選後 | 74(43.) | 77(52.) | ||||
| 79.10 | 84(50.34) | (50.) | 73(49.) | ||||
| 80.夏 | ダブル選挙後 | 92 | 81 | 76 | |||
| 80.10.23 | 政治同友会から木曜クラブ結成。 | 93(56.37) | |||||
| 参院徳島地方区の内藤健が入会。 | 94 | ||||||
| 80.12.26 | 衆参7名が新規入会(小阪徳三郎・竹内黎一・野中英二・有馬元治・佐藤信二・松尾官平・新自由クラブを離党して木村守男) | 101
大軍団になる |
|||||
| 81.2.28 | 82(57.24) | 75(46.29) | 50(44.6) | 43(32.11) | |||
| 81.10.29 | 参院秋田地方区の野呂田芳成。 | ||||||
| 81.11.5 | 参院茨城地方区の岩上二郎。 | ||||||
| 81.11 | 109(65.44) | ||||||
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)