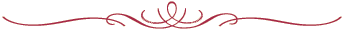
| �⑫�E���ێ�{���n�g�h�_�l�B�n�g�h�ƃ^�J�h�̐����I�Ⴂ�ɂ��� |
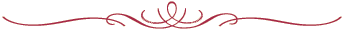
�@�i�ŐV�������Q�O�P�R�D�O�P�D�Q�S���j
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
| �@�����ŁA���ێ�{���n�g�h�_���l�@���Ă������Ƃɂ���B |
| �@�i������̃u���O�j | ||
| �@�u���ێ�{���n�g�h�v�ƃJ�e�S���[��ݒ肵�����ɉ��炩�̃C���[�W���N���Ȃ��Ƃ�����A�����{�̐����j�ɑ��Ă��Ȃ蕶�ӂł��邱�Ƃ����o���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A�����������x���̐����ʂ������A���ł������̒��ɂ��̎�̎҂������Ƃ����̂����낤�B���{�̖����͈Â��������Ƃ������S���o����̂͂������l�ł��낤���B�����������Ƃł͖{���̐����j�������Ă��Ȃ��A�Ђ��Ă͖����̐����h���}���Ȃ��Ǝv���̂ɖ{�T�C�g��݂��邱�Ƃɂ���B �@�u���ێ�{���n�g�h�_�v���l������Ӌ`�́A��X�̐������o���ɍ����̒��ɘS�ƋÌł��鎩���}�������R���h���}�ɑ��鐭���I���`�̖ӂ���߂ł���B����l�ɑ��Ă̓R�y���j�N�X�I�Ռ���^���邾�낤�B������́A��������҂��Ĉȉ������t���Č���B�N�����S�����Ȃ������Ƃ�����A����͂�����̕M�̖͂����̂����ł��낤�B �@�܂��A�ŏ��ɖ��炩�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A��㍶���������@���Ȃ鎞�ł��u���{�����}�v���ꊇ��ɂ��āu���A�e�N�A���e�A���Ӂv��n���̈�o���̂悤�ɂ��Ă������N��}�I�K���ɑ��āA�u����͊ԈႢ�ł������v�Ǝw�E���Ă������Ƃł���B������ʑ��I�ȃ}���N�X��`�I�̐��ᔻ�_�����ؐ������ɐU��ꂽ���ʂł���A���̃}���N�X�������ɑ������Ă����Ƃ�����A�����������ȑΉ��͂��Ȃ������ł��낤�A�Ƃ�����͍l���Ă���B �@������ɁA�u���{�����}���ꊇ��ɂ��Ĕ��A�e�N�A���e�A���Ӂv���キ�咣����ΎЋ��ƂȂ�A����������咣����ΐV�����Ȃ�S�����Ӗ��ȓ�����������ꑱ���Ă����̂���㍶�h�^���j�ł������B���̋��傪�����̎S��ł���̂ɁA���̂��ƂɋC�Â����Ƃ����Ȃ������w���ҁA����ɕt���]���}������ł���悤�Ɏv����B �@�ނ���A�������O�̕����d��ŁA���̗��j�I�Ӗ���[���m��A�u���{�����}�v�̐���̈ꋓ�����ɔ����ږ����Ή����Ă����߂�����B�Ȃ�ƂȂ�A���ێ�{�����`�����Ă����n�g�h�̐��u�{���I�ɍ��X�v�������̂ł���������ł���B�{���A�����m��̂��w�ԂƂ������ł��邪�A����ȃ}���N�X��`����{���X�ɉ���ɓǂނ��Ƃɂ��A�]�v�ɐ����I���`�ɂȂ��Ă����Ƃ����o�܂�����悤�Ɏv����B �@������̂��̈������ȉ��_���悤�Ǝv���B �@�u�����{�́A�����鍶�����]���悤�ɖ{���ɐ����̈������ł������̂��v�A������l���Ă݂悤�B�����̍��h�C���҂́u���������v�Ɖ]���ׂ��Ă���B�������A������́A�����v��Ȃ��B�ނ���A�u���E�j��H�Ɍ���@�؍��Ƃł͖��������̂��v�Ɗς�B���Ƃ�葊�ΓI�Ȃ��̂ł��邩��A���z�I�@�؍��Ƃł������Ƃ͉]��Ȃ��B�����܂ő��ΓI�ɉ����@���Ȃ���{�j��ɂ����Ă��A���E�j�̐��j��̑��̂ǂ̍��̂�������Ƃ�����r�̏�ł̂��Ƃł͂���B�u���ێ�{���n�g�h�����[�h���������{�́A�o�ϓI�����̐��������邱�ƂȂ���A�H�L�Ȃ閯���`�̊ѓO���Ă������Ƃ�n�����Ă����v�̂ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ��]��������ł���B �@���₻���ł͂Ȃ��Ƃ����Ȏ��R�A���ۂ������Ĕے肵�悤�Ƃ���҂����邾�낤�B���������ҒB�ɉ]�������B�Ȃ�A��́A�N�̂��A�ł��������̔т��H���A�Љ�I��������������ł����̂��B���ꂱ�������̗v���ł���A���̗v���ɉ����Đ��ێ�{���n�g�h�قǂ��܂��������Ă��������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B �@�m���ɕ��s���ۂ͂��܂�����B�����������̌��@�����̖@���ɏ]���A����͐l����O�I�n�ӍH�v�ɂ���āu�X�ɓ�������d�|���ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��̂��v�ƌ����Ԃ������B���ێ�{���n�g�h�����[�h���鎞��ɉ����Ă����A���h�͊K����̍X�Ȃ鍶�X�������Ă̗Ƃݏo���ׂ��ł͂Ȃ������̂��B����������ɁA�����u����v����̂��^������悤�ȕs���̓������I���N�ᔻ�ɏI�n���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B����͉��̈Ӗ��������ނ���L�Q���v�������B �@������̊ς�Ƃ���A��㌛�@�͊v�����̂悤�Ȃ��̂��K�肷��ɂ͎����Ă��Ȃ��B�������A���̑��̏��K��ɂ����Ắu���E�j��H�Ɍ����i�I�K��̌n�v�ƂȂ��Ă��鐢�E�ɐ���̌��@�ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B���̌����ɑ���A������玩�R�s���`�A���ē����I���{��`�̐����Ő���������s�����̂��u���ێ�{���n�g�h�v�B�ł������B���̈Ӌ`�ƌ��E���ǂ�������̂��A���ꂪ�{�e�̊�ڂł���B �@�u���ێ�{���n�g�h�v�ɂ��āA�c���p�h�����̂悤�Ɍ���Ă���B
�@�u���ێ�{���n�g�h�v�Ƃ́A�g�c���u�y�����A�o�ϕ����v�̑��H����~���A�r�c���u�����{���A���x�o�ϐ����v�̘H���œ��P���A�������܂ܓ��P���A�p�h���u���{�����_�v�ŗ͋������ݍ��݁A�啽�A��֎������n�����]���B���̃n�g�h�̐���͎��̂悤�ɗv��ł���B
�@���̃n�g�h���P�X�T�O�N�ォ��W�O�N�㏉���܂Ŏw���͂��������Ƃɂ�薢�\�L�̍��ƓI���W�������炵�A���ʓI�ɓ��{�͐��E���Q�̒n�ʂ܂ŏ��l�߂邱�ƂɂȂ����B�W�O�N�㏉���A�^�J�h�̒��]���������a������ɋy�сA�ȍ~�^�J�h�����ǂ����[�h���邱�ƂɂȂ�A�����Ȉ����I�����̗����őΕĒǐ�����ɑ���A����܂ł̍��x��H���ׂ��Ă������ƂɂȂ����B���̗��ꂪ�Q�O�O�U�N���݂̏����܂Ŋ�ƂȂ��Ă���B �@�ȉ��A���̌n���̃n�g�h�ƃ^�J�h�̐����I�Ⴂ��Δ䂳���Ă������Ƃɂ���B �@�Q�O�O�U�D�W�D�Q�P���ĕҏW�@������q |
| �y���ێ�{���n�g�h�_�l���̂P�z |
| �@���̎Љ�v�z�͎n���̓�������{�^���̊|���Ⴂ�����ė����B���ꂩ��U�T�N���߂��č��Ȃ����ς�����߂Ă��Ȃ��B����ȋC������̂ŁA���������M�[��\���グ�����B��������u���w���^���㉺���v�̒��ŖG��I�Ɏw�E���Ă���Ƃ���̂��̂ł��邪�A�����̎҂��܂��ǂ�ł��Ȃ����Ƃ������Ă��܂ł����Ă��F�m����Ȃ��B����������ŌJ��Ԃ��ɂȂ�̂͒v�����Ȃ��B���̖��ς������Ȃ�������{�ɂ�������Љ�v�z�͈������Ƃ��O�i���Ȃ��ƐM����̂ɂł���B���������A�u���w���^���㉺���v��ǂ�ł݂悤�Ɖ]���C�ɂȂ��Ă���邾�낤���ӂӂӁB �@���ɓ�������]�����ƂŌ����Ԃ�荇���������B������́A����܂ł͎ᑢ�̕��ۂʼn��ӋC�ȂƉ]���邱�Ƃ�����Ĕ������T���Ă����B�C�����Ίҗ���z���ĂR�ɂȂ��Ă���B�����\���ȗ�낤�B����̉]�킹�ĖႤ�B���ɓ�������]�����̂͐M�p���Ȃ������ǂ��B�q�҂͓�����Ƃł�������Ղ������B������Ղ����ƂȂ�Ȃ�����R��B��������]���̂́A���l���܂��\���əł��Ă����Ȃ�����ł��邩�A���邢�͂��������C���̎҂ł��邩��ɉ߂��Ȃ��B������͍��h���ɐ������Ȃ����a�ȏ�����焈Ղ��Ă������A���̎��͕�����Ȃ����������͂͂�����]����B��������]���҂̒m�����i�����M�p�ł��Ȃ��B �@���Ė{��B�u���ێ�{���n�g�h�v�ƃJ�e�S���[��ݒ肵�����ɉ��炩�̃C���[�W���N���Ȃ��Ƃ�����A�����{�̐����j�ɑ��Ă��Ȃ蕶�ӂł��邱�Ƃ����o���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A�����ʂɂ��Ă����������x���̎҂������B�e���r�ɏo�Ă���\�w�ɗ]��R�����e�[�^�[�̂������l�����i���邾�낤���B���炭��l�Ƃ��Ă��Ȃ��B���������A���̉�������꓾�S�������Ă���҂����������Ǝv���B�����ŕt�������Ă������h���̒��ɂ����̎�̎҂������B���ێ���̃n�g�h�^�J�h�̐��������^�ɐ��j������ł���Ɖ]���̂ɈӊO�ɖ��m�ł���B���̑���ɍ��h���̐����j�I�ɂ͂��قLjӖ��̂Ȃ������j�ɋ�����҂������B����͒��x�A���E�j�Ɍւ����{�̖����j�ƂȂ�ƈĊO�ɕ\�w�����m��Ȃ��ȂɃt�����X�v���A���V�A�v���ƂȂ�ƌ��ė����悤�ɃW�F�X�`���[����Ō��p�Ɏ��Ă���B�����������_�Ƃ���̓��{�̖����͈Â��A�������Ƃ������S���o����̂͂���������ł��낤���B �@�͌鏫���ɗႦ��A�}�`���A���i���x���̂��̂ƒm��ׂ��ł��낤�B�����������x���ł͖{���̐����j�������Ă��Ȃ��A�Ђ��Ă͖����̐����h���}���Ȃ��Ǝv���̂ɖ{�T�C�g��݂��邱�Ƃɂ���B�u���ێ�{���n�g�h�_�v���l������Ӌ`�́A��X�̐������o���ɍ����̒��ɘS�ƋÌł��鎩���}�������R���h���}�ɑ��鐭���I���`�̖ӂ���߂ł���B����l�ɑ��Ă̓R�y���j�N�X�I�Ռ���^���邾�낤�B������́A��������҂��Ĉȉ������t���Č���B�N�����S�����Ȃ������Ƃ�����A����͂�����̕M�͂̂Ȃ��̂����ł��낤�B �@�܂��A�ŏ��ɖ��炩�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ����ƂƂ��āA��㍶���������@���Ȃ鎞�ł��u���{�����}�v���ꊇ��ɂ��Ĕᔻ�ΏۂƂ��A�u���A�e�N�A���e�A���Ӂv��n���̈�o���̂悤�ɏ����Ă������N��}�I�K���ɑ��āu����͊ԈႢ�ł������v�Ǝw�E���Ă��������B������ʑ��I�ȃ}���N�X��`�I�̐��ᔻ�_�����ؐ������ɐU��ꂽ���ʂł���A���̃}���N�X�������ɑ������Ă����Ƃ�����A�����������ȑΉ��͂��Ȃ������ł��낤�Ƃ�����͍l���Ă���B �@������ɁA�u���{�����}���ꊇ��ɂ��Ĕ��A�e�N�A���e�A���Ӂv�����a�Ɏ咣����ΎЋ��ƂȂ�A������}�i�I�Ɏ咣����ΐV�����ƂȂ�Ȃ�Ɖ]�����_�I�ɂ͂قړ����œ����`�Ԃ������قȂ�Ɖ]���Ⴂ�ł����Ȃ��������A�V�����^���ɒ^���ė����̂���㍶�h�^���j�ł������B�P�X�U�O�N�O��A�V�������X�����o�ꂵ�����������Ƃ̗��_�I�����͊J�Ԃ��Ȃ������B���ꂼ�ꂪ�l�|�����������ŗ��_�I���r���ׂ���Ă��Ȃ��B���̋��傪�����̎S��ł���Ƃ�����͍l���Ă���B�Ћ��I�������͊��ɑ̐����ێ�ł���B�V�����͑̐��O�ł��邩���m��Ȃ����o��ȗ����ɂT�O�N���o�߂��Ă���̂ɐ����̕\����ɏo�Ă���܂łɎ����Ă��Ȃ��B�V���Ƃ��A���̎S��ɋC�Â����Ƃ����Ȃ������w���ҁA����ɕt���]���}������ł���悤�Ɏv����B�����������Ƃłܑ͖̂Ȃ��B �@�Q�O�O�U�D�W�D�Q�P���ĕҏW�A�Q�O�P�R�D�O�P�D�Q�V���ĕҏW�@������q |
| �y���ێ�{���n�g�h�_�l���̂Q�z |
| �@���������Ӗ��ł͂ނ���A�������O�̕����d��ŗ��j�ʂł������B���̗��j�I�b���̈Ӌ`��[���m��A���{�����}�����̈ꋓ�����ɔ����ڂȂ��Ή����Ă����߂�����B�Ȃ�ƂȂ�A���ێ�{�����`�����Ă����n�g�h�̐��{���I�ɍ��X�������̂ł���������ł���Ǝv����B�����l����O�I�Ɍ��đP���ł��邱�Ƃ��@�m���đ����̎҂��x�������̂ł͂Ȃ��낤���B�Ɖ]�������̎���̎��ۂ́A�����ېV���疾���ېV�ւ̗���A�����ېV����哌���푈�܂ł̗���ŁA�����ېV�̉�V�^����P���Ȃ������͂��s��ӔC�����Ǖ����ꂽ���Ƃɂ��P���Ȃ����Ȃ������ېV�ȗ��̉�V�^���̗��ꂪ�ꎞ�I�ɂ��敜�����{��Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B����Ӗ��Ő�O�I�������������@����A�×����̓ꕶ�I�b�q�Љ�������Ă����B�������O��������������z�Ɋ����ē����n�߂��̂ł͂Ȃ��낤���B������̃n�g�h�����ɑǎ�肵�Ă������ゾ�����̂ł͂Ȃ��낤���B �@���Ƃ����j�͂����͈�ӓ|�̂��̂ł͂Ȃ��B�s����@�ɍ��ۋ��Z���{�鍑��`�̓��{�x�z�A���ׂ̈̃^�K�Ƃ߂�����Ƃ���ōu�����A��x�ƍ��ۋ��Z���{�鍑��`�ɉ���ʂ悤��������čs�����{�ł��������B��㒼�ォ��P�X�V�O�N��܂ł́A���̓�x�N�g�����������鎞��ł������B�̂ɒP���ɑP������ł������Ƃ͌����Ȃ��B�������Ȃ���A�����̔@�����ۋ��Z���{�鍑��`�̃����T�C�h�I�Ȏx�z���ѓO���鎞�ォ�猩��A��قǑ��ΓI�Ɏ��R�ȓ��{�ł������悤�Ɏv����B �@�{�����̕ӂ�̋@���܂Œm��̂��w�ԂƂ������ł��邪�A���h�҂͑����}���N�X��`����{���X�ɉ���ɓǂނ��Ƃɂ��]�v�ɐ����I���`�ɂȂ��Ă����Ƃ����o�܂�����悤�Ɏv����B������̂��̈������ȉ��_���悤�Ǝv���B �@�����{�́A�����鍶�����]���悤�ɖ{���ɐ����̐��A�����̑e�����������̂��낤���B�u���W���A�̐��K��ɂ��]�����w�j�����˂Ȃ�Ȃ����Ƌy�юЉ�����̂��낤���B������l���Ă݂悤�B�����̍��h�҂̓u���W���A�̐����ӂR�����Ă���B�������A������́A�����v��Ȃ��B�ނ���A�����������]���Ƃ���́u�����{�͐��E�j��H�Ɍ���@�؍��Ƃł͂Ȃ������̂��v�Ɗς�B���Ƃ�葊�ΓI�Ȃ��̂ł��邩�痝�z�I�@�؍��Ƃł������Ƃ͉]��Ȃ��B�����܂ő��ΓI�ɉ����@���Ȃ���{�j��ɂ����Ă�������̐��E�̑��̂ǂ̍��̂�������Ƃ�����r�̏�ł̂��Ƃł͂���B�u���ێ�{���n�g�h�����[�h���������{�́A�o�ϓI�����̐��������邱�ƂȂ���H�L�Ȃ��㌛�@�I�����`�̊ѓO���Ă����v���Љ��`���Ƃ�n�����Ă����̂ł͂Ȃ��̂��A�X�ɉ]���ΐ^�ɓ��{���ւ�ׂ��ꕶ���{�̋����̊��͂��\�o�����������������̂ł͂Ȃ��낤���v�Ƃ������Ƃ��]��������ł���B���̈������A�ꕶ���{�_�𗝉����Ȃ��Ɠ��S�ł��܂����A����͕ʂ̋@��ɏ���B �@�u�����{�@�؍��Ƙ_�A�v���Љ��`���Ƙ_�v�ɑ��āA���₻���ł͂Ȃ��Ƃ����Ȏ��R�A���ۂ������Ĕے肵�悤�Ƃ���҂����邾�낤�B���������ҒB�ɉ]�������B�Ȃ�A�P�X�V�O�N��_�Ƃ��Ă��̑O��̐��\�N�ԁA��́A�N�̂��A�ł��������̔т��H���A�Љ�I��������������ł����̂��B���ꂱ�������̗v���ł���A���̗v���ɉ����Đ��ێ�{���n�g�h�قǂ��܂��������Ă��������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B����������̂Q�O�P�Q�O�@�I�ł͕s���I������荹�����ꂽ���A�����������̂Ƃ͖����̌��͂������ɑ����Љ�����̂ł͂Ȃ��̂��B��U���ɔے莖�ۂ�_���̂͌����ł͂Ȃ��B�����̐��������r���Ă݂�A��قǂ܂Ƃ��ȎЉ�����̂ł͂Ȃ��낤���B �@���̈����ł�����Ȃ��҂Ɏ��̂悤�ɉ]���������Ă������B���h���̃o�C�u���Ɂu���Y��`�҂̐錾�v�i���Ɂu���Y�}�錾�v�Ɩ�Ă���j�����邪�A�����́u�{���Q�A�v�����^���A�Ƌ��Y��`�ҁv�̍��̖����Ɂu�ߓn���Љ�̏�����v���L����Ă���B�����ɏq�ׂ��Ă���P�O�{��̖w�ǂ������{�����Ɏ�������Ă���B���̏ڍׂ̌����͂����ł͊�������B������v���A�����{�͕�����Ȃ��u�ߓn���Љ��`�Љ�v�ł͂Ȃ��������B���Ȃ��Ƃ����̖G��I�Љ�����̂ł͂Ȃ��낤���B �@�m���ɒP���Ɂu�ߓn���Љ��`�Љ�v�Ɖ]���ׂ��ɂ͖����ȍ��ۋ��Z���{�鍑��`�̈����A����ɋK�肳��鏔���x�A���s���ۂ���荪�{�ɂ����Ă͑̐�������Ă����B�������A����ł����A�����̌��@�����̖@���ɏ]���āA�l����O�I�n�ӍH�v�ɂ���đQ�����ǂ̕ϊv�]�n���傢�ɂ������̂ł͂Ȃ��̂��ƌ����Ԃ������B�Ƃ�킯���ێ�{���n�g�h�����[�h���鎞��ɉ����Ă����A���h�͍��o�l�Ƃ��āu�ߓn���Љ��`�Љ�v�̂��������Ɍ����čv�����ׂ��ł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B�j���͋t�Ƀn�g�h�����[�h���鎞��ɉ����č��h�^�������������A�^�J�h�����[�h���鎞��Ɏ����Ă͍����̔@���S���N�ǂ��Ă���B����ł͘b�����Ⴄ�A�t�ł���ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B �@�n�g�h�����[�h���鎞��Ɍ���I�Ȗ��N�ᔻ�ɏI�n���Ă������a�n�A�v���������ɋ����ė����}�i�n�̑o���Ƃ��A�v���Ηǂ�����ʂɉ߂����ė������̂ł���B����Ɖ]���̂��A���_�̑������炵�ă{�^�����|���Ⴆ�ė������ƂɌ���������̂ł͂Ȃ��낤���B����������ŁA���a�n�A�}�i�n�̗��ҍ��h�^���Ƃ������̈Ӗ����Ȃ��ނ���L�Q���v�Ȃ��̂ł����Ȃ������Ƒ����������B�������������{�̗��j�K�肪����Ă����Ƃ���Ɍ��������߂���Ƃ̉����o�������B���ꂪ������j�ςł���A�{�̔����ł���B �@ �Q�O�O�U�D�W�D�Q�P���ĕҏW�A�Q�O�P�R�D�O�P�D�Q�V���ĕҏW�@������q |
| �y���ێ�{���n�g�h�_�l���̂R�z | ||
| �@������̊ς�Ƃ���A��㌛�@�͊v�����̂悤�Ȃ��̂��K�肷��ɂ͎����Ă��Ȃ��B�������A���̑��̏��K��ɂ����Ắu���E�j��H�Ɍ����i�I�ȋK��̑̌n�ƂȂ��Ă���B���E�ɐ���̌��@�ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B���̌����ɑ���A������玩�R�s���`�A���ē����I���{��`�̐����Ő���������s�����̂����ێ�{���n�g�h�̐����ł������B���̈Ӌ`�ƌ��E���ǂ�������̂��A���ꂪ����Ă������j��ł������B�����₤�̂��{�e�̊�ڂł���B �@�u���ێ�{���n�g�h�v�ɂ��āA�c���p�h�����̂悤�Ɍ���Ă���B
�@�u���ێ�{���n�g�h�v�Ƃ́A�g�c���u�y�����A�o�ϕ����v�̑��H����~���A�r�c���u�����{���A���x�o�ϐ����v�̘H���œ��P���A�������܂ܓ��P���A�p�h���u���{�����_�v�ŗ͋������ݍ��݁A�啽�A��֎������n�����]���B���̃n�g�h�̐���͎��̂悤�ɗv��ł���B
�@���̃n�g�h���P�X�T�O�N�ォ��W�O�N�㏉���܂Ŏw���͂��������Ƃɂ�薢�\�L�̍��ƓI���W�������炵�A���ʓI�ɓ��{�͐��E���Q�̒n�ʂ܂ŏ��l�߂邱�ƂɂȂ����B�W�O�N�㏉���A�^�J�h�̒��]���������a������ɋy�сA�ȍ~�^�J�h�����ǂ����[�h���邱�ƂɂȂ�A�����Ȉ����I�����̗����ō��ۋ��Z���{�鍑��`�̎w�߂���{��̐��������ɑ���A���ʓI�ɂ���܂ʼnc�X�ƒ~���Ă������x��H���ׂ��Ă������ƂɂȂ����B���̗��ꂪ�Q�O�O�N�㏉���̏�������ɍX�ɃG�X�J���[�g���A�Q�O�O�X�������ɂ�閯��}�O�㐭����������P�������A�Q�O�P�Q�O�@�I�ɂ�莩���̈��{���������������X�ɃG�X�J���[�g���悤�Ƃ��Ă���B �@�ȉ��A�{�e�Ɋ֘A���������̉ߋ��̏��������L���Ă����B �@������u�P�P�v�Ƃ���B�ȉ��̂��Ƃɒ��ӂ����N���ꂽ���B���{���h�^���̏K�������������P�b�^�C�i�z�ł��������ƂɋK�肳��āA���Ȃ��ƂɁA���{���h�^���ɑ����Đ��Љ�̃v���Љ��`����S�����͉̂��ƕێ�I�����^�}���ł������B�L�\�̎m�����X�ɓ��{���h�^���Ɍ�������A�̐����ɓ��荞�݁A���{�^�}�n�̃n�g�h�Ɉʒu���A�����{�̃v���Љ��`�I�������������Ă������ƂɂȂ����B�����ɐ����{�����̑傫�ȝ�������Ď�邱�Ƃ��ł��悤�B �@�����^�}�͂₪�ĂP�X�T�T�N�Ɏ��R����}��n�o���邪�A�}���͗l�X�ȃn�g�h�Ɨl�X�ȃ^�J�h�����������荇�����тł������B���̒��ŁA�ő吨�͉����Ă������̂́A�g�c���J�c�Ƃ��A�r�c���l�������ԂƂ��A�n�g�^�J�₶��ׂ��I�ȍ����h����������݁A�c���p�h�𑍐��Ƃ��A���̎������R�Ɉʒu���Ă����啽���F�|��ؑP�K�܂Ŏ��邢����g�c�w�Z�h�ł������B���������{�����j��̃n�g�h�Ɖ]���B �@�����{�����j��̃n�g�h�Ƃ́A��㌛�@���T�ˏ��炵�A���̑�j�̒��Ŏ�Ƃ��ē����ɗ�݁A�O���͌��㐢�E�������鍑�ۋ��Z���{�̘g���ɔ[�܂錇�ׂ������Ȃ�����A�����Ő�㌛�@�I���ۋ����ɂ������o���Ƃ������Ȃ荂���Ȑ����|�H�����]���B�����K��ł���Ǝv���B �@���̃n�g�h����ォ��P�X�V�O�N��܂ł̐��ێ�{���܂�嗬�h���`�����A�}���̃^�J�h�ƕ\�ʓI�ɂ͑��a���Ȃ���A�ꗬ�Ō������Η��R����������S���čs�����B�n�g�h�́A��O���̍��Ǝ�`�I���{�I�������x�Ɖ]�����Ɠ��]�𐭎��哱�I�ɑ��삵�A������������ɔ\���������Ɖ]���j��������ł���B���̊��ԁA�����{�͓����ɐ������A���x�o�ϐ������Ăэ��݁A���E�j��ɋH�Ȃ锭�W�𐋂��A���Ĉ��ۂ̘g�g���Ȃ�����������I�ȍ��ۋ����ɂ��v�����A�W�A�A���ߓ��A�A�t���J��������̎^���������B������v���Α傢�Ȃ�P������ł������B �@�����{���h�^���́A��㌠�͓��ǎ҂̂��̂悤�ȓƓ��̐��������Ƌǖʂ͂��A�A�ɗz�Ƀn�g�h�ƒ�g���ׂ��ł������B�Ƃ��낪���ۂɂ́A�n�g�h���^�J�h���\�c�ЂƂ��炰�Ƀ}���N�X��`�I���ʋ����ɏ]���đœ|�����ׂ��ێ甽���I�̐��h�ƒf���A�}��������`�I�Ȑ��{�����}�ᔻ�^���ɏI�n���Ă����B���ɐ����œ|���č����邪�A�����Đ�����������ӎv���\�͂���������^���ɖv�����Ă����ɉ߂��Ȃ��B �@�Q�O�O�U�D�W�D�Q�P���ĕҏW�A�Q�O�P�R�D�O�P�D�Q�V���ĕҏW�@������q |
| �y���ێ�{���n�g�h�_�l���̂S�z |
| �@���{���h�^���́A�����{�̗����҂ƂȂ������{�����}���̃n�g�h�I�^���ɑ��ė]��ɂ����e���ȑΉ������Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B���A���{�����}���̃^�J�h�I�^�����A�n�g�h���オ�z���Ă������x�����ۋ��Z���{�鍑��`�ɏ���n���A�����z�����ɂ������Ă��鎞�A���҂����ʂ����X��X���ׂ��ł͂Ȃ��낤���B�u���{�����}�v�ɑ��閜�N��{���ᔻ�قǎ��ۂɂ�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B �@��Ȃ����ƂɁA���{���h�^���́A���{�����}���̃n�g�h�������������@�������Ă������ɂ����Ƃ�����ɔ����{���̐��^�����J��L���A�^�J�h�������@�����Ă��錻�ݕN�ǂ������A����O���̔ᔻ�^���ɏI�n�������͂���Ƃ����o�܂������Ă���B���ꂪ���R���̈ӂȂ̂��͕�����Ȃ����A���������������Ή������Ă���B�Ћ��^�����ɋ{���|�s�j�n�����^�����^�ɔᔻ����˂Ȃ�Ȃ��̂́A���̔ƍߐ��ɉ����Ăł���B �@�v���ɁA���{�����}���̃n�g�h������ǎ��̂���ł������ƌ������A���̌��E��˔j���X�Ȃ鍶����̐����^���ݏo�����߂ɕُؖ@�I�Ɍ��������ׂ��ł͂Ȃ��낤���B�n�g�h������̌������̂͋g�c���J�c�Ƃ���r�c���l�y�ѓc���p�h�A�啽���F�A��ؑP�K�����ł��邩�炵�āA���̎���̐��������������A���������߂�ׂ��Ƃ���͕������ċ����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B �@�M�҂́A���ێ�{���h���ꎞ���`�����Ă����n�g�h�̒��ł��c���p�h�������U���ێ���͐^���̍��h�����ł͂Ȃ��������Ɛ��肵�Ă���B���ۂɂ́A�Ñ�o�_�����̑卑��I�����ł������Ƃ݂Ȃ��Ă���B�X�T�m�E�Ƃ݂Ȃ����������邪�I�I�N��k�V�I�ł������Ɖ�����̂����߂��Ǝv����B������O�̑P�������ł���A�A�ɗz�ɂ��̌�̓��{�����ɉe����^���Ă���B �@����̂ɁA���̂��Ƃ�k��������l�I�V�I�j�Y�������b�L�[�h������p�ӎ����Ɏd�|���A�����I�ɑ������̂ł͂Ȃ��̂��B�l�I�V�I�j�Y�����������Čĉ����A���̍ۋ{���|�s�j�n�������ُ�ɂ͂��Ⴂ�����ɂ͏L�����̂�����Ƃ̉����������Ă���B���{���h�^���͐V�������Ƃ��ǂ��A���̊ϓ_�����炫�������Ă��Ȃ��B�ނ���A���������̌����Ƃ��ċ��ɍň������Ă���B�ʂ����Ăǂ���̎~�ߕ����������̂��낤���B �@�p�h�ɂ��ẮA�u�c���p�h�_�v�ijinsei/kakuei/tanakakakuei.htm�j�ő����������Ă���̂ŎQ�Ƃ��ꂽ���B�M�҂����ɐG��Ă���������������̂ŋL���Ă����B����́A�p�h�����b�L�[�h�ٔ��ʼnH�����i�߂��ꂽ�܁A���������̓r�����V�����n�ٌ�m�Ɉ˗��������Ƃł���B�p�h�͉��䂦�������O�����Ȃ����ɂ���ĐV�����n�ٌ�m�Ɉ˗������̂��낤���B���ꂪ������҂����邾�낤���B �@������j�ςɋ���Ηe�Ղł���B�M�҂́u�p�h���U���ێ���͐^���̍��h�v���ɗ��ĂA���������ɖ{���\����ŁA�p�h�������Ƃ͈Ⴄ�^�������̌n���ł��낤�Ɖ��肵�ĐV�����n�ɕK���̎v���ŏ����M�����߂��Ɖ����邱�Ƃ��ł���B �@�ł���Ƃ���Ȃ�A�V�����́A�p�h���m�����͂ގv���ō����L�ׂ������������Ǝ~�߂�ׂ��ł������B�V�����n�ٌ�m�͑S���͂Ŋp�h�~�ςɌ����ׂ��������B���ۂɂ͂��̗L�\�����ő���������Ċp�h�l�ߐ����咣�����`�Ղ��Ȃ��B���炭�A�������S�̂��������̊p�h�ςɉЂ�����ĔM�S�ƂȂ�Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B�Ԃ��Ԃ����c�O�Ȃ��Ƃł������B �@����ɂ��Ă��A�p�h�ގ��ɓS�r��U������{���|�s�j�n�̂����܂�����B�ނ�́A���b�L�[�h�����E���Œ��̂P�X�V�U�i���a�T�P�j�D�V�D�Q�W���A�H�ɗ\�肵�Ă�������}���𗂂T�Q�N�ɉ������A�ٗ�ɂ��}�j�㏉�߂Ă̗Վ��}�����J���A�{���E������ψ������A���̖`���̈��A�Ɗ�����A�O���̓c���O�̑ߕ߂��ւ炵���ɓ`���A�Ίp�h�����̓O�ꐄ�i���Ԃ������ٗ�̕��X�Ȃ�ʈӎv����������B���̎��̗l�q�ɂ��Ă̏ڂ����L�^�����\����Ă��炸�A�閧���̔Z�����̂ƂȂ��Ă���B �@�p�h�̂��̌�͓����̊肤�ʂ�̂��̂ƂȂ�A�����I�ɍi�E���ꂽ�B�����Ȃ��s�j�́A�����Ċp�h�����������̌����Ƃ��Ă����l�Ɏw�e���Ȃ���A���ɂȂ��ĉ]�����ƂɊT�v�u��قǕn�R���Ă����̂��낤�B�������猩�Ă��قǂ̊z�ł��Ȃ��͂��T���~�̋��~�����ɊO������̉������Ɏ���o���Ă����v�ȂǂƊp�h�����ĂȂ����J���Ă���A�����J�Ȏ��ɓ}���̔��蔏��Ɖ]�����܂��t���ł���B���Ɍ�蓾���̖ʁX�ł͂Ȃ��낤���B �@�������A��ÂɂȂ��čl����Ύ��̂��Ƃ����炩�ɂȂ�B�����݁A�����A����̃^�J�h�n���\�����v�Ə̂��Ď����玟�ւƉ����������Ă��鏔���x�́A�n�g�h����ɒz���ꂽ�P���̎Y������ł���B�^�J�h�n�͉����}���ʼn����ɋ��z���Ă���̂��낤���B�������F������˂Ȃ�Ȃ����낤�B���ۋ��Z���{�̃V�i���I�_��}������ĉ����邾�낤���B �@�M�҂͊��Ɂu��㌛�@�������v���Љ��`�̂���ƔF�����쎝���点���߂�^����W�]����v�ŏq�ׂ����A���ێ�{���̃n�g�h���������A�����{�̃v���Љ��`����ǂ��Ƃ��čݒn�y���^�̍��h�^����W�J�����H�L�Ȃ��̂ł������̂ł͂Ȃ��낤���B�ނ�͈�x�Ƃ��ă}���N�X�̃}�̎��������ɂ��Ȃ��������A�}���N�X���č���������}���N�X��`�҂�����قǃ}���N�X��`�I�ŁA���E�Ɋ�����e�����̊ێ��ݒn�y���^�Љ��`�����n�����~�݂��Ă������̂ł͂Ȃ��낤���B�����ɁA���E�̊�ւƉ]������̍��x�o�ϐ��������W������A�C�X�������E�Ƃ��悭�e�����^������Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B �@���Ă݂�A���ێ�{���n�g�h�̐����A���Ɋp�h�����̌��т��������A�p�����ׂ��ʂ��p�����A�V�ݒn�y���^�̃n�g�h�������ċ����Ă������Ƃ������㐭���̃e�[�}�ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B���̂��Ƃ��w�E���Ă������������B���̊ϓ_�Ɉ٘_������A�M�҂͂͂��ł�������ӎv������B���X�Ƌc�_���悤�ł͂Ȃ����B �@�Q�O�O�W�D�P�D�Q�Q���ĕҏW�A�Q�O�P�R�D�O�P�D�Q�V���ĕҏW�@������q |
| �y�n�g�h�ƃ^�J�h�̐����I�Ⴂ���̂P�A�����̐��_�z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�ȉ��A���̌n���̃n�g�h�ƃ^�J�h�̐����I�Ⴂ��Δ䂳���Ă������Ƃɂ���B�n�g�h�ƃ^�J�h�ɂ́A�����̐��_�ɉ����Ď��̂悤�ȑ����ƍ��ق�����B�X�̎���ł͗l�X�ł��낤���炵�āA�n�g�h�̏ꍇ�ɂ͍ݒn�n�Љ��`�h�̓c���p�h�Ƒ啽���F���A�^�J�h�̏ꍇ�ɂ̓l�I�V�I�j�Y���n�^�J�h���]���N�O�Ə���Y��O���ɒu���B�ʔ������邽�߂ɂ�����}�̌�����Βu���Ă����B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�n�g�h�ƃ^�J�h�̐����I�Ⴂ���̂Q�A�����_�z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�n�g�h�ƃ^�J�h�ɂ́A����ɉ����Ď��̂悤�ȑ����ƍ��ق�����B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() (���_�D����)�@
(���_�D����)�@