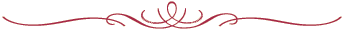
| 議会政治家の申し子としての角栄その3、政治処理能力 |
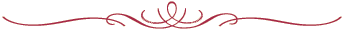
(最新見直し2010.1.4日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
|
角栄は、生粋の党人派政治家であり、大衆的支持基盤を持つ議会政治の落とし子代議士であった。それを証左する事項を以下掲げる。これを知れば、角栄こそ左派政治家の鏡と云うべきだろう。逆に、仮に社共の政治家の実態を見よ、無能さばかりが見えてくるではないか。角栄の政界追放は国際金融資本帝国主義の差し金に相違ないが、これに呼応した日本サヨ運動派は、ひょっとして手前達のそういう無能さと正体暴露から来るジェラシーだったのではなかろうか。 |
| 【3、「勉強せよ、専門知識をもて、議員立法せよ」】 | |
| 角栄の議員立法については「議員立法」に記した。角栄は、実績を踏まえて、「政治家たるるもの、国会で国政に携わる者は、全てのことは無理にしても、一つや二つ、誰にも負けない専門分野を持たなくては、国家国民のための政治家にはなれん!」という考えから、党の各委員会、小委員会、分会の「勉強会」以外に、田中派内にも各分野の勉強会を連日開かせ、一人一人に専門分野の知識を、その道の専門家と丁丁発止で討論ができるように育てていった。これが、後に、田中派が「総合デパート」と云われるようになる下地となった。ちなみに、勉強会の費用を飲食代まで全て派閥事務所が負担した。「勉強会」は、「同じ釜の飯を食った仲間意識」の醸成にも役立つこととなった。 角栄が政策研究に余念が無かったことを裏付ける福田赳夫の角栄評がある。
|
| 【4、「議会討論を重視し、率先した」】 | |
|
角栄の議会に対する態度を物語る当人の国会弁舌がある。1947年、初めて登院した衆議院本会議で「自由討議」(フリートーキング)をテーマにしての演説である。
「自由討議」(フリートーキング)制度は、新憲法が制定された当初、国会法第78条において「各議院は、国政に携わる議院に自由討議の機会を与えるため、少なくとも、二週間に一回その会議を開くことを要する」と定められ開始された。ところが、わずか数回行われただけで、1955年の国会法改正によって実益の無い制度として削除された。このようにして、国会から自由清新な議論が消えていった。 |
|
【5、「官僚に使われるのではなく、使いきろうとした。官僚の使い方がうまかった」】 |
|||
|
角栄は、「官僚に使われるのではなく、使いきろうとした」。次のような弁を残している。
角栄は、官僚の話を聞くのがうまかった。それも、事務次官や局長など上のクラスの人だけではない。必要とあらば、例え一課長とも気軽に会った。官僚は、自分の担当については頭で整理できている。その考えを上手に聞き出し、時には政策などに活かした。その意味で、官僚の使い方がうまかった。
マックスウェーバーの言は次の通り。
|
| 【6、「野党対策国対政治の元祖」にして野党との議論を好んだ】 | |
小林吉弥氏は、「究極の人間洞察力」の中で、角栄の野党との議論好きな様子を次のように伝えている。
これは功罪相半ばすることになったが、角栄は、野党に対して力で押し切るのではなく、「足して2で割る国対政治」を志向した。「佐藤栄作内閣時代から国対の持つウェイトが次第に大きくなり、田中内閣時代には、全ての協議事項が国対での『根回し』を前提とするようになってしまった。そして、お茶を飲みながら、あるいは食事をとりながら妥協を図るということが習慣になり、ここから、国対政治の腐敗が始まる。もちろん、自民党だけでできるわけはなく、相手方あってのことである」(浜田幸一「日本をダメにした9人の政治家」)。結局、野党がだらしないということになるのだが、あろうことかそういう反省に向かうことなく、角栄の国対政治術を非難して事済ませている。 |
| 【7、「責任政治を目指した」】 | ||
|
| 【8、「政策論争を好んだ」】 |
| 若手議員を掴まえては政策論争したと伝えられている。政策がおかしければ、おかしいとはっきりと口にした。発想力の豊かさに感心したと伝えられている。自然と門下生教育となった。 |
| 【9、「後援会を組織し、機関紙を発行し続けた」】 |
| 角栄は、後援会として「越山会」を組織した。最盛期会員10万を擁した。新潟3区の自民党員1万5千人にも拘わらず長岡市に置かれた新潟県本部を頂点として、その下に都市単位の連絡協議会が青年部、婦人部と同列で置かれ、この連絡協議会の下に単位「越山会」が結成されていた。新潟3区内33市町村のすみずみまで網の目を張り、その数330の支部を数えていた。1町平均10の越山会が結成されていたことになる。後援会機関紙「月刊越山」は毎月5万部が国許に送られた。 これを思うのに、角栄の後援会作りとその機能のさせ方は、「代議士と選挙区との関係のあり方としてのモデル例」として注目に値するのではなかろうか。日本左派運動が全く無視していることではあるが、在地型社会主義を地で行く実践ではなかろうか。これを思えば、社共、新左翼の空理空論ぶりのみが浮き彫りになる。れんだいこは、ニセモノと本物の然るべき立ち現れの差であろうと思料する。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)