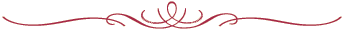
| 田中角栄の文筆能力、話法について |
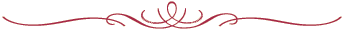
(最新見直し2006.2.19日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、角栄の文筆能力、話法について確認しておくことにする。 2005.9.8日再編集 れんだいこ拝 |
| 【角栄の文章論】 | |||
角栄は、自らの文筆能力について次のように語っている。
1963(昭和38).5月.角栄は、文芸朝日6.1日号に自らペンを取り、次のような文章を載せている。一部を抜粋引用する。(小林吉弥「角栄がゆく」207P、徳間書店、1983.6.30日初版より)
|
| 【早坂秘書の角栄の話法論】 | |
早坂秘書は、角栄の話法の特徴について次のように述べている。
|
| Re::れんだいこのカンテラ時評833 | れんだいこ | 2010/10/24 |
| 【角栄の文章能力評】 れんだいこは、このところ角栄に色気づいている。天理教教祖中山みきと角栄につき知れば知るほど楽しくてしようがない。れんだいこブログに興味のある方は、こたびもお付き合い願いたい。ここで、角栄の文章能力について言及しておく。近視眼的「田中角栄諸悪の元凶観」から一度離れて角栄を遠望した時、元文学青年にして文達者であった素の角栄が見えてくる。これを確認しておく。 角栄は、文章を書くのも得意で能筆家であり且つ自筆文をモットーにしていた。幹事長、蔵相などの激務のさなかでも可能な限り自ら筆をとった。やむを得ず代筆させるときでも、でき上がった原稿に納得のいくまで赤筆を入れた。簡単なインタビューでも、口述がそのまま原稿になるよう配慮していた。文体は簡潔な散文調であった。所信表明演説の草稿も角栄自身が書きあげ演説している。こういう首相はなかなか出てこない。 角栄の文才は既に、1933(昭和8)年、15歳の時に認められている。二田尋常高等小学校高等科卒業時、卒業生総代として答辞を読んでいる。この時凝りに凝った文案を作成し、立派に読み上げている。「残雪はなお軒下にうずたかく、いまだ冬の名残りも去りがたけれど、わが二田の里にも、更生の春が訪れようとしています」云々。 卒業後暫くの間、自宅の独学で中学講義緑を学んだり、漢詩を暗誦したり、書道に熱中している。余程進学したかったことと将来の進路を掴もうとして充電中であったものと推測される。「明治大正文学全集」、大衆雑誌「キング」、姉が読んでいた「婦女界」などを耽読している。新潮社の雑誌「日の出」に懸賞小説を投稿し、「三十年一日の如し」で選外佳作5円貰っている。「私の最初の収入は原稿料なのですよ。子供の頃、文士にあこがれましてね。モノを書くということでは、みなさんの先輩かな」と回顧している。 1966(昭和41)年、日経の「私の履歴書」に登場した角栄は、他の多くの者がゴーストライターを用意しているのに自ら書き上げている。「最初の5回分は口述筆記の原稿に手を入れたものを載せたが、読んで自分でも気に入らなかったのだろう、6回目からは自ら筆をとって書いた。本人の書いたものは俄然面白くて読みやすい。かなりノッて書いたようで、予定の30回では終わらず5回分を追加している」とある。 これを読んだ「近代批評の神様」と云われて名高い文芸評論家の小林秀雄が日経新聞編集局に次のような葉書を寄越した。「貴紙連載中の田中角栄氏による『私の履歴書』を愛読しております。文章は達意平明、内容また読む者の胸を打つ。筆者によろしくお伝えください」。 この葉書が編集局長から政治部を通して早坂茂三秘書の手に渡ったと早坂著「オヤジとわたし」に記されている。これにつき、れんだいこは従前、川端康成が角栄文を高く評価していたと書いていたが正しくは小林秀雄のようである。ここに訂正させていただく。川端康成の評があるのかどうかは分からない。 当時大学生の長女真紀子がそれをききつけて、「パパ、小林秀雄がパパの文章をほめてたそうよ」と云いに行ったら、角栄は「そうかい、へえー。・・・で、小林秀雄って誰だい?」と聞き返したという逸話が残っている。「オヤジとわたし」では、その遣り取りは早坂秘書と角栄で為されたものであり、それを知らされた真紀子が翌日に早坂秘書に電話を入れ、「あれ、本当に小林秀雄さん?」との確認が有った云々と記されている。 それにしても、田中角栄と小林秀雄の「一瞬の遭遇」が面白い。こう評している小林一喜著「戦後精神における近代と超近代」(文芸社、2000.5月初版 )にネット検索で出くわした。(アドレスが長い為割愛する)早速取り寄せ読むことにした。 ちなみに、れんだいこの知る小林秀雄の凄さは次のところにある。1929(昭和4)年、当時「中央公論」と並んで最も権威ある総合雑誌であった「改造」の懸賞論文に一等当選の栄誉を得たのは後に共産党指導者になる宮本顕治の「敗北の文学」で、次点が小林秀雄の「様々なる意匠」であった。当時の審査員がそう評したと云うことであって作品の優劣ではない。共にプロレタリア文学を論じていた。 宮本顕治の「敗北の文学」はマルクス主義の通俗的教条を振り回して芥川文学を評していた。次のような観点を披歴している。概要「ブルジョア・リアリズムとしての自然主義文学よりプロレタリア.リアリズムの勝利へ――この道程は、近代文学の必然的方向であり、より重大なことは、彼らの属した非プロレタリア階級の認識そのものが、既に主観客観の同一性を持ち得なかったのである」、概要「主観的認識が、同時に客観的認識足り得る歴史的必然に立ち得る文学的見地、自己の階級的主観が同時に世界の客観的認識としての妥当性を持つ者は、プロレタリア階級のみである」、概要「現代文学の先端が、プロレタリア文学の旗によって守られているということを認定することが肝要である」、「芸術が形象的思想である以上、プロレタリア芸術家は、何よりも骨の髄まで、細胞の中まで、プロレタリア的な感情によって貫かれていなければならないのである」、「芥川氏の場合、究極、労働階級を知らず、観念論の無力を自覚し得なかった」、「『社会主義の武器を持ってブルジョアジーへの挑戦を試みなかった彼の限界性。根本的批判』がなさればならない、という『批評の党派性』を身につけねばならない」、「芥川文学に『一つの彷徨時代。社会的進歩性』を認めることができても、ブルジョワ文学が、他の何物にも煩わされることなく、ひたすらに芸術的完成を辿った過程は、芥川竜之介の自殺を一転機とするブルジョワ文学の敗惨の頁によっ て、終結を告げたと見ていい」。 これに対し、小林秀雄は既にかの時点でマルクス主義の通俗的教条に批判的な論評を加えている。「私には文芸評論家が様々な思想の制度をもって武装している ことをとやかくいう権利はない。ただ鎧というものは安全では有ろうが、随分重たいものだろうと思うばかりだ」、「マルクス主義 文学、――恐らく今日の批評壇に最も活躍するこの意匠の構造は、それが政策論的意匠であるが為に、他の様々な芸術論的意匠に較べて、一番単純なものに見える」、「私は、ブルジョワ文学理論のいかなるものかも、又プロレタリア文学理論のいかなるものかも知らない。かような怪物の面貌を明らかにする様な能力は人間に欠けていても一向差し支えないものと信じている」、「私は、何物かを求めようとしてこれらの意匠を軽蔑しようとしたのでは決してない。ただ一つの意匠をあまり信用し過ぎない為に、むしろあらゆる意匠を信用しようと努めたに過ぎない」。 当時に於いては宮本顕治の論の方が鋭いように思えたのであろうが、あれから80年を経た今日では小林秀雄の批評の方こそ 「時代に媚びず阿ねず」で文芸論的な眼が確かなのではなかろうか。未だにそう思わない者も居るだろうから、「マルクス主義の通俗的教条」に対する態度の論であるとしておこう。 そういう真贋を見抜く眼を持つ当代一の文芸評論家である小林秀雄が同じく当代一の政治家であった田中角栄の文を称賛した意味は大きい。小林秀雄の孤高の精神からして、今をときめく幹事長故の角栄文激賞ではない。素の角栄文を高く評価して、その評価から幹事長の地位に上り詰め、いずれ首相にまでなろうとしている政治家・角栄を首肯したのに相違ない。小林一喜氏は、「確と相通じた両者の精神の交点」と評し絶賛している。「類は友を呼び、あい親しむ」の法理の絶好例ではなかろうか。このことを教えてくれた「戦後精神における近代と超近代」を読まずにおれるか。 その角栄の書は筋が良かったらしい。端正で勢いのある字を書き、書道家が褒めたと云う。政治家に色紙や額の題字書きはつきものだ。角栄は自筆をモットーにしており、「こんなに書かされたら死ぬ」と文句をいいながらも、山積みの色紙に一切手抜きせず、真剣に筆を執った。その先に支持者のそれぞれの顔を見ていたのだろう。今こういう労を取る政治家が果たして何人いるだろうか。 「田中角栄の文筆能力、話法について」 (ttp://www.marino.ne.jp/~rendaico/kakuei/sisosiseico/bunphitunoryokuco.htm) 2010.10.24日 れんだいこ拝 |
||
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)