| 三 申し立ての理由
検察庁法第4条は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」と規定する。本規定は、検察官は不偏不党、公平無私の立場から真実を究明し、事案の真相を解明することを職務とすると解されている。
そして、検察官は職務の遂行に関して「その意思に反して、その官を失い、職務を停止され、又は俸給を減額されることはない。但し、懲戒処分による場合は、この限りでない」(同法第25条)と身分が保障され、被疑者・関係者に対する捜索、証拠の差し押さえ、逮捕、勾留、接見禁止処分、起訴などが認められている(刑事訴訟法第47条ほか)。これらは検察官が公平な捜査を行ない、真相を解明することを期待して定められたものである。
しかし、障害者団体「凛の会」の郵便不正に関連して昨年逮捕された厚生労働省の村木厚子元局長の事件(以下「村木事件」とする)においては、検察は「虚構のストーリー」を作り上げて特権を濫用したばかりか、その虚構が明らかになって村木元局長の無罪が確定したにもかかわらず、検察官として責任を取ろうとしていない。審査申立人は、貴会の手続きにより、事件に関与した検察官に対する厳正な処分を求める。
四 村木事件の詳細
村木事件における逮捕及び起訴に関係した検察内部の動きは以下のとおりと承知している。
① 事前協議と処分協議の流れ
検察の内規では、高級官僚を逮捕、起訴する場合には事前に上級庁と協議することになっている。事前協議とは、村木元局長を逮捕するか否かの検察内部の協議であり、処分協議とは、元局長を起訴するかどうかの検察内部の協議のことである。
<大 阪 地 検> <大 阪 高 検> <最 高 検>
小林敬検事正 ① 中尾巧検事長 ② 樋渡利秋検事総長
玉井英章次席検事 → 太田茂次席検事 → 伊藤鉄男次席検事
大坪弘道特捜部長 齊藤雄彦刑事部長 鈴木和宏刑事部長
前田恒彦主任検事 ← 他刑事部検事全員 ← 他刑事部検事
他特捜部検事 ④ 前田恒彦主任検事 ③
大坪弘道特捜部長
上のとおり大阪地検・小林検事正室において、玉井次席検事、大坪特捜部長、前田主任検事及び本件捜査に関与した他の特捜検事らが出席し、事前協議を行なう。初めに前田主任検事が事前協議資料(過去の捜査資料と証拠物)に基づき、それまでの捜査の経過を説明する。村木を逮捕できるか否か、あらゆる角度から協議され、この協議では「逮捕すべし」との結論に達する。
この結論を踏まえ、小林検事正の名で大阪高検の中尾検事長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して事前協議資料を送付する(図①)。これを受けて大阪高検では、齊藤刑事部長室に刑事部の全検事と地検の前田主任検事、大坪特捜部長が集まり、地検と同様の協議を行なう。まず前田主任検事が事前協議資料を持参して説明し、地検と同様にあらゆる角度から協議がなされる。やはり同様に「逮捕すべし」との結論に達する。協議の出席者全員がそのまま中尾検事長室に行き、太田次席検事も出席して同様の事前協議をする。同じく「逮捕すべし」との結論に達し、それを踏まえて中尾検事長名で樋渡総長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して事前協議資料を送付する(図②)。
最高検では、樋渡総長室に伊藤次席検事、鈴木刑事部長、その他刑事部の検事が出席し、送付された事前協議資料などに基づいて処分協議を行なう。その結果、「逮捕すべし」との意見に達し、それを踏まえて樋渡総長名で中尾検事長宛てに「逮捕すべし」との意見を付して捜査指揮がなされる(図③)。これを受けた中尾検事長が同人名で小林検事正宛てに「逮捕すべし」との捜査指揮がなされ(図④)、これを受けた大阪地検では前田主任検事が逮捕状請求書を作成し、同人名で大阪地裁に請求して発布され、村木元局長は逮捕されたのである。
このように、「検察官一体の原則」により、村木元局長の逮捕に当たっては大阪地検、大阪高検、最高検がそれぞれ事前協議を行ない、最終的には樋渡総長から逮捕の指示がなされたのである。被審査検察官は、いずれもこの事前協議及び処分協議に関与した中心的検察官である。これだけの協議を重ねながら、捜査はきわめてずさんであった。無辜の人間を長期拘束した責任は重い。貴会により処分をなされなければならない。
処分に当たっては、その軽重が問題となる。「検察官一体の原則」を踏まえれば、検事総長が最も重い処分を受けるべきだと断じざるを得ない。なお、大阪地検で捜査を統括したのは、大坪特捜部長、大阪高検で捜査を統括したのは太田次席検事であるので、その両名の責任は重い。一部メディアは、逮捕起訴した大阪地検の小林検事正以下の検察官の厳正処分について報じていたが、それは「検察官一体の原則」を正しく認識していない見解である。主任検事が失態を演じても、主任検事のみを処分することは「検察官一体の原則」からできないシステムになっている。それゆえに、過去の冤罪事件において検察官の責任が問われ、処分されたことは一度もない。
② 虚偽の証明書作成の流れ
村木元局長らが虚偽の証明書を作成したとされる検察の虚構のストーリーは、以下のとおりである。
凛の会元会員河野克史(一審有罪、被告控訴) ①石井一民主党副代表に対して口利きの指示を依頼
↓①
石井副代表元私設秘書で凛の会創設者の倉沢邦夫被告(一審一部無罪、検察控訴) ②倉沢邦夫元秘書が石井副代表に口利きを依頼
↓②
石井副代表 ③石井議員が架空の証明書発行を電話で指示
↓③
厚生労働省・塩田幸雄元部長 ④塩田元部長、村木元局長に証明書発行を指示
↓④↑⑦
村木厚子元局長(一審無罪確定) ⑤村木元局長、上村元係長に証明書発行を指示。「ちょっと大変な案件だけどよろしくお願いします」
↓⑤↑⑥
上村勉元係長(公判中) ⑥上村元係長が虚偽の証明書を村木元局長に手渡し、⑦村木元局長が塩田元部長に手渡す
本件は、石井副代表による「議員案件」の事案であることを前提として捜査が進められた。かりに議員案件でなければ、検察の上のストーリーは完全に崩壊する。これは、倉沢元秘書から押収した手帳に「04年2月25日に石井副代表と会っていた」かのようなメモがあったからである。ところが、前田主任検事らは事前協議までにこのメモの裏付けを取っていなかった。事前協議においても、議員案件であるのか否かの裏付け捜査の指揮がなされることはなく、結局、村木元局長逮捕までに裏付けは取られていない。
議員案件を前提として口利きの依頼や虚偽の証明書発行などの流れが作られ、保釈や逮捕をちらつかせながら倉沢元秘書、塩田元本部長、上村元係長に虚偽の供述をさせ、内容虚偽の検面調書が作成された。特に被審査申立人である國井広樹特捜部検事は、上村元係長の取り調べを担当し、保釈させないと脅迫して、村木元局長から指示があったと内容虚偽の検面調書を作成した。これは、虚偽公文書作成、同行使罪に該当する犯罪である。その大前提である議員案件の裏付けという重大な捜査の基本がなされていなかった。なぜ村木元局長の逮捕までに裏付け捜査をしなかったのかきわめて不可解である。いずれにしても検察側の重大な過失である。この点だけでも、事前協議に関与した検察官は懲戒免職処分に値する。村木元局長逮捕の前に石井副代表の議員案件でないことが明らかになっておれば、村木元局長の逮捕はなかったのだ。
後に明らかになったことだが、倉沢元秘書と石井副代表が会って口利きについて話したとされる「04年2月25日」は、石井副代表は千葉県内でゴルフをしており、倉沢元秘書と会うことは物理的に不可能であった。昨年9月10日には弁護人と検察官が出席して大阪地裁で公判準備手続きが行なわれているが、その翌日である11日頃に前田主任検事が石井副代表の事情聴取を行なっている。この際、石井議員は自ら手帳を示したが、前田主任検事はぺらぺらとめくってみただけで、それ以上の事情聴取はしなかった。前田主任検事は当日の石井副代表の行動を確認し、ゴルフの件など詳しく事情聴取して検面調書を作成すべきであった。これが検察官としての本来の仕事である。だが、前田主任検事は、この段階で石井副代表のアリバイが成立してしまうと議員案件でないことが確定し、上記のストーリーが崩壊するため、あえて検面調書を作成しなかったと思われる。
前田主任検事は、その結果を大坪特捜部張、玉井次席検事、小林検事正に報告したものとみられ、小林検事正は上級庁である大阪高検に、大阪高検は最高検にそれぞれ報告したものと思われる。事前協議と処分協議に関与した検察官は、昨年9月11日頃に本件が議員案件ではないことを認識していたものと思われる。議員案件でなければ検察のストーリーは雪崩式に崩壊することはその段階で認識できたのである。だが、検察内部でこの事実には緘口令が敷かれたのか、メディアに漏れることもなかった。まさに「検察一体」となって証拠隠しをしたのである。
そして、検察は本年1月27日の村木元局長の初公判においても虚構のストーリーに沿った冒頭陳述を行なっている。前年9月の事情聴取で議員案件でないことは明らかになっていたにも関わらず、その証拠を隠し、自作のストーリーを守るべく暴走を続けたのである。なお、3月4日の公判に出廷した石井副代表は、その証言は手帳で確認しながら「04年2月25日には千葉県内のゴルフ場にいた」旨を証言、ゴルフ場でのプレイの記録やスコアなどで裏付けられた。以上のように、石井副代表による議員案件でないことは明らかだったにもかかわらず、村木元局長逮捕の前に適正な捜査をしなかった検察の責任はきわめて重いと言わざるを得ない。
③ 改竄された証拠
事前協議において、上村元係長から押収したフロッピーディスク(FD)が証拠として十分に検討されなかった点についても述べたい。このFDは裁判では証拠提出されていないが、重要な問題を含んでいた。偽造された証明書の原稿は、このFDに入力されていたが、データの最終更新日時が改竄されていたことが本年9月21日に明らかになったのである。
FDは上村元係長の自宅から押収されたもので、データの最終的な更新日時は昨年5月26日の押収時点では「04年6月1日午前1時20分」となっていたが、約1ヶ月半後の7月13日に「04年6月8日午後9時10分56秒」と改竄されていた。この3日後の16日にディスクは元係長に返却されている。 データの更新日時が6月8日だった場合には、村木元局長が虚偽の証明書の作成を指示したという「虚構のストーリー」に合致する。前田主任検事はストーリーに沿った改竄を行なったのである。
前田主任検事は、改竄が明らかになった9月21日のうちに逮捕されるという異例の事態になった。これは前田主任検事一人に責任を押し付けようとする検察の組織的な隠蔽工作であり、断じて看過することはできない。前田主任検事については証拠隠滅(刑法第104条)で本年9月22日付け大林宏検事総長宛、三井環名義で刑事告発した。
五 検察による虚構のストーリーの完全崩壊
① 厚労省・塩田幸雄元本部長らの証人尋問
本年2月8日に行われた証人尋問で、塩田元本部長は議員案件であることとニセ証明書発行を村木元局長に指示したことを否定し、検察の捜査は「壮大な虚構ではないかと思った」とまで証言した。その後は上村元係長の証人尋問も行なわれているが、元係長は単独でニセの証明書を作成したことを証言、村木元局長の指示など検察のストーリーを完全否定した。さらに取り調べ中につけていた「被疑者ノート」を提出、裁判所はこれを重視した。このノートには虚偽の証言を引き出そうと保釈をちらつかせる検事の言葉などが克明に記載され、また村木元局長の指示がなかったことも記載されていた。
さらに取り調べを担当した検察官6名の証人尋問も実施された。すでに検察のストーリーが崩壊したにもかかわらず、検察官はあくまでもストーリーを維持するために検面調書の特信性の証言をさせた。驚くべきことに、検察官らは6名とも取り調べの際に作成するメモを廃棄したとウソの証言している。検察官の取り調べのメモについては、最高裁が判例で「捜査上の公文書」と認定し、最高検も「適正な管理」を全国の高検、地検に通達している。本件メモには村木元局長に有利なことも書かれていたはずだが、こうしたメモは判決が確定するまで保管するのが検察官の義務である。
この検察官6名については偽証罪(同第169条)が成立すると思われるので、本年9月22日付けで大林宏検事総長宛てに三井環名義で刑事告発をした。なお、本年5月26日、大阪地裁は上村元係長の供述調書15通の証拠採用を却下した。その理由は上村元係長の「被疑者ノート」の内容と同様であった。裁判所は検察側が虚偽の供述をさせていたことを認定したのだ。これにより村木元局長の無罪が事実上確定した。
② 論告求刑
既にメディアも既に村木元局長の事実上無罪を報じていたにもかかわらず、検察は6月3日の論告求刑公判で懲役1年6月を求刑した。上村元係長の検面調書は証拠採用されなかったのであるから、村木元局長の共謀を認定する証拠は存在しない。本来であれば、検察官として取るべき対応は論告求刑を放棄するか、無罪の論告を行なうかのいずれかしかない。ところが、検察側は最後まで暴走をやめなかったのである。なお、村木元局長の公判経過については、公判の都度、小林検事正名義で中尾検事長、樋渡検事総長、千葉法務大臣宛てに書面で公判における立証内容、反証、次回期日予定等が報告されている。これを三長官報告という。 したがって、事前協議及び処分協議に関与した検察官は、大阪地裁の公判経過については充分認識していた。 然るに、上級庁からの公判対策等についてのチェック機能はまったく果たされていない。特に、6名の検察官がメモを廃棄したとの証言についても、その前後に何らの対応もされていない。
③ 無罪判決
9月10日、当然ながら大阪地裁は村木元局長に無罪判決を言い渡した。同月21日に検察は控訴を断念、めずらしくメディアも検察の捜査批判を展開した。「暴走した特捜部」「裏付け捜査不足」「幹部のチェック不全」「検察の構図を全否定」「特捜捜査の見直し迫る」「密室での取り調べに批判」「特捜捜査による冤罪」「検察捜査の徹底検証を」「完敗 検察に衝撃」「構図優先 裏付けずさん」などと大々的に報じたのである。だが、検察が控訴を断念したのは「勇気ある決断」ではない。虚構のストーリーはあくまで虚構でしかなく、控訴審で勝てる見込みがないからである。村木元局長は164日間も勾留され、4回目の保釈請求でようやく保釈された。既にその頃は石井副代表の議員案件であることも崩れ去っていたのだが、検察は保釈に反対したのである。このような不正義があろうか。
村木元局長は逮捕された昨年6月14日から今回の判決まで一年半近くも裁判闘争を続けざるを得なかった。精神的、肉体的苦痛に加えて経済的な負担も大きかっただろう。元局長とその周囲の人間は検察の虚構とメンツに振り回され続けたのである。 この事件は、検察の前代未聞の不祥事といっても過言ではなく、検察全体の信用を失墜させた事件である、と評することができるであろう。関与した検察官については、懲戒免職以外にないと思料される。
貴会の機能と存在については、十分機能していないとの批判もあるが、今回は法務大臣も積極的に関与した検察官の処分を検討すべきではないか。 勇断をもって厳正な処分勧告を行ない、ぜひ存在感を示してほしい。また、柳田稔法務大臣も関与した検察官の処分を検討すべきではなかったか。
六 まとめ
被疑者や関係者の虚偽の供述で捏造された典型的な冤罪事件であることは一審判決で明らかとなった。 本件捜査についての検察官の重大な落ち度は、①議員案件であるか否かを裏付け捜査しなかった、②FDを十分検討しなかった、③石井副代表の事情聴取で議員案件でないことは明らかであったのにその証拠を隠蔽した、④公判において6名の取り調べ担当検事が取り調べメモを廃棄したと証言したこと、⑤虚構のストーリーであることが明らかとなった後もなりふりかまわず公判が遂行されたこと、⑥論告求刑公判でも本来であれば論告を放棄するか無罪論告すべきであるのに、懲役刑を求刑したこと、などが事前協議と処分協議に関与した全検察官全員の重大な落ち度として認定されなければならない。
七 改革案
現行の制度を見直し、検察審査会と同様の民意を反映する制度にすべきである。検察審査会は、検察官の処分に対してそれが適正であるか否かを審査するのみであって、本件村木元局長の事案については審査の対象外である。検察官による不当逮捕、勾留、起訴などについても審査できる制度を作るべきである。と言うのは、最近の検察の暴走が批判されているが、その暴走をチェックする制度が日本には存在しないからである。選挙権を有する国民が委員となって、逮捕起訴の不当、冤罪事件を審査する、菅直人政権は政治主導で法案の成立を期することを切に望みたい。以上。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
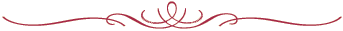
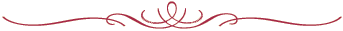
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)