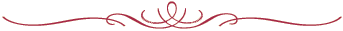
| ロッキード事件の伏線考 |
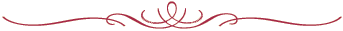
更新日/2018(平成30).6.19日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| れんだいこのロッキード事件顕彰で見えてきたことをメッセージしておく。あれから30数年、見えてきたこととして、この事件により致命傷を負った者と丸儲けした者とを判然とさせることが必要ではなかろうか。深手を負った者は角栄と児玉である。丸儲けした者は中曽根である。これは偶然か、これを問いながら検証していくのがロッキード事件の早分かりであろう。 確かにこの事件を通じて「戦後なるもの」が清算された。しかし、清算後に遣ってきたのは、恐ろしいほどの売国政治である。中曽根から小泉まで30年かけてこの国は脳粗鬆(そしょう)になってしまった。 2005.7.15日 れんだいこ拝 |
| 【ロッキード事件の政治的背景】 |
| ロッキード事件の背景はいろいろ考えられる。ここでは、その1・アメリカー国際金融資本の角栄観、その2・資源外交、その3・ロッキード・ダグラス・ボーイング三社の航空機売り込み競争、その4・ロッキード社の秘密対外工作、その5・サンクレメンテ会談、その6、その6・日英首脳会談時のヒース首相の売り込み、その7、売り込み競争の結果の6観点から考察しておく。 |
| 【その1・サンクレメンテ会談】 |
|
1972(昭和47).1月、サンクレメンテ会談がこういう背景で行われている。表向きのメインテーマは、米中の頭越し外交の追認、日米繊維交渉の結果に対する確認、円の通貨切り上げの確認と、最後に沖縄返還の最終的合意及び詰めの作業の打ち合わせであった。 |
| 【その2・アメリカ当局の角栄観】 |
| 1972(昭和47)年、田中首相は就任と同時に日本列島改造論・日中国交復交に「決断と実行」で着手し、従来のアメリカ一辺倒政策とは違った自主的な新しい政策を強力に打ち出していった。今日、アメリカがこの角栄政治に恐怖を抱いた様子が明かされている。ホワイト・ハウス当局は、CIAに命じて角栄の政策と思想、そのブレーンに至るまで再チェックさせ、首相としての動向の調査、分析を徹底させている。 今日公開された国務省レポートは、「何をやりだすか分からん男。日本のためには優れた政治家であっても、それがアメリカの利益になるかどうかは未知数である」として、神経を尖らせていた様子を明らかにしている。概略は「アメリカ特務機関の角栄レポート」に記した。 |
| 【その3・資源外交】 |
|
ロッキード事件の考察に当たっては、アメリカの保守本流(その奥の院としての国際金融資本、その表舞台としての米英ユ同盟)が、この時日本(の政治家)に対してどんな謀略をしかけたか、
この観点からも追跡せねば真実像が見えてこない。 |
| 【その4・ロッキード・ダグラス・ボーイング三社の航空機売り込み競争】 | |
|
7月下旬、日米通商箱根会談が開かれた。この席で、日本側は、航空機や濃縮ウラン、農産物などの緊急輸入を呈示していた。この政府間の交渉を受けて、ロッキードをはじめ、グラマン、ボーイングといったアメリカの民間航空機製造会社が、こぞって日本に売り込みをかけてきた。 8.31日、ハワイのクイリマホテルで日米首脳会談(田中.ニクソン会談)が開かれた。安全保障、経済摩擦等様々な懸案が話し合われているが、真意は日中交渉の米側への報告と了承を得ることにあったものと思われる。
この時、竹下副幹事長、金丸国会対策委員長、亀岡経理局長等20数人が同行している。真偽不明なるも、その中の大物議員の一人が「ニクソンがロッキード、ロッキードと言うので困ったよ」とオフレコで語っているとのことである。 こうした事情から、1972(昭和47)年は、ロッキード・ダグラス・ボーイング三社の航空機売り込み競争が過熱していた年であった。他方、国家向け軍用機の売り込みも稼動していた。この年、次期対潜哨戒機(PXL)を廻って、「自力国産か輸入調達か」かの極めて高度な政治判断が要求されていた。10.9日、国防会議が四次防大綱を決定し、次期対潜哨戒機(PXL)の国産化を白紙還元している。10.11日、田中首相はこの決定を受け、PXLを「国産から輸入」に重点を置く方針転換を表明している。この決定の背後にあった動きまでは分からない。ロッキード・ダグラス・ボーイング三社の売り込み競争に拍車がかかったことは容易に想像できる。 |
| 【その5・ロッキード社の秘密対外工作】 | |
|
この時期、日本の航空旅客会社全日空は機種選定の年に当たっており、22機を購入しようとしていた。ロッキード・ダグラス・ボーイング三社がこの大型商戦に色めきたち、売り込みの為に秘密代理人、商社、政府高官にも触手を伸ばした事は十分考えられる。ロッキード社は、東京事務所代表クラッター氏をしてその任にあたらせた。 この頃のロッキード社の経営状態を知っておく必要がある。橋本登美三郎運輸大臣がエアバス導入延期を発言した時期、その直前にはトライスターのエンジンを製造していた英国ロールスロイス社が倒産、国家管理に移されている。このためロッキード社は6500人の従業員を解雇、ニクソン大統領に緊急特別融資を直訴している。
こうした流れが全日空の機種選定作業の一旦中止工作と並行しつつ進んでいた。つまり、ロッキード社の商戦勝ち抜きのお膳立てが日米合作で進められていたという背景が垣間見られる。 |
| 【ロッキード社、全日空、丸紅考】 | ||||
ロッキード社について、「荒木睦彦氏のアラキラボ<ロッキード事件「田中支配」とは何であったのか?> 」の「(3)ロッキード事件の役者たち」が次のように記述している。これを転載しておく。
|
| 【その6・日英首脳会談時のヒース首相の売り込み】 | ||||||||||||||
| 9月、東京で、2つ衛首脳会談が開かれた際に、ヒース英国首相が、田中首相に対し、概要「世界一騒音が小さい英国ロールス・ロイス社製のジェットエンジンを搭載した航空機を購入することで、日本は、英国と米国という二人の友人に手助けできる」と協調し、米国ロッキード社の新型機トライスターの購入を働き掛けた(同機は、英国ロールス・ロイス社製ジェットエンジンを搭載していた)。田中首相が、「(機種に就いては)検討中」とだけ答えた。 2006.7.20日付け読売新聞が、「ロッキード事件、英国首相、購入働きかけ 機密文書 72年の首脳会談で」の見出しで、次のように報じている。
|
||||||||||||||
| 【その7・売り込み競争の結果】 | |
|
1972(昭和47).10.31日、全日空がトライスター機の採用を発表している。11.2日、全日空は、ロッキード社に対し、トライスター21機を購入するというレター・オブ・インテント(注文指示書)を出している。1機50億円で、全機で1050億円だった。
こうして、ニクソンとロッキード社の関係は封印され、何ら訴追を受けない身分の安全が保証された。これがアメリカ流の政治決着のさせ方である。片や、我が日本ではどのようなシナリオが進行して行く事になったか、これが以下の動きである。 |
| 【「文芸春秋11月号」と「外人記者クラブで記者会見」のワナ】 |
| 田中政権は、「文芸春秋11月号」と「外人記者クラブで記者会見」で足下を激震された。これについては「在任中の流れ2」に記す。 |
|
|
| この問題の重要性は次のことにある。この二事件によって田中政権が瓦解されたのではない。多くの評論はそのように見立てているが皮相的過ぎよう。れんだいこは、、この二事件が田中政権瓦解策として用意周到に仕掛けられ、田中政権はこの仕掛けに乗せられ政権禅譲に向かったと解している。政権禅譲後も隠然と政治力を持ち続ける田中角栄に対して、最後の止めとしてロッキード事件が更に仕掛けられたと見立てる。こう捉えないと、歴史の真相が見えてこない。 2008.12.27日 れんだいこ拝 |
| 【ロッキード社史】 |
| ロッキード社の社史は次の通り。 1912年、アイルランド系アメリカ人のアラン・ロッキードとマルコム・ロッキード兄弟によって民間飛行機製造会社として設立された。その後、同社の設計者ジャック・ノースロップが独立すると、アラン・ロッキードは自社を売却した。1932年、倒産。投資家に買収され社名は存続した。第二次大戦中、軍用機の製造で大躍進した。戦闘機では、山本五十六搭乗の陸攻機を撃墜したP−38ライトニングを始め、ジェット戦闘機の先駆けと群雄割拠していた。いわれるF−80哨戒機のハドソンなどを開発、米軍に採用された。1970年代、世界の軍事産業の過半を占有している米国では、ボーイング、ノースロップ、グラマン、ロッキードが群雄割拠していた。(真山仁「ロッキード第3回」、週間文春2018.5.24日号)参照 |
| この時代、ジェット化の波に乗り遅れてしまい、民間機市場ではボーイングとマクドネル・ダグラス(MD)から大きく離されていた。ボーイングは広島・長崎へ原子爆弾を投下したB-29を製造した会社。ボーイングとMDはかつてライバル関係にあったが、1996年、MDはボーイングに買収される。ロッキードはその後イスラエルとの関係を深め、主にイスラエル軍の戦闘機を製造している(Lockheed Martin Israel Ltd) 。ボーイングはロックフェラーがコントロールしている。ロッキードはロックフェラーに潰され、民間旅客機市場に入り込む事ができなかった。ロッキード事件によってボーイングのライバルはマクドネル・ダグラスのみとなり、そのマクドネル・ダグラスもボーイングに買収され、ロッキードはイスラエルに乗っ取られ、イスラエル軍のお抱え軍事企業となっていった。ロックフェラーはもちろんイスラエル建国の大きな立役者。1930年代に作られたパレスチナ考古学博物館(西エルサレム)が、今はロックフェラー博物館という名で呼ばれている。 |
| 【ロッキード事件勃発直前の動き】 |
| ロッキード事件発生の直前の動きを、その1・フォード政権下の動き、その2・角栄の動きの2観点から見ておくことにする。 |
| 【フォード政権下でのロッキード社告発の動き】 | |
| 1975(昭和50).8.25日、ロッキード社の疑惑が追求されている。アメリカ上院の銀行・住宅・都市問題委員会(プロクシマイヤー委員長)公聴会で、ロッキード社のホートン会長が喚問され、3時間以上に亘って同社の賄賂商法が追求された。この時、海外での政治献金が2200万ドルにのぼることが明らかにされている。続いて、SEC(米国証券取引委員会)が調査に乗り出していくことになる。 当時フォード政権下の国務長官は引き続きキッシンジャーであり、1975.11.28日、司法長官・エドワード・レビに次のような書簡を送っている。
この書簡は、12.12日、ワシントンの連邦地裁に提出され、判事は公表禁止の保護命令を出した。 |
|
| この「キッシンジャー書簡」をどう見るべきか。字面しか追えない自称インテリ達は、キッシンジャーがあたかも「特定の外国高官の氏名、国籍を第三者に開示」を抑制していたかのように受け取るのだろう。トリッキーに見ることのできるれんだいこはむしろ、キッシンジャーが「特定の高官漏洩」に着手し始めたことを窺う。事実、キッシンジャーの抑制は何の功も無く、チャーチル委員会にロッキード社の秘密資料が渡り、この保護命令は無意味となる。キッシンジャー辺りになるとこれぐらいの芸当は朝飯前だろうに。 2005.1.11日 れんだいこ拝 |
|
| 10.23日、社会党の楢崎弥之助氏が、衆議院予算委員会で、アメリカ上院の銀行・住宅・都市問題委員会(プロクシマイヤー委員長)の動きを踏まえ、政府を追及し、関係資料の提出を要求した。しかし、マスコミ始め無視され、殆ど報道されなかった。 |
| 【三木首相の予言】 | |
| 1975(昭和50).12.27日、第77回通常国会が召集され、会期は翌年の5.24日までの150日間に決まった。三木内閣は、昭和51年度総予算を成立させることを最大の課題としていた。 12.29日、三木首相は、首相官邸の小ホールでの記者団と納会の席上、次のように述べた。
|
| 【角栄の動き】 |
|
76年の元旦、目白の田中邸宅に700名の年賀客が訪れ、田中はこの時、「三月には資産を公開し、金脈問題について釈明する。そして全国を遊説する。三木はどうにでもなる。福田には絶対に政権を渡さない。大平はオレの後だ」と述べ、復権への意欲を燃やし始めていた、と伝えられている。しかし、正確にはどのような謂いであったのか、やや捻じ曲げられているのではなかろうか、この言葉通りに受け取るには難がある。 |
| 要するに、角栄は、迫りくる危機に対して全く無警戒だったことが分かる。 |
| 1.7日、角栄は、田中派7日会の新年総会で、「一年近い謹慎で、体力も気力も十分で有ります。今年は選挙の年、みんなで頑張ろう」と述べるなど、約30分にわたって熱弁を奮った。「角栄再浮上宣言」と受け止められ、会場は「また春が来るぞ」と沸いた。 |
| 要するに、角栄は、「再浮上宣言」で立ち上がった途端に、出会い頭でロッキード事件に襲われたことになる。 |
| 【春日民社党委員長の「日本共産党委員長リンチ事件」質疑】 |
| 1976(昭和51).1.23日、みき首相の政府演説に続いて衆参両院で代表質問が行われた。この時、春日一幸民社党委員長が「日本共産党委員長リンチ事件」を取り上げた。1.29日より衆院予算委員会で総括質疑が始まる。 |
| 【「スモール・ミキ」のロビイスト活動について】 | |||
現代政治研究会の「田中角栄 その栄光と挫折」は、次のように記している。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)