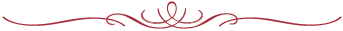
| 履歴その1、新潟時代 |
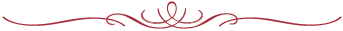
更新日/2018(平成30).6.19日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 1966(昭和41).2月から約1ヶ月にわたり日本経済新聞の連載企画「私の履歴書」35回連載。角栄自身の書き下ろし。小林秀雄は、「文章は達意平明、内容もまた読む者の胸を打つ」と感想を伝えている。 2005.1.14日再編集 れんだいこ拝 |
| 越後は新潟の別名。越後の越はコシとも呼ばれ、日本書紀には「越の国はまつろはぬ民の住むところ」と記されている。大和朝廷時代は、日本海方面に住む蝦夷の別名であり、アイヌと同系列の民族とされている。クシとも呼ばれ、今でも千島アイヌは自らをクシと呼んでいる。コシは高志、古志とも書かれた。 古くは、京の町を荒らしまわり、源頼光に切って取られたという酒天童子の言い伝えがある。西山町の北の端の国上山の中腹に、国上寺(こくじょうじ)という古い寺があり、その経蔵の中に「酒呑(天)童子絵巻」がある。それによれば、酒天童子とは、越後国上山のふもとの砂子塚で生まれ,和納(わのう、現在の西蒲原郡分水町辺り)で育った。美形の童子で、「外道丸」と呼ばれて、国上寺のお稚児になった。長じては都の近くの丹波・大江山に隠れ住み、時に都大路に神出鬼没して平安貴族から金銀財宝を奪うことを好み、姫たちをかどわかした。今日その行状はヌエ化されて伝えられており神秘のヴェールに包まれているが、考えようによれば貧しい民衆に危害を加えてえらず一種の義賊であったかも知れない。 越後は昔から遠流の地であり、親鸞が承元元年(1207)年、日蓮も流されてきている。「頂きに立て!田中角栄とR・ニクソン」は次のように記している。
戦国武将として勇名をはせた上杉謙信、諸国遊行僧として有名な良寛和尚は、角栄の生まれた故郷西山の隣町出雲崎の名主の家に生まれている。「頂きに立て!田中角栄とR・ニクソン」は次のように記している。
戊辰戦争では新鋭ガトリング銃を縦横に用いて官軍を一時は敗走せしめた長岡藩筆頭家老・河井継之助、「国家改造法案」を書いて天皇大権発動によるクーデターによる国家改革を構想し、後の2.26事件を誘引した論客・北一輝、日本国の起死回生のため真珠湾奇襲攻撃を実行した連合艦隊司令長官・山本五十六、「我は荒浜村(柏崎市原発所在地)の一寒民たり」と云い続けた創価学会の創始者牧口常三郎、敗戦の荒廃の中でふてぶてしくも「堕落論」を著した坂口安吾など、多くの革命児を生んでいる。 角栄の生まれた二田村には物部神社が鎮座している。その縁起は、「物部弓削守屋大連は、蘇我馬子大臣の仏教導入に反対して敗れ、物部氏は滅亡した。だが、首(おびと)姓の物部氏の一族は、石上神宮の祭祀に携わって残り、奈良時代には石上朝臣となった」等々とある。 その境内には、「天明義民の碑」と書き込まれた石碑が立っている。天候不順に因る天明の飢饉(1871年から88年)の頃、領主・堀家の苛政に対し、西山町19部落が一丸となって20年間にわたり江戸表への直訴を繰り返した。途中、獄門、死罪、流刑などの極刑に処せられたが諦めず、とうとう幕府の最高裁判所であった評定所の裁断によって勝訴を得る。封建社会にあって史上空前の出来事であった。越後にはこうした空気が潜在している。 椎谷浜のある椎谷は、昔から奥州の白河、安芸の広島と並んで日本三大馬市の一つで、7.1日には市が立っていた。椎谷の馬市は、明治15,6年にも4千頭から6千頭ぐらいの馬が集まったと伝えられている。角栄の父が馬喰(ばくろう)だった背景にはこうした事情がある。 昔から良質の米どころであり、コシヒカリはその代名詞でもある。酒杜氏職人が全国各地の酒蔵に出かぎに出かけた歴史を持つ。越後名物として、笹団子、雪あられ、地酒、鮭の瓶詰め、三条の刃物が有名である。 角栄が生まれた二田村は明治から大正初め頃まで石油ブームで沸き返っていた。西山油田が発掘され、地方から続々と人が集まり、石油油田やぐらが林立していた。角栄が生まれた頃にはブームが去り、不景気風が漂っていた。角栄はこの地に生まれ、「大横綱の羽黒山、浪曲の寿々木米若、演歌の三波春夫」と並ぶ故郷の英雄となる。 |
| 1918(大正7)年、角栄誕生 | ||||
| 5.4 | ◎【誕生】新潟県刈羽郡二田村(ふただむら、後に西山町、現在は柏崎市)大字坂田1540番地で出生。当時の村落は各家が代々の家号を持っており、田中家は「角右エ門」と呼ばれていた。二田村は山あいが海岸近くまで伸びてきている地形で、古くからの交通の要衝地で神社・寺社の多い文化の豊かな地域であった。田中家の家紋は剣片喰(かたばみ)である。 | |||
| ◎【家系】父は角治(次)、母はフメ。母の生家は西山町の真宗大谷派善照寺の檀家。姉2人、後に妹4人の8人兄弟の次男として生まれる。但し、兄の角一が6歳で早世したため実質長男の立場で育った。この地域では長男は「あんにゃ」と呼ばれ大事にされた。 | ||||
| ◎【土地柄】二田村(ふただむら)は日本海側に面し、明治から昭和にかけて日本有数の油田があった(最盛期は日本の産油高の50%)お陰で、住民の暮らしは比較的豊かだった。それなりの田畑を所有している農家が多く、石油汲み上げの人足仕事もあり冬に出稼ぎせずに済んだと云う。 | ||||
| ◎祖母コメに可愛がられる。「祖母コメは庄屋の娘で、村のうわさでは三美人の一人とか云われ、見識が高く田んぼに入らなかった」と伝えられている。祖父捨吉は近郊に知られた宮大工の棟梁で、土木建築一式を請け負っていたようである。二田村の円満寺の住職と縁戚で檀家総代を務めていた。 次のような母フメの伝が残されている。
|
||||
◎父角治は「田んぼが嫌いで百姓仕事をせず」牛馬商をしていた。次第に手広くなり、北海道の月寒(つきさむ)に牧場を開く夢を抱き、オランダから高額のホルスタイン種牛を3頭輸入したが、不運にも病死に見舞われ大失敗となった。以来家産が傾き、角栄の幼少年時代は、借金だらけの極貧下となった。その後養鯉業、競馬業いろいろ手を出すが思うようにならず、母フメの下積みの苦労を増したようである。角栄の担任となった金井先生は、父親の角治について次のように語っている(「君は田中角栄になれるか」)。
|
||||
◎母フメは、一家の大黒柱として5反7畝の田んぼを耕し、7人の子供を育てた。
金井先生は、母親のフメについて次のように語っている(「君は田中角栄になれるか」)。
|
||||
| 角栄の祖父捨吉は、宮大工の棟梁であったと云う。れんだいこは、これを格別注視する必要があると思い始めた。角栄は、隔世遺伝で祖父の頭脳を引いているのではなかろうか。宮大工は、世界に誇る日本建築の大工の棟領である。且つ、角栄が生まれ過ごした二田村は古くからの交通の要衝地で神社・寺社の多い文化の豊かな地域であった。これは何を意味しているか。 れんだいこはその後、日本古代史を紐解いた。判明することは、国譲り以来の出雲王朝と大和王朝の和と武の織り成す歴史的二重構造である。これによれば、角栄は、出雲王朝系の伝統文化を引き継ぐ宮大工系譜の有能士と云うことになる。このことの重要性は、いくら強調しても分からない者には分からないので、以上簡単に示唆しておく。 2009.2.11日 れんだいこ拝 |
| 1920(大正9 )年、角栄2歳 | |||||||
| ◎男の子が育たない家系の為か宝のような気持ちで育てられたが、幼少時はやや病弱であったようである。
◎2歳のときジフテリアにかかり、高熱が続いて生死不明になった。祖母、母の神社・仏間の必死の願いが届けられたかやがて病状が回復した。但し、これがもとでドモリになったのだと祖母は言った、とある。 ◎「外出は大抵祖母と一緒だった」といわれるようにおばあちゃん子であった。母が田んぼの世話、祖母が子守りという分担だった。 |
|||||||
| 1922(大正11 )年、角栄4歳 | |||||||
| ◎ある時角栄は、越後の大雪にやられてずり落ちた屋根雪の下敷きになった。祖母があわてて鍬で掘り出したところ、その時鍬の先が角栄の眉間に当たり鮮血を迸らせた。その結果助けだされたので感謝すべきことであったが、傷は終生額に残ることになった。 | |||||||
| 1925(大正14)年、角栄7歳 | |||||||
| 4月 | ◎二田尋常小学校(校長・草間道之助・35才の頃)入学。草間校長の教育方針は、鞭(ムチ)を使わず自然の教化をモットーにしていた。この校長は角栄少年を眼に掛け可愛がった。角栄も尊敬していた。後年の1947(昭和22)年、角栄が衆院選挙に打って出た際、真っ先に協力を求めている。 | ||||||
| ◎通学路は、林の中や、がけのふちなどを通っており、同級生と語り合いながら角栄も通った。冬は半分雪の中に埋もれてしまう学び舎であった。「学校は、勉強も大切だが、一日も休まないで通うなら、それだけで学校に行く値打ちがある」という母の戒めに従って、一日として休むことなく登校し、角栄は毎日欠かさず日記をつけたと伝えられている。 | |||||||
◎三つの校訓として、一・「至誠の人、真の勇者」、二・「自彊不息(じきょうやまず・常に努力して、怠ってはならない)」、三・「去華就実(何事も飾らず、実直にせよ)」が額に掲げられており、角栄少年はこれに親しんだ。角栄は次のように記している。
|
|||||||
| ◎少年期は吃音(どもり)癖と対人赤面症に悩んで内気になったと伝えられている。信仰心の厚かった祖母が自宅近くの菩提寺(諏訪神社ともある)に連れて行き、頻繁な願掛けをしたという。家の手助けを良くする少年で読書好きでもあったようである。 | |||||||
| ◎二田尋常高等小学校をほぼ「全甲」で通し、神童とささやかれていた。ドモリに悩みながらもクラスの級長を務め信望を得ていた。「度胸のよさと明るさは父親、緻密さと記憶力は母親似。成績は百点評価で98点をつけた」(小学校時代の恩師・金井満男)と回顧されている。 | |||||||
| ◎先生達の思い出によると、角栄少年は一、二年生頃はさほど目立った存在ではなかったが、三年生になると級長が選ばれるが当然のように角栄がなり、以降卒業するまで級長を続けた。「四、五年生になって、ぐっと頭角を現した」、「成績の席次は一年が二番で、後は卒業まで首席を続けた」と伝えられている。 | |||||||
| 1929(昭和4)年、角栄11歳 | |||||||
| ◎4年になると師範学校を出たばかりの金井満男先生が担任になった。この先生とも終生の交わりが続くことになった。ある日のこと、金井先生が昼休みの時の雑談でまっ茸を家に送りたいと何気なく云ったことがあった。昼休みが終わって授業が始まろうとしたとき、田中級長と級友達がみかん箱二つにあふれそうになっているまっ茸の山を持って教員室に入ってきた。角栄級長の「先生は親孝行もんだ。まっ茸を家に送りたいといっているので、みんなで手分けして集めよう」の呼びかけで五十人の生徒が裏山へ行って取って来たという。 びっくりした金井先生が「有難いが多すぎる」というと、角栄が「何をいうんだ。どうしても全部送ってて下さい。家で使えなければ、近所、隣に分けてやれるだろうに。そうすりゃ近所のみんなも喜ぶがね」と云う。一本取られた先生がその通りにしたところ、「まっ茸は家ではとても食べきれなかったが、隣近所にあげたらとても大喜びされた」と親が言ってきた。「負うた子に教えられた心境でしたね」と述懐していたことが伝えられている。(馬弓「戦場の田中角栄」参照) |
|||||||
| ◎4年生の或る日のこと、軟式テニスが盛んだった同校では、校庭の真中にテニスコートがあった。高等科の生徒がコートを独占して横暴だった。こうした上級生の横暴に遂に我慢しきれなくなった角栄は、グランドの真中に両足を踏ん張って、「ねら(君たち)よく聞け。ここはお前達だけのグランドではないぞぉ」と大音声を張り上げた。その気迫に押されて、高等科の腕白大将たちもテニスを止めた。この一部始終を見ていた金井先生は、上級生の仕返しを心配したが、「俺は恐れていない。絶対大丈夫だ」と言い切った。実際に何事も起こらなかったが、「4年生の子供で、こんな筋道の通ったことをいい、見通しまでつけて、それが外れない。勇気もあるが、その判断の的確さには舌を巻きました」と述懐していたことが伝えられている。 | |||||||
| ◎或る日のこと、金井先生は、若気の至りというか昔から祟りがあると恐れられていた用水池に「迷信をぶちこわす気で」飛び込み、泳いで見せた。角栄は真っ青になり、「それから一週間くらいは、先生タタリはなかったか」と毎日、尋ねたと伝えられている。 | |||||||
◎或る日のこと、金井先生は、宿題を忘れた生徒を叱って、級長だった角栄に「この子を剣道部の道具部屋に入れておけ」と命じ、角栄はその通りにした。翌日、村の駐在所の巡査が、角栄のところへ来て、その事実を確かめた。そのあくる日の新聞に、「金井訓導、生徒を監禁」と報道された。びっくりした角栄少年は駐在所に駆けつけ、精一杯の抗議をしている。金井先生は不当な監禁事件のフレームアップで転校させられた。後年、角栄は次のように述懐している。
|
|||||||
◎或る時、金井先生は角栄少年にせがまれ、ちょんがり(浪花節)の芝居小屋に連れて行った。演題は「乃木将軍」だった。金井先生の思い出談。
|
|||||||
◎記憶力のよい角栄は、一度聞いただけでその文句や節回しを覚え、さっそく翌日教室で復唱して見せた。同級生たちは角栄の浪花節にひきこまれ、毎日昼休みになると聞き惚れたという。担任の金井先生はのちに新聞にこう語っている。
浪花節を覚えることで、角栄は吃音を克服した。しかしそれだけではない。角栄はこうしてクラスの人気者になり、自信を身につけることができた。芸は身を助けるという諺の子供版であったことになる。 |
|||||||
◎金井先生は、角栄少年の優秀さを次のように語っている。
金井先生の総評は次の通り。
後に、角栄は、金井先生を越後交通に招いている。 |
|||||||
| 1930(昭和5)年、角栄12歳 | |||||||
| ◎5年生の9月、金井先生の後を笠原先生が担任になった。この頃のある日のこと、習字の時間に同級生の一人が騒いだ。笠原先生が「誰かッ」と叱ったところ、嫌疑が角栄に向かった。角栄は立って弁解しようとしたが、ドモリ癖で「頭にカッと血が上り」顔が真っ赤になるばかりで抗弁できなかった。口篭もっている角栄少年を再度叱ったところ、たまらなくなった角栄は、すりおろしていた墨硯を力ごと床に叩きつけてしまった。ドモリを直そうとすればするほどドモってしまう悩みの日々が続いた。 角栄は次のように述べている。
|
|||||||
| ◎「角栄は、この習字事件をきっかけにドモリを直すべく努力することになった。以降、漢詩・お経を読み、浪花節をうなることによりドモリを克服した。ほぼ同時に対人赤面症も止んだと云われている。「人間は誰しも何かの点でコンプレックスを持っている。それに押しつぶされる者もいれば、克服する者もいる。自らの手で吃音を克服した少年は、やればできるという自信をものにした」(水木楊「田中角栄その巨善と巨悪」) | |||||||
| ◎5年生の秋、学芸会が行われ、源義経が兄頼朝の不興を買い、弁慶と共に東北へ逃げる一幕「弁慶安宅(あたか)の関」で、角栄は金剛杖を突いて山伏姿で登場し弁慶役を演じた。弁慶が安宅の関で、白紙の巻物をあたかも勧進帳のように読み上げる場面がハイライトの一つであるが、角栄は、セリフに節をつけて歌うようにしゃべる工夫、伴奏をつけってもらったりの工夫で、どもらずにしゃべることができた。「お急ぎ候ほどに、これは早や、安宅の関におん着き候」云々と見事な台詞(せりふ)回しを口上し、満場割れんばかりの拍手喝采を得た。元々角栄のどもり癖を知る担任は舞台監督をやらせようとしていたが、角栄は、「絶対にどもらないから、舞台に出してください」と直訴しての役であった。弁慶役の成功により、すっかりどもりの克服への自信をつけた。「人生、何事も逃げねェで真正面から立ち向かっていけば、どんな苦しみも乗り越えていける」という処世法を身につけたことになる。 | |||||||
| ◎担任の先生は「お前は5年終了で柏崎の中学校へ行けるぞ、どうだ、行かないか」と進学を勧めてくれたが、この時父親の牧場経営、続く養鯉業の失敗で、田中家の家運はすっかり底をついていた。「母の苦労を思うと柏崎の中学進学への気が進まず、小学校の高等科へ進むことにした」。「ある先生は、『他の生徒に比較して、良すぎて成績のつけようがない。参った。先生ならどうしますか』と先輩の教師に相談したほどであった」と伝えられている。 | |||||||
| 1931(昭和6)年、角栄13歳 | |||||||
| ◎4月、二田尋常高等小学校入学。「比較的成績の良かった私は、先生から『お前は5年終業でも柏崎の中学校に行ける』と進学をすすめられていた。しかし、母の苦労を思うと中学には気が進まず、小学校の高等科に進むことにした」(「私の履歴書」)。「高等科へ進むことを決めた私は、中学の講義緑をとって勉強をすることにした」とある。 | |||||||
| ◎この頃、「男児志を立てて郷関を出づ 学もし成るなくんば死すとも帰らず 骨を埋むあにただ墳墓の地のみならんや 人間至るところ青山あり」(釈月性の「壁に題す」)を愛唱したとある。 | |||||||
| ◎高等小学校校長・草間道之輔の薫陶を得る。この草間氏は、「大変な読書家でもあり、長い教育生活を通じて、ついに生徒にムチをふるったことがない」という立派な教師であり、角栄の「終生の恩師」であったと評価されている。草間校長は、角栄少年に3つの教訓を教えている。それは「至誠の人こそ真の勇者」、「自彊不息」(じきょうふそく、常に努力し怠ってはならない)、「去華就実」(飾るより実直が良い)。 | |||||||
◎ この頃、次のような言葉に触れ、角栄はいたく気に入り勉学に励んだと伝えられている。
|
|||||||
| ◎9月、満州事変勃発。日本の大陸侵略が本格化する。 | |||||||
| ◎金井先生は、角栄少年の能力を惜しみ、中学校進学を勧めた。しかし、角栄少年は、田中家の財政状態を思い、「先生、おれ中学には行かないつもりです」と断っている。「もしも田中家の経済状態が許すなら東大に入学し、銀時計で卒業しただろう」と述懐している。 | |||||||
| ◎6年生の時、地方競馬に夢中の親父が至急電報で「五、六十円送れ」と云って来て、角栄少年が親戚の材木屋に借金申し込みに行ったところ、「お前の親父も金の算段の後先も考えずに駄目な男だなぁ」と云われる等、苦労している。この時、「金の威力、金の値打ち、金の化け物」に気づかされたと云う。 | |||||||
| 1933(昭和8)年、角栄15歳 | |||||||
| 3.25 | ◎二田尋常高等小学校高等科卒業。卒業生総代として答辞を読んでいる。この時凝りに凝った文案を作成し、立派に読み上げている。
|
||||||
◎卒業後直ぐに働くこともなく暫く無聊日々を過ごした。田中家の生活は苦しく、角栄の働きを当てにしたかったであろうが、角栄の思うままに過ごさせた。これにつき、後に父が次のように述懐している。
|
|||||||
| ◎この年の春から初夏にかけて、自宅の独学で中学講義緑を学んだり、漢詩を暗誦したり、書道に熱中している。余程進学したかったことと将来の進路を掴もうとして充電中であったものと推測される。「明治大正文学全集」、大衆雑誌「キング」、姉が読んでいた「婦女界」などを耽読している。 | |||||||
| 5月 | ◎新潮社の雑誌「日の出」に懸賞小説を投稿し、「三十年一日の如し」で選外佳作5円貰っている。「私の最初の収入は原稿料なのですよ。子供の頃、文士にあこがれましてね。モノを書くということでは、みなさんの先輩かな」と回顧している。 | ||||||
| 7.1 | ◎その頃、県は国の補助を得て、生活にこまった農民の救農土木工事を始めていた。角栄は、「よし、自分もあれをやってみよう」と志して、村の教農土木工事で働くようになった。これが生まれてはじめての労働体験となった。母親が買ってくれた地下足袋を履き、朝の5時半から夕方の6時半まで土方仕事に暮れ、「我ながらよく働いた」。初めて1ヶ月の労働で給金15円50銭を得たが、「労働が正当に評価されていない」として1ヶ月で辞める。
◎そこで面白い人物にあった。角栄に次のように語り、角栄は得心したと云う。
|
||||||
| 7.末 | ◎一ヵ月後給料を貰ったとき、一日50銭の31日分で女並みの給料しか貰えなかった。「私の労働が正当に評価されていないではないか」と腹を立て辞めている。請負業者の使いの者が人一倍働いていた角栄を惜しんで給料上げるからといってきたが、「土方の勉強は十分した」、「将来、勉強して技術を身に付け、工事監督になるつもり」として断わっている。 | ||||||
| 8月半ば頃 | ◎その頃、柏崎で県が土木工事派遣員を募集していた。薄給であったが一応は県の役人で、学歴も中卒以上となっていた。角栄がこれに応募したところ、高等小学校卒は角栄だけの中採用された。履歴書にしたためられた田中の字が抜きん出て良く書かれていた為とされている。習字の練習が思わぬところで役立つことになった。こうして初めて家を離れて柏崎に出て役所の建物の一室で一人暮らしの自炊生活をすることになった。以降約半年ほど勤務することになった | ||||||
| ◎角栄が今度は役所の一員として先に勤めていた会社の工事監督人としてやってくることになった。「おみそれしました」と頭を下げてきた、と伝えられている。
◎役場に勤めていた三つ年上の娘「電話3番の君」と初恋を経験する。「いつか必ず東京へ出て、うんと勉強したい」と云う角栄に、「東京へ出られるように、神様に祈ってあげるわ」と励ましてくれた、とある。 |
|||||||
| 1934(昭和9)年、角栄16歳 | |||||||
| 3月 | ◎隣村の土木係をしていた土田老人が、角栄の日頃の向学心を知っており、概要「先日、東京で大河内先生(郷里出身の大実業家)にお会いした。君の向学の希望を伝えたところ、先生は「よろしい、寄越しなさい」と承諾された。君は大河内邸の書生として学校へ通わせてもらえるぞ」との知らせを持ってきた。当時、理化学研究所の科学者且つ経営者であった大河内氏は、農村工業論を唱え、柏崎にもピストンリングや電線・自転車をつくる工場などを稼動させていた。
◎角栄は、天啓の如くに上京を決意し、その日のうちに母の承諾を得て行動を起こすことになった。母は快諾し、「こういう時がくると思って、お前の月給は、そのまま積み立てておいた」といって、旅の支度金85円を渡してくれた。 ◎この時、母親が息子に送った言葉が次のようなものであり、角栄は、これらの言葉肝に銘じ、宝物のように胸の奥深くにしまいこんだと伝えられている。
|
||||||
| 3.25日 | ◎青雲の志を抱いて上京。多くの同僚に見守られながら柏崎駅から信越線回りで上野駅へ向かう。「男子ひとたび志を立てて郷関を出ずれば」で故郷を後にする。この時「電話3番の君」が、人目につかぬよう次の停車駅で見送ってくれ、「よく勉強が出来ますように、番神さまにお祈りします」の手紙を渡してくれた、とある。この「電話3番の君」の後日譚がある。戦後、角栄が衆院選挙に立候補して柏崎小学校で第一声を挙げた時、聴衆の最前列に子供を両脇にした「電話3番の君」が居て、互いに目礼したと云う。 | ||||||
| ◎高崎で、競馬巡業中の父に50円を手渡す。桐生の姉に20円を送る。母フメの「男は腹巻に必ず10円札を入れておきなさい。どこで事故があって死んでも、無一文では笑われます」の言いつけを守り、残り15円のうち10円札を腹巻の中に秘める。 | |||||||