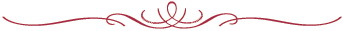一躍時の人となった小室は、同じく『思想』に昭和四三年二月から昭和四四年三月にかけて全五回「社会科学における行動理論の展開」を連載し、それでもって、昭和四五年七月には、日本社会学会が若手研究者の奨励賞として設けられた第一一回城戸浩太郎賞を受賞した。
会津高校の卒業生
小室が城戸賞をもらったというのは、昭和二六年に卒業した先輩ということもあって、会津高校在学中の私の耳にも入ってきました。私の三年生のクラス担任が田﨑行威という英語の教師で、小室の会津高校時代の同級生であったために、時間があると、決まって小室の話をしました。『評伝小室直樹』でも書かれていますが、京都大学に受験に行ったおりに、金を取られたか、無くしたかして、会津まで歩いて帰ってきたということや、家が貧乏で飯が食えなくて、芋ばかり食っていたとか、頭を剃ってメンタムを塗っていた、といったエピソードを語ってくれました。
岩波の「思想」に掲載された論文は、あくまでもアカデミズムの世界のことですが、ジャーナリズムの世界でも知られるようになったきっかけは、「エコノミスト」の昭和四五年一月号に載った『社会科学革新の方向』によってでした。同年一〇月には、TBSの『人物』で小室が取り上げられ、「がんばれ るんぺん先生」とのタイトルで紹介されたのでした。東大の田無寮に住んでいた小室が、一躍時の人となったのです。
小室の出自と学問
小室が生まれたのは、現在の東京都渋谷区神宮前で、戸籍上は昭和七年九月九日となっていますが、『評伝小室直樹』の筆者である村上篤直さんは、生年月日に疑問を呈しています。もっと早く生まれていた可能性があるというのです。小室が母親チヨと河沼郡柳津村で暮らすようになったのは、昭和一七年になってからです。父親の小室隆吉は、昭和一二年にはこの世を去っていますから、東京の食料事情が悪化し、空襲の危険性がたかまったために、母親の実家に身を寄せることになったのです。柳津村国民学校に編入しましたが、小室はかなり大人びていたようで、同級生を子ども扱いにしていたそうです。
小室が柳津村国民学校を卒業し、会津中学に入学したのは昭和二〇年四月のことです。戦後の学制改革もあって、会津中学と会津高校の両方で学ぶことになります。
小室が昭和二六年四月、京都大学の理学部に合格したのは、昭和二六年四月のことです。専門課程で数学を専攻しました。小室が数学をマスターしたことで、経済学や政治学、さらには社会学の分野で新たな学問の領域を開拓することになったのです。数理経済学が注目を集めるようになってきていたこともあり、その分野のパイオニアであった、市村真一に私淑するとなったのです。
小室が京都大学の理学部数学家を卒業したのは、昭和三〇年三月でした。引続いて四月には大阪大学大学院経済学科修士課程に入学します。市村が大阪大学の社会科学研究所に招かれたので、小室も一緒に付いて行ったのです。社会学ばかりでなく、経済学者としても知られた高田保馬が初代室長となり、京都大学の市村と森嶋通夫を招聘して、一躍数理経済学の牙城となり、大阪大学社研が経済学をリードした時代があったのです。
国士市村真一の弟子
小室は市村を通して、平泉澄の教えを直に受けることになります。東京帝国大学の国史の教授であった平泉は、大東亜戦争の敗北もあって、アカデミズムを追われました。しかし、その門下生たちが日本の再生を果たすために、平泉の許へ集まっていたのです。とくに市村は敗戦の報に接し、自刃しようとした国士で、平泉を師として仰いでいました。平泉が昭和二九年に千早鍛錬会を再会すると、小室も参加して、市村ばかりでなく、高弟である鳥巣通明、田中卓、村尾次郎から、日本の国柄の精神を叩きこまれたのだった。
率先して参加したのは、皇室を重んじる会津精神が小室の血には流れていたからだと思います。小室は「母方は会津の士族」と公言していましたが、そのことを裏付ける位牌が今も残っています。チヨの祖父の寅像(蔵)の死亡年月日の昭和二年二月十九日の下に、会津藩士と書かれているからです。会津藩士の末路は哀れなものがありました。農家の養子となって、苗字を変えて野に埋もれた人も、かなりの数にのぼったといわれます。小室の母のチヨは、祖父寅蔵から苦労をしたことを聞いたに違いありません。
学問的には小室はニュートラルな立場に終始しましたが、根本的な精神としては、一貫して愛国者でした。会津の武士道にこだわり、朱子学の意義を説いたのは、平泉や市川の流れを汲んでいたからです。
小室は指導教官でもあった市村が、平泉の門下生らとともに、自らが塾頭となって昭和三〇年一二月一八日に大阪府吹田市に「清々塾」を開設すると、第一期生となりました。精神の鍛練も怠らなかったのです。平泉は開塾式で、吉田松陰の「士規七則」を論じながら、「大厦は現に傾き始めましたが、何とかこれを支え、もって回天の大事を為し遂げねばなりません。これが、私の士規七則を講じた所以であります」と訴えたのでした。会津武士の精神を重んじる小室が感涙に咽んだことは、容易に想像がつきます。
フルブライト留学生
小室は昭和三二年の「理論経済学の基本問題」で、経済学の修士号を取り、昭和三三年一月には「デモンンストレーション効果と市場の均衡および安定」という論文を発表し、経済学者としての地位を固めました。いよいよ海外に雄飛する道が拓けたのは、市村が推薦したからで、小室は昭和三四年八月二七日、フルブライト留学生として、横浜港から氷川丸に乗って、アメリカに向かって出発しました。大きな日の丸を警策に結んで、風呂敷包みを抱えての旅立ちでした。
小室にとってのアメリカ留学の目的は、マサチューセッツ工科大学で、サムエルソンから教えを受けることであり、そこで博士号を手にすることでした。学問的な好奇心が旺盛な小室は、サムエルソンばかりか、ハーバード大学にまで出かけ、パーソンズの講義を聴いたりもしています。
小室がマサチューセッツ工科大学で博士号論文の提出資格を得るためには、筆記試験と論文試験をパスしなければなりません。小室が躓いたのは、語学ができなかったからです。いくら天才小室であっても、解答を制限時間内に英文で書くのは難しかったようです。数理経済学者としては、サムエルソンからも御墨付きを得ていたにもかかわらず、落第をしてしまったのです。失意のどん底に落とされた小室は、市村に「もう死にます」との手紙を書いています。これに慌てた市村は、八方手を尽くして思いとどまらせようとしました。
東京大学で博士号
小室がそこまで落胆したのは、自らの不甲斐なさが我慢ならなかったからでしょう。たまたまそんな小室を励ましてくれたのが、ミシガン大学で計量政治学を勉強していた永井陽之助でした。永井の口利きで、小室は東京大学で学ぶことになり、同じく修士号まではスンナリいきました。しかし、そこでまた壁にぶつかったのです。アメリカでそうであったように、またもや嫌がらせをされたのです。博士課程での指導教官であった京極純一に提出した論文が、数年間にわたって放置されたのです。これに腹を立てた小室は京極を「論文審査義務違反で訴えるぞ」と脅して、ようやく「衆議院選挙区の特性分析」は東京大学大学院法学政治政治研究科の博士論文として承認されたのです。すでに昭和四九年になっていました。
社会学の分野での小室の活躍が目立つようになるのは、その頃からです。すでに田無寮を出て、マック・ヴェーバーの研究家大塚久雄が住む石神井公園の近くのアパートに転居していました。東京大学では社会学部の富永健一ゼミのサブゼミとして、昭和四七年四月に小室ゼミがスタートしました。富永自身が小室から、理論経済学と数学を教えてもらったこともあって、富永ゼミの学生が小室から指導を受けたのです。昭和四九年四月には、独立して小室ゼミとして、本格的に活動することになりました。しかし、東京大学の社会学研究科では、小室が目の上のたん瘤となり、追い出しにかかります。単位をもらうためではなく、学問をしたい者たちが、東京大学以外からも集まるようになったからです。
アノミーの理論展開
アカデミズムの世界ではそうであっても、世間は小室を放っておきませんでした。ジャーナリズムが小室をスターに押し上げたのでした。毎日新聞は昭和四九年六月、懸賞論文「日本研究賞一九七五・日本の選択」を公募しました。入賞金目当てで応募した小室の「危機の構造―現代日本社会崩壊のモデル」が入賞した三編のうちの一つに選ばれたのです。要約すると、天皇共同体が敗戦によって崩壊して急性アノミーが生じ、高度経済成長によって村落共同体が解体して単純アノミーが発生しました。これらのアノミーは企業、官庁、学校という機能集団が共同体としての性格を帯びることで収拾されるとみられましたが、機能集団と共同体とは本来矛盾するものであるため、この矛盾が新たなアノミーを拡大再生産するのが構造的アノミーで、それが日本の危機の構造だと位置づけたのです。アカデミズムからは黙殺されましたが、日本の知識人に大きな衝撃を与えたのでした。
私のような一般大衆まで小室の本を貪り読むようになったのは、昭和五五年八月、小室が『ソビエト帝国の崩壊』を世に問うたからです。小室は昭和三一年四月の段階で、平泉の門下生が出していた機関誌『桃李』に「スターリン批判からソ連の崩壊へ」といった論文を書いていましたが、それを学問的に見地から、より掘り下げたのでした。それで小室は世に知られるようになり、数々のベストセラーによって、日本人は何を為すべきか、何に気を付けるべきかについて、分かりやすい言葉で警鐘を乱打したのです。
会津の教学を尊重
思想的なバックボーンとしては、会津藩の朱子学を最終的な拠り所としたのです。私は一度だけ会津高校の同窓会に出たことがあります。小室が講演をすると聞いたからです。残念ながら、酒に酔ってべろべろになった小室は、堂々巡りをするだけで、核心部分を話すことはありませんでした。朱子学という思想が会津藩にあったことで、いかに逆賊と呼ばれようとも、激動の時代に身を処することができました。世界が混迷を深めているなかで、日本の覚悟が問題となっているにもかかわらず、全てが後手後手に回っています。とくに政治家や官僚は責任を果たしていません。最近になってようやく、小室が言いたかったことが分かるような気がしてなりません。
今日、柳津町の花ホテルで講演をするようになったのは、小室が柳津時代に住んだ家を、たまたま花ホテルさんが購入されたので、塩田社長から声がかかったからですが、村上篤直さんの『評伝小室直樹』がなければ、話ができなかったと思います。村上さんには感謝です。