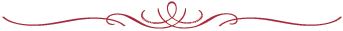
| 田中角栄履歴語録 |
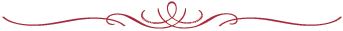
(最新見直し2009.10.25日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、角栄の履歴語録を確認する。 2010.11.20日 れんだいこ拝 |
| 【今太閤角栄の感慨】 | |
|
| 【角栄の母の思い】 | |
|
| 【角栄の母について】 | |
|
| 【長男的責任自覚について】 | |
角栄は、原日本人とでも云うべき感性と責任感の篤い人物であった。特に、冠婚葬祭を大事にしていた。次のように語っている。
|
| 【母の励まし】 | |
|
| 【越後人の気質】 | |
|
| 【親孝行】 | |
|
| 【ディアナ・ダ―ピン】 | |
|
| 【結婚する時の女房への三つの誓い】 | |
|
| 【角栄の政治家転身述懐】 | |
|
| 【母の戒め】 | |
|
| 【角栄のせっかち論】 | |
|
| 【角栄の名前の由来】 | |
|
|
|
|
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)