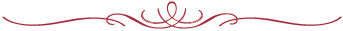
| 第71回国会、田中首相演説に対する各党の質疑に対する答弁 |
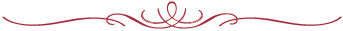
(最新見直し2012.1.5日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「第70回国会、田中首相演説に対する各党の質疑に対する答弁その1」に続く第71回国会に於ける角栄の答弁を確認しておくことにする。この答弁を通して、1970年代の日本の在り方が現在の日本と大きく異なっている、即ち1970年代の日本がインフレ下に苦闘する、だがしか諸事前向き建設的な正々堂々たる日本であるとすれば、現在の日本がデフレ下に苦吟する如何に矮小なホワイトハウスの御用聞きしかしていない日本であるかが分かろう。こんな日本に誰がしたと云う怒りを媒介にさせて読んでもらいたいと思う。2012年の巻頭に相応しいブログである信ずる。 2012.1.4日 れんだいこ拝 |
れんだいこのカンテラ時評№1014 投稿者:れんだいこ 投稿日:2012年 1月 4日 |
| 【1973.1.29日、衆議院における日本社会党・石橋政嗣の質問に対する田中首相答弁】 ここで、「第70回国会、田中首相演説に対する各党の質疑に対する答弁その1」に続く第71回国会に於ける角栄の答弁を確認しておくことにする。この答弁を通して、1970年代の日本の在り方と現在の日本との違いが分かろう。1970年代の日本はインフレに苦闘していた。政治家は、いわば上り調子の中で舵取りしていた。国会質疑から判明するのは、諸事前向き建設的な正々堂々たる日本の姿であろう。現在の日本は逆にデフレ下に苦吟している。それは良いとしても、国会質疑から判明するのは、諸事ホワイトハウスの御用聞きしかしない質の劣化した日本である。こんな日本に誰がしたと云う怒りを媒介にさせて読んでもらいたいと思う。2012年の巻頭に相応しいブログである信ずる。 (以下、本文) まずまず第一に、内閣に対する御所論に対してお答えを致します。先の総選挙で、自由民主党は、284と云う絶対多数の議席を獲得し、引き続き政権を担当致しておるのでございます。しかし、私は、総選挙を通じまして、国民の政治に対する期待や不満を痛いほどに感じ取ったのでございます。これらの期待に応えて行くことが内閣に課せられた政治課題だと考え、懸命な努力を続けたいと考えるのでございます。(拍手) インフレに対する措置、予算その他の御質問にお答えを致します。国民福祉の向上、国際収支の不均衡の是正、物価の安定の三つの課題を同時に解決することは大変困難な問題でございますが、全力を挙げてこれが解決に取り組んでまいりたい決意でございます。 まず、48年度予算案は、国民福祉の向上という国民の期待に正面から取り組み、財政に課せられた役割を果たすという立場で編成をしたのでございます。48年度経済見通しに於ける中央、地方を通ずる政府の財貨サービス購入は16.6%増となっておりまして、GNPの名目成長率16.4%とほぼ同程度のものとなっておりますので、この予算がインフレ予算と云われるようなものではないことは、これを見てもご理解賜れると思うのでございます。 なお、国債について言及がございましたが、前年度当初予算の依存度は17%でございましたが、今年度の国債発行高を16.4%にとどめるなど、経済の動向に十分配慮を致して居る訳でございます。また、調整インフレの考えは全くないことを明らかに致しておきます。 対外均衡の達成の為には、輸入の拡大、輸出の適正化、経済協力の拡充などが一層推進されなければならぬ訳でございます。経済活動全体が均衡ある姿で安定した成長を続けることが物価安定の基本であることは申すまでもないことでございます。この為には、財政金融政策の適切な組み合わせが必要でございます。特に、国内の過剰流動性を押さえるため、金融面の対策も取られつつある訳でございます。 当面の物価対策としましては、輸入の積極的拡大を図って参りたい、こう考えます。先ほども御指摘ございましたが、48年度予算の説明書による広い意味での物価対策費は、1兆3500億円ということでございます。流通対策、生鮮食料品対策、交通料金対策、地価住宅対策など、特に重点的な対策につきましては、3300億円を計上致しておりまして、これが金額は、前年対比51.2%増という計上を致しておる訳でございます。これらの対策を総合的に推進することによりまして、消費者物価を押さえて参りたい。しかし、これは政府だけの力でできるものではないので、野党の皆さんも含めて格段のご協力を説にお願いを致します。(拍手) 法人税の税負担を高めるというお話でございましたが、48年度の改正におきましては、産業関連の租税特別措置の改廃により、来年度400億円の増税措置を講じた訳でございます。また、固定資産税につきましても、その負担を高める措置が講じられておりまして、この面からも税負担は加重されることになっておる訳でございます。 48年度の国債発行額、先ほど申し上げた通りでございます。国債発行額2兆3400億円のうち、資金運用部の引き受けが4700億円ございますので、市中消化予定額は1兆8700億円でございまして、47年度の補正後の予定額と同額であることをご承知いただきたいと思うのでございます。 公共事業費は、総額2兆8千億円でございますが、この公共事業費が、消化ができないような大幅なものではないかと云う御説でございますが、対前年度補正後7.6%の伸びでございまして、関係省庁の消化能力を十分勘案をして編成したものでございます。 公共料金について言及がございましたが、これは極力抑制せられなければならぬことは当然でございます。しかし、人件費等のコスト上昇の中で料金だけを固定化することは困難な面もございます。もちろん、国鉄、地下鉄のように公共性の高い、国民生活に密接な関係のある料金については、財政援助を大幅に拡大を致しまして、必要最小限の負担増にとどめることと致しておるのでございます。 土地対策についてのご提案にお答えを致します。一定規模以上の土地の取得は市町村の許可事項にせよという御提案でございましたが、一定規模以上の土地につきまして、市町村を経由して都道府県知事に届け出をさせることに致し、都道府県知事が、投機的取引と認め、合理的な土地利用を阻害すると認めるものにつきましては、中止勧告をすることを立法化して参りたいと考えております。次に、地域開発は、地方公共団体が主体となることが原則であり、その推進に当たりましては、住民の意思が十分反映されるよう、一層の配慮を致して参ります。 地方自治体の土地先買い権を強化せよとの御提案でございますが、国土の総合開発を進めるに当たり、特に一体として開発し、整備し、又は保全する必要のある地域は、特定地域の制度を設けて参ります。この特定地域につきましては、一定期間、特に土地の投機的取引を防止し、開発行為を凍結する必要があります為に、土地取引の届け出、勧告制と合せて、地方公共団体等による土地の先買い制度を創設して参りたいと考えます。また、公有地拡大推進法による先買い制度の対象区域の拡大についても、検討を続けておるのでございます。 また、御提案によります問題につきましては、税制調査会でも議論をせられた訳でございますが、基準となるべき標準地価として何が適当であるかについて一般的な合意が確立しないままに、その実行を図ることは困難であると云う面がございます。税制のみによって土地に対する一種の公定価格制度を推進することは無理がございます。むしろ、利用規制等を含めた税制以外の法制の整備が先決であります。(拍手)土地の増価分に大幅な分離課税をという御提案でございますが、仮に一定基準の土地評価額を上回る部分の土地譲渡益に対して重課せよということでございますれば、何を基準とするかということで難しい問題が存在を致します。また、現に保有するあらゆる土地について強制的に評価、課税するということであるとすれば、最近において投機目的の為に取得した土地については税負担が相対的に低く、古くから保有し、本来の事業の用に供しておる土地ほど税負担が重くなるといった問題も生ずるのでございます。今申し上げた問題は、この国会に法案として提案をするのであります。これは非常に画期的なものであります。(拍手) その意味において、皆さんから建設的ご審議と早期成立の為のご協力をお願いいたします。(拍手) なお、列島改造を取りやめろと云うお話でございますが、一億余にのぼる国民のうち、国土の僅か1%の地域に32%、3300万人が過度に集中をしておるような現況を改めない限り、諸般の問題の解決は困難であります。(拍手) これは、自由民主党内閣でなくとも、社会主義的国家におきましても、都市に集中を抑制しておる現在を考えれば、お分かりになることであります。(拍手) この狭い日本を総合的に利用せずして、いろいろな問題が解決できるとは思えません。(拍手) しかも、公共用地の取得、都市周辺に於ける空港の建設等に対して、一坪運動も行われておるではありませんか。このような状態を考えるときに、列島改造を進めずして諸般の問題が解決しないことを明らかに致します。(拍手) 福祉対策について申し上げます。ILОの102号条約につきましては、疾病、失業、老齢及び業務災害の各部門において、我が国の水準は、条約の条件を満たしており、現在でも一応批准可能と考えておるのであります。しかし、その批准につきましては、基準を満たしていない部門の今後の方向を定め、全体についても将来の見通しを立てた上で態度を決める事が妥当であると考えておるのであります。 各種年金の充実についての御提案がございましたが、政府としても、48年度の予算編成の最重点項目として、年金改善を取り上げた訳でございます。具体的には、厚生年金及び国民年金について、いわゆる5万円年金の実現を目途とする年金額の大幅引き上げ、物価スライド制の導入を図るとともに、老齢福祉年金を夫婦月額1万円に引き上げるなど、大幅な改善措置を講ずることと致した訳でございます。賦課方式への切り替えの問題等もございますが、被保険者に比べ受給者数が少ない現段階においては、当年度に必要な給付費用をその年度の保険料で賄うとすれば、当面は比較的に軽い負担で給付改善を行う事も可能かと思います。しかし、今後は受給者数が急増を致して参りますので、給付改善を行わない場合でも、保険料負担は今後急激に高価なものとなるなど、将来に大きな禍根を残すことになる訳でございます。年金制度の健全な発展を図る為には、長期的視野に立った財政運営が肝要でございまして、政府としては、今回の改正に当たって、現行の財政運営の在り方の基本を変更することは適当でないという結論に達したわけでございます。 公害対策について申し上げます。政府としては、中公審企画部会の中間報告の趣旨を真剣に受け止め、環境水準、排出基準の強化等を進めますとともに、環境破壊をもたらさないような産業構造への転換を図って参ります。また、開発に際しましては、事前に環境に及ぼす影響を十分調査し、環境に悪影響を及ぼさない範囲で開発を進めるなど、環境保全の為の施策を強力に推進をしなければなりません。苫小牧東部、むつ小川原等の大規模な工業開発プロジェクトについて、公害を未然に防止し、自然環境の保全を図る為、十分な事前調査を引き続き実施して参ります。開発に当たりましては、これらの調査の成果を踏まえ、且つ地域の住民の意向を質しつつ、各地域の環境制御が可能な範囲内で工業開発の規模を定めることとしたいと考えております。また、工場施設の配置に当たっては、工場環境の整備基準により規制することとし、公害に対する常時監視体制を整備して参ります。その意味で、これを取り辞めるということは考えておりません。公害防止費用の原因者負担の原則は、公害対策基本法におきまして、我が国においても既に確立しておることは御承知いただきたいと思います。 自動車の排気ガスによる公害の防止等についての御指摘がございましたが、従来から段階的に規制を強化しておる訳でございます。更に、昭和50年には、米国のいわゆるマスキー法に匹敵する厳しい規制を実施する方針でございます。自動車メーカーは、これらの規制に適合する有害物質除去装置の開発に対して、現に全力を挙げて推進を致しておりますし、政府としても、公害防止技術の開発には懸命に取り組んでまいりたいと考えます。(拍手) 所得減税についてのお話がございましたが、初年度3150億円、平年度3700億円に及ぶ減税を行うことに致しました。これは所得税の自然増収額1兆2596億円の27.2%でございまして、このような減税の結果、夫婦、子二人の標準世帯におきましては、課税最低限114万9060円ということになった訳であります。私は、これが最も良いものだとは考えておりません。しかし、西ドイツの77万円、英国の93万円、フランスの100万円を比べて、そこまできた努力はひとつ御理解を賜りたい。(拍手) 日本の夫婦、子二人の標準世帯114万9060円は、日本より所得のはるかに多いアメリカが132万4000円であることを、これもひとつ御理解を賜りたいと思うのでございます。(拍手) 但し、これをもって足れりとしておるものではないことを付言致しておきます。 防衛費と攻撃性の強いT2改機などの問題について言及がございましたが、防衛費につきましては、世界の各国が必ず、自分を守る為に防衛費を組んでおります。私も、今日勉強して参りましたが、日本以外の国々で、歳出に占める防衛費で日本より小さい国は見当たりませんでした。(拍手) しかも、一番大きいのは40%を越している国もございますし、30%を越している国もございます。四次防を含めて、我が国の歳出に占める防衛費は、僅かに7.1%、8%未満である事実も十分ご理解をいただきたいと思いまして、私は、やはりこの程度の負担は、日本の独立と自由を守る為には必要なものである、こう考えておるのであります。(拍手) 我が国の防衛力は、憲法に許容する範囲内に限られ、侵略的、攻撃的な装備は保有できません。これは、石橋さん御指摘の通りでございます。四次防もこの制約に従って作られたものでございます。48年度予算の中にも、その意味で、攻撃的な装備は一切含まれておりません。FST2改支援戦闘機につきましても御言及がございましたが、自衛の為に必要な装備でございまして、同機の行動半径は短く、攻撃的脅威を与えるようなものではないことは、御専門である石橋さん、十分ご理解をいただきたい、こう思います。 どこまで日本の軍事力を増強するのか、平和時における自衛力の限界なるものについて御言及がございましたが、先ほども申し上げましたように、我が国の防衛力は、憲法の許容する範囲内で、国防の基本方針に則り、斬進的に整備を進めておるものでございますが、昨秋四次防を決定しました際、我が国の防衛力は今後どこまでも無制限に増加するのではないということを明らかにできれば、国民の防衛に関する理解を得る為にも幸いであると考え、平和時の防衛力として防衛庁に勉強、研究をするように指示したものでございます。これは非常に難しい問題でございますが、防衛庁では真剣に研究をしてくれておるのでございます。先般その考え方につきまして説明を聞いたのでございますが、中間報告の段階でございまして、最終的な説明を受けるには至っておらない訳でございます。現に勉強中と御理解賜りたいと思う訳でございます。 北朝鮮、北越、東独と国交を樹立せよ、これらの国連加盟に努力せよという趣旨の発言がございました。いわゆる分裂国家にはそれぞれ特有の歴史的、政治的な背景と事情があり、当事者間の関係も異なるので、一律に論ずることはできません。政府は、人道、文化、スポーツ、貿易の分野で北鮮との関係がやり易くなることを期待しておる訳でございます。北ベトナムとも、これまであった接触は、全般の和平実現により拡大の余地ができて参りました。外交関係の設定を行う前に戦後復興等、北ベトナムとの交流増大のため、やることはたくさんある訳でございます。東独につきましては、東西両独間の基本的条約の批准も間近になっておりますので、遠からず東独との外交関係を設定できると考えております。ドイツ民主共和国の国連加盟等につきましては、東西両独間の合意に基づいて近く双方の加盟申請が行われ、今秋の国連総会において亀井が実現するものと予想されます。(発言する者あり) これは分裂国家に対して御説明をしておるのでございます。朝鮮、ベトナムにつきましては、当事国の意思を尊重する立場から、南北両鮮間の話し合い、北ベトナム和平後の進展と睨みあわせて考えて参りたいと考えるのでございます。 日米安全保障条約と四次防の中止の問題について御発言がございましたが、先ほど申し上げましたように、我が国の防衛力は、憲法を守り、必要最小限でなければならないと云うことでございます。また、必要最小限の負担で独立と自由を守るためには、日米安全保障条約が不可欠なのでございます。そういう意味で、日米安全保障条約を維持しながら、最小限の負担で日本の独立、自由を守って参りたいと云う悲願を御理解賜りたい。(拍手) アジア平和保障会議の問題について御言及がありました。アジアの平和維持は、我が国をはじめアジア諸国共通の関心事でございます。ベトナムに実現しつつある和平を確固たるものにする為、アジア・太平洋諸国による国際会議の開催の可能性を現に考えておるのでございます。その方途はいろいろございます。目下鋭意検討中でございます。タイで起っているような事件が世界各地で起らないように努力をしなければならぬという御指摘でございますが、その通りでございます。その為には、これから日本の経済援助、技術援助、また内容の改善等に対しても格段の配慮をして参るつもりでございます。 最後に、政治資金及び議員定数の不均衡の問題等についてのご言及がございましたので申し上げます。政治資金規正法改正の問題につきましては、政党政治の消長、我が国の議会制民主主義の将来に関わる重大な問題で在りますが、幾たびか改正法案が国会に提案されながら廃案になった経緯があることは周知の通りでございます。(発言する者あり) これを今日の時点に立ってみると、金のかかる選挙制度あるいは政党の在り方をそのままにしておいてこれを具体化することにいろいろと無理があることを示しておるように思うのでございますが、工夫によっては、その方法も見出し得るものと考えるのであります。今後は政党本位の金のかからない選挙制度の実現への動向を踏まえつつ、さらに政党法の在り方なども含めて、徹底した検討と論議を積み重ねて参りたいと考えます。 衆参両院議員の選挙区別定数の合理化かは、もとより重要な問題であることは申すまでもありません。選挙区別の定数をどう改めるのかと云う問題は、両院議員の総定数、選挙区制、選挙制度をどうするかという問題と切り離して結論を出すべきものではなく、選挙制度全体の根本的改善の一環として検討すべき性格の問題であると考えておるのであります。先の第七次選挙制度審議会でも、選挙制度全般にわたって民本的改善を行う場合、その一環として各選挙区の定数をどのように定めるかと云う点から審議が行われるという報告を受けております。政府としましてはこのような考え方を元にして、世論の動向、各政党の御意見等も十分に聞きながら、慎重に検討して参ります。以上。(拍手) |
れんだいこのカンテラ時評№1015 投稿者:れんだいこ 投稿日:2012年 1月 5日 |
| 【1973.1.29日、衆議院における自由民主党・倉石忠雄の質問に対する田中首相答弁】 倉石君にお答えを致します。まず、経済協力の在り方を再検討し、政府開発援助を量、質の面で拡大をすべしということでございますが、我が国の経済協力は、1971年実績におきましては、量的におきまして米国に次ぐ第二位の地位を占めているのでございます。しかし、質的には、政府援助は約その24%にとどまっておりまして、DACの平均数字を下回っております。世界第二位の経済力を持つに至った我が国でありますので、政府開発援助の量的拡大、借款条件の改善、アンタイイングの推進等、重点を置いて参りたい、こう考える訳でございます。 第二には、インドシナ地域における復興、和平の定着の為のアジア諸国による国際会議の開催等についての御発言でございましたが、先ほども申し上げました通り、インドシナ地域の復興と安定に貢献するには、単独で協力をする場合、国際協力を通ずる場合、いずれの方法も考えられますが、我が国と致しましては、両面を考究すべきだと考えておるのでございます。至難の事業であるだけに、多くの国々の共同参加が求められることが効率的ではないかと考えております。その為には、社会体制を異にする国々をも含めた関係各国との相談を重ねて参りたい、こう考えます。しかし、バンドン会議のような派手なものは必ずしも考えておらない訳であります。地道な外交努力を展開することが先決であり、その段取りはかねてから検討しておる次第でございます。 第三は、日ソ関係についての御発言でございましたが、日ソ関係は、経済、貿易、文化の各分野において年とともに着実に進展を致しておりますことは御承知の通りでございます。政府としては、今後とも互恵平等の原則の上に立って、隣国ソ連との多面的な関係の発展を図る方針でございます。しかしながら、同時に、日ソ関係を真に安定的基礎の上に発展せしめる為には、懸案の北方領土問題を解決し、平和条約を締結することが不可欠でありますので、政府は、引き続きソ連との交渉に一層の努力を続けて参りたい、こう考えます。(拍手) 貿易、経済問題で日米間にある感情のもつれをどうするかということでございますが、日米両国は経済関係の維持、強化が、両国の為ばかりでなく、世界経済の発展にとっても不可欠であることを十分認識を致しておるのでございます。私は、ハワイでニクソン大統領と話し合いを致しましたときに、日本としては、両三年以内に国際的な均衡を達成するよう努力をすることを申し述べ、理解を得て参っておる訳でございます。対米貿易収支の不均衡是正に対しては、政府も、国民の理解を得て、精力的に行っておる訳でございます。しかし、今年末までの予想を致しますと、去年よりもなお日本から米国への貿易、俗に云う対米出超が拡大を致しておるのでございまして、対米貿易是正の為に、なお一層の努力を続けて参らなければならない、こう考えておるのでございます。アメリカに対しても、日本に対する輸出の促進等に対して努力をしてもらうよう、要請も致しておる訳でございます。日米間の貿易不均衡と云うような問題は、どうしても国民各位の協力を得て、正常なものにしなければならない、それは焦眉の課題であると云わざるを得ないのであります。政府はこれが解決に全力を傾けるつもりでございますが、国民皆さんのご協力も切に願いたいのでございます。(拍手) 国の安全保障に対する基本的見解について御発言がございました。自国民の生命と財産を守らなければならないことは国の義務であります。その為、国防の基本方針に基づいて、最小必要限の自衛力を漸進的に整備し、将来、国連が有効な平和維持機能を果たし得るに至るまで、どうしても日米安全保障体制を維持しなければならぬのであります。先ほどもお答えを申し上げましたが、最も合理的な負担において専守防衛の実を挙げておる日本としては、日本だけで平和と独立を守れないと云う状態でありますので、日米安全保障条約と合せて、日本の完璧な安全を保障しておる、これは不可分なものであるということを、十分ご理解いただきたいものでございます。(拍手) 言うなれば、日米安全保障条約と云うものがもし廃棄されて、日本だけで防衛を行うとしたならば、今のような四次防が大きいなどという考え方、そんなものでは日本が守れるものではないという事実を、十分ご理解をいただきたい、こう思うのでございます。(拍手) その意味で、国連が有効な平和維持機能を果たし得る日まで、日米安全保障条約を維持して参る、こう申し上げておるのでございます。 しかし、これらの問題だけで解決できるのではなく、国際協調の為の積極的な外交、物心両面における国民生活の安定と向上、国民が心から愛することのできる国土建設等の内政諸施策を推進して、これらの努力の総合の上に、我が国の独立と安全が保障されると考えるのでございます。先ほども御発言がございましたが、我が国は、平和な島国に閉ざされて、恵まれた四半世紀を過ごして参りましたので、ややもすれば防衛問題に対する国民の関心が薄いかもしれませんが、その当否はさておき、国会の内外において論議が積み重ねられ、国民の合意が得られるように、政府は努力をして参りたいと考えるのであります。 基地に対する住民感情の問題等に対しての御発言がございました。しかも、基地に対する住民感情の問題と、安保廃棄というような問題、これは別な問題ではないか、別の問題として取り扱うべきであるということでございました。また、地域開発に支障のないように、支障となるものについては返還を求めたり、周辺整備事業に万全を期すようにという御注意でございますが、全く同感でございます。現在、いわゆる安保反対と云う政治的な立場と、地域的な基地問題とが結び付けられているという側面があることは、全く御指摘の通りなのであります。我が国の安全を確保し、アジアの平和に資する為には、日米安全保障条約体制が必要であり、その為に必要とされる米軍施設、区域は、日本国民全体の安全と平和の為に存在をするのでございます。従って、施設、区域周辺住民の不便や負担は、国民全体でこれを分かち合うということでなければならぬのであります。(拍手) 政府としましては、地域の福祉と発展にとってできる限り支障にならないように努力を傾けますとともに、周辺対策に万全を期する所存でございます。先般の日米安保協議委員会において十か所の施設、区域の整理統合が合意されました。これからも積極的に、地域開発の必要のあるところの基地の周辺整備等、住民各位の期待に応えられるように整備をして参りたいと考えておるのでございます。 住民登録の拒否の問題についてでございますが、自衛隊についての住民登録が事実上拒否されておることは、国民としての権利義務行使の基礎となるものだけに、まさに憲法で保障された基本的人権に関わる重要問題であって、甚だ遺憾なことであります。こんなことが行われてはなりません。(拍手) こういうことが現に行われておって、憲法の基本的人権などを論ずるということ自体がオカシイのであります。(拍手) 政府は、この問題を地方自治の基盤をも脅かす重大な問題であると考えており、地方公共団体の良識を信頼して今日までその是正方を指導してきたところでありますが、今後もこのような認識に立って、速やかな事態の解決の為に更に努力を重ねます。(拍手) しかし、これは小さな問題ではありません。与野党とか、考え方の違いではないのです。憲法の基本的人権を守るということの第一ページにある問題であります。(拍手) 目的の為に手段を選ばないというような問題に、かかることが使われることは甚だ遺憾であります。(拍手) 賃金上昇が生産性上昇を上回り、物価に跳ね返ることにらならないかと云う御指摘でございますが、昭和43年度以降、賃金上昇率が生産性上昇率を上回る傾向が見られます。これは、物価問題の元となっておる先進工業国で、賃金が生産性で賄えない、賃金が生産性を上回るというような問題が続くと、どうしても、西欧先進国に現われておりますように、卸売物価に影響致します。それはすぐ消費者物価に繫がるのでございます。そういうことが起らないようにと、先ほども施政方針演説で政府の基本的な考え方を述べた訳でございます。(拍手) その意味において、長期的に見ますと、我が国においては、両者は均衡がとれて推移をして来たと認められておるのでございます。しかし、最近、物価や賃金の上昇が目立っておりますので、労使における価格及び賃金の決定が、国民経済全体の中で均衡のとれた形で行われることが望ましい、こう考えておるのでございます。 国民福祉の指標を策定し、福祉社会のビジョンを国民に示さなければならないという意味の御発言でございました。全く御指摘の通りでございます。政府は、今年度を社会福祉の年として、社会福祉拡充を目指して予算編成を致したのでございますが、新しい長期経済計画の最重点項目の一つとして、国民福祉の充実も考え、またこの長期経済計画の中に、長期間にわたる社会保障の位置づけということを答申していただこうということを考えております。なお、この答申というものをいただきましたら、体系の整備等も含めて、計画的に社会保障の充実を図って参りたい、こう考えておるのでございます。 教育の根本に対する所見如何という問題でございますが、「教育は、次代を担う青少年を育て、民族悠久の生命をはぐくむ為の最も重要な課題である」と演説で申し述べましたが、私は教育が一番大切な問題であるとしみじみと感じておるのであります。(拍手) お互い人の子の親であります。我々の生命には限りがあります。しかし、日本民族の生命は悠久なのであります。我々の子供や孫が国際人として尊敬され褒められるような人になって貰いたいと思わない親はないと思います。私は、そういう意味で、教育と云うものは、知識を得るところではなく、人格形成の場でなければならない、(拍手) こう真に考えておるのでございます。 日本人として培わなければならない心は本当に教え込まれるような理想的教育環境を整備する為に、政府は思い切った施策を行うつもりでございますし、国民がこの教育充実の為に真に努力を傾けられ、政府の施策に協力されることを心から期待してやみません。(拍手) 特に先ほど倉石君の述べられた通り、教育の任務は民族的伝統の継承と民主社会の規範の体得の上に個人の可能性の豊かな開花を図ることによって平和な国家、社会の形成者を育成することができるのだと云う考え方も全くその通りでございます。(拍手) お互い、政府を鞭撻していただいて、世界に冠絶した、日本に本当に適合した教育環境を作ることに努力をして参りたいと思います。(拍手) |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)