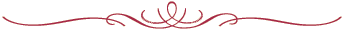米国とイランはゆっくりと、確実に、しかし確信や達成感、満足感はほとんどないまま、正式には「包括的共同行動計画」として知られている2015年の核合意を新しくした形での合意の可能性に向かって、ますます近づきつつある。
1年半近い交渉の末、ワシントンとテヘランはEUの草案を熟考しているが、これは合意案の特定の側面に対する双方の不安だけでなく、何よりも両者の信頼関係が完全に欠如していることを反映している。
一方、イスラエルの政治・安全保障関係者は、こうした動きを大きな懸念と疑念を持って見守っている。このような合意を完全に回避することが可能かどうか、あるいはその影響をどのように抑えるのが最善かについては意見が分かれるかもしれないが、今回の合意はイスラエルの国益を損ない、地域と世界の安定を脅かすだけだという点では広く意見が一致している。
イスラエルでは、合意の可能性が高まり、実現に近づくにつれ、それを声高に拒否する動きが強まる。これは提案された協定が提示する根本的な、そしておそらく解決不可能なジレンマを反映している。それは主に、イランが核軍事力を獲得するのを阻止することに主眼が置かれているが、テヘランによって行われるその他の不安定化を図る活動を阻止することには主眼が置かれていないということである。
これは確実とは言い難いが、復活した協定が少なくともその期間中はイランの核軍事力獲得への歩みを止めると仮定するならば、これには代償が伴う。イランに課せられている現在の制裁が解除され、政府の財源と、おそらくイスラム革命防衛隊の財源が満たされる。そうなれば、テヘランの政権は地域破壊的な政策を継続できるだけでなく、より強力にそれを行うことができるようになる。
新たな合意が成立するかどうかにかかわらず、イスラエルとイランの敵対関係は中東政治の不変の特徴であり続けるだろう。
ヨシ・メケルバーグ
さらに、イラン政府は、主に石油とガスの輸出によって得られる余剰資金の一部を、同国が直面している悲惨な経済状況の改善、ひいては社会不安の抑制に活用できるため、政権支配を強化・長期化させることができるようになる。
一方、2018年にドナルド・トランプ大統領が当初の核合意から離脱し、厳しい制裁を再強化してから経過した4年間は、イラン当局の核開発を止めることも、国内の不安を抑えることもできていない。実際はまったく逆で、イランはこれまで以上に核爆弾制作に近づいている。
イスラエルの強い追い風を受けたトランプ大統領の協定離脱の決断は、イランの核開発計画をさらに意欲的に継続させることに成功しただけの失策であったという点では広く意見が一致しているが、だからといってこのことは、現在審議中の新たな協定が、イランがイスラエルとより広い地域の安全保障にもたらす課題に対する答えであると、イスラエルの意思決定者を必ずしも納得させるものではない。
この懸念は核軍拡競争にとどまらず、シリアやイエメンでのイランの存在、レバノンでシーア派に支援されるヒズボラ、ガザでの過激派組織への支援に端を発している。
このため、イスラエルは苦境に立たされている。さらに複雑なことに、2015年の包括的共同行動計画(JCPOA)調印時にイスラエルの首相であり、当時のオバマ米大統領とこの問題で対立したくてたまらず、その過程で両国の特別な関係を危険にさらす覚悟があったベンヤミン・ネタニヤフ氏とは異なり、現首相のヤイール・ラピード氏は、米国とイスラエルの関係を悪化させるようなリスクは冒さないだろう。
イスラエルの利害を調整する上で、米国と協力し、両国関係の長期的なダメージを回避するための取り組みは、当然のことながら最優先事項であり続けるはずだ。だからといってそれは、イスラエルの高官が核取引の結果について深い懸念を表明し、核取引を放棄しないまでも、少なくともその条件を厳しくするようワシントンを説得しようとすることを妨げるものではない。
核取引に対するイスラエルの批判者の中で最も率直なのは、モサドのデビッド・バルネア長官である。 彼は、「結局、これは嘘に基づいた協定になるだろう」と言ったと伝えられている。その主な理由は、イランが最近、国連の核監視機関である国際原子力機関(IAEA)が、イランの未申告研究施設で見つかった人工ウラン粒子に関する3年間の調査を終了しない限り、新たな協定を結ぶことを拒否したからだ。この発見が確かならば、イランの最終目的は依然として核能力の開発であるという評価が強まるだろう。
バルネア氏の考えでは、もし協定が締結されれば、調査は立ち消えになるか、あるいは不正行為があったと結論づけられたとしても、米国が再び協定から離脱することにはつながらないだろう。
こうした懸念から、ベニー・ガンツ国防相は、米国の国家安全保障顧問のジェイク・サリバン氏との会談のためにワシントンへ急行することを決定し、イランの核開発プログラムに関して、いかなる協定とも別に一種の保険証券と抑止力として、米国は実行可能な軍事的選択を保持しなければならないというメッセージを伝えると、後にラピード氏も繰り返した。
スイスを訪問したイスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領は、現在の役割はほとんど儀礼的なものであるものの、イランの過去の核合意での義務違反に関する調査の継続を求める声に彼の意見を付け加えた。このことは、これがイスラエルの社会と政治においてほぼ普遍的な総意が存在する話題であることを示唆している。
このように核協定の復活を阻止するための外交努力を重ねているが、大統領選挙キャンペーン中にそのような戦略的行動を約束したバイデン政権が署名に踏み切れば、イスラエルによってそれが行われるのを阻止される可能性はほとんどないことをイスラエルの意思決定者たちはよく理解している。
イスラエルに残された道は、特にワシントンとの間で、イランの核開発や周辺国などでの敵対的活動を封じ込めるための秘密作戦を継続できるような合意を形成することである。
また、イスラエルはおそらくイランの核施設に対する査察を強化するよう国際社会に圧力をかけ続け、自らも軍事オプションの開発を続けるだろう。これは最後の手段であるばかりか、良くても成功率が極めて低く、特に少なくとも暗黙の国際的合意なしに実行された場合、その可能性は低く、おそらく非現実的であるとわかっているからである。
イランのイブラヒム・ライシ大統領が、イスラエルが自国の核施設を攻撃した場合破壊すると脅したのは、テヘランである種のパニックが起こっていることを示しているか、あるいは、制裁解除と引き換えに支持されていない譲歩をする用意があるという国内批判から政権を守ろうとする有権者管理の試みや、イスラエルに対する好戦的な言葉は常に都合のよい目くらましになるという認識を示唆しているかもしれない。
しかし、新たな合意が成立するかどうかにかかわらず、イスラエルとイランの敵対関係は中東政治の不変の特徴であり続け、さまざまな分野で低強度の対立が起こり、手に負えなくなる恐れのある段階的拡大の真のリスクも存在する。