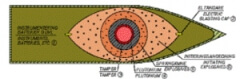| 9月6日深夜3時8分、北海道を襲った最大震度7の地震は、道内全域をブラックアウト(停電)に陥れた。私たちは広域停電の恐怖をまざまざと見せつけられたのである。295万戸が停電し、発生から丸1日たっても約131万戸分しか電源は回復しなかった。完全復旧には1週間以上かかる見通しだ。
道内全域の長時間にわたるブラックアウトの原因は意外なものだった。それは、震源地に近い北海道電力苫東(とまとう)厚真火力発電所(厚真町、165万キロワット)が大きなダメージを受け、一時停止せざるを得なくなったからである。この火力だけで道内の電力の約半分を担っていた。苫東厚真の脱落の結果、電力網全体で需給バランスが一気に不安定化した。そして道内の他の火力発電所が次々に停止し、道内全域停電という事態に陥った。
電力安定供給を至上使命としてきた電気事業者にとっては、まさにほぞをかむ事態である。この事態を招いた原因として、強大な権限を背景に科学的判断を避け続けた原子力規制行政がある。
泊原子力発電所(泊村)の3基の原子炉の総出力は207万キロワット。苫東厚真火力の出力を補って余りある。しかし、泊原発は3・11後にいったんフル稼働運転をしたものの、2012年5月5日に定期点検に入り、今日に至るまで停止したままだ。そう、日本は「原発ゼロ」になったのである。
今、泊原発の原子炉内の燃料棒は全て引き抜かれ、使用済み燃料プールにおいて冷却されている。今回の地震で泊村の最大震度は2であった。そもそも、原子炉は強固な岩盤に直付けされている上に、一般の建造物に比べてはるかに厳しい耐震強度が、昔から課せられてきた。
つまり、この震度2程度の揺れでは、何ら影響を受けずに運転を続けていたはずである。そうすれば、今次の「全道大停電」は回避できた可能性が高い。ただし、「もし泊原発が再稼働していたならば」という仮説ではあるが。
では、なぜ3・11から7年以上もたっているのに、いまだに原発が再稼働していないのか。そこには東日本大震災当時の首相、菅直人氏の深謀がある。2011年5月、菅氏は首相の立場を最大限に利用し、首都圏に最も近い静岡県の中部電力浜岡原発を、その非望のもとに停止させた。権力を持ってすれば、理にかなわない原発停止要請も事業者に強いることができることを天下に示したのである。
続いて菅氏は、原発が「トントントンと再稼働しない」ための奇手を次々に打っていくことになる。最も強力な手段が2012年9月に発足した原子力規制委員会である。
規制委は「ザル法」と言われる原子力委員会設置法により、強大な権限を持つ「3条委員会」として発足した。そして、その長である原子力規制委員長は絶大なる権力を一身に集めている。そのことを菅氏は2013年4月30日付の北海道新聞に臆面もなく吐露している。
原発ゼロに向けた民主党の工程表は、自民党政権に代わり白紙に戻されました。「トントントンと元に戻るかといえば、戻りません。10基も20基も再稼働するなんてあり得ない。そう簡単に戻らない仕組みを民主党は残した。その象徴が原子力安全・保安院をつぶして原子力規制委員会をつくったことです(中略)独立した規制委の設置は自民党も賛成しました。いまさら元に戻すことはできない」
「北海道新聞」2013年4月30日19面、特集『幻の原発ゼロ』
このように巧妙に仕組まれた「脱原発装置」である原子力規制委の委員長に就いた田中俊一氏は、政権を去った菅氏の「意志」を見事に受け継いだ。菅氏の北海道新聞への吐露に先立つこと1カ月余り、2013年3月19日に俗称「田中私案」なるものを委員会に示したのである。
その文書のタイトルは「新規制施行に向けた基本的な方針」。この文書は暴論極まりない。つまり、文書を作成した責任者の明記がないばかりか、一体この文書が最終的にどのように取り扱われたのか、杳(よう)として知れないのである。
とどのつまり、何ら法的根拠に基づかない私案にもかかわらず、それが大手を振ってまかり通る状況ができたのである。しかも、この私案にはまさに「奸計(かんけい)」が巡らされていた。その最たるものが、国内すべての原子力発電所をいったん全て停止し、運転再開の前提条件となる安全審査を異様に厳しい規制基準の下でゼロからやり直すというものだった。
つまり、菅氏が放った「浜岡原発停止要請」の見事なまでの水平展開を成し遂げたのである。そのことを見届けた上で、上記の北海道新聞紙上での「勝利宣言」と相成ったということになる。「愚相」と揶揄され続けた中での完勝劇であった。
ところで、泊原発の3基の原子炉は加圧水型軽水炉(PWR)である。3・11で重大アクシデントを起こした福島第1原発はいずれも沸騰水型軽水炉(BWR)だった。
両者は、その仕組みにいささかの違いがある。現在、国内で安全審査を通過して稼働している原子炉は9基ある。内訳は九州電力4基、四国電力1基、関西電力4基。いずれもPWRである。
では、他の電力各社のPWRが再稼働にこぎつけている中で、なぜ北海道電力の泊原発は再稼働していないのであろうか。その最大の理由は審査の基準とすべき地震動がなかなか策定されないことにある。2015年12月には、それまでの550ガルから620ガルに引き上げることでいったん決着したかに見えた。しかし、事はそうたやすくはなかった。
基準地震動の策定の際に、これまで必ず問題にされてきたのが「活断層の有無」である。北海道電力の泊原発は他の電力各社のPWRと歩調を合わせるかのように新規制基準に合わせるべく追加的な安全対策を進めてきた。ところが、2017年4月になって、規制委員会から泊原発のある積丹半島西岸の海底に「活断層の存在を否定できない」という判断が下された。
このことによって、泊原発の再稼働は全く先が見通せなくなり、窮地に追い込まれた。なぜか。「活断層の存在を否定できない」という規制委は、北海道電力に「活断層がないことを証明してみよ」と迫っているのである。これはいわゆる「悪魔の証明」であり、立証不可能だ。積丹半島西岸の海底をくまなくボーリングし、活断層がないことを証明するのは現実的ではない。
つまり、非合理極まりない非科学的なことを規制権限を盾に事業者に強いているのである。事業者はその対応に苦慮し、多大な労力と時間を費やすことを強いられているのが現実だ。
もっと言えば、規制委は自ら科学的判断を避けているとも言えるが、これは今に始まったことではない。規制委発足間もない2012年12月、委員長代理の島崎邦彦氏が、日本原電敦賀原発2号機の敷地内の破砕帯について「活断層の可能性が高い」と指摘した。
しかしその後、内外の専門家が科学的に慎重な検討を重ねた上で、この破砕帯は「断層ではない」と報告されている。この活断層の有無をもって、事業者を手玉にとる「島崎ドグマ(偏見)」は、氏が委員会を去った後も亡霊のように生き続けているのである。
ちなみに、震度7に相当する目安の地震動は400ガル以上とされている。よって、仮に620ガルを基準地震動とすれば、泊原発は震度7にも十分耐え得る強度を持つ。もっとも、今回の地震では震源地近くで1505ガルが観測されている。2007年の中越沖地震の際、東京電力柏崎刈羽原発では当時の基準地震動の数倍程度の地震動に対して原子炉は安全に停止した。泊原発では、100~300ガル程度の地震動を検知すれば自動停止する仕組みになっている。 なお、泊原発1~3号機で実際に検知された地震加速度はいずれも10ガル以下であった。つまり、もし今回の地震発生時に泊原発が稼働していれば、全道大停電は防げた公算が大きいのである。
規制委発足から間もなく6年。原子力規制委は一体、いつになれば科学的、技術的リテラシーに欠ける集団から脱皮できるのであろうか。さもなくば、全道大停電のような悲劇がまたいつ国民を襲うかもしれない。言い換えれば、原子力規制自体が「社会リスクを生む」という、国民への背信行為をもうこれ以上許してはならない。
|