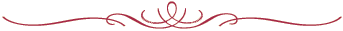
| �Ȋw�Z�p�������u�������̌����v���̂Q |
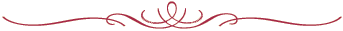
�@�i�ŐV�������Q�O�P�P�D�O�R�D�Q�P���j
| ���^(A)�@���̂̎�ނƋK�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@���q�F�ɂ͊j����̌��ʐ�������������������������Ă���A���ꂪ����ɂȂ�炩�̌����ő�ʂɕ��U�����悤�Ȏ��Ԃɂ�������ƌ��q�F�~�n�̎��ӂɑ��đ傫�ȍЊQ���y�ڂ��悤�ɂȂ邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���̂悤�Ȍ��q�F���̂̐����ɂ��Ď��ۓI�Ȓm���̂Ȃ��������̌����ɂ����Ă͎�X�̉��z�I�ȕ��U�̊ϓ_���痝�_�I�������s���A����� �̌����͌��q�F�̍ЊQ�ɂ��Ă̔F����^���A���̑�������A���i����̂ɖ𗧂����A�����ł́A���q�F�̌p���^�]�Ƃ���Ɋ֘A���������ɂ��m���ƌo��
������ɑ����Ă���A��茻���I�ȑz��Ɋ�đ��u�̌̏Ⴀ�邢�͉^�]�̌��ɂ�ċN�蓾��ƍl�����鎖�̂̌o�܂𐄑������̌��ʂ��l�����Č��q�͔�
�����̈��S����]�������@����ʓI�ɍs���Ă���B�����Ă��̂悤�ȋN�蓾��ƍl�����鎖�̂̂����ōő�̂��́AMaximum Credible
Accident(�ȉ� MCA �Ɨ��̂���) ���N�����Ƃ��Ă����ӂ̌��O�ɑ��ĂقƂ�ǂ̏�Q�����y�ڂ��Ȃ��悤�Ɏ{�݂��A�~�n��I�肷�邱�Ƃ��v������Ă���B�����ŁA���ʉ䍑�ɐݒu��\�肳��
�Ă��鐅��p�F�A�K�X��p�F�̍ň��z�莖�̂ɂ��ĕv�X�̎�ȊJ�����ł���č��A�p���̍l�������T�ς��Ď��ɋL���C
�@(1) ����p�F�� MCA (�č��̍l����)(�Q�l���� (2)�A(3)�A(7))�@�\����p�n�̑傫�Ȕj���̌��ʁA�F�S�̗�p���[���ɍs���Ȃ��Ȃ�A�F�S�̑����ȕ���(10% ���x)�Ɋ܂܂�Ă������������������U����Ċi�[�e����ɏ[�����āA���ꂪ���X�ɘR�k����悤�Ȏ��̂��l�����Ă���B�R�k���͎��̂̒���ɂ����Ė� 0.5% / ���ł��āA(�\ 1 ���Q��)�T�����̑��̎�i�ɂ�Ĉ��͂��ቺ���邽�߁A���̔����㔼����̘R�k�ʂ͖� 0.1% ���x�Ƒz�肳��Ă���B�����̌�������̘R�o�͂��낤���A�����ȏ���A���̋C�ۏ����������\���͏����A�������A���͒ቺ�ɂ��R�k���̌����A�������� ���̕���A�Z���̈ړ����ɂ�āA���̏Ǝ˗ʂ͑Q������X���ɂ���A�ŏ��̔����ȓ��̘R�k�ɂ����̂��x�z�I�ł���ƍl������B �@(2)�K�X��p�F��(�p���̍l����)�@�R���핢�ɏ����ȘR�k�������ԂŁA�ꎟ��p�n���j�����ċ�C���N�����E�����̎_�����i�ޏ���͂������ʁA�����Ԃɘj�đS���x 250�L�����[(�S���������� 2�~103�L�����[����)�Ə��ʂ� Sr �����U�����Ƒz�肵�Ă���B �@�ȏ�̂悤�� MCA �̍ۂ̍ЊQ�͊F���Ƃ��Ă��悢���ł���A�t�ɂ����A�F���ɋ߂����Ƃ����q�F�ݒu�̊�Ƃ���Ă���ɂ�������炸�A�e���Ƃ����q�F���̂ɔ�����O�ҍЊQ�ی����x��݂�����ɂ�����x�ȏ�̎��̂ɑ��Ă͍��ƕ⏞���l�����Ă������ł���B �@���̖����m���āA���q�F�̎��̂����������[���@�艺���čl���Č���ƁAMCA�Ƃ������̂́A�N�蓾��ƐM�����鎖�� credible accidents (�Ⴆ�A���ʂ̕������������ꎟ��p�n�ɏ[������悤�Ȏ���)�ƁA�z����̎��� conceivable accidents (�Ⴆ�A�i�[�e��ɕ������������[�����Ă���Ƃ��������̌����Ŋi�[�e�킪�j������悤�Ȏ���)�̋��E�ɂ�����̂ł��āA�������q�F�̉^�]�o���ɖR�� ���q�ϓI�Ȋ�̓�������ł́A�ǂ��܂ł��N�蓾�� (credible) �ƍl���邩�͐��Ƃ̓��@�Ɋ���f�Ɉˑ�������Ȃ��̉��ɂ���B(Rf3�AP/2407) �@����̉�X�͑��Q�]�����s���ׂ����̂̋K�͂Ƃ��ẮAMCA �ȏ�̉��z�I�Ȏ��̂������đz�������� 100�`1,000 �{�̎��̂ɑ�������105-107�L�����[���U�̏ꍇ���l���邱�Ƃɂ���B�Ȃ����݂܂łɎ��ۂɂ��������̂͏����ŏ��K�̂̂��̂ł��邪�A�Q�l�̂��߂��̎�v�Ȃ��̂ɂ��Ă̊T�����\ 2 �ɂ܂Ƃ߂Ă������B �� 500MW �̌��q�F�̂��̏ꍇ�R�k�ʂ�
�@�\ 2 ��Ȍ��q�F�����@���݂܂łɌ��q�F�Ŕ���������Ȏ��̂� 4 ������B
�@�ȉ��ɂ��̊T�����̂�B �@�@ NRX (�J�i�_�A�`���[�N���o�[������)�@NRX �͓V�R�E�����A�d�������A�y����p�^�A�M�o�� 3 ��KW�̌����F�ł���B
�@�AEBR-1 (�A�����J�A�������q�F������)�@EBR-1�́A���������q���B�F�ŁA�Q�k�E�����ANa��p�^�A�M�o�� 1,400KW �ł���B
�@�B Windscale (�C�M���X)�@Windscale �� Pu ���Y�F�͓V�R�E�����A���������E��C��p�^�ŁA�M�o�͕͂s���B2��̂����A��1���F�Ŏ��̔����B
�@�C NRU(�J�i�_�A�`���[�N���o�[)�@�V�R�E�����A�d�������E�y����p�^�A�M�o�� 20 �� KW �̌����ł���B
�@I �T�^�I���q�F�ƘF���̕����������̗e���@�l�@���錴�q�F�̓E������R���Ƃ���M�o�͖� 50 ��KW�A�����q������ 1013�̌��q�F�ŕ��ϔR����֎����� 4 �N�Ƃ���B���̒����ʼn��肳��鎖�̂͘F���R�������t�ɒB���������������ő�ɂȂČ�ɂ�������̂ƍl����B�R����ւ̎������Ƃ����ƁA��� �~�n�����̍��łׂ̂�悤�ɕ~�n�͎�Ƃ��ē��͘F�p�n�Ƃ����ϓ_���炫�߂�̂ŁA�{�����̌��ʂ͓��͘F�̏ꍇ�ɍł��悭�K��������̂ł���B�����o�͂ł� �Ă��ޗ������F�̏ꍇ�͔R���T�C�N�����Z���Ƒz�������̂ŁA���˔\�����ʂƂ��̓��������ς����A�R���̎�ށA�^�]���@�̑���Ȃǂɂ�ē������U �L�����[���̏ꍇ�̑��Q�z�͎�ϓ�������̂Ǝv����B�����Ƃ����͘F�Ɋւ��邩���茻�݂ɂ����Ă͔R�ė��̌���Ɖ^�]���R����ւ��i���̕����ł��邱 �ƁA���݂̐v�l���W�߂Ă݂�Ƒ�G�c�ɂ��� 1 �N�Ȃ������N�ɂ킽�Ă��邱�ƁA�X�ɐg�̏�Q�ɉe�������j��̃C���x���g���[�͂���ʂ̔R�Ď��Ԃł͖����O�a�ʂɒB���Ă��Ȃ����ƁA�Ȃǂ���L�̂悤 �ȍl�����ɂ�Ĕ��f���A�R���T�C�N���� 4 �N�Ƃ��邱�Ƃɂ����B���̂悤�Ȍ��q�F���ɂ��镪���������̑g�����v�Z���B�����ɂׂ̂���o�̊������l�����āA���o���������� 1 �L�����[���Ɋ܂܂��X�̊j��ʂ̃L�����[�����߂� (���^(D)�̕\1���Q��) �@II ���U����镪���������̑e���@���˔\�������R���̂�n�Z�����A���U�����W�߂�Ƃ����ŋߍs��ꂽ��A�̏d�v�Ȏ����̌��ʂɂ��A���U�̊����͎�Ƃ��ĕ����������̏��C���ɂ�邱�Ƃ��������Ă���A���̒l�͑�̎��̒ʂ�ł���B
�@�]�āA�����ł͂��̊����ŕ��������������U�����ꍇ����ɑz�肵���B�������Ȃ���A���̓_�Ɋւ��Ă͍���̌����ɂ܂ׂ��_�������̂ŁA�ɒ[�ꍇ�Ƃ��� �������������A���̓����ʂɔ�Ⴕ�Ĉ�l�ɕ��U�����ꍇ���z�肵���B �@III ���o�����������̐����@��X�̋C�ۏ����̂��Ƃł̕����ɂ�����e�����Z�o����Ƃ��ł��d�v�ȗv�f�͕��U���Ԃƕ��o�����Ɋ܂܂�闱�q�̗��x���z�ƕ��o���̉����̉��x�Ƃł� ��B���U���Ԃɂ��ẮA�R���̎_�������̓R���e�i�[����̘R�k�Ȃǂ̂悤�Ȕ�r�I�����Ԃɂ킽����o���\����ꍇ�Ƃ��Đ����Ԃɘj�ĕ��U�����ꍇ �Ǝ��̒���Z���Ԃɕ��U����镧�ꍇ�̓��z�肵���B �@���q�̗��x���z�Ɖ����̉��x�ɂ��ẮAWASH �ŗ^�����Ă���ȏ�̋�̓I�ȍ��������邱�Ƃ͎��ۂɕs�\�ł����̂ŁAWASH �̒l�����̂܂܍̗p���A���ꂼ�ꂨ���肻���Ǝv����ꍇ���\���� 2 �̏ꍇ���l�����B���Ȃ킿���o���x�ɑ��Ă͏퉷�ƍ���(3000��F�A1650��C)�Ƃ��Ƃ��B �@���x���z�͉��ƍH��o�̓T�^�ɑ������钼�a 1�ʁA7�ʂ����ꂻ�ꎿ�ʒ����l�Ƃ����̕��z���l�����B �@�Q �l �� ��
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@���^(B)�@�z�肷�錴�q�F�ݒu�_�Ǝ��ӂ̏� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@I �T�^�I�~�n�@���Q�̕]���ɓ��ẮA���q�F���ݒu�����n��̏�z�肷��K�v������B�������킪���ł́A��^���q�F�̕~�n�Ƃ��Č��݊m�肵�Ă���͓̂��C���ȊO�ɂȂ����~�n��Ƃ������̂��m�肵�Ă��Ȃ�����Ȃ̂œT�^�I�Ȍ��q�F�~�n��z�肷�邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł���B �@�����œ��C������ю�̑�^���q�F���n�̎��ӏ������������ʁA�����ł͓d�͎��v�̒��S�n�ł����s�s���炨�悻 100Km �Ȃ��� 150km ����A���C�݂ɖʂ����C�ӂ� 2�A3 �̒n�_��I�сA�����ɂ��ƂÂ��ėތ^�I�Ȍ��q�F�~�n�Ǝ��ӂ̏�z�肷�邱�Ƃɂ����B �@�d�͎��v���S�n����̋����͑��d��ɂ��֘A�����R�߂����L���ł��邪�A�u���S���̍l���ɂ�āA�ݗ����d���~�n�Ƃ��čœK�ł���Ǝv����n�_����A30�}�C�����ꂽ�ꏊ�ɐݒu������̂Ƒz�肷��v�Ƃ����A�����J���ł̍l���� (1) ����݂Ă��A��L�̐����́A�l�����x�̍����킪���̏ꍇ�A�\���Ó��Ȃ��̂Ǝv����B �@�܂��C�ݕ��߂ɐݒu����Ƃ����̂́A�펞���ʂ̗�p�p�����͐�݂̂��瓾�邱�Ƃ́A�킪���͐�̎��Ԃ���݂Ă��Ȃ�̍��������ƍl�����邩��ł���B �@����ɁA�킪���̈�ʓI�n�����������l������K�v�������B���m�̂悤�ɁA�킪���͖k������쐼�ɂ����Čʏ�ɒ����̂т������ł��邪�A�� �� 200Km �Ȃ��� 300Km �̋����ȕ��������n�̒������ɂ́A�w�ŎR�������Ă���A���݂���щ͐�ɂ��ċ͂��ɕ��암�����݂���݂̂ł���B �@�l���͊T�˂��̕��암�ɏW�Ă��邪�A���̂�����r�I�L�����ϕ�����Ȃ��A���p�ɖʂ������l�A��_�A�����n��ɂ͂Ƃ��ɐl�������W���S���l���̖� 1/3 �����̒n��ɂ����ď������{�� 3 ��G�ƒn�т��`�����Ă���B���Ƃ��A�S���̕��ϐl�����x�� 241 �l/Km2�ł���̂ɑ��āA�����s�敔�̐l�����x�� 12,236.8�l /Km2�A���s��12.591.2�l/Km2�A���É��s�� 5,345.6�l/Km2�ŁA���̒��ɂ� 3 ���l���z�������l�����x�������n�悷�炠��B �@�{�����Ɏg�p�������� (2) �́A���a 30 �N�̍��������ɂ��ƂÂ������̂ł��邪�A�l���̑����A�Ƃ��ɓs�s���ɂ����鍂�����������w�E���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿���a 25 �N�`���a 30 �N�̑S�����ϑ������́A7.3% �ł����̂ɑ��āA�����s�敔 29.4%�A���s 26,4%�A���É��s 23.4%�ł����B �@�Ȃ��A�킪���͎l�ʊC�ɐڂ��Ă��邪�A�} 1 ���疾���Ȃ悤�ɁA�͂� 1,000Km �Ȃ��� 1,500Km �ɂ��āA�\�A�A�����A���N�ȂǏ��O���̗̓y�ɒB���邱�Ƃ��A���Q�]���̏ォ�炠�炩���ߏ\�����ӂ��Ă����K�v������Ǝv����D �@�ȏ�̉��肨��т킪���̓�������A���Q�]���ɕK�v�Ȍ��q�F�ݒu�_����т��̎��ӂ̏�ތ^�����āA�}2 �Ɏ����悤�Ȃ��̂ɑz�肵���B �@���Ȃ킿�A�S�ʓI�Ȓn�`�̊O�ςƂ��āA�C�ݐ��ɕ��s�ɑ���R�n���l���A500km ����� 1,000m �̓����������q�F�̐ݒu�����C�݂��炻�ꂻ�� 80Km ����� 100Km �̒n�_�ɂ�����̂Ƃ����B �@���q�F�̕~�n���E�́A�A�����J�� 2�A3 �̗�����Q�l�Ƃ��A���̔��a�� 800m �Ɖ��肵�� (�V�c�s���O�|�[�g�A2,600�t�B�[�g�A�����L�[�A2,000�t�C�[�g�A�h���X�f�� 2,600�t�B�[�g)�B �@���ɁA���q�F���ӂ̐l�����z�ɂ��ẮA���q�F����50Km �Ɏ���n��̎��ۂ̐l���ɂ��Ē��ׂ����ʁA���q�F���甼�a 20Km �ȓ��̒n��ɂ�����l���́A�} 3 �Ɏ�����Ă���悤�ɁA �@P = 393R2.19( P �͔��a RKm �̔��~���̐l��)
�@�̎��ɏ]�đ�������ƍl����̂��A�K���ł��邱�Ƃ��킩���B20Km �ȉ��̒n��ɂ��ẮA�} 3 �ł������Ȃ悤�ɑ����̌X�����قɂ��Ă���ʂɍl�����邱�Ƃɂ����B �@�} 4 �͉�X����グ���n�_�̂��� 2�A3 �̂��̂ɂ��āA���̎��Ӓn��ɂ�����s�s�̕��z���������̂ł��邪�A����͊e�n�_�ɂ�������̂����q�F�𒆐S�Ƃ�������~���ɁA��S�s�Ɍ��������� ��v�����ăv���b�g�������̂ŁA����ɂ�ĊT�����̓�����m�邱�Ƃ��ł����B���Ȃ킿�A���q�F���� 100Km �Ȃ��� 140Km �ɑ�s�s���W�����Ă���A��������s�s�̎��� 30Km �Ȃ��� 40Km �ɂ��Ȃ�l���̖��W�������邱�ƁA�܂����q�F���� 15Km�A�Ȃ��� 20Km �ɁA�����s�s�̎U�����Ă��邱�Ƃ�������ꂽ�B �@�����œs�s�l���̎��Ԃ������ׂ��̂����A�����ތ^�I�ɁA���̂悤�Ȃ��̂ɑz�肵���B���Ȃ킿�A��s�s�͌��q�F���� 120Km �̒n�_�ɂ���A���̕�����͒��a 25Km �̉~�ŁA�l�����x�� 12,200�l/Km2 �ł��� (�S�l�� �� 600 ���l)�B����ɂ��̎���ɐl�����x 2,200�l/Km2�A20Km �̕������s�s���Ӓn�т�����B�܂��A���q�F�̔�r�I�ߖT�ɂ��钆���s�s�́B���q�F���� 20Km �̋����ɂ���A�l�� 10 ���l�A���̊g����͒��a 10Km �̉~�ł��� (�l�����x 1,270 �l/Km2)�B���̑��̒n��ɂ��Ă��S���̕��ϐl������ъC�ݒn�т̓������l�����āA300�l/Km2 �̐l�����x�ň�l�Ɋg���Ă�����̂Ƃ���B �@���̎��ɂ�������ː������̊g�U�Ƃ���ɂ�鑹�Q�]���̐��i���炵�āA�ł��d�v�ł���͉̂����̒ʉ߂���n�т̐l�����x�Ɗg����Ƃł���A�܂����̂̒��x�A���q�F����̋����̑��֊W�ɂ�āA�S�l�����܂��d�v�Ȉ��q�ƂȂĂ���̂ł��낤�B �@���������d�v�x�̍l�@����A���ϓI�Ƃ��������ނ���ތ^�I�ɏ�L�̐������������̂ł��邪�A����ɂ�đ��Q�̉ߏ��]������������ł��낤���A�܂��s���ɉߑ�Ȃ��̂Ƃ��Ȃ�Ȃ��ł��낤�B �@�Ȃ��A���q�F���C�݂ɐݒu������̂Ƒz�肵�����R�̌��ʂƂ��āA�����Ƃɑ���l�����K�v�ƂȂ�B�S���̊C�݉����� 26,819.1Km �ł���̂ɑ��āA�� 1 ��Ȃ����� 4 ��̋��`������ 2,627 �`�ŁA�C�ݐ��� 10Km �� 1 ���`�̕��z�����ƂȂ�B �@(�� 1 �� 2,199�A�� 2 �� 294�A�� 3 �� 78�A�� 4 �� 56�B�v 2,627 �\ ���a 32 �N(3)) �@�ȏ�̂悤�ɁA���q�F�ݒu�_����т��̎��ӂ̏�z�肵�����A������̒ʂ�̕~���n�������ɑ��݂��邩�ǂ����͕ʖ��ł���A�܂��� �ꂪ�~�n��ƂȂ�ׂ����̂ł��Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�������Ƃ��āA����͑S�����I�ȑz��ł��Ȃ��B���q�F����s�s���炨�悻 100Km �Ȃ��� 150Km �̊C�ݕ��߂ɐݒu�����Ƃ���A�����炭������z��������Ȃ�Ȃ��̂Ƃ��čl����������Ȃ��Ȃ�ł��낤�B �@�Q�l����
�@II �~�n�ƋC���@��ɓT�^�I�~���n�Ƃ��ĂƂ�グ���~���n�ɂ�����C�ۏ����ɂ��ẮAWASH �̃f�[�^�����̂܂g�����Ƃ���邳��Ȃ��̂͂����܂ł��Ȃ��B��X�͓T�^�I�~�n���쐬�����Ƃ��Ƃ肠�������C���ق����n�_�̂��������Ɋϑ��f�[�^������ ������̂ɂ��Ăł��邾�����m�Ȏ��������邱�Ƃ������������A��X���K�v�Ƃ���f�[�^�����ׂĂ���Ă���n�_�͂قƂ�ǂȂ��̂ŁA���ԓI�����I�Ȑ��� ���l�����āA���C�����߂Ɠ������Ďq���߂� 2 �����ɂ��ċC�ے��ϑ����̋����Ē������s�Ȃ��B�Ȃ��Ďq���߂��Ƃ肠�����Ƃ������Ƃ́A�Ďq���߂ɑ�^�F�̌��n�����݂���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A �������̌��n�Ɩڂ���Ă���n�_�ƋC�ۏ���r�I���Ă���Ɣ��f���ꂩ�f�[�^��������x�������Ă���Ƃ������R�ɂ��ƂÂ����̂ł���B���ʓI�ɂ� �ĕ\���{�A�����{�̑�\�I�Ǝv���� 2 �n�_���ΏۂɂƂ肠�����̂ŁA���݂̂悤�ȕ~�n�I��̍l�����ɂ�ĕ~�n���I��邩����A�����ɓ���ꂽ�C�ۃf�[�^�͂��Ȃ�̕��Ր������Ă���� �̂Ǝv����B���ꂻ��̌��ʂ͎��̏��\�̒ʂ�ł���B���̃f�[�^�ω��������̂�T�^�I�~�n�ɂ�����C�ۏ����Ƃ݂Ȃ��āA�g�U�������Ȃǂɓ����퐔 �͂���ɂ���B
�@1. �������@�@(1) ����
�@(2) �t�]�A�Ă����̋敪�@1 �� 2 ��̍��w�ϑ��ł͊e�����ɑ���߂��Ȃ��̂ŁA�������Q�Ƃ̏㑼�̋C�ۊϑ�����(�_�A�V�C����)���狁�߂��B�_�A�V�C�Ƌt�]�A�Ă����Ƃ̊W�͍�ʌ� ����s�̓S���ɂ�錸���ϑ����ʂȂ�҂ɉp���C�ۋǂ̈���x�A���ޕ��@���Q�Ƃ��Ď��̋K���ɂ�蕪�ނ����B
�@(3)�@1 �� 2 �� (0�A12��)�̑S���̍��w�ϑ����ʂ���n��� 200m �̍����̉��x������C/100m �ɂ��Ă��ꂼ��Ă����A�t�]�̕��ό��������߂Ă݂����S���Ƃ��قƂ�Ǔ����l�ł����̂őS�����ς�p�����B�@(4) �~ �� ��
�@2 �������ʂ̕]���@(1) �Ă����A�t�]�̔������ԗ��ɂ����@WASH �ɂ���č��̔������ԗ��� 1 �� 2 ��̓��莞���̊ϑ��l�݂̂�p���ē��v�������̂Ǝv���A��₩������l�ƂȂ邪�A����̒����ł� 1 �� 8 ��̎�����p���ċ��߂Ă���̂ň�w�Ȃ炳�ꂽ���ϒl�ƍl���鎖���ł���B �@�Ȃ��A��ʌ�����s�̓S������ 300m �ɂ����Ė� 1 �N�� (1943 �` 1944�N)�ɂ킽�薈���Ԃ̉��x�ϑ����s���Ă���̂ŁA���̎����ɂ�肵��ׂ����ʂ͂Ă��� 64% �t�] 36% �ō���̒���(���C��)�ƂقƂ�Ǔ����l�������Ă���B �@(2)�~�J���Ԃɂ����@�~����Ԃŋt�]�����݂��邱�Ƃ͋C�ۊw�I�ɂ����ɂ킸���̉Ɨ\�z����邪�A����̒����ł��S���Ԃ� 1% �ȉ��ł����B�����Ɏ������B����s�̓S���̊ϑ��ɂ��ƁA�t�] 106 ���̂����킸�� 3 �����~�����ɔ�������t�]�Ƃ��Ċϑ�����A�S���Ԃɑ��Ă� 1% �ȉ��ƂȂ��BWASH �ɂ���S���Ԃ� 3% ���t�]�ō~�����Ƃ��Ȃ��Ƃ����č��̌��ʂƂ͎�ق錋�ʂƂȂ��B �@(3) �n��ɂ��Ⴂ�ɂ����@�C��w�I�Ɍ���Ɠ��C���͕\���{�I�A�Ďq�n���͗����{�I�ȋC����������Ă��邻�̉e�����ł��悭�����Ă���̂͋t�]�A�Ă����̔䗦�ł��āA�� �q�n���ł��~�G�A�܁A�J�V�������̂ŋt�]�̔䗦���������B����Ɋ֘A���ĕĎq�n���͍~�J���Ԃ������B�܂��t�]���̋C����p�ٕ\���{�̕������ɑ傫���̂� �����������ł���B��w���̕����p�x�͗��n���Ƃ��吨�I�ɂ͂悭���Ă��邪�n�㕗���͊C�ݐ��A�n�`�Ȃǂ̉e�����傫�������Ă���̂ŁA�H�Ⴂ���傫���ǒn ����������������Ă���B �} 4 �z�茴�q�F�ݒu�_���ӂɂ�����s�s���z�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@���^(C)�@�����̊g�U�A���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�� �� �� ���@���q�F�̎��̂ɂƂ��Ȃĕ��ː������͌��q�F�̕����n��̋�Ԃ���ђn�\�ɕ��z����B�����Ă��̔Z�x���z�̗l�q�́A���q�F���߂ł́A���̗̂l���A�� �Ȃ킿�A���ː������̎�ށA���x�A���o�p�����ԁA���o���x��C�ۏ�Ԃɂ�č��E�����B���q�F���牓���͂Ȃꂽ�Ƃ���ł́A��Ƃ��ċC�ۈ��q�����ː��� ���̔Z�x���z�ɉe�����y�ڂ��B�{���^�ł͕��z�̌��ς�߂��߂̕������A����сA���o���̏��������A�C�ۈ��q���g�U�ɋy�ڂ��e�����L�q����B �@I ���o���̏��������@���o���́A���ː������̋C�̂���є����q����Ȃ鉌���Ƃ��ĕ����n��ɉ^���̂ł��邩��A���o���x�ƕ��o�̍s�Ȃ��鎞�ԂƂ͊g�U�ɂ�����d�v �Ȉ��q�ł���B�����́A����������q�F�̎��̗̂l���Ɉˑ����Ă���B�g�U�̂͂��܂���o���̍����́A���̌�̒n�\�ʂł̔Z�x�ɑ傫���e������B�������� �o���x�ƍ����Ƃ̊W�͌��݂̂Ƃ��됸���ɂ͒m���Ă��Ȃ��B�{�����ł� WASH �ɂ��������������o�̏ꍇ�ɂ́A�������ɂ� 860m�A���]���ɂ� 400m �ɏ㏸������̂Ƃ����B����͕��o���� 1,650��C �̏ꍇ�ɑΉ����Ă���B �@II �g�U�������ɂ����@��C�g�U�̎����͋K�͂��傫���Ȃ�A������@����ё��u���ȒP�łȂ��l���A�o����傫���Ȃ�̂ł��܂�s���Ă��Ȃ��B�]�āA���������͌̕� �Ɉ��p������O�̂��̈ȊO�͂قƂ�ǂȂ��Ƃ��Ă悢�B�����������͔�r�I�ߋ��G�̎����݂̂ł���B�������āA��C���̊g�U�̌����̑啔���͗��_�I �����ł���B���̏�A����痝�_�I�������A�Z�x�̋�ԕ��z�m�Ɏ�������^����͏��Ȃ��A���̕��z�̕W���������Ԃ��邢�͕��������Ƌ��ɂǂ̂悤 �ɕς邩�A�C�w�̈���x�Ƃ̊W�͂ǂ����Ƃ��������������B(1)����ɑ����ۏ�K�v�ȋ�ԓn�x���z�Ɍv�Z�o�����̓I�̎����������o����Ă���B (2)(3)(4)(5) �����́A���Ƃ��� WASH ���w�E����悤�ɁA�����ȗ��_�I�����ɗ����̂ł͂Ȃ����A�g�U�̃p�����[�^�[�ɓK���Ȓl���Ƃ�Ȃ�A�����Ă��̎��́A�������͈͓��̐��x�Ŏg�p���� ���Ƃ��ł�����̂Ƃ݂��Ă���B�Ȃ��ł� Sutton �ɂ�ė^����ꂽ���́A���ۂ̌v�Z��K���ƍl�����A�A�����J�ɂ�����ЊQ�]���v��� (Hazard Summary Report)(6)�A�C�M���X�C�ۋǂ̕��@(7)�Ȃnj��ݍs���Ă��鎖�̉�͂̑啔���͂��̎��ɂ��ƂÂ��Ē��ړI�A�ԐړI�Ɍv�Z�����{���Ă���B �@Sutton �̎� �����_�ɑ��� Sutton �̎��́A�����̓_(x�Ay�Az)�ł̋�ԔZ�x�� �� �Ƃ���A�i�}���j�ŗ^������B���T�� h �͌��̒n�㍂�Ax�Ay�Az �͂��ꂼ��Z�x����n�_�̌�����̕��������A������牡�����̋�������ђn�㍂�ł���Aq �͒P�ʎ��Ԃ̕��o�ʁAu �͕��ϕ����An�ACy�ACz �͋C�ۏ�Ԃɂ���܂�퐔�ł���B �@���̎�X�̏�Ԃɑ����A�̔Z�x�v�Z���������Ă��邪�A���̎��̌`�A�Ƃ��ɐ����Z�x���z�������l�ƌ����ɔ�r���Ă��̑Ó������f�[�^�̒ɂ� �ċᖡ�����_���͂Ȃ��A�܂�n�ACy�AC�� �̒l�ƋC�ۏ����Ƃ̊W�����m�ɒ�߂��Ă͂��Ȃ��B�����̘_�����Ƃ��Ό�L�� Chamberlain (13) �̘_���� Sutton �ɂ�ė^����ꂽ�l�̎�X�ȕs��v���w�E���Ă���B �@������������ȍ���͗��_���ꎩ�g���琶���Ă�����A�ނ����C�̏�ԕω��̑��l�����痈����̂Ƃ݂���B �@���̎� ���(7) �� Sutton �ɂ�鐂���Z�x���z�̎��������ƍ���Ȃ��_�����ǂ��邽�߁A�V���������������������ʂ̌`�̎����B���Ȃ킿(1)�����(2)�ɑ����A�i�}���j���A����ł���B������ J0 �͗뎟�̑� 1 �� Bessel �����ł���Ai �͋����P�ʂ܂����A���Am�Am1 �͋C�ۂ̃p�����[�^�[�ł���B �@���҂̎��̂Ƃ��ɑ傫�����ق�(1)�����(3)�ɔ���悤�ɁA���������̊g�U���������̒���(1)�ł� Z2 �Ƃ��āA(3) �ł� Z �Ƃ��ē��Ă��邵�A������ɓ���� B �� (1) �ł́�B�ł��� (3) �ł� B �ł���B�������Đ������z�̍��̑��ɕ��������ɂ��Z�x�̋H�ߗ��ɑ傢�ɍ�������A���̍��͉������̊g�U�ɂ͒��邵���e������B���̎��� Sutton �̎��̔�r�́A�ŋߌ��\���ꂽ�����ȔZ�x�̋�ԕ��z�̑���̕� (8)(9)(2) �ɂ��Ƃ����āA��㎩�g�ɂ�ĂȂ���Ă���B(10)(11) �����ł͂��̌��ʂɂ��ďڂ����q�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�ߋ����ɂ��Ă͐����Z�x���z����Ґ����Z�x���z�ɂ��āA Sutton �̎������̎������悢�\�v���������Ɣ��\����Ă���B �@�p���C�ۋǂ̕��@ ���̕��@�� 1959 �N�p���C�ۋǂ����\�������̂� (7) ������u�p���@�v�Ƃ��Ă�����̂ł���B����� Sutton �̎�����b�ɂ��n��Z�x���A�i�}���j�ŗ^����B���͌�����̋����A�Ƃ͂��̋����ōő�Z�x�� 1/10 �̔Z�x�ɂȂ闼�[�̈ʒu�̊p�����AH �͉_�̍����ł��āA�Ƃ���� H �͋C�ۏ�Ԃ��Ȃ킿�A�����A���ˁA�_�ʂɂ�Ē�܂� A�`F �� 6 �̃J�e�S���[�ɂ��Ă��ꂼ��}����ѕ\�ɂ�ė^�����Ă���B���̕��@�̌v�Z�͔�r�I�ȒP�ő�̂̌��ς���ɂ͈ꉞ���p�o���邪�����Ƃ̔�r������ ����Ă��Ȃ��B���a 34 �N 2 ������� 6 ���Ɍ��q�͋C�ے�����s�����˂���ѓ��C���ɂ����� 4 ��̒�����Ԃ̕��̊g�U�����̌��ʂ��������ݓ���ł�������Ƃ̔�r�̕ł���ɂ��A10�y1 �͈͓̔��ō����Ƃ̌��_���o����Ă���B(12) �Ȃ��A�����Z�x�ɂ��ď�L�O�҂��r���Č��ʂ��} 1 ������} 2 �Ɏ����B �@�{�����ŁA�l�I���Q����ѕ��I���Q�̎��Z�ɂ��������g�U�̕������� Sutton �̎��ł��鐂�������ɕ��z�Ɋւ��āA�ߋ����ł̎����l��m�ACy�ACz�A�̋C�ۃp�����[�^�[�̋C�ۊw�I�����ɂ��Ă��낢����_���w�E����Ă���B���� Sutton �̎���I�͎̂�ɂ��̗��R�ɂ�Ă���B�܂��p���C�ۋǂ̕��@�͌v�Z���ȒP�ŁA�����n��ɂ�������o�����z�̂��������̗l�q��m�邽�߂ɂ͕֗��ł� �邪�A�����I�ɂ���킳��Ă��炸�A�{�����ŗ��p���邽�߂ɂ͕s�ւȂ̂ō̗p���Ȃ����B�܂����C���ł̎����A���̑��ߋ����̎����̔�r�ł悢���ʂ� �Ƃ�������̎��� Sutton �̎����r�����Ƃ��낷�łɎw�E�����悤�ɉ������ő傫�ȍ�������ꂽ�B�} 4 �ɒn�\�ʂł̔Z�x���z���r�������̂������B���̐}�̌v�Z�ɗp����ꂽ�C�ۃp�����[�^�[�� Sutton �̎��ɂ��Ă� WASH �ɂ����Ďg�p���ꂽ�T�^�I��������ѓT�^�I�t�]�ɑ���l��p�����̎��ɂ��ẮA�C�w�̈���x�������Ă̂�����������ыt�]�ɑΉ�������̂Ƃ��� 0 ����� 0.3 ���I��v�Z�ɂ����Ă���B���̔�Z����A�����́A Sutton �̎����������AWASH �ł����Ă���o�����[�^�[�ɂ��Ζ{�����ŗv������Ă���悤�ȍЊQ�̏���Ɖ������������Ƃ��ł�����̂Ɣ��f�����B���Ȃ킿�A���̏���͉ߏ��]���� �ȂĂ��Ȃ��Ƃ����_�ŁA�܂������͉ߑ�]���ɂȂĂ��Ȃ��Ƃ����_�ŁA�\���Ӗ��������̂ł�����} 4 ����эl�����̂ł���B �@�Ȃ��A�} 5 �ɂ� Sutton �̎��ɂ�����p�����[�^�[���A���Ƃ��A�ŋߖ��ɂȂ� Farmer �_��(14) ���邢�� Chamberlain ��(15)���g�p���Ă���l�������ꍇ���̔Z�x���z���ǂ��ς邩�e����������ʐς��ǂ��ς邩�������Ă���B
�@�g�U�̌��ʂ��} 6 �����} 10 �ɗv��Ă���B(���U���} 9 �A�} 10 �� 107�L�� ���[�̕��o�ɂ��Đl�I��Q�̗l�q��Ꭶ�������̂ł���B)�����ɂ��t�]��Ԃƒ�����ԂƂł͂������邵������������B���Ȃ킿�A�t�]���ɂ͔Z�x �̂��Ȃ�Z�������������������܂ʼn^���\��������Ƃ������Ƃł���B�������C�ۏ�Ԃ������Ԃɂ킽�Čp������ƍl���邱�Ƃ͌����I�łȂ��B �������A����ł����������Ȃ�̋����ɒB����ƍl�����悤���A�܂������Ȃǂ̕ω��́A���ϓI�ɂ͔Z�x�͔����Ȃ�ł��낤���A�e����������ʐς͂��Ɗg ����ł��낤�B�i�[�\�������j�����̋}���ȕ��o�Ƃ��ĉ��肳�ꂽ�������o�̏ꍇ�ɂ͉����͍ŏ��㏸���A���ꂩ��g�U���Ēn�\�ɂ��ǂĂ���B���̍� �����o�̏ꍇ�ɂ͑�C�ɂ��H�߂������ʂ��傫���̂Œn�\�ʂł̕��o��蓖�R�n�\�ő�Z�x�͏������Ȃ�A�܂��A���q�F����͂Ȃꂽ���̒n�_�ōő�ɂ� ��B �@III �����ƉJ�ɂ��~���@���q�F������U���ꂽ���ː������������q���邢�͋C�̂Ƃ��Ċg�U����ꍇ�n�\�ʂɒ���������A�܂��J�ɂ�Ē��������肷�邱�Ƃ����R�\�z����� ���B���̊ԑ�́A���q�F���̂̔����܂��͌��q�F�̉��˓�����̋C�̕��ː������p���ɂƂ��ȂāA�����n��̔_�앨�A�q���A���O�̋��Z�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ� �d�v�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B �@�}6�A�}7�A�} 8 �͂����̌��ʂ��l�������ꍇ�̕����n�\�ʂ̔Z�x������킵�Ă���B �@�{�����ł͒��҂���э~�J�̌��ʂ̖��ɂ��Ă̎戵�� WASH �Ɠ��l Chamberlain �ɂ�錤���̌��ʂ��g���B�����������q�̒��~���x�Ƃ��Ă͎��ʒ����l���a�� 1 �ʂ̗��q�O���[�v�ɑ��Ă� 10-4m/sec 7�� �̗��q�ɂ� 10-2m/sec �Ƃ����l���������Ă���B �@Chamberlain �ɂ��A���V�ł́A�����q�́A���̂����̒Ⴂ������������N��Ɖ��肳��A�܂��n��ɒ����������q�̗ʂ������o���̋����������Ɍ��������Ɠ����e������ ������̂ƁA���肷��B���Ȃ킿 Sutton �̎������������ꍇ������ �� �� Vg �~���x�Ƃ�����A�i�}���j�B�܂��A�n��Z�x�́A�i�}���j�B �@�J�ɂ�Ă�������o���̍~���̂��߂ɋɑ��݂���ʂ̌����́A�ł���킳��A�������ĕ��V���̔Z�x�͊g�U�̎��ɂ��̈��q��������悢���ƂɂȂ�B���̏ꍇ�̃��̒l�� Chamberlain �ɂ�ė^�����Ă��̂��g���B(�\ 2 �́A�����̌v�Z�Ɏg�p�����l������) �@����J�ɂ��n�\�ɉ^�ꂽ�ʃւ́A�i�}���j�ŕ\�킳���B�J�ɂ��Ȃ������ʂ���э~�J�ɂ�钾���ʂ��} 12 �ȉ��Ɏ�����Ă���B
�@�����ɂ����ʂ��n��Z�x�ɋy�ڂ��͎̂��ʒ����l 7�ʑ����̗��q�ŁA�������t�]���̏� ���ɑ傫���B�܂��~�J�̉e���͒������ɗ��q�̑傫���ꍇ�ɂ����Ă���B�Ȃ��A�~�J�̌� �ʂ�(6)������킩��悤�ɍ������o�ł����o���̍����̉e���͂�����Ă��Ȃ��B �@�Q�l����
�@�}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)