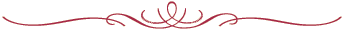
| 日本に於ける原子力政策史その2 |
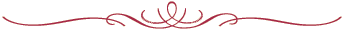
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5).1.19日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「日本に於ける原子力政策史その2」をものしておく。れんだいこの理解が弱くスケッチ風にしか書き込めないが次の要点を確認しておく。広瀬隆・著「腐食の連鎖」、「オウム事件の本番」、藤田祐幸(慶応大)氏の「日本の原子力政策の軍事的側面」、「2004年日本物理学会第59回年次大会
社会的責任シンポジウム 現代の戦争と物理学者の倫理とは」、「阿修羅原発版」、有馬哲夫氏の「原発・正力・CIA」(新潮社 、2008.2月初版)その他を参照する。2012年4月、書店で鬼塚英昭著「黒い絆 ロスチャイルドと原発マフィア 」(成甲書房; 2011.5.21日初版 )を見つけ購入した。貴重な資料がふんだんに取り入れられているので、これを取り込むことにする。 日本の原子力史を検証して判明する事は、日本の原子力行政が、「正力-中曽根コンビ」によって推進されたということである。しかも、恐ろしいほど政治政争絡みであり、原子力と軍事防衛と宇宙開発が三点セットで推進されていったということである。「我が国における原子力行政の闇」の部分であり、以下、二人の動きを中心に見ていくことにする。 「ウィキペディア原子力事故」、「ウィキペディア原子力事故の一覧」、「日本の原子力関連事故一覧」参照。 2007.7.21日、2012.05.19日再編集 れんだいこ拝 |
| 【商業用原子炉の運転開始】 |
| 1970.3.14日、日本初の商業用軽水炉として、日本原子力発電の敦賀1号機が大阪万博開幕に合わせて稼働し、万博会場への送電を開始した。 1970.11月、関西電力の美浜1号機が運転開始する。日本における商業用原子炉の運転開始日となる。 1971.3月、東京電力の福島第一原発1号機が運転開始する。 1971.5.19日、美浜1号機で安全注入の誤信号のため原子炉自動停止。 1971.11.24日、社会党の欠席の元に沖縄返還協定が成立し、同時に非核三原則が付帯決議として衆議院で採択された。吉田茂以来日本政府は一貫して核保有は合憲であると言い続けてきたが、佐藤政権は初めて国策としての非核を鮮明にした。これが1974年の佐藤栄作ノーベル平和賞受賞に結実する。 ところで、ノルウェーのノーベル賞委員会が20011年に出版した「ノーベル平和賞・平和への百年」の中で、「佐藤氏はベトナム戦争で米政策を全面的に支持し、日本は米軍の補給基地として重要な役割を果たした。後に公開された米公文書によると、佐藤氏は日本の非核政策をナンセンスだと言っていた」などとして、「佐藤氏を選んだことはノーベル賞委員会が犯した最大の誤り」であったとして当時の選考委員会を批判している(2001.9.5日、朝日新聞)。 |
| 【1972-74年の田中政権時代の原子力行政】 | ||
|
1972.7月、関西電力の美浜2号機が運転開始する。
原発政策について「五、つりあいのとれた産業発展」のなかで次のように書いている。
1974.6月、田中政権下で、原発の立地支援のための交付金などを定めた電源3法(電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法)を成立させた。これにより原発交付金の仕組みができる。
|
||
|
|
||
| 田中政権の原子力推進行政はオイルショックに伴うものだったとはいえ、角栄唯一の失政と窺う。この当時、原発のそのものの技術的不完全性、悪魔科学性の知見が弱かった時なので割引せねばなるまいが。 2013.7.8日 れんだいこ拝 |
| 1971/5/19 | 美浜1号 | 安全注入の誤信号のため原子炉自動停止。 | 安全系関係事故 |
| 1970/12/4 | 美浜1号 | 若狭幹線事故波及のための原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 1971/9/11 | 美浜1号 | インバーター電源故障のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1971/11/26 | 敦賀1号 | 主蒸気隔離弁5%閉試験中、パイロット弁不調のため主蒸気隔離弁1個が前閉、調査のため原子炉手動停止。 | 安全系関係事故 |
| 1972/2/1 | 敦賀1号 | バイメタル電源装置定期切り替え中、電源喪失のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1972/8/11 | 美浜2号 | 主変圧器の捲線間短絡のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1972/12/7 | 敦賀1号 | 起動変圧器二次側母線短絡のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1973/8/28 | 美浜2号 | 一次冷却水ポンプの電源アニュラス貫通部短絡のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1974/5/4 | 福島1-1号 | B-制御棒駆動水圧ポンプシャフト損傷。調査のため原子炉手動停止。 | 制御棒関連事故 |
1974年5月、インドが初の核実験。
| 【1975.3月、「安全優先、国民本位の原子力開発をめざす日本共産党の提言」】 | |||
|
1975.3.27日、日本共産党中央委員会が、「安全優先、国民本位の原子力開発をめざす日本共産党の提言」を発表した(福井市で不破哲三書記局長(当時)が発表)。「日本共産党の六つの提言の第4項目」で次のように述べている。
3月28日付け赤旗が次のように記している。
次のように評されている。
|
| 【その後の原子力行政】 |
| 1975.10月、九州電力の玄海1号機が運転開始する。 1975.11月、関西電力の高浜2号機が運転開始する。 1976.1.30日、不破書記局長が「安全体制抜きの原子力政策は根本からの転換をはかれ」と衆議院予算委員会で追及する(「前衛」2011年6月号再掲)。 1976.3月、中部電力の浜岡1号機、東京電力の福島第1原発3号機が運転開始する。 |
| 【西ドイツ再処理工場大事故に関する報告書】 | ||||
| 「1970年代に大手メディアが報道した原発情報」(高校国語問題作成素材 2012/1/1) http://kokugo99.seesaa.net/article/392336409.html
|
| 【1977.6月、日本共産党経済政策委員会が「日本経済への提言」】 | |
1977.6月、日本共産党経済政策委員会が「日本経済への提言」(単行本)を発表する。これを仮に「1977年文書」と命名する。(「資料:日本共産党の原発政策③」、「資料:日本共産党の原発政策④」を参照する)「提言」は次のように述べている。
そして①総合的な審議会の設置で、原子力問題の再検討の実施、②原子力安全委員会の設置(今日のそれではない権限を持つ)、③原子力発電所の全面的な総点検(必要があれば回収、改善や運転中止を明言)、④軍事利用の危険防止の措置、⑤自主的、民主的、総合的な研究・開発体制の確立をあげた。それに基づく定量計算では「原子力発電については、先にのべたような厳しい規制を加える。われわれの計算では、現在着工中のものだけを考慮に入れ、それ以外のものはストップすると仮定している。さらに、完成しても、総点検の実施などで危険なものは操業を中止することもあり得るので、稼働率を政府見通しよりもかなり低く見込んでいる」と原発操業を前提としている。
|
1977.9月、四国電力の伊方1号機が運転開始する。
動燃による核燃料サイクル計画は、東海再処理工場の運転に対してカーター政権の介入を受けしばらく停滞した。
| 1975/1/17 | 高浜1号 | 送電線事故による外部電源喪失と所内電源系統の撹乱のための原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 1975/1/23 | 敦賀1号 | 送電線の撹乱による負荷喪失のための原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 1976/1/27 | 敦賀1号 | 落雷による送電線遮断により負荷喪失したため原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 1976/3/15 | 敦賀1号 | 主蒸気止め弁の開閉テスト中、主蒸気止め弁のテスト用電磁弁に異物がかみ込み、主蒸気止め弁が誤作動したため原子炉自動停止。 | 安全系関係事故 |
| 1976/6/1 | 福島1-1号 | B-制御棒駆動水圧ポンプのシャフトが損傷。Aポンプに切り替え、原子炉は運転を継続。 | 制御棒関連事故 |
| 1976/6/3 | 福島1-2号 | 空調用冷却水漏出のため再循環ポンプM-Gセット2Aがショートし再循環ポンプ1台が停止したため、2B再循環ポンプ切り替え、原子炉は出力を下げて運転を継続。 | 再循環ポンプ関連事故 |
| 1976/6/14 | 福島1-2号 | 中間停止点検中、炉心スプレイ系配管の一部に異常を発見。 | 安全系関係事故 |
| 1976/7/7 | 福島1-3号 | 速度設定回路不調なためA-再循環ポンプが停止、原子炉は出力を下げて運転を継続。 | 再循環ポンプ関連事故 |
| 1976/7/18 | 高浜1号 | 制御棒クラスタ駆動用電源故障のため原子炉自動停止。 | 制御棒関連事故 |
| 1976/7/18 | 高浜1号 | 制御棒クラスタ駆動用電源故障のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1976/8/12 | 福島1-1号 | 発電器励磁機回路故障のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1976/8/27 | 島根1号 | 蒸気タービン主蒸気止め弁テスト中、主蒸気止め弁のテスト用電磁弁が誤作動したため原子炉自動停止。 | 安全系関係事故 |
| 1976/10/4 | 敦賀1号 | 落雷による送電機遮断のため負荷が喪失し、原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 1976/11/22 | 福島1-3号 | B-再循環ポンプの電動機中性点設置装置の母線締め付け部の締め付け不良により支持絶縁板が損傷し、B-再循環ポンプが停止、原子炉は出力を下げて運転を継続(手動停止)。 | 再循環ポンプ関連事故 |
| 1976/11/22 | 福島1-3号 | B-再循環ポンプの電動機中性点設置装置の母線締付部の締付不良により支持絶縁板が損傷し、B-再循環ポンプが停止、原子炉は出力を下げ運転継続。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1976/11/29 | 美浜2号 | 落雷による送電機遮断に蒸気加減弁制御機構の不調があり原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 1977/4/28 | 美浜1号 | 電磁弁の不具合により主蒸気隔離弁が閉じたため原子炉自動停止。 | 安全系関係事故 |
| 1977/5/31 | 敦賀1号 | 定期検査中、原子炉停止時冷却系配管のひび割れを発見。 | 安全系関係事故 |
| 1977/12/21 | 高浜2号 | 制御用電源回路の誤動作のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1977/12/25 | 福島1-3号 | M-Gセット制御系回路不調により再循環ポンプ(B)が停止。原子炉は運転を継続。 | 再循環ポンプ関連事故 |
| 1978/1/13 | 高浜2号 | E計器用電源喪失により蒸気発生器給水流量が変動し水位上昇のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1978/8/21 | 敦賀1号 | 原子炉圧力検出器の誤作動により原子炉自動停止。 | 安全系関係事故 |
| 1978/9/3 | 敦賀1号 | 若狭幹線への落雷のため原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 1978/11/21 | 福島1-1号 | 計装用電源回路の誤動作のため原子炉自動停止。 | 内部電源・電気回路関連事故 |
| 1978/12/16 | 美浜1号 | 原子炉起動準備中、誤動作によりM-Gセットが停止したため制御棒が落下。 | 制御棒関連事故 |
| 1978/12/23 | 高浜2号 | 送電線への落雷により外部電源が喪失したため原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
| 【相次ぐ原発事故時代以降の原子力行政】 |
1979年、米国のスリーマイル島事故。 政府は核燃料サイクル計画の頓挫を受けて、軽水炉でプルトニウム燃料を燃やすプルサーマル計画へと重心を移しながらも、再処理工場の建設工事を継続し、「もんじゅ」の再開の機会を図りつつある。技術的にも経済的にも成り立ち得ないこれらの計画を国策として推し進めるその背後には、一貫した核政策が背後にあることを見逃すことができない。核燃料サイクル計画に対し、軍事転用の技術的可能性を論ずることが、反原発運動や反核兵器運動の内部においてタブー視される傾向があったことも、指摘しておかねばならない。 |
| 1979/1/26 | 東海2号 | A-再循環ポンプフレーム振動上昇と、モーター下部軸受温度上昇のためA-再循環ポンプ停止、調査のため原子炉手動停止。 | 再循環ポンプ関連事故 |
| 1979/3/1 | 敦賀1号 | 落雷による送電線遮断により負荷が喪失したため原子炉自動停止。 | 外部電源喪失事故 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)