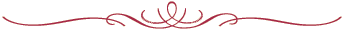
| 武田圭史急変死事件 |
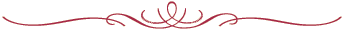
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).4.30日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「武田圭史急変死事件」を確認しておく。 2007.7.21日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【武田圭史(たけだ けいじ)履歴】 |
| 武田 圭史(1970年 - )は、日本の情報工学者。慶應義塾大学環境情報学部教授。専門分野はドローン、ITマネジメント、情報倫理。 自衛隊時代には、防衛庁航空自衛隊において、航空警戒管制組織および新レーダーシステムの運用や、同庁内に向けた情報システムの企画・開発などに従事していた。最終的な階級は一等空尉。 情報セキュリティ黎明期より研究に携わっている。特に侵入検知システムにおいては、日本で最初に侵入検知の研究を始め、世界で初めての正規表現方式を用いた侵入検知システムの開発を行っていた(博士学位論文"Network intrusion detection by traffic monitoring"参照)。 また、情報セキュリティの推進にも貢献しており、積極的な活動を行っている。代表的なものとして、経済産業省の実施する情報セキュリティ対策強化キャンペーン「CHECK PC !」の監修や、日立ソリューションズによる「セキュリティいろはかるた」の監修が挙げられる。 また、カーネギーメロン大学による同日本校の立ち上げや、NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会による産学情報セキュリティ人材育成検討会への有識者としての参加など、様々な方面で情報セキュリティ人材の育成に携わっている。 |
|
|
| 【武田圭史変死事件】 |
| 【武田圭史の2007.7.21日、「柏崎刈羽原発上空の飛行に危険はないのか?」】 | ||||||
2007.7.21日、武田圭史「柏崎刈羽原発上空の飛行に危険はないのか?」。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)