関西南部の紀伊半島では過去に、関西電力が五カ所で原発建設を計画しましたが、住民運動で一基の建設も許していません。紀伊水道の穏やかな海に面した和歌 山県日高町もその一つ。「日高原発」の建設を巡り、人口七〇〇〇人の小さな町を二分した熾烈なたたかいがありました。関電が一九六七年に同町阿(あ)尾 (お)で、続いて小(お)浦(うら)に建設をもくろみます。「豊かな海を守ろう」と漁師や町民、三〇キロ圏の周辺住民、そして医師が立ち上がります。巨額 の補償金で住民分断を図る関電。建設まであと一歩と追い込まれながら、押し返した住民。約四〇年のたたかいを経て、ついに原発の火種を消しました。(新井 健治記者)
「板子一枚下地獄」
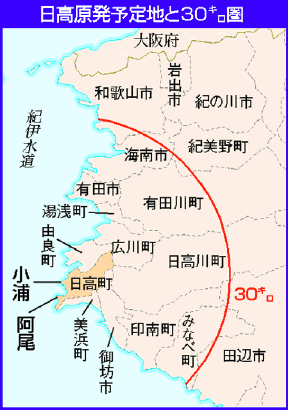
「漁師の世界では『板子(いたご)一枚下地獄』と言ってな、お互い助け合わないと生きていけない。町長、この気持ちがわかるか」―。漁師の濱一己さんの叫びが、議場にこだまします。壇上には二〇年にわたり原発を推進してきた一松春(はじむ)町長(当時)の姿が。
板子とは舟底に敷く揚げ板のこと。板子の下には危険な海が広がります。漁師は命がけで漁をし、いざという時には身を投げ打っても仲間を助けます。原発はこの人間関係をずたずたにしました。
関電は一九七五年、小浦崎の突端を埋め立て一二〇万キロワット二基の原発建設を計画。約七億円の漁業補償金を提示し、漁師は推進派と反対派に二分されま した。方杭(かたくい)浜の濱さん(62)の自宅から、小浦崎までわずか八〇〇メートルです。「親からもらった海を子どもたちにつないでいくには、原発で海を汚したらあかん」と濱さん。「日高町原発反対連絡協議会」事務局長として反対派を引っ張りました。濱さんが町長に訴えたのは、一九九〇年の比井崎(ひいざき)漁協総代会。同漁協は阿尾、小浦など日高町沿岸九漁港の漁師が会員です。世論に押された漁協
は建設拒否を決定。直後に原発反対の町長が当選し、建設は事実上ストップします。ただ、ここまで来るのは長い道のりでした。
アカのレッテルで分断
日高町で原発建設の話が持ち上がったのは一九六七年。関電はまず阿尾で計画。住民の反対で頓挫すると、小浦に持ちかけます。最初に動いたのは女性たちでした。「男は黙って働いて、しゃべるのは女に任せたんやな」と振り返るのは「原発に反対する女の会」のメンバーで元教師の鈴木静枝さん(93)。今は阿尾港の見える高台の特別養護老人ホームに入居しています。鈴木さんの反対の原点は戦争です。「人を殺していいと教育した。もう、騙されたないわ、お上の言うことは信用できへん、との思いがあった」と言います。原発も突如、“お上”から。「『原発さえできれば豊かになれる』という、ありがたい話なので疑った」。直感でその危うさを見抜きました。「難しいことは分からんが、お上の言うことは聞かんと」と推進派からは言われました。原発反対はお上に反対すること。「わたしらは『アカ』ということになってね」と笑います。
同町は関電とともに、建設を推進。反対だった住民も、関電の接待攻勢や就職斡旋で賛成に転じます。漁協も理事の大半は推進派に。親兄弟、親戚でさえ賛成 派と反対派に分かれ、漁船の進水式や結婚式にも呼ばないなど狭い町内が険悪なムードに包まれました。阿尾港の漁師として建設に反対し、今は比井崎漁協組合長を務める初井敏信さん(63)は、「周囲の漁師が次々に切り崩されていく。本当に阻止できるのか、不安とのたたかいだった」と振り返ります。
立ち上がった周辺住民
一九八一年、関電は原発建設に必要な環境アセスメントの陸上調査を開始。後は漁協が海上調 査に同意すれば、建設が始まることになっていました。調査を巡り、漁協は何度も総会を開きます。理事会が受け入れ議案を提案しても、反対派の組合員が激し く抵抗して紛糾、総会は流会、散会を繰り返しました。ぎりぎりの状況の中、一九八六年にチェルノブイリ原発事故が起きます。事故では原発から三〇キロ圏が立ち入り禁止区域に。この事故に危機感を深めた日高
町と周辺自治体(御坊市と八町)の住民が翌八七年、「日高原発反対30キロ圏内住民の会」を結成します。「原発は一自治体だけの問題ではない」との結成呼
びかけ文は、福島原発事故にも通じる先駆的な視点でした。同会事務局長で元中学教師の橋本武人(たけんど)さん(御坊市)は「授業が終わってからビラを配り、学習会を開き、それこそ東奔西走の毎日だった」。同会は建設反対の世論づくりに尽力。日高郡市で一七の住民の会を組織し、署名を集めました。日高町と隣接するすべての自治体(五市町)で、有権者の過半数が署名し、推進派を包囲しました。「会ができる前は『建設を阻止できないのでは』という気持ちも。ところが、運動を始めると圧倒的に反対世論が強い。場さえ作れば住民は立ち上がると肌で感じた」と橋本さん。
医師31人が意見広告
激しいせめぎ合いが続く中、医師たちも立ち上がります。一九八八年三月、日高医師会(日高郡市)の医師三一人が、連名で新聞に意見広告「恐ろしい原発はいらない」(写真左)を出したのです。日高町で唯一名前を連ねた古田医院の古田浩太郎院長(71)は「住民の健康を守る医師にとって、その対極にあるのが原発」と言います。病院勤務医から一九七五年に開業した古田さん。「帰郷した時、息子と見た紀伊水道の夕日が忘れられない。この海を守りたくて反対した」。住民の信頼が厚い医師の意見広告は、世論づくりの弾みに。橋本事務局長は「医師の意見広告は署名集めに大きな効果があった」と指摘します。
原発から福祉の町へ
反対世論が高まっても、一松町長は建設に固執しました。30キロ圏内住民の会は「町長を変えるしかない」と「新しい日高町をつくる会」を結成。同会は一九九〇年の町長選で「原発に頼らない町政」を掲げた志賀政憲さんを擁立、当選させます。町議の大半は推進派。志賀さん(74)は議会対策で苦労しました。「建設に反対すれば国から交付金が来ない」と攻撃されましたが、周辺自治体に先駆け福
祉センターを造り、中学までの医療費無料化を実現。原発に代わり福祉の町づくりをすすめました。その結果、過疎化がすすむ県内では珍しく、日高町はここ二〇年、人口が増えています。紀伊水道は数少ない天然の高級魚クエで有名。同町はクエを観光資源化、観光客も大勢訪れるようになりました。前出の濱さんもクエ漁師です。「今は近隣自治体や大阪からも感謝の電話が来る。在職中は悩んだが、判断は正しかった」と志賀前町長。八期にわたり原発反対を貫いた一松輝夫町議(62)は「私が反対した一番大きな理由は、関電に田舎の良さを破壊されたこと。札束で頬を叩くような仕打ち
への怒りだった」と言います。「どちらかと言えば、右翼なんだけどね」と笑う一松町議。「甘言に惑わされず原発を許さなかった地域を誇りに思う」。
隣市で核燃施設の計画
志賀さんを継ぎ、二〇〇二年から町長を務める中善夫さんも原発反対です。関電は建設をあき らめませんでしたが、二〇〇五年に国が小浦の「開発促進重要地点」(現在は重要電源促進地点)指定を解除、実質的に建設は不可能になりました。一九六七年 以来、約四〇年くすぶり続けた原発の火種は鎮火しました。ただ、油断はできません。二〇〇三年、使用済み核燃料の中間貯蔵施設を日高町隣の御坊市に建設する計画が明らかに。30キロ圏内住民の会は「日高原発・
核燃施設反対30キロ圏内住民の会」と名称を変え、活動を続けています。
古田さんらは「使用済み核燃料中間貯蔵施設建設に反対する医師の会」(深谷修平会長)を立ち上げました。日高医師会の会員九〇人に呼びかけたところ、六〇人が会の趣旨に賛同しました。 同会事務局長で龍神医院(美浜町)院長の龍神弘幸さん(58)は、「医療従事者の良心にかけて反対を貫く」と言います。龍神さんは民医連の和歌山生協病 院を経て、一九九六年に開業。「核燃施設は今でこそストップしているが、全国に原発がある限り、いつ再燃するかわからない。火種を消すには、原発を止める しかない」。原発で二分された町内も、月日が経ち修復されたかに見えます。福島原発事故で、反対運動の意義は明らかになりつつありますが、濱さんは「自分たちが正し
かった、とは強調しない。逆に『もともと同じ漁師やないか』と、こちらから推進派だった人に声をかけている」と気を遣います。初井組合長は言います。「国
や関電が人間関係を壊したのは大きな罪。反省してほしい」。
日高原発建設を巡る動き
1967年 町長が阿尾に原発誘致表明。町議会が誘致決議
1968年 阿尾区及び比井崎漁協が反対決議
町長が原発誘致の白紙撤回を表明
1975年 関電が小浦での環境調査を町長に申し入れ
1978年 小浦区と比井崎漁協が環境調査受け入れを決議
1979年 スリーマイル島原発事故。町長は環境調査を凍結
1980年 町長が環境調査凍結を解除
日高町原発反対連絡協議会結成
1981年 関電が陸上調査開始
1984年 海上調査受け入れを巡り比井崎漁協総会が流会
1985年 比井崎漁協総会は紛糾の末、継続審議
1986年 チェルノブイリ原発事故
1987年 日高原発反対30キロ圏内住民の会結成
1988年 医師31人が新聞に意見広告を発表
比井崎漁協総会で海上調査の議案が廃案
1990年 比井崎漁協理事会が「原発にとりくまない」と決定
原発反対派の志賀政憲さんが町長当選(3期)
2002年 原発反対派の中善夫さんが町長当選(3期目)
2005年 国が開発促進重要地点の指定を解除
(民医連新聞 第1515号 2012年1月2日)

