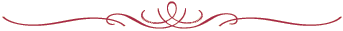
| (代)来日宣教師の日本レポート考 |
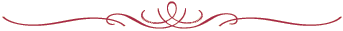
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.4.5日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、来日宣教師の日本レポートを確認する。 2013.4.29日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【宣教師ザビエルレポート】 | |||||
| 1551.3月、ザビエルは都を去り平戸に戻った。残していた贈り物用の品々をもって山口へ向かい、 再び領主の大内義隆に拝謁した。それまでの経験で、日本では外見が重視されることを見抜いたザビエルは一行にきれいな服を着せ、ゴア総督の国書を献じ、その他貴重な文物を献上した。大内義隆は喜んで布教の許可を与え、ザビエルたちのための住居まで用意し、教会を建てた。フロイスの日本史によると、概要「ザビエルはインドの総督の大使のように装い、絹の着物を着て大名を訪問し、インドからの贈り物を献上した」と記している。ミヤコの天皇の代わりに山口の大内義隆に贈物をささげたことになる。
その時にささげられた贈物は、その数13であった。1551年に書かれた「義隆記」には次のように記されている。
ザビエル自身は、ローマへの手紙で次のように書いている。
|
|||||
|
ザビエルは、日本に滞在中、5通の手紙を送っている。すべて鹿児島から出した手紙である.日付は在日3ヵ月後の11.5日になっている。ゴアにいる同僚あての手紙が一番長く、日本人についての報告は驚くほど細かく正確である。日本から出した手紙は2年間の間ほかにはない。
1552.1月、インドへ戻ってから書いたローマの同僚あての長い手紙が残っている。鹿児島,都,豊後,そして主に山口での活動についての手紙である。
ザビエルは次のような日本論、日本人論を記している。ペドロ・アルベ、井上郁二訳「聖フランシスコ・ザビエル書簡抄」を参照する。
|
|||||
2020.8.7日、山中 俊之 株式会社グローバルダイナミクス 代表取締役社長/山中俊之「宣教師・ザビエルも驚愕!江戸・寺子屋の高すぎる教育レベル」。
|
| 【ルイス・フロイス神父レポート】 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ルイス・フロイス神父の履歴は「来日宣教師列伝、日本人宣教師列伝」に記す。ルイス・フロイスは、1585年に「ヨーロッパ文化と日本文化」を著わしている。ここでは「ルイス・フロイス神父の日欧文化比較論」を確認する。吉田幸男氏の「ルイス・フロイスと佐賀藩内儀方」を参照する。宣教師ルイス・フロイスは、中世日本の女性とその風貌、子供の様子、習俗風習について、次のように日欧文化比較している。
|
| 【ルイス・フロイス神父の織田信長論】 | ||||||||||||||||||
| 「日本に来たポルトガル人」の「ルイス・フロイスについて●フロイスと信長●宣教師の人物評」を参照する。当該サイトは「無断で複製・転載を禁じます。引用する際はメールでご連絡頂いた上、当ホームページよりの引用を明記してください」とあるが、今のところ他にない論考になっているので引用転載参照せざるをえない。 1569(永禄12)年、ルイス・フロイスが初めて織田信長に会った。以降、フロイスは、1579(天正7)年にイエズス会の総元締の巡察師ヴァリアーノの通訳として信長に安土で面談するまでの間に18回もの面談を許されることになる。対面した場所は普請中だった二条城の現場だった。織田信長がフロイスを出迎え、1時間半から2時間ほど会話した。この時、織田信長は南蛮の風物に強い関心を示している。延暦寺や石山本願寺など反信長の戦国大名と結託した既成の仏教勢力に手を焼き、そのあり方に辟易していた信長は、キリスト教義も含めて西欧事情に対する好奇心、仏教勢力をおさえる必要、南蛮貿易による畿内の商業の活性化、鉄砲の入手の利便さ等々の理由もあってフロイスの畿内での布教を許可した。 この時のフロイスと信長のやり取りが次のように記されている。
同年六月一日付で書かれた彼の書翰で、信長をこのように伝えている。
「1569.7.13フロイス書翰」は次のように記している。
|
| 【ルイス・フロイス神父の朱印状要請の顛末】 | ||
フロイスは、永禄十二(一五六九)年の信長との対面時に京都に自由に滞在できるための朱印状を強く求めている。その後の流れが次のようになる。都のキリシタンが集まり、朱印状を得るため和田惟政に銀の延べ棒を三本届けた。惟政はこれでは足りないと考え、自分の延べ棒七本と合わせて十本にして、信長に依頼した。すると信長は金や銀を贈る必要はなく、無償で私に与えると答えた。そして、惟政が草案を作成し、フロイスの意向を伺った上で朱印状を作成するように指示した。こうしてフロイスに信長朱印状が渡されたが、その朱印状は残念ながら現存しない。フロイス書翰(1569.6.1書翰)に記された朱印状のポルトガル語訳によると、フロイス書翰に記された朱印状の要点は以下である。
フロイス書翰には、信長朱印状を得た後、まもなくして足利義昭から「制札」を受け取ったと記されている。しかしながら、その内容については触れず、ただ「信長のものと意味や文言の違いはほとんどありませんでした」と書かれているだけである。一方、フロイス「日本史」には「公方様の制札」として内容が詳細に記されている。以下の通りである。信長朱印状と同内容である。
1569年夏にルイス・フロイスは織田信長のいる岐阜城を訪れた。京都で伴天連追放の綸旨が発せられたため、信長に救いを求める必要が生じたからであった。信長はフロイスが岐阜にやってきたことを知ると、すぐに岐阜城に呼び寄せて宣教師の保護を約束した。あわせて自身の居城である岐阜城を案内した。フロイスはその岐阜城の壮麗さを詳細に書き綴っている(1569.7.12フロイス書翰)。 |
| 【ルイス・フロイス神父の岐阜城レポート】 | |
ここでフロイスが書翰で書き記した岐阜城に関する内容は次の通り。織田信長は自身の栄華を体現するために、岐阜城を築城した。「美濃国の民は岐阜城を信長の「極楽」と呼んだという」とある。岐阜城は1567(永禄10)年に織田信長が斉藤龍興から奪取した稲葉山城のことで、金華山の麓に建つ城郭である。
|
| 【ルイス・フロイス神父と日乗の宗義論争】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ルイス・フロイス神父と日乗の宗義論争」が行われている。フロイスは次のように記している。天台宗の僧・日乗は、畿内のキリシタンから「アンチキリストとか悪魔の化身」と呼ばれていた。フロイス自身も概要「彼は生来身分の低い家系であり、背が低く、大変醜く、卑しい人物です。また無知で、日本の宗旨に関する学識もなければ、教養もありません。最も鋭敏で抜け目のない才能をもっていました。話すことにたいへん自由奔放で、弁舌の才では日本のデモステネスである」と記している(1569.6.1書翰)。デモステネスは、古代アテネの政治家で、彼の演説は明確で力強かったため、古典古代第一流の雄弁家にあげられる。 フロイスは日乗の人となりを次のように記している。
「言継卿記」という公家の日記の永禄十一年四月十五日条に「朝山日乗上人去年以来摂州に籠者也、不慮之至也、依勅定遁今日上洛云々」とあり、日乗が摂津で囚われの身となっていたことが裏づけられる。 信長が足利義昭を室町将軍にさせるため上洛すると、正親町天皇は朝廷の回復を信長に依頼するため、日乗を仲介者とした。フロイスの「(1969.6.1書翰」は「信長は日乗を気に入っていた」、「日乗は信長に『宣教師のいるところは騒乱が起きて破滅するので、信長が美濃に戻る前に宣教師を追放するよう』と進言した。しかし、信長は一笑に付し、『予は汝の肝がこうも小さいことに驚いている。予は宣教師を追放するつもりはない。すでに彼が都に滞在するだけでなく、何処の国にも思いのままに行くことができるための許可状を与えており、公方様も同様であるからである』と答えた」と記している。 フロイスが永禄12年4月20日妙覚寺にいる信長のもとを訪れた時のこと。信長は「仏僧達はなぜフロイスを憎悪するのか」と尋ねた。ロレンソ「それは暑いか寒いかであるとか、徳か不徳かという論争のようなものです」。信長「フロイスらが神や仏を敬うか」。ロレンソ「神仏はどちらも私達と変わらない人間であり、妻子を持ち、生まれ死ぬ人間であるので敬いません。そして、神仏は自身を死から救い解放することができず、人間を救うことはより不可能なことです」。その時、日乗はフロイスの側にいたが、信長を前にして一言も話さなかった。フロイスもロレンソも、そこにいるのが日乗であることを知らなかった。座敷と外の縁には入りきれないほどの領主達がいた。信長は日乗に「日乗上人、お主はこれに対して何と言うか。何か尋ねてみよ」と言った。この信長の発言によって、日乗と宣教師の宗論が始まった。宗論は二時間に及んだ。 「ルイス・フロイス神父と日乗の宗義論争」につき今のところ他にないので、「ルイス・フロイスについて●フロイスと信長●宣教師の人物評」文を参照する。これによれば以下のやり取りになる。但し、次のように註釈している。
日乗は信長に「これは陰謀であります。殿下、彼等は人々を欺いている者ですので、彼等を追放し、二度と当諸国に戻らないように、すぐさま追放するよう命じてください」と述べた。信長は笑って、「お主は気後れしたか。問うてみよ。彼等は答えるであろう」と返した。日乗は尋ねなかったので、今度はロレンソが質問した。
その他の問いに対しても、日乗は知らぬと答え、お主らが答えてみよと返答するばかりであった。ロレンソが詳しく説明すると、日乗「禅宗の『本分』とデウスは同じである」と答えた。フロイスらは論拠を挙げてその違いを説明したが、日乗は信長に宣教師の追放を要求し、「彼等が都に滞在していたために足利義輝は殺された」と述べた。これに対して、信長はもともと神仏を崇めていなかったので、日乗の言うことを無視した。
日乗は激しく怒りながら、部屋の片隅に掛けてあった信長の長刀に向かって突進し、長刀の鞘を外し始めた。信長はすぐさま立ち上がり、日乗を後ろから取り押さえ、和田惟政と佐久間信盛、他の領主達は反対側から駆け寄って日乗を捕まえた。そして、力づくでその手から長刀を取り上げた。皆は日乗を大いに嘲り、信長は笑いながら「予の面前でそのようなことをするのは大変無礼である」と言った。他の領主も、日乗に対して同様のことを述べた。特に和田惟政は、「信長の前でなければ直ちに日乗の首を刎ねていたであろう」と語った云々。 |
| 【安土問答】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1579(天正7)年5月、安土の浄厳院にて法華宗(日蓮宗)と浄土宗の間で宗論が行われた。 これを「安土宗論」(「安土問答」、「安土法論」)と云う。「信長公記」の天正7年の箇所に「五月中旬の事に候」として書き始められている。それによると、浄土宗僧侶の覚蓮が安土の町で7日間の法談(説法)をしていたところに法華宗徒の大脇伝介、建部紹智が論争を挑んできた。覚蓮が「そなたたちが帰依する僧侶を呼べばその方に答える」と述べ、これを受けて京都より僧侶を呼び寄せ、宗論を行えと迫った。この噂が信長に伝わり宗論が行われる運びとなった。信長は、審判者を出すから討論の結果と勝負を書類にして報告せよと申し付けた。「左(さ)候はば、判者(はんじゃ)を仰せ付けらるべく候間、書付を以って勝負を御目に懸け候へと、御諚候て」。これによりそれぞれの代表が宗論の場に臨むことになった。「歴々の僧衆、都鄙(とひ)の僧俗、安土へ群れ集まり候」と当時の安土周辺の模様が記録されている。 宗論は旧暦5月27日に寺中警護の中で行われた。宗論が行われた場所は、その前年に信長が建立した浄土宗の金勝山浄厳院。この地は、もともと佐々木六角氏頼が建立し六角氏の菩提寺であった慈恩寺(天台宗)があったが、信長が、近江(八幡市多賀町)にあった興隆寺の堂舎を移し、栗田郡の金勝寺より明感という僧侶を招いて金勝山浄厳院と改称していた。信長はこの寺を、近江・伊賀両国の総本山した。「その場所の立派なこと、座席の準備、仏僧の格式、民衆の集合という点では、ヨーロッパの著名な大学で上演される公開劇の雰囲気を備えていた」と当時来日していた宣教師フロイス(「日本史」の著者)は記述している。 浄土宗側の代表は、霊誉玉念、安土西光寺の教蓮社の聖誉定安、近江の正福寺開山想蓮社の信誉洞庫、京都知恩院内一心院の助念(記録者)の4人。法華宗側は、美濃斉藤道三の帰依僧妙覚寺(常光院)の日諦、京都頂妙寺の日珖、京都妙満寺の久遠院の日淵(日雄)、京都妙顕寺内法音院の僧大蔵坊の4人。この8人が問答することになり各4人が対座した。また判者は当時京都五山の識者として有名だった日野・正明寺の鉄叟景秀とその伴僧の華渓正稷、因果居士(華厳宗の学者?)、法隆寺の仙覚坊(法相宗の学僧)の4人。宗論の奉行衆は信長の家臣の菅屋長頼、堀秀政、長谷川秀一、矢部家定。また「信長殿御名代」として織田信澄も立ち会った。(油屋常由の弟妙国寺、普伝) 問答の内容は次の通り。
討論は互角の勝負とみなされたが、浄土宗側が問うた「妙」についての問いに法華宗側が答えられなかった為、不利となった。宗論の結果は、信長の事前の命令通り書付を持って信長に提出され、目を通した信長の行動はすばやく(「宗論勝負の書付上覧に備えらるるのところ、即ち、信長公時刻を移さず」)宗論の場へ往き、浄土宗側に扇や杖などを与えて賞した。8月2日、聖誉定安は、信長からあらためて感状(上官や君主が功や業績などを認め賞した旨を書いた書状)と銀子50枚を贈られ功を慰労され、一代の面目をほどこした。これは宗論を戦ったのが浄土宗側では結局彼1人であったことが認められた。これにより西光寺は名刹となった。 法華宗側への沙汰を申し渡した。最初に不審を発した法華の信徒・大脇伝介を斬り捨てている。理由は、この者実は長老の宿を仕った者であるのに、長老の味方もせず、人にそそのかされて不審を申し懸け、「都鄙(とひ)の騒ぎ」を惹き起こしたのは不届きである、というものであった。 僧侶普伝が打ち首にされた。また宗論の場に出席した普伝という僧は、九州出身で、昨年秋から滞京していたが、一切経のどこそこの箇所に何々の文字があるといったことを空でいえるほどの博識があり、信長と近衛前久との雑談に出てくる僧であった。彼はどこの宗派にも属していなかったが、「八宗は兼学したが、法華はよき宗派なり」とよく周囲にもらしていたのにかかわらず、常々「信長申し候はば、何れの門家にもなるべし」と言っていた。近衛殿は普伝の行動について、「ある時は紅梅の小袖、ある時は薄絵の衣装などを身に着けており、自分の着ている破れ小袖などを結縁であるといってよく人に与えている」と話していたが、調べてみれば小袖は実は借り物で、まがいものの破れ小袖であったことが判明した。法華宗徒は「かほどに物知りの普伝さえ聞き入り、法華宗となった」と評判が立てば法華も繁盛するであろうと考えて普伝に協力を頼んでいた。普伝も多額の賄賂と引換えに法華宗となることを承諾していた。信長はそれらの行状を訊いてから、理由を申しつかせて斬罪に処した。 理由の1つは、僧としての在り様が「老後に及び虚言をかまへ、不似合」。宗論に勝った暁には終生にわたって身上を保証するとの確約をもって法華宗に招かれ、届も出さずに安土へ下ったこと、日頃の申し様と大いに異なる曲事の振舞いであるとの咎めであった。理由の2つめは、今回の事、「人に宗論いわせ、勝ち目に候はば罷り出づべしと存知、出でざる事、胸の弱き仕立、相届かざる旨」、つまりお前は自ら法問を立てることもせず、他人に宗論をまかせた。これは法華方が優勢になった時のみ自分も出ればよいと算段した上での行いであり、その性根の弱さは不届きというほかない」といったことになる。信長は、実質のない言葉で人の心を惑わす行為をひどく嫌い、また卑怯に見える態度を嫌った。 さらに信長は残った法華僧に対し、「諸侍軍役勤め、日々迷惑仕り候に、寺庵結構仕り、活計を致し、学文をもせず、妙の一字に、ツマリ候し事、第一曲事(くせごと)に候」。つまり、侍たちが日々軍役を務めて辛酸を舐めている横で、汝ら寺庵衆は安穏として贅沢をなし、学問もせず、ついには妙の一字の解釈にも詰まる体(てい)たらくに至った、このこと曲事に尽きる、といったことになる。 そして堺まで逃げたもう一人・建部紹智も追捕して斬罪に処している。 信長は、その上でしかしながら法華宗は「口の過ぎたる者」ゆえに、後日、宗論に負けたとは決して申さぬであろう。「ならば本日敗れた証拠として、汝らは宗門を変えて浄土宗の弟子となるか、それとも今後決して他宗を誹謗せぬ旨の墨付を提出するか、いずれかを選ぶべし」とせまった。法華僧はこれを受けざるを得なかった。その上で信長は、法華宗側に、法華宗十三ヶ寺が連名で、下記のような3ヶ条の起請文(詫証文)を書かさせている。
さらに法華宗に「可被立置之旨」に感謝する旨、もし違反した場合は法華宗悉く成敗されても恨みに思わない旨、も誓わせ、宗論の奉行衆へ提出させている。この詫証文(起請文)は、題目曼荼羅に書いたもので、信長へのものと浄土宗の本山京都知恩院へのものであった。またさらに京都の法華(日蓮)宗の諸寺へ罰金を科し、日珖以下の桑峯寺(桑実寺か?)籠居など厳しく処罰した。 |
|
織田信長は黒人を見てその肌を洗わせた。
ある宣教師が織田信長に謁見する為に安土城を訪れた際に、一人の黒人がその宣教師に同行していた。信長は宣教師との会話よりも、その後ろに控えていた肌の黒人に興味を覚えた。信長はなぜその様な色をしているのかを質問した。宣教師は答えた。「生まれた時からこの様な色でございます」。それを聞いても信長は半信半疑で、家来に命じて目の前でその者の背中を洗わせた。いくら洗っても肌は黒色であった。そこで初めて信長は、世界にはこの様な肌の色をした住民が居ることを理解した。信長はこの者を引き取り、名を弥助と改め信長に仕えさせたと言われている。 |
イエズス会のコスメ・デ・トーレスは次のように記している。
|
イタリア人宣教師、ニェッキ・ソルディ・オルガンティーノは次のように記している。
|
日本にあまり好意的でなかったアレッサンドロ・ヴァリニャーノは次のように記している。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)