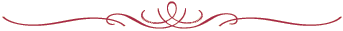
| れんだいこのイエズス会考、ネオシオニズム系宗教結社考 |
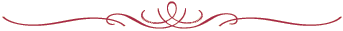
(最新見直し2013.10.29日)
| れんだいこのカンテラ時評№1179 投稿者:れんだいこ 投稿日:2013年10月27日 |
| れんだいこのイエズス会考その1 ここで突如の感があるが、「ザビエルの来日布教」の政治的意味を問いたい。一般に、「ザビエルの来日布教」は「キリスト教伝来」として知られ、そう記述されている。しかしながらこの見地だけでは失当で、それはあまりにも表層的な受取りに過ぎる。そういう通説ものばかりなので、そういうものばかり学んで却って目が曇らされてしまう。もっと云えばバカになる。 日本史上の凡そ16世紀の戦国時代、これを世界史的に見れば、改宗ユダヤ人がキリスト教宣教師として世界各地を探訪し始め、後の植民地化の足掛かりを築き始めていた。云うなれば、宣教師の跳梁は来る植民化時代の地均しであり、「宣教師は植民地化の先兵」と位置付けられるものであった。個々の宣教師の主観的意図がどうであれ、イエズス会、その後に続くフランシスコ会、ドミニコ会、アゴスチノ会等々の活動そのものの本質はそのようなものである。宗教はそのように悪用される。そういうことを確認する必要があろう。念のために補足しておけば、宗教そのものを批判しているのではない。教義が邪悪であれば、その邪悪性が政治にうまく利用される、そういう傾向性について指摘している。 歴史上、この時代の宣教師はキリスト教の系譜に位置づけられている。しかし、宣教師の属する結社の教義、それに基づく活動をみれば、キリスト教義のユダヤ教&ネオシオニズム的読み取りで新たに結社されたものばかりであり、彼らを裏で操作する国際ユダ屋の操りでしかなかった。 表見キリスト教ではあるが内実はユダヤ教&ネオシオニズムであり、共通して改宗ユダヤ人が内在している。彼らの活動の本質は宗教に名を借りた政治&軍事活動であった。彼らのイズムによる世界の植民地的秩序化こそが狙いであり、その請負として飼われ、その先兵として送り込まれていたに過ぎない。これを裏付けるのが彼らが本国の国王なり結社なりバチカンに送られた通信である。まだ一部しか開示されていないが、政治&軍事的スパイ活動の様子をあけすけに伝えている。 そういう意味で、戦国時代に来日進出して来たイエズス会、その後に続くフランシスコ会、ドミニコ会、アゴスチノ会等々のネオシオニスト的素性がもっと詮索されねばならない。それらは宗派上はカトリック派に属する信徒団体ではあるが、教義的にも運動的にも変種カトリックであり、ユダヤ教的ネオシオニズム的な傾向を持つ秘密結社であることが知られねばならない。 故に、イエズス会宣教師ザビエルの来日は、キリスト教の伝来というにとどまらず「ネオシオニズム来襲の嚆矢である」とみなしたい。言い換えると、「ザビエルのキリスト教伝来は、ネオシオニズムの日本来襲第一陣であった」と表記されるべきであろう。従来の記述は、最も肝腎な部分であるこの側面を抜かして「キリスト教伝来」をのっぺらぼうに説いていることになる。 れんだいこは、学問的にキリシタンの命名には問題があるのではなかろうかと考えている。キリシタンならまだ許容できた。実際にはバテレンは即ち改宗ユダヤ人シオニスタンであった。シオニスタンは俗にいう「似ても焼いても食えない」手におえない連中である。これを隠す為に、さもキリスト教徒であるかのように偽装演出し、その咎めはキリスト教が受けるよう細工しているのではなかろうか。こう確認したい。これも案外と重要な指摘である。「原日本論新日本論」応用による「クリスチャン論シオニスタン論」である。 2006.1.28日、2013.10.26日再編 れんだいこ拝 |
| れんだいこのカンテラ時評№1180 投稿者:れんだいこ 投稿日:2013年10月28日 |
| れんだいこのイエズス会考その2 「れんだいこのイエズス会考その1」で述べたように、今から約500年前の日本史上の戦国時代、日本初のネオシオニズムが来襲し大勢のキリシタンを誕生させた。狙いは、世界の例で分かるように日本を植民地化することであった。丁度この頃から日本で「主家殺し」、「王殺し」、「在地宗教殺し」の三点セットが激化している。キリシタン大名の支配するところに共通してこういう現象が現れている。これを偶然と見るべきだろうか。 通俗史書は何の関わりをも見ようとせず、単に時系列的に出来事を記して足りている。そういう歴史では真相が見えてこない。何故に歴史を学ぶのか意義が分からなくなろう。そういうことからする歴史嫌いが増えているようにも思われる。れんだいこは、そういう歴史記述に挑み続けている。歴史は今に繋がる生きているもので学べば面白く有益なものである。そういう歴史学を取り戻す史学を打ち立てたい。 時の織田、豊臣、徳川政権が彼らの策謀を見抜いた。織田信長は安土城建立の頃からバテレン離れしている。それまでの天下布武の過程ではかなりバテレン勢力の後押しを得ている形跡がある。その道中、宣教師と仏教坊主と宗義問答を闘わせている。どういうやり取りが為されたのか興味があるがネット上には出てこない。こういう知りたい情報に限ってネットには出てこない恨みがある。 宣教師フロイスの「日本史」に多少の記述があり、これが紹介されているが、かなり身びいきに問答改竄されていようから参考にしかならない。その信長の晩年、バテレン勢力の差し金と推定できる荒木村重の乱が起り、これを見事に鎮圧したものの明智光秀の本能寺の変で討ち取られている。 結果的に、その後継の豊臣-徳川政権が渾身の知力、武力で死闘的攻防の結果、彼らを撃退した。ここが世界各地の籠絡された植民地と違う日本史の気高い面である。その結果、良し悪しは別として鎖国へと導かれた。何事にも功罪が相半ばしてあるので一面的な断定は控えるべきだろうが、少なくとも得たものと失ったものを秤に掛けて時宜を評せねばなるまい。時間軸を抜きにした単調な礼賛、批判は愚かであろう。そういう評論ばかり目にするけれども。我々の父母祖はかの時、相手の素性を見破り賢明に対処したと解すればよい。よほど能力があったと評するべきであろう。 太田龍が早くよりこの観点を打ち出している。この視角は珍しい。これを聞かされた時のれんだいこはピンとこなかったが、以来、検証してみて、数々の証拠が「太田龍の言の正しさ」を物語っていることに気づいた。 これが真実だとすると、当時の支配者・豊臣秀吉の「バテレン追放令」には充分すぎる根拠があったということになる。こうなると、従来の「バテレン追放令」から鎖国へ至る過程を否定的に評する見方を変えねばなるまい。従来の歴史記述は大幅に変えられねばなるまい。学問が学問足り得る為には、この内在的必然性を検証せねばならない。 今、この問題の考察をしたくなった理由は、目下の日本が日本史上あり得なかったネオシオニズムによる露骨な支配を許しているからである。稀代のシオニスタンによって首相、官邸、政府、野党各党をも含む「政財官学報司警軍」の八者権力機関が彼らの御用聞きによって占拠されてしまっている。このことを凝視したい。 はっきり云っておく。小ネズミも前原もシオニスタンではないのか。現代日本政治の与野党対立なるものは、その同じ穴のムジナが猿芝居しているに過ぎないのではないのか。連中が、国庫秘蔵金の郵政事業金を放出し、次に皇室解体、憲法改正、自衛隊の軍事戦闘化と戦後構造の諸「改革」に矢継ぎ早に乗り出している。既に主要事業及び産業の有望企業は中曽根以来の民営化路線の下で無残にも外資化されている。我々はこれ以上指をくわえて座して眺めるべきかということが問われている。 ここまでが、「2006.1.28日」の記述である。かの時より民主党政権を経て今は安倍政権下にある。ネオシオニズムの日本席捲の流れは流れは止まらないばかりかますます激しくなっている。民主党政権時、自公政治に劣らないネオシオニズム御用政治を見せつけられて来た。今に至る民主党に対する嫌悪感は、この時以来のものである。 この流れの中で目下、安倍政権が、福島原発事故対応不能下での原発再稼働、その輸出、その建て替え、TPP推進、消費税増税、公共料金の値上げ、物価上昇政策、憲法改正、自衛隊の武装海外派兵、所得格差推進、相変わらずの国債刷りまくり等々目を覆わんばかりの悪政を矢継ぎ早に打ち出している。安倍の後継を待ち受けている石破となると更に酷いネオシオニズム御用聞きの徒輩である。もう無茶苦茶としか言いようがない。 おとなしい日本人はどこまで耐えるべきなのか。この局面に於いて現代人の我々が何を為すべきか。受け皿となる闘う主体が出てこないのか。出てこないのならどう創るべきなのか。これを共に考え歴史に有意な活動歴を遺そうと思う。この思いから書かれたのが本稿である。「ザビエルの来日布教」の「元一日」から解かないと真相が見えてこないのではなかろうかと思い説き明かしたつもりである。 補足。ネオシオニズムに容喙された政治はなぜことごとく本来期待されている政治の逆ばかりするのだろうかの問いをしておく。れんだいこの解は思想ないし精神の歪みであるとする。ここが全ての発祥元なのではなかろうかと思っている。 ネオシオニズム以外の世界の諸思想、精神は凡そシルクロード的交易で足りて良しとする。独りネオシオニズムがワンサイド取引に狂奔する癖があるのではなかろうか。彼らは、ただひたすらに金貨を集積し資本となし、それで世界を思うままに操れるとする妄想を逞しゅうしている。そこから悪事の限りを発想し世界改造を構想していると見なす。そういうワンワールドを虚妄とする精神と思想と運動を生み出し、対するものを生み出したいと考えている。 |
| れんだいこのカンテラ時評№1181 投稿者:れんだいこ 投稿日:2013年10月29日 |
| れんだいこのイエズス会考3 「れんだいこのイエズス会考その1、2」を踏まえて、当時のネオシオニズム(以下、「バテレン」と記す)の日本政治への容喙ぶりを確認しておく。学説にはネオシオニズム論そのものがないので、ましてや「その容喙ぶりの検証」なぞあるべくもない。当時の信者数、宣教師数の推移等を比較論的に検証してみたいが、そういう資料がない又は公開されていないのでできない。そういう訳で、表に出ているキリシタン大名、武将のバテレンとの相関関係、それが綾なした王権闘争を炙り出してみる。 一般にキリシタン大名としては大友宗麟、大村純忠、有馬晴信、結城忠正、高山右近、小西行長、黒田孝高(官兵衛)、蒲生氏郷、支倉常長、織田有楽斎、織田秀信、細川忠興、前田利家などが知られている。しかしそういう列記では何も見えてこない。王権闘争を見る観点がないからである。 れんだいこが見るところ、松永久秀(1510年)、明智光秀(1528年)、織田信長(1534年)、荒木村重(1535年)、豊臣秀吉(1536年)、高山右近(1552年)もキリシタン大名として確認されるべきではないのか。ここでは紙数を増すので論拠については述べない。この六者がバテレン来襲以降の戦国期末王権闘争に直接的に関与している。 このうち、織田信長と豊臣秀吉は「半」キリシタン大名であり、バテレンに操られながらも自前権力を創出し丁々発止したのは衆知の通りである。この六者が王権を得ようとして戦国期末の政権争奪戦を演じている故に重要な役割を果たしている。この動きを見ない戦国史論なぞあり得て良い訳がない。これを確認しておく。 1565(永禄8)年、松永久秀が、三好三人衆と共に13代足利将軍・義輝を攻め滅ぼしている(永禄の変)。いわゆる「王殺し」である。日本史上、王家同士の「王殺し」は多々あるが、いわば平民側からの「王殺し」は恐らくこの時が初めてである。故にもっと注視されねばならない出来事であろう。こういう「王殺し」は、極論すればバテレン来襲と共に始まっていると見なせよう。 1567(永禄10)年、久秀が東大寺大仏殿を焼いている。相手方の三好三人衆が東大寺に陣を敷いたとはいえ日本有数の仏閣財産が焼失せしめられている。この「在地宗教殺し」もバテレン来襲と共に「故意に」始まっていると見なせよう。「神社仏閣焼き」の例はそれまでにもなくはないが、日本系内部の抗争では極めて珍しい例であり、バテレン来襲と共にあちこちで始まったと窺う必要があろう。この時期までは、久秀がバテレンの後押しを得た王権候補筆頭だったと思われる。 1569(永禄12)年、織田信長が足利義昭(義輝の弟)を擁立して上洛してくると久秀父子はいち早く降伏し信長の家臣となる。これには大和国取り物語で在地権力側の筒井順慶の奮闘が関係していた。この時点で、久秀が王権候補筆頭の座から抜け落ち、信長がその地位に就いたと思われる。 1571(元亀2)年、織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちしている。この時も、日本有数の仏閣財産が焼失せしめられている。当然、これも久秀の東大寺大仏殿消却と同じ線の「在地宗教殺し」の類であると思えばよい。この頃までは、信長はバテレンと蜜月時代であった。これに堺の町方衆、茶の湯を通じての仲立ちが確認できる。千利休なぞも相当に臭い隠れキリシタンであることが間違いない。本稿ではこれ以上述べない。 1576(天正4)年、織田信長が近江守護六角氏の居城観音寺城の支城のあった安土山に築城を開始する。この頃より信長は次第にバテレン勢力を警戒し始めバテレン離れの傾向を見せている。 1577(天正5)年、久秀が、上杉謙信、毛利輝元、石山本願寺などの反信長勢力と呼応して大和信貴山城に立て籠もり反旗を翻す。10月、織田軍が信貴山城を包囲し、織田軍の総攻撃が始まると爆死した。享年68歳。久秀は、バテレンの教唆により、バテレン離れし始めた信長征討戦に挑み敗れた。捨て駒にされたと思えばよい。 1578(天正6)、織田家でも有数の重臣となっていた荒木村重が突如、信長に反旗を翻し有岡城(伊丹城)に立てこもる。これも、バテレンの教唆により始められた信長征討戦第二弾と思えばよい。村重旗下の高山右近が苦悩の末、織田方に寝返る。徹底抗戦一年後、村重がほぼ単身逃亡し一族が皆殺しにされている。村重の家臣を捨てての単騎逃亡なぞは日本系のものではない。殉死的美学を拒否しているバテレン系精神の為せるワザと窺う必要がある。 1579(天正7)年、信長が完成した安土城の天守閣に移り住む。信長の絶頂期となる。この間、信長は、1569(永禄12)年、フロイスとの最初の二条城の建築現場での会見以来、記録に残るだけでも18回、他の宣教師を含めて14年間に31回以上会見している。信長はバテレン教の教義や科学知識に興味を持ち議論を好んだが帰依することはなかった。 この頃、「切支丹来朝実記」によると、仏僧の前田徳善院玄以に、「自分は彼らの布教組織を破壊し、教会を打ち壊し宣教師を本国に返そうと思うがどうか」と諮問している。今まで宣教師との蜜月時代を振り返り、「我、一生の不覚なり」と漏らしている。この時点から、バテレンが信長に代わる王権候補を探し始めたと思えばよい。 1582(天正10)年、信長が、明智光秀軍により本能寺の変で横死する。この事変をバテレンの差し金と読まない推理は何とも味気ない。これの論証は別稿に譲る。光秀の叛旗は信長征討戦第三弾であり、信長は三度目に打ち取られたことになる。この瞬間、光秀がバテレンの後押しを得た王権候補筆頭となった。 但し、備中高松城の攻城戦を展開していた羽柴秀吉軍すぐさま引き返し、山崎の合戦で光秀軍を打ち破った。これを光秀の三日天下と云う。この時、高山右近は光秀軍下にあったが呼びかけに応ぜず秀吉の幕下に駆けつけ、先陣を切り光秀軍一万五千に対して二千の兵で打ち破り武勲を上げている。こうして、秀吉が天下を取った。山崎の合戦での秀吉の勝利は、バテレンが光秀から秀吉に乗り換えざるを得なかったことを意味する。 1587(天正15)年、秀吉もバテレンの後押しを得て王権に辿り着いていたが突如、「バテレン追放令」を発布する。1591(天正19)年、千利休が切腹を命ぜられ余儀なくされている。これをバテレン内通との絡みで捉えない千利休論は意味がない。以降の流れを記すこともできるが略す。バテレンは最後の望みとして高山右近に期待していたが、史実は徳川家康が王権を取るのは衆知の通りである。 戦国史の一連の流れの中に、かく「ネオシオニズムの日本攻略」を見るのがれんだいこ史観である。その一部始終をフロイス「日本史」が事細かに記録している。興味深いことに、松永久秀、明智光秀、織田信長、荒木村重、豊臣秀吉、高山右近を特記している。この理由を素直に読み解けば、「王殺し」以降の「ネオシオニズム系政権誕生」までにかくも容喙していた故の記述と云うことになろう。単に戦史物語としではなく「バテレンの日本攻略史」の顛末を文書にしイエズス会にレポートしたものと窺うべきではなかろうか。 この見立てを披歴したのは、既成の史書が戦国史に立ち現われている「ネオシオニズムの日本攻略」ぶりをほぼ完璧に封じ込め、差し障りのない記述に終始しているからである。しかしこうなると、一番肝要な観点を抜きにしての歴史考証、歴史記述となり、そういうものが面白くないのは当たり前だろう。気の抜けたビールを飲まされていると思えばよい。その点、れんだいこの歴史考は喉越しが良かろうふふふ。 2006.1.28日、2013.10.29日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)