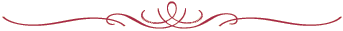
| 徳川幕府のキリスト教禁教史 |
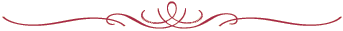
更新日/2020(平成31→5.1日より栄和改元/栄和2).8.7日
この前の経緯は「豊臣秀吉の伴天連(ばてれん)追放令」に記す。
| 【徳川家康の対バテレン教初期政策】 |
| 「ウィリアム・アダムスとカトリック教会の対立」その他を参照する。 |
| 秀吉亡き後、キリシタンとの戦いは、徳川家康に引き継がれていくことになる。 1600(慶長5)年、豊臣政権の五大老を努めていた家康は、豊後に漂着したオランダ船リーフデ号の航海長で、イギリス人のウィリアム・アダムス(三浦按針)を家臣として召し抱えた。しかし、これは相当な厄介を招いた。即ち、当時のオランダ、イギリスはプロテスタントの国で、スペインなどカトリック国と敵対していた。家康に召抱えられたアダムスらは、家康に西欧の宗教事情を吹き込み、カトリック系の世界植民地化構想を暴露する惧れがあった。そういう予見から、在日カトリック系宣教師達は、アダムス以下 リーフデ号の乗組員を処刑するように家康に申し出たり、一人の神父を派遣して彼に日本を去るように説得したりした。さらに最終手段として、プロテスタントからカトリックへと改宗するように迫っている。ヨーロッパの宗教対立がそのまま極東の島国に持ち込まれた図式であった。しかし、家康から見れば、ポルトガル、スペイン以外の貿易相手が出現したことになる。それを良しとした家康の決断により、在日カトリック系宣教師達の試みはいずれも失敗に終わった。 政権を握った徳川家康は、初期の頃、宣教師の布教活動を許可・黙認した。それは、ポルトガルやスペインとの貿易の利点の方が優った為であった。以前から活動していたイエズス会をはじめ、フランシスコ会、ドミニコ会、アウグスティノ会の宣教師が来日するようになった。家康は、外交上の必要からこれらの活動を黙認したが、秀吉の禁教令を取り消すことはせず、キリスト教を受け入れる意向は全く持っていなかった。 長崎では、1601(慶長6)年、イエズス会の教会が再建された。この教会で、日本で最初の2名の司祭が叙階されている。1583年に創設されていたミゼリコルディアの組”は病院のほか施設も経営し、活性化しつつあった。大村、有馬、天草等は南蛮国のようになった。教会が聳え立ち、セミナリヨの生徒も増えていった。京都の教会には日本で最初の修道女会が出来た。キリシタン比丘尼(びくに)と呼ばれたこの修道女たちは、宣教師たちの入り込めない上流婦人のあいだに入って宣教した。 1609(慶長13)年、長崎で「マードレ・デ・デウス号事件」が勃発した。これは、前年にキリシタン大名として知られる有馬晴信の朱印船が、マカオに寄港した際、晴信の家臣である朱印船乗務員とポルトガル人が争い、60余名の日本人が殺害される事件に端を発している。翌年、この事件に関与したアンドレ・ペッソアが、通称マードレ・デ・デウス号に乗って長崎に来航し、家康に釈明した。朱印船の生き残った乗組員から事件の顛末を聞いた長崎奉行・長谷川左兵衛は、家康の前で彼らの弁護者となった。家康は、有馬晴信に命じてペッソアを召喚させようとしたが、ペッソアはこれに応ぜずデウス号に乗り込み出帆しようとした。これに対し、有馬晴信は、長谷川左兵衛らとデウス号を包囲攻撃し、4日目にデウス号は沈没した。これを「マードレ・デ・デウス号事件」と云う。 この事件をきっかけに、家康はキリシタン弾圧へと傾斜していく。キリシタンの春は終わりを告げ、一足飛びに厳しい冬を迎えていくことになった。 1611(慶長11)年、に来日したスペイン使節が、諸港を測量した。その目的を家康から訪ねられたアダムスは、「エスパーニャ(スペイン)は、まず托鉢修道士たちを派遣し、彼らの後で兵士たちを送り込みます。このようなやり方で外国を支配下に入れていきます。そのために各港にどの船が入港できるか知るためです」と述べ、すべての宣教師を国外に追放すべきであると進言した。 家康が、アダムスを重用し、オランダ、イギリスとの通商、国交を閉ざす意志を明確にするや、カトリック側は、ついに、日本全国を、親カトリック陣営と、反カトリック=親プロテスタント陣営と、真二つに分裂させ、反カトリックの徳川幕府政権を武力で転覆する大作戦構想を立てた。 「マードレ・デ・デウス号事件」は、「岡本大八事件」を生む。同事件とは、家康の側近・本多正純(ほんだまさずみ)の与力にしてキリシタンの岡本大八が、有馬晴信に対し、家康が、デウス号を沈没せしめた事件の恩賞として、豊臣時代に失った有馬氏の旧領を戻す意向があると伝えたことにより、晴信がその斡旋として多額の金品を賄賂(わいろ)として渡したところ着服された。その後不審を抱いた晴信が直接、本多正純に問い合わせたところ、大八の虚偽が発覚し、贈収賄事件が露見した。逆恨みした大八が晴信の長崎奉行暗殺計画を暴露し、1612(慶長17)年、大八は処刑され、有馬晴信は甲斐(かい)国に流され、後に処刑されたという事件である。 家康は、「岡本大八事件」の後、キリスト教禁止を表明し、その摘発を行った。家康は貿易のために、はじめはキリシタンを黙認していたが、ここに至って禁教の方針をとった。その結果、旗本のジョアン原主水(はら もんど)や、大奥の侍女ジュリアおたあなどが改易(かいえき)・追放処分となった。 信者に信仰を捨てるよう に命じ、従わない者は死刑にした。家康が何よりも恐れていたのは、秀吉の遺児秀頼が大のキリシタンびいきで、大阪城にこもって、スペインの支援を受けて徳川と戦うという事態であった。当時の大阪城内には、宣教師までいた。 |
| 【徳川家康の「キリシタン禁令」と、「宣教師の国外追放令」から鎖国まで】 | |
| 1614(慶長18)年、家康は大阪攻めに先立って、全国に「キリシタン禁令」と、「宣教師の国外追放令」が発布された。これにより、幕末さらに明治政府までに引き継がれる長く厳しい迫害の幕が切って落とされた。
日本各地にいた外国人宣教師、高山右近などの有力なキリシタン、日本修道女たちは長崎へ送られ、400名あまりが数隻の船に分乗して、マニラ・マカオに追放された。この中の何人かの宣教師は、日本に潜伏、または再潜入し命を懸けて宣教活動を行ったが、そのほとんどは殉教した。 1614年以降、全国各地で潜伏キリシタンの摘発、拷問、死刑が続いた。主なものは次の通りである。1619.10月、京都大殉教。ヨハネ橋本太兵衛ほか幼児を含む52名が鴨川の六条河原で処刑された。同10.15~、小倉・豊後日出・熊本でディエゴ加賀山隼人ら18名が殉教。1922年、長崎大殉教。1623.12.4日、江戸大殉教。ヨハネ原取水が殉教。 1624年、江戸幕府はスペイン人の渡航を禁じた。次のように指弾している。
同2.16~、広島で、フランシスコ遠山甚太郎他2名が殉教。1927.2.21日~、島原・雲仙でバルタザル内堀他28名が殉教。1929.1.12日、米沢でルイス甘糟右衛門他52名が殉教。 1633~34年、徳川幕府は日本鎖国令を発し、スペインとの外交を閉ざした。 全国に寺請け檀家制度を設け、全国民を仏教寺所属の信徒として登録させた。これによりキリシタンを取り締まった。更に、5人組制度による相互扶助及び監視密告体制を作り上げた。イエスや聖母マリアの聖像を踏ませる「踏み絵」による摘発が続いた。これによって信仰の有無を判断するというのは日本独特の遣り方であった。家光は、「キリシタンを密告した者に賞金を出すなどして、キリシタンを完全になくさせようとした」。 1633.7.28日~、長崎西坂でジュリアン中浦(司祭)他2名が殉教。1936.2.25日、大坂でディオゴ結城了雪(司祭)が殉教・1637.11.6日、長崎西坂でトマス金鍔次兵衛(司祭)が殉教。 1637~38年、キリシタン勢力による島原・天草の乱が起り、約4万人の農民が一 揆を起こして、「全滅」した。原城で信徒2万7千余人が殉教した。これをようやく平定した翌39年に、ポルトガル人の渡航を禁じた。これは鎖国と言うより、 朝鮮やオランダとの通商はその後も続けられたので、正確には キリシタン勢力との絶縁と言うべきである。 1639.7月、江戸でペトロ岐部(司祭)が殉教。 |
|
| これを野蛮な宗教弾圧と思うべきか。今日判明することは、危険な世界征服勢力から
国の独立を守ろうとする英明な防衛政策だったのではなかろうか。同時代の他の諸国例えばメキシコやフィリピンを見よ、彼らの固有の文化・文明そのものがスペイン人に破壊されてしまった(「JOG(003) 悲しいメキシコ人」)。日本も戦国時代に同じ運命に陥る危険があった。世界の諸国が次々と篭絡されていく中で、一人日本の支配者は賢明に対処した。秀吉や家康の反キリシタン政策は国家の独立を守る戦いとして貫徹され、これが成功したからこそ今日に至る日本があったのではあるまいか。 願うらくは、引き続いての西欧事情の動向調査であったであろうが、この方面は怠りその後泰平の世を謳歌させていくことになった。特に新奇創造の芽を潰していくことになったことが惜しまれることであった。しかし、彼我の力関係を考えると当時の鎖国体制化は賢明な措置であったと充分に考えられよう。 2006.3.7日 れんだいこ拝 |
| 【徳川家康の対バテレン政策事情考】 | ||||||||
2020.9.5日、 「徳川家康「キリスト教を徹底弾圧した」深い事情」。
|
政治顧問としての天海。金地院崇伝(京都南禅寺の僧)
| 【東インド会社考】 | |
「」。
|
| 【人吉城跡敷地内地下室のユダヤ教施設「ミクヴェ」遺構】 | ||
| 1997年から98年にかけて、熊本県人吉市の人吉城跡敷地内に、江戸時代の築造とされる「謎の地下室」が発見された。その構造や伝承などから、郷土史家の間では「隠れキリシタンの遺構」との説が出ている。人吉市教育委員会は「証拠がない」と慎重な姿勢をとり続けている。 地下室は、人吉・球磨地域を約700年にわたって治めた相良(さがら)家の家老職、相良清兵衛(せいべえ、1568~1655)の屋敷跡で、見つかった。南北8・5メートル、東西9メートル、高さ3メートル以上の大規模なもので、石積みの壁に囲まれていた。国指定史跡の人吉城跡を整備するため85年度に始まった発掘調査がきっかけだった。2001年度には、そこから約120メートル離れた清兵衛の息子の屋敷跡で、似た構造の地下室が発見された。どちらも床へと続く階段状の通路があり、床には地下水をためる長方形の貯水池が掘り下げられていた。貯水池には底まで下りられる水中階段があった。似たような地下室遺構は国内でほかに見つかっていないといい、人吉市は、清兵衛の屋敷跡で05年に開館した人吉城歴史館に地下室を復元し展示。息子の屋敷跡の地下室も、見つかった場所で展示している。これらの地下室について、人吉市文化財保護委員長を務めた郷土史家の原田正史さん(91)=岡山県倉敷市=が6年前、自費出版した「驚愕(きょうがく)の九州相良隠れキリシタン」(人吉中央出版社)で、キリスト教の洗礼などに使われた秘密の礼拝施設だった可能性に言及した。今年2月には人吉・球磨地域で発行されている月刊誌で、キリスト教と関係の深いユダヤ教徒が身を清める施設「ミクヴェ」の遺構によく似ていることを初めて指摘し、強調した。 |
||
| 2022年9月20日、(本紙関西研究室研究員・波勢邦生)「人吉城跡敷地内の地下室はユダヤ教関連か?」。 | ||
また旧約聖書の研究者、山森みか氏(テルアビブ大学東アジア学科日本語主任)は、「ミクヴェ」の宗教的意味と機能について指摘する。
人々の耳目を集める熊本の遺構「謎の地下室」は、人吉城歴史館にて見学できる。観光サイトには、スペイン・ジローナ県のユダヤ教博物館展示の中世ユダヤ教ミクヴェと酷似との書き込みも確認できる。またインターネット上では、青森県新郷村の観光資源「キリストの墓」や都市伝説「日ユ同祖論」と重ねて語る向きも見られた。日ユ同祖論とは、イスラエルの失われた十支族に日本人の起源があるという珍説だ。同説は、16世紀のペドロ・ホレモン著『日本中国見聞録』にて「そんなことは断じてあり得ない」と言及されており、古くから人々の興味とロマンを刺激したことで知られる。現在でも「カタカナとヘブライ語が酷似しているから、日本人とユダヤ人は同一起源だ」という奇抜な意見がネット上で散見される。また青森県の「キリストの墓」は戦前に偽書「竹内文書」を元にして造られたもので、後に観光資源となった。関連書籍によれば、キリストの妻の名は「ユミ子」だという。 なお、人吉・球磨地方は歴史的には仏教文化圏として知られている。また肥後人吉藩主・相良氏はキリシタン大名ではない。同地方は、むしろ浄土真宗と日蓮宗への禁制と「隠れ念仏」のあった土地として知られる。はたして人吉城跡「謎の地下室」は、ユダヤ教ミクヴェなのか。または単なる貯水槽なのか。 |
||
2023.1.21日付け朝日新聞デジタル、村上伸一「謎の地下室遺構をユダヤ教ラビが視察」。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)